健康・医療オンライン診療について 国民・患者の皆様へ
Ⅰ オンライン診療の役割・効果
- 在宅で訪問診療とオンライン診療を組み合わせることで、受診の機会が増えた
- 糖尿病などの慢性疾患で定期的な通院が必要であり、オンライン診療と組み合わせることで治療を継続しやすくなった
- 医療機関が遠方で通院が困難であったが、オンライン診療で受診しやすくなった
- 感染症流行時も人と接触せずに受診でき、安心した
- 育児・介護や仕事などで通院が困難だったが、オンライン診療で受診しやすくなった
Ⅱ オンライン診療を利用する際の注意点
患者さんの安全の確保のため、オンライン診療では次のような制限がありますので、ご注意ください。
(例)
- メールやチャットのみで診療することはできません。
- 緊急を要する症状である場合など、医師がオンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライン診療を中止し、速やかに対面診療に切り替えます。
- 初診から麻薬や向精神薬を処方することはできません。また、基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する、特に安全管理が必要な薬品(精神神経用剤、糖尿病用剤等)や、8日分以上の処方もできません。
- 医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。
オンライン診療の安全で適切な利用のために、厚生労働省では患者の皆様に知っておいてほしいこと・ご協力いただきたいことを「安心・安全にオンライン診療を受けるためのチェックリスト」として整理・公表しています。ぜひご活用ください。
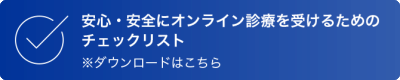
Ⅲ オンライン診療の受診の流れ
まずはかかりつけの医師か、お近くの医療機関にお尋ねください。
※医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
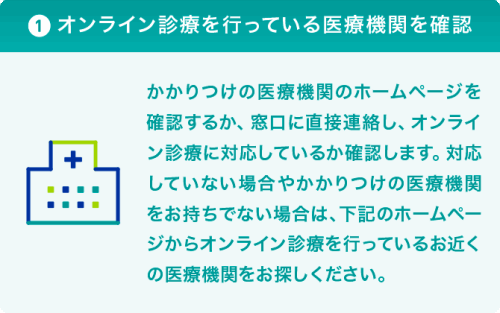
▷医療機能情報提供制度(医療情報ネット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
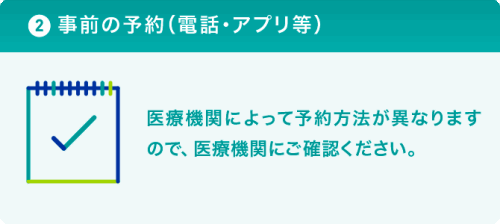
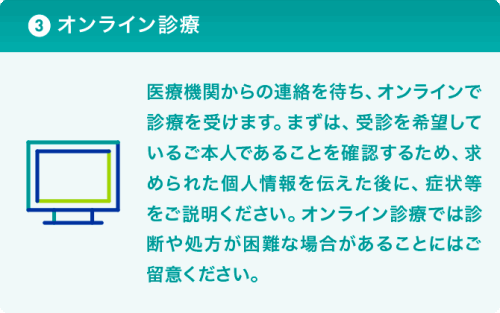
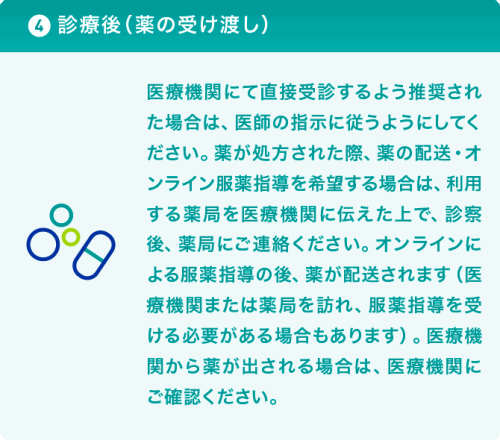
Ⅳ オンライン診療を利用する皆様に知っていただきたいこと・ご協力いただきたいこと
上記指針を踏まえて、オンライン診療を利用する患者の皆様に知っておいてほしいこと・ご協力いただきたいことを「安心・安全にオンライン診療を受けるためのチェックリスト」として作成しました。
ぜひご活用ください。
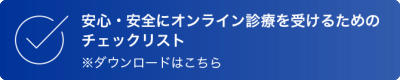
活用例
- オンライン診療を受ける前に、オンライン診療の注意点や患者側において対応すべきことを確認する
- 医療機関が指針をきちんと遵守しているかを確認する
Ⅴ 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出て、オンライン診療を実施している医療機関
- オンライン診療を実施している医療機関のリストは、各都道府県において公表されています。お住まいの自治体を選んでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
- かかりつけの医療機関をご確認いただくか、かかりつけの医療機関がない・かかりつけの医療機関がオンライン診療に対応していない場合は、お近くの医療機関をお探しください。
- ご利用前に、医療機関のホームページや問い合わせ窓口に連絡して、オンライン診療に対応しているかご確認ください。
Ⅵ よくあるQ&A
Q:オンライン診療を利用する時に必要なものは?
A:パソコンやスマートフォン、タブレット等の情報通信機器が必要です。
なお、メールやチャットのみで診療することはできません。
プライバシーが守られ、インターネット接続が可能な環境で利用いただけます。
患者さん本人であることを医師が確認するために、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)も必要です。
※保険診療を受ける場合は健康保険証が必要です。
Q:誰でも利用できるの?
A:緊急を要する症状である場合など、医師がオンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライン診療を中止し、速やかに対面診療に切り替えます。
Q:オンライン診療を利用したときの支払い方法は?
A:医療機関によって支払い方法が異なります(例:クレジットカード払い、後日窓口支払い、後日振り込み等)。事前に医療機関にご確認ください。
Q:オンライン診療を利用したときの薬の受け取り方法は?
A:薬の配送・オンライン服薬指導を希望する場合、利用する薬局を医療機関に伝えた上で、診察後、薬局にご相談ください。オンラインによる服薬指導の後、薬が配送されます。(医療機関または薬局を訪れ、服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)
医療機関から薬が出される場合は、医療機関にご確認ください。
Q:どの薬でも処方されるの?
A:オンライン診療では、医師の判断により、一部の医薬品について処方できない場合があります。また、8日以上の処方ができないなど、一定の処方も制限されています。
→「オンライン診療で処方を受けるに当たって注意が必要なお薬一覧」もあわせてご確認ください。
Q:緊急避妊の目的で利用できるの?
A:緊急避妊に関しては、特定の医師※1が、対面診療が困難であると判断した場合に限り、産婦人科等※2によるオンライン診療を初診から受けることが可能です。ただし、処方は一錠のみであり、薬局※3において薬剤師による指導を受け、薬剤師の前で内服する必要があります。また、避妊ができているか確認するため、産婦人科医による直接の対面診療を約三週間後に受診します。
※1 女性の健康に関する相談窓口等(女性健康支援センター、婦人相談所、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを含む。)に所属する医師、またはそうした相談窓口と連携している医師
※2 産婦人科医または厚生労働省が指定する研修を受講した医師。
※3 オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧
(https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html)
- 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&Aはこちらのページの「Ⅲ オンライン診療の適切な実施に関する指針等の関連ルール」からご確認ください。
オンライン診療指針等に関するお問い合わせ窓口
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」等に関するお問い合わせの
コールセンターとメール窓口を設置いたしました(令和7年6月)。
*委託事業者:有限責任監査法人トーマツ
○コールセンター
電話番号: 080-7666-5801
090-6723-3812
080-3412-1187
受付時間: 平日 午前9時00分~午後5時00分
その他: 3回線ご用意しておりますので、つながりにくい場合は他の電話番号に
おかけいただくか、留守番電話にお問い合わせ事項や折り返し先をお伝
えいただきますようお願いいたします。
○メール窓口
メールアドレス: online-medical-qa●tohmatsu.co.jp
*迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えて
おりますので、「●」を「@」に置き換えてください。



