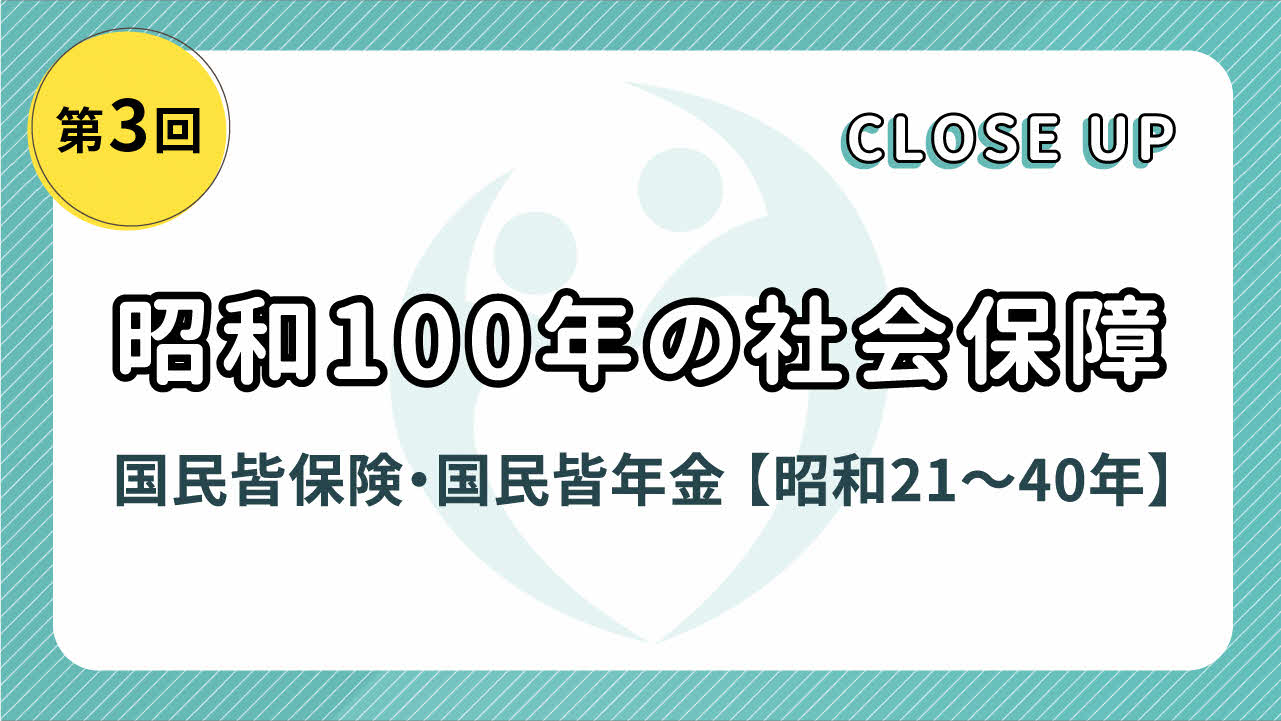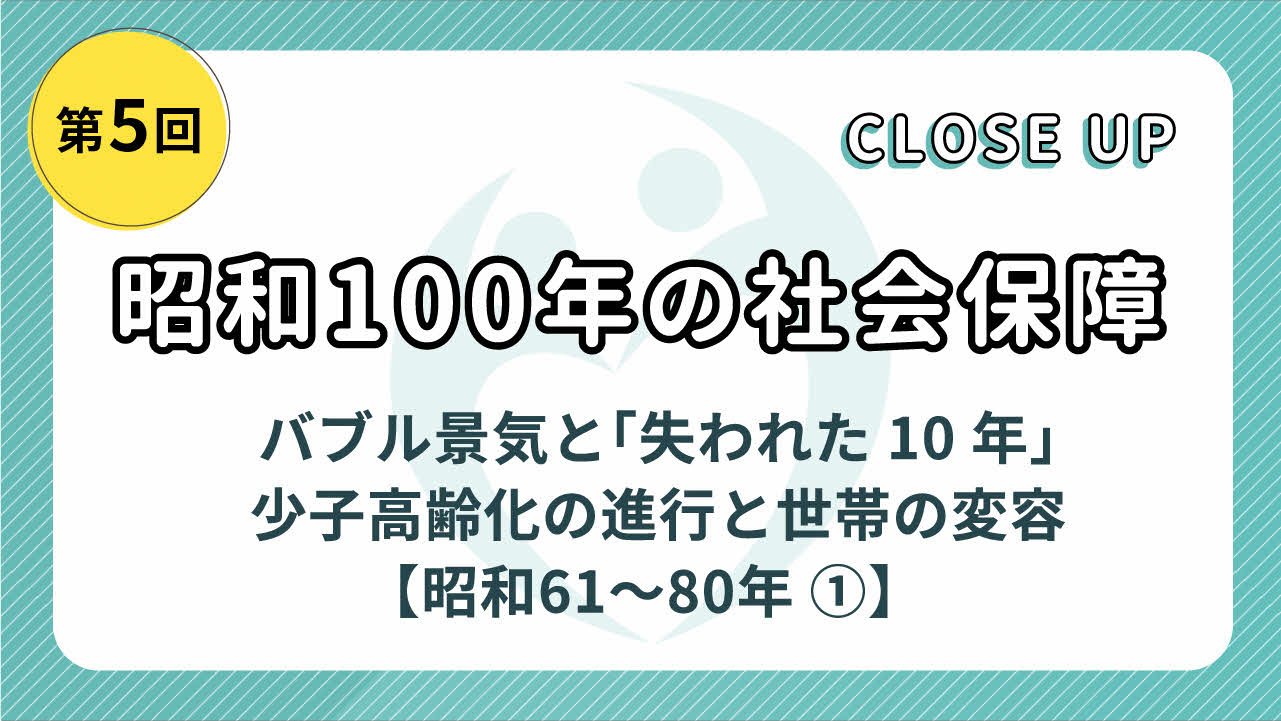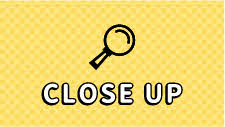- ホーム >
- 報道・広報 >
- 広報・出版 >
- WEBマガジン「厚生労働」 >
- 「昭和100年企画」第4回 拡大から充実へ 昭和41~60年(1966~1985)
「昭和100年企画」第4回 拡大から充実へ 昭和41~60年(1966~1985)
ー 昭和100年企画 全8回 ー
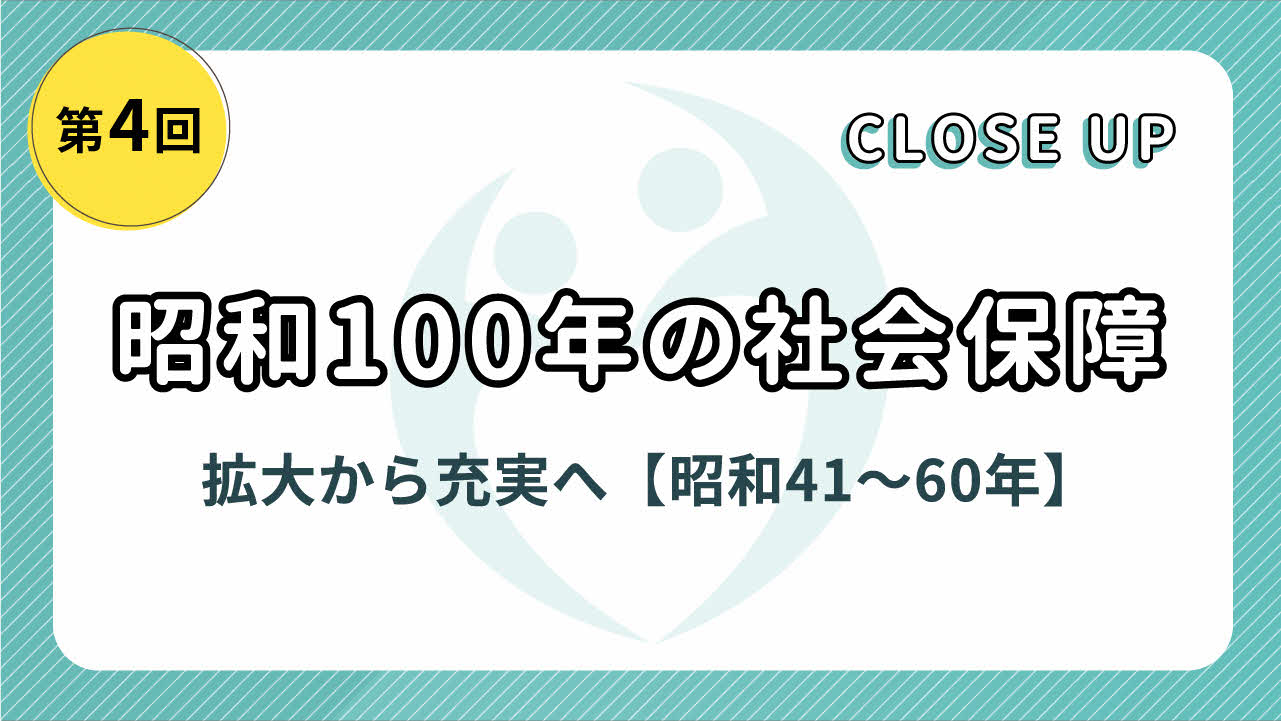
どんな時代だったのか
経済大国としての地位確立
しかし、高度経済成長は永遠ではありませんでした。昭和48(1973)年と昭和53(1978)年に石油危機(オイルショック)が発生し、社会は狂乱物価に見舞われることとなります。これを克服した後も、経済成長率は半減したままで、以後、低成長の時代が続くこととなりました。
家庭で子育てや家事に専念していた専業主婦が、子どもの養育費など家計の補助のためにパート等で働くようになったのも、概ねこの時期と重なります。1970年代以降、専業主婦の割合は低下し、代わって共働き世帯が増加することとなりました。
また、平均寿命の延びにより、昭和45(1970)年に総人口に占める65歳以上人口の割合が7%を超え、我が国も他の先進諸国と同様、「高齢化社会」になりました。昭和59(1984)年には、女性の平均寿命が80歳を超え、「人生80年時代」と言われるようになりました。
この時期の社会保障
福祉元年―医療・年金の給付拡充
医療保険では、定率負担であった患者の自己負担金について一定額以上を払い戻す「高額療養費制度」が導入されました。また、老人医療費無償化が開始され、一部自治体で行われていた高齢者の医療費自己負担の“肩代わり”が、国の制度として全国一律に実施されることとなりました。
年金制度では、年金額の計算方法が改善されて、5万円年金(男子平均月額賃金の6割)となり、併せて物価上昇に応じて年金額が自動的に改定される「物価スライド制度」が導入されました。
これらが実施された昭和48(1973)年は「福祉元年」と呼ばれ、その後にも給付の拡充を期待させるものでした。
石油危機で暗転、財政収支の維持が課題に
医療保険では、老人医療費無料化施策が改められ、新たに制定された老人保健制度で自己負担が復活することになります(昭和58(1983)年)。また、主にサラリーマンが対象となる健康保険等の加入者が退職後に国民健康保険に加入することから、高齢者の加入割合が高い国民健康保険の財源の一部を、健康保険等の保険者が実質的に支援する仕組みが導入されました。
この頃から少子高齢化が意識されるようになり、厚生年金の支給開始年齢の繰り下げが検討されるようになります。
このほか、高年齢者雇用安定法(昭和46(1971)年)、児童手当法(昭和46(1971)年)、雇用保険法(昭和49(1974)年)( i )などの法整備が行われました。
( i )従来の失業保険に、雇用構造の改善や労働者の職業能力向上を組み入れ、雇用に関する総合的な機能をもつ新たな制度として、雇用保険制度を創設した。
※本記事は、厚生労働省が中央法規出版(株)に委託し、中高生から高齢者まで幅広い層向けに作成したものです。
関連記事