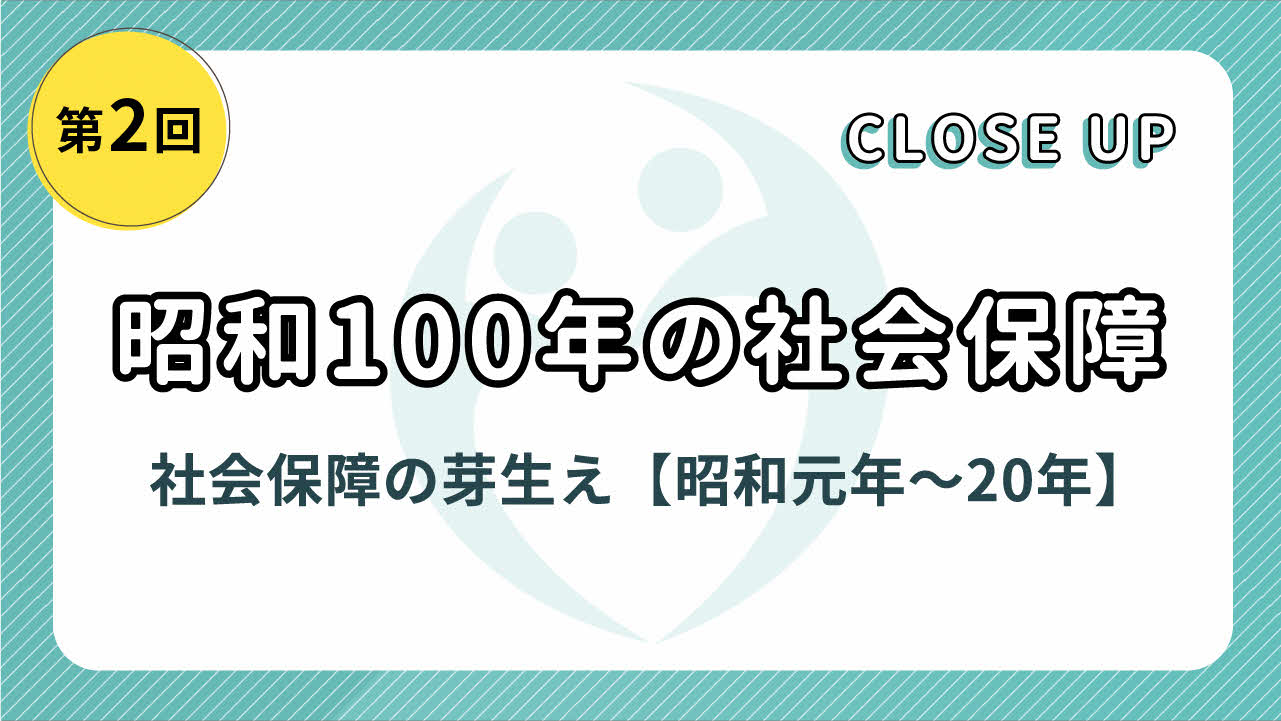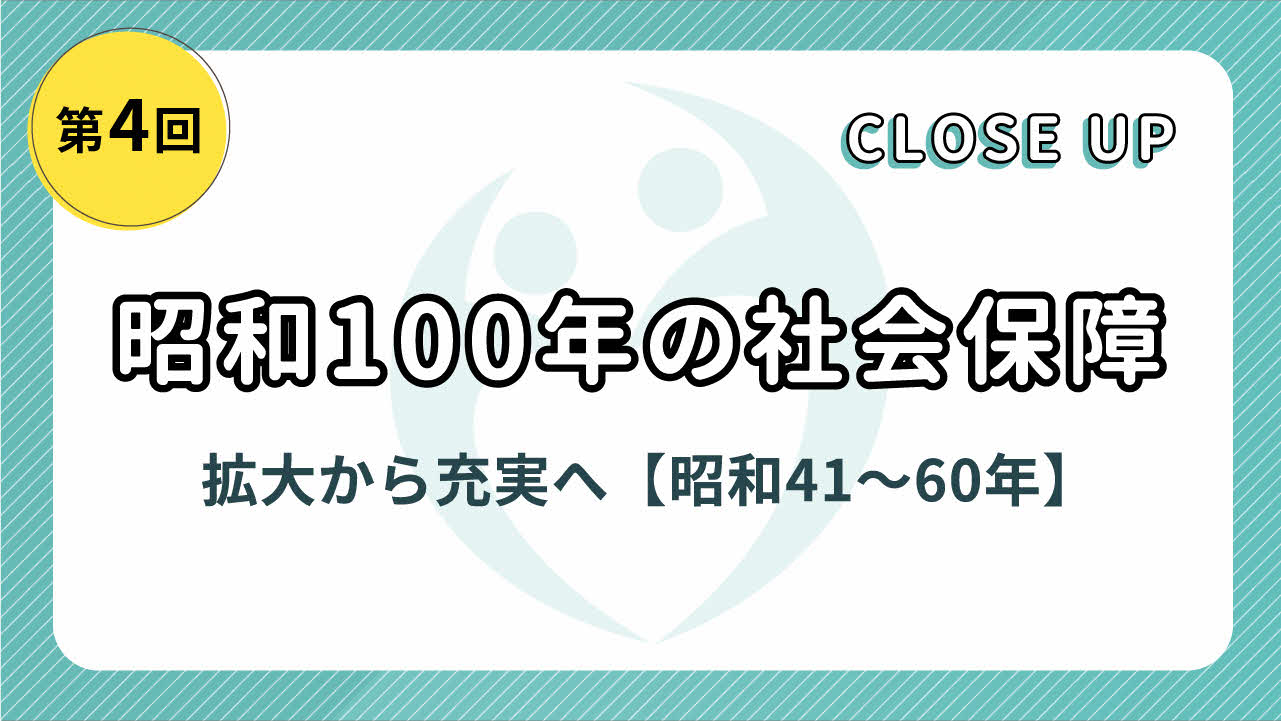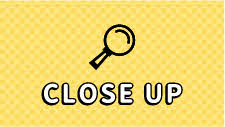- ホーム >
- 報道・広報 >
- 広報・出版 >
- WEBマガジン「厚生労働」 >
- 「昭和100年企画」第3回 国民皆保険・国民皆年金 昭和21~40年(1946~1965)
「昭和100年企画」第3回 国民皆保険・国民皆年金 昭和21~40年(1946~1965)
ー 昭和100年企画 全8回 ー
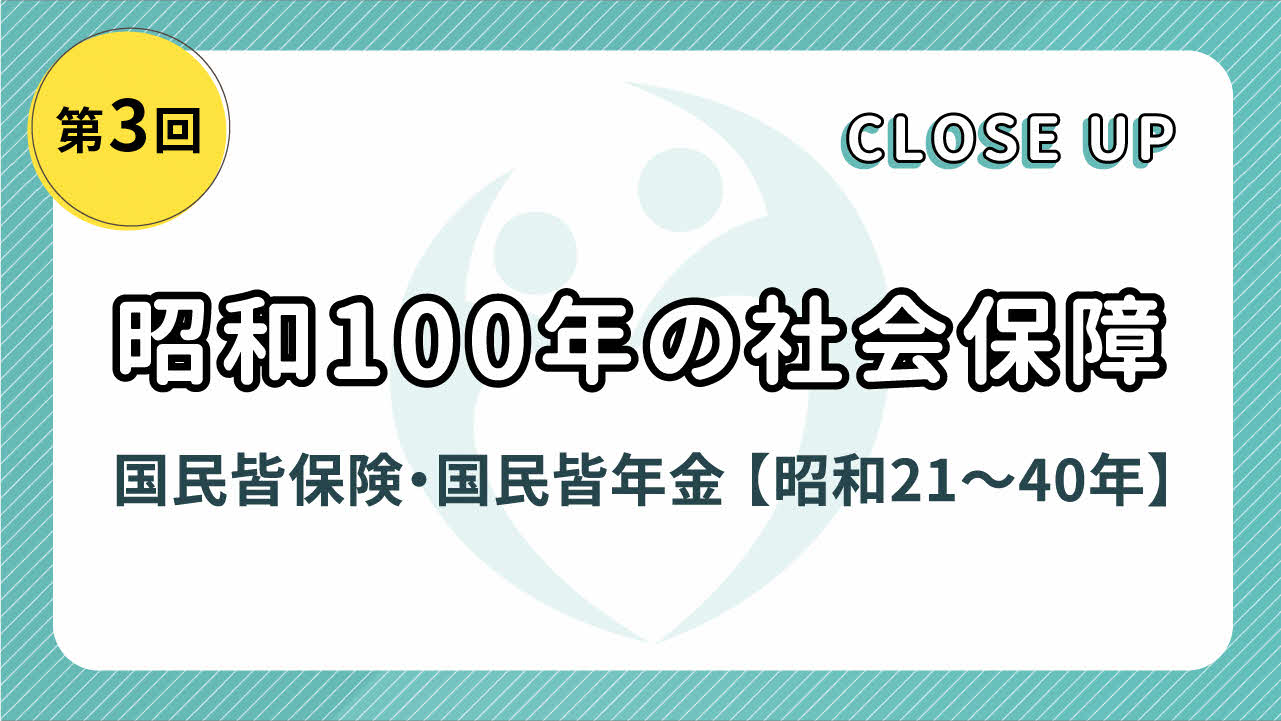
どんな時代だったのか
復興から高度経済成長へ
その後も生産活動の拡大は目覚ましく、昭和30(1955)年から昭和47(1972)年まで、実質経済成長率が平均10%前後で推移する「高度経済成長」が続きました。産業構造は、第一次産業(農林水産業)中心から第二次産業(製造業、建設業等)、第三次産業(卸売・小売業、運輸・通信業、サービス業など)へとシフトし、地方の農山村から都市部へと、人口の移動が大きく進みました。
また、終身雇用や年功賃金などの「日本型雇用慣行」が普及・定着し、「男は仕事、女は家庭」という家族モデルが一般化したとされるのが、この時期です。
この時期の社会保障
国民皆保険・国民皆年金
この勧告を踏まえ、昭和36(1961)年に、国民誰もが公的医療保険に加入して医療を受けられる仕組み(=国民皆保険)と、国民誰もが公的年金保険に加入して老後等に年金を受け取れる仕組み(=国民皆年金)が実現しました。
医療分野は健康保険と国民健康保険( i )が、年金分野は厚生年金と国民年金( ii )が並び立つ形となり、就業形態等に応じて、全ての国民がいずれかの保険制度に加入することとなりました。
なお労働分野でも、雇用労働者を対象に失業時に給付を行うことで生活の安定を図る「失業保険」(現:雇用保険)と、業務上の事由等による労働者等の傷病等に対して必要な保険給付を行う「労災保険」が創設されました(いずれも昭和22(1947)年)。
( i )昭和36(1961)年4月1日までに、全ての市町村に国民健康保険事業実施を義務づけた
( ii )新たに政府が農業者や自営業者等を対象とする国民年金事業を開始した
福祉三法/六法
※本記事は、厚生労働省が中央法規出版(株)に委託し、中高生から高齢者まで幅広い層向けに作成したものです。
関連記事