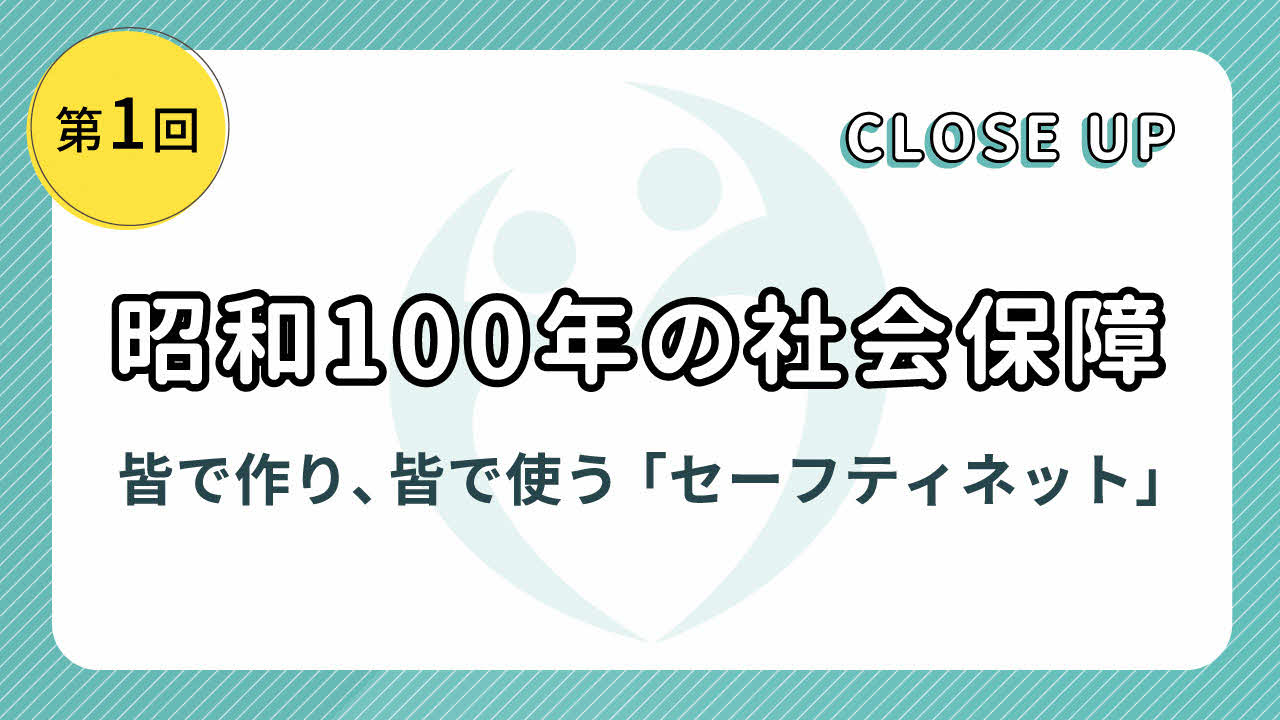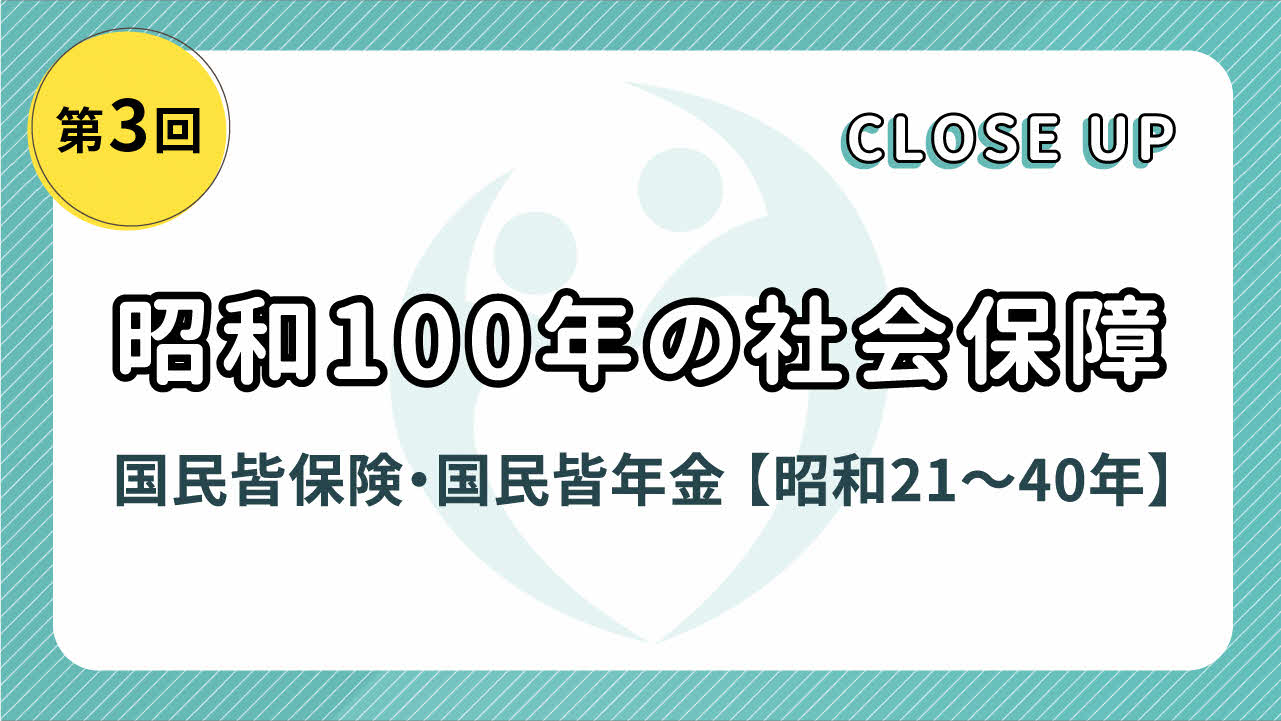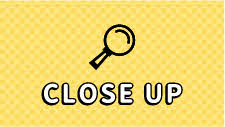- ホーム >
- 報道・広報 >
- 広報・出版 >
- WEBマガジン「厚生労働」 >
- 「昭和100年企画」第2回 社会保障の芽生え 昭和元年~20年(1926~1945)
「昭和100年企画」第2回 社会保障の芽生え 昭和元年~20年(1926~1945)
ー 昭和100年企画 全8回 ー
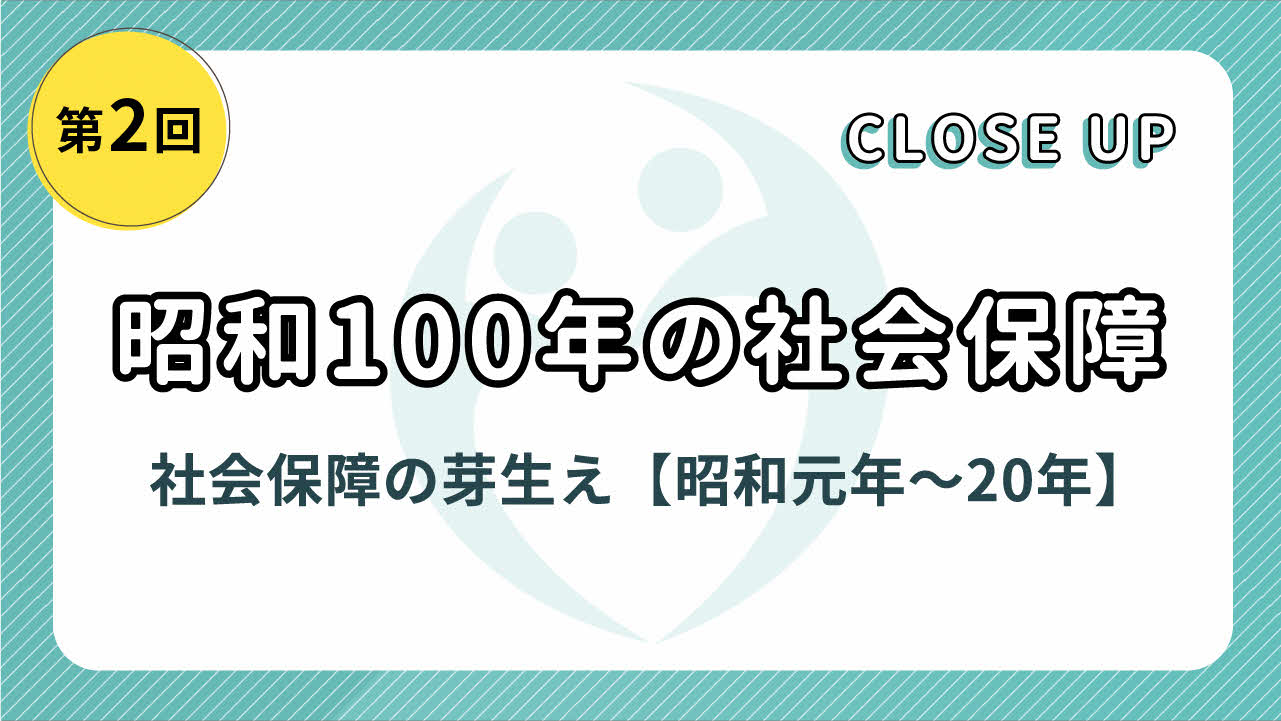
どんな時代だったのか
昭和不況そして敗戦
理由の一つは、景気の悪化です。都市部には失業者があふれ、農村部も生糸や米の価格暴落などで生活が非常に厳しくなり、工場ストライキや小作人争議などで、世情は予断を許さなくなります。そうしたなか、海軍軍人たちによる5.15事件(昭和7(1932)年)、陸軍部隊による2.26事件(昭和11(1936)年)などが起き、政財界の要人の暗殺も横行しました。
二つ目の理由は、国際関係の悪化です。ソ連が近隣諸国の政権を転覆させ、共産主義化を進める一方、ドイツ、イタリアでは国家社会主義を掲げる専制政府が誕生し、領土奪取に走ります。一方、各地に広大な植民地を持つなど豊かな国とされるイギリス、フランスなどはそれぞれ経済圏を構築して対抗します。我が国も自活のために海外発展を目指しますが、外交的にも思わしい成果を得られず、国際連盟脱退(昭和8(1933)年)など孤立していきました。
そうしたなか、我が国はドイツ、イタリアとの三国同盟を経て、経済制裁の重圧をかけてくるアメリカ、イギリスなどとの戦争に踏み切ります(昭和16(1931)年)。しかし経済力の差は大きく、我が国は敗戦し、戦争が終結しました(昭和20(1945)年)。
この時期の社会保障
礎(いしづえ)の創生――健康保険、旧国民健康保険、厚生年金保険の創設
まず、労使折半で保険料を納め、病気やけがに際して医療を受けられる「健康保険制度」が昭和2(1927)年に施行されました。制度を創設した背景としては労使関係の対立の緩和を図ること等があり、当初は加入対象を鉱工業労働者に限るなど、適用は限定的でしたが、当時の仕組みの骨格は現在まで引き継がれています。
続いて、農村部の保健衛生水準の改善と医療費負担の軽減のため、昭和13(1938)年に「国民健康保険制度」が創設されました。創設当時は、保険者の設立も加入も原則として任意とされていましたが、地域単位で健康保険に加入できない国民全般を対象とした制度でした。労働者とその家族は職場を通じて健康保険に加入し、それ以外の人(農業者、個人事業者など)は地域単位の国民健康保険に加入する今日の「国民皆保険」の体系の基礎は、このときに端を発しています。
そして「厚生年金保険」の創設です。明治期から、国家公務員や軍人には国から退役後に恩給が支給されていましたが、広く民間労働者を対象とした「労働者年金保険」が、戦争中の昭和17(1942)年に発足しました(昭和19(1944)年に厚生年金保険と改名)。労使折半で保険料を負担し、老齢・障害・死別などに対応して、年金が支給されることになりました。
なお、「厚生省」が誕生したのも、この時期です。戦時下における国民の体力向上を図り、保健・福祉に関する行政の拡充刷新する目的で、昭和13(1938)年1月に発足しました( i )。
( i )戦後、厚生省内の労働部局が「労働省」として分離したが、2001年の省庁再編で「厚生省」と「労働省」が合併し「厚生労働省」となった
※本記事は、厚生労働省が中央法規出版(株)に委託し、中高生から高齢者まで幅広い層向けに作成したものです。
関連記事