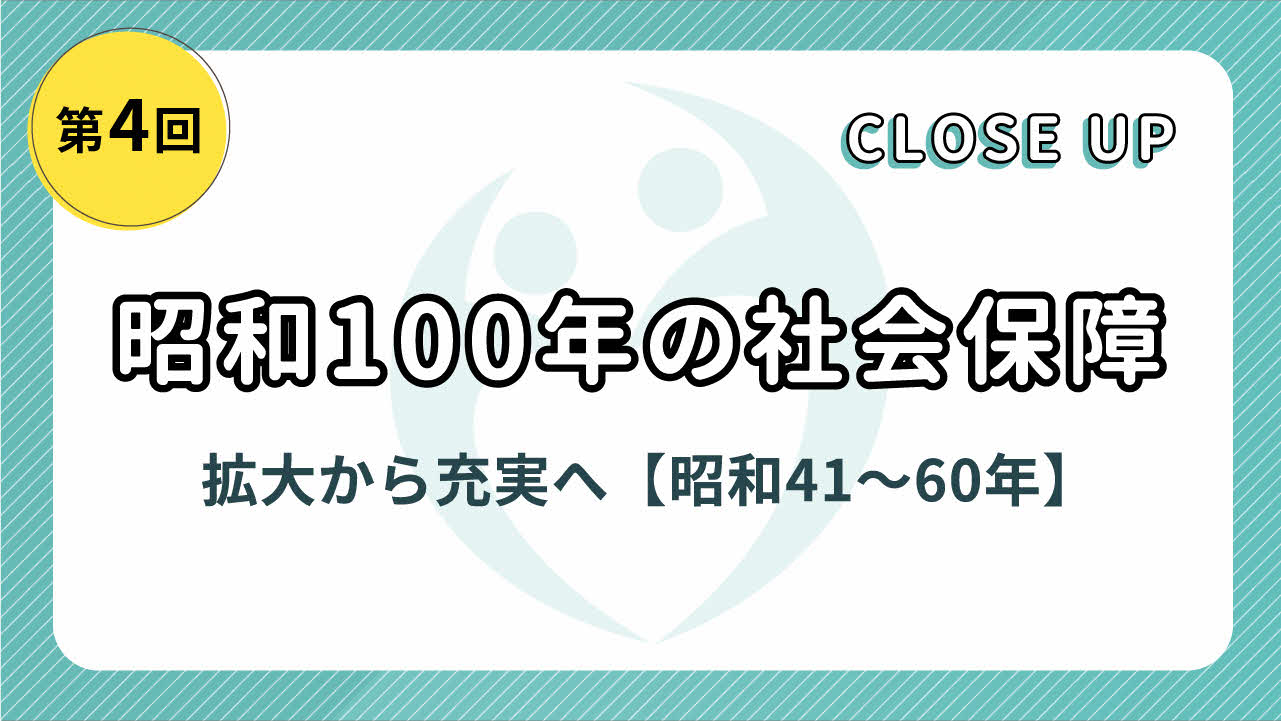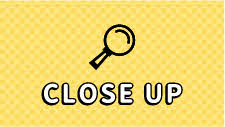- ホーム >
- 報道・広報 >
- 広報・出版 >
- WEBマガジン「厚生労働」 >
- 「昭和100年企画」第5回 バブル景気と「失われた10年」―少子高齢化の進行と世帯の変容 昭和61~80年(1986~2005)【1】
「昭和100年企画」第5回 バブル景気と「失われた10年」―少子高齢化の進行と世帯の変容 昭和61~80年(1986~2005)【1】
ー 昭和100年企画 全8回 ー
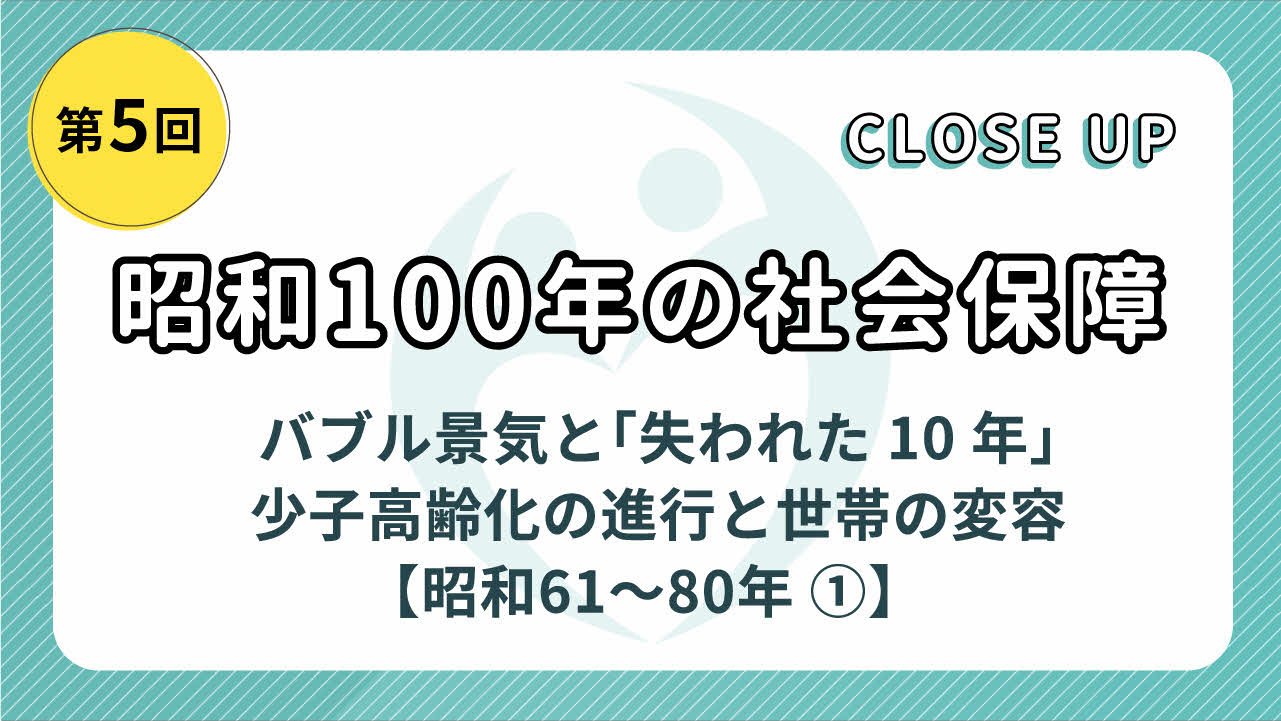
この年代は2回に分けてご紹介します。
今回は「どんな時代だったか」という社会の変化を説明し、次回はそれに応じた社会保障政策の対応について解説します。
どんな時代だったのか
経済や社会に大きな変化
この期間には、男性正社員の長期勤続を前提とした雇用形態が変化していきました。共働き家庭が専業主婦世帯を上回るようになる一方、バブル崩壊後の経済の停滞などを背景に、非正規雇用労働者が増えていきます。
少子高齢化が本格化
まずは「高齢化」についてです。昭和初期の平均寿命は男女とも40歳代でしたが、高度経済成長期以降、医療技術の進歩や保健衛生水準の向上も相まって高度経済成長期以来急速に伸び、世界トップになりました(昭和65(1990)年時点で、男性75.92歳、女性81.90歳)。
その結果、人口に占める65歳以上の人口比率が高まり、我が国では他国と比べ、「高齢化社会」(7%以上)から「高齢社会」(14%以上)への移行が24年間(昭和45(1970)年から昭和69(1994)年まで)と極めて短期間でした。長寿自体は、めでたく喜ばしいことです。ただ国民皆保険・皆年金の観点から見れば、年金や医療の給付費が増え制度運営に見直しが求められることになります。特に寝たきりや認知症に伴う家族の介護負担と「社会的入院」への対応が社会問題になりました( 1 )。
急速に進む高齢化で、社会保障への支出が国の財政にとって大きな負担となっていきます。経済成長は依然として低迷して税収は伸び悩み、赤字国債(国の借金)によって財源調達することが恒常化していきました。こうしたなか、「高齢化への対応に必要な経費を安定的に確保するため」という名目で、消費税が昭和64(1989)年に導入されました(当初税率3%)( 2 )。
次に「少子化」についてです。一人の女性が生涯に産む平均子ども数を示す指標を「合計特殊出生率」と呼びます。この数値が2.0前後であれば人口規模は長期的に安定します。明治以降、社会の近代化を背景に人口が倍増しましたが、それには高い出生率がありました。
我が国では、昭和50(1975)年に2.0を割り込み、その後も低下を続けています。昭和64(1989)年の「1.57ショック」は大きく報道されましたが、政府の人口問題部署は「合計特殊出生率はやがて回復する」の見立てで鎮静化を図りました。しかしそれが誤りであったことは今では明らかになっています。ちなみに、この期間の最初の年である昭和61(1986)年の出生数は138万人でしたが、昭和80(2005)年には106万人でした。出生数が死亡数(108万人)に逆転され、人口減少時代へと突入しています。
この時期、政府は「ゴールドプラン」(昭和64(1989)年)、「エンゼルプラン」(昭和69(1994)年)、「障害者プラン」(昭和70(1995)年)などによって、介護政策、子育て対策、障害者対策を様々に検討し、国民への啓発を高めていきました。
( 1 )社会的入院とは、病状はある程度安定し、必ずしも入院による治療の必要はないにもかかわらず、適切な居住の場や生活支援を得られないために、病院が受け入れて生活支援を続けている状態のこと。
( 2 )現在の税率は10%。また税収は社会保障4経費(年金、介護、医療に加え、子ども・子育て支援)となっている。
( 2 )現在の税率は10%。また税収は社会保障4経費(年金、介護、医療に加え、子ども・子育て支援)となっている。
※本記事は、厚生労働省が中央法規出版(株)に委託し、中高生から高齢者まで幅広い層向けに作成したものです。
関連記事