- ホーム >
- 政策について >
- 分野別の政策一覧 >
- 雇用・労働 >
- 労働基準 >
- 安全・衛生 >
- 労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きについて >
- 労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きの方法(フローチャート) >
- 既存化学物質
既存化学物質
労働安全衛生法において「既存化学物質」である化学物質については届出の必要はありません。
既存化学物質とは、次の1~4に該当する化学物質をいいます。
なお、労働安全衛生法における既存化学物質については、下記ホームページで検索することができます。
厚生労働省ホームページの内の「職場のあんぜんサイト」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html
既存化学物質とは、次の1~4に該当する化学物質をいいます。
なお、労働安全衛生法における既存化学物質については、下記ホームページで検索することができます。
厚生労働省ホームページの内の「職場のあんぜんサイト」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html
1 政令で定める既存化学物質
政令で定める既存化学物質とは、労働安全衛生法施行令第18条の3に定められた化学物質で、次の(1)~(4)のいずれかに該当するものです。
(1) 元素
一種類の原子(同位体の区別を問わない。)からなる物質のすべての状態(励起状態、ラジカル等を含む。)をいい、単体を含むもの。
(2) 天然に産出される化学物質
鉱石、原油、天然ガスその他天然に存在するそのままの状態を有する化学物質及び米、麦、牛肉その他動植物から得られる一次産品又はこの一次産品を利用して発酵等の方法により製造される化学物質であって分離精製が行われていないもの。
(3) 放射性物質
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第2条第2項の放射性物質
(4) 労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により労働大臣がその名称等を公表した化学物質
これは、昭和54年6月29日までに製造され、又は輸入された化学物質で、官報で以下のように公表されています。
昭和54年2月 5日 労働省告示第9号
( 昭和54年5月31日 労働省告示第49号で一部改正)
昭和54年5月31日 労働省告示第50号
昭和54年8月31日 労働省告示第98号
なお、昭和54年2月5日の告示において、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第3項の規定により厚生大臣及び通商産業大臣が公示した化学物質([1] 化審法における官報公示整理番号が以下に示す番号以前のもの、[2] 日本薬局方第8改正(昭和46年)に収載されたもの(官報公示整理番号なし))をも同時に公表しているため、これらは安衛法においても既存化学物質として取り扱います。
(1) ― 1197
(2) ― 3166
(3) ― 3535
(4) ― 1365
(5) ― 5363
(6) ― 1553
(7) ― 2117
(8) ― 652
(9) ― 2607
(1) 元素
一種類の原子(同位体の区別を問わない。)からなる物質のすべての状態(励起状態、ラジカル等を含む。)をいい、単体を含むもの。
(2) 天然に産出される化学物質
鉱石、原油、天然ガスその他天然に存在するそのままの状態を有する化学物質及び米、麦、牛肉その他動植物から得られる一次産品又はこの一次産品を利用して発酵等の方法により製造される化学物質であって分離精製が行われていないもの。
(3) 放射性物質
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第2条第2項の放射性物質
(4) 労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により労働大臣がその名称等を公表した化学物質
これは、昭和54年6月29日までに製造され、又は輸入された化学物質で、官報で以下のように公表されています。
昭和54年2月 5日 労働省告示第9号
( 昭和54年5月31日 労働省告示第49号で一部改正)
昭和54年5月31日 労働省告示第50号
昭和54年8月31日 労働省告示第98号
なお、昭和54年2月5日の告示において、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第3項の規定により厚生大臣及び通商産業大臣が公示した化学物質([1] 化審法における官報公示整理番号が以下に示す番号以前のもの、[2] 日本薬局方第8改正(昭和46年)に収載されたもの(官報公示整理番号なし))をも同時に公表しているため、これらは安衛法においても既存化学物質として取り扱います。
(1) ― 1197
(2) ― 3166
(3) ― 3535
(4) ― 1365
(5) ― 5363
(6) ― 1553
(7) ― 2117
(8) ― 652
(9) ― 2607
2 厚生労働大臣が名称を公表した新規化学物質
これは、「労働安全衛生法第57条の3第3項の規定により、厚生労働大臣が名称等を公表した新規化学物質」で、新規化学物質の届出等を受けて厚生労働大臣が官報で名称等を公表した化学物質です。
3 既存化学物質扱いとなる特定の化学物質(昭和54年3月23日付け基発第132号)
これは、既存化学物質のみから構成される特定の化合物等で、次のいずれかの場合に該当するものです。
(1)分子間化合物等
次の[1]~[6]までに掲げる化学物質のように2以上の化学物質が集合し、単一の化学構造を有する化学物質を形成しているとみなされる場合であって、その集合した個々の化学物質が全て既存化学物質であるときには、当該単一の化学構造を有する化学物質は、既存化学物質として取り扱います。したがって、集合した個々の化学物質のうち、いずれかの化学物質が既存の化学物質でない場合には、その集合体である化学物質は新規化学物質として届出が必要になります。
[1] 分子間化合物
一般に二種類以上の安定な分子が直接結合してできる化合物で比較的容易にもとの成分に分解できるようなものをいい、分子化合物ともいいます。
(例) CaCl2・4CH3OH CoCl2・6NH3
[2] 水和物
分子間化合物のうち、水と他の分子が直接結合してできる化合物をいいます。できた化合物が結晶のとき、この水を結晶水といいます。
(例) CuSO4・5H2O MgSO4・H2O MgCl2・H2O
[3] 包接化合物
二種類の分子のうち、一方の分子がトンネル形、層状又は立体網状構造の結晶を作り、その結晶の隙間に他の分子が入り込んで結晶を作ったような構造を有する化合物をいいます。
(例) ヒドロキノンとメタノールからできる包接化合物
[4] 有機酸又は有機塩基の塩(金属塩を除く。)
有機酸の塩又は有機塩基の塩をいいます。
この場合、(ア)有機酸と無機塩基の塩、(イ)有機塩基と無機酸の塩、(ウ)有機酸と有機塩基の塩、のいずれも該当します。
(ウの例) 酢酸とピリジンとの反応物
[5] オニウム塩(正、負両イオンが既存化学物質から生成されるものである場合に限る。)
オニウム塩とは、化学結合に関与しない電子対を有する化合物が、当該電子対によって、他の陽イオン形の化合物と配位結合して生ずる化合物をいいます。
なお、正、負両イオンが既存の化学物質から生成されている場合とは、オニウム塩の対イオンが既存の化学物質の構成部分となっている場合をさします。
(例1) ジメチルエーテルと塩化水素からできるジメチルオキソニウム=クロリド
(CH3)2O + HCl → [(CH3)2OH]+ Cl-
(例2) テトラエチルアンモニウム=ブロミド (テトラエチルアンモニウム=クロリドと臭化物イオンが既存化学物質)
(C2H5)4N+ Br- ((C2H5)4N+ Cl- と Br-)
[6] 複塩
2種以上の塩が結合してできる化合物であって、それぞれの塩を構成するイオンがそのまま存在しているものをいいます。
(例)K2SO4と[Al(H2O)6](SO4)3 からできるミョウバン
[1] 分子間化合物
一般に二種類以上の安定な分子が直接結合してできる化合物で比較的容易にもとの成分に分解できるようなものをいい、分子化合物ともいいます。
(例) CaCl2・4CH3OH CoCl2・6NH3
[2] 水和物
分子間化合物のうち、水と他の分子が直接結合してできる化合物をいいます。できた化合物が結晶のとき、この水を結晶水といいます。
(例) CuSO4・5H2O MgSO4・H2O MgCl2・H2O
[3] 包接化合物
二種類の分子のうち、一方の分子がトンネル形、層状又は立体網状構造の結晶を作り、その結晶の隙間に他の分子が入り込んで結晶を作ったような構造を有する化合物をいいます。
(例) ヒドロキノンとメタノールからできる包接化合物
[4] 有機酸又は有機塩基の塩(金属塩を除く。)
有機酸の塩又は有機塩基の塩をいいます。
この場合、(ア)有機酸と無機塩基の塩、(イ)有機塩基と無機酸の塩、(ウ)有機酸と有機塩基の塩、のいずれも該当します。
(ウの例) 酢酸とピリジンとの反応物
[5] オニウム塩(正、負両イオンが既存化学物質から生成されるものである場合に限る。)
オニウム塩とは、化学結合に関与しない電子対を有する化合物が、当該電子対によって、他の陽イオン形の化合物と配位結合して生ずる化合物をいいます。
なお、正、負両イオンが既存の化学物質から生成されている場合とは、オニウム塩の対イオンが既存の化学物質の構成部分となっている場合をさします。
(例1) ジメチルエーテルと塩化水素からできるジメチルオキソニウム=クロリド
(CH3)2O + HCl → [(CH3)2OH]+ Cl-
(例2) テトラエチルアンモニウム=ブロミド (テトラエチルアンモニウム=クロリドと臭化物イオンが既存化学物質)
(C2H5)4N+ Br- ((C2H5)4N+ Cl- と Br-)
[6] 複塩
2種以上の塩が結合してできる化合物であって、それぞれの塩を構成するイオンがそのまま存在しているものをいいます。
(例)K2SO4と[Al(H2O)6](SO4)3 からできるミョウバン
(2)ブロック重合物及びグラフト重合物
ブロック重合物及びグラフト重合物であって、その構成単位となる重合物がすべて既存の化学物質である場合は、当該ブロック重合物及びグラフト重合物は、既存の化学物質とみなします。
[1] ブロック重合物
重合度の低い2種類以上の重合体(単一モノマーからなる重合体、複数モノマーからなる重合体のいずれも可。
次の [2] でも同様)を結合させることにより得られる高分子化合物をいいます。
[2] グラフト重合物
幹となる高分子化合物に枝となる重合体を接ぎ木するような形で結合されることにより得られる高分子化合物をいいます。
注:上記3の(1)、(2)中の「既存の化学物質」には、労働安全衛生法第57条の3第1項に基づき新規化学物質の製造・輸入届がなされたものの、官報への名称公表がまだなされていない物質が含まれます。すなわち、これらの物質については、名称公表前であってもその物質を「既存の化学物質」とみなして3の(1)、(2)を適用します。
[1] ブロック重合物
重合度の低い2種類以上の重合体(単一モノマーからなる重合体、複数モノマーからなる重合体のいずれも可。
次の [2] でも同様)を結合させることにより得られる高分子化合物をいいます。
[2] グラフト重合物
幹となる高分子化合物に枝となる重合体を接ぎ木するような形で結合されることにより得られる高分子化合物をいいます。
注:上記3の(1)、(2)中の「既存の化学物質」には、労働安全衛生法第57条の3第1項に基づき新規化学物質の製造・輸入届がなされたものの、官報への名称公表がまだなされていない物質が含まれます。すなわち、これらの物質については、名称公表前であってもその物質を「既存の化学物質」とみなして3の(1)、(2)を適用します。
| ※平成24年2月より、昭和54年3月23日付け基発第132号通達の運用を一部変更しました。 |
| ※平成25年3月より、3(1)[1]~[6]について事例を追加しました。 |
4 既存化学物質扱いとなる特定の高分子化合物
(1)昭和61年8月27日付け基発第504号通達により既存化学物質扱いとなるもの
新規に製造され、又は輸入される高分子化合物について、既存の化学物質(下記※参照)である単量体(モノマー)等から構成され、また、数平均分子量が2,000以上で、さらに次の[1]から[8]のいずれにも該当しない場合には、これを既存の化学物質として扱うものです。
[1] 正電荷を有する高分子化合物
[2] 総重量中の炭素の重量の比率が32パーセント未満の高分子化合物
[3] 硫黄、ケイ素、酸素、水素、炭素又は窒素以外の元素が共有結合している高分子化合物
[4] アルミニウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム又はマグネシウム以外の金属イオン(錯体金属イオンを
含む)がイオン結合している高分子化合物
[5] 生物体から抽出し、分離した高分子化合物及び当該高分子化合物から化学反応により生成される高分子
化合物並びにこれらの高分子化合物と類似した化学構造を有する高分子化合物
[6] ハロゲン基又はシアノ基を有する化合物から生成される高分子化合物
[7] 反応性官能基(注2参照)を有する高分子化合物であって、当該高分子化合物の数平均分子量を当該数
平均分子量に対応する分子構造における反応性官能基(下記※※参照)の数で除した値が10,000以下のもの
[8] 常温、常圧で分解又は解重合するおそれのある高分子化合物
※: (1)中の「既存の化学物質」の範囲
上記(1)中の「既存の化学物質」には、労働安全衛生法第57条の3第1項に基づき新規化学物質の
製造・輸入届がなされたものの、官報への名称公表がまだなされていない物質が含まれます。
すなわち、名称公表前であってもその物質を「既存の化学物質」とみなして(1)を適用します。
※※: 反応性官能基を有する高分子化合物の例
イソシアン酸基、分岐アクリル酸基、分岐メタクリル酸基、エポキシ基、酸無水物、酸ハロゲン化物、
アルデヒド、アミン、フェノール類、チオフェノール類、含硫黄酸基若しくはその誘導体、アジリジン類、
保護されたイソシアン酸基、イミン、イソチオシアン酸基、ビニルスルフォン、ハロシラン基、
アルコキシシラン基、3若しくは4員環ラクトン等の構造を有する高分子化合物
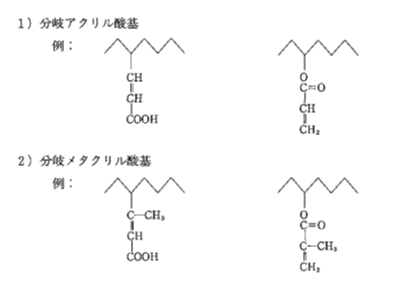
[1] 正電荷を有する高分子化合物
[2] 総重量中の炭素の重量の比率が32パーセント未満の高分子化合物
[3] 硫黄、ケイ素、酸素、水素、炭素又は窒素以外の元素が共有結合している高分子化合物
[4] アルミニウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム又はマグネシウム以外の金属イオン(錯体金属イオンを
含む)がイオン結合している高分子化合物
[5] 生物体から抽出し、分離した高分子化合物及び当該高分子化合物から化学反応により生成される高分子
化合物並びにこれらの高分子化合物と類似した化学構造を有する高分子化合物
[6] ハロゲン基又はシアノ基を有する化合物から生成される高分子化合物
[7] 反応性官能基(注2参照)を有する高分子化合物であって、当該高分子化合物の数平均分子量を当該数
平均分子量に対応する分子構造における反応性官能基(下記※※参照)の数で除した値が10,000以下のもの
[8] 常温、常圧で分解又は解重合するおそれのある高分子化合物
※: (1)中の「既存の化学物質」の範囲
上記(1)中の「既存の化学物質」には、労働安全衛生法第57条の3第1項に基づき新規化学物質の
製造・輸入届がなされたものの、官報への名称公表がまだなされていない物質が含まれます。
すなわち、名称公表前であってもその物質を「既存の化学物質」とみなして(1)を適用します。
※※: 反応性官能基を有する高分子化合物の例
イソシアン酸基、分岐アクリル酸基、分岐メタクリル酸基、エポキシ基、酸無水物、酸ハロゲン化物、
アルデヒド、アミン、フェノール類、チオフェノール類、含硫黄酸基若しくはその誘導体、アジリジン類、
保護されたイソシアン酸基、イミン、イソチオシアン酸基、ビニルスルフォン、ハロシラン基、
アルコキシシラン基、3若しくは4員環ラクトン等の構造を有する高分子化合物
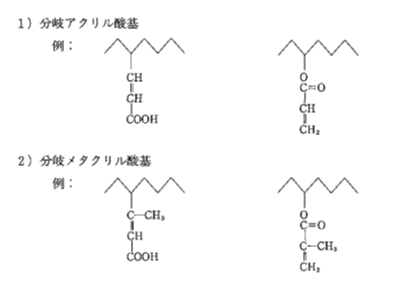
|
●高分子化合物製造・輸入報告の廃止 4(1)の条件に該当する高分子化合物については、昭和61年8月27日付け事務連絡により 「高分子化合物製造・輸入報告」の提出をお願いしていましたが、平成24年11月12日付けで この事務連絡は廃止され、報告は不要となりました。 |
(2)平成24年11月12日付け基安化発1112第2号通達により既存化学物質扱いとなるもの
国際的な整合化を図るため、次の[1]又は[2]に該当する高分子化合物についても、既存の化学物質として取り扱い、新規化学物質製造・輸入届及び少量新規化学物質確認申請を不要としました。
なお、[1]及び[2]において、「既存の化学物質」には、(a)昭和61年8月27日付け基発第504号通達により既存の化学物質として扱われる物質(上記4(1)参照)、及び(b)新規化学物質製造・輸入届を提出済みで官報への名称公表がまだなされていない物質も含まれます。すなわち、これらの物質については「既存の化学物質」とみなして[1]、[2]を適用します。
[1] 2種類以上の単量体等から得られる有機高分子化合物であって、その重量割合の合計が99%を超える単量体等から得られる別の有機高分子化合物が既存の化学物質である場合。なお、目的とする有機高分子化合物の製造の場合であって、残り1%未満の重量割合を占める単量体等が新規化学物質である場合には、当該単量体等について新規化学物質製造・輸入届、少量新規化学物質確認申請等の手続がなされている必要があること。
(例:A-B-C共重合物において、A-B共重合物が既存の化学物質であって、AとBの重量の合計が99%を超えている場合。)
[2] 2種類以上の単量体等から得られる有機高分子化合物であって、その重量割合の合計が98%を超える単量体等から得られる別の有機高分子化合物が既存の化学物質であり、残り2%未満の重量割合を占める単量体等が既存の化学物質であって、かつ、当該単量体等が次のiからviまでのいずれにも該当しない場合。
i 安衛令第16条第1項に掲げる製造等が禁止される有害物等(ただし、第9号を除く。)
ii 安衛令別表第3に掲げる特定化学物質(ただし、第1号の8、第2号の38及び第3号の9を除く。)
iii 安衛令別表第5第1号及び第4号に掲げる四アルキル鉛及び加鉛ガソリン
iv 安衛令別表第6の2に掲げる有機溶剤
v 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第1条第1号、第3号、第4号に掲げる鉛、鉛合金及び鉛化合物
vi 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の17、第38条の18又は第38条の19により講ずべき措置が規定されている1,3-ブタジエン、1,4-ジクロロ-2-ブテン、硫酸ジエチル及び1,3-プロパンスルトン
(例:A-B-C共重合物において、A-B共重合物が既存の化学物質であって、AとBの重量の合計が98%を超えており、かつ、Cが既存の化学物質(ただし、i~viには非該当)である場合。)
なお、[1]及び[2]において、「既存の化学物質」には、(a)昭和61年8月27日付け基発第504号通達により既存の化学物質として扱われる物質(上記4(1)参照)、及び(b)新規化学物質製造・輸入届を提出済みで官報への名称公表がまだなされていない物質も含まれます。すなわち、これらの物質については「既存の化学物質」とみなして[1]、[2]を適用します。
[1] 2種類以上の単量体等から得られる有機高分子化合物であって、その重量割合の合計が99%を超える単量体等から得られる別の有機高分子化合物が既存の化学物質である場合。なお、目的とする有機高分子化合物の製造の場合であって、残り1%未満の重量割合を占める単量体等が新規化学物質である場合には、当該単量体等について新規化学物質製造・輸入届、少量新規化学物質確認申請等の手続がなされている必要があること。
(例:A-B-C共重合物において、A-B共重合物が既存の化学物質であって、AとBの重量の合計が99%を超えている場合。)
[2] 2種類以上の単量体等から得られる有機高分子化合物であって、その重量割合の合計が98%を超える単量体等から得られる別の有機高分子化合物が既存の化学物質であり、残り2%未満の重量割合を占める単量体等が既存の化学物質であって、かつ、当該単量体等が次のiからviまでのいずれにも該当しない場合。
i 安衛令第16条第1項に掲げる製造等が禁止される有害物等(ただし、第9号を除く。)
ii 安衛令別表第3に掲げる特定化学物質(ただし、第1号の8、第2号の38及び第3号の9を除く。)
iii 安衛令別表第5第1号及び第4号に掲げる四アルキル鉛及び加鉛ガソリン
iv 安衛令別表第6の2に掲げる有機溶剤
v 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第1条第1号、第3号、第4号に掲げる鉛、鉛合金及び鉛化合物
vi 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の17、第38条の18又は第38条の19により講ずべき措置が規定されている1,3-ブタジエン、1,4-ジクロロ-2-ブテン、硫酸ジエチル及び1,3-プロパンスルトン
(例:A-B-C共重合物において、A-B共重合物が既存の化学物質であって、AとBの重量の合計が98%を超えており、かつ、Cが既存の化学物質(ただし、i~viには非該当)である場合。)



