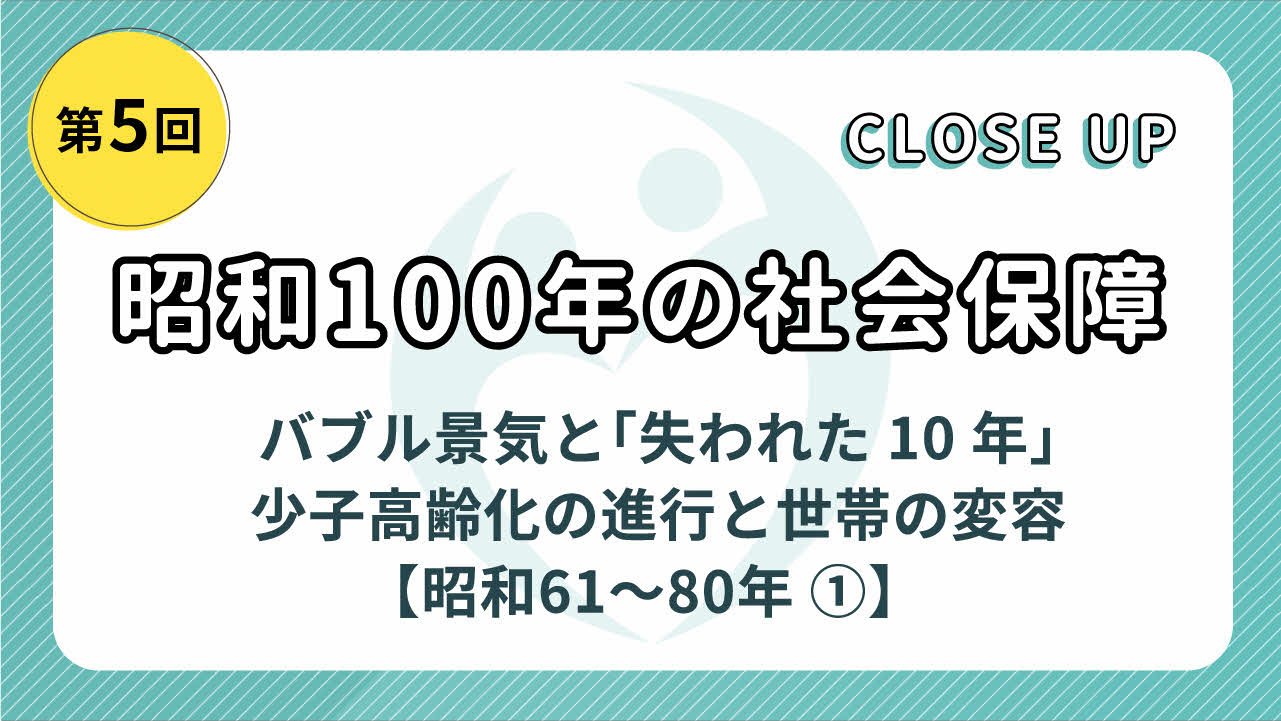- ホーム >
- 報道・広報 >
- 広報・出版 >
- WEBマガジン「厚生労働」 >
- 基礎年金の創設、介護保険の創設、基礎構造改革、少子化対策 昭和61~80年(1986~2005)【2】
基礎年金の創設、介護保険の創設、基礎構造改革、少子化対策 昭和61~80年(1986~2005)【2】
ー 昭和100年企画 全8回 ー
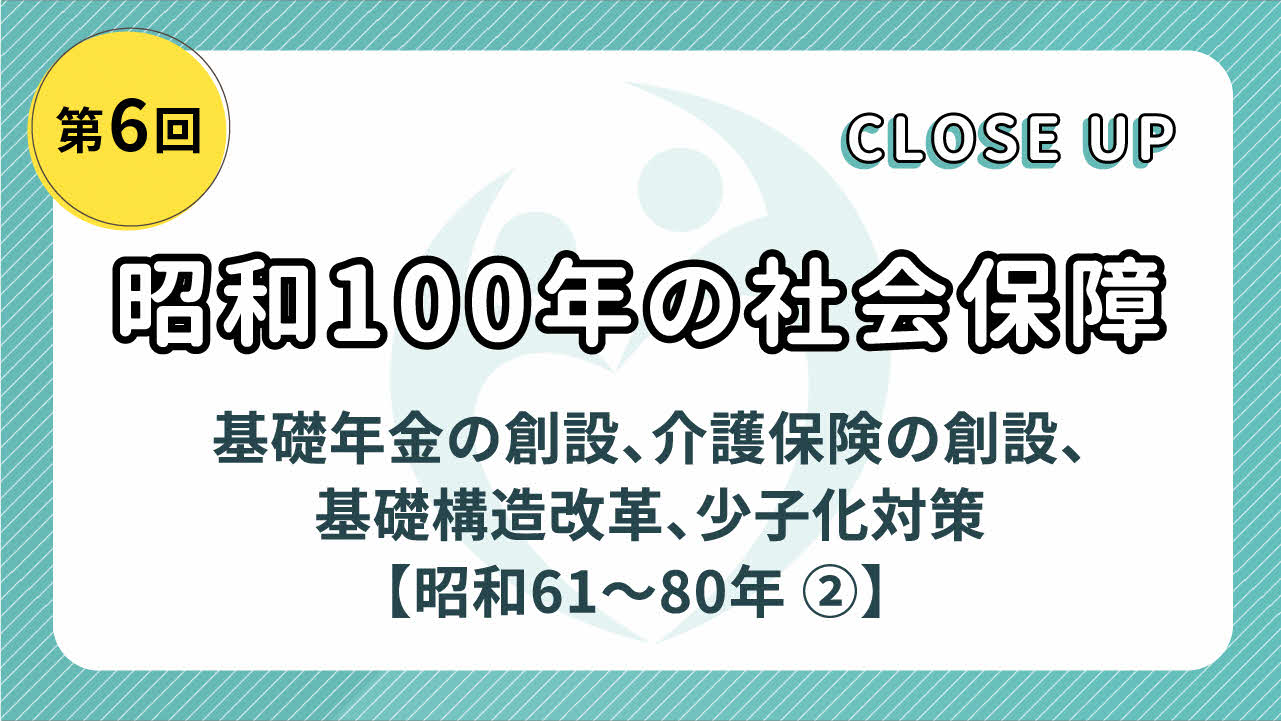
この年代は2回に分けてご紹介します。
前回はこの時期の社会変化について説明しましたが、今回はこの時期に導入された政策面の対応について解説します。
前回「第5回 昭和61~80年(1986~2005)①」
この時期の社会保障
基礎年金の創設、支給開始年齢の引き上げ
そのため、これ以降の年金制度改正は、長期的に制度が持続可能であるように、かつ、国民が納得できるように、「給付と負担のバランス」を図ることが重要な課題となります。あわせて、この時期には、国民皆年金としての保障を確保するために必要な所要の修正が行われました。
① 基礎年金制度の創設
そこで、全国民共通の基礎年金を創設するとともに、厚生年金等の被用者年金を基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成し、雇用労働者は上乗せで2階部分の厚生年金を受け取れるようにする構造改革が行われました。
同時に、それまで任意加入の位置づけだった「雇用労働者に扶養される配偶者」も基礎年金の対象とすることで、任意加入していないと離婚したり障害を負ったりしたときに年金制度の保障が受けられないという問題が解消されました。また、20歳前に障害の状態となった人に対しても、20歳から障害基礎年金が支給されるよう改められました( 1 )。
あわせて、厚生年金の給付水準と現役世代の収入とのバランスをとる趣旨で、給付額の計算方法が一部見直されました。
-
( 1 )これまで、20歳からの国民年金の加入期間前に障害の状態になった場合に、20歳に達したときから障害福祉年金が支給されていました。また、本来は「保険料を納付していること」が給付の前提となります。ただし、それでは20歳前からの障害者は障害年金を受け取れないので、国民皆年金の趣旨に照らして20歳から給付対象に加えられました。
② 支給開始年齢の引き上げ
それも「定額部分」「報酬比例部分」という2つのパートに分けて引き上げることとして、男性は昭和76(2001)年から昭和100(2025)年、女性は昭和81(2006)年から昭和105(2030)年という時間をかけての引き上げとなりました(女性については現在も引き上げの途上にあります)。
支給開始年齢の引き上げに伴い、60歳から65歳までの高齢者の雇用促進と所得補填が重要な政策課題となったことを受けて、「高年齢者雇用安定法」が改正され、昭和81(2006)年4月から、①65歳までの定年の引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入( 3 )、③定年の定めの廃止のうち、いずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが事業主に義務づけられました。
-
( 2 )60歳台前半の老齢厚生年金は、昭和60(1985)年改正で「特別支給の老齢厚生年金」という位置づけに改められ、昭和69(1994)年改正で定額部分についての引き上げが決まり、昭和75(2000)年改正で報酬比例部分の引き上げが決まった。
-
( 3 )昭和81(2006)年当時は、継続雇用にあたり企業側で対象者を限定する基準を設けることができる仕組みとしていたが、昭和88(2013)年からは、この基準を段階的に撤廃していき(経過措置)、原則として労働者が希望すれば、65歳までの雇用を確保することが事業主に義務づけられた。
なお、経過措置も昭和99(2024)年度末を以て終了し、本年4月からは、希望者全員の65歳までの雇用確保措置は全面施行となっている。
③ 保険料水準固定とマクロ経済スライド
この調整は、現役世代の人口減少や平均余命の長さ、経済成長などに応じて毎年の給付水準を引き下げる「マクロ経済スライド」という方法で行うものとされました。
介護保険制度の創設
こうした状況の中で、従来の老人福祉・老人医療制度による対応から、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして昭和75(2000)年4月、介護保険制度が創設されました。
介護保険制度では、高齢者の自立支援という基本理念のもと、それまで高齢者福祉サービスと高齢者医療サービスの双方に分かれていた介護サービスを、一つの制度として統合したほか、サービス提供事業者として社会福祉法人・医療法人・民間企業・農協・生協・NPOなど多様な主体に参入を認め、利用者が自らの選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられるサービスを選んで契約を結べる仕組みとしています。
また、介護保険制度は給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用しており、40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、介護保険料を毎月支払うこととなっています。
この保険料を財源の一部として介護保険サービスが運営されており、65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができるほか、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合に、介護サービスを受ける仕組みとなっています。
社会福祉基礎構造改革(措置から契約へ)
行政権限でサービスをあてがう方式=措置制度は、戦後間もない時期の圧倒的に供給が足りない状況下で、より優先度が高い人を確実に保護・救済するために実践され、その後も定着していたものでした。しかし時代が移り、少子高齢化、家庭機能の脆弱化、障害者の自立と社会参加の進展などにより、支援を必要とする対象範囲は国民各層へと広がることとなります。
社会福祉の諸制度は、かつてのような限られた人・世帯の保護・救済にとどまらず、生活課題を抱える人・世帯の「生活の安定」を支える役割を果たすことが求められたのです。
その社会的要請に応えるため、福祉サービスの参入規制を緩和して供給主体を増やし、事業者とサービス利用者を対等な立場であると位置づけ、利用者の選択と契約によるサービス利用を原則としました。こうして形成される「福祉サービス市場」で公正な競争と利用者保護が適正に行われるように、契約書の取り交わしが事業所に義務づけられ、サービス内容の情報開示、第三者評価、苦情解決の仕組みが法制化されました。これら一連の改正を「社会福祉基礎構造改革」といいます。
障害者福祉においては昭和78(2003)年度から、利用者がサービスを選択する利用方式(支援費制度)が始まりました( 4 )。
また、先ほど述べた社会福祉基礎構造改革の一環として、認知症や知的障害等で判断能力が十分でない状態の人も、新しい仕組みの下、契約の当事者として主体的に必要なサービスを利用できるように、意思決定や手続きを支援する事業として、「地域福祉権利擁護事業」( 5 )が新設されました。
-
( 4 )その後、昭和81(2006)年に「障害者自立支援法」が施行され、法律の裏付けのもと、国の費用負担を義務化して安定財源を確保し、介護保険の要介護認定のように支援の必要度を判定する「障害程度区分認定」や、定率1割の利用者負担の導入などが図られました。あわせて精神障害が新たに制度の対象に加えられ、既存の施設・事業体系が再編されました。
2010(昭和85)年には利用者負担に「所得に応じた負担軽減の仕組み」が組み込まれ、事実上の応能負担に見直されました。2012(昭和87)年には自立支援法に代わる「障害者総合支援法」が制定され、対象範囲への難病等の追加、給付の拡充など見直しが図られました。 -
( 5 )昭和82(2007)年度に「日常生活自立支援事業」と改称されています。
「子育てと仕事の両立支援」と「子育ての環境整備」
あわせて、共働き世帯の「育児との両立」を支援する趣旨で、「育児休業法」が昭和67(1992)年に施行され、出産後の産前産後休業に加え、子が1歳になるまでの間で希望する期間の育児休業を取得して職場復帰できる道が開かれました。加えて、原則満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した人に対して、給付を行う「育児休業給付金」が、雇用保険から支給されることになりました(昭和70(1995)年~)。
さらに、昭和78(2003)年には、仕事と子育てを両立しやすい職場づくりに向けて自治体や企業に行動計画の策定を義務づける「次世代育成支援対策推進法」と、少子化対策の理念や責務を規定した「少子化社会対策基本法」が制定されました。
医療費の自己負担引き上げ
サラリーマンらが加入する被用者保険の本人負担は、昭和59(1984)年9月までは初診時のみ800円の定額負担+入院後1カ月まで1日500円の定額負担とされていましたが、同年10月から1割の定率負担へと見直され、以後、昭和72(1997)年に1割から2割、さらに昭和78(2003)年に3割へと引き上げられました。
70歳以上の高齢者の自己負担は、昭和58(1983)年に老人医療費無料化が終了して「外来月400円、入院1日300円(2か月を限度)」の定額負担となっていましたが、昭和72(1997)年には外来の請求が1日単位に改められ(1日500円(月4回まで)、入院は1日1000円)、昭和76(2001)年には外来・入院とも1割の定率負担に刷新されました。その後、昭和77(2002)年には現役並みの所得がある高齢者について負担割合が「2割」に引き上げられました( 6 )。
また、入院中に提供される食事について、食材料費として「1日当たり600円」を患者に求める「入院時食事療養標準負担額」が、昭和69(1994)年から導入されました( 7 )。
-
( 6 )現役並み所得のある70歳以上の自己負担割合は、昭和81(2006)年には「3割」へと引き上げられた。
-
( 7 )以後、金額の引き上げが繰り返されて、現在では「1食あたり510円」となっている。
※本記事は、厚生労働省が中央法規出版(株)に委託し、中高生から高齢者まで幅広い層向けに作成したものです。
関連記事