自然毒のリスクプロファイル:二枚貝:記憶喪失性貝毒
詳細版
| 有毒種 | 記憶喪失性貝毒による毒化がみられた動物は、二枚貝類ではムラサキイガイ(図1)、イガイ、 ホタテガイ(図2)、マテガイなど、頭足類モンゴウイカ、甲殻類ダンジネスクラブ(ホクヨウイチョウガニ)、スベスベマンジュウガニ(図3)、魚類アンチョビーなどで、さらにこれらを摂食した水鳥やカリフォルニアアシカにも 記憶喪失性貝毒の蓄積がみられた[1, 2]。記憶喪失性貝毒は珪藻シュードニッチャPseudo-nitzschia属、ニッチャNitzschia属、アンフォラAmphora属によって 産生され、Pseudo-nitzschiamultiseries、Pseudo-nitzschiaaustrali、Pseudo-nitzschia seriatasのドウモイ酸産生能が高い。 紅藻フジマツモ科ハナヤナギ、サンゴモ科カニノテ、ケヒメモサヅキ、マサゴバシリ科ニセイバラノリなどから高濃度の記憶喪失性貝毒が検出された。
  図1 ムラサキイガイ   図2 ホタテガイ  図3 スベスベマンジュウガニ |
| 中毒発生状況 | 1987年にカナダで死者3名を含む107名の集団食中毒が初めて発生[3]して以降、記憶喪失性貝毒による中毒は起こっていない。 |
| 中毒症状 | 記憶喪失性貝毒による中毒症状は食後数時間以内に吐気、嘔吐、腹痛、頭痛、下痢が起こり、重症の患者では記憶喪失、混乱、平衡感覚の喪失、けいれんがみられ、昏睡により死亡する場合もある[3]。 |
| 毒成分 | |
| (1)名称および化学構造 | ドウモイ酸
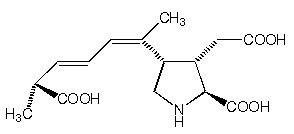 図4 ドウモイ酸の構造式 |
| (2)化学的性状 | ドウモイ酸は分子内に3つのカルボキシル基をもつ酸性イミノ酸で水に易溶だが、酸性下ではカルボキシル基の解離が抑制され水への 溶解度が低下し、不安定である。 |
| (3)毒性 | ドウモイ酸のマウスに対するLD50値は、腹腔内投与で4 mg/kgである[4]。マウス(体重20 g)にドウモイ酸50 μgを腹腔内投与すると、 後肢で腹部を激しくかきむしりながらぐるぐると回るスクラッチシンドロームとよばれる特徴的な動きを示す。 |
| (4)中毒量 | カナダの中毒事例では、軽症者ではドウモイ酸量60~110 mg、重症者では115~290 mgにも達した[3]。 |
| (5)作用機構 | ドウモイ酸は中枢神経伝達物質L-グルタミン酸のアゴニストとして作用して、神経細胞のイオンチャネル型グルタミン酸受容体に結合する。ドウモイ酸が脳に侵入した場合、海馬、視床、扁桃体細胞を壊死させる[5]。 |
| (6)分析方法 | ドウモイ酸の検査、定量は「食品衛生検査指針、理化学編」[6]に参考法としてHPLC-UV法が記載されている。試料を抽出溶媒(メタノール:水=1:1)で抽出し、遠心分離、遠心限外ろ過し、得られたろ液をHPLC分析に供し、242 nmにおける吸光度で検出、定量する。ドウモイ酸の分析にはLC/MSまたはLC/MS/MS法[7]が、検査法としてはELISA法[8, 9]も開発されている。 |
| (7)参考 | わが国では、記憶喪失性貝毒(ドウモイ酸)に対する監視体制や規制値は定められていないが、輸出する場合には外国の規制値(20 ppm)を準用する。 |
| 中毒対策 | 毒化した貝類の見極めは外見からはできず、一般的な調理加熱では毒素は分解しない。現時点では有効な中毒対策法はない。 |
| 文献 |
|
| 参考図書 |
|
厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課
水産安全係
電話 03-5253-1111(内線4244)



