健康・医療内分泌かく乱化学物質関係
内分泌かく乱化学物質について
ホルモン活性を有する化学物質が生体の内分泌系の機能を変化させることにより、健全な生物個体やその子孫、あるいは集団(またはその一部)の健康に有害な影響を及ぼす可能性が、一部の野生生物の研究や、基礎的な内分泌学、内分泌毒性学、生殖毒性学の研究から示されたことにより、厚生労働省はこの問題を一つの重要な検討課題と位置づけ、この問題の把握や作用のメカニズムの解明のため関係省庁・研究機関と連携を図りつつ、平成10年(1998年)4月から生活衛生局長 (当時)の私的検討会として、「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会」を設置し、現在に至るまでその検討を進め、それに必要な各種の研究を推進してきました。
内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会
| 検討会では、 | |
1.身の回りにあり人体に取り込まれる可能性のある数万種類に及ぶ化合物の、ホルモン活性や関連する特性、使用状況などを調査し、更に詳細に検討する優先順位付けを行う。 2.優先順位の高い物質から順に、実際に人々の健康に有害な影響を及ぼし得るか否かを詳細に検討(詳細試験)する。 |
|
と言う、2段階の手続きを踏む事と致しました。その理由として以下が挙げられます。 |
|
|
1.今までに既に規制を受けている化学物質の中で、ホルモン活性を有する事が判明した物質について、今までの化学物質の有害性を評価する方法に照らして緊急に「使用禁止」などの追加処置を必要とするものは、見つかっていない事(※1)。 2.詳細試験は、今までとは異なった視点から有害性を検討する必要があることが示されつつある事、即ち、胎児や新生児、小児から成人、老人、に至る一生涯を視野に入れ、且つ内分泌系のみならず、神経系、免疫系も考慮した、今までとは異なった試験法、あるいは今までの試験法を改良する事を検討する必要があるという事(※2)。
※1:内分泌かく乱化学物質問題が提起された当初は、生殖系への影響により子孫が生まれなくなるのではないか、と言う危惧が中心でした。実際に、野生生物に於いてその様な事例が示されましたが、その際の化学物質の暴露量(体が取り込んだ量)が人で想定される量よりもかなり多いこと、影響を受けたのが水棲動物であったり卵から孵る動物であったことなどが指摘されます。これらの動物は、性染色体の雌雄と実際に成体(おとな)になった時の雌雄が一致しない事がよくあり、性染色体が雌雄を厳密に決定する人やマウス、ラットなどの哺乳類と違う面を持っています。即ち、前者の動物では、もともと、性染色体が雌雄を決める決め手とならず、むしろ環境的な要因が決め手となっていることが詳しく分かってきています。これに対して後者では、性染色体(その中にある性決定遺伝子)が厳密に雌雄を決めています。 哺乳類の実験動物(ラットやマウス)を用いて検討したところ、生殖能力の低下を測定するために今まで通常に行われてきた試験(生殖毒性試験)では、人が曝される可能性のある量でのホルモン活性では、生殖機能に影響が観測されない事がわかってきました。 |
|
厚生労働省の取り組み
スクリーニング手法については、スキーム図の①、②及び③の試験をバッテリーとして適応することにより、数万種類の検討対象化学物質のホルモン活性を順次調べることが可能となっており、その結果を基に、詳細試験に資するべき物質の優先リストが提供されるようになります。
優先リストは、化学物質について新しい情報やスクリーニング試験の結果が得られると、化学物質の逐次ソーティング(並べ替え)(例えば、ホルモン活性が強い結果が得られた化合物は上位に、また、弱い結果が得られたものは下位に、化学物質の位置は移動する。)が行われることにより、時間とともにその内容が充実して行く様になっています。また、リストにはスクリーニング試験の結果以外の情報(生産など)を加味することが可能であり、包括的な優先順位付けが可能となっています。 優先リスト上位の化合物から逐次、詳細試験(現在開発中)を行うこととしております。その結果による有害性評価と、実際の暴露状況の評価を経て、リスク評価を行い、「要リスク管理」物質及び「リスク管理は当面不要」物質にふるい分けられ、前者については何らかの施策が講じられ、後者については新たな科学的知見により再評価が必要となるまで暫定的にholdされます(留め置かれます)。(この手順を踏まない例外として、農薬等、多世代試験などの大型詳細試験がすでに実施されている物質について、そのデータが内分泌かく乱性の評価に十分であると考えられた場合には、直ちに有害性評価、暴露評価、リスク評価を実施する場合があります)。
試験スキーム
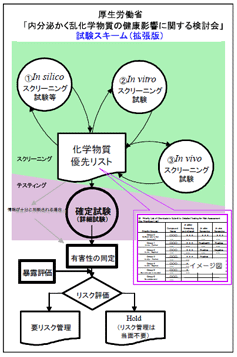
厚生労働省の取り組み(概要)
内分泌かく乱化学物質とは、内分泌系の機能に変化を与える外因性化学物質のうち生体に障害や有害な影響を起こすものを指すが、現時点では、合成ホルモン剤の薬理効果のような例を除けば、ヒトに対して内分泌かく乱作用が確認された事例はない。この点については、平成13年に中間報告書追補を取りまとめた時点と大きく変わっていない。
中間報告書追補において提示された行動計画について、これまでの取組の成果と、今後更に進めるべき具体的課題の概要は、以下のとおりである。
また、これらを踏まえ、中間報告書追補で策定された行動計画についても更新・見直しを行った。
第1章 重点課題の検討成果と今後の取組
第1節 試験スキーム
〔取組の成果〕
1 スクリーニングについては、①In silico スクリーニング(電算機内予測)、②細胞系、無細胞系を用いたin vitro スクリーニング試験、及び③卵巣摘出動物又は幼若動物、あるいは去勢動物等を用いたin vivo 試験が実施され、データの蓄積が進んだ。
2 確定試験(詳細試験)については、生体の成長過程(胎児期・新生児期・思春期)や生体反応(神経系、内分泌系、免疫系などの高次生命系に及ぼす変化)を包括的に検討する試験法の開発を進めている。
〔今後の取組〕
1 試験系を構成する各試験についてガイドライン及び評価基準を整備する。
2 精度及び網羅性の高いスクリーニング手法の開発整備を行って、ホルモン様作用(低用量域の作用を含む)を有することが生物学的に説明可能な物質の順位付け、リスト化を継続かつ高度化する。
3 そのためにスクリーニング試験に関しては、エストロゲン受容体に加え、アンドロゲン受容体、甲状腺受容体系等を加え、強化スキームを検討する。
4 マイクロアレイ技術を用いたパスウェー・スクリーニングを第4の項目として追加することを検討する。
5 詳細試験に関しては、神経・内分泌・免疫ネットワークの発生・発達・成熟・老化を考慮した「げっ歯類一生涯試験法」を開発する。
6 リスク評価を行い、ヒトに対する内分泌かく乱作用の可能性があると判断された物質に関して、暴露の実態も踏まえた上で、用途制限や監視等必要な法的措置又は行政措置を講ずる。
第2節 採取・分析法
〔取組の成果〕
1 中間報告書追補(平成13年12月)において暫定的に取りまとめられた「食品中の内分泌かく乱化学物質分析ガイドライン」について、必要な情報を収集し、再検討した結果、改訂すべき根拠となる新たな知見は得られなかった。
2 生体試料中の低濃度の化学物質を分析するための一般試験法、及び生体試料中に混入する3種の化学物質(ビスフェノールA、フタル酸エステル類、ノニルフェノール)の分析ガイドラインを取りまとめた。
3 実験動物の飼育飼料中に存在する化学物質を分析するための一般試験法、及び飼料中に混入する可能性のある3種の化学物質(ビスフェノールA、フタル酸エステル類、ノニルフェノール)の分析法についてガイドラインを取りまとめた。
4 実験動物について、飼育環境及び実験環境からの化学物質暴露の状況を調べるため飼料、床敷等中のビスフェノールA、フタル酸エステル類、ノニルフェノール、植物エストロゲン、エストラジオールの含有量を測定した。その結果、これら化学物質が検出されたサンプルもあったことから、動物実験の実施に際しては、用いる飼料、床敷等のロット番号、入手可能な当該化学物質の分析データを明示するとともに、必要に応じて基礎暴露量を正確に把握するために飼料等中の化学物質濃度を測定して、論文、報告書等に記載する等の配慮が必要である。
〔今後の取組〕
1 効率の良い分析法やより精度、感度に優れた分析法の構築に関して情報収集を行い、分析ガイドラインの充実を図る。
第3節 低用量問題
〔取組の成果〕
1 内分泌かく乱作用については、成体では、内在性ホルモンへの適応があることやこれまでの調査研究結果から、さしあたり障害性の焦点にはならないものと判断される。
2 一方で、胚細胞期・胎生期・新生児期・思春期といった形態形成期、機能が安定する前の時点における影響を糸口にした作用機構の解明が研究の焦点となりつつある。
3 低用量問題は、同時に取り上げられた閾値問題、相乗・相加性、用量相関問題などを構成要素とし、相互に密接な関連をもつ。
4 内分泌様活性をもつ化学物質の作用機構の解明や、アリールカーボン受容体とエストロゲン受容体シグナルの相互作用関係の認識などから、作用機構の多様性が判明しつつあり、このことが低用量問題や複合効果の解明にも影響をもつと考えられる。
5 内分泌かく乱作用として、生殖系、免疫系、神経系など、いわゆる高次生命系への影響が焦点となっており、種々の試験結果が明らかになりつつあるが、未だ不明な点が多く、さらに作用機構を解明するための取組が求められる状況にある。
6 なお、問題の解明の中で、膜受容体が発見され、遺伝子機能を介さないホルモン様作用について理解が進むとともに、現状では未知の要因が介在していることを念頭において検討を進めることの意義も喚起された。
〔今後の取組〕
1 低用量問題を解明するため、以下の調査研究を進める。
・低用量域のホルモン様作用を検出する実験結果の再現性に関する問題を克服するための調査研究
・高感受性期としての胎生期・新生児期・思春期における暴露による内分泌かく乱作用について、作用機構の解明や評価基準決定のための調査研究
・高感受性期において低用量で作用が発現したとの試験結果に関して、継続的及び系統的な情報収集、並びに①閾値問題、②非線形の用量相関、③相加反応などの問題を踏まえた、試験結果の解釈のための調査研究
・免疫系、甲状腺―中枢神経系・行動などの高次生命系に与える影響を検討するための調査研究
・ゲノミクス手法を利用した知見の調査研究
2 内分泌かく乱性に関する試験の評価に関する包括的なガイドラインを策定する。
第4節 暴露疫学等調査
第4-1節 生体暴露量等
〔取組の成果〕
1 以下の物質について、生体試料(血液、尿、毛髪等)中の濃度を測定した。 ビスフェノールA、クロロベンゼン類、パラベン類、フタル酸エステル類、ベンゾ(a)ピレン、PCB、ダイオキシン類、クロルデン、有機スズ化合物、4-ノニルフェノール、ハロゲン化炭化水素系殺虫剤、有機リン系殺虫剤、有機塩素系殺虫剤、有機フッ素系化合物、植物エストロゲン、重金属、揮発性有機化合物 (なお、物質ごとに研究対象者、測定に用いた生体試料等が異なっている。) クロルデン以外の上記物質は、いずれかの生体試料中に含まれており、環境中暴露の点から問題となりうる。
2 生体暴露量を検討していく過程で、ビスフェノールA は代謝されて血中から速やかに消失すること、また、フタル酸エステル類は体内でモノエステル又はジエステル型に代謝されることが明確になった。
〔今後の取組〕
1 引き続き、内分泌かく乱作用が疑われる環境汚染化学物質について、同一母体の複数部位からの生体試料(さい帯血等を含む)の採取及び濃度分析データの蓄積を行うことにより、母体からの暴露の実態を解明する。
2 これらの物質の生体内に存在する量(体内負荷量)の範囲で、生体にどのような作用を発現するのか否か、代謝・解毒の全容も含めて明らかにする。
3 今後、生体試料中の分析を進めると同時に環境中の値(バックグラウンド値)を経時的に観測することによって生体暴露の影響を評価する。
第4-2節 疫学研究
〔取組の成果〕
疫学研究の現状について、文献的考察を行った。
1 有機塩素系化合物などの化学物質と、乳がん、子宮体がん、卵巣がん、前立腺がん、精巣がん、甲状腺がんについての疫学研究からの報告が複数あったが、関連があることを支持するには、依然として知見は不十分である。
2 高濃度のPCB 暴露が、甲状腺機能に何らかの影響を及ぼしているという複数の研究があるものの信頼性の高い報告はなく、関連があることを支持するには、依然として知見は不十分である。一般環境レベルでのPCB 暴露やその他の有機塩素系化合物との関連について言及するには、依然として知見は不十分である。
3 器官形成にかかわる問題のうち、尿道下裂については、1 件のコホート研究でDES による有意なリスクの上昇が示されていた。停留精巣については、1 件の介入研究でDESによる有意なリスクの上昇が示されていた。DES については、器官形成への影響があるとする限定的な報告があるが、関連があることを支持するには依然として知見は不十分である。その他の化学物質については、疫学研究はほとんど存在せず、関連について言及するには、依然として知見は不十分である。
4 有機塩素系化合物による小児神経発達への影響については、複数の地域でのコホート研究からの報告があるが、他の要因による影響や、暴露・神経発達双方の評価指標や評価時期などが多様であり、関連があることを支持するには、依然として知見は不十分である。
5 精子数低下については、化学物質の高濃度暴露群での質の低下について複数の報告があったが、精巣毒性による影響である可能性があり、内分泌かく乱作用によることの関連を支持するには、依然として知見は不十分である。
6 免疫機能への影響についての検討を今回追加したが、成人期の高濃度PCB 暴露がアレルギーのリスクを増加させるという報告や、胎児期乳幼児期の一般環境レベルの暴露がアレルギーのリスクを減少させるという報告があり、結果が一致せず、関連について言及するには、知見は不十分である。
7 日本人を対象とした疫学研究の報告は、依然としてほとんどない。
〔今後の取組〕
1 日本国民の代表となりうる対象者を設定し、
・内分泌かく乱作用が疑われる化学物質の暴露
・その影響が懸念される疾病 についての現状把握と継続的な監視を行う。
2 主として日本人を対象とした、生体試料の収集と利用を含めた、疫学の方法論に基づく相当規模の研究を進める。
3 いわゆる内分泌かく乱作用が疑われる化学物質のヒト健康影響に関する研究を継続的に総括(刊行論文のレビュー及び更新)し、その成果を継続して広く国民に周知する。
第5節 リスクコミュニケーション
〔取組の成果〕
1 内分泌かく乱化学物質問題の特徴を以下のように整理した。
・提出された仮説が従来の化学物質の有害性発現の概念を超えるものであったこと
・事実ならば大変な問題であるが、その検証が容易ではない仮説であること
・実際に仮説検証作業が始まってからも、研究者の間で意見が別れるほど相反する結果が報告されていること
・従来の科学的(毒性学的)手法では予測できない結果(逆U字現象など)が報告されていること
・現在までに合成ホルモン剤の薬理効果のような例を除けば、ヒトに対して内分泌かく乱作用が確認された事例は認められておらず、有害性の内容や対象化学物質が明らかになっている従来の化学物質管理とは大きく異なること
2 その上で、厚生労働省と国民の間の情報や意見の交換にあたって、特に行政が国民に情報等を発信する場合の方法や留意点をまとめた「内分泌かく乱化学物質問題のリスクコミュニケーションガイドライン」を作成した。
3 リスクコミュニケーションに資するため、本書の概要の解説を試みた。
〔今後の取組〕
1 リスクコミュニケーションを継続的に実施し、その結果を改善に生かす。
内分泌かく乱化学物質のQ&A
ビスフェノールAの低用量影響について
| ビスフェノールAについては、近年、動物の胎児や産仔に対し、これまでの毒性試験では有害な影響が認められなかった量より、極めて低い用量の投与により影響が認められることが多数報告されており、妊娠されている方(これらの方の胎児)や乳幼児がこの物質を摂取すると影響があるのではないかという懸念が持たれています。本ページでは、ビスフェノールAの低用量影響に関する報告の概要及び関連するサイトの情報をまとめています。 | ||||
| Medline等の公開情報において、『Bisphenol A』を検索単語とし、2012年から1997年までの約5500の文献から、1日の体重当たりの投与量単位がマイクログラム及びそれ以下の領域で実施された実験を抽出し、内容を吟味の上選択した約120文献について、動物種、投与時期、投与経路、投与量、影響などの情報を整理し、表にまとめたものである。 | ||||
| 厚生労働省 | ビスフェノールAについてのQ&A | |||
| 食品安全委員会 | 食器などのプラスチック製品に含まれるビスフェノールAに関するQ&A | |||
| US FDA | Bisphenol A (BPA): Use in Food Contact Application | |||
| US NIEHS | Questions and Answers about Bisphenol A | |||
報告書等
○内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会
○研究報告書等[244KB]
○その他の研究費で行われた研究報告書
2017年度「体外受精による出生児の健康及びフタル酸類の受精卵及び出生児に対する影響に関する文献調査」[306KB]
国際機関の関連報告
| |
|||
| Global Assessment of The State-of-The-Science of Endocrine Disruptors(原文) | |||
| 内分泌かく乱化学物質の科学的現状に関する全地球規模での評価(厚生労働省版:日本語訳) | |||
| State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012 | |||
| Full report(原文) | |||
| Summary for Decision-Makers (原文・日本語訳PDF[2.4MB]) | |||
| |
|||
| Workshop report on oecd countries activities regarding testing, assessment and management of endocrine disrupters (22-24, September 2009, OECD) | |||
| OECD加盟各国における内分泌かく乱化学物質の管理に関するワークショップ報告(PART2部分の日本語訳:国立衛研) | |||
| |
|||
| EDSP21 Work Plan Summary Overview(原文・日本語訳PDF[369KB]) | |||
| Weight-of-Evidence: Evaluating Results of EDSP Tier 1 Screening to Identify the Need for Tier 2 Testing(原文・日本語訳PDF[682KB]) | |||
| |
||
| Endocrine disruptor関連情報 | ||
| |
||
| Endocrine disruptor関連情報 | ||
| State of the Art of the Assessment of Endocrine Disruptors Final Report (原文・日本語訳PDF[1.6MB]) |
||
| |
||
| Key scientific issues relevant to the identification and characterisation of endocrine disrupting substances: JRC Report 2013(原文) | ||
| Information sources and databases on Endocrine Active Substances: 2011(日本語訳PDF[598KB]) | ||
| The JRC Vision for an Endocrine Active Substances Database and Web Portal: 2010(日本語訳PDF[510KB]) | ||
| |
||
| Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: EFSA Journal 2013;11(3):3132 (原文・ 日本語訳PDF[1.3MB]) | ||
| |
||
リンク
お問い合わせ先
医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
TEL:03-5253-1111



