- ホーム >
- 報道・広報 >
- 広報・出版 >
- WEBマガジン「厚生労働」 >
- 未来(あした)のつぼみ
未来(あした)のつぼみ
マクロとミクロの両方の視点で 人材開発行政に取り組みたい
大きな制度改正に限らず、日々の地道な積み重ねが厚労行政の可能性を広げています。ここでは、厚生労働省の若手職員たちの取り組みや気づきを紹介します。

坂井眞子
人材開発統括官付人材開発政策担当参事官室 政策係員
私は、人材開発統括官付人材開発政策担当参事官室に所属し、人材開発政策の企画立案および調整、企業内外の学び・学び直しやデジタル人材の育成に取り組んでいます。
少子高齢化および人口減少が進行し、働き手の確保がますます重要となるなか、デジタル社会の進展など企業・労働者を取り巻く環境は大きく変化しており、長い職業人生で労働者に求められる役割・知識・スキルも変わっています。そのような状況を踏まえ政府においても、「リ・スキリングによる能力向上支援」を三位一体の労働市場改革の柱の一つとして掲げ、「デジタル人材の育成」「個人の自律的な学びの支援」など各支援施策の充実を図っているところです。
一方で、当省で実施している能力開発基本調査を見ますと、自己啓発を実施した労働者の割合は、令和5(2023)年調査で正社員では44.1%、正社員以外では16.7%と約10年間横ばいとなっており、自律的な学び・キャリア形成の必要性について十分な理解を得られていない状況があります。
私は現在、職業能力開発促進法に定める職業能力開発基本計画の策定に向けた業務に携わっています。現在の第11次職業能力開発基本計画は今年度が最終年度になることから、来年度から令和12(2030)年度までの5年間の次期計画を策定する時期に入っており、同計画の策定に向けた検討会を実施し、検討会に関する資料作成、関係者との調整などを行っています。
上記のとおり労働環境がめまぐるしく変化している一方、学びに対する個人の意識がなかなか上がらない状況下で、今後必要なことは何かを考えるのは非常に難しいと感じています。
また、今年度は2カ月間、労働局研修に行かせていただきました。そこでは、個々の労働者の働き方や中小企業の人事の方々の考え方を知ることができ、当省施策の受け手を想像して発信をする重要性に気づくことができました。人材開発行政は社会や個人の意識の変化を映すもので、非常に前向きなものと捉えています。世の中にアンテナを張りながら、マクロとミクロの両方の視点を常に持ち続け業務に励みたいと考えています。
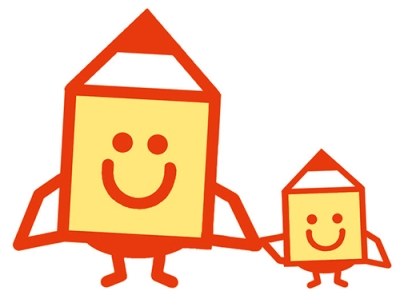
「ハロートレーニング~急がば学べ~」のロゴマーク
▶第11次職業能力開発基本計画についてはこちら
| 出典: 広報誌『厚生労働』2025年3月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |



