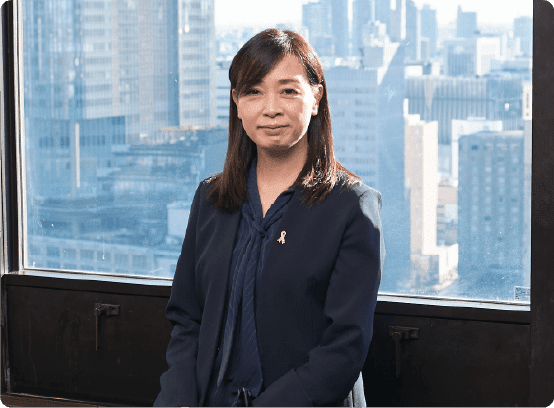子育てをしながら
社会に貢献する喜び
健康・生活衛生局移植医療対策推進室長島田 志帆SHIMADA Shiho
平成16年入省。難病・アレルギー対策、環境保健(環境省出向)、がん対策、国際保健、医師確保等医療政策、新型コロナウイルス対策(医療担当)、医学教育(文科省出向)担当等を経て、令和6年8月より現職。
医科ベテラン・管理職
医療政策国際保健・留学ワークライフバランス
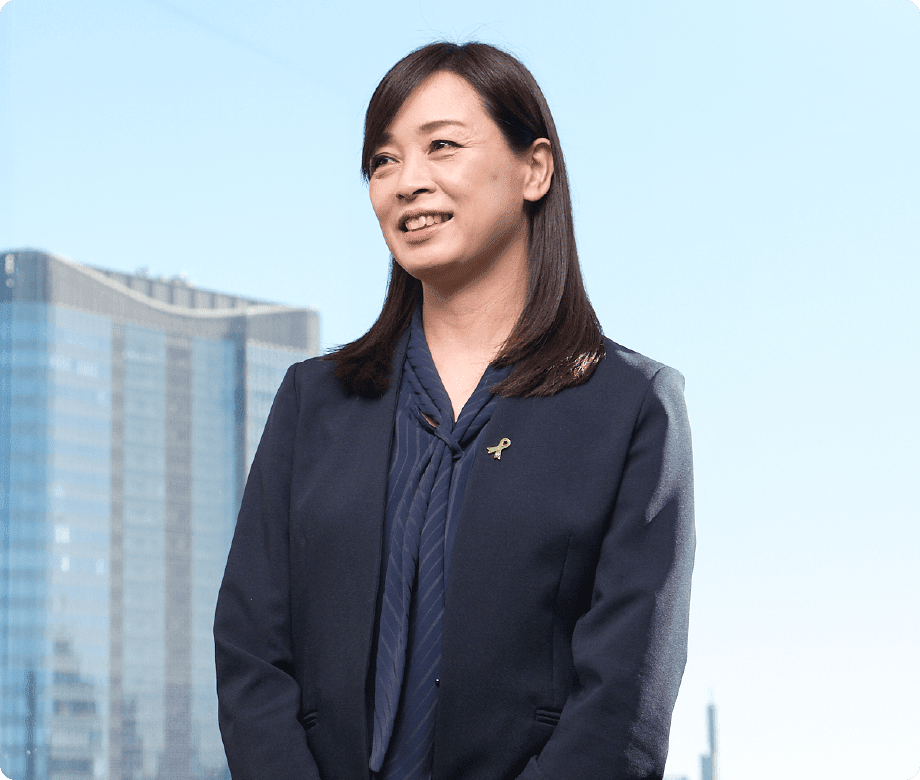
平成16年入省。難病・アレルギー対策、環境保健(環境省出向)、がん対策、国際保健、医師確保等医療政策、新型コロナウイルス対策(医療担当)、医学教育(文科省出向)担当等を経て、令和6年8月より現職。
医科ベテラン・管理職
医療政策国際保健・留学ワークライフバランス
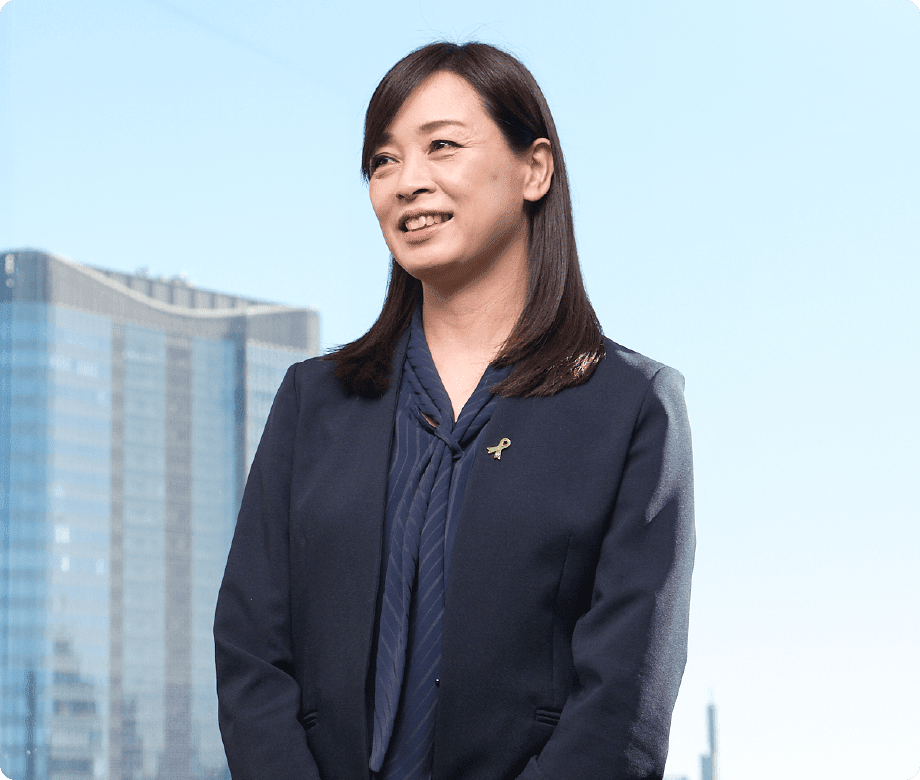
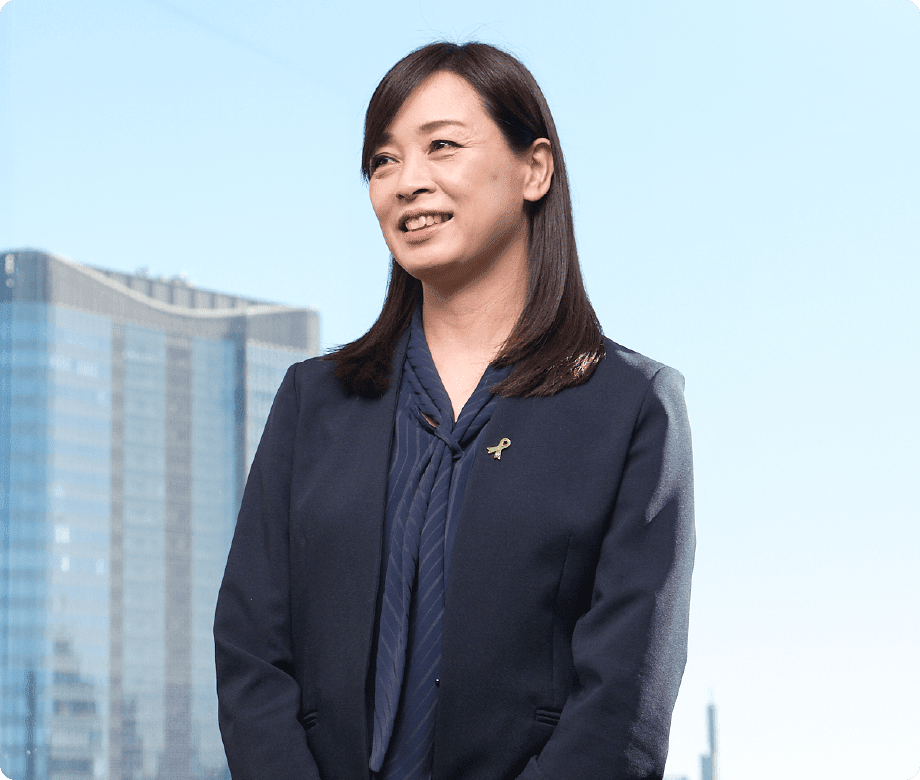
この思いを抱いたのは、医学部3年生の時に、歯科医師である父に同行し、ネパールの歯科医師のいない村で、NGO活動を行った経験からです。それまで、臨床医として来院患者を診るというイメージを持っていましたが、村の方々に歯磨き指導を行ったことで、個々の患者を病院で待って診療するのではなく、集団や社会に対して自ら働きかけることの重要性に気づきました。医師として、仕組みを作り、より大きな影響を与える仕事ができる医系技官に魅力を感じ、私のキャリアが始まりました。
患者の命を守るための政策を実現するためには、広い視野を持ち、戦略的に物事を進める能力が求められます。入省から20年以上が経ちました。失敗やつらいこともありますが、日々新たな課題に挑戦し続けることにやりがいを感じています。異動が多くて大変ではないかという指摘もありますが、どの部署でも必要なスキルは共通しており、知見は雪だるま式に広がり、専門性の幅と深みが増していきます。それぞれのポストには学びややりがい、出会いがあり、視野がどんどん広がっていきます。一見関係がないように思えるポストも、後から見ればつながっています。各部署での仕事を通じて多くの方々に出会えたことに感謝しています。
入省後は1~2年おきに部署を異動し、様々な保健医療施策を担当しました。
学生時代から憧れていた国際保健分野には計3回携わり、日本政府代表団の一員として世界保健機関(WHO)総会(ジュネーブ)に参加しました。ここでは、WHOが作成するガイドライン案に対して日本の立場を反映させるべく、会議での発言や、他国の支持を得るためのバックヤードでの調整も行いました。日本が達成したユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(すべての人が適切な保健医療サービスを支払い可能な費用で受けられる状態)を世界に広めるために、どのように日本が貢献できるかについては大きなアジェンダでした。
文部科学省に出向し、2050年ごろの未来社会を見据えた医学部教育改革にも取り組みました。人口構造の変化や科学技術の進展により、医療の現場は急速に変化しています。基礎疾患を有する高齢患者の割合のますますの増加、地域医療の重要性の更なる拡大、災害リスクエリアに居住する人口割合の増加‥日本の未来予想図を医学部の先生方と共有し、喧々諤々の議論を経て、医学部教育において患者や生活者を総合的にみる姿勢を養う資質・能力の位置づけを行い、モデル・コア・カリキュラムを改訂しました。
現在は移植医療政策を担当しています。患者と移植医だけでは成立せず、ドナーとのつながりが不可欠な特殊な医療であり、行政の役割(仕組み作り)が重要です。現在、日本の臓器移植は他国と比べて少ない中、臓器提供の意思のある方の臓器が希望する患者に確実に移植されるよう、救急や脳外科等の提供医、あっせん機関、移植医に加え、ドナー家族や移植経験者、法律家やマスコミ等とも連携し、政策改革を進めています。具体的には、現在臓器移植ネットワークのみが担っている臓器のあっせんを複数の機関で行い、移植希望患者が複数の移植医療機関に登録できるようにするなど、制度運用の改善に取り組んでいます。
私は臨床医としての経験1年で入省しました(臨床研修必修化前)。たった1年でも、臨床経験が行政での企画立案に活きていると感じています。例えば、ERで「何度も救急受診を繰り返す患者には、病院で待つのではなく、社会環境を変えることで助けられるのではないか」といった問題意識を持ったことは、現在厚生労働省で保健医療行政に携わる原点となっています。また、患者診療の実際をはじめ、当直・オンコール等の医師の働き方、電子カルテ・検査オーダーの運用といったちょっとしたことでも、実際に経験しているかどうかで、施策の企画立案の質は大きく異なると実感しています。
最近では、臨床経験を長く積んでから入省する方も増えました。このHPを読んでいる方の中にも「臨床が長く、これまで行政と関わる機会がなかったが、大丈夫か」と心配される方がいるかもしれません。確かに若い頃に入省して行政経験を積むことはキャリアの強みとなりますが、臨床経験は必ず厚生労働省で役立ちます。行政のいろはは優しい(笑)先輩方が教えてくれますし、最近はeラーニング中心に研修も充実しています。
厚生労働省は敷居が高く堅苦しそうな印象を持たれるかもしれませんが、身構える必要はありません。医系技官採用HP等で案内されるセミナーやインターンに一度参加してみてください。堅苦しいどころか、「柔らかい」医系技官が多いことに驚かれるかもしれません。私も学生時代に医系技官の先輩と交流し、「こんな面白い人たちと働きたい」と感じたことを思い出します。
若いうちに入省すると、キャリアの早い段階から多くの貴重な経験を積むことができます。その中でも、留学の機会は特に大きな可能性を広げてくれます。私自身、入省から5年目にハーバード公衆衛生大学院で学位を取得するチャンスを得ました。日本の医師が一般的に「留学」する際、その多くは研究留学等の学位取得を伴わないものですが、学位を取得する留学は、構造的に当該分野を学ぶことができます。ハーバードでは、公衆衛生・疫学の基礎的な知識をはじめ、社会行動科学や経済効果分析、人口学、マスコミ対応、リーダーシップ論等、幅広い分野を学びました。ハーバード大学は、世界中から優れた学生を集め、次世代のリーダーを育成することに情熱を注いでいます。世界各国から集まった留学生との交流は非常に刺激的で、多様な文化や価値観に触れることで、視野が一気に広がりました。日本の医療システムや公衆衛生政策が国際的にどのように評価されているかを理解し、日本の強みや改善点を再認識することができたことは、私にとって意義深いものでした。
また、卒業後、多くの院生が在学中に行う就職活動を経ずとも、学んだ知識を活かしてすぐに実務に携わることができるのも、行政官として留学する大きな強みであると思います。
令和7年1月現在、小学校6年生と保育園年長児の2人の子どもを育てながらフルタイムで仕事を続けています。子育てとの兼ね合いで泊まりの出張は難しい状況ですが、日帰りで全国を出張し、病院の先生方と意見交換を重ね、現場の課題に取り組んでいます。
子育てをしながら社会に貢献する仕事を責任ある立場で続けられていることは幸せなことだと思います。家事や育児をしながらの毎日は大変ですが、職場や周囲の理解と支えがあってこそ、なんとか両立できていると実感しています。家族、保育園や学童、職場の方々、元気に育つ子どもたちに、感謝の気持ちでいっぱいです。
大変なこともありますが、仕事で行き詰まっても家族に癒やされ、逆に子育てで行き詰まっても職場での居場所が心の支えになることもあります。また、子育てをしていると、例えば子どもの健診や予防接種、学校での健康教育など、霞ヶ関で企画立案する施策が現場にどのように浸透しているか、エンドユーザーとして見る機会が多く、仕事にフィードバックできます。普段仕事では接することのないような様々なバックグラウンドを持つママ友との交流を通じて、世界が広がっているとも感じます。こうした多角的な視点を持てる点は、子育てをしながら仕事をすることのメリットのひとつだと感じています。
テレワークや有給休暇を活用し、子どもの学校行事や体調不良等にも柔軟に対応しています。土・日・祝日は基本的に仕事は休みで、業務の状況に応じて夏季休暇や節目休暇も取得可能です。
厚生労働省では、育児や介護をしながら常勤で働き続けられる職場環境を整える意識が、病院勤務時よりも高いように感じます。もし臨床の現場で勤務していたなら、このような責任ある立場で仕事を続けるのは難しかったかもしれません(最近はそういった意識の高い臨床現場が以前より増えていると聞いてはいますが)。
「興味のあることにはまず数年、一生懸命取り組んでみなさい。その知識・経験・人間関係が次の分野での強みとなる。」
大学の恩師の言葉です。医系技官に関心があるものの、95%以上の医師が歩む臨床医としてのキャリアと悩んでいた頃、この言葉に背中を押され、厚労省に入省しました。臨床への恋心は今もありますが、医系技官として臨床にリスペクトを持ちながら仕組み作りに取り組むことに大きな意味を感じています。
関心を持ってこのHPを読んでくださったあなた、是非一緒に仕組み作りで人の役に立つ仕事をしませんか。