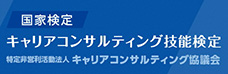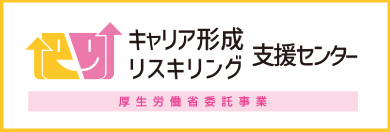グッドキャリア企業アワード2024
企業向けセミナー(名古屋)
を開催しました!
令和7年2月4日(火)、ツドイコ貸会議室(名古屋)において「グッドキャリア企業アワード2024企業向けセミナー」を開催しました。当日は企業の経営者、人事労務担当者を中心にご来場いただき、厚生労働省による挨拶、アワードの審査委員も務められた廣石忠司氏(専修大学経営学部 教授)による基調講演、及び、2024年度受賞企業3社を交えたパネルディスカッションを実施しました。
開会挨拶
厚生労働省の挨拶として、佐藤悦子人材開発統括官付参事官(若年者・キャリア形成支援担当)付キャリア形成支援室長より、「人口減少やデジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、労働環境が急速に変化している。この変化に対応し、経済社会の発展を支えるためには、従業員が自らのキャリアビジョンを持ち、自律的にキャリア形成に取り組むことが重要である。厚生労働省は、こうした取組を積極的に推進している企業を『グッドキャリア企業』として表彰しており、本日のセミナーでは、受賞企業の取組紹介を通して、キャリア形成支援の重要性について理解を深めていただきたい。」と述べました。
基調講演
「組織に求められるこれからのキャリア形成支援」をテーマに、廣石忠司氏(専修大学経営学部 教授)による基調講演を行いました。
《基調講演概要》
1.キャリア形成支援施策推進の障害にはどういうものがあるか
「キャリア施策は、皆他人事」と考えている組織が多く、人事担当者として頭を悩ませている方も多いのではないか。
従業員からは・・・なんでこんなことをやるのか?
管理職からは・・・キャリアは自分で考えること
役員(経営者)からは・・・重要なものだと思うから、人事がやれ
どうしても動かない従業員は、危機意識がないと動かない組織開発の問題と同じである。キャリア意識がなければ流されるだけ、リスキリングしなければ現状維持にとどまるだけとなり、動かなければ「将来は自分の仕事がなくなるかもしれない」という感覚をどうしたら持ってもらえるかを考えなければならない。
2. どうすればその障害を乗り越えられるか
【 問題=理想-現実 】
理想がなければ問題は見えず、現実を把握しなければ問題は見えないため、まず現実を直視すること、すなわち従業員にとって現在の仕事はどのような意味合いなのか、それぞれの個人の考え方をとらえることが重要となる。
組織の中で個人の考え方をとらえる場は1on1ミーティングの場であり、個人のキャリア形成の要は、1on1ミーティングを担っている「管理職」であると言うことができる。プレイングマネージャーの場合が多い「管理職」が、いかに「部下の育成」を自分の仕事と意識して取り組める環境を作るかが鍵になる。例えば、「優秀な人材を他部門に転出させた管理職の評価を高くする。」等、部下のキャリア支援を人事考課の評価項目に設定するというのは一つの方法である。また、キャリア支援の意味を実感させるために、社長は役員に、役員は部長に、部長は課長にといったように、実際に上長からの1on1を体験する等して、意味があると実感できれば実践できるはずではないだろうか。
3. 究極的に人事部がめざすべきこと
今まで述べてきたことを実現するためにはトップの理解がまず必要である。 新しいことを始める時は必ず抵抗する人達が出てくるため、キャリア施策を展開する場合の第一歩として、経営トップを味方につけることがとても大切である。
経営トップの理解を得るためには、最初の段階で小さくても良いから実績づくりを行うことが有効である。例えば、「離職率の低下」「モラール サーベイの結果向上」「資格の取得者数の増加」「キャリア相談窓口への訪問件数」といった実績を、可視化して示すことが説得力を持つことになる。
そして、経営トップに期待されるのは、社員のキャリア形成支援を「自分ごと」として捉え、できれば自ら動いてもらうことである。本年度のアワード「大賞」受賞の西日本電信電話株式会社様と住友生命保険相互会社様は、自分からメッセージを発信し、場合によっては自ら話をしている。それにより会社の本気度が社員に伝わり、経営トップが旗を振り全社的運動としてキャリア形成支援という風土をつくっていく。それが最終的な目標になるのではないか。グッドキャリア企業アワード2024受賞企業の好事例等も参考にしながら、Attraction&Retention(魅力のある、社員がやめたくないと思える企業)を目指していただきたい。
☞受賞企業の好事例はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/career-award/past_winners.html
パネルディスカッション
コーディネーターに廣石氏を迎え、グッドキャリア企業アワード2024受賞企業3社の代表者、人事担当による取組・事例紹介をはじめ、パネルディスカッションを行いました。
<コーディネーター>
廣石 忠司 氏 専修大学経営学部 教授
<パネリスト>
グッドキャリア企業アワード2024大賞:
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キャリアデザイン支援室室長(人事部長兼務) 釘本 健太郎 氏
グッドキャリア企業アワード2024イノベーション賞:
株式会社就労センター 代表取締役 長井 映樹 氏
株式会社デンソー 人事企画部 担当係長 杉浦 秋彦 氏
<パネルディスカッション概要>
パネルディスカッションでは、前半に各社パネリストが自社のキャリア支援における主要な取組について解説した。キヤノンマーケティングジャパン株式会社の釘本氏は、退職理由を分析し、把握した課題をもとに、様々なキャリア支援施策を展開していく自社のキャリアデザイン支援室のアプローチ方法について語った。きっかけは、若手社員の早期離職者増加の危機感であった。退職理由の分析から着手し、会社に起因する理由(仕事・職場・経営・制度、等)による退職を「不幸な退職」と定義。「不幸な退職をなくせ」をテーマとして、節目ごとに実施する年代別のセミナーや、目標管理面接とは別に実施する上司と部下のキャリア面談等、様々なキャリア支援施策に反映している。短期的にはキャリア支援の成果は見えにくいが、地道に取り組みを進めていけば、社員一人ひとりのキャリア自律につながり、その結果従業員のリテンションに繋がっていくと考えている。
株式会社就労センターの長井氏は、目の前の仕事に追われ、人事専門の職員もいない状況で消極的だったキャリア形成について、積極的に取り組み始めた経緯について語った。多くの障がい福祉事業所の中から選ばれる理由は「職員」にあり、利用者の生活を支える「職員」の継続が重要であり、そのためには職員一人ひとりの成長が欠かせないと考えたからである。具体的には、入社時に3年後の理想像を考える「ビジョンシート」、半期ごとの目標設定を行う「目標管理シート」、毎月の上長による「1on1面談」で、受容・承認をベースにしたフィードバックを実施している。また、管理者を「理念の伝道師」として、組織の理念定着を図るとともに、従業員の自律的形成を促進するために、管理者のコーチングスキル向上を目指した研修を実施している。利用者からは「この事業所を選んでよかった。」、職員からは「ここで働いてよかった。」と言ってもらえる組織を目指している。
株式会社デンソーの杉浦氏は、自社のキャリア自律に向けた管理職の意識・行動の変革の取組について語った。約5万人いる従業員のキャリア自律を実現するには、仕組みを整えるだけでなく、管理職の力を借りることが不可欠である。個人と組織がそれぞれ目指す、Will-Can-Mustの姿の重なりを目指すには、マネジメントによる仕事の意味付けがポイントであり、部下と上司間の対話の質が求められる。そこで、対話の鍵となる約3,000名の管理職を対象に、①【構造化】:面談で効果的な対話を可視化・上司の役割を明確化、②【自分事化】:面談後のアンケート結果のフィードバック、③【共有化】:社内の好事例の共有、の3つのポイントで支援を実施している。このように、管理職に多様なデータを提供し、現場でPDCAを回してもらうことで、対話の質の向上につなげ、従業員のエンゲージメント向上の効果を上げている。
Q1-1 キャリア自律の重要性を経営層に理解してもらうための指標等について(2社へ質問)
「経営層の理解は必須で、一般的なキャリアに関する課題だけでなく、その企業固有の課題を示すことが重要だと思っている。弊社の場合、若手の定着率が課題だったため、離職率の変化や定量的データを伝えていきながら、キャリアデザイン支援室の立ち上げにより、『キャリア元年』と位置付けることを示した。方向性を見据えて手順を定めていきながら、バックキャストの視点で定期的にマイルストーン報告を行うことで進捗を可視化し、状況が変化する中でも都度経営層の理解を得ながら進めている。」
(キヤノンマーケティングジャパン株式会社)
「個人の成長が会社の大義実現や事業成長に繋がることを示すことが大事だと思う。キャリア自律をはかることがエンゲージメント向上につながることや、専門性の分類と一人ひとりの成長度合いの可視化を行って、具体的なスキルの向上を指標として示すことなど、経営層にキャリア自律の価値を伝えることが重要と感じている。」
(株式会社デンソー)
Q1-2 経営者の立場として、キャリア自律で一番気にしているポイントは?(1社へ質問)
「従業員の熱意のある行動やマインドセットのような想いの共有が重要と感じていて、経営者としては単に指示を出すだけでなく、なぜそれをするのか、現状の課題、期待される結果を伝え、率先垂範で行動することが大切だと思う。想いを共有し、行動で示すことで、従業員の行動にも表れると考えている。」
(株式会社就労センター)
Q2 キャリア自律に関する労働組合の問題意識について(2社へ質問)
「会社と労働組合は独立した組織であり、それぞれの課題認識に基づいて活動している。労働組合は組合員意識調査を通じて、キャリアに関する項目も含めた課題を共有して意見交換を行い、会社側はキャリア相談窓口やポータルサイトを提供することで、労使が補完し合いながら連携している。」
(キヤノンマーケティングジャパン株式会社)
「会社と労働組合の関係は変化していて、以前は会社・組合それぞれの立場で意見をぶつけて、折り合いをつけることが多かったが、現在は職場の課題を共有し、同じ景色をみながら会社・労働組合で協力して取り組む関係になっている。キャリア自律についても労使で協力し、面談やキャリアの状況についてのデータを共有して議論を進めている。」
(株式会社デンソー)
Q3-1 キャリアパスの複線化が難しいイメージがある社会福祉施設職員の3年後・5年後のありたい姿をどのように示しているか(1社へ質問)
「社会福祉施設の職員の中には、利用者さんと直接関わることが何よりも好きだという方の比率が、他業種に比べて高いと思う。そのような方には専門性を高めることに重点を置いている。一方で、管理職や事業開発、経営企画などのキャリアを志望する職員もいて、職員に適した関わりを持つことを考えると、福祉の枠の中でも幅広いキャリアプランの選択肢を見いだせると考えている。」
(株式会社就労センター)
Q3-2 キャリアパスの複線化が難しいイメージがある技能社員の3年後・5年後のありたい姿をどのように示しているか(1社へ質問)
「技能社員のキャリア形成は、まず安全や品質などの明確な組織目標(MUST)を伝え、メンバーが自身のWill-Can-Mustを考えやすくすることが一つポイントである。二つ目に個人ではなく職場全体でキャリアを考え、先輩社員の背中を見ながら考えられるようにするなど、キャリアを考えるハードルを下げること。三つ目にキャリアルートは一つではなく、技能の習熟や職域の拡大など多様な選択肢があることを示すことが鍵だと思う。」
(株式会社デンソー)
Q4 キャリア形成支援を進めてきて一番大変だったことは?
「若い層のキャリア教育の理解度にばらつきがあることと、世代として私も含む今の管理職層がキャリアについて考える機会がほぼなかったことが課題だった。これに対処するため、全管理職にキャリア自律を実感してもらう研修を行うことから着手した。その後、年代別のセミナーや上司と部下のキャリア面談を実施するなど、課題を捉えながら、地道に取り組んでいくことが必要と感じている。」
(キヤノンマーケティングジャパン株式会社)
「管理者からの『なぜ今更?』や『他にやるべきことがあるのでは?』という反応だった。これに対して、まずはその意見を受け入れ、共感を示しながら、自分のビジョン、想いを伝え、協力を依頼した。小さな成功体験から、『やって良かった』ということを実感してもらうことで、徐々に理解と協力を得ることができた。」
(株式会社就労センター)
「大変だったのは、年齢や職種による制限があることで活躍先が絞られてしまうといった制度上のバリアを取り除きながら、キャリアを実現する手段を同時に整えることであり、2021年からの3年間で、公募や兼業制度の導入を一気に進めてきた。関係部署を巻き込んで進めるのは大変だったが、だからこそプログレスの旗印が非常に大事だったと思う。今後はこの熱を冷まさず、継続的に取り組むことが課題である。」
(株式会社デンソー)
Q5 退職者ヒアリングの結果をもとに、社内で改善に取り組んだことは?(1社へ質問)
「退職者ヒアリングを通じて、組織や年代など様々な属性を踏まえつつ、ヒアリング結果を分析する基準を確立したことが大きかった。その結果、例えば、社員が自ら手を挙げて異動を希望できる、社内 FA 制度の導入にも関与した。また、退職後1年後のヒアリングも実施し、退職者のキャリア感を聞き取り、様々な施策に生かしていけるように取組を進めている。」
(キヤノンマーケティングジャパン株式会社)
Q6 部下と上司間の対話の質が高まる部署の特徴について(1社へ質問)
「組織のビジョンやミッションを小さい職場の単位でも明確に示していて、そのメンバーがキャリアを考えやすくなっている。例えば、製造部門では面談時にデータを使って成果を具体的に伝えることで、部下が自分の貢献度を実感できている。また、全ての基盤にあるのは、上司が日常的に部下に関心を持ち、常日頃から対話を重ねていることも一つの特徴だと思う。」
(株式会社デンソー)
Q7 社内、社外のキャリアコンサルタントの活用について
女性の活躍推進に向けた施策の中で社外のキャリアコンサルタントを活用している。提供するコンテンツとセットで面談を行う形で、特に社内外の区別はなく、状況に応じて適切に活用している。
(キヤノンマーケティングジャパン株式会社)
社内のキャリアコンサルタントは在籍してなく、社外のキャリアコンサルタントを活用している。外部の専門家に参加してもらい、取り組みを進めている。
(株式会社就労センター)
キャリア相談室に相談が入ると社内のキャリアコンサルタントが対応している。技術畑や事務畑など、社内コンサルタントのキャリアに応じて適切な相談者がつく点が特徴だと思う。
(株式会社デンソー)
総括
総括の中で廣石氏は、3社の事例発表と質疑応答を通じて、キャリアの自律の鍵は管理職にあることを強調された。「管理職自身のキャリア形成と発信力が重要であり、キャリア形成支援室等の専任セクションがその支えとなる。専任セクションを設けるのが難しい企業も多いが、その中で管理職をサポートする制度や仕組み作りが今後の人事部に期待されている。本日のセミナーがキャリア形成支援を一層進める企業、これから進めていく企業の参考になれば幸いである。」と述べ、パネルディスカッションを締めくくった。
イベントレポート
- グッドキャリア企業アワード
2024企業向けセミナー
【名古屋】 - グッドキャリア企業アワード
2024表彰式 - グッドキャリア企業アワード
2022企業向けセミナー
【大阪】 - グッドキャリア企業アワード
2022表彰式 - グッドキャリア企業アワード
2020表彰式 - グッドキャリア企業アワード
2019表彰式 - グッドキャリア企業アワード
2018企業向けセミナー - グッドキャリア企業アワード
2018プレイベント - グッドキャリア企業アワード
2017企業向けセミナー
【大阪】 - グッドキャリア企業アワード
2017企業向けセミナー
【福岡】 - グッドキャリア企業アワード
2017表彰式 - グッドキャリア企業アワード
2017プレイベント - グッドキャリア企業アワード
2016企業向けセミナー - グッドキャリア企業アワード
2016表彰式