座談会
- 薬系技官採用情報top
- 座談会
- 薬系技官 座談会

薬系技官 座談会
-
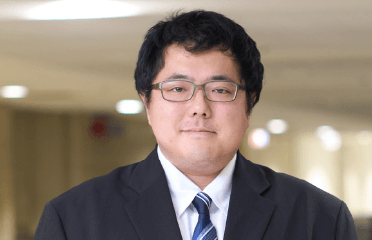
- 医薬局
総務課 課長補佐 - 山下 雄大YAMASHITA Yudai
- 医薬局
-

- 医薬局
総務課 薬事専門官 - 蓮見 由佳HASUMI Yuka
- 医薬局
-

- 医政局
医薬産業振興・医療情報企画課
室長補佐 - 武内 聡TAKEUCHI Satoshi
- 医政局
-

- 医薬局
医薬品審査管理課 審査調整官 - 三宅 晴子MIYAKE Haruko
- 医薬局
厚労省に入省しようとした
きっかけは?
私はもともと医薬品に関心があり、民間就職も考えていましたが、公務員試験の1次試験後に各省の説明会があったので、試しに話を聞いてみました。その説明が思いのほかおもしろかったのがきっかけでした。
私は強い思い入れはありませんでした。修士課程では医学系の大学院で再生医療の材料について民間企業の人と研究していたのですが、「なんか違うな」と思い、民間とは合わないと感じたことがきっかけでした。そして「幅広い経験をしたい」と思い、厚生労働省の仕事を選択しました。
私は、特に公務員に限らず色んな進路があるかなと思っていた中で、「年齢制限等もあるし後からは入りにくいからまずやってみよう」と思ったのが第一の理由です。色々な選択肢がある中、とりあえず入省して、自分の感覚と違うなら辞めれば良いと思っていましたが、気づけば10年経っていました。私は「その環境で過ごすことが嫌だとは感じない」、ということは生活の長い時間を割く仕事の上では重要だと思っているのですが、実際に入省して仕事をすると、職場の人がよくコミュニケーションをとりつつ真剣に議論し、粘り強く課題解決について考える、ということが自分にとってそれなりに馴染むものだったので、その中で仕事させてもらいつつ今に至ります。
私も、武内さんと似たような感じで、自分の性格上民間企業には向いていないなあと思い、将来どうしようかなと思って、試しに霞が関OPENゼミに業務説明を聞きに行ってみたんですよね。その前までは役所は堅物な感じの人が多いのかなと勝手に思っていましたが、実際に働いている人たちと会ってみると気さくな感じで、良い意味で予想を裏切られました。そんなことから、この職業に興味を持ち、そこから色々考えてみて、特定の団体の利益を追求するより、公益に関わって、広く社会に資することをしたいと思ったのがきっかけです。
入省して感じたギャップは?
予想以上に薬学以外をバックグラウンドとして持つ方々と働くことが多いですね。法令関係の知識がある方々はもちろんですけど、私がこれまで経験した部署だと、労働技官の方とか獣医の方とかとも一緒に仕事をしたりして、様々な人と仕事で関われる環境だと感じています。そうした方々とコミュニケーションをとって業務をする中で、自分の見識や仕事の幅を広げられると思います。
「大学の知識は仕事では使わないだろう」と思っていました。だからこそ知らない事に関わることが多いだろうなとタカをくくっていたが、働いてみると思った以上に知らないことが多いと感じています。
逆もありますね。私の場合、大学の研究室では認知症に関わるアミロイドβやその産生酵素などをテーマとしていましたが、最近、抗アミロイドβ抗体の認知症治療薬であるレカネマブが出てきた。15年経って、当時学会などで“将来的な創薬に期待”とされていたターゲットがちょうど実臨床で世に出てきて、行政の仕事として見聞きすることがあり興味深いと感じたりします。しかし、行政としての視点は、同じものを見ていても研究者の視点とは大きく異なったりもしていて、見聞きしてきたテーマでも知らないことが多いとも感じました。
結局のところ、学部や研究内容といった背景なんか気にせずに入ってきてほしいですね。
視点を変えて、官庁訪問時に激務、労働環境が悪いといった話はありましたが、特に最近は働き方が変わってきており、テレワークなどが進んでいます。最新の労働環境は是非人事担当にきいてみてください。
厚労省で働くことの
楽しさ・苦労は?
「こうした方が良いのでは?」と自分が感じたことを実現できる、あるいはその可能性を作れることですかね。仕事の本質はそこだと思います。ただし、その実現に向けた調整プロセスに年単位で必要なことが普通にあるのは、大変なところかもしれません。
私は、影響力が広いことに関われることだと思いますね。国の行政は法律であったり、予算施策であったり、社会的影響力が広いものが多い。そういったものを社会実装できるのは大きな魅力だと感じています。
私のひそかな楽しみですが、参加した大きな会議や取材を受けた次の日の業界紙で、自分たちの発信がどのように表現されているのかを見るのが楽しみだったりします。苦労も多いですが、私たちから直接発信できる機会は少ないので、うまく伝えないといけないと感じています。
物事の裏側を見られるのは楽しいと思います。この職場は2年くらいで異動になるので、いろいろ分野に携われるのも楽しいところだと思います。
そうしたところだと、働き始めてからニュースを見たときの解像度が上がったと感じています。自分が直接詳しくない分野でも、ニュースになった結果に対し、裏にある背景や関係者の動きがあるのだろうと推定できてそれも楽しいです。
あとは苦労だけど、いろんな小さな苦労はあるけど、落とし込むと、結局やっぱり人間関係に苦労するのかなと思う。
自分の中のこだわりをどう調整していくかという感覚が必要だと思います。こだわりの温度感が相手と違うと苦労します。徐々に色々な人と調整できるようになってきて、人間関係において重要なことを学んできたなと感じています。厚生労働省は他の省庁と比べても様々な人と関わることができるから、苦労も多いけど、世の中がシンプルに動いていないことがよくわかる。
入省直後と今で仕事に対する
考え方などを教えて欲しい
最初は全体像が全く見えてこなかった。仕事を通じて徐々に全体像が見えてきて、トータルの仕事量が分かるようになります。そうなると、マネジメントをどんどん考える必要が出てきます。働き始めは個人的な視点で仕事を見ていたので、自分の仕事を上司にやってもらえたら、「私の仕事を減らしてくれてありがたい」と思っていました。しかし、それは組織として良くないということに気付きました。やるべき人がやるべき事をやらないと、組織としてのマネジメントができていない体制になってしまう。
部下に必要な仕事を任せて、スキルアップしてもらい、組織としてのボトムアップを目指すこともマネジメントとして重要になってくるよね。
他に付け加えるとすれば、お金関係も考え方が変わるよね。
中堅になると徐々に予算に関する仕事に携わってくるようになり、必要な予算の規模感も見えてくるようになりました。
制度を変えようとすると、関係する費用負担をどうするのか検討したり、有識者の意見を聞いたり、前もって様々な用意をすることが必要になります。そういう意味では全体像を見る力が必要になってくるのだと感じています。
無尽蔵にお金を使えるわけではない、ということが目の前の大きな壁として立ちはだかってきます。そういう意味でも、全体像を知ってバランスをとる必要がありますよね。
最後に、学生へひと言
今、このパンフレットを読んでくれている人たちは、何かしら厚生労働省の薬系技官という仕事に興味がある方だと思います。この座談会を通じて、厚生労働省で薬系技官として働いている人の思いを知っていただき、皆さんの職業選択の一助になればうれしいです。
私はそこまで情報収集せずに入省しました。私のような人もいるので、気軽にこの仕事に興味を持ってもらえればと思います。
この仕事は全員に合う仕事ではないと思っています。だからこそ、いろんな選択肢のなかで、「まぁまずはやってみようか」と思って、厚生労働省の薬系技官を選んでもらえたらうれしいなと思います。
こういう職場もあるんだということを知ってもらって、厚生労働省の薬系技官も皆さんの選択肢の1つに加えてもらえればと思います。
