STOP!過労死
- トップ
- ICTの活用による労働効率化と医療サービス向上の取組事例
病院の取組
ICTの活用による労働効率化と医療サービス向上の取組事例
社会医療法人石川記念会HITO病院(愛媛県四国中央市)

昭和51年に石川外科医院として開設した後、平成25年に新築移転して開院した社会医療法人石川記念会HITO病院。心臓病、脳卒中、がん、糖尿病の4大疾病をカバーしながら、地域の救急医療の拠点としての役割を果たしている。急性期と回復期病棟を併せ持つケアミックスで病床数は228床。スタッフは約540人で50人を超える常勤医師を擁している。県境にあるHITO病院では、スタッフ確保に課題感を持ち、柔軟な働き方の整備に取り組んできた。中でもICT活用によって生み出したシステムは他病院からの視察も相次ぐなど、医療界の常識を変える改革となっている。
医師の引き上げでチャットを導入
病院がある四国中央市は、15年後には人口が約2万人減少すると予測されている。生産年齢人口の減少を背景に「専門職が仕事に専念できる、働く人に選ばれる環境作りが必要でした。人口減少は今の体制では乗り切れない。組織のあり方、その前提を見直す必要がありました。」と理事長は開院直後からの課題意識を語る。

「開院直後からスタッフ確保が課題だった」と話す理事長
HITO病院が働き方改革にICTを取り入れたのは平成29年。当時2人いた脳神経外科医のうち、1人が大学病院に引き揚げられ、院内の脳神経外科を1人で回すか、縮小するかの2択を迫られる事態となった。現在CXO(Chief Transformation Officer)を務める脳神経外科医は「毎日電話がバンバン鳴り続けて、バーンアウトになりそうでした。ただ、近隣で脳卒中を診ることができる病院はここだけ。私自身、四国中央市の出身で、地元の患者さんに貢献したいという思いで帰ってきたので、なんとかしたいという気持ちでした。」と振り返る。
そこで導入したのがスマートフォンで使えるチャットアプリだ。現在でも院内の主な連絡ツールはPHSであるところが多く、HITO病院も例に漏れず基本は対面か電話だった。「医師の指示や承認が必要な仕事が多いため、手術や外来診察で医師が捕まらない限り仕事が始められず、スタッフの時間外労働につながりやすいという課題がありました。」と理事長は語る。チャットを導入したことで、急ぎ対応が必要な連絡には医師がすき間時間で返事をできるようになり、全体の作業効率が上がった。新型コロナウイルス禍では、新規患者数、救急搬送件数が増える一方、濃厚接触者の出勤停止により人手が減っている状況だったが、時間外勤務時間数はさほど増えなかった。このことも、ICT活用によって労働効率性が改善したことを如実に示している。
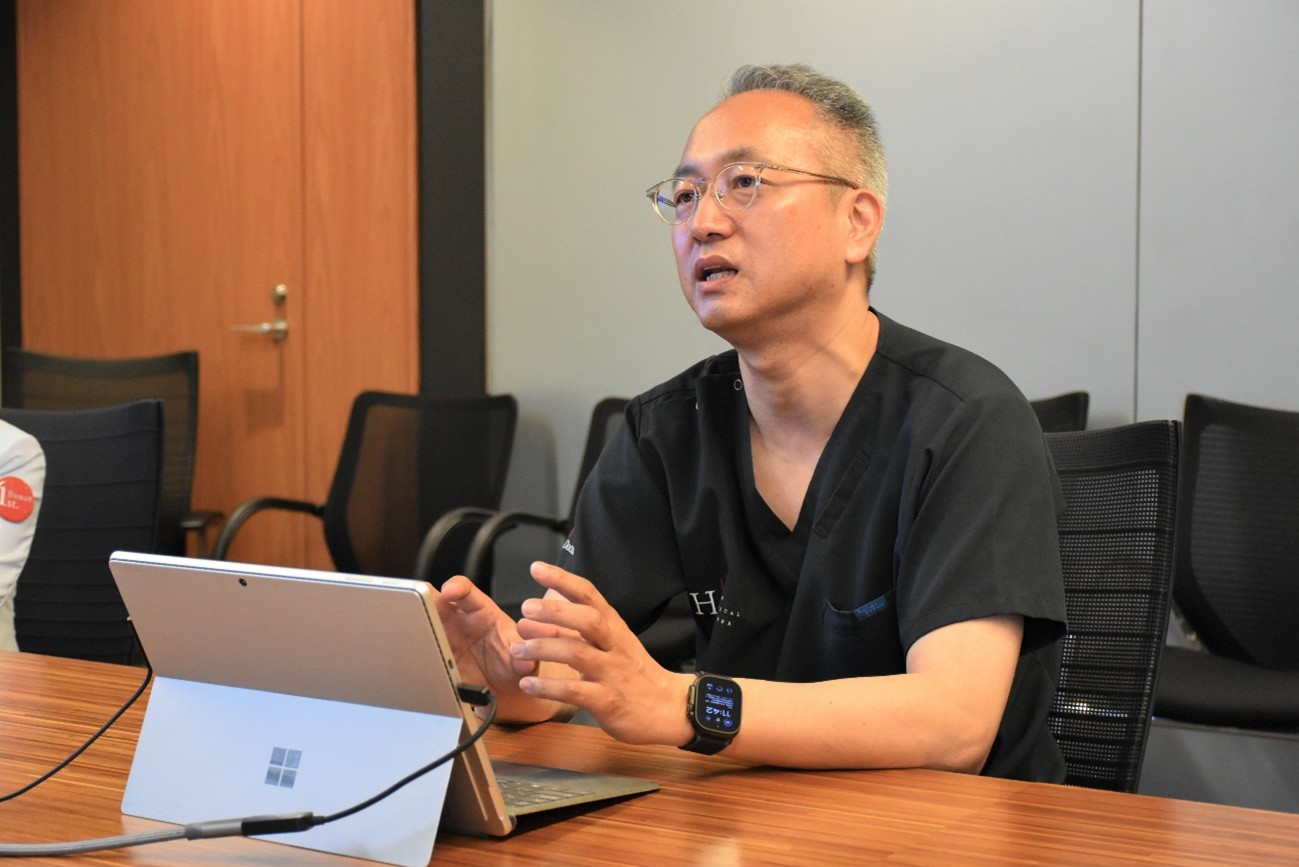
チャットによる業務効率化の成果について説明する脳神経外科医
また、連絡の心理的ハードルが下がり、特に現場スタッフから上がってくる情報量が増えたという。その結果、患者対応の初動も早くなり、早期治療にもつながった。脳神経外科医は「なにより電話と比べてストレスが軽減されました。また、グループチャットの中では他の人の目があるのでハラスメントも起きにくい。若いスタッフにとっては受け入れやすいコミュニケーション方法なのではないかと思います。」と話す。
まずは限られた範囲でスタートしたチャットの活用だったが、目に見える効率化により徐々にスマートフォンの導入数を増やし、今ではスタッフ1人につき1台支給されている。ランニングコストも業務の効率化により解決した。例えば、リハビリテーション科では毎日の朝礼をチャットに代替することで診療報酬の1単位となる20分を捻出した。その分が増収につながり、導入台数拡大の追い風となった。
多職種協働で医療サービス向上

ベッドサイドに常駐するスタッフ。チャットのおかげでナースステーションを離れても情報が得られるようになった
チャットの導入により、医療サービス自体の改善も図られた。HITO病院では、「多職種協働セルケアシステムⓇ」という、病棟内を複数のセルに分け、看護師やメディカルスタッフがチームとなって各セル付近に常駐してケアを行う仕組みを採用している。入院患者の7割が75歳以上と高齢化が進む中、より患者と距離の近いケアの必要性が叫ばれていたが、当時のスタッフの勤務拠点はナースステーション。引き継ぎや患者資料の照会もナースステーションで行い、コールで呼ばれたらベッドへ向かうというのが普通だったためどうしてもタイムラグが生じてしまっていた。チャットを使えばナースステーションから離れても患者の情報を共有することができるため、働く場所をナースステーション中心からベッドサイドへと転換することができた。この仕組みにより、看護師はなんと1日で移動する距離4~5キロ、申し送りのチャットへのシフトを含め、時間にして100分も削減することに成功し、その時間を本来業務である患者のケアに充てられるようになった。
チャットがもたらした利点は、労働効率化だけにとどまらなかった。病棟ごと、診療科ごとなどで医師や看護師、薬剤師、セラピストといった多職種のグループチャットを作って情報のやりとりをすることで、他の職種のスタッフとの距離が縮まり、スキル向上にも一役を買っている。脳神経外科医は「多職種と働いて学ぶことは非常に重要。今後、在宅訪問などに行くときも、特に若いスタッフは困ってしまうこともあると思いますが、スマートフォンがあればわからないことは検索できるし、知見のある専門職と遠隔でつながることもできる。この環境で慣れ親しんだ人が、今後病院から在宅の方にシフトしていったら、そこでICTを活用しながら病院の専門職とつながって、アドバイスを受けながら地域を支えていくこともできるのではないか。」と展望を語る。
新たなデバイスや生成AIも活用
HITO病院ではさらなるICT活用も進めている。令和5年には、クラウドファンディングを行い、遠隔で視点映像を共有できるスマートグラスを購入。訪問看護を行うスタッフと院内の専門職がリアルタイムでつながり、専門職の指導を受けながらケアサービスを提供している。令和3年には13人の患者が誤嚥性肺炎による再入院となっていたが、遠隔指導を実施した令和5年は0人と大きな成果を上げている。

スマートグラスを装着してケアにあたるスタッフ
さらに院内のスタッフと会話ができるデバイスを患者の自宅に設置する遠隔見守りシステムも実証実験中だ。今後は生成AIと電子カルテを活用し、患者情報の迅速な抽出や文書作成に応用できる仕組み作りにも注力していくという。
今後の課題は看護師のエンゲージメントと働きがいの向上だという。令和2年からは新人看護師に1人1台タブレットを支給し、翌年からはeラーニングシステムを導入。従来の集合研修を主とする教育体制からeラーニングとOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング=日常業務の中でスキルを獲得する訓練 )を組み合わせた研修に切り替えた。
「専門職はどこでも働けますから、『ここで学べる何か』が無いと残ってくれない。今と昔では価値観が変わっているので、私たちが合わせていくことが必要だと思っています」と理事長。病院経営と人手不足の解消に向けてもICTの果たす役割は大きく、HITO病院は今後もさらなる改革で「選ばれる病院」作りに邁進していく。
