STOP!過労死
- トップ
- 物流業界の魅力向上につながる老舗運送会社の働き方改革取組事例
企業の取組
物流業界の魅力向上につながる老舗運送会社の働き方改革取組事例
株式会社塚腰運送(京都府京都市)

明治43年創業の株式会社塚腰運送
株式会社塚腰運送は明治43年創業で、物流運送を中核事業としつつ、電気工事、アウトソーシング、観光、教育など多角的な事業を展開している。従業員数は連結で約700人、全国に35拠点を構える。精密機械や半導体製造装置の輸送・搬入・据え付けを得意とし、計測機器メーカーや産業用蓄電池メーカーなどの商材も取り扱う。2024年問題と呼ばれる物流業界の大きな変革期に、長時間労働、人手不足、高齢化といった課題が山積する中、同社は独自の働き方改革に取り組んできた。
「魅力ある会社」を目指して
塚腰運送が働き方改革に乗り出したのは約20年前、取締役事業部長は「高齢化が進む中で事故の発生率が高くなり、若手が入ってこない、育たないという悪循環に陥っていた。」と語る。人手不足から休暇が取れない、労働時間が長時間になるといった状況を打破するため、「会社全体を魅力ある会社にしていく必要があった。」と強調する。
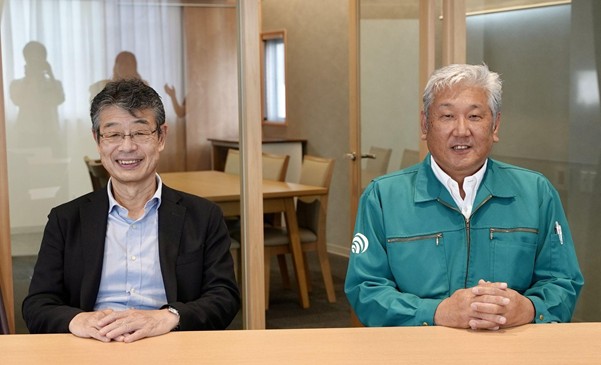
「若手が入ってこない、育たないという悪循環に陥っていた」と語る取締役事業部長(左)と「IT点呼の導入で、ドライバーの意識が変わってきた」と語る業務管理課長
まず着手したのは、職場環境の整備だった。朝礼の実施、ラジオ体操の導入、アルコール検査の徹底など、基本的なことから始めた。並行して、社屋の全面改装にも着手。従来の運送会社のイメージとはかけ離れた、バーのようなレイアウトの事務所を設けるなど、大胆な改革を進めた。車両についても、安全装備やオプションをほぼフル装備で導入し、快適な運行環境を整備した。
業務管理課長は「私が初めて塚腰運送に来た時は、社屋の変わりように驚いた。」と話す。「まるでどこかのバーのようで、運送会社とは思えなかった。」と笑う。 課長自身も20歳からドライバーとして業界に入り、現場の実情を熟知している。それだけに、会社が変わろうとする熱意を肌で感じたという。
DXの推進と2024年問題への備え
その後同社はIT化を積極的に推進した。平成27年にはIT点呼制度を導入し、各営業所の点呼業務を標準化。同29年には動態管理システムを刷新し、事故やアクシデント発生時の迅速な対応を可能にした。同31年には血圧測定を導入し、ドライバーの健康管理を強化。独自のガイドラインを作成し、健康状態に基づく乗務可否判断を行うようにした。
課長は「IT点呼の導入で、ドライバーの意識が変わってきた。」と語る。「以前は営業所によって点呼の温度感がバラバラだったが、IT点呼によって一定の温度感でドライバーを送り出せるようになった。」と評価する。 また、動態管理システムの導入で、ドライバー自身も「会社がデータを収集しながら運行管理している。」と意識するようになり、安全運転への効果も表れているという。
2024年問題への対応も、着々と進めてきた。令和2年頃から現場における待機時間や付帯業務の状況を調査し、数値化して分析。顧客に対して待機料を請求するなど、運賃の適正化にも取り組んだ。
課長は「待機時間が拘束時間の長期化につながっていることが顕著だった。」と指摘する。「運行改善基準告示に則った形で運行を計画すると、分割休息を取らざるを得なくなり、結果として休息の質が低下してしまう。」と課題を語る。 そこで、フェリー輸送の活用や出荷時間の前倒し、リードタイムの延長などの対策を実施。荷主との粘り強い交渉により、これらの対策を実現した。
ベテランドライバー「フェリーの利用で本当に楽になった」

フェリーの利用で「体力的にも本当に楽になりました」と語るベテランドライバー
塚腰運送で43年のキャリアを持つベテランドライバーは、改革前の働き方について、「昔は夕方にお客さんのメーカーに積みに行って、そのまま目的地が遠方であれば、東京、九州とかを一気に走り出した。次の日の9時10時、午前中に必ずつけるというのが当たり前だった。」と振り返る。
休憩時間についても「休憩時間の規定もほとんどなく、もう本人の体力任せと言いますか、それに限っていたと思います。」と振り返る。 しかし、現在は「4時間に30分の休憩というのは、もう確実に決められていて、一日の拘束時間がもうきっちりと決められているので、次の日運行するまでに必ず9時間以上休息を取ることになっている。」と労働環境が大きく改善されたことを強調する。
フェリーを使った長距離輸送について、「現役の頃はフェリーに乗って北海道へ何回も行くことがありました。フェリーに乗っている時間は休養できますので、体力的にも本当に楽になりました。」と語る。
改善アイデアで労働災害防止にも取り組む
労働災害防止にも力を入れている。平成28年から「価値創造大会」を開催し、現場からの改善アイデアを形にする取り組みを行ってきた。令和5年には昇降設備の設置義務に関する法改正があったが、塚腰運送ではそれ以前から、荷台からの落下事故防止対策に取り組んできた。
課長は「落下事故で肋骨を骨折したドライバーがいたが、打ち所が悪ければ命を落としていたかもしれない。」と振り返る。「二度とこのような事故を起こしてはならない。」という思いから、墜落制止のためトラックアオリに取り付ける簡易作業床を開発し、導入したという。 現場の意見を取り入れ、使いやすさを追求したことが、高い評価につながっている。
これらの取り組みの結果、ドライバーの労働時間は大幅に改善された。令和6年の年間労働時間は令和4年から13%減少。 有責事故も平成30年の29件から、一昨年は4件まで抑え込むことができた。 有給休暇消化率は74%まで向上し、離職率は一昨年と昨年で0%を達成した。
事業部長は「お客様に対して価値のある仕事ができるようになり、その対価をいただけるようになった」と経営的な効果を語る。「特殊な搬入などを行っているので、それに対していただく部分も大きく、利益率の改善もできている。」と胸を張る。 また、広報活動にも力を入れ、ホームページの更新や社外報などで積極的に情報発信している。

IT点呼をするドライバー
塚腰運送の改革は、まだ道半ばだ。課長は「点呼の自動化が進む中でも、人の気持ちを汲み取る仕組みを維持していきたい。」といい、「ドライバーの出発前や帰着時のちょっとした機微を、自動化によって見過ごしてしまうことがないようにしたい。」と懸念を示す。 同時に、バイタル情報の活用など健康管理の高度化も目指し、「『塚腰のドライバーになったら健康になった』と言われるような状態を目指したい。」と意気込む。
事業部長も「バイタル情報をしっかり数値化して把握することが今後重要になる。」と指摘する。「まだDXができていない部分もあるので、そのあたりをもっと改善し、デジタル化をさらに進めていきたい。」と展望を語る。 また、社内コミュニケーションも大切にしており、「価値創造大会のように年に一回全国から集まる場を設けている。」という。塚腰運送の20年にわたる働き方改革は、物流業界が直面する課題に対する先駆的な解決策を示しているといえるだろう。
