| 第5章 | 調査結果から得られた示唆 |
| ここでは法人アンケート調査、個人アンケート調査の結果を産業分野別に概観した後、今後、専門的・技術的分野の外国人の就業を促進していくための具体策を検討する際、特に注目するべきポイントについて整理していくこととする。(なお、以降で「外国人就業者」と表記する場合、「専門的・技術的分野に就労する外国人」を意味するものとする) |
法人アンケート結果の概要(全産業分野)
| 回答法人の基本属性 | ||||||||||
| 回答件数 | 従業員規模 | 外国資本が入っている法人の割合 | ||||||||
| 0-30人未満 | 30-100人未満 | 100-300人未満 | 300人以上 | |||||||
| 1,272件 | 29.1% | 21.5% | 26.2% | 19.3% | 17.4% | |||||
| 外国人の就業の有無と人数等 | ||||||||||
| 外国人のいる法人の割合 | 全従業員に占める外国人従業員の割合 | 全従業員に占める 非正規従業員の割合 |
外国人就業者に占める 非正規従業員の割合 |
|||||||
| 42.4% | 2.0% | 25.3% | 69.2% | |||||||
| 外国人の間接雇用等の状況 | ||||||||||
| 外国人派遣労働者の受入れ割合 | 法人単位での請負契約による 外国人を受け入れている割合 |
外国人個人事業主と請負契約を 交わしている割合 |
||||||||
| 4.6% | 4.2% | 6.1% | ||||||||
| 外国人就業者の属性 | ||||||||||
| 在留資格(上位3つ) | 外国人従業員に留学経験者の 占める割合 |
出身国・出身地域(上位3つ) | ||||||||
| 日本人の配偶者、人文知識・国際業務、教授 | 15.1% | アメリカ、イギリス、中国 | ||||||||
| 外国人就業者の活用の理由(上位3つ) | ||||||||||
| 国籍に関係なく優秀な人材を探すため、外国人ならではの技能・発想を取り入れるため、海外とのネットワーク構築のため | ||||||||||
| 1. | 産業分野ごとにみた特徴 |
| (1) | 製造業 |
| 回答法人の基本属性 | |||||||
| 回答件数 | 従業員規模 | 外国資本が入っている法人の割合 | |||||
| 0-30人未満 | 30-100人未満 | 100-300人未満 | 300人以上 | ||||
| 287件 | 8.4% | 17.1% | 39.4% | 32.1% | 23.3% (+5.9ポイント) |
||
| 外国人の就業の有無と人数等 | |||||||
| 外国人のいる法人の割合 | 全従業員に占める外国人従業員の割合 | 全従業員に占める 非正規従業員の割合 |
外国人就業者に占める 非正規従業員の割合 |
||||
| 32.1%(−10.3ポイント) | 0.3%(−1.7ポイント) | 9.7%(−15.6ポイント) | 43.4%(−25.8ポイント) | ||||
| 外国人の間接雇用等の状況 | |||||||
| 外国人派遣労働者の受入れ割合 | 法人単位での請負契約による 外国人を受け入れている割合 |
外国人個人事業主と請負契約を 交わしている割合 |
|||||
| 5.6%(+1.0ポイント) | 4.2% | 2.4%(−3.7ポイント) | |||||
| 外国人就業者の属性 | |||||||
| 在留資格(上位3つ) | 外国人従業員に留学経験者の 占める割合 |
出身国・出身地域(上位3つ) | |||||
| 日本人の配偶者、人文知識・国際業務、教授 | 31.0%(+15.9ポイント) | 中国、韓国、アメリカ | |||||
| 外国人就業者の活用の理由(上位3つ) | |||||||
| 国籍に関係なく優秀な人材を探すため、海外とのネットワーク構築のため、海外との取引等が増えてきたため | |||||||
| 注) | ( )内は全体における平均値との差。 |
| 外国人従業員若しくは経営権を保有する外国人がいる法人の割合は、従業員規模が大きい方が高くなっているが、従業員規模が比較的大きい「製造業」では、その割合が全体よりも若干低くなっている。また、外国人がいる法人においても、全体の従業員数と比較して、外国人従業員の人数は非常に少なくなっており、分野全体として、外国人が就業している割合が非常に低くなっていると考えられる。ただし、他の産業分野に比べて、派遣労働者や請負契約のような間接雇用によって外国人の受入れを行っている法人の割合はそれほど多くはないものの、それらの形態で外国人を受け入れている場合は大規模に行っていることは注目に値する。 外国人を活用している場合には、「海外とのネットワークの構築のため」、「海外との取引等が増えてきたため」、「海外進出の足がかりとするため」のような理由を挙げている法人が多くなっている。外国人従業員の出身地は、日本の製造業の多くが進出しているアジア地域が中心となっていること、「国内の大学から紹介」を通じて職に就く外国人を活用している法人の割合や外国人従業員に占める留学経験者の割合が他の分野よりも高くなっていることともあわせて考えると、「製造業」では日本と出身国との架け橋となるような人材を求めていることが推測される。 なお、「製造業」では、「技術」や「人文知識・国際業務」やまた若干ではあるが「研究」の在留資格を有している外国人を活用している法人の割合が高くなっていること、国内の大学を通じての入職が多くなっていることから、また前述のように架け橋となるような人材を求める傾向があることから、この分野で就労する外国人は、研究職、エンジニア、貿易事務等職で、彼らの持つ専門性や技術を活かして活躍している人が多いと考えられる。しかし、その一方で従来、安価な労働力として外国人を活用してきた法人の割合が高いと考えられる製造業では、外国人の活用の理由として「人件費削減のため」といった理由を挙げる法人の割合が他の分野よりも高くなっていることも否めない。 |
| (2) | 通訳・翻訳・語学学校 |
| 回答法人の基本属性 | ||||||||
| 回答件数 | 従業員規模 | 外国資本が入っている法人の割合 | ||||||
| 0-30人未満 | 30-100人未満 | 100-300人未満 | 300人以上 | |||||
| 94件 | 51.1% | 26.6% | 10.6% | 6.4% | 3.2% (−14.2ポイント) |
|||
| 外国人の就業の有無と人数等 | ||||||||
| 外国人のいる法人の割合 | 全従業員に占める外国人従業員の割合 | 全従業員に占める 非正規従業員の割合 |
外国人就業者に占める 非正規従業員の割合 |
|||||
| 53.2%(+10.8ポイント) | 10.3%(+8.3ポイント) | 80.5%(+55.2ポイント) | 90.7%(+21.5ポイント) | |||||
| 外国人の間接雇用等の状況 | ||||||||
| 外国人派遣労働者の受入れ割合 | 法人単位での請負契約による外国人を 受け入れている割合 |
外国人個人事業主と請負契約を 交わしている割合 |
||||||
| 3.2%(−1.4ポイント) | 13.8%(+9.6ポイント) | 28.7%(+22.6ポイント) | ||||||
| 外国人就業者の属性 | ||||||||
| 在留資格(上位3つ) | 外国人従業員に留学経験者の 占める割合 |
出身国・出身地域(上位3つ) | ||||||
| 日本人の配偶者、人文知識・国際業務、教育 | 5.7%(−9.4ポイント) | イギリス、アメリカ、カナダ | ||||||
| 外国人就業者の活用の理由(上位3つ) | ||||||||
| 外国人ならではの技能・発想を取り入れるため、国籍に関係なく優秀な人材を探すため、外国人のほうが高い専門能力を持つため | ||||||||
| 注) | ( )内は全体における平均値との差。 |
| 「通訳・翻訳・語学学校」においては、全従業員に占める外国人従業員の割合、1法人あたりの外国人従業員数ともに他の分野と比べると圧倒的に多く、そのほとんどが非正規従業員となっている。日本人、外国人に関わらず、全従業員に占める非正規従業員の割合も高くなっており、この産業分野においては契約期間を限定した雇用形態を望んでいる法人が多くなっている。さらに、他の分野よりも間接雇用によって外国人を活用している、また個人事業主との契約をしている法人の割合も高くなっていることから、通訳や翻訳に関する案件等において派遣労働者を活用したり、法人単位若しくは個人事業主と請負契約を結んで対処しているケースが多くなっているのではないかと考えられる。 この分野の中でも特に語学学校では、語学教師としてのネイティブスピーカーを必要としていると考えられる。そのため、イギリス・アメリカ・カナダ等の英語圏の出身者が多くなっており、一方、留学経験者の割合は低く、個人アンケート調査の結果からも分かるように仕事上では高度な日本語能力は要求されていない。また邦人側では、「外国人ならではの技能・発想を取り入れるため」や「外国人の方が高い専門能力を持つため」等を外国人を活用する理由として挙げるケースが多くなっている。つまり、「外国語を教える外国人」としてのスキルが重視されていることが伺える。 この分野で就労する外国人の在留資格として主なものは、「日本人の配偶者等」となっている。入職経路が知人・友人等の紹介が最も多くなっていることはこうした就労を目的としない在留資格を保有する人たちが、何らかの紹介によって職に就いているケースが多いのではないかと考えられる。また、「日本以外での新聞・雑誌・求人誌・HP」を通じて職に就くケースも他の分野より若干多くなっており、ネイティブスピーカーを確保するために、海外で人材を募集して日本につれてくることがあるものと想定される。このため、外国人を活用する際の問題点として「採用コスト」、「募集方法」を挙げる法人の割合が高くなっている。また、既に述べたように非正規従業員の割合が、日本人・外国人を問わず高い分野特性からか、「定着性」を問題と挙げる法人の割合も比較的高かった。 |
| (3) | 卸売・小売・商社 |
| 回答法人の基本属性 | ||||||||||
| 回答件数 | 従業員規模 | 外国資本が入っている法人の割合 | ||||||||
| 0-30人未満 | 30-100人未満 | 100-300人未満 | 300人以上 | |||||||
| 200件 | 63.5% | 18.5% | 10.0% | 4.5% | 18.5% (+1.1ポイント) |
|||||
| 外国人の就業の有無と人数等 | ||||||||||
| 外国人のいる法人の割合 | 全従業員に占める外国人従業員の割合 | 全従業員に占める 非正規従業員の割合 |
外国人就業者に占める 非正規従業員の割合 |
|||||||
| 25.0%(−17.4ポイント) | 1.9%(−0.1ポイント) | 38.2%(+12.9ポイント) | 32.0%(−37.2ポイント) | |||||||
| 外国人の間接雇用等の状況 | ||||||||||
| 外国人派遣労働者の受入れ割合 | 法人単位での請負契約による 外国人を受け入れている割合 |
外国人個人事業主と請負契約を 交わしている割合 |
||||||||
| 3.0%(−1.6ポイント) | 2.0%(−2.2ポイント) | 3.0%(−3.1ポイント) | ||||||||
| 外国人就業者の属性 | ||||||||||
| 在留資格(上位3つ) | 外国人従業員に留学経験者の 占める割合 |
出身国・出身地域(上位3つ) | ||||||||
| 人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、教育 | 31.6%(+16.5ポイント) | 中国、フランス、台湾 | ||||||||
| 外国人就業者の活用の理由(上位3つ) | ||||||||||
| 国籍に関係なく優秀な人材を探すため、海外とのネットワーク構築のため、海外との取引等が増えてきたため | ||||||||||
| 注) | ( )内は全体における平均値との差。 |
| 「卸売・小売・商社」は、日本人の同僚や顧客とのやり取りの頻度が高い職場であるため、日本語の能力や日本の商習慣等に馴染みのある人が好まれると考えられる。そのため、この分野は他の分野と比べて留学経験者の採用が多くなっている。これは、外国人を採用・活用する際の問題点として、「文化・習慣の違い」、「職場内での意思の疎通」、「取引先・顧客との意思の疎通」、「日本企業の仕事の進め方への適応」等コミュニケーション能力に起因すると考えられる問題を挙げている割合が高いことからも類推できる。 業務内容を反映して、外国人を採用・活用する理由としては、「海外との取引等が増えてきたため」、「海外とのネットワーク構築のため」を挙げる法人の割合が高くなっており、入職経路もそうした企業活動と関連して、「国内外の取引先からの紹介」や「海外にある同系列の会社・職場からの派遣」が多くなっている。なお、外国人従業員は、日本の貿易相手の中心となっているアジア出身者が多くなっている。 |
| (4) | 旅行・ホテル |
| 回答法人の基本属性 | ||||||||||
| 回答件数 | 従業員規模 | 外国資本が入っている法人の割合 | ||||||||
| 0-30人未満 | 30-100人未満 | 100-300人未満 | 300人以上 | |||||||
| 251件 | 29.5% | 31.9% | 21.9% | 12.0% | 2.4% (−15.0ポイント) |
|||||
| 外国人の就業の有無と人数等 | ||||||||||
| 外国人のいる法人の割合 | 全従業員に占める外国人従業員の割合 | 全従業員に占める 非正規従業員の割合 |
外国人就業者に占める 非正規従業員の割合 |
|||||||
| 23.1%(+19.3ポイント) | 1.5%(−0.5ポイント) | 37.0%(+11.7ポイント) | 76.8%(+7.6ポイント) | |||||||
| 外国人の間接雇用等の状況 | ||||||||||
| 外国人派遣労働者の受入れ割合 | 法人単位での請負契約による 外国人を受け入れている割合 |
外国人個人事業主と請負契約を 交わしている割合 |
||||||||
| 2.8%(−1.8ポイント) | 0.8%(−3.4ポイント) | 1.6%(−4.5ポイント) | ||||||||
| 外国人就業者の属性 | ||||||||||
| 在留資格(上位3つ) | 外国人従業員に留学経験者の 占める割合 |
出身国・出身地域(上位3つ) | ||||||||
| 技能、人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、 | 38.6%(+23.5ポイント) | 中国、韓国、フィリピン | ||||||||
| 外国人就業者の活用の理由(上位3つ) | ||||||||||
| 国籍に関係なく優秀な人材を探すため、外国人ならではの技能・発想を取り入れるため、日本人では、必要な従業員を充足できないため | ||||||||||
| 注) | ( )内は全体における平均値との差。 |
| 「旅行・ホテル」において、外国人を採用・活用する理由としては、「日本人では、必要な従業員を充足できないため」というものが、他の産業分野よりも若干多くなっていた。「技能」の在留資格を保有している者が多くみられるように、この分野ではレストランでのコックとして活躍する人材もいると考えられる。また、「国内従業員の国際化のため」という理由も若干高くなっていること、アジア出身者の割合が高くなっていることは、近年日本からアジアへの旅行者が増えたり、逆にアジアから日本への旅行者が増えていることも関係していると考えられる。 なお、この分野で就労する外国人従業員は、他の分野と比較して直接顧客と接する機会が多くなるものと考えられる。そのため、外国人従業員を活用する際の問題点としては、「文化・習慣の違い」、「職場内での意思の疎通」、「取引先・顧客との意思の疎通」、「日本企業の仕事の進め方への適応」等コミュニケーション能力に起因すると考えられる点を問題とする割合が高くなっている。このようなコミュニケーション能力の不足に対処するためか、「旅行・ホテル」においては、外国人従業員の間では日本への留学経験者の割合が他の分野より高くなっていたり、既に日本に滞在している人が利用することができる公共職業安定所や外国人雇用サービスセンターのような「公共職業紹介機関」を通じて入職するケースが他の分野より若干多くなっている。 |
| (5) | 金融・保険・証券 |
| 回答法人の基本属性 | ||||||||||
| 回答件数 | 従業員規模 | 外国資本が入っている法人の割合 | ||||||||
| 0-30人未満 | 30-100人未満 | 100-300人未満 | 300人以上 | |||||||
| 108件 | 45.4% | 27.8% | 14.8% | 6.5% | 67.6% (+50.2ポイント) |
|||||
| 外国人の就業の有無と人数等 | ||||||||||
| 外国人のいる法人の割合 | 全従業員に占める外国人従業員の割合 | 全従業員に占める 非正規従業員の割合 |
外国人就業者に占める 非正規従業員の割合 |
|||||||
| 51.9%(+9.5ポイント) | 10.0%(+8.0ポイント) | 12.6%(−12.7ポイント) | 14.3%(−54.9ポイント) | |||||||
| 外国人の間接雇用等の状況 | ||||||||||
| 外国人派遣労働者の受入れ割合 | 法人単位での請負契約による 外国人を受け入れている割合 |
外国人個人事業主と請負契約を 交わしている割合 |
||||||||
| 10.2%(+5.6ポイント) | 3.7%(−0.5ポイント) | 1.9%(−4.2ポイント) | ||||||||
| 外国人就業者の属性 | ||||||||||
| 在留資格(上位3つ) | 外国人従業員に留学経験者の 占める割合 |
出身国・出身地域(上位3つ) | ||||||||
| 企業内転勤、日本人の配偶者、人文知識・国際業務 | 9.2%(−4.9ポイント) | ブラジル、アメリカ、フランス | ||||||||
| 外国人就業者の活用の理由(上位3つ) | ||||||||||
| 国籍に関係なく優秀な人材を探すため、海外とのネットワーク構築のため、外国人ならではの技能・発想を取り入れるため | ||||||||||
| 注) | ( )内は全体における平均値との差。 |
| 今回の調査では、特に「金融・保険・証券」においては外資系企業を多く調査対象としたため、外国資本の参入している割合及び経営権を持っている外国人がいる割合は、他の分野と比べて高くなっている。このような法人属性を反映して、在留資格は「投資・経営」の割合が他の分野よりも大幅に高くなっている。 また、「企業内転勤」の在留資格を保有する者の割合も高くなっている。これに呼応するかのように入職経路としては「海外にある同系列の会社・職場からの派遣」が多くなっており、外国人従業員の出身地域もそれぞれの法人の本拠地となっている場合が多いため、欧米出身者が中心となっている。 「企業内転勤」で派遣されている場合が多いことを反映して、雇用形態としては正規従業員が大半を占めており、個人アンケート調査によると企業内転勤で派遣されている人は、いずれは出身国等に戻っていく意向を持っているケースが多い。 なお、こうした「投資・経営」、「企業内転勤」を保有している人が多いために、法人としての外国人就業者のための住宅環境に対する対処を行っている割合は最も高くなっている。 加えてこの分野で特徴的なのは、「国内の人材紹介業者・人材派遣会社」のような法人が介在して職に就くケースが他の分野よりも若干多く見受けられることである。 |
| (6) | 私立大学・研究機関 |
| 回答法人の基本属性 | ||||||||||
| 回答件数 | 従業員規模 | 外国資本が入っている法人の割合 | ||||||||
| 0-30人未満 | 30-100人未満 | 100-300人未満 | 300人以上 | |||||||
| 214件 | 0.9% | 13.1% | 43.5% | 39.3% | 0.0% (−17.4ポイント) |
|||||
| 外国人の就業の有無と人数等 | ||||||||||
| 外国人のいる法人の割合 | 全従業員に占める外国人従業員の割合 | 全従業員に占める 非正規従業員の割合 |
外国人就業者に占める 非正規従業員の割合 |
|||||||
| 89.7%(+47.3ポイント) | 3.4%(+1.4ポイント) | 41.0%(+15.7ポイント) | 72.1%(+2.9ポイント) | |||||||
| 外国人の間接雇用等の状況 | ||||||||||
| 外国人派遣労働者の受入れ割合 | 法人単位での請負契約による 外国人を受け入れている割合 |
外国人個人事業主と請負契約を 交わしている割合 |
||||||||
| 6.5%(+1.9ポイント) | 3.7%(−0.5ポイント) | 11.2%(+5.1ポイント) | ||||||||
| 外国人就業者の属性 | ||||||||||
| 在留資格(上位3つ) | 外国人従業員に留学経験者の 占める割合 |
出身国・出身地域(上位3つ) | ||||||||
| 教授、教育、日本人の配偶者等 | 21.8%(+6.7ポイント) | アメリカ、中国、イギリス | ||||||||
| 外国人就業者の活用の理由(上位3つ) | ||||||||||
| 国籍に関係なく優秀な人材を探すため、外国人ならではの技能・発想を取り入れるため、外国人のほうが高い専門能力を持つため | ||||||||||
| 注) | ( )内は全体における平均値との差。 |
| 従業員数100人以上の規模の法人が約9割を占め、他の分野と比べて規模が大きい「私立大学・研究機関」は、外国人就業者がいる割合が最も高い分野である。この分野で従事する外国人は、大半が語学講師として活躍していると考えられる。そのため、彼らの出身国もアメリカ・イギリスと英語圏が多く、在留資格は「教授」や「教育」が多くを占めている。また、若干ながら個人アンケート調査でみられるように語学教師としてではなく、研究活動の一環で日本の研究機関で働いているケースや留学生への相談係として対応するための大学職員として従事している者もいる。このような仕事の内容を反映して、外国人従業員を採用・活用する理由は、「外国人ならではの技能・発想を取り入れるため」、「外国人の方が高い専門能力を持つため」といったものが多くなっていた。なお、大学という特性を反映し、入職経路は国内外を問わず大学や知人、友人を通じての紹介が多くなっている。 この分野は、外国人を採用・活用するにあたって、「特に問題ない」と感じている法人の割合が最も高い等、比較的外国人の活用に関しては馴染みのある分野であるためか、今後も外国人の活用を現状維持したり、積極的に活用しようとする法人が他の分野と比べて多くなっている。なお、この分野では「入国管理手続」を問題として挙げる法人の割合が最も低かった。「教授」、「教育」等の在留資格はある一定の要件を満たせば比較的容易に発行されるのではないかと思われる。 さらに、従業員規模が大きく、スケールメリットが働くためか「住宅環境について、宿舎等の用意や家賃補助等の何らかの対処を行っている」法人の割合が、「金融・保険・証券」や「製造業」と同様に高くなっている。 |
| (7) | 情報・通信 |
| 回答法人の基本属性 | ||||||||||
| 回答件数 | 従業員規模 | 外国資本が入っている法人の割合 | ||||||||
| 0-30人未満 | 30-100人未満 | 100-300人未満 | 300人以上 | |||||||
| 32件 | 46.9% | 18.8% | 15.6% | 18.8% | 50.0% (+32.6ポイント) |
|||||
| 外国人の就業の有無と人数等 | ||||||||||
| 外国人のいる法人の割合 | 全従業員に占める外国人従業員の割合 | 全従業員に占める 非正規従業員の割合 |
外国人就業者に占める 非正規従業員の割合 |
|||||||
| 53.1%(+10.7ポイント) | 1.9%(−0.1ポイント) | 11.5%(−13.8ポイント) | 37.5%(−31.7ポイント) | |||||||
| 外国人の間接雇用等の状況 | ||||||||||
| 外国人派遣労働者の受入れ割合 | 法人単位での請負契約による 外国人を受け入れている割合 |
外国人個人事業主と請負契約を 交わしている割合 |
||||||||
| 3.1%(−1.5ポイント) | 12.5%(+8.3ポイント) | 9.4%(+3.3ポイント) | ||||||||
| 外国人就業者の属性 | ||||||||||
| 在留資格(上位3つ) | 外国人従業員に留学経験者の 占める割合 |
出身国・出身地域(上位3つ) | ||||||||
| 技術、人文知識・国際業務、日本人の配偶者等 | 41.4%(+26.3ポイント) | 中国、アメリカ、韓国 | ||||||||
| 外国人就業者の活用の理由(上位2つ) | ||||||||||
| 国籍に関係なく優秀な人材を探すため、海外とのネットワーク構築のため | ||||||||||
| 注) | ( )内は全体における平均値との差。 |
| 「情報・通信」は今回厳密には調査対象としていなかったため、外資系企業というカテゴリーの中に含まれていた可能性が高い。そのため、他分野と比べ外国資本の入っている割合や経営権を有する外国人の割合が高くなっている。 外国人従業員の活用理由としては、近年、日本からアジア各国へこの分野でのアウトソーシングが進んでいることを反映して、「海外とのネットワーク構築のため」が他の産業分野よりも比較的高い割合を示しており、中国や韓国等アジア出身者が多くなっている。 なお、この分野では、先に挙げた「海外とのネットワーク構築のため」といった海外との架け橋となるような人材を求める傾向があることを反映して、日本への留学経験者の割合が高くなっていたり、外国人従業員を活用する際の問題点として、「職場内での意思の疎通」、「取引先・顧客との意思の疎通」等のコミュニケーション能力に起因すると考えられる点を危惧する声が強くなっている。 また、この分野ではプロジェクト単位で業務を発注し、常駐型の社員として他社の社員を受け入れることも多く、それを反映して法人単位での請負契約による外国人の受入れも他の分野に比べ多くなっている。 |
| 2. | 活用戦略別にみた特徴 |
| 今回の法人アンケート調査で、現在外国人を活用している法人における活用の理由(図表5−1)をみると、ほとんどの産業分野において、「国籍に関係なく優秀な人材を探すため」という理由が第1位になっているが、これ以外の活用理由に着目すると、外国人の活用戦略はA型(海外とのネットワーク重視)とB型(外国人ならではの技能・能力重視)の大きく2つに分類することができる。 |
図表5−1 外国人の活用戦略
| A型(海外とのネットワーク重視) | B型(外国人ならではの技能・能力重視) | その他 | ||||||
| 海外とのネットワーク構築のため | 日本の外資系企業と取引等が増えてきたため | 海外との取引等が増えてきたため | 海外進出の足がかりとするため | 外国人のほうが高い専門能力を持つため | 外国人ならではの技能・発想を取り入れるため | 国籍に関係なく優秀な人材を探すため | 日本人では、必要な従業員を充足できないため | |
| 製造業 | ○ | △ | ◎ | |||||
| 通訳・翻訳会社・語学学校 | △ | ◎ | ○ | |||||
| 卸売・小売・商社 | ○ | △ | ◎ | |||||
| 旅行・ホテル | ○ | ◎ | △ | |||||
| 金融・保険・証券 | ○ | △ | ◎ | |||||
| 私立大学・研究機関 | △ | ○ | ◎ | |||||
| 情報・通信 | ○ | △ | △ | △ | ◎ | |||
| 注) | 印は各産業分野における上位3位。◎は1位、○は2位、△は3位。 |
| それぞれの産業分野を上記の2つの活用戦略に当てはめていくと、下表のように「製造業」、「卸売・小売・商社」、「情報・通信」はA型、「通訳・翻訳会社・語学学校」、「私立大学・研究機関」はB型となる。 |
| 活用戦略 | 産業分野 |
| A型(海外とのネットワーク重視) | 製造業 |
| 卸売・小売・商社 | |
| 情報・通信 | |
| B型(外国人ならではの技能・能力重視) | 通訳・翻訳会社・語学学校 |
| 私立大学・研究機関 | |
| その他 | 旅行・ホテル |
| 金融・保険・証券 |
| (1) | A型「海外とのネットワーク重視」 |
(製造業、卸売・小売・商社、情報・通信)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「海外とのネットワーク重視」型の「製造業」、「卸売・小売・商社」、「情報・通信」では、海外との取引等のために、その取引先の言語や商習慣になじみがあり、日本と海外の間の架け橋となる人材を求めており、その戦略の中で外国人が活用されていると考えられる。 この活用戦略をとる法人では、外国人を活用している割合、また就労している外国人の数は決して多くはないものの、他の活用戦略をとる法人と比べて、外国人従業員の間で留学経験者が占める割合が3割と高くなっている。これは、日本で留学を経験した者は、出身国に関しての商習慣や文化に関する知識があると同時に、日本の文化や商習慣に比較的になじみがあることと関係していると思われる。 「海外とのネットワークを重視」する法人における今後の外国人の活用意向は、それほど高くはないが、既に活用している法人の間では、今後人数を増やしていこうとする法人が2割強、現状を維持していこうという法人が3分の1近くいる。 外国人を採用・活用する際の問題点としては、他の活用戦略をとる法人と大きく変わらないものの、「文化・習慣の違い」、「職場内での意思の疎通」、「日本企業の仕事の進め方への対応」といった点を挙げている割合が高くなっている。そのため、「海外とのネットワークを重視」する活用戦略をとる法人においては、既に述べたように、日本語、日本文化にある程度なじみがあると考えられる留学生をどのように活用していくかが重要になってくる。 |
| (2) | B型「外国人ならではの技能重視」 |
(通訳・翻訳会社・語学学校、私立大学・研究機関)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「外国人ならではの技能・能力を重視」型の法人の第1の特徴は、外国資本が参入している法人はほとんどいないにも関わらず、外国人のいる法人の割合が8割にのぼる等非常に高くなっており、かつ全従業員に占める外国人従業員の割合も比較的高くなっていることである。この活用戦略をとる法人である「通訳・翻訳・語学学校」や「私立大学・研究機関」は、語学教師を配していることが多いと考えられ、ネイティブスピーカーとしての外国人の特性を活用していこうという法人であると言える。 そのため、これらの法人で従事する外国人は留学経験者の占める割合が他の活用戦略をとる法人に比べて低くなっており、入職経路としても、「日本以外での新聞・雑誌・求人誌・HP」をみて応募してきたケースや「海外の大学などからの紹介」によって職に就くようになったケースが多くなっている。 なお、「外国人ならではの技能・能力を重視」している法人では、日本人、外国人に関わらず、非正規従業員が占める割合が5割近くになる等、雇用期間を限定しての契約形態が非常に多くなっているが、この傾向は、外国人従業員の間ではさらに顕著となっており、8割にのぼる外国人従業員は非正規従業員として就労している。また、法人が直接的に雇用するだけではなく、外国人の派遣労働者を活用する等、間接雇用による外国人の活用や、外国人の個人事業主との契約も多くなっている。 今後の活用意向については、他の活用戦略を持っている法人と比べて現状維持若しくは人員増加の意向を持っている法人の割合が7割近くにのぼっているように非常に高くなっており、「外国人ならではの技能や能力」を必要とするこの分野では、外国人就業者への必要性は今後強いものと考えられる。 「外国人ならではの技能・能力を重視」している法人では、既に述べたように、非正規従業員として活用される外国人の割合が高い、並びに間接雇用、個人事業主との契約が多いといった、この分野特有の外国人の活用方法によって就業する外国人が不利な立場に追い込まれないよう配慮していく必要がある。 |
| (3) | その他 |
| 外国人を日本において活用していく際には、既に述べたように、大きくA型、B型という2つの戦略のもとに活用していると言えるが、これらの分類に明確に区分することができない産業分野として、「旅行・ホテル」並びに「金融・保険・証券」がある。 「旅行・ホテル」においては、前節でも記述したように、外国人従業員の間では「技能」の在留資格を保有している者が多く見られる(115ページ参照)。この分野で「技能」の在留資格を保有して就労している人は、主としてレストランのコック等の職に就いていると考えられる。このような職種について、外国人が活用されるのは、外国人ならではの技能・発想が必要とされるとともに、日本人では、本場の味を提供するために必要な技能を持った従業員を充足できないことの表れであると言えよう。 また、他の産業分野よりも外国資本が参入している法人の割合が高い「金融・保険・証券」では、外国人就業者は「海外にある同系列の会社・職場からの派遣」によって日本で働くようになった人の割合が高くなっており、それと同時に「投資・経営」や「企業内転勤」の在留資格を保有する者が多くなっている。 この活用戦略をとる法人では、同系列の法人・グループ内での企業内転勤が多いことを反映してか、一般的には非正規従業員として就労する割合の高い外国人従業員でも雇用期間が定められていない正規従業員として就労するが多くなっている。 なお、「金融・保険・証券」のうち、既に外国人を活用している法人では、今後とも現状を維持していこうとする法人が半数以上を占めているように、外国人を引き続き活用しようという法人は多い(55ページ図表3−21参照)。しかしながら、企業内転勤が多いということは、ある一定の期間を経ると出身国に戻るケースも多いものと考えられるため、この分野での外国人の就労を円滑に進めていくためには、企業内転勤が多い、正規従業員が多い等の特性に応じた雇用管理を実施していくことが望まれる。 |
| 3. | 調査結果から得られた示唆 |
| (1) | 産業分野によって外国人就業者に求められる素質は異なる |
| 外国人が就業している法人のうち、「通訳・翻訳・語学学校」、「金融・保険・証券」の2分野は他分野に比べて全従業員に占める外国人従業員の割合が高く、全体平均2.0%に対し、「通訳・翻訳・語学学校」では10.3%、「金融・保険・証券」では10.0%となっている(25ページ図表3−5参照)。また、1法人あたりの外国人従業員の割合はそれほど高くないものの、外国人が就業している割合が非常に高くなっているのは、「私立大学・研究機関」であり、9割に及んでいる。(23ページ図表3−4参照)。 既にみたように、「通訳・翻訳・語学学校」、「私立大学・研究機関」では、ネイティブスピーカーとしての外国人への必要性があるために、外国人の就業が多くなっていると考えられる。一方、「金融・保険・証券」においては、外国人就業者の占める割合は高いものの、その多くは、外資系企業の中での経営者、管理職として働いていたり、企業内転勤の形で派遣された者も多く含まれていると考えられる。 この結果、上記の3分野ではいずれもの外国人就労機会は多いと同時に、外国人の雇用管理に関するノウハウに一定の蓄積があると考えられるが、人材に求められる素質が異なるために、必要とされる雇用管理も異なってくると思われる。 そのため、これらの分野において、それぞれ外国人に対してどのような雇用管理を行っているかをさらに詳細に調査していくことによって、今後外国人を活用していきたいと考えている法人にとっての参考となるであろう。
|
| (2) | 外国人就業者は雇用契約に一定の期限がある者が多い |
| 今回の法人アンケート調査の中では、外国人従業員に占める非正規従業員の割合は69.2%となっており、今回調査回答法人全体の平均の非正規従業員比率25.3%に比べて非常に高い数値を示している。これを分野別にみると、「製造業」(外国人従業員に占める非正規従業員の割合43.3%、調査回答法人全体の非正規従業員の割合9.7%)、「旅行・ホテル」(同79.5%、37.0%)、「私立大学・研究機関」(同72.5%、41.0%)、「情報・通信」(同33.3%、11.5%)、「出版・印刷・広告代理」(同58.8%、13.8%)等で外国人は日本人も含めた全従業員よりもの非正規従業員として働いている比率が大幅に高くなっていることがわかる。 なお、非正規雇用契約については、「各企業において労働条件通知書の発行がおろそかになりがちな実態がある」という指摘がある。これらのことを考えあわせると、今後は、(1)上記分野で外国人の非正規比率が高い理由や、(2)上記分野での非正規雇用契約の際の契約内容(雇用期間、勤務条件、職務内容等)の実態について、さらに詳細な調査の実施を検討する必要もあろう。 |
図表5−2 非正規従業員の占める割合(単位:%)
| 全回答法人 | 外国人がいる法人 | 外国人がいない法人 | |||
| 外国人従業員 | |||||
| 全体 | 25.3 | 25.2 | 69.2 | 25.6 | |
| 産業分野 | 製造業 | 9.7 | 7.9 | 43.3 | 16.5 |
| 通訳・翻訳・語学学校 | 80.5 | 82.5 | 90.8 | 49.8 | |
| 卸売・小売・商社 | 38.2 | 38.2 | 33.3 | 38.3 | |
| 旅行・ホテル | 37.0 | 40.7 | 79.5 | 33.9 | |
| 金融・保険・証券 | 12.6 | 8.9 | 14.7 | 17.7 | |
| 私立大学・研究機関 | 41.0 | 41.9 | 72.5 | 24.5 | |
| 情報・通信 | 11.5 | 9.2 | 33.3 | 14.7 | |
| 出版・印刷・広告代理 | 13.8 | 4.2 | 58.8 | 20.5 | |
| その他 | 70.1 | 79.1 | 41.6 | 56.5 | |
| 従業員 規模 |
0〜30人未満 | 23.8 | 18.7 | 47.1 | 26.0 |
| 30〜100人未満 | 30.3 | 31.6 | 51.3 | 29.7 | |
| 100〜300人未満 | 28.8 | 32.3 | 53.7 | 25.0 | |
| 300人以上 | 24.7 | 24.6 | 75.4 | 25.2 | |
| 外資の参入状況 | 入っている | 15.7 | 15.3 | 22.9 | 22.6 |
| 入っていない | 28.6 | 29.7 | 78.2 | 25.9 | |
| 注) | 各項目の対象となる法人数については27、29、31ページの図表3−6、3−7、3−8を参照。 |
| (3) | 「通訳・翻訳・語学学校」に多い外国人個人事業主 |
| 今回調査回答法人のうち、とりわけ「通訳・翻訳・語学学校」の分野では外国人個人事業主との請負契約が多くなっている。調査回答法人平均の「外国人個人事業主との請負契約がある」ケースが6.1%なのに対し、「通訳・翻訳・語学学校」分野では28.7%が「外国人個人事業主との請負契約あり」としており、また「外国人個人事業主との請負契約あり」とした法人全体の平均契約人数が7.0人であるのに対し、「通訳・翻訳・語学学校」分野における平均契約人数は12.1人となっている(40ページ図表3−14参照)。 外国人が被雇用者として就労する場合と比べ、個人事業主として就労するケースは決して多くはない。しかし、請負契約については労働関連法の範囲外であること等から、契約面において個人事業主が必要以上の不利益を被る可能性は否定しきれない。こうしたことを考慮すると、今後「通訳・翻訳・語学学校」分野を中心に、外国人個人事業主との請負契約の実態を整理把握していくことも有効だと考えられる。 |
| (4) | 外国人就業者の入職経路は産業分野ごとに異なる |
| 外国人就業者の入職経路は多岐にわたっており、そのなかでも「日本での新聞・雑誌・求人誌・HP」が主なものであるものの、産業分野ごとにそれぞれ特徴があることも指摘できる。 「金融・保険・証券」においては、今回の調査回答法人に外資系企業が含まれている割合が高いことを反映して、「海外にある同系列の会社・職場から派遣」されるという企業内転勤の経路をたどって入職しているケースが多くなっている。今回、この分野で雇用されている外国人は他の分野の外国人と比べて、正規従業員として雇用されている者の割合が非常に高くなっていることも、こうした企業内転勤の多さと関連していると言えよう。また、「金融・保険・証券」では、「国内の人材紹介業者・人材派遣会社」のような法人が介在した入職のケースが多く見受けられた。近年、金融関係をはじめとしてヘッドハンティング等により高度な専門知識・技術を持つ人材についての人材紹介を行う企業が増えている。この分野で外国人が「国内の人材紹介業者・人材派遣会社」を通じて職に就くケースが若干ながら多くなっているのは、このような人材紹介・人材派遣会社の動きが影響しているのではないかと推測される。 一方「通訳・翻訳・語学学校」においては「日本での新聞・雑誌・求人誌・HP」の他に「現在の会社・職場の外国人、友人・知人からの紹介」のように人脈を主とするケースが多くなっているものの、他の分野と比較して特徴的であったのは、「日本以外での新聞・雑誌・求人誌・HP」を通じての応募、就職も多くなっていることである。これは、既述のとおり、語学教師としてネイティブスピーカーを確保するべく、海外において募集・採用活動をしているためであると考えられるが、このように海外で募集、採用活動を行っている法人は採用コストを問題視する声が若干強くなっている。 このように産業分野によって入職経路とその背景は異なっており、外国人雇用の促進を考える場合には、産業分野に応じた若しくはその業界が求めている採用のプロセスに着目することが重要だと思われる。 |
図表5−3 産業分野によって異なる入職経路
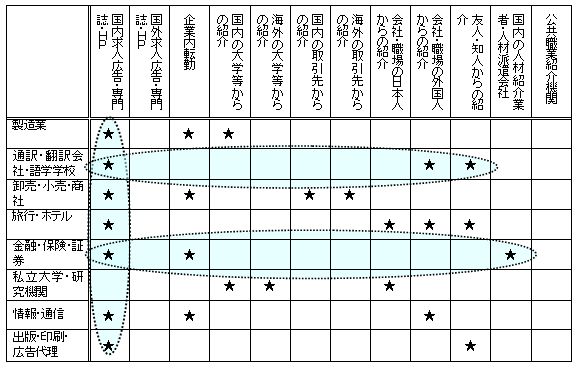
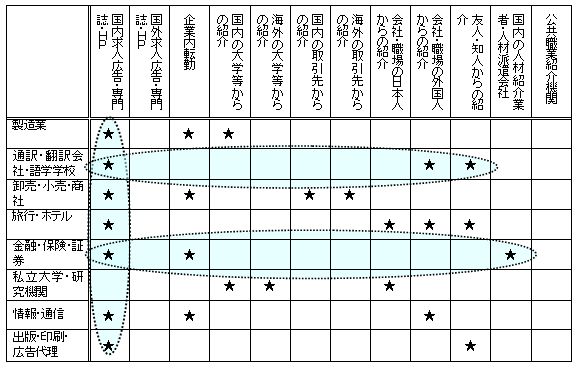
| 注) | ★印は各産業分野における上位3位。 |
| (5) | 外国人就業者の社会保険への加入は不十分である |
| 「国民皆保険・皆年金」制度をとっている我が国では、若干の例外を除いて各種の社会保険制度については、日本国内で働く外国人にも日本人と同じ制度が適用されることになっている。 今回の個人アンケート調査によると、健康保険や年金保険については、多くの人が勤め先で公的な健康保険や年金保険に加入していたり、自分で国民健康保険や国民年金に加入しており、いずれにも加入していない若しくは加入しているかどうか分からないという回答は少なくなっている。ところが、雇用保険、労災保険については、加入しているかどうか分からないという回答が多く、加入していると自覚している人の割合は4割以下になっている(94〜95ページ参照)。 以上のような状況を鑑みると、国籍に関わらず日本で就労している上では、我が国の社会保険に加入しなければならないということを周知させ、加入を促進していくことが必要になってくる。 ただし、その一方で検討しなければならないのは、我が国で就労している外国人たちが、必ずしも社会保険への加入を希望していないことである。個人アンケート調査によると、日本での各種社会保険への加入が選択できる場合には、加入を希望するかについては、健康保険で加入を希望する人が半数を超えたものの、他の社会保険については加入を希望する人の占める割合が半数以下になっている(95ページ図表4−28参照)。 特に加入を希望する割合が4割程度にとどまっている年金保険については、保険料の納付期間が国民年金の場合は25年、厚生年金の場合は20年に達しないと老齢年金を受給することができないために、負担と受益の関係が見えにくい状況にある。外国人の場合は、日本以外での就労経験があったり、いずれは出身国に帰っていこうと考えている人もいる。就労活動を一貫して日本で営んでいくのであればよいが、それ以外の場合には、年金保険の加入期間を日本において、ときには海外においても満たすことができないケースが生じうる。また出身国等の日本以外の年金保険に加入しており、日本で年金保険料を納入すると海外の年金保険制度と重複して加入する場合がでてくる。このような理由から年金については加入を希望しない人の割合が高くなっていると思われる。 前者に対処するためには、年金保険加入者には「脱退一時金」の支給を受ける権利があることを認知させていくこと、また保険料の最低納付期間をみたせば、日本国外においても年金を受給することができることを認知させていくことが重要となってくる。また、現在既に年金の加入期間の通算を行うためにドイツ、イギリスとの間で社会保障協定を締結している。この社会保障協定の締結相手国をさらに拡大させていくことにより、より多くの外国人の年金保険への加入期間の分断や複数国の年金保険への重複加入を防いでいくことができよう。 また、雇用保険、労災保険に関しては、加入しているかどうかわからないという回答がいずれも3割を超えている。これらに関しては、加入を希望する者も5割近くにまでのぼっていることから、外国人を雇用する事業主に対して、加入を徹底させていくとともに、就労する外国人に対してもこれらの社会保険に加入することが必要であるということを周知させていくことが重要である。 |
| (6) | 外国人就業者にとって「住宅の確保」は深刻な問題のひとつである |
| 外国人を雇用する法人の側はそれほど大きな問題としてとらえていないが、日本で就労する外国人のうち、最も多くの人が生活する上で問題であると考えているのは「住宅」である。我が国の民間の賃貸住宅では、保証人が必要となることが多く、外国人は保証人を立てることに苦慮することも多いと考えられる。ところが、外国人就労者のために、勤め先が宿舎や借り上げ社宅、寮を用意している法人は外国人を雇用している法人の中でも、全体の約3分の1にとどまっており、それ以外の法人で就労している人は、自ら住宅を探さなければならない環境にある。 外国人を積極的に活用していこうと考える場合には、彼らに対して住宅を用意することはなくとも、法人が賃貸住宅の保証人となったり、保証人を必要としない住宅を紹介していくことも一つの方策として考えられる。 また、外国人の中には、日本の住宅の狭さや家賃の高さについて不満を訴える人もいる。一般的に日本の家屋の広さは海外のものに比べて劣るといわれている。しかし、家賃が高いが故に十分な広さの家に住むことができない場合もある。専門的・技術的分野で働く外国人は必ずしも賃金が高いという理由で日本で働いている人が多いわけではないが(102ページ図表4−33参照)、家賃が高く、十分な広さの家に住むことができなければ、日本で働くインセンティブにとって一つのマイナス要因となるであろう。これに対処するためには、現在、法人、個人両アンケート調査で3割程度であった家賃補助(52ページ図表3−20、97ページ図表4−30参照)等の活用も一つの手段であると考えられる。 |