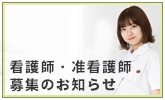リハビリテーション科 職場紹介 No.6
 リハビリテーション科入口 入園者の方が作られた手芸作品などを飾っています |
 手芸部の活動 押し絵作成の様子 |

「リハビリテーション科」の具体的な業務(仕事)内容を教えて下さい。
|
入所者の方々が現在の生活を維持できるように、それぞれのセラピストの立場からリハビリテーションの業務に取り組んでいます。 現在、リハビリテーション科(以下リハ科)には理学療法士3名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・義肢装具士2名が在籍しています。(義肢装具室はすでにホームページで紹介されています。) 理学療法士は起きる・立つ・歩くなどの動作や呼吸器リハビリ、痛み軽減のリハビリをしています。 作業療法士は精神機能の賦活や手指機能のリハビリをしています。リハビリの一環として、手芸部の運営もしています。 言語聴覚士は病気や障害、加齢によって食べ物を飲み込むことが難しくなった方への摂食嚥下機能訓練、その他にも言語療法や構音訓練をしています。 精神機能の賦活や摂食嚥下機能訓練においては、3職種でそれぞれの専門分野で係わりをもって協力して対応しています。 他科とのチームアプローチとして、栄養サポートチーム(NST)にリハ科から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が参加しています。週一回病棟を回診して、他職種と情報を交換しリハビリに役立てています。 |
  リハビリテーション科 リハ室 季節毎に装飾を変えてます 3~5月は桜の木と五月人形です |
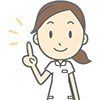
この職場で印象深いことはなんですか。
|
入所者の方々は気軽に声を掛けてくださり、いろいろなお話をしてくださいます。障害をもっているけれども明るい方が多く、昔のことや園内外のことなどを詳しくお話しくださる方もいらっしゃいます。 園内には、生活の自立した方が暮らす一般舎と不自由者棟と病棟があります。一般病院の退院と違い、現在は対象者が退所されることがありません。ですので、退院後も自宅に伺ったり、リハ科に来られたりと入所者の方々と長く深く接することが多くなります。リハビリの一環で一緒に散歩や山菜取りに出かけたこともありました。 |
 病室での座位保持訓練の様子 |

栗生楽泉園ならではの業務はありますか。
|
当園では年に数回程度、レクリエーションとして様々なイベントをおこなっています。七夕、運動会、年忘れ会など季節ごとのレクリエーションの準備はリハ科が主体となっておこなっています。詳しくはホームページに随時掲載されているので、そちらをご覧ください。 また、入所者の方にはハンセン病の後遺症があることにも配慮しています。例えば、視覚障害の方が多いのでその方の誘導や物品の配置、光量の管理などに注意しています。 対象者へのリハビリ期間は長くなっていきますので、遊びやゲームの要素を取り入れたり、楽器を利用するなど音楽も取り入れています。 |

平行棒を使用した 歩行訓練の様子 |

今後取り組んでいきたいことはありますか。
|
リハビリをされていない方やリハ科にあまり来られない方とも接する機会を増やしていきたいと思っています。その上で、他職種とチーム医療連携を行うことで転倒予防や肺炎予防に取り組み多くの入所者の方々のお役に立てればと考えています。 |

温熱療法における パラフィン浴の様子 |

摂食嚥下機能訓練の様子 |
※パラフィン浴 パラフィン(ろう)を50数度に温めて溶かしたものに、両手を数回浸けて温めます。 関節を温めてその後動かすことにより、関節の動きが悪くなるのを防止します。 |
||
| ▼前のページへ戻る | ▲ページトップへ |