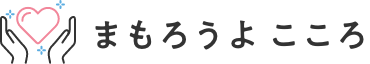2024.02.16
interview
企画・制作 朝日新聞社メディア事業本部
ソーシャルワーカー(精神保健福祉士)
伊藤次郎(いとう・じろう)さん
ソーシャルワーカー(精神保健福祉士)。人事コンサルティング会社、精神科クリニック勤務を経て2013年、ICTを活用した自殺ハイリスク者への相談支援を開始。2014年にNPO法人OVA(オーヴァ)を設立。厚生労働省「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」や東京都「自殺総合対策東京会議」の委員を務める。
「死にたい」という気持ちは目には見えません。自殺のリスクが高い人と、どうつながることができるのか。自殺防止の相談支援に取り組むOVA代表の伊藤次郎さんはこの10年、ICT(情報通信技術)を活用し、生きづらさを抱えた人たちの思いに耳を傾けてきました。かつては“当事者”でもあった伊藤さんは、死にたい気持ちの底にあるのは孤独感だと話します。命の門番とも言われる「ゲートキーパー」活動や、死にたいほどつらい気持ちに寄り添うために必要な支援や環境づくりについて聞きました。
扇情的な自殺報道は「見ない、聞かない、シェアしない」

──2020年の新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、自殺者が増加しました。特に女性とこどもが増えている背景をどう捉えていますか?
複数の要因が絡まり合っていて一概には言えませんが、大きくいえば感染症の拡大によって人と人とのつながりが脆弱(ぜいじゃく)になり、お互いの悩みにも気づきづらくなり、孤独感が高まったことがあると思います。
女性の場合は宿泊業や飲食業を中心に非正規雇用者がコロナ禍で契約を打ち切られた影響もあるかもしれません。こどもは大人に比べて活動量も多いですが、休校や課外活動の中止など、活動が大幅に制限され、友達との交流も減って、ストレスが高まっていたように思います。小中学校の不登校児童生徒数や児童虐待相談対応件数は感染が拡大した2020年度以降も過去最多を更新し続けています。
──この数年、若い世代の著名人の自殺が相次ぎました。以前と比べると報道が抑制的になった印象を受けます
著名人の自殺がメディアでセンセーショナルに報道されると、その後の自殺死亡率が増加する現象は世界中で起きています。これは「ウェルテル効果」と呼ばれます。WHO(世界保健機関)が作成した自殺報道のガイドラインに沿って、抑制的に報道するメディアが増えたことは非常に良い傾向だと思います。ただ今は個人がSNSなどで自由に発信できる時代です。不適切な情報や報道を個人がシェアし、拡散されることで、 周囲の人たちの自殺リスクを高めてしまう可能性があります。一人ひとりが扇情的な報道や情報を「見ない、聞かない、シェアしない」ことを心がける必要があると考えています。
“死にたい”と思っている人を可視化したICT技術
OVAは、広告のマーケティング技術を応用した自殺ハイリスク者への相談支援団体です。「死にたい」といった自殺関連用語をインターネットで検索すると、相談を促すための広告が表示され、特設サイトに誘導する仕組みです。特設サイトからはワンクリックで相談メールを送ることができます。現在、OVAの職員約50人のうち、約30人の臨床心理士や精神保健福祉士などの専門家が相談に対応しています。
──インターネット広告を使った支援活動を始めた経緯を教えてください
2013年の6月に若者の自殺死亡率についてニュースになっているのを見聞きしました。でも、“死にたい”と思っているかどうかは目に見えません。もしそれがわかれば、支援につなげられるのではと思いました。そこで、インターネットで検索している人の数を調べてみたところ、「死にたい」という言葉がひとつの検索エンジンだけで月に十数万回も検索されていることがわかりました。
検索している人に向けて、相談窓口の広告を出せば、直接情報を届けられると考え、2013年から活動を始めました。現在は、自殺防止活動に取り組む自治体と連携して、そのエリアで自殺に関連する言葉を検索するとOVAの広告が表示される仕組みになっています。相談者は20、30代が多いです。

──この10年の活動で変化を感じたことは何でしょうか?
ICTを活用した自殺対策は明らかに進みましたね。一つは、自殺リスクの高い人にリーチできるようになったこと。特定の地域で自殺念慮者を把握するだけにとどまらず、「DV被害」「いじめ」「虐待」などのワードを調べている人たちに向けて適切な広告を出すなど、より詳細に困っている問題に応じてリーチできるようになりました。もう一つは、従来の電話相談から、メールやオンラインチャットで相談を受けられるようになったことです。今の若者は普段、テキストでコミュニケーションを取っていますよね。電話だと心理的ハードルが高くなってしまうため、最初のコンタクトとしてSNSやメールは非常に有効だと考えています。
一方で変わらないことは、死にたいという気持ちの背景にあるのは「孤独感」だということです。生活困窮や病気などそれぞれ抱えている問題は異なりますが、居場所のなさや孤独感は共通しています。生活のあらゆる場面で見られる昨今の効率化は、人間同士のつながりを弱め、孤独感を高める社会を加速させているようにも感じています。
「ゲートキーパー」「パパゲーノ効果」とは
──伊藤さん自身、10代の頃に「死にたい」思いを抱えていたそうですね。当時、その気持ちを誰かに打ち明けていましたか?
いいえ、誰にも言いませんでした。学校での勉強の成績もそれなりで、運動部の部長を務めていて、先生や周囲からは順風満帆に見えたでしょうから、悩みなどないと思われていたかもしれません。でも、考えていることが人と違い過ぎていて、「自分はおかしいのでは?」と幾度となく思いました。誰かにわかってほしい気持ちはありましたが、家族を含めて、自分の思いをうまく伝えられる気がしませんでした。私の場合は、たまたま自分の気持ちや考えを文字にして、気持ちを整理していくことができました。読書を通じて「先人たちも自分と同じようなことで悩んでいたんだ」と受容される感じを得たのも大きな体験でした。
──死にたいという気持ちを伝えることは簡単ではありません。それでも一歩を踏み出すには何が必要だと思われますか?

死にたいほどのつらさは、おそらく数カ月、数年かけて追い込まれていった結果だと思います。人間はストレスがたまると、心と体と行動に変化が起きます。眠れなくなったり、お酒の量が増えたり、衝動買いを繰り返したりなど、人によって反応はそれぞれ違いますが、ストレスがかかると自分はどのような反応が出るのかを知っておいてほしい。早めに自分でサインに気づくことができれば、助けを求めやすくなると思います。
相談を受ける側は、「自分だから話してくれたんだ」と思い、「話してくれてありがとう」と受け入れてほしい。相手の思いを聞き、抱えている問題を整理して、例えば眠れないのだったら医師へ、借金に悩んでいるのだったら弁護士へ相談してもらう。このように必要な支援につなげることが「ゲートキーパー」の役割です。1人で支えるのではなく、チームで支えることも大事です。
──近年、自殺防止に効果があるという「パパゲーノ効果」という言葉を聞くようになりました
センセーショナルな自殺報道によって自殺者が増えるという「ウェルテル効果」とは反対に、自殺を思いとどまった体験談や物語に触れることに自殺を抑制する効果があるという考え方です。パパゲーノとはモーツァルトのオペラ「魔笛」の登場人物のこと。死にたいほどつらい気持ちを抱えながらも生きることを選択したストーリーに対し、自分を重ねる「同一視」と、他者の言動から学ぶ「観察学習」の観点から、有効だと考えられます。こうした観点からメディアが自殺予防に取り組むことに期待しています。
テクノロジーは道具、どう使うかが大事
──これからの自殺防止対策に必要なことは何でしょうか?
AIの台頭やテクノロジーのさらなる発展といった社会環境の変化によって、取り残されたり排除されたりする人が出てくるでしょう。その結果、自分が社会に役立っている感覚が薄れてしまうことを危惧しています。そのためにも、人と人がつながり、社会参画していく機会を作っていける枠組みや仕組みを、テクノロジーを活用しながら作っていきたいと思っています。
検索連動型広告の活用で、自殺リスクが高い人にアプローチをすることはかなりできるようになりました。一方で、「死にたい」とつぶやいている人を標的にしたネット上の犯罪もいまだにあります。悪意の手よりも先に、支援の手が届く方法論も考える必要があります。
「死にたい」という気持ちには、「問題解決ができるなら生きたい」という気持ちも含まれています。そのはざまで揺れ動いている状態なので、他者に「死にたい」と打ち明ける行為は、生きるための行為でもあるのだと思います。死にたいほどに苦しい気持ちをこれからも受け止められるような活動をしていきたいです。