ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 医療事故情報収集等事業 > 第8回全般コード化情報の分析について
第8回全般コード化情報の分析について
第8回全般コード化情報の分析について
1.全般コード化情報の収集状況
| 報告施設数 | :72施設(前回88施設) |
| 収集期間 | :平成15年4月〜6月 |
| 全般コード化情報事例数 | :12909件(前回10504件) |
2.分析方針
分析は以下の方針に基づき実施した。| 1) | 収集した事例について、頻度を単純集計した。なお、発生場面、発生内容については、患者の性別ごとの集計も行った。 |
| 2) | 収集した事例について、項目間の相互関係を把握するため、それらのクロス集計を行った。 |
| 3) | 報告事例の多い「処方・与薬」「ドレーン・チューブ類の使用・管理」「療養上の世話、療養生活の場面」および影響度の大きい事例の割合が高い「医療機器の使用・管理」「輸血」については、該当するデータを抽出のうえ、項目間のクロス集計を行った。 |
3.分析項目
以下の項目について、単純集計、クロス集計を行い、この結果を集計表とグラフに整理した。
<単純集計>
以下の項目について単純集計を行った。
| ・ | 発生月(A) |
| ・ | 発生曜日(B) |
| ・ | 発生時間帯(C) |
| ・ | 発生場所(D) |
| ・ | 患者の性別(E) |
| ・ | 患者の年齢(F) |
| ・ | 患者の心身状態(G;多重回答) |
| ・ | 発見者(H) |
| ・ | 当事者の職種(I;多重回答) |
| ・ | 当事者の職種経験年数(J) |
| ・ | 当事者の部署配属年数(K) |
| ・ | ヒヤリ・ハット事例が発生した場面(L) |
| ・ | ヒヤリ・ハット事例が発生した要因(N;多重回答) |
| ・ | 間違いの実施の有無および事例の影響度(O) |
<クロス集計>
以下の項目間のクロス集計をおこなった。
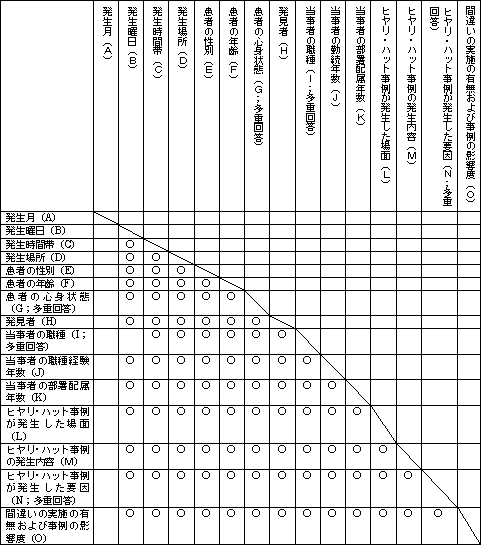
4.分析結果
1)全事例【12909事例】
報告事例数が約2割増加している(前回10504例)が、頻度分布に特におおきな変化は見受けられず、全体的にほぼ同様な傾向となっている。
○発生曜日【図1−2】
これまでと同様、平日(月〜金)の発生件数は土・日よりも多いが、平日の中で特定の曜日に集中する傾向は見当たらない。
○発生時間帯【図1−3】
これまでと同様、6〜7時台になると増加し、8〜11時台にほぼピークとなり、12〜19時まではやや減るもののほぼ一定頻度となり、20時以降減少するという日内変動を示している。
○患者の性別【図1−5】
これまでと同様、男性患者に発生したヒヤリハットの件数が女性患者よりも多い。男性患者には何らかのリスク要因があることが強く示唆される。
特に51〜80歳で「処方・与薬」「ドレーン・チューブ類の使用管理」「療養上の世話等」における男女による発生頻度の差が大きくなっており、中高齢の男性患者へのアセスメント等を強化する必要があると推察される。
○患者の年齢【図1−6】
これまでと同様、71〜80歳、61〜70歳、51〜60歳の順に多く、この3区分で約半数を占めており、中高齢患者のリスク要因が高い可能性がある。次いで0〜10歳の区分での発生が多い。
○職種経験年数、部署配属年数【図1−10〜11】
経験年数0年、1年の事例が、職種経験では約3割、部署配属年数では4割を占める。新入職員および部署異動後の教育・指導体制の充実が求められる。
○発生場面【図1−12】
これまでと同様、「処方・与薬」、「療養上の世話」+「その他の療養生活の場面」、「ドレーン・チューブ類の使用・管理」の順でヒヤリハットが発生している。
○発生要因【図1−13】
これまでと同様、発生要因として「確認」をあげている件数が最も多く、ついで「観察」「心理的状況」「勤務状況」「判断」となっている。個別の選択肢で見ると「勤務状況」では「多忙であった」「夜勤であった」が突出しており、「心理的状況」では「思い込んでいた」「慌てていた」「他のことに気をとられていた」が多い。これらの状況が確認不足等を引き起こしている可能性が推測される。
○影響度【図1−14】
間違いが実施された事例が3分の2となっている。実施前に発見されたが患者への影響が大きいと推測される事例が141件発生していた。
○患者年齢×患者性別【図1−15】
11―50歳代の若年者には男女性差はみられない。
○発生内容×患者性別×患者年齢【図1−17 (1)−(5)】
処方・与薬で0歳から40歳代の若年者には男女性差はみられない。
○発生内容×患者性別×患者年齢【図1−17 (6)−(8)】
50歳から80歳代で男性の方が多い。
○影響度×患者性別【図1−19】
間違いが実施されたのは男性の方が多い。
2)処方・与薬
○発生時間帯【図2−3】
これまでと同様二峰性の頻度分布を示し、午前では8〜11時台、午後は16時〜19時台の発生頻度が多い。
○発見者、当事者の職種【図2−8〜9】
これまでと同様、同職種者が発見するケースと、当事者本人のケースが多く、看護職者による自己確認、相互確認によって発見される割合が高い。
○発生要因【図2−14】
個別選択肢として、「看護職間の連携不適切」をあげる事例が302件あった。
○発生場面×発生内容【表2−2】
「内服×無投薬」が最も多く、ついで「内服×与薬時間・日付間違い」「末梢静脈点滴×投与速度速すぎ」「内服×過剰与薬」となっている。
「患者間違い」、「薬剤間違い」という重篤な結果につながりかねない事例も1割以上発生している。
○発生内容×患者性別【図2−17】
無投薬も男性の方が多い。
3)ドレーン・チューブ類の使用管理
○発生曜日・発生時間帯【図3−2〜3】
時間帯、曜日による発生頻度の差があまり見られなかった。全事例の頻度分布と比較すると、相対的に土・日、夜間などのリスクが高いと推測される。
○患者の心身状態【図3−7】
相対的に「意識障害」「痴呆・健忘」という状態が多く、リスク要因となっている。
○職種経験年数【図3−10】
職種経験0年と1年の発生頻度がほぼ匹敵している
○影響度【図3−15】
「間違いが実施」がおよそ3/4を占め、未然に発見されにくいといえる。
○発生場面×発生内容【表3−2】
栄養チューブ、末梢静脈ライン、中心静脈ラインの「自己抜去」が3割を占めている。
○発生内容×患者性別【図3−17】
ドレーン・チューブの自己抜去も男性の方が多い。
4)医療機器の使用・管理
○発生時間帯【図4−3】
今回の集計では10〜11時台の発生頻度がもっとも多かった。
○患者の年齢【図4−6】
61〜70歳、71〜80歳についで0〜10歳台での発生割合が高い。
○発見者【図4−8】
これまでと異なり、今回の集計では「同職種者」による発見事例が多かった。
○発生場面【図4−12】
輸液・輸注ポンプおよび人工呼吸器によるヒヤリハットが半数以上となっている。
○影響度【図4−15】
実施されていれば患者への影響は大きい(生命に影響)と思われる事例が18件(4.4%)と大幅に増えている。
○発生場面×患者性別【図4−16】
酸素療法機器、輸液・輸注ポンプも男性の方が多い。
○発生内容×患者性別【図4−17】
設定忘れ、電源入れ忘れも男性の方が多い。
5)輸血
全事例の件数が増加しているにもかかわらず、輸血に関するヒヤリハットの発生件数は前回より減少した。
○発生場所【図5−4】
病室での発生が減少し、ICUでの発生が増加している。
○当事者の職種【図5−9】
前回集計から「看護師」による発生割合が6割を超えている。ついで「医師」、「臨床検査技師」によるヒヤリハットが多く報告された。
○影響度【図5−15】
実施されていれば患者への影響は大きい(生命に影響)と思われた事例が9件(10%)報告された。
6)療養上の世話等
○発生曜日、発生時間帯【図6−2〜3】
曜日、時間帯による発生頻度の差が小さいが、時間帯では6〜7時台がやや多い。
○患者の年齢【図6−6】
71〜80歳台がもっとも多い。
○患者の心身状態【図6−7】
歩行障害、下肢障害の発生頻度が多い。
○発生内容【図6−13】
転倒が半数以上を占める。
○発生内容×患者性別【図6−17】
転倒・転落も男性の方が多い。
第8回全般コード化情報集計結果
図表目次
2)処方・与薬
3)ドレーン・チューブ類の使用・管理
4)医療機器の使用・管理
5)輸血
6)療養上の世話等
全般コード化情報集計結果
(第8回報告事例 12909件)
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 医療事故情報収集等事業 > 第8回全般コード化情報の分析について

