IAHのヒツジBSE病原性実験は現在も継続されている。組織の免疫細胞化学試験で得られたBSE罹患動物のデータが発表されている(Foster他 2001年)。BSE症例7頭(6頭は現在も生存)すべてにおいてCNS及びLSR組織がPrPSc免疫染色性を示したが、他の組織はこのような染色性を示さなかった。発表された結果からは得られた情報はARQ/ARQ型チェビオット種ヒツジにおける実験的BSEの臨床的症例に関するデータに限られているが(平均潜伏期間は、5g経口曝露後約25ヵ月)、心臓、肺、肝臓、胸腺を含む主要臓器の大半はPrPSc免疫染色性を示さなかった点に注意する必要がある。腎臓糸球体についてはごく弱い染色性が認められた。試験対象とした骨格筋及び生殖組織ないし皮膚についてはPrPScが存在する証拠は得られていない。
試験対象とした末梢神経(迷走神経、撓骨神経、坐骨神経)のうち、経口曝露によりスクレイピー病原性を示すことが多くの研究者によって示唆されているのは迷走神経のみであり、体性末梢神経はPrPSc免疫染色性を示していない点も興味深い。このような動物から採取した一定範囲の組織に関する感染性生物学的検定が現在行われている。潜伏期間の中の各時点で殺処分した動物に関する試験はまだ完了していない。暫定データは、動物によっては一部のリンパ組織から感染後早期にTSE感染性(PrPSc免疫染色性など)の証拠を検出できるというJeffrey他(2001年)の所見を支持するものである。
ロムニー種(潜伏期間範囲20〜37ヵ月に関する現在のデータ)
| − | 咽頭後リンパ節(LN) | 曝露4ヵ月後 |
| − | ペイエル板 | 曝露4ヵ月後 |
| − | 脾臓 | 曝露10ヵ月後 |
| − | 腸間膜LN | 曝露16ヵ月後 |
| − | 回腸盲腸LN | 曝露16ヵ月後 |
| − | 縦隔LN | 曝露16ヵ月後 |
| − | 扁桃 | 曝露16ヵ月後 |
| − | 顎下LN | 曝露16ヵ月後 |
| − | 遠位回腸(ペイエル板を除く) | 曝露16ヵ月後 |
| − | 腸間膜LN | 曝露16ヵ月後 |
| − | 肩前LN | 曝露16ヵ月後 |
| − | 気管支縦隔LN | 曝露16ヵ月後 |
| − | 脳及び脊髄 | 曝露16ヵ月後 |
| − | 肝臓(低レベルの感染性) | 曝露16ヵ月後 |
| − | 腸 | 曝露16ヵ月後 |
| − | 迷走神経 | 曝露16ヵ月後 |
| − | 噴門洞 | 曝露22ヵ月後 |
| − | 第四胃 | 曝露22ヵ月後 |
| − | 腹腔腸間膜神経節(交感神経) | 曝露22ヵ月後 |
ニュージーランドサフォーク種(初期臨床症例の潜伏期間24ヵ月に関する現在のデータ)
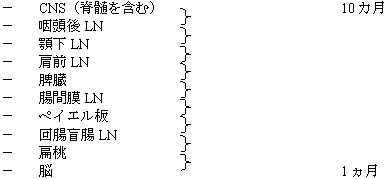
この試験では、ロムニー種ヒツジの一部については消化管全体にわたり腸神経系(ENS)ニューロンのPrPSc免疫染色性が認められたが(噴門洞の染色性が最も低かった)、ペイエル板については免疫染色性は認められないことも明らかにされた。
これまでのところ、臨床的症例でも胸腺の免疫染色性は検出されておらず、体性末梢神経幹(坐骨神経、横隔神経)や脊髄神経根の免疫染色性も検出されていない。
この試験からは、骨格筋感染性に関する新しいデータは得られていない。
同等の接種を行ったARQ/ARR型(BSE/スクレイピー感受性異型接合体)ロマニー種ヒツジでは、接種後約4年が経過したが、これまでのところ正常である。
試験で逐次殺処分した動物ではこれまでのところどの組織からもPrPScは検出されていないことから、これらの組織では曝露後最大2年間については確実に感染性が見られないと思われる。
これらのデータから、経口経路で比較的大量のBSE病原体に実験的に感染させたウシとは異なり、ヒツジの場合、少なくともARQ/ARQ型スクレイピー/BSE感受性個体では、潜伏期間早期に広範囲のリンパ組織が侵襲される可能性があると思われる。新しく得られたデータは、ヒツジに経口曝露したBSEは特に感染性又はPrPScの組織分布の点でスクレイピーとほぼ同じ病原性を示すというこれまでの見解と一致する。
BSEに実験的に感染させたヒツジから採取した組織の感染性力価データは得られていない。
ロムニー種及びサフォーク種ヒツジをBSE病原体に対して経口曝露したVLA試験(Jeffrey他 2001年)において採取された組織のマウス生物学的検定は不完全なものであるが、曝露を受けたロムニー種(ARQ/ARQ型)のヒツジから得た一定の組織については、RIII系マウス用量反応曲線から感染性力価の近似を得るに十分な潜伏期間データが得られている(S. Bellworthy、私信)。
曝露(マウス[ic+ip]ID50/g として104.0の接種材料5gに対する曝露)16ヵ月後までにヒツジの脾臓の感染性力価はマウス(ic+ip)ID50/gとして102.8に接近すると思われる。曝露10ヵ月後の値はこれよりも低く、その後に上昇する(データは不完全)。他のリンパ組織における曝露16ヵ月後の値はおそらく101.0であるが、その後上昇し、曝露22ヵ月後には(依然前臨床状態であるが)中枢神経系の感染性は103以上になる。
臨床的症状が発症したヒツジ(潜伏期間20〜28ヵ月)からはまだデータが得られていない(Jeffery他 2001年)。
2001年2月8日・9日に採択された本報告書の付属文書 3「飼育条件下で小型反芻動物からBSEが検出された場合に備えた先制リスク評価」(EC 2001年a)はこの試験の結果に基づくものであり、従って、BSE病原体に実験的に曝露したロムニー種(ARQ/ARQ型)ヒツジの組織感染性分類に関してこの付属文書は引き続き適用される(表 3)。