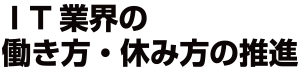長時間労働是正に向けた15の勘所
長時間労働是正に向けた
15の勘所
15の勘所
●●●●●●●
< 問題解決の勘所12 >
●●●●●●●
問 題
仕様以上の過剰品質の開発を行う
▼
勘所12
開発スコープを明確にし、規模の拡大を防止すべし。
開発スコープを明確にし、規模の拡大を防止すべし。
背 景
より良いシステムを顧客に提供することはITエンジニアとしての誇りです。
しかし、それが行き過ぎると、仕様を過度に超えた品質(つまり「過剰品質」)を作り込むということが往々にして起こります。
当然のことですが、過剰品質を作りこむには多くの時間が必要とされます。
それが長時間労働を生む大きな原因の一つなのです。
しかし、それが行き過ぎると、仕様を過度に超えた品質(つまり「過剰品質」)を作り込むということが往々にして起こります。
当然のことですが、過剰品質を作りこむには多くの時間が必要とされます。
それが長時間労働を生む大きな原因の一つなのです。
「限られた予算のなかで(お金)」「決められた期日までに(時間)」という制約のなかで、「何を」「どの様に」「いつまでに」作るのかという諸要素の組み合わせを決める。
これが開発スコープですが、「何を」に関わる品質は開発スコープのなかで決められます。
つまり実現すべき品質には絶対的な基準はなく、開発スコープのなかで相対的に、つまり予算、納期等とのバランスを考えて決められるものです。
これが開発スコープですが、「何を」に関わる品質は開発スコープのなかで決められます。
つまり実現すべき品質には絶対的な基準はなく、開発スコープのなかで相対的に、つまり予算、納期等とのバランスを考えて決められるものです。
ですから、「過剰品質」の開発は予算、納期等の他の要素に、予算を超えてしまう、納期が遅れる等の形で犠牲を強いることになります。
長時間労働はそのなかの一つの犠牲なのです。
長時間労働はそのなかの一つの犠牲なのです。
解決策
「過剰品質」の開発が起こらないようにプロジェクトマネジメントを整備する。
これが基本的な対応策になり、以下に示す勘所はそのための施策です。
なお、機能追加や変更、その他過剰な要求が争われた「過剰品質」を招くプロジェクトマネジメントの重要性については、過去の判決からも学ぶことができます。
これが基本的な対応策になり、以下に示す勘所はそのための施策です。
なお、機能追加や変更、その他過剰な要求が争われた「過剰品質」を招くプロジェクトマネジメントの重要性については、過去の判決からも学ぶことができます。
解決策1
過度な規模拡大につながることを防止するために、開発スコープを明確に設定します。
解決策2
開発スコープの明確化には、PMBOKのスコープマネジメントを活用することを勧めます。
解決策3
具体的には、それに従い、「プロジェクトの目標を達成するために必要な成果物とタスクの定義」、「プロジェクト期間を通じてその定義の見直し(必要に応じて)」、「必要な成果物とタスクが完成されていることの保証」を顧客に対して明確にしていく。
詳しくは、プロジェクトマネジメント協会(PMI)が発行する「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK)」をみてください。
詳しくは、プロジェクトマネジメント協会(PMI)が発行する「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK)」をみてください。
ヒントとなる取組事例
■スミセイ情報システム株式会社の取組
プロジェクトとPMO及び法務が連携し、案件毎にスコープと納期をモニタリングし、ステアリングコミッティに改善提案を行います。
ダメな場合にはスコープ自体を見直す(コントロール)こともあります。
ダメな場合にはスコープ自体を見直す(コントロール)こともあります。
■株式会社熊本計算センターの取組
前工程(契約前交渉)において、カスタマイズが大きい改修要件については、開発スコープを明確化し、規模の拡大を防止しました。