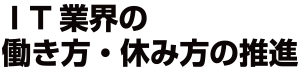長時間労働是正に向けた15の勘所
長時間労働是正に向けた
15の勘所
15の勘所
●●●●●●●
< 問題解決の勘所11 >
●●●●●●●
問 題
検収要件が明確にされない
▼
勘所11
検収要件に一致するよう、仕様に基づきレビュー・試験項目を早期に洗い出すべし。
背 景
納入時の検収では、顧客は納入されたソフトウェアが要求仕様に合っているかを検査し、合否の判断をします。
検収に合格すると一定の期日以内に発注者から受注者に費用が支払われてプロジェクトが完了します。
検収に合格すると一定の期日以内に発注者から受注者に費用が支払われてプロジェクトが完了します。
しかし、納品物と仕様の間に不具合があれば、どこに原因があるのかを調査し、受注者側にその責任がある場合には、不具合を修正する手戻り作業が受注者の費用負担によって行われることになります。
また、検収要件が明確にされていなかったために、不具合が発生することもあります。
この場合には、仕様変更が発生し、検収とともに開発にも予定外の作業が発生することになります。
いずれの場合にも、予定外の作業が発生することになるので、長時間労働が発生する大きなリスクとなります。
この場合には、仕様変更が発生し、検収とともに開発にも予定外の作業が発生することになります。
いずれの場合にも、予定外の作業が発生することになるので、長時間労働が発生する大きなリスクとなります。
解決策
こうした検収段階での納品物と仕様の間の不具合を避けるには、つぎのような対応策が有効です。
解決策1
事前に要求仕様に基づき検収要件を洗い出し、チェック項目を明確にします。
さらにチェック項目は発注者側とともにレビューし確認します。
さらにチェック項目は発注者側とともにレビューし確認します。
解決策2
要求仕様からプロトタイプを作成し、事前にチェック項目を発注者とともに決めておきます。
解決策3
以上の作業は開発工程の早い段階から始め、その都度関係者と確認します。
こうしたことが手戻りや予定外の作業の発生を防ぐことになります。
こうしたことが手戻りや予定外の作業の発生を防ぐことになります。
解決策4
以上のプロジェクトでの取り組みに加えて、検収要件をチェックリスト化し、社内で共有する等の社内体制の整備を進めます。
解決策5
検収項目やテストレビューなどのセルフチェックについては、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会がまとめた「検収計画書(情報システム検収テンプレート)」が参考になります。
ヒントとなる取組事例
■ユークエスト株式会社の取組
要求仕様からプロトタイプを作成し、そこから試験仕様書における具体的な項目を確定させ、発注者にもレビューに参画してもらい、仕様と検収要件を一致させることで手戻り作業の発生を防ぎました。
■株式会社熊本計算センターの取組
プロジェクトマネージャが以前に関わったプロジェクトでの反省をもとに、検収要件をチェックリスト化して、社内の関連する部署で共有し、リーダーやメンバーの使い勝手がいいものにしました。