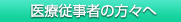最終更新:平成22年2月8日
厚生労働省
新型インフルエンザ対策推進本部
事務局
注意事項
1)このQ&Aは、国内産の新型インフルエンザワクチン(国内産ワクチン)と、特例承認された海外産の新型インフルエンザワクチン(輸入ワクチン)を扱っています。特に断りがない限り、両方に共通した内容となります。
2)輸入ワクチンの詳細については「2.輸入ワクチンについて」を参照してください。
3)いずれも、新型インフルエンザ予防接種事業に基づくものです。
〈このQ&Aで使っている表現〉
○国内産ワクチン:国内産の新型インフルエンザワクチン
○輸入ワクチン:平成22年1月20日付けで特例承認された海外産の新型インフルエンザワクチン
・GSK社製ワクチン:グラクソ・スミスクライン社製「アレパンリックス(H1N1)筋注」
・ノバルティス社製ワクチン:
ノバルティス ファーマ社製「乳濁細胞培養A型インフルエンザHAワクチンH1N1「ノバルティス」筋注用」
:新規に追加された問
:従来のQ&Aから更新された問
※ これから接種を受ける方々にご確認いただきたいこと
- (問)
- 今回の新型インフルエンザワクチン接種事業の目的は何ですか?
- (問)
- ワクチンはいつ、どこで接種できますか?
- (問)
- ワクチン接種の費用はいくらですか?
- (問)
- 優先接種対象ではない人は、いつから接種できるのですか?
- (問)
- 1歳未満の子どもは接種できないのですか?
- (問)
- インフルエンザワクチンで健康被害が発生した場合は、どのような対応がなされるのですか?
1.新型インフルエンザワクチンについての一般的な情報
- (問1)
- インフルエンザワクチンにはどのような効果が期待できますか?
- (問2)
- タミフルやリレンザといった抗インフルエンザウイルス薬と新型インフルエンザワクチンはどう違うのですか?
- (問3)
- 季節性インフルエンザワクチンは新型インフルエンザにも効果がありますか?
- (問4)
- 新型インフルエンザにかかった人でも、新型インフルエンザワクチンの接種が必要ですか?
- (問5)
- ワクチンの効果はどのくらい持続しますか?
- (問6)
- 流行のピークが過ぎたあとに、ワクチンを打つ意味はありますか?
- (問7)
- 新型インフルエンザワクチンの接種によって引き起こされる症状(副反応)にはどのようなものがありますか?
- (問8)
- インフルエンザワクチンにはチメロサールという添加剤が含まれているとのことですが、安全ですか? チメロサールが入っていないものはないのですか?
- (問9)
- 新型インフルエンザワクチンの接種を受けることが適当でない人や接種時に注意が必要な人はどういった方ですか?
- (問10)
- 新型インフルエンザワクチンを接種しても、おなかの子どもへの影響はないのですか?授乳中でも問題はありませんか?
- (問11)
- 新型インフルエンザワクチンと他のワクチンは同時に接種することができますか?
- (問12)
- 他のワクチンを最近接種しました。新型インフルエンザワクチンを接種するには、間隔はあけないといけないのですか?
- (問13)
- 新型インフルエンザワクチンの接種は何回受ければよいのでしょうか?
- (問14)
- 1回目と2回目の接種の間はどのくらいあけたらいいのですか?
- (問15)
- 新型インフルエンザワクチンはどういう方法で接種するのですか?
2.輸入ワクチンについて
- (問1)
- 輸入ワクチンと国内産ワクチンは何が異なるのですか?
- (問2)
- 輸入ワクチンと国内産ワクチンでは、有効性に差があるのですか?
- (問3)
- 輸入ワクチンは安全ですか?
- (問4)
- 輸入ワクチンはどのような手続きを経て輸入ができるようになるのですか? また、輸入ワクチンの安全性はどのように確認されますか?
- (問5)
- 特例承認とは何ですか?
- (問6)
- アジュバントとはなんですか?なぜ入っているのですか?安全ですか?
- (問7)
- 妊婦には接種しない方がよいのはなぜですか?
- (問8)
- 輸入ワクチンの1つには、国内産ワクチンと異なり、原材料として動物の培養細胞を用いていると聞きました。細胞培養とはなんでしょうか? そのようにして作られたワクチンは安全でしょうか?
- (問9)
- 輸入ワクチンの1つには、海外のウシに由来する原材料が使われていると聞きました。BSEなど、安全性に問題はないのですか?
- (問10)
- スイスでは規制当局がノバルティス社製ワクチンを、自己免疫疾患の患者に用いるべきではないとの勧告を行った、と報道で聞きました。日本でも自己免疫疾患の患者に対してこのワクチンを使わないようにするのでしょうか?
3.新型インフルエンザ予防接種事業について
- (問1)
- 今回の新型インフルエンザワクチン接種事業の目的は何ですか?
- (問2)
- ワクチンはいつ、どこで接種できますか?
- (問3)
- ワクチン接種の費用はいくらですか?
- (問4)
- 今回の新型インフルエンザワクチンは日本国内でどれくらい確保できているのですか?
- (問5)
- 新型インフルエンザワクチンの優先接種対象者とはどのような人でしょうか?
- (問6)
- 優先接種対象者は新型インフルエンザワクチンを接種しなくてはいけないのですか?
- (問7)
- 優先接種対象ではない人は、いつから接種できるのですか?
- (問8)
- 1歳未満の子どもは接種できないのですか?
- (問9)
- インフルエンザワクチンで健康被害が発生した場合は、どのような対応がなされるのですか?
- (問10)
- 住民票と異なるところに長期滞在している場合に、現在地でのワクチン接種ができますか?
- (問11)
- 基礎疾患がありますが、かかりつけの主治医が受託医療機関ではありません。どうやって接種を受ければよいですか?
- (問12)
- 受託医療機関ではない医療機関の入院患者は接種できないのですか?
- (問13)
- 外国人でも接種できますか?
- 1.
- 新型インフルエンザワクチンについての一般的な情報
(問1)インフルエンザワクチンにはどのような効果が期待できますか?
インフルエンザにかかるとはどういうことなのか、そのプロセスにそって、ワクチンの効果を説明しましょう。
ただし、新型インフルエンザワクチンは今回はじめて製造されたものですから、その効果についてのデータは限られています。そこで、製法が同じであることから、新型インフルエンザワクチンの効果は、季節性インフルエンザワクチンの効果と同じであろうという前提のもとに、以下にご説明します。
まず、インフルエンザにかかる発端はインフルエンザウイルスが体の中に入ってくることですが、これをワクチンで防ぐことはできません。手洗いやうがいなどが重要になります。
次に、体内へ入ったウイルスは細胞に侵入して増殖します。この状態を感染といいますが、ワクチンがこの感染を抑える働きは保証されていません。
ウイルスが増殖すると、数日の潜伏期間を経て、発熱やのどの痛みなどのインフルエンザの症状が引き起こされます。この状態を発症といいます。ワクチンは、この発症を抑える効果については一定程度、認められています。
※感染しても、必ず発症するというわけではありません。感染しても症状なしに済んでしまう人もいます。
発症後、多くの方は1週間程度で回復しますが、なかには肺炎や脳症などの重い合併症が現れ、入院治療を必要とする方やお亡くなりになる方もおられます。インフルエンザの重症化とは、肺炎などの合併症があらわれることを指します。
もともと基礎疾患をお持ちの方や妊婦さんなどは健康な成人よりも重症化する可能性が高いと考えられています。ですから、今回の新型インフルエンザワクチンの接種は、これらの方に優先的に行うことで、重症化を効率的に防ぐのを目標としています。
以上のように、インフルエンザワクチンは、打てば絶対にかからない、というものではありませんが、たとえかかっても病気が重くなることを防いでくれるのです。
ただし、この効果も100%ではないことにご注意ください。
なお、季節性インフルエンザワクチンの有効性については、国立感染症研究所のQ&Aに詳しく記載されていますので参考にしてください。
参考:国立感染症研究所 感染症情報センターホームページ
「インフルエンザQ&A(2008年度版)」(4)ワクチン接種
http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/fluQA/QAdoc04.html
(問2)タミフルやリレンザといった抗インフルエンザウイルス薬と新型インフルエンザワクチンはどう違うのですか?
タミフルやリレンザなどの抗インフルエンザウイルス薬は、主に発熱などの症状が出たあと(発症後)に治療のために服用します。
一方、インフルエンザワクチンは、重症化を防止する目的で、インフルエンザにかかる前の健康な時に接種します。
注;抗インフルエンザウイルス薬は、予防的に投与される場合もあります。
(問3)季節性インフルエンザワクチンは新型インフルエンザにも効果がありますか?
今年使用されている季節性インフルエンザのワクチンは、今回の新型インフルエンザウイルスに対しては有効ではないと考えられています。
(問4)新型インフルエンザにかかった人でも、新型インフルエンザワクチンの接種が必要ですか?
インフルエンザに対する免疫は、ワクチン接種以外に、実際にインフルエンザにかかることによっても獲得されます。
したがって、新型インフルエンザに既にかかった方については、免疫がすでに獲得されているため、ワクチンの接種を受ける必要はないと考えられます。
<すでに免疫を獲得していると考えられる方>
- 専門の検査(PCR検査など)により新型インフルエンザに罹患したことが確定した方
- すでに感染したと考えられる方(2009年の夏以降、A型のインフルエンザと診断された方注))
注;厚生労働省が行っている調査によると、2009年夏から2010年1月28日現在までに、国民が感染しているインフルエンザの大部分は新型インフルエンザウイルスによるものです。
(問5)ワクチンの効果はどのくらい持続しますか?
季節性インフルエンザワクチンでは、これまでの研究から、ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した(小児の場合は2回接種した)2週後から5カ月程度と考えられており、国内産の新型インフルエンザワクチンでも同程度と考えられます。
※ 輸入ワクチンの効果がどれくらい持続するかについては、現在製造販売会社が試験を継続しています。
(問6)流行のピークが過ぎたあとに、ワクチンを打つ意味はありますか?
(平成22年2月5日現在)
新型インフルエンザの患者数は、全国的には減少傾向ですが、まだ全国で1週間に約35万注)人が新しく新型インフルエンザにかかっていると推計され、油断はできません。
また、過去のパンデミックインフルエンザの経験では、一度流行が終息した後にも再流行することがあり、今回の新型インフルエンザにおいても今後再流行が起こる可能性があります。そのため、新型インフルエンザワクチンを接種することにより、今後起こりうる再流行に備えることができます。
ただし、インフルエンザウイルスが変異することにより、今回の新型インフルエンザワクチンを接種しても期待する効果が得られなくなることがありえます。
注:定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外の全国の医療機関を1週間に受診した患者数の推計値
(問7)新型インフルエンザワクチンの接種によって引き起こされる症状(副反応)にはどのようなものがありますか?
ワクチンは免疫をつけるために接種します。この免疫の獲得は、わたしたちがもともと持っている免疫反応を利用するのですが、免疫がつく以外の反応が見られることもあり、これらを副反応といいます。
季節性インフルエンザワクチンの場合、比較的頻度が高い副反応としては、接種した部位(局所)の発赤(赤み)、腫脹(腫れ)、疼痛(痛み)などがあげられます。
また、全身性の反応としては、発熱、頭痛、悪寒(寒気)、倦怠感(だるさ)などが見られます。
まれではありますが、ワクチンに対するアレルギー反応(発疹、じんましん、発赤(赤み)、掻痒感(かゆみ))が見られることもあります。
接種した部分の発赤(赤み)、腫脹(腫れ)、疼痛(痛み)は、接種を受けられた方の10〜20%に起こりますが、通常2〜3日で消失します。全身性の反応は、接種を受けられた方の5〜10%に見られ、こちらも通常2〜3日で消失します。
その他に、非常に重い副反応注)の報告がまれにあります。ただし、重い副反応の原因がワクチン接種であるかどうかは、必ずしも明らかではありません。
今回の国内産の新型インフルエンザワクチンも、程度の問題はありますが、同様の副反応が予想されます。
実際の接種後に現れた副反応については、報告に基づいて順次公表しており、これまで(平成22年1月29日現在)のところ、季節性インフルエンザワクチンとほぼ同程度の副反応が報告されています。
注:非常に重い副反応;ギランバレー症候群、急性脳症、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、肝機能障害、喘息発作、紫斑など
※ 輸入ワクチンについては、疼痛などの局所反応が国内産に比べて高い傾向がみられます。詳しくは、「2.輸入ワクチンについて」問2 をご覧ください。
※ 副反応などについての公表情報はこちら
(問8)インフルエンザワクチンにはチメロサールという添加剤が含まれているとのことですが、安全ですか? チメロサールが入っていないものはないのですか?
新型インフルエンザワクチン(輸入ワクチンを含む)の複数回接種用のバイアル製剤(小瓶に注射液が充てんされている製剤)には、季節性インフルエンザ用の製剤と同様、チメロサールなどの保存剤が使用されています。
チメロサールは殺菌作用のある水銀化合物で、ワクチンには防腐剤として入れられます。
過去において、海外で、このチメロサールと発達障害との関連が指摘されました。しかし、最近の疫学研究では、その関連はないとされています。
ただし、予防的な対応が大切であるとして、各国ともワクチンから除去・減量の努力を行っています。
今回の新型インフルエンザワクチンでは、チメロサールの使われているものと使われていないものがあります。プレフィルドシリンジ製剤(あらかじめ注射器に注射液が充てんされている製剤)では使われていません。この製剤は主に産婦人科を対象として配分されていますから、こちらの製剤による接種をお望みの妊婦さんは、かかりつけ医に依頼してください。
参考1:平成21年9月18日「新型インフルエンザワクチンに関する意見交換会」 資料4
参考2:国立感染症研究所 感染症情報センターホームページ
「インフルエンザQ&A(2008年度版)」(4)ワクチン接種
http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/fluQA/QAdoc04.html
(問9)新型インフルエンザワクチンの接種を受けることが適当でない人や接種時に注意が必要な人はどういった方ですか?
【予防接種を受けることが不適当と考えられる方】
基本的に季節性インフルエンザワクチンと同様、以下のように考えられます。
(1) 明らかに発熱している方
(2) 非常に重い急性疾患にかかっている方
(3) 接種を行う新型インフルエンザワクチンの成分によってアナフィラキシー注)を起こしたことがある方
(4) 上記に掲げる方のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
注:アナフィラキシーとは、医薬品などによって引き起こされることのある急性の過敏反応です。詳細は、以下をご参照ください。
(独)医薬品医療機器総合機構「重篤副作用疾患別対応マニュアル」
http://www.info.pmda.go.jp/juutoku_ippan/juutoku_ippan.html
○「アナフィラキシー」
http://www.info.pmda.go.jp/juutoku_ippan/file/jfm0803003_ippan.pdf
【接種の判断を行うに際し、注意を要する方】
次のいずれかに該当する場合は、健康状態や体質などから接種の適否などを慎重に判断した上で、注意して接種します。
(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害、呼吸器疾患(気管支喘息など)などの基礎疾患を有する方
(2) 以前の予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方および全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方
(3) 過去にけいれんの既往のある方
(4) 過去に免疫不全の診断がなされている方および近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
(5) 接種を行う新型インフルエンザワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方
(6) 鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対してアレルギーを起こすおそれのある方
※輸入ワクチンは、上記の方々に加え、以下の方々にも注意が必要です。
・妊婦の方と妊娠している可能性のある方・・・国内産を接種することが望ましいです
(詳細は「2.輸入ワクチンについて」問7 )
・子ども、基礎疾患のある方・・・
子どもや基礎疾患のある方全員が接種できる量の国内産ワクチンを用意していますが、輸入ワクチンの接種をお考えの場合は、医師とよく相談し、国内産ワクチンとの比較を含め、輸入ワクチンの有益性と危険性を十分に評価した上で、慎重に判断してください。
参考1:A型インフルエンザHAワクチン(H1N1株)添付文書
参考2:厚生労働省ホームページ 「インフルエンザQ&A」Q.12
参考3:国立感染症研究所 感染症情報センターホームページ
「インフルエンザQ&A(2008年度版)」(4)ワクチン接種
http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/fluQA/QAdoc04.html
(問10)新型インフルエンザワクチンを接種しても、おなかの子どもへの影響はないのですか?授乳中でも問題はありませんか?
※国内産ワクチンと輸入ワクチンで異なります。
【国内産ワクチンについて】
現在までのところ、妊娠中にインフルエンザワクチンの接種を受けたことにより流産や先天異常の発生頻度が高くなったという報告はありません。
なお、新型インフルエンザワクチンの複数回接種用のバイアル製剤(小瓶に注射液が充てんされている製剤)には季節性インフルエンザ用の製剤と同様にチメロサール等の保存剤が使用されています。今回の新型インフルエンザワクチンでは、プレフィルドシリンジ製剤(あらかじめ注射器に注射液が充てんされている製剤)には保存剤の添加は行われておらず、保存剤の添加されていないワクチン接種を希望する妊婦さんは、プレフィルドシリンジ製剤が使用できることとしています。(チメロサールの詳細は「1.新型インフルエンザワクチンの一般的な情報」問8をご参照ください)
また、授乳期間中でも、インフルエンザワクチンを接種して支障はありません。
インフルエンザワクチンには、病原性をなくしたウイルスの成分を用いており、接種後にウイルスが体内で増えることはありません。ですから、母乳を介してお子さんに影響を与えることはありません。
【輸入ワクチンについて】
輸入ワクチンは、妊娠されている方や授乳中の方には、接種しないことが望ましいとされています。(詳細は「2.輸入ワクチンについて」問7 をご参照ください)
参考1:国立成育医療センターホームページ 「妊娠と薬情報センター」
インフルエンザ薬に関する最新情報
http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html
参考2:国立感染症研究所 感染症情報センターホームページ
「インフルエンザQ&A(2008年度版)」(4)ワクチン接種
http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/fluQA/QAdoc04.html
参考3:日本産科婦人科学会ホームページ
「妊娠している婦人もしくは授乳中の婦人に対しての?新型インフルエンザ(H1N1)感染に対する対応Q&A」(ホームページは随時更新されますので、最新の情報をご確認ください。)
一般向けhttp://www.jsog.or.jp/news/html/announce_20091109a.html
医療関係者向けhttp://www.jsog.or.jp/news/html/announce_20091109b.html
(問11)新型インフルエンザワクチンと他のワクチンは同時に接種することができますか?
※国内産ワクチンと輸入ワクチンで異なります。
【国内産ワクチンについて】
国内産の新型インフルエンザワクチンについては、医師が必要と認めた場合、他のワクチンと同時接種することも可能です。
ただし、ワクチンによっては、接種が適当な方と不適当な方などが異なります。ですから、同時に接種を希望されるワクチンがある場合は、医師にご相談ください。
【輸入ワクチンについて】
今回の輸入ワクチン注1にはアジュバント(免疫補助剤)が入っていることから、他のワクチンの同時接種については、控えることが望ましいとされています注2。
注1;アジュバントについては、「2.輸入ワクチンについて」問6 を参照してください。
注2:海外等の情報を踏まえた検討が必要であり、当面差し控えることが望ましいと考えられます。(薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会[平成21年12月26日]および薬事・食品衛生審議会 薬事分科会[平成22年1月15日])
参考:A型インフルエンザHAワクチン(H1N1株)添付文書
(問12)他のワクチンを最近接種しました。新型インフルエンザワクチンを接種するには、間隔はあけないといけないのですか?
新型インフルエンザワクチンを接種する際には、他のワクチンとの接種間隔として、
○生ワクチン※1)の接種を受けた方は、通常、27日以上
○不活化ワクチン※2)の接種を受けた方は、通常、6日以上
をおいてから接種することとされています。
参考:A型インフルエンザHAワクチン(H1N1株)添付文書
※1:生ワクチン;BCG, ポリオ, 麻しん風しん混合(MR), 麻しん(はしか), 風しん など
※2:不活化ワクチン;DPT/DT, 日本脳炎, インフルエンザ, B型肝炎, 肺炎球菌 など
※1、※2;国立感染症研究所 感染症情報センターホームページ
http://idsc.nih.go.jp/vaccine/atopics/atpcs003.html
(問13)新型インフルエンザワクチンの接種は何回受ければよいのでしょうか?
新型インフルエンザワクチンは1回もしくは2回接種する必要があります。年齢やワクチンの種類により接種回数が異なります。
2回接種の場合、2回目には1回目に接種したワクチンと同じ種類のワクチンを接種してください。
○ 1回目:国内産ワクチン→ 2回目:国内産ワクチン (異なる会社のワクチンでも構いません)
○ 1回目:ノバルティス社製ワクチン → 2回目:ノバルティス社製ワクチン
接種回数・接種量は1回目接種時の年齢で判断して差し支えありません。
例)1回目接種時に12歳で2回目接種時に13歳である場合、12歳として考えていただいて差し支えありません。
| 国内産ワクチン | 輸入ワクチン | ||
|---|---|---|---|
| GSK社製ワクチン | ノバルティス社製ワクチン | ||
| 2回接種 | 13歳未満 | 対象者なし | (3歳以上18歳未満)注2) 50歳以上 |
| 1回接種 | 上記以外注1) | (6か月以上)注2) | 18〜49歳 |
注1:国内産ワクチンは、基礎疾患を有する方であって、著しく免疫が抑制されていると考えられる方に接種する場合は医師とよく相談のうえ、2回接種としても差し支えありません。
注2:小児への接種に当たっては、国内産ワクチンと比較して、その有益性と危険性について医師と十分相談をしていただき、慎重に判断してください。
なお、国内産ワクチンの接種回数については、国内での臨床試験結果等を踏まえて見直しを行い、上の表のお示しした結果になっております。
(問14)1回目と2回目の接種の間はどのくらいあけたらいいのですか?
※国内産ワクチンと輸入ワクチンでは異なります。
【国内産ワクチン】
国内産の新型インフルエンザワクチンは、2回接種を行う場合は、1〜4週間の間隔をあけて2回目を接種することとされていますが、免疫効果を考慮すると4週間あけることが望ましいとされています。
【輸入ワクチン】
輸入の新型インフルエンザワクチン(ノバルティス社製ワクチン)は、2回接種を行う場合は、少なくとも3週間の間隔をあけて2回目を接種することとされています。
参考:A型インフルエンザHAワクチン(H1N1株) 添付文書
(問15)新型インフルエンザワクチンはどういう方法で接種するのですか?
新型インフルエンザ予防接種事業における新型インフルエンザワクチンは、国内産ワクチンも輸入ワクチンも「注射」により接種します。
スプレー式のワクチン(経鼻ワクチン)はありません。
注:日本で承認されていないワクチンを接種した場合は、健康被害救済の対象になりませんので、ご留意ください。
【製品名と製薬企業名】
●「A型インフルエンザHAワクチンH1N1「□□」」 ※□□には以下の「」内の名称(4種類)が入ります。
「化血研」(財)化学及血清療法研究所、「北研」(学)北里研究所、「ビケン」(財)阪大微生物病研究会、「生研」デンカ生研(株)
●「アレパンリックス(H1N1)筋注」 グラクソ・スミスクライン株式会社(以下、GSK社)
●「乳濁細胞培養A型インフルエンザHAワクチンH1N1「ノバルティス」筋注用」 ノバルティス ファーマ株式会社(以下、ノバルティス社)
| 国内産ワクチン | 輸入ワクチン | |||||||
| 製品名 | A型インフルエンザHAワクチンH1N1 | アレパンリックス(H1N1)筋注 | 乳濁細胞培養 A型インフルエンザHAワクチンH1N1「ノバルティス」筋注用 |
|||||
| 「化血研」 | 「北研」 | 「ビケン」 | 「生研」 | |||||
| 製造方法 | 鶏卵培養 | 鶏卵培養 | 細胞培養 | |||||
| 性状 | 透明〜わずかに白濁 | 乳濁製剤 (調製後※3) |
乳濁製剤 | |||||
| 投与方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 | 筋肉内注射 | |||||
| 用法・用量 | 1歳未満 0.1mL 2回 1-6歳未満 0.2mL 2回 6-13歳未満 0.3mL 2回 13歳以上 0.5mL 1回 |
6ヵ月‐9歳 0.25mL 1回 10歳以上 0.5 mL 1回 |
3‐17歳 0.25mL 2回 18‐49歳 0.25mL 1回 50歳以上 0.25mL 2回 |
|||||
| 製剤の種類※1 | バイアル | バイアル | シリンジ | バイアル | バイアル | バイアル | バイアル | |
| 保 存 剤 ※2 |
チメロサール | なし | あり | なし | あり | あり | あり | あり |
| フェノキシエタノール | あり | なし | なし | なし | なし | なし | ||
※1 バイアル製剤:小びんに注射液が充てんされている製剤。
シリンジ製剤:あらかじめ注射器に注射液が充てんされている製剤。
※2 複数回接種用バイアルの開封後の細菌汚染防止のために用いられる防腐剤のこと。季節性インフルエンザワクチンなどでも使用されています。
チメロサール;エチル水銀に由来する防腐剤であり、海外で過去に発達障害との関連性が指摘されましたが、最近の疫学研究ではその関連はないとされています。
フェノキシエタノール;妊娠動物等での催奇形性試験の結果には問題ありませんが、妊婦への使用実績は確認されていません。
※3 接種直前に、抗原製剤を添付のアジュバント(免疫補助剤)を含む専用混和液と混合して調整します。
- 2.
- 輸入ワクチンについて
(問1)輸入ワクチンと国内産ワクチンは何が異なるのですか?
海外で製造されたワクチンについては、以下の点などで国内産ワクチンとは異なっています。
(1) 国内での使用経験・実績(臨床試験を除く)がなかったこと
(2) 国内では使用経験のないアジュバント注1)(免疫補助剤)が使用されていること
(3) 国内では使用経験のない細胞を用いた細胞培養注2)による製造法(細胞培養)が用いられているものがあること(ノバルティス社製ワクチン)
(4) 投与経路が筋肉内(国内産は皮下)であること
(5) 製品によって、用法・用量が異なること
(6) 妊婦には接種しないことが望ましいこと
(7) 他のワクチンとは同時に接種しないことが望ましいこと
注1:アジュバントについては、「2.輸入ワクチンについて」問6 をご参照ください。
注2:細胞培養については、「2.輸入ワクチンについて」問8 をご参照ください。
(問2)輸入ワクチンと国内産ワクチンでは、有効性に差があるのですか?
輸入、国内産それぞれの場合で、年齢によって、1回接種で良い場合と2回接種が必要な場合がありますが、規定された用法・用量で接種すれば、国際的に用いられている有効性の基準注)を満たす結果が得られています。
注:ヨーロッパ規制当局の医薬品委員会が示したパンデミックインフルエンザの基準
(問3)輸入ワクチンは安全ですか?
国内で使用できる輸入の新型インフルエンザワクチンには2つの製品があります。
まず前提として、輸入ワクチンにも国内産ワクチンにもある頻度で副反応注)が現れることをご理解ください。
(1) GSK社製ワクチンについては、副反応(出現頻度)として、注射部位の疼痛(痛み)(98%)などが報告された他、全身倦怠感(だるさ)(46%)、頭痛(35%)などが報告されており、別々の臨床試験なので厳密な比較はできませんが、国内産の新型インフルエンザワクチンと比べて副反応の出現頻度が高い傾向がみられました。
一方、注射部位の発赤(7%)の出現頻度は、国内産ワクチンより頻度が低くなっています。
(2) ノバルティス社製ワクチンについては、国内臨床試験で副反応(出現頻度)として、注射部位の疼痛(68%)が報告され、別々の臨床試験なので厳密な比較はできませんが、国内産の新型インフルエンザワクチンと比べて副反応の出現頻度が高い傾向がみられました。一方、頭痛(14%)は国内産ワクチンと同程度、全身倦怠感(3%)は国内産ワクチンより出現頻度が低い傾向が見られました。
なお、現時点で確認できた範囲では、国内や海外での臨床試験の結果や海外での使用実績において、特に問題とするべき副反応の発生は確認されていません。ただし、極めてまれではありますが、重篤な副反応も起こりえます。
注:「副反応」とは、ワクチン接種において、その目的である免疫をつけることに伴って発生する、免疫反応以外の反応のことをいいます。通常の医薬品で言う「副作用」と同様の意味です。詳しくは、「1.新型インフルエンザワクチンについての一般的な情報」問7 をご参照ください。
| GSK社製ワクチン※3) | ノバルティス社製ワクチン | 国産H1N1ワクチン | ||
| 抗原量 アジュパント 対象年齢 投与方法 |
3.75ug 有(AS03) 20〜64歳 筋注、N=100 |
3.75ug 有(MF59) 20〜60歳 筋注、N=98 |
15ug 無 20〜59歳 皮下注、N=100 |
|
| 主 な 副 反 応 ※1) |
注射部位の疼痛 | 98% | 68% | 36% |
| 注射部位の発赤 | 7% | 17%(紅斑) | 38% | |
| 注射部位の腫脹 | 17% | 3% | 18% | |
| 全身倦怠感 | 46% | 3% | 20% | |
| 頭痛 | 35% | 14% | 12% | |
| 間接痛 | 14% | 2% | - | |
| 筋肉痛 | 44% | 2% | - | |
| 重篤な副反応※2) | 重篤な副反応なし | 重篤な副反応なし | 2件 (注意すべき副反応) |
|
出典1:薬事・食品衛生審議会薬事分科会(平成22年1月15日)資料
出典2:平成21年11月11日新型インフルエンザワクチンに関する有識者との意見交換会 資料1より抜粋
注)臨床試験は、いずれも別の試験であるため、厳密な比較はできない。
※1)主な副反応は、3製剤それぞれの国内で行われた計3つの臨床試験において、10%以上発言し、かつ2つ以上の試験で報告された事象を抜粋。
※2)1回目接種後21日までの結果。
※3)臨床試験において、強い疼痛、倦怠感などが報告されている。
(問4)輸入ワクチンはどのような手続きを経て輸入ができるようになるのですか? また、輸入ワクチンの安全性はどのように確認されますか?
輸入ワクチンの輸入には、前提として、わが国の薬事法に基づく輸入の承認を得る必要があります。ただし、通常の手続きに従って、承認を得るとなると、今回の新型インフルエンザワクチンに関しては、今シーズン中の輸入が間に合わなくなります。
そこで、優先接種対象者のみならず、健康な成人を含めて接種を必要とする方々に接種を行うためには、国内産ワクチンだけでは不足することから、特例的に、通常の承認の要件を緩和し、緊急に承認を与える「特例承認」を適用しました。
特例承認の規定を適用しましたが、安全性等については、国内外の臨床試験の結果などに基づいて確認を行いました。また、特例承認後も、国内外の安全性情報等の速やかな収集を行います。
(問5)特例承認とは何ですか?
海外で承認された医薬品(今回の場合はワクチン)について、
(1) わが国で疾病のまん延その他の健康被害の拡大防止のため緊急に輸入する必要があり、この医薬品の使用以外に適当な方法がない場合、
(2) わが国と同等の水準の承認制度のある国で販売などが認められている医薬品であることを前提として、
通常の承認の手続き・要件を一部満たさなくても、承認を与えることができる制度のことです。 特例承認であっても、安全性、有効性などの確認をおろそかにするわけではありません。特例承認時までに確認できる国内外の安全性、有効性などのデータを踏まえ、薬事・食品衛生審議会での審議を経て、特例承認を与えるかどうか厚生労働大臣が決定するものです。
(問6)アジュバントとはなんですか? 安全ですか?
アジュバントとは、ワクチンと混合して投与することにより、目的とする免疫反応を増強する物質(免疫補助剤)です。
ワクチンの成分の中で抗原(免疫反応を引き起こさせる物質のこと。インフルエンザワクチンの場合、ウイルスの成分の一部から作られる。)のみを接種するよりも、アジュバントを加えたほうが免疫反応が強くなることから、少ない量の抗原で製剤を作ることが出来ます。
安全性については、今回特例承認された輸入ワクチンは、抗原が同じであってアジュバントを含まない製剤(国内産の新型インフルエンザワクチンなど)よりも、注射部位の疼痛(痛み)などの副反応注)が発生する頻度が高いことが指摘されています。ただし、今回特例承認された輸入ワクチンで使われているアジュバントについては、海外でいずれも、数千万回の接種実績があるものです。
なお、今回の輸入ワクチンで使用されているアジュバントは、スクワレンといった油性の物質が用いられており、界面活性剤であるポリソルベート80により乳化されるオイルアジュバントの一種と分類されています。
アジュバントの入ったワクチンは国内でも承認されていますが、アルミニウムに由来する種類であり、今回の様なオイルのアジュバントは国内で初めてです。
注:「副反応」とは、ワクチン接種において、その目的である免疫をつけることに伴って発生する、免疫反応以外の反応のことをいいます。通常の医薬品で言う「副作用」と同様の意味です。詳しくは、「1.新型インフルエンザワクチンについての一般的な情報」問7 をご参照ください。
(問7)輸入ワクチンを妊婦には接種しない方がよいのはなぜですか?
輸入ワクチンについては、妊婦の方や授乳している方に対しての使用経験が限られており、臨床試験データが乏しいことなどから、今回の特例承認に際しては、接種しない方が望ましいこととなりました。
なおWHO(世界保健機関)は、「非臨床試験では生ワクチンやアジュバント無添加、添加ワクチンが受胎能、妊娠、胚や胎児の発生、出産、出産後の発育に影響するとの証拠はない。妊婦へのインフルエンザ罹患が重症化するリスクを考慮すれば、規制当局により禁忌とされていなければ、アジュバント無添加/添加又は生ワクチンに関わらず接種することができる」としています。
(問8)輸入ワクチンの1つには、国内産ワクチンと異なり、原材料として動物の培養細胞を用いていると聞きました。細胞培養とはなんでしょうか? そのようにして作られたワクチンは安全でしょうか?
細胞培養とは、ワクチンの製造方法の一種で、今回特例承認された輸入ワクチンのうち、ノバルティス社製ワクチンに使われています。
細胞培養は、鶏卵による培養よりも、生産効率は高いとされます。
ノバルティス社製ワクチンについては、その製造過程において、他のインフルエンザワクチンが発育鶏卵を用いるのとは異なり、細胞培養の手法を用いてワクチンを生産しています。この細胞(MDCK細胞と呼ばれる細胞)を用いた製剤については、国内では初めての承認となります。この細胞については、動物の体内で、投与された細胞自身が増殖する性質がありますが、細胞は製造工程で徹底して除去されており、生体には影響がないとされています。加えて、細胞培養のインフルエンザワクチンと鶏卵培養のインフルエンザワクチンの間で、副反応の発現頻度等に大きな違いがないことから、ノバルティス社製ワクチンの製造方法に関する安全性については、承認の可否に関わる問題はないとされました。なお、この細胞を用いたワクチンは、ヨーロッパでも販売が認められています。
(問9)海外ワクチンの1つには、海外のウシに由来する原材料が使われていると聞きました。狂牛病(BSE)など、安全性に問題はないのですか?
GSK社製ワクチンについては、その製造過程で、わが国の基準で使用が認められていない原産国のウシの胆汁から作られた物質を用いています。そのため、理論上完全には伝達性海綿状脳症注(TSE。BSEもこの一種です)のリスクを排除することはできませんが、ヨーロッパの基準に準拠しており、また厳しい製造条件で製造していることにより、そのリスクは極めて低いと考えられます。
注:脳の組織にスポンジ(海綿)状の変化を引き起こす神経系の病気です。この一種としてウシ海綿状脳症(BSE)があり、BSEに感染したウシ由来の食べ物などを食べることで、ヒトにおいても神経症状を引き起こすことが疑われています。
(問10)スイスでは規制当局がノバルティス社製ワクチンを、自己免疫疾患の患者に用いるべきではないとの勧告を行った、と報道で聞きました。日本でも自己免疫疾患の患者に対してこのワクチンを使わないようにするのでしょうか?
スイス規制当局からの要請により、輸入ワクチンの製造会社であるGSK社とノバルティス社は、急性で重篤な自己免疫性疾患への接種は推奨されないと添付文書を改訂しています。その一方で、EMEA(欧州医薬品庁)を含むスイス以外の国やGSK社のワクチンが使用されているカナダの規制当局は、同様の添付文書の改訂は求めていません。
また、各社とも本剤が自己免疫疾患を悪化させたことを示唆する報告はないため、スイス以外の国で添付文書の改訂を行う必要はないと判断しているとのことです。
なお、ヨーロッパで、輸入ワクチンの投与後に、膠原病などの自己免疫疾患の症状が悪化したとの報告はありますが、因果関係は不明とされています。
これらのことを踏まえて、自己免疫疾患をお持ちの方々が、輸入ワクチンを接種する際には、よく医師と相談した上で、接種の必要性をご判断ください。なお、我が国では、自己免疫性疾患に限らず、重篤な急性疾患である場合には接種不適当とされております。
今後、国内外で関係する新たな安全性情報が得られれば、適切に公開して参ります。
参考:スイスのノバルティス社製ワクチン及びGSK社製ワクチンの添付文書の該当部分の抄訳 「本剤に対する明らかな自己免疫疾患の患者を含んだ臨床試験は存在しない。また、抗原及び/又はアジュバントが自己免疫疾患の悪化をもたらす可能性を否定できないため、急性で重篤な自己免疫疾患の患者に対する本剤の接種は、推奨されない。」
- 3.
- 新型インフルエンザ予防接種事業について
(問1)今回の新型インフルエンザワクチン接種事業の目的は何ですか?
今回の新型インフルエンザウイルスは、感染力は強いのですが、多くの感染者はかかっても軽症のまま回復しています。また、タミフル等の治療薬も有効です。
ただし、国民の大多数に免疫がなく、感染が拡大する可能性があることや、糖尿病やぜん息などの基礎疾患がある方や妊婦さんなどが重症化する可能性が高いことが懸念されていました。また、健康な成人の方の中でも重症化する方や死亡される例は見られています。
今回の新型インフルエンザワクチンの接種は、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこととともに、こうした患者さんが集中発生して医療機関が混乱することを防ぐことを目的としています。
(問2)ワクチンはいつ、どこで接種できますか?
新型インフルエンザワクチンは、それぞれの接種対象者ごとに各都道府県が設定した時期から接種を受けることができます。平成22年2月上旬には全ての都道府県で、すべての方が接種可能となりました。
接種を受けることができる医療機関については、市町村のホームページや広報資料などをご覧下さい。
(問3)ワクチン接種の費用はいくらですか?
今回の新型インフルエンザワクチンの接種費用については、接種を受ける方に実費をご負担いただくこととしております。1回目の接種は3600円、2回目の接種は2550円(ただし、2回目の接種を異なる医療機関で受けた場合は、基本的な健康状態等の確認が再度必要となるため、3600円)です。輸入ワクチンも国内産ワクチンも、1回あたりの接種費用は同じです。
ただし、所得の少ない世帯の方などについては、費用負担の減免措置注)が市町村によって行われます。
注:市町村民税非課税世帯の方のご負担を軽減できる財源(1歳〜13歳未満の方は6,150円、その他の年齢の方は3,600円(基礎疾患を有する方のうちの一部の方は6,150円)に相当する額)が確保されていますが、具体的な費用負担額軽減措置の内容については、各市町村で異なっていますので、お住まいの市町村におたずねください。
(問4)今回の新型インフルエンザワクチンは日本国内でどれくらい確保できているのですか?
今回の新型インフルエンザワクチンについては、国内産ワクチンは、平成21年10月19日の週から順次、接種を開始しており、平成21年度内に5,400万回分注)確保できる予定です。
また、海外企業から9,900万回分注) 程度を確保できる見込みです。
注)回数は成人量換算
(問5)新型インフルエンザワクチンの優先接種対象者とはどのような人でしょうか?
今回の新型インフルエンザに関しては、多くの方は軽症のまま回復している一方、基礎疾患を有する方等において重症化する可能性が高いという特徴があります。
また、今回の新型インフルエンザの予防接種については、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことやそのために必要な医療を確保することを、その目的としています。
そこで、死亡や重症化のリスクが高い方を優先すること、またその方々の治療に従事する医療従事者を優先すること、この2つを優先接種対象を決める際の基本的な方針としています。
(優先接種の対象者)
(1) インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員を含む)
(2) 妊婦および基礎疾患を有する方
(3) 1歳から小学校3年生に相当する年齢の方
(4) 1歳未満の方の保護者、優先接種者のうち、予防接種が受けられない方の保護者等
(その他の対象者)
○小学校4年生から6年生、中学生、高校生に相当する年齢の方
○65歳以上の方
※現在は、上記以外の方々についても接種対象者としています。
(問6)優先接種対象者は新型インフルエンザワクチンを接種しなくてはいけないのですか?
今回の新型インフルエンザワクチン接種については、あくまでも個人の意思が尊重されます。 優先接種対象者についても、接種義務が生じるものではありません。該当する方のうち、希望者は接種ができます、というものです。
(問7)優先接種対象ではない人はいつから接種できるのですか?
2月上旬には全ての都道府県で、すべての方が接種可能となりました。
なお、新型インフルエンザワクチンの接種スケジュールについては、各都道府県が、接種状況などを踏まえて設定することとしています。各都道府県で開始時期等に差異が生じる場合もありますが、都道府県ごとに感染状況や接種状況は異なるため、全国一律にはならないことにご理解ください。
(問8)1歳未満の子どもは接種できないのですか?
国内産ワクチンについては、1歳未満のお子様は、予防接種によって免疫をつけることが難しいため、お子様本人は優先的に接種する対象者(優先接種対象者等)に含めず、その保護者を優先的に接種することとしています。
今回の新型インフルエンザワクチンの接種を受けるか否かについては、個人の意思が尊重されるものですが、1歳未満のお子様本人への接種は、免疫をつけることが難しいため推奨されません。ただし、優先接種対象者等以外の方々への接種が開始されるに当たって、保護者の方が、有益性とリスクを十分に考慮した上で、強く希望する場合は、接種を行うことを妨げるものではありません。
なお、所得の少ない世帯の方などについては、費用負担の軽減措置が市町村によって行われます。
具体的な費用負担軽減措置の内容については、各市町村により異なりますので、お住まいの市町村におたずねください。
※ 輸入ワクチンについては、1歳未満の方に限らず子どもへの接種を保護者の方が希望される場合には、その有益性と危険性、国内産ワクチンとの違いについて医師と十分相談をしていただき、慎重に判断していただくこととしています。
(問9)インフルエンザワクチンで健康被害が発生した場合は、どのような対応がなされるのですか?
今回の新型インフルエンザのワクチン接種に伴い健康被害が発生した場合の救済措置について、平成21年12月4日から新しい制度が実施されました。詳細については、ホームページをご覧ください。
※新型インフルエンザの予防接種による健康被害救済制度についてはこちら
(問10)住民票と異なるところに長期滞在している場合に、現在地でのワクチン接種ができますか?
今回の新型インフルエンザワクチンは、国と契約した受託医療機関で接種してもらいます。住民票と異なる地域であっても、この受託医療機関であれば、国内どこででも接種を受けられます。
ただし、低所得者等に対する接種費用の負担軽減措置については、住民票のある市町村と相談する必要があります。
(問11)基礎疾患がありますが、かかりつけの主治医が受託医療機関ではありません。どうやって接種を受ければよいですか?
新型インフルエンザワクチンは国と契約をした受託医療機関でなければ接種できません。したがって、かかりつけの医療機関と相談し、受託医療機関を紹介してもらう必要があります。
また、市町村がホームページ等で公表する受託医療機関リストを参照することも可能です。
なお、基礎疾患をお持ちの方が、かかりつけの医療機関以外の受託医療機関で接種する場合は、かかりつけの医療機関から「優先接種対象者証明書」の交付を受け、受託医療機関に提出、または提示して下さい。
(問12)受託医療機関ではない医療機関の入院患者は接種できないのですか?
受託医療機関ではない医療機関は、国の事業としてワクチンを接種できないので、これらの医療機関の入院患者の方で、接種を受けられたいときは、優先接種対象者証明書に基づき他の受託医療機関の医師から接種を受けることとなります。
(問13)外国人でも接種できますか?
外国籍の方についても、日本に在住されている方であれば、接種スケジュールに従って接種を受けることが可能です。
詳細はお住まいの自治体の広報誌等でご確認ください。
以上