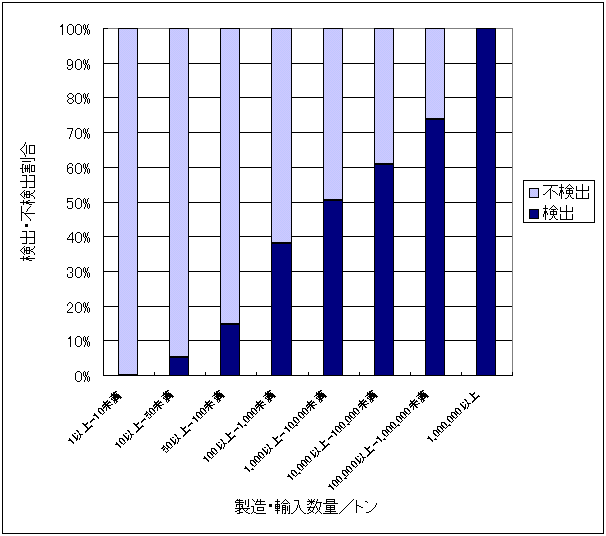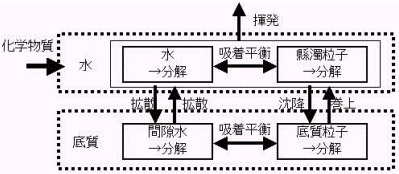
�S�|�S�D�\�I�\�����l���������O�R�����x�̌������ɂ���
(1) ���ĉ��̎��O�R�����x�ɂ������ȓK�p���O�E�y���[�u
�@���Ẳ��w�����R�����x�ɂ����ẮA���̋K���̓K�p������̂����O������ŁA���X�N�]���̊ϓ_�ɗ��r���A�\�I�\�����l�����Đ����E�A�����ʂ̏��Ȃ����w�����A���ԕ��Ƃ��đ��̉��w�����ɕϊ��������́A�A�o��p�i���ɂ��āA�͏o�Ώۂ��珜�O������A�͏o�����̌y����}�铙�̑[�u���u�����Ă���B
| ���{ | �č� | �d�t | |||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
���A�o��p�i
|
|
|
|||||
�������q������
|
|
|
(2) �䂪���̎��O�R�����x��L����@�߂ɂ����钆�ԕ��y�їA�o��p�i���̎戵���i�ڍׂ��ʎ��Q�Ɓj
| �@ | ���w�����R���K���@ | �J�����S�q���@ | �_�����@ | �@ |
| ���ԕ� �@�i���P�j |
�����O�R���̑Ώۂ��珜�O �ȉ��̏ꍇ�Ɏ��O�R���̑Ώۂ��珜�O�����B
|
���L�Q�������̑Ώۂ��珜�O ���O�ɐ\���o�āA�J���҂��V�K���w�����ɂ��炳��Ȃ��|�̊m�F���邱�Ƃɂ��Ώۂ��珜�O�����B ��̓I�ɂ́A���̏��������ꍇ�Ɋm�F���Ȃ����B
|
�@ | �@ |
| ��\�I | ���s�̉��w�����R���K���@�ł́A���O�R���̑ΏۊO�Ƃ͂���Ă��Ȃ��B | �@ | �@ | |
| �A�o��p�i | ���s�̉��w�����R���K���@�ł́A���O�R���̑ΏۊO�Ƃ͂���Ă��Ȃ��B | �@ |
���@�߂̓K�p���O �A�o��p�i�ł���ꍇ�A�_�����@�͓K�p����Ȃ��B�i���Q�j |
�������E�A���̔��Ƃ̋��v�����̌y�� ���O�ɓ͂��o�āA�͏o���̋L�ړ��e�ɏ]���Đ����E�A�����s���ꍇ�ɓK�p�����B �i�͏o���̎�ȋL�ڎ����j
|
| �i���P�j | ���ԕ��ł��邱�Ƃɂ��āA���O�m�F���邱�Ƃɂ���ċ��̑Ώۂ��珜�O���Ă����Ƃ��ẮA�I�]���w�j���̐������ʂ̊Ǘ����s���I�]���w�ی�@������B |
| �i���Q�j | �_�����@�̘g�g�݂Ƃ͕ʂɁA�e�`�n�i���A�H�Ɣ_�Ƌ@�ցj�̃K�C�h���C���Ɋ�Â��A�A�o�����_��̈��S����A�o�����O�Ɋm�F���Ă���B |
�i�ʎ��j
| �P�j���s�̉��w�����R���K���@�ɂ�������i���ԕ��Ɋւ���m�F���x�̊T�v |
�@���s�̉��w�����R���K���@�ɂ����ẮA���i���ԕ��̐����E�A���ɂ��ẮA���O�R�����s�v�Ƃ���Ă���B
�@���i���ԕ��Ƃ��Ďg�p����V�K���w�����̐����E�A�����Ǝ҂́A���炩���߁A�u���i���ԕ��Ƃ��Ă̐V�K���w���������i�A���j�v�揑�v�A�y�ѕʓY�Ƃ��āu�m�F���v���o����K�v������B
|
(1)�v�揑 �@��ȋL�ڎ����͎��̂Ƃ���B
(2)�m�F�� �@�m�F���ɂ́A���i�����Ǝ҂��A���Y�V�K���w���������Ǝ҂���w�����铖�Y�V�K���w�����̑S�ʂ����i�̐����Ɏg�p����|�m�F�������Ƃ��L�ڂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B |
| �Q�j�I�]���w�ی�@�ɂ����钆�ԕ��̎��O�m�F���x�̊T�v |
�@�I�]���w�ی�@�i���蕨���̋K�����ɂ��I�]���w�̕ی�Ɋւ���@���j�ɂ����ẮA�����Ƃ��Ďg�p���ꂽ���Ɩ��͎g�p����邱�Ƃ��m���ł���Ƃ��Čo�ώY�Ƒ�b�̊m�F���邱�Ƃɂ���āA���������Ə�����Ă���B
�@�m�F���悤�Ƃ��鎖�Ǝ҂́A�����m�F�\�����y�ь����g�p�̏ؖ������o���Ċm�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
(1)�����m�F�\���� �@��ȋL�ڎ����͎��̂Ƃ���B
(2)�����g�p�̏ؖ��� �@��ȋL�ڎ����͎��̂Ƃ���B
|
�@�s�����́A���Ɍf������������ׂĖ������ꍇ�̂݁A�m�F���s�����ƂƂ��Ă���B
|
| �R�j�J�����S�q���@�ɂ������\�I�����̎��O�m�F���x�̊T�v |
�@�J�����S�q���@�ɂ����ẮA���Y�V�K���w�����̎戵�����̏��猩�Ė\�I�̉\�����Ⴂ�ꍇ��\�I�ɂ��ĊǗ����s������ꍇ�ɂ��ẮA�J���҂����Y�V�K���w�����ɂ��炳��邨���ꂪ�Ȃ��|�̌����J����b�̊m�F���邱�Ƃɂ���āA�V�K���w�����̐������͗A���O�̗L�Q���������Ə�����Ă���B
�@�m�F���悤�Ƃ��鎖�Ǝ҂́A�m�F�\�����y�ѓ��Y�V�K���w�����̐������͎戵�����@���L�ڂ������ʂ��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
(1)�m�F�\���� �@��ȋL�ڎ����͎��̂Ƃ���B
(2)�V�K���w�����̐������͎戵�����@���L�ڂ������� �@��ȋL�ڎ����͎��̂Ƃ���B �@(�@)�������悤�Ƃ���ꍇ
�@(�A)�A�����悤�Ƃ���ꍇ �@�@�戵���ݔ��A��ƕ��@ |
�@�s�����́A�m�F�\���ɑ��A���Ɍf���������ׂĖ������ꍇ�̂݁A�J���҂��V�K���w�����ɂ��炳��邨���ꂪ�Ȃ��|�̊m�F���s�����ƂƂ��Ă���B
|
(3) �d�t�ɂ����钆�ԕ��̎戵��
�@�䂪���ɂ����ẮA���ԕ��̐����Ǝ҂�����S�ʑ��̉��w�����ɕω�������ꍇ�̂݁A���Y���ԕ������O�R���̑Ώۂ��珜�O���Ă��邪�A�d�t�ɂ����ẮA���Y�V�K���w�����̐����Ǝ҂��g�p����ꍇ�����łȂ��A���ƎҊԂŎ������ꍇ�ł����Ă��A���ԕ��̓͏o���e�̌y���[�u���u�����Ă���B
| (1)���ԕ��̒�` |
�@���A���̉��w�����ɓ]�����邽�߂̉��w�I�H���̂��߂ɐ�������A�����ď���ꖔ�͎g�p����鉻�w�����̂��Ƃ������B
| (2)���� |
�@�������A���̏����������Ƃ����߂���B
|
| (3)�͏o���e�̌y�����̓��e |
�@���̎����̓͏o���s�v�Ƃ����B
(4) ���n���\�I�Ǘ����Ȃ���Ă���ƍl�����鎖��
�@�ȉ��̏ꍇ�̂悤�ɁA�g�p�i�K�ʼn��w�����������ɕ��o����Ȃ��悤���n���ŗp�����A�p���i�K���ɂ����Ă��\���ȊǗ����Ȃ���邱�Ƃ��S�ۂ����ꍇ�ɂ́A���Y���w�����ɂ��\�I�̉\���͒Ⴂ�ƍl������̂ł͂Ȃ����B
|
(1)���^�̑��u���ł̂ݎg�p�����M�}�� �@�\���ȋC���������������^�̉��M�E��p�p�@����ł̂ݎg�p�����M�}�̂ł����āA���Y���w�����̏�ԂŊ����֔r�o����邱�Ƃ��Ȃ��悤�p���ɍۂ��K���ȏ����������ꍇ�B (2)�����̃`�b�v�����H���Ŏg�p�����t�H�g���W�X�g�i�����������t�j �@�����̃`�b�v�����H���ɂ����āA�V���R���E�G�n��ɓh�z�����t�H�g���W�X�g�́A�h�z�̒i�K�ő啔�����p�t�Ƃ��ĉ������A�ċp���������B�E�G�n��ɓh�z���ꂽ�t�H�g���W�X�g�ɂ��Ă��A��H���ŏ����E�������ꐻ�i�ɂ͎c��Ȃ��B���������Ǘ��̏��m�F�ł���ꍇ�B (3)�����̃`�b�v�̕��~�܂ɗp������ᕪ�q�ʂ̎������� �@�\���ȋC�����������������̃`�b�v�����H�����ł̂ݎg�p����A���~�܂ƂȂ�i�K�ʼn��w�����ɂ���č����q�������ɕω����鉻�w�����B�H��������̔r�o�E�p�����K�ɊǗ������ƂƂ��ɁA�S�ʂ��ϊ�����邱�ƁA�ϊ���̍����q�������̐��̓��ւ̎�荞�݂ɂ��\�I�̉\�����Ⴂ���Ɠ����m�F�ł���ꍇ�B |
(5) �e���ɂ����鉻�w�����̎��O�R�����x�̓����ɂ���
| �� | �@���� ����N���� |
�@���̖ړI |
| ���{ | ���w�����R���K���@ 1973.10.16���� 1986.5.7���� |
��𐫂̐����L���A���l�̌��N�Ȃ������ꂪ���鉻�w�����ɂ����̉�����h�~���� |
| �č� | �L�Q�����K���@(TSCA) 1976.10.11���� |
�l�̌��N���͊��Ȃ��s���ȃ��X�N�������炷���w�������K������ |
| �J�i�_ | �J�i�_���ی�@ 1988.6.28���� 1999.9.14���� |
�������̖h�~��ʂ��Ď����\�ȊJ���ɍv������ |
| �d�t �i���̍����̗p�G�C�M���X�A�t�����X�A�h�C�c�A�C�^���A�A�x���M�[�A�I�����_�A���N�Z���u���O�A�f���}�[�N�A�A�C�������h�A�M���V���A�X�y�C���A�|���g�K���A�t�B�������h�A�I�[�X�g���A�A�X�E�F�[�f���A�m���E�F�[�A�A�C�X�����h�A���q�e���V���^�C���j |
�댯�ȕ����̕��ށA��A�\���Ɋւ����V�� �C���w�� 1967.6.27���� 1992.4.30���� |
�l�y�ъ��ւ̐��ݓI�ȃ��X�N�Ɋւ���A�Z�X�����g�����A���ށA�\�����s�� |
| �X�C�X | ���ی�Ɋւ���A�M�@ 1983.10.7���� ���w�i�@ 2000.12.15���� |
�l�A�����y�ѐA���A���̐��������̋y�ѐ�������L�Q�ȉe������ی삵�A�y��̖L�`�����ێ����� |
| �I�[�X�g�����A | 1989�N�H�Ɖ��w�i�i�͏o�E�R���j�@ 1990.1.17���� 1997.6.30���� |
�J�����S�q���A���O�q���y�ъ��ւ̃��X�N���A�Z�X�����g���A�����Ɗ���ی삷�� |
| �؍� | �L�Q���w�����Ǘ��@ 1990.8.1���� 1996.12.30���� |
�������N�y�ъ��ւ̊�Q��\�h���A�L�Q���w������K�ɊǗ����� |
| �t�B���s�� | ���a���@6969 1990.10.26���� 1994.1.1�{�s |
���N�܂��͊��ɕs���ȃ��X�N�^��Q��悷�鉻�w�����̗A���A�����A���H�A�̔��A���ʁA�g�p����єp�����K���A�����܂��͋֎~���邱�� |
| �j���[�W�[�����h | 1996�N�L�Q�������E�V����(HSNO)�@ 1996.6.10���� 2001.7.2�{�s(�L�Q������) |
�����тɍ����̌��N�y�ш��S��ی삷�� |
| �n���K���[ | ���w�����̈��S�Ɋւ���2000�N��15���@ 2000.4.26���z 2001.1.1�{�s |
�i�O���j�\�ȍō����x���̌��N�ƌ��S�Ȋ��ɌW�鍑���̌������m�ۂ��邽�߁A���w�����̈��S��ۏ��� |
(6) ���Ăɂ�����ᐶ�Y�ʉ��w�����Ɋւ���戵��
| �P�D�č��ɂ�����戵���ƋߔN�̎�g |
�@�s�r�b�`�ɂ����ẮA�N�Ԑ����i�A���j�\�萔�ʂ��ꎖ�Ǝғ�����P�O�g�������̐V�K���w�����ɂ��ẮA�ȉ��̂Ƃ��莖�O�̏��F���邱�Ƃɂ��A�����O�͏o�ɂ�����葱���ȑf������[�u���u�����Ă���B���̐��x�Ɋւ��ẮA�����̎��Ǝ҂�����̉��w�����̓͏o���s���ꍇ�ɂ����鍑�����ʂ̐����Ɋւ���K��͂Ȃ��A�ʂ̃��X�N�ɉ������f�����B
|
���ᐶ�Y�ʉ��w�����̎��O���F���x�i�ꎖ�Ǝ҂�����P�O�g�������j��
|
�@�Ȃ��A��L�̂�����v���ɂ��ẮA1995�N�ɔN�Ԑ��ʂ��u�������ʂP�g�������v����u�ꎖ�Ǝ҂�����10�g�������v�ɕύX���ꂽ�B���̍ۂ̘_���Ƃ��ẮA�ȉ��̎������������Ă���B
|
| �Q�D�d�t�ɂ�����戵���ƋߔN�̎�g |
�@�u�댯�ȕ����̕��ށA��A�\���Ɋւ���@���A�K���A�s���K��̋ߎ����Ɋւ���w�߁i67/548/EEC�j�v�ɂ����ẮA��s�̔N�ԗ\�萔�ʖ��͗ݐϗ\�萔�ʂɉ������A�ȉ��̂悤���i�K�I�ɓ͏o������������߂Ă����B
(1)���S�͏o
�@���Y�ʁA�p�r�A�Ő������f�[�^�i�}���Ő��E�ψٌ����E�Q�W���Ԕ������^�Ő��A���ԓŐ��j�����܂ޓ͏o����s�̂U�O���O�܂łɒ�o
(2)���ʓ͏o
�@���Y�ʁA�p�r�A�Ő������f�[�^�̈ꕔ�i�}���Ő��A�ψٌ����i�������̍ٗʂɂ��~�W���R�}���Ő��j�j�����܂ޓ͏o����s�̂R�O���O�܂łɒ�o
�@���Y�ʁA�p�r�A�Ő������f�[�^�̈ꕔ�i�}���Ő��j�����܂ޓ͏o����s�̂R�O���O�܂łɒ�o
(3)�͏o�s�v
�@�Ȃ��A���݁A�d�t�ɂ����ẮA�u�����̉��w��������̐헪�v�i���B�ψ���쐬�����j�܂��A�V���ȉ��w��������̋c�_���Ȃ���Ă���A���̒��ŁA���w�����Ǘ��ɌW�鎑���̍œK�z���̊ϓ_����A��L�̃f�[�^��o�̋`���t����臒l�̌������̋c�_���Ȃ���Ă���A��̓I�ɂ́A���݂��u�P�g���ȏ�v���u�P�O�g�����`�P�O�O�g���ȉ��v�ɕύX����ƂƂ��ɁA�N�Ԑ����E�A�����ʂ��u�P�O�O�g�����v�A�u�P�O�O�O�g�����v�ƂȂ閈�ɁA���L�͂Ȏ����̎��{�����߂�Ƃ����i�K�I�Ȏd�g����Ă���Ă���B
(7) ���ʐV�K���w�����̎��O�m�F���x�̊T�v
�@���w�����R���K���@�ɂ����ẮA�N�Ԃ̐������ʖ��͗A�����ʂ̑S���ɂ����鍇�v���ʂ��P�g���ȉ��̐V�K���w�����i���ʐV�K���w�����j�ɂ��āA���Y���w�����̐����E�A���J�n�O�ɐ����E�A���̗\�萔�ʓ��������J����b�A�o�ώY�Ƒ�b�A����b�ɐ\���o�āA(1)�����ɂ�����P�N�Ԃ̐����ƗA���̍��v���ʂ��P�g���ȉ��ł���A����(2)�����̒m�����画�f���ē��Y���w�����ɂ��������������A�l�̌��N�Ȃ������ꂪ�Ȃ����Ƃ��m�F���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�m�F���ꂽ���ʂ͈͓̔��ŁA���Y���w���������͗A�����邱�Ƃ��ł��鐧�x���݂����Ă���B
�@���x�̏���ƂȂ��Ă��鐻���E�A���\�萔�ʂP�g���ɂ��ẮA���a�S�W�N�̉��w�����R���K���@����̍ۂɁA���ɁA���m��������͓�𐫁E���~�ϐ��E�����Ő�������������艻�w�����ɊY�����鏭�ʐV�K���w��������肷�邱�Ƃ�����ȏꍇ�����蓾���Ƃ��Ă��A�����̐����E�A�����ʂ̏����N�ԂP�g���Ƃ��Ă����A�l�̌��N��Q�𖢑R�h�~���邱�Ƃ��ł���Ƃ̔��f�Ɋ�Â����̂ł���B
�@�Ȃ��A���w�����R���K���@�ɂ����鍂�~�ϐ��̈ʒu�t���́A�ȉ��̗�̂Ƃ���A�H���A���̉ߒ��Ő��̓��Z�x���������������邱�Ƃɂ������Z�x�������Z�x�Ől�ɐێ悳���\�����l���������̂ł���B���̈Ӗ��ŁA���w���������o�R�Ől�ɂ��ێ悳���ʂ�]������ۂɂ́A���Z�x�ƂƂ��ɁA�~�ϐ����l�����邱�Ƃ��K�ł���B
|
�����o�R���Ă̐l�̌��N�ւ̉e���Ɋւ���
|
|||||||||||||||
|
�g�F���~�ϐ������i�Z�k�{��10000�{�j�A�k�F��~�ϐ������i�Z�k�{��100�{�j�Ƃ���B�Ȃ��A��L�ɂ����Ă͉��w�����̎�v�Ȑێ�o�H�ƍl�����鋛��ނ̐ېH�̏ꍇ��Ꭶ�B |
�i�ʎ��j
������艻�w�������P�g�������ɕ��o�����ꍇ�̊����Z�x�̗\��
�@���w�����R���K���@�ɂ����鏭�ʐV�K���w�����̎��O�m�F���x�ɂ����ẮA�N�Ԃ̐����E�A�����ʂ̑S���ɂ����鍇�v���ʂ̏���l�͂P�g���Ƃ���Ă���B���̏���l�̑Ó����ɂ��āA�ȉ��̂Ƃ���A������艻�w�����̈�ł���f�B���h����������Ƃ��ėp���āA����ꂽ���撆�ɔN�ԂP�g�����o���ꂽ�Ɖ��肵���ꍇ�̊����Z�x�̗\���A�y�ы���ނ̐ێ�ɂ��\�I��z�肵���ȈՂȃ��X�N�]���ɂ��m�F���s�����B
| �P�D�Ώە��� |
�@������艻�w�����̒��ň�����e�ێ�ʁiADI)���ł��Ⴂ�f�B���h�����iADI:0.0001mg/kg/day(*1))��ΏۂƂ����B
| *1: | �����ȁA�����Ȋw�����u������̃_�C�I�L�V���ނɊւ��钲���v���ʕ��\�����i����11�N8��2���j |
�@�Ȃ��A�����ɗp�����f�B���h�����̕����f�[�^�͈ȉ��̂Ƃ���B
| ���q�� | �@�@�@380.9 |
| ���n��x(mg/L) | �@�@�@�@ 0.022 |
| ���C��(Pa) | �@�@�@�@ 4.3�~10�|�S |
| ���z�W���iLog Kow�j | �@�@�@�@ 5.61 |
| �����Z�k�{�� | �@ 14,500 (��2) |
| �i�i���j���{������@���w�����^���\����@�J���������i���a57�N3���j�A�o�ώY�ƏȊ������w�����_�����ʁi���Q�j�j |
| �Q�D�\�I�̍l���� |
�@�S�����ʂŔN�ԂP�g���̃f�B���h���������N�p�����Đ�������A���̂����̈�芄��������̐���ɕ��o���ꂽ��A�����̕������~�ς��ꂽ����ނ�l���ێ悷�邱�Ƃɂ��\�I��z�肷��B�Ȃ��A�����ł͈ȉ��̓�̊C���z�肷�邱�ƂƂ���B�Ȃ��A��C�y�ш������o�R�̖\�I�ɂ��Ă͖���������ƍl���A�����ł͍l�����Ȃ����ƂƂ���B
(1) �z�肵������
�@�ؗ����Ԃ����������Ƃ��s���Ă���L�͈͂̐���Ƃ��āA�����p�y�ѐ��˓��C��I���B
| ���� | �ʐ�(km2) | ���[(m) | �ؗ�����(��) |
| �����p | 1,380 | 45 | 45.6 |
| ���˓��C | 21,827 | 37 | 547.5 |
| �i���y�Z�p�������������������A�i���j���ۃG���b�N�X�Z���^�[�������j |
�@�����̐���ɑ��āA�S���̔N�Ԑ��Y�ʂP�g���̂����A����l���ɔ�Ⴕ�����ʂ��g�p������o�����Ƒz�肵�āA�����p�ɂO�D�Q�W�g���A���˓��C�ɂO�D�P�T�g���̃f�B���h���������o�����Ɖ��肵���B
(2) �\���ɗp�������f���y�ъe��W��
�@����ɂ�����\�w���ƒꎿ�ō\�������Q�R���p�[�g�����g���f���iSAFECAS�j��p���āA�ȉ��̉���Ɋ�Â������n���ԔZ�x���v�Z���A����ɐ����Z�k�{�����悶�邱�Ƃɂ��A�����Z�x�y�ы��̒��Z�x���Z�o�����B
| �����ɗp�����Q�R���p�[�g�����g���f�� |
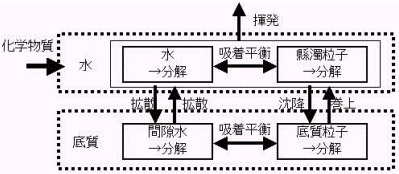 |
�i�v�Z�̑O������j
| �E | ���������x�F | ��𐫂̂��߃[���Ɖ���B���̑��̔��I�ȕ��x���[���Ɖ���B |
| �E | ���t�萔�F | ���z�W����p����Mackay�̃t�K�V�e�B���f���ł̑��֎�Koc=0.41�~Kow���琄�Z�B |
| �E | ����ނ̐ێ�ʁF | ���\�I�W�c�̋���ޑ��H�҂�z�肵268g/day���g�p�B �i�����Ȃ̍����h�{�����i1995�N�j�ł̕��ϒl�ƕW��������Z�o�����X�T�p�[�Z���^�C���l�j |
| �E | 50kg |
| �E | ���̑��̊��p�����[�^�̓��f���̃f�t�H���g�l�ł���ȉ��̒l���g�p�B
|
| �S�D�\������ |
�@�Ώې���ւ��ꂼ��A�O�D�Q�W�g���^�N�i�����p�j�A�O�D�P�T�g���^�N�i���˓��C�j�̑��x�ŗ��������Ɖ��肵���ꍇ�ɗ\�������e���}�̒��Z�x�y�ѐێ�ʂ͈ȉ��̂Ƃ���B
| �@ | �����p | ���˓��C |
| �����Z�x(mg/L) | 0.59�~10�|�U | 0.62�~10�|�V |
| �ꎿ���Z�x(mg/kg) | 1.6�~10�|�R | 0.17�~10�|�R |
| ���̒��Z�x(mg/kg) | 0.78�~10�|�Q | 0.83�~10�|�R |
| �ێ��(mg/kg/day) | 0.42�~10�|�S | 0.44�~10�|�T |
�@���ꂼ��̐���ɂ�����ێ�ʂ��`�c�h�l�i0.0001mg/kg/day�j�Ɣ�r����ƁA�ێ�ʁ^�`�c�h�̒l�́A�����p�ł͂O�D�S�Q�A���˓��C�ł͂O�D�O�S�ƂȂ����B
(8) ���w�����r�o�c���Ǘ����i�@�ɂ�����o�q�s�q�Ώە����I��̍ۂ̖\�I�̍l����
�@���w�����r�o�c���Ǘ����i�@�ɂ�����o�q�s�q���x�̑Ώە����i����w�艻�w�����j�ɂ��ẮA�ȉ��̗v���������ƂƂ���Ă���B
|
�@���ɁA�\�I�v���̔��f��ɂ��ẮA�W�R�c��i���P�j�ɂ�����R�c�̌��ʁA�u���艻�w�����̊��ւ̔r�o�ʂ̔c�����y�ъǗ��̉��P�̑��i�Ɋւ���@���Ɋ�Â�����w�艻�w�����y�ё���w�艻�w�����̎w��ɂ��āi�j�v�ɂ����āA���L�̂悤�ȍl�����̐�����������Ă���B
| ���P | �������R�c����ی�����@�o�q�s�q�Ώە������ψ��� �������R�c���������@�o�q�s�q�@�Ώۉ��w�������ψ��� ���w�i�R�c����S������@���w�����Ǘ����i�@�Ώە����������ȉ� |
| �@����w�艻�w�����̑I���Ƃ��ẮA�����ꂩ�̗L�Q���i���Q�j�ɕ��ނ��ꂽ�����ŁA�u�P�N�Ԃ̐����E�A���ʁv�����ʈȏ�܂��͈�ʊ����ōŋ߂P�O�N�Ԃŕ����n�悩�猟�o���ꂽ���̂ɂ��ẮA�����_�Ő����E�A�����̎戵�����Ȃ����Ƃ����炩�ł�����̂������u�����L�͂Ȓn��̊��ł̌p���I�ȑ��݁v��������̂Ƃ݂Ȃ��A�I��ΏۂƂ��邱�Ƃ���{�Ƃ��邱�Ƃ��K���ł���B�������A���ɏd�Ăȏ�Q�������炷�����y�юg�p�`�Ԃ��猩�Ė��炩�Ɋ����ɕ��o����₷�������ɂ��ẮA�u�����E�A���ʁv����菬�������x���̂��̂��u�����L�͂Ȓn��̊��ł̌p���I�ȑ��݁v��������̂Ƃ݂Ȃ��A�I��ΏۂƂ��邱�Ƃ��K���ł���B �@��̓I�ȁu�P�N�Ԃ̐����E�A���ʁv�ɂ́A�����葽���Ɗ������猟�o����₷���Ȃ�P�O�O�g������{�Ƃ��A��菬�������x���̂��̂��ΏۂƂ���ꍇ�͂�����P�����̂P�O�g���Ƃ���̂���̍l�����ł���B �܂��A�n�d�b�c�ɂ����č����Y�ʉ��������̖ڈ��Ƃ��Ă���P�O�O�O�g������{�Ƃ���l����������B |
| �P�D������ �Q�D�ψٌ��� �R�D�o�������Ő� �S�D�z�������Ő� �T�D��Ɗ����e�Z�x���瓾����z�������Ő���� �U�D���B�^�����Ő� �V�D���쐫 �W�D���ԓŐ� �X�D�I�]���w�j�� |
(9) ���ȍ��{�����ɂ����鐻���E�A�����ʕʂ̌��o��
�@���Ȃ����{���Ă��鉻�w�������������Ԓ����i���{�����j�ɂ����ď��a�S�X�N�x���畽���P�Q�N�x�܂łɒ����ΏۂƂ��ꂽ�����Ɋւ��āA�ߋ��̉��w�����̐����E�A�����ʂƊ�������̌��o�̊W�������Ƃ���A�ȉ��̂Ƃ���ƂȂ����B�i���j�@�����E�A�����ʂ̏��Ȃ��敪�قnj��o�����͏������Ȃ��Ă���A�P�O�O�g���̋敪�����ɂ��Č��o�����͍X�ɑ傫����������X���������Ă���B�܂��A�ߋ��̐����E�A�����ʂ��N�ԂP�O�g�������̏ꍇ�ɂ́A����܂ł̂Ƃ��댟�o���т͂Ȃ������B
| �i���j | �����E�A�����ʂ̃f�[�^�́A�o�ώY�ƏȂ̐����E�A���ʂɊւ�����Ԓ������ʁA���w�������������Ԓ����A�_��v���A���Ԃ̃f�[�^�x�[�X�y�ѐ������Ǝ҂ւ̕�����蒲���ɂ��B |
|
�����E�A�����ʋ敪���̌��o�ꗗ
|