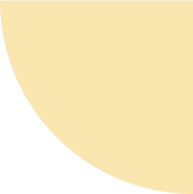
どんな環境で
難聴になるの?
大きな音を長時間、長期間にわたって聞き続けることにより、有毛細胞がダメージを受け、音が聞こえにくくなることがあります。
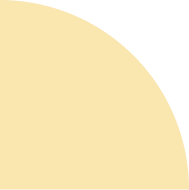
「聞こえにくさ」につながる可能性のある環境
例えば、次のような環境に長時間いると、音が聞こえにくくなる可能性があります。
騒音性難聴とは?

大きな音にさらされたことによる聴力の低下のことを指します。
長時間大きな音を聞き続けることで、音を伝える役割をしている有毛細胞がダメージを受け、高い音から徐々に聞こえにくくなっていきます。じわじわと症状が進行していくため、自分では症状に気づかない場合が多いです。
職場において、
どんな作業環境が「聞こえにくさ」につながるの?
・鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う作業場
・インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバーを使用してボルトやナットを締め付ける作業場
・ショットブラストを使用した金属の研磨作業場
・携帯用研削盤やベルトグラインダーを用いた金属の表面研削や研磨の作業場
他の作業場についてはこちらから
騒音障害防止のためのガイドライン「騒音の職場」
長時間の騒音にさらされる時はどうすればいいの?
-
休憩を効果的に取り入れて、長時間の連続的な騒音ばく露を避ける
-
耳の健康を定期的にチェックし、早期の聴覚障害の兆候を見逃さない
-
聴覚保護具である耳栓や耳覆い(イヤーマフ)を使用する
-
職場でのコミュニケーションを工夫し、騒音によるストレスを軽減する方法を探す
労働者の耳を守るために
~作業環境管理~

作業環境管理では、事業者は作業場における騒音レベルを定期的に測定し、その結果に基づいて必要な対策を講じることが求められます。
騒音レベルが高い場合は、設備や作業工程の改善、または聴覚保護具の使用を義務づけることで、労働者の健康を守ることが重要です。
また、測定結果は記録し、一定期間保存しましょう。
労働者の耳を守るために
~騒音対策の方法~

-
騒音発生源対策
・低騒音型機械の採用
・給油や部品交換による発生原因の除去
・防音カバー、ラギング等の取り付けによる遮音
・消音器、吸音ダクト等の取り付けによる消音
-
伝播経路対策
・配置の変更による距離減衰
・遮蔽物や防音塀の設置
・建屋内部の消音処理
・音源の向きの変更
-
受音者対策
・防音監視室の設置
・作業スケジュールの調整
・遠隔操作の導入
・耳栓や耳覆いの使用
健康診断、騒音の健康診断に基づく事後措置
-
事業者は、労働者に対し労働安全衛生法等で定められた健康診断を実施する必要があります。
-
健康診断には一般健康診断と特殊健康診断があり、業務に応じて異なる検査項目が定められています。
-
健康診断結果は受診者全員に通知し、異常の所見がある場合は医師の意見を聴取する必要があります。
-
医師の意見に基づき、必要があれば就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を講じることが求められます。
-
これらの措置により、労働者の健康と安全を確保することが目的とされています。
詳しくはこちらから
職場の健康診断実施強化月間
こちらもご参考
治療と仕事の両立支援ナビ
「聞こえにくさ」を感じたら...
耳鼻咽喉科を受診してみませんか?
近くの耳鼻咽喉科を探してみましょう!
(協力:一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会)
