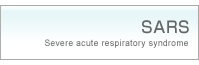
重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報
1 医療機関における対応
(1) 疑い例と可能性例の検体採取
| (1) | 検体の採取にあたっては、保健所の指示に従う。 採取前に保健所に連絡し、採取方法、採取至適時期、検体の種類を確認したうえで採取時期を決定し、採取を行う(参考1)。 |
| (2) | 採取する検体の種類は、検査指針の3に基づく (ウイルス分離同定用検体については、その至適採取時期を考慮し、必ず抗体検査用のペア血清(急性期と発症後21日以降の回復期)を確保する必要がある) |
| (3) | 疑い例の検体採取にあっては、事前に本人の了解を得て行う。 |
(2) 検体の送付
| (1) | 検体の送付に際しては保健所に連絡する。 |
(3) SARSコロナウイルス以外の検査について
| (1) | SARSコロナウイルス以外の病原体の検査については、従来の基準に従う。 |
2 保健所における対応
| (1) | 医療機関から連絡を受けた保健所は、検体の採取方法、採取時期について地方衛生研究所と調整し、地方衛生研究所への検体送付/搬入等の事務を行う。 |
| (2) | 「疑い例」・「可能性例」の報告様式中の症例IDを厚生労働省結核感染症課に確認し、医療機関に教示すると共に、今後の情報管理に使用する。 |
| (3) | (2)については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」(厚生省保健医療局長通知平成11年3月19日付け健医発第458号)に基づいて行う。 |
3 地方衛生研究所における対応
(1) 検体の取扱について
| (1) | 医療機関における検体採取方法(参考1) 医療機関における検体採取方法等について、技術的な支援を行うとともに、搬入/送付時間、方法等を打ち合わせて受け入れ態勢を準備する。 |
| (2) | 医療機関からの検体取扱(参考1) 届いた検体は適切な方法で処理を行い、SARSコロナウイルスの検査を行う場合には、必ずオリジナルの臨床検体を適切な形で-80℃にて保存する。 |
| (3) | 国立感染症研究所への検体送付方法(参考1) 検体を送付する際には、事前に国立感染症研究所情報センターに検体提出票にて連絡し、入手した検体IDを検体にラベル貼付して送付する。 |
(2) 検査方法について
| (1) | PCR検査(参考2) |
| (2) | ウイルス分離(参考3) |
(3) 検査結果の取扱について
| (1) | 国立感染症研究所への連絡 検査結果は陰性陽性にかかわらず、感染症情報センターに連絡し、陽性の場合には、確認検査の依頼を行う。 |
| (2) | 管轄の保健所および医療機関への連絡 あらかじめ地域で合意された方法に従って、医療機関および保健所に検査結果とその後の対応を連絡する。 |
4 国立感染症研究所における対応
(1) 検査方法について
| (1) | PCR検査 SARS-コロナウイルスに特異的なプライマーでRT-PCRを行う。現時点で、感染研で使用しているプライマー、PCR条件については、参考2を参照。 |
| (2) | ウイルス分離 地衛研から送付されたウイルス分離用検体について、VeroE6細胞を用いてSARS-コロナウイルスの分離を行う。検体の処理法等については、参考3を参照。 |
| (3) | 抗体検査 中和試験、ELISA、間接蛍光抗体法などによって、急性期と回復期のペア血清で抗体価の上昇によって判定する。現在、地衛研への配布が可能な抗体検査用の抗原を開発中であるが、当面は、抗体検査は感染研で行う。なお、血清の採取時期などについては、感染研情報センターHPに掲載する予定である |
(2) 検査結果の取扱について
| (1) | 地方衛生研究所への連絡 RT-PCR、ウイルス分離および抗体検査で陽性結果が確認された場合は、感染研情報センターから速やかに連絡する。 |
| (2) | 厚生労働省への連絡 RT-PCR、ウイルス分離および抗体検査で陽性結果が確認された場合は、感染研情報センターから速やかに連絡する。 |
参考
(以下の参考文献については、国立感染症研究所感染症情報センターホームページで、随時、最新情報を提供中)
http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update.html
-
参考1 SARSコロナウイルスに関する検査対応について
(国立感染症研究所 感染症情報センター)参考2 RT-PCR法によるSARSコロナウイルス遺伝子の検出
(国立感染症研究所 ウイルス第三部第1室)参考3 SARSコロナウイルス検出のためのウイルス分離用検体の採取・処理法およびウイルス分離
(国立感染症研究所 ウイルス第三部第1室)