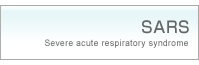
重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報
(参考1)
(国立感染症研究所 感染症情報センター)
1. SARSにおける病原体検査方針
(1) 国立感染症研究所ウイルス第三部第1室(以下感染研)ではSARSコロナウイルスに関する特異的検査を行うが、それ以外の既知の病原体の検査は地衛研もしくは病院検査部で行う。
(2) 疑い例(suspected case)、可能性例(probable case)全員についてSARSコロナウイルス特異的ウイルス学的検査を実施する。
疑い例(suspected)でSARSコロナウイルス特異的検査において、複数の施設の結果が陽性であった場合、その時点で可能性例(probable case)として扱う。
(3)-1 (SARSコロナウイルス以外の病原体検査)
すべての疑い例(Suspected case)、可能性例(Probable case)について、原則的には地衛研もしくは病院検査部において、通常の病原体取り扱いに準じて飛沫感染、接触感染の予防に特に留意をしながらBSLレベル2で既知の肺炎を起こす(異型肺炎含む)病原体の一次スクリーニングを行うものとする。これには、一般細菌培養、迅速診断法(連鎖球菌など一般細菌、レジオネラ、クラミジア、マイコプラズマ、アデノウイルス、インフルエンザウイルス、RSウイルス、その他について、地域における患者発生状況を考慮して、必要な病原体について検討する)、血清学的方法(マイコプラズマ、クラミジア)を含む。
(3)-2 SARSコロナウイルスの検査対応
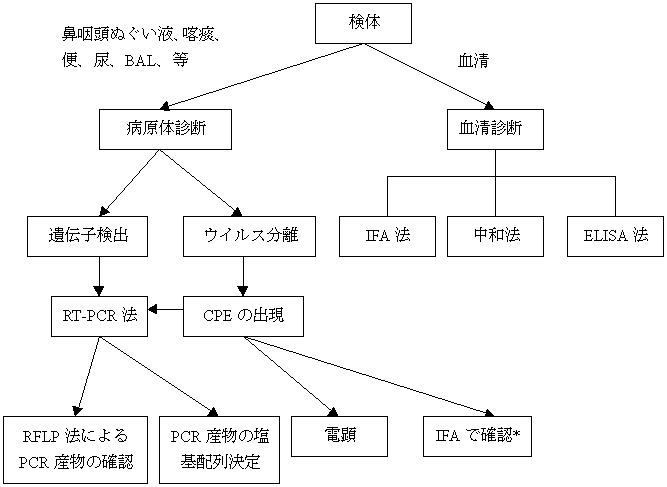
* 現時点では、SARSコロナウイルス同定用の抗血清が無いため、基本的にはRT-PCR法により同定検査を行う
(3)-2a (SARSコロナウイルスの分離)
(3)-1に加えて、すべての疑い例(Suspected case)、可能性例(Probable case)について、ウイルス分離が可能なBSLレベル3施設を有する地衛研ではSARSコロナウイルスを目的としたウイルス分離を行う。SARSコロナウイルス分離に使用する培養細胞はVeroE6とする。LLCMK2細胞は当初疑われていたhuman metapneumovirusについて感受性があるが、SARSコロナウイルスには感受性はない。CPEが出現した場合には培養上清、培養細胞、当該臨床検体を感染研に送付する。地衛研においてウイルス分離が困難である場合は、臨床検体を感染研に送付する。感染研に送付する場合は、いずれの場合も行政検査として対応するため、4.の検体受付に基づいて実施する。
(3)-2b(SARSコロナウイルスの遺伝子検索)
SARS:診断検査の入手状況と検査方法の実際(5月1日 5訂)
・臨床検査結果の解釈に関する提言
・SARSの臨床検査に対する提言
http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update45-lab.htmlを参照のこと。
RT-PCR法を用いてSARSコロナウイルスの検出を試みる際は、上記マニュアルを参照に地衛研において実施する。複数の施設での陽性確認が必要であるため、陽性結果が得られた場合は感染研にも検体を送付する。地衛研において実施が困難である場合は、臨床検体を感染研に送付する。送付に際してはウイルス分離と同様行政検査として4.の検体受付に基づいて実施する。
2. 病原体検査のための検体採取方針
SARSの診断検査のための検体採取について(WHO 4月29日)
http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update41-ss.htmlを参照のこと。
| 1) | 検体の採取時期
|
地域におけるSARS関連コロナウイルス肺炎の集団発生での臨床経過中のウイルス量の前向き研究(4月30日)
http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update44-HKong.htmlを参照のこと。
2) 検体毎の採取方法と検体送付方法
全ての検体について、48時間以内に検体を輸送することが可能な場合には、検体採取後直ちに冷蔵庫に保存し、4℃(保冷剤)で輸送する。48時間以上輸送することが不可能な場合は、検体採取後直ちに施設内で-70℃以下の冷凍庫に保存し、冷凍(ドライアイス)にて輸送する。ドライアイスは密閉した容器に入れないこと。梱包の方法は(送付容器PDF版)を必ず参照のこと。
-
(ア) 便(発症早期から発症1カ月頃までRT-PCR法で検出可能であるが、発症10日頃の検体の陽性率が最も高くほぼ100%。): 10〜50mlの便を50mlの生食に懸濁し、遠心分離後、上清2〜3mlを蓋付き容器に入れ、パラフィルムにてシールし、ビニール袋にいれる。 (イ) 喀痰(疾患初期及び病状悪化時の検体): 通常の方法にて、自分で出せる場合には滅菌生理食塩水もしくは水道水で複数回うがいをして口腔内雑菌を除いた後、喀痰を採取してもらう(唾液の混入は可能な限り避け、口腔内常在菌の混入を抑える。)。密栓できる喀痰専用容器(滅菌済み)に入れてフタをしてジップ付きプラスティック袋に入れて速やかに提出する。検体採取の際は、周りの人に飛沫が飛ばないよう区切られた部屋で行うなどの対策を講じる必要がある。採痰ブース(陰圧)があればより理想的である。人工呼吸器管理の場合には無菌的な操作のもとに、滅菌されたカテーテルを使って気管吸引液を採取する。採痰容器は密栓できる喀痰専用容器(滅菌済み)に採取後、ジップ付きプラスティック袋に入れて速やかに提出する。 (ウ) 鼻咽頭拭い液あるいは鼻咽頭洗浄液/吸引液(疾患初期及び病状悪化時の検体): 通常の方法にて、鼻咽頭拭い液の場合には両方の鼻孔内を、口腔咽頭拭い液の場合には咽頭後壁および扁桃領域を拭い、スワブを2ml [注:綿棒が乾燥する状態や、大量の液体に浸した状態ではウイルスの検出が困難になります。1.5〜2 mlであれば綿棒が適度に液体に浸る程度となり、ウイルスの検出に最適です。] のウイルス輸送液体培地、ない場合は生理食塩水内に入れ、柄を折りとったのち、蓋をする。洗浄液/吸引液の場合には、1〜1.5mlの生理食塩液を鼻腔内に注入し、その後鼻咽頭分泌物を吸引する。もう一方の鼻孔についても同様に行い、吸引液は清潔試験管にいれる。 (エ) 尿(発症後3日間は検出されないため、少なくとも発症4日以降。発症10日頃の検出率は50%程度。その後検出率は漸減。): 50mlの尿を遠心分離し、沈査を2〜3mlの上清に懸濁させ、コニカル試験管(ファルコンなど)にいれ、パラフィルムにてシールする。 (オ) 血清(最低限、急性期と発症20日以降の2点。): 急性期血清はSARSが疑われた時点で即座に、回復期血清は発症20日以降に採取、輸送する。血液は血清に分離した後、それぞれ血清で1?2ml程度が必要である。できれば、1週間毎に1-2mlづつ血清を保存し、可能な限り多くの病日の検体を輸送する。
3.コロナウイルスについて、SARSコロナウイルスの安定性、抵抗性について
コロナウイルスはヒトではこれまで風邪症候群の原因ウイルスの一つでしかなかったが、動物ではかなり様々な病気をおこす。実験動物の分野ではマウス肝炎ウイルス、家畜の分野では豚伝染性胃腸炎、鶏伝染性気管支炎など、愛玩動物の分野では猫伝染性腹膜炎等々がある。コロナウイルスに属するウイルスは3つの血清型に分けられる。ウイルス粒子の表面にはS (spike,surfaceあるいは E2), M (membrane), E(small membrane), HE (hemagglutinin esterase) 蛋白、内部にN (nucleocapsid)蛋白がある。このうち、HE蛋白は1部のウイルスにのみ存在する。S蛋白は中和活性、膜融合、レセプターとの結合を担っている。コロナウイルスの特徴としてmutation及びRNA recombinationの頻度が高いことが挙げられる。
検体の採取、検査の実施にあたっては、以下の情報をよく理解しておくことが重要である。
WHO研究施設ネットワークが集積したSARSコロナウイルスの安定性と抵抗性に関する最初のデータ (5月4日)
http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update47-data.htmlを参照のこと。
| 1) | 37℃で4日間保存すると、検出限界以下にウイルス量は減少する。 |
| 2) | 4℃では、21日目にも感染性が残る。4℃4日間保存のウイルス量は10の5.7乗 程度。 |
| 3) | 再凍結(-80℃)4日間保存でのウイルス量は10の6.7乗程度。 |
| 4) | 室温でプラスチックなどに乾燥した状態でウイルスが付着していると2日間程度感染性がある。 |
| 5) | 便中、特にpHの高い下痢便中では4日間程度生存する。 |
| 6) | 血清については、56℃30分の通常の処理で感染性はなくなる。 |
| 7) | エタノールでは10分程度でウイルスは不活化する。 |
| 8) | アセトン20分間処理あるいはエーテル10分間処理で、完全 にウイルスが不活化されない報告もあり注意が必要。 |
| 9) | 0.1%程度のNP40では20分処理しても感染性が残る(ドイツの研究所からの報告)。 |
| 10) | 石鹸やリタージェントでの感染性の不活化は困難である。 |
4. 感染研での検査の範囲と結果報告
(1) 感染研において行う検査は、SARSコロナウイルスについての特異的検査とする。
(2)暫定的結果の報告は可及的速やかに行うものとする。
(3)結果は情報センターを通して、行政担当部局と医療機関への同報送信とする。
(4)情報センターでは、すべての情報をいれたデータベースを維持するものとし、結果報告の管理も行う。
5. 検体受付
(1) 感染研による検査は、医療機関、保健所、都道府県、地衛研などの合意の元、行政からの依頼によるものとする。病院からの直接の問い合わせについては、情報センターにて、ここに記載する原則を説明することとする。
(2) 上記1の (3) のクライテリアに合致するものは、まず情報センターにて受付を行い、情報センターが患者および各検体に対して各々ID番号をつける。今後は、すべての連絡にこのID番号を使用する。この際、医療機関担当者、検査担当者、行政担当者のコンタクトリストを受け取るものとする。
(注)症例IDは、都道府県番号+患者イニシャル+感染研にて受付順のシリアルナンバー(001より始まる)+診断カテゴリー(S:Suspected;P:Probable;D:Discarded R;researchとし、これはカテゴリーが変わった場合には、SP(SからP)、SD(SからD)のように連続して付記する)とし、検体IDは、症例IDに引き続く、_(アンダーバー)+検体種別(P鼻咽頭ぬぐい液・洗浄液;S喀痰;R肺胞洗浄液;B血液;U尿;F便;Mその他)+検体採取日時(患者から採取した日付で、例えば2003年4月4日午後3時5分であれば、0304041505とする。午前9時5分であれば、0304040905(AM)とする。)+(同時に数検体とった場合には順に1、2と括弧内に入れる)ものとする。CPE陽性培養上清の場合には、検体種別の前にYをいれる。
(3) この情報とともに、情報センターは、ウイルス3部第1室に検体受付を連絡し、ウイルス3部第1室が具体的な検体送付方法とタイミングについて先方の担当者と相談する。
(4) 検体の搬送方法は、基本的に天然痘の検査材料の輸送方法(添付2)に準じるものとし、上記 (3) によって合意された時間指定で送付するか、持参するものとする。
(5) 検体受付時間は、原則として勤務時間帯(9:00?17:00)とし、土曜日、日曜日、祝祭日は検体を受けることはできない。但し、緊急の場合には、個別に対応する。
| (添付) | 検体の送付方法はこの中に詳しく説明されています。 1.「重症急性呼吸器症候群(SARS)管理指針」(PDF 100K) 2.「検査材料の採取・送付に関する追加情報」 (PDF 64K) |
◆連絡先
国立感染症研究所感染症情報センター
〒162-8640 東京都新宿区戸山1-23-1
TEL03-5285-1111(代)、 FAX03-5285-1129
◆検体送付先
国立感染症研究所ウイルス第三部
〒208-0011 東京都武蔵村山市学園4-7-1
TEL042-561-0771、FAX042-561-0812
(注)この検査対応方針は、現時点までの知見に基づく、暫定的なものであって、今後の新たな知見の発見、あるいは国内の状況によって、随時更新されるものとする。