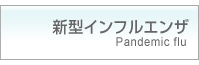
新型インフルエンザ対策関連情報(英語版はこちら)
新型インフルエンザ対策行動計画
<総論>
<総論>
| 背景 |
|
新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたウイルスとは表面の抗原性が全く異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生する。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を持っていないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらす。
20世紀では、1918年(大正7年)に発生したスペインインフルエンザ大流行が最大で、世界中で約4千万人が死亡したと推定されており、我が国でも約39万人が死亡している。また、1957年(昭和32年)にはアジアインフルエンザ、1968年(昭和43年)には香港インフルエンザがそれぞれ大流行を引き起こしており、医療提供機能の低下を始めとした社会機能や経済活動の様々な混乱が記録されている。 近年、東南アジアを中心に高病原性鳥インフルエンザ(A/H5N1型)が流行しており、このウイルスがヒトに感染し、死亡例も報告されている(2003年(平成15年)12月〜2005年(平成17年)10月の間で、ヒトの発症者122名、うち死亡者62名)。また、高病原性鳥インフルエンザの発生がヨーロッパでも確認されるなど、依然として流行が拡大・継続しており、ヒトからヒトへ感染する新型インフルエンザの発生の危険性が高まっている。 新型インフルエンザに対する国際的な取組としては、これまで、世界保健機関(WHO)が、世界に4つあるWHOインフルエンザコラボレーティングセンター(日本、米国、英国、オーストラリア)の協力を得て、インフルエンザパンデミック対策を進めてきている。2005年(平成17年)5月には、WHOが「WHO Global Influenza Preparedness Plan(WHO世界インフルエンザ事前対策計画)」を公表し、各国がこれを基準として自国の国民を守るための行動計画の策定を進めている。 一方、我が国では、2003年(平成15年)10月、厚生労働省に「新型インフルエンザ対策に関する検討小委員会」が設置され、対策の検討を進め、2004年(平成16年)8月に同委員会で「新型インフルエンザ対策報告書」を取りまとめた。その検討開始後には、我が国でも家きんにおいて高病原性鳥インフルエンザ(A/H5N1型)が発生(山口県・大分県・京都府)し、感染家きんの防疫措置が講じられるなど緊迫した状況となり、政府全体の対応として、2004年(平成16年)3月に「鳥インフルエンザ緊急総合対策」が取りまとめられるとともに、早期通報促進、移動制限区域内の農家への補償等を内容とする家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の改正が行われた。同年11月には、高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル(平成15年9月農林水産省消費・安全局長通知)が見直され、家畜伝染病予防法に基づく高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針として策定された。 さらに「新型インフルエンザ対策報告書」の提言に基づき、2005年(平成17年)4月には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく「感染症の予防の総合的推進を図るための基本的な指針」(平成11年厚生省告示第115号)等を改正し、ワクチン開発や抗インフルエンザウイルス薬の備蓄等に係る規定を盛り込み、対策を進めてきたところである。 このように我が国においても対策を段階的に進めてきたところではあるが、今般、さらに新型インフルエンザウイルス発生の危険性が高まってきていることから、迅速かつ確実な対策を講ずるため、「WHO世界インフルエンザ事前対策計画」に準じて「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定することとした。 |
| 流行規模の想定 |
|
新型インフルエンザ発生の流行規模は、出現した新型インフルエンザウイルスの病原性や感染力の強さ等に左右されるものであり、現時点でその流行規模を完全に予測することは難しいが、今回の新型インフルエンザ対策行動計画を策定するに際しては、「新型インフルエンザ対策に関する検討小委員会」において一つの例として推計された健康被害を踏まえて想定した。
この推計は、米国疾病管理センター(以下、「CDC」という。)により示された推計モデル(FluAid 2.0 著者Meltzerら、2000年7月)を用いて、我が国の状況をそのまま当てはめて行ったものである。推計の結果、全人口の25%が新型インフルエンザに罹患すると想定した場合に医療機関を受診する患者数は、約1,300万人〜約2,500万人(中間値約1,700万人)と推計されている。 この推計の上限値である約2,500万人を基に、過去に世界で起こったインフルエンザパンデミックのデータ;アジアインフルエンザ等を中等度(致死率0.53%)、スペインインフルエンザを重度(致死率2%)として、新型インフルエンザの病原性が中等度の場合と、重度の場合について推計した。その上限値はそれぞれ、中等度の場合では、入院患者数は約53万人、死亡者数は約17万人となる。また、重度の場合では、中等度と重度の場合の死亡率から推計すると、入院患者数は約200万人、死亡者数は約64万人と推定される。なお、これらの推計においては、新型インフルエンザワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等による介入の影響(効果)、現在の我が国の衛生状況等については考慮されていないことに留意する必要がある。 また、全人口の25%が罹患し、流行が8週間続くという仮定の下での、中等度の場合での入院患者の発生分布の試算では、1日当たりの最大入院患者数は、10万1千人(流行発生から5週目)となっている。さらに、重度の場合には、1日当たりの最大入院患者数も増大すると推定される。 |
| 対策の基本方針 |
|
|
|
新型インフルエンザの出現時期を正確に予知することは困難であり、また、その出現そのものを阻止することは不可能である。また、地球規模でヒト・モノがダイナミックに動いている時代でもあり、世界中のどこかで新型インフルエンザの出現が起これば、我が国への侵入も避けられないと考えられる。 なお、鳥インフルエンザのまん延防止を的確に講じることにより、新型インフルエンザの出現を遅らせることは可能であると考えられている。 従って、新型インフルエンザ対策の目的は、家畜衛生部門との連携を図ることにより、新型インフルエンザの出現を可能な限り防止し、公衆衛生的な介入により、発生初期の段階でできる限り封じ込めを行うとともに、パンデミック時における感染拡大を可能な限り阻止し、健康被害を最小限にとどめ、社会・経済機能の破綻に至らせないことである。 このため、発生・流行時に想定される状況を念頭におき、新型インフルエンザの発生に係るWHOのフェーズごとに、我が国における行動計画をあらかじめ確立しておく必要がある。また、この行動計画を事前に関係者に広く周知し、具体的な行動が速やかにとることができるよう準備しておく必要がある。なお、各フェーズにおける対策に必要となる資器材等については、事前に準備計画を策定し、それを実行して準備体制を整えておくことが重要である。本行動計画は、国における新型インフルエンザ対策の行動計画であり、したがって、都道府県が新型インフルエンザ対策を行う際は、国の行動計画も踏まえ、地域の実情に応じて、必要な対策を行うことが重要である。 本行動計画は国としての対策の具体的方針を示すものであり、各種ガイドラインやマニュアル等を基に具体的な対応を取っていくものとする。 なお、新型インフルエンザのパンデミックは必ずしも完全に予測されたように展開するものではないことが想定されることから、常に行動計画やガイドライン、マニュアル等を見直し、必要に応じて修正を行っていくこととする。 |
|
|
新型インフルエンザ対策を推進するに当たり、関係機関等の役割を踏まえた政府の取組を以下に示す。
|
|
|
|
新型インフルエンザへの対策は、その発生状況等に応じてとるべき対応が異なることから、あらかじめ状況を想定し、各状況において迅速かつ的確な対応ができるよう、平時より対応方針を定めておく必要がある。
上述の「WHO Global Influenza Preparedness Plan(WHO世界インフルエンザ事前対策計画)」においては、パンデミックが起こる前からパンデミックがピークを迎えるまでを状況に応じて6つのフェーズに分類して、それぞれの対応等を規定している。そこで、我が国においても、このWHOの定義に準じて6つのフェーズに分類し、さらにフェーズごとに国内で新型インフルエンザが発生していない場合(国内非発生)と国内で新型インフルエンザが発生した場合(国内発生)に細分化して、我が国のパンデミック行動計画を定めることとした。 我が国の段階の決定については、WHOが宣言(実施)するフェーズの引き上げ、及び引き下げに連動させて新型インフルエンザ対策推進本部長が決定し、具体的対応については、我が国の各段階に基づく行動計画を実施することとする。なお、2005年(平成17年)11月14日現在は、WHOによればフェーズ3とされており、我が国の状況はWHOフェーズ3の国内非発生の段階となる。従って、当面の対応は、本行動計画における「フェーズ3A」(フェーズ3の国内非発生)以降の段階について取っていくこととなる。
|
|
|
我が国における行動計画は、その目標と活動を、WHOの示した加盟各国の包括的目標を参考に、「計画と連携」「サーベイランス」「予防と封じ込め」「医療」「情報提供・共有」の5分野に分けて立案している。各分野に含まれる内容を以下に示す。
|