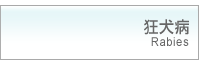
狂犬病について
健感発第1116003号
平成18年11月16日
各
- 都道府県
- 政令市
- 特別区
社団法人 日本医師会 感染症危機管理対策室長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長
狂犬病の流行地域より帰国し、当該疾病への感染が疑われる患者の診療等に関する周知の徹底について
今般、別添のとおり、フィリピンからの帰国者で狂犬病の輸入感染症例が確認されました。
我が国においては昭和33年以降、動物における狂犬病の発生は認められていませんが、世界各地ではいまだ狂犬病の流行が続いていることを踏まえ、狂犬病発生地域における滞在期間中に動物に咬まれるなど、狂犬病に感染したおそれのある者等について、別紙の対応要領に基づく適切な対応が講じられるよう、医療機関等の関係者に対する周知徹底を要請します。
※ 別添としてプレスリリース(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/11/h1116-2.htmlにリンク)を添付。
(別紙)
狂犬病の発生地域において感染動物又は感染が疑われる動物による咬傷を受け帰国した者が医療機関に受診した場合の対応要領
1 狂犬病の発生がない地域について
平成18年11月16日現在、厚生労働省が狂犬病の発生していない地域として指定しているのは以下の地域である。
台湾、オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー、ハワイ諸島、アイスランド、アイルランド、英国、スウェーデン、ノルウェー
2 主な感染源動物
- (1)アジア及びアフリカ イヌ、ネコ
- (2)西欧諸国及び北米 キツネ、アライグマ、スカンク、コウモリ、ネコ、イヌ
- (3)中南米 イヌ、コウモリ、ネコ
3 上記1の地域以外の地域において動物に咬まれるなどにより受傷した者への発症予防措置について
- (1)現地医療機関において発症予防措置が講じられていない場合
受傷原因動物が狂犬病に感染していないことが確認されない場合は、可能な限り早期に発症予防措置として暴露後ワクチン接種プログラムを開始すること。- (1)ワクチンの種類;組織培養不活化狂犬病ワクチン
- (2)ワクチン接種プログラム
初回接種日を0として0、3、7、14、30、90日の6回接種
- (2)現地医療機関において発症予防措置が講じられている場合
現地において受けた発症予防措置の内容を十分聴取の上、暴露後ワクチン接種プログラムが完了していない場合には、国内ワクチンを用い引き続き措置すること。
4 患者等への対応について
- (1)病室内での患者の診察については、標準予防策(手袋、マスク等の装着)で十分であること。
- (2)患者の入院については、その症状等も考慮し、個室への入院が望ましいこと。
- (3)面会の制限は特に必要としないが、患者の唾液等の体液にはウイルスが排出されることから、直接の濃厚接触を避けること。
- (4)患者が発症する1週間前以降に患者の体液等に濃厚接触し、狂犬病ワクチン未接種の者については、暴露後ワクチン接種プログラムについて、十分説明の上実施する必要があること。
- (5)ウイルスはアルコールなど通常の消毒により失活すること。
- (6)致死性の経過をとることから、患者やその家族等への十分な精神的ケアが必要であること。
5 狂犬病流行地域への渡航者への事前対応について
渡航予定者より相談を受けた場合においては、渡航中むやみにイヌや野生動物に接触しないことを周知するとともに、特に発生の多い地域への渡航者については、希望に応じてあらかじめワクチン接種を行うこと。
(参考)狂犬病の特徴
狂犬病は狂犬病ウイルスの感染によって引き起こされる致死的な動物由来感染症であり、以下のような特徴がある。
- (1)有効な治療法はないため、発症すれば100%死亡すること。
- (2)狂犬病患者の大半では潜伏期が1〜3ヶ月と長いこと。
- (3)ほとんど全ての哺乳動物が罹患すること。
- (4)地域によって感染源動物が異なること。
- (5)発病する前に狂犬病ウイルス感染の有無を知る手段がないこと。
現在でも狂犬病ウイルスに有効な薬剤はなく、狂犬病発生国では罹患動物に咬まれた場合の対応として、直ちに狂犬病ワクチン接種等を始めて、潜伏期間中に免疫を獲得させる狂犬病暴露後発症予防が行われている。