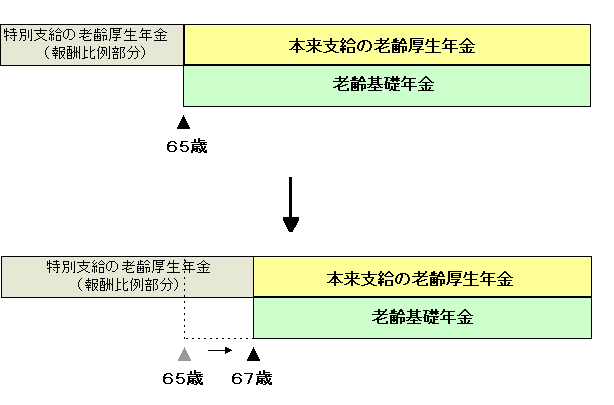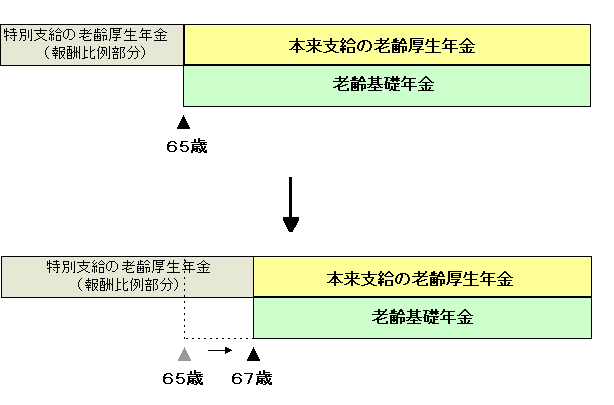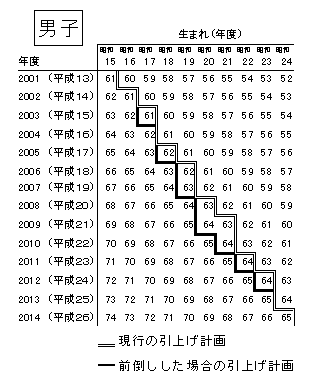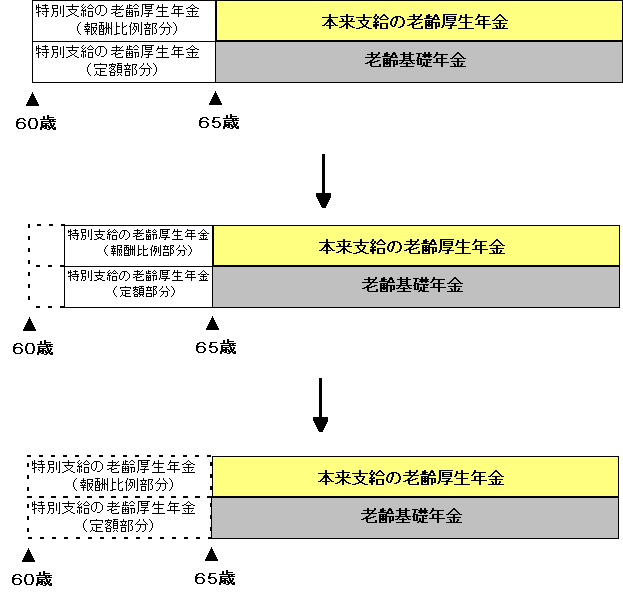2.給付の見直しの手法
(3) 支給開始年齢
1)老齢基礎年金・老齢厚生年金(本来支給)の支給開始年齢の65歳から67歳への引上げ
| 老齢基礎年金・老齢厚生年金(本来支給)の支給開始年齢を、65歳から、平成28(2016)年度以降平成31(2019)年度まで、3年ごとに1歳ずつ67歳に引き上げる。 |
【考え方】
- 支給開始年齢引上げを検討し始めた昭和55年時点と比較して、平均余命は65歳男子で2年、65歳女子で3年伸びており、また、国民年金が導入された昭和36年当時と比較すると65歳男子は5年、65歳女子は7年伸びている。これらを踏まえ、支給開始年齢を65歳から段階的に67歳に引き上げるものである。
【男子の場合】
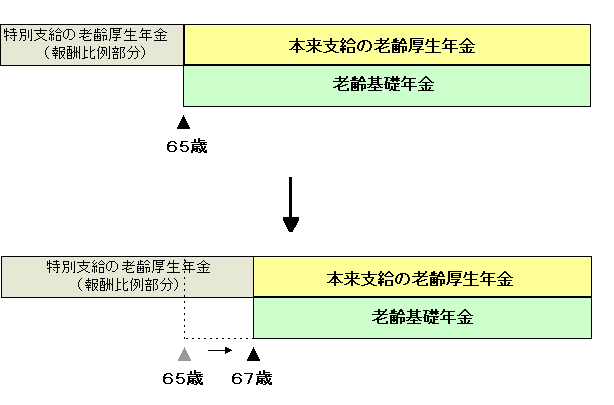
- (注)老齢基礎年金及び本来支給の老齢厚生年金は2年遅れの67歳時点で受給権が発生する。
【参考】
- 米国では1983年に支給開始年齢を67歳(2027年施行)に引き上げている。
【経過措置】
- 女子についても男子と同じ支給開始年齢引上げ計画とするが、所要の経過措置を講じる。
-
| |
【影響】 |
|
| |
厚生年金最終保険料率 |
|
| |
(対標準報酬) |
▲ 1 1/2 % |
|
| |
(対総報酬) |
▲ 1 % |
|
| |
国民年金最終保険料 |
|
| |
▲ 3千円 |
|
|
2)特別支給の老齢厚生年金定額部分の支給開始年齢引上げ計画の前倒し
○男子の場合
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、平成13(2001)年度以降平成25(2013)年度まで3年ごとに1歳ずつ65歳に引き上げることとなっているが、この計画を早め、平成13(2001)年度以降平成21(2009)年度まで、2年ごとに1歳ずつ引き上げる。
○女子の場合
|
【考え方】
- 今後、世代間の不均衡を縮小していく観点から、できるだけ早期に支給開始年齢を引き上げていくものである。
-
【現行の仕組み】
- 男子については、平成13(2001)年度から平成25(2013)年度、女子については平成18(2006)年度から平成30(2018)年度にかけて、60歳から65歳に、3年ごとに1歳ずつ引き上げることとなっている。
|
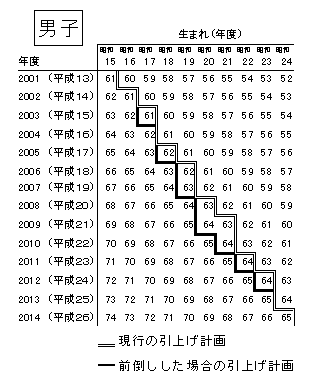 |
【変更後の仕組み】
- 男子については、平成13(2001)年度から平成21(2009)年度、女子については平成18(2006)年度から平成26(2014)年度にかけて、60歳から65歳に、2年ごとに1歳ずつ引き上げることとする。
|
【参考】
- ○ イタリアでは、年金給付費の対GDP比を抑制するため、92年に決めた2年ごとに1歳ずつ引き上げる計画を、94年に1.5年ごとに1歳ずつ引き上げることとした。
- ○ 欧米諸国の多くは、我が国の引上げ計画よりも早く65歳支給を本則とすることとなっている。
-
| |
【影響】 |
|
| |
厚生年金最終保険料率 |
|
| |
(対標準報酬) |
▲ 0.1% |
|
| |
(対総報酬) |
▲ 0.1% |
|
|
3)特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分(別個の給付)の支給開始年齢の引き上げ
| 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を定額部分の支給開始年齢と同様、平成13(2001)年度以降平成25(2013)年度まで、3年ごとに1歳ずつ65歳に引き上げる。
|
【考え方】
- 平均余命の伸長や少子高齢化が進行する中で高齢者の本格的な就労に資するため、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(別個の給付)の支給開始年齢を60歳から段階的に65歳に引き上げる。
【男子の場合】
- 特別支給の厚生年金の定額部分の引上げ計画にあわせて、特別支給の厚生年金の報酬比例部分(別個の給付)の支給開始年齢を引き上げる。
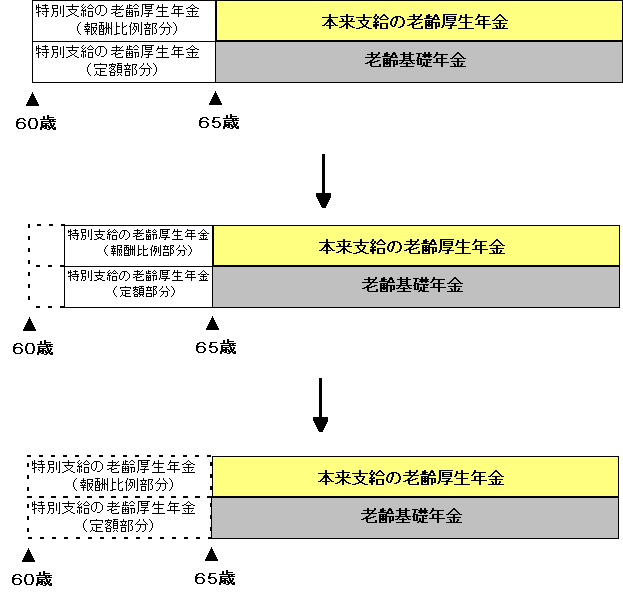
(注)現行の仕組みでは、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は60歳を維持し、定額部分の支給開始年齢のみ60歳から段階的に65歳に引き上げることとなっている。
【経過措置】
- 女子については、5年遅れの計画とする。
-
| |
【影響】 |
|
| |
厚生年金最終保険料率 |
|
| |
(対標準報酬) |
▲ 3 % |
|
| |
(対総報酬) |
▲ 2 1/2 % |
|
|