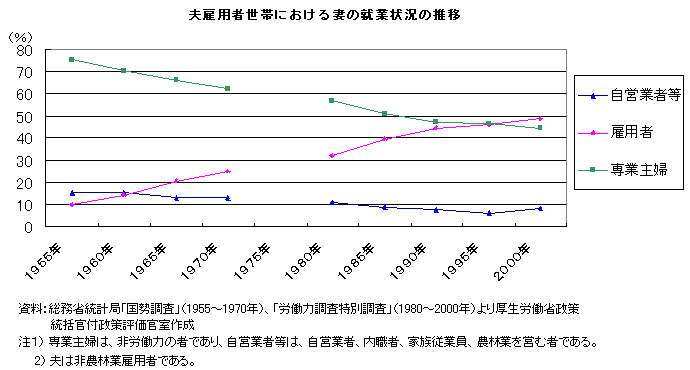
1 女性の働き方の変化
| ○ | 夫が雇用者である世帯の妻の就業状況をみると、1955年には妻が専業主婦の世帯が74.9%を占めていたが、その後女性の労働市場進出等が進み、1990年代には妻も雇用者である共働き世帯の割合が専業主婦世帯の割合を上回った。 |
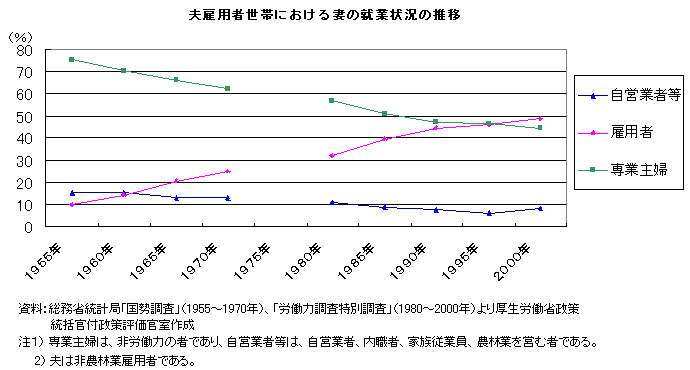
| ○ | 世代別に女性労働力率の変化をみると、団塊の世代を含む1946〜50年生まれの世代は、結婚後、専業主婦となる者が多く、25〜29歳の労働力率は42.7%と前後の世代と比較して最もM字型の底が深い。その後、晩婚化に伴う25〜29歳層の未婚者割合の増加や25〜29歳層の有配偶者の労働力率上昇等を背景に、1956〜60年生まれの世代以降、M字型カーブの底は30〜34歳層にシフトしている。 |
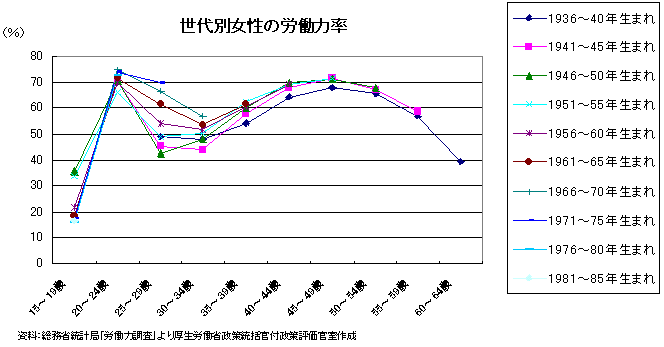
2 基幹的・専門的な労働力として働く女性の増加
| ○ | 就業意識の高まりや高学歴化を反映して、役職者につく女性や専門的・技術的職業に就く女性も増加し、平均勤続年数も長期化している。年齢階級別大卒者割合を世代別にみると、従来、年齢上昇とともに低下傾向にあったが、新しい世代では、25〜29歳から30歳代にかけて大卒者割合は同水準を保っており、高学歴女性が就業を継続する割合が高まっている。 |
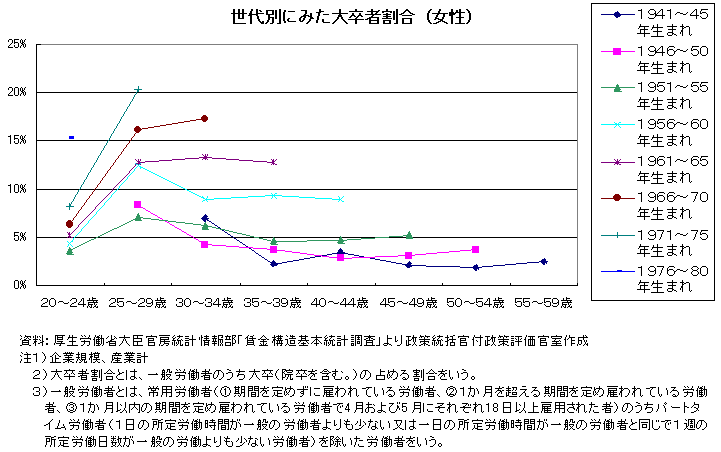
3 パートタイム労働者の動向
| ○ | 女性雇用者の伸びにはパートタイム労働者の増加が大きく寄与している。世代別に過去10年間の女性雇用者の増減をみると、団塊の世代を含む1947〜56年生まれでは雇用者全体の伸びのうち7割近くをパートタイム労働者が占め、1957〜66年生まれではパートタイム労働者が増加する一方、その他の雇用者数は減少しており、パートタイム労働者による就業が中高年女性の雇用を支えていることがわかる。 |
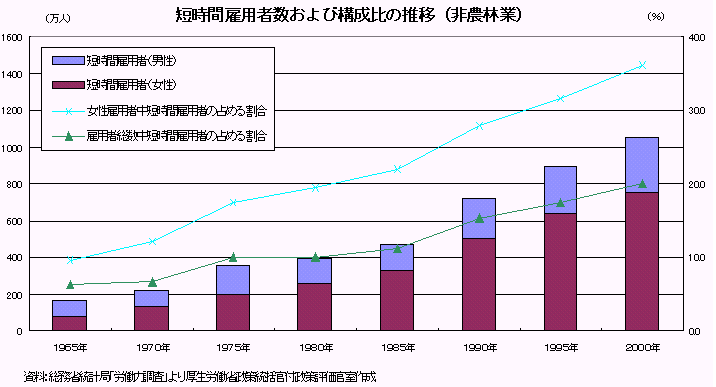
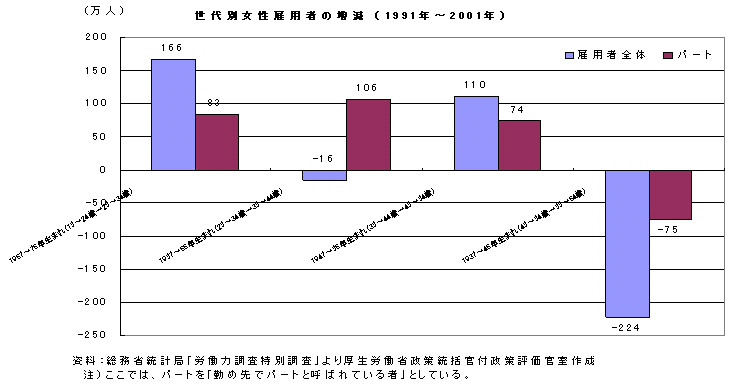
| ○ | 働く側からみても、「短時間のパート」については家庭生活との両立等の観点から自発的に選択される割合が高い。 |
| ○ | パートタイム労働者の増加に伴い、正社員と比べ責任の重さ等の違いはあるにしても、基幹的な役割を担うパートタイム労働者が増大している。 |
| ○ | パートタイム労働者全体の3割を占める「その他のパート」については、正社員として働ける会社がなかったため選択した者の割合が「短時間のパート」より高く、また、正社員を希望しながらやむなく短時間就労している者や会社の都合等で短時間就労している者の割合は、バブル崩壊以降、趨勢的に上昇している。 |
| ○ | 正社員の雇用機会が不足し、非自発的なパートタイム労働者が増加している背景には、正社員とパートタイム労働者との処遇の差によるコストの違いがあると考えられる。パートタイム労働者と正社員との賃金格差は拡大傾向にあり、勤続年数別賃金カーブにも顕著な差がみられる。 |
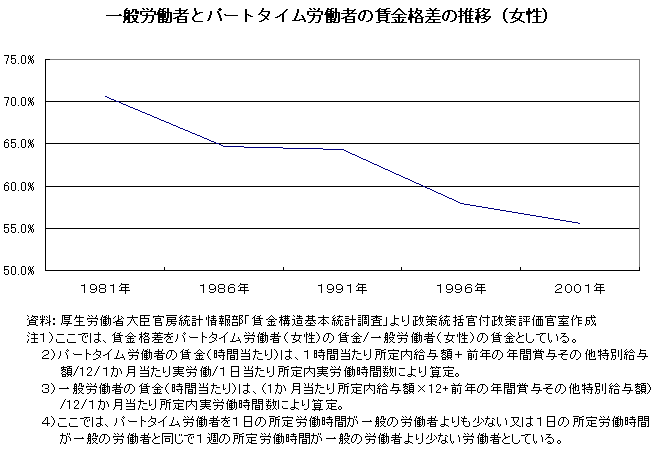
4 新しい働き方の模索
| ○ | 就業形態の多様化が進む中で、「基幹的な業務を担い、拘束性の高い」フルタイム正社員か「補助的なパート等の非正社員」かの二者択一ではなく、フルタイム正社員より一週間の所定労働時間は短いが、フルタイム正社員と同様の役割、責任を担い、同様の能力評価や賃金決定方式の適用を受ける短時間正社員制度が新しい働き方の一つとして注目されている。現在フルタイム正社員で働く女性で短時間正社員を好ましい働き方と考える者は3割弱を占めている。 |
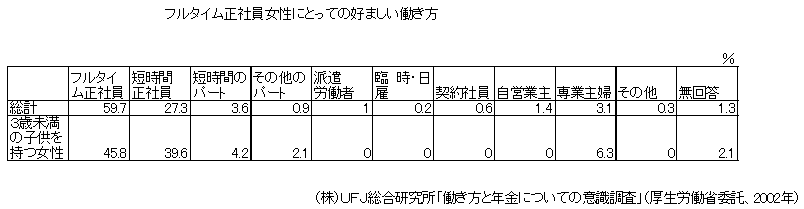
5 夫婦の働き方の変化
| ○ | 妻の就業状況および所得階級別分布を時系列でみると、夫の被扶養者として補助的に働く者と本格的に働く者との二極化の傾向がみられる。 |
| ○ | 夫の所得と妻の就業の関係をみると、おおむね夫の所得が高いほど妻の無業割合が高くなる傾向にあるが、以前と比べるとその関連性は弱くなっている。また、夫婦とも高所得である割合が上昇するなど配偶者の収入と夫婦単位の働き方の関係は多様化している。 |
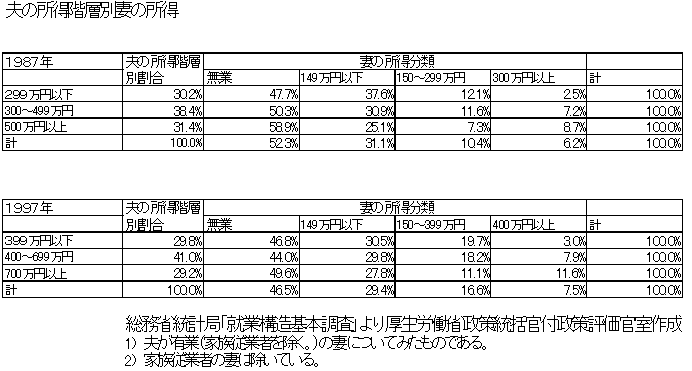
| ○ | 子どものいる夫婦の働き方の現状と理想を比較すると、実際は双方フルタイムの共働きや片働きをしている者にも、一方がフルタイムで他方がパートの共働きや双方パートの共働きへの志向がみられる。 |
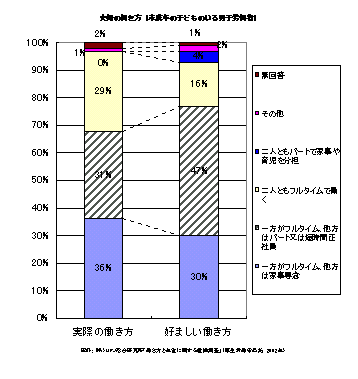 |
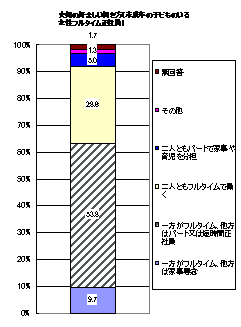 |
| ○ | 若い年齢層ほど夫が家事に参画する傾向がみられ、また、夫の家事・育児の遂行頻度はいずれの年齢層においても上昇傾向にある。さらに、若い男性ほど家庭や地域活動と仕事を両立させる生き方や家庭を重視する生き方を支持している。 |
6 今後の女性や夫婦の働き方
| ○ | 女性の就労理由や就労パターンがさまざまなものとなっている中、女性がその能力を十分発揮できるよう環境を整備することが重要な課題であるとともに、夫婦の働き方についてもさまざまなニーズや志向に応じて選択を行うことができる環境を整備することが必要である。 |