(1) 起床・就寝時間
ふだんの日は起床時間・就寝時間ともに早くなっている。
第4回調査(3歳6か月)以降の子どものふだんの日の起床・就寝時間をみると、起床時間は午前8時以降が減少、就寝時間は午後10時以降が減少し、起床時間・就寝時間ともに早くなっている。
第6回調査の日曜日の起床時間・土曜日の就寝時間をふだんの日と比較すると、起床時間・就寝時間ともに遅い時間帯の割合がふだんの日より多くなっている。(図4)
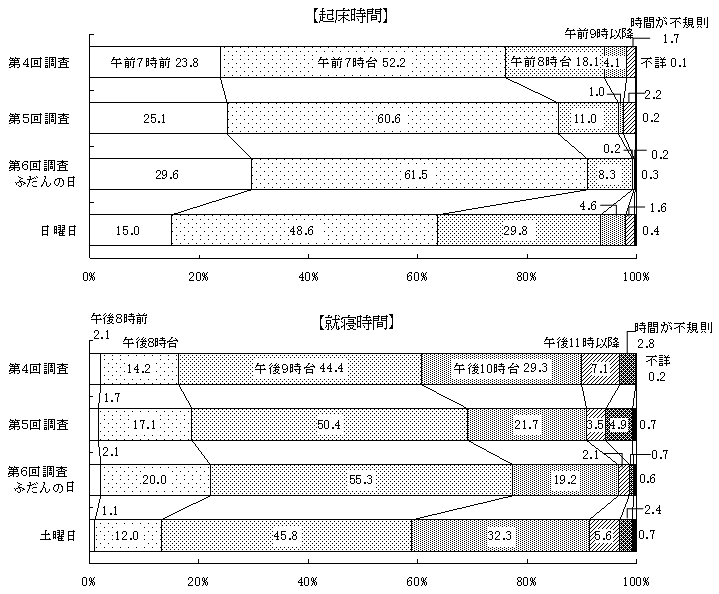
注:1)第4回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 36,691)を集計。 |
ふだんの日の子どもの就寝時間を父母の就寝時間別にみると、母の就寝時間が「午後9時前」では、子どもは「午後9時台」までに98.3%が就寝し、母が「午後9時台」では子どもは「午後9時台」までに97.5%が就寝している。
父の就寝時間が「午後9時前」では子どもは「午後9時台」までに87.3%が就寝し、父が「午後9時台」では子どもは「午後9時台」までに89.3%が就寝している。
父母の就寝時間が午後10時以降では、いずれの時間帯でも子どもは「午後9時台」が5割を超え、「午後10時台」が約2割と、同様の傾向となっている。(図5)
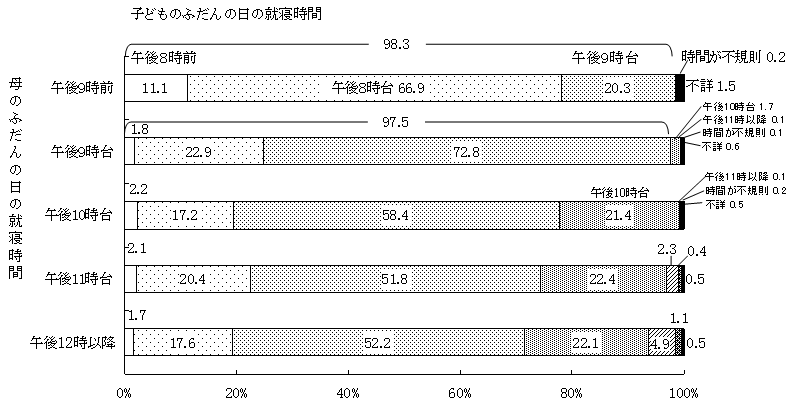
注:1)母と同居している、第6回調査の回答を得た者(総数 38,201)を集計。 |
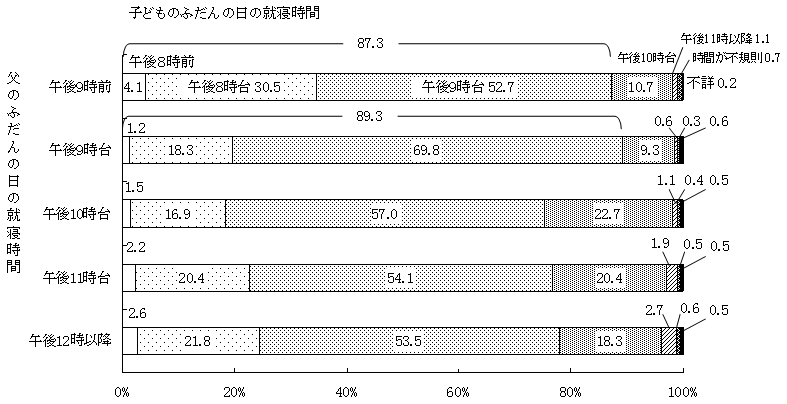
注:1)父と同居している、第6回調査の回答を得た者(総数 36,040)を集計。 |
(2) 遊びのようす
児童館や児童公園などで遊ぶ子は約8割。
「よく遊ぶ」が多い場所は、「自宅」が95.1%と最も多くなっている。次いで「児童館や児童公園などの公共の遊び場」で「よく遊ぶ」が15.1%となっており、「ときどき遊ぶ」(63.6%)と合計すると「遊ぶ」は78.7%となっている。
一方、「遊ばない」が多い場所は、「空き地や路地」が59.3%、「原っぱ、林、海岸などの自然の場所」が40.8%となっている。(表3)
「同い年の子」、「大人(親、祖父母等)」と遊ぶ子は約9割。
「よく遊ぶ」が多い相手は、「きょうだい」が73.1%と最も多くなっている。次いで「同い年の子」と「よく遊ぶ」が50.8%、「大人(親、祖父母等)」と「よく遊ぶ」が50.5%となっており、「ときどき遊ぶ」と合計すると「遊ぶ」は「同い年の子」88.9%、「大人(親、祖父母等)」93.1%となっている(表3)。
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気にかかることは「近所に友だちがいない」が3割超。
遊び場所で気にかかること(複数回答)は、「雨の日に(家以外で)遊べる場所がない」が51.0%と多くなっている(表4)。
友だちとの関係で気にかかること(複数回答)は、「近所に友だちがいない」が34.4%と多くなっており、「近所に友だちがいない」が気にかかる場合の遊び相手を総数と比較すると、「同い年の子」と「よく遊ぶ」割合が37.2%と低く、「ひとり」で「よく遊ぶ」割合が49.5%と高くなっている(表5、図6)。
|
表4 遊び場所で気にかかること(複数回答)
|
表5 友だちとの関係で気にかかること(複数回答)
|
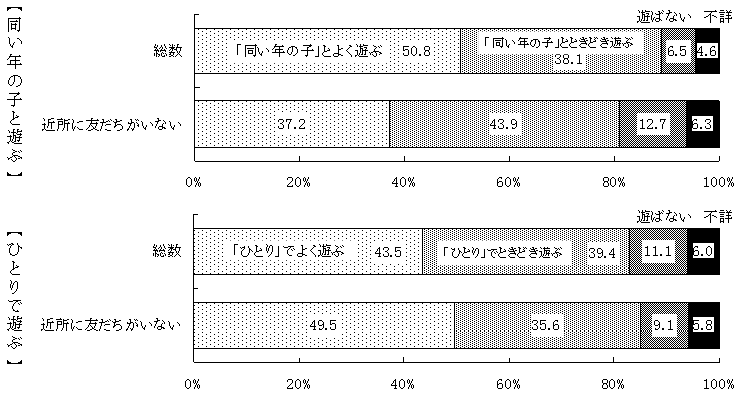
注:1)第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。 |
(3) 習い事
習い事をしている子は半数以上。
男児は「水泳」、女児は「音楽(ピアノなど)」が最も多い。
「習い事をしている」子は56.6%で、そのうち第5回調査で「習い事をしている」子は35.8 %となっている(図7)。
性別に習い事の種類(複数回答)をみると、男児では「水泳」が23.0%、女児では「音楽(ピアノなど)」が24.9%と最も多くなっている(図8)。
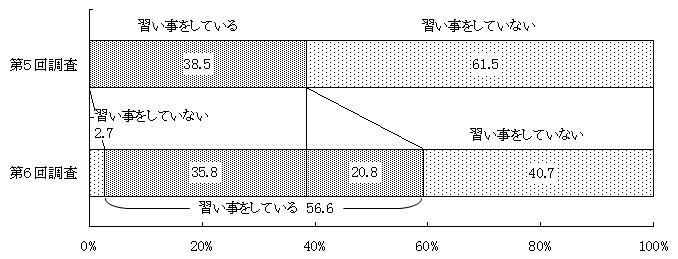
| 注:第5回調査と第6回調査の「習い事」の回答を得た者(総数 36,926)を集計。 |
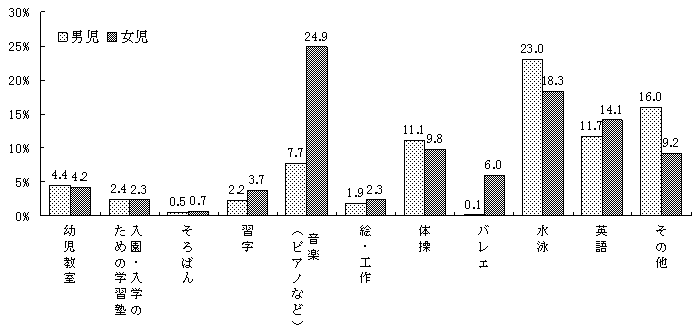
| 注:第6回調査の回答を得た者(総数 38,535(男児 20,013、女児 18,522))を集計。 |
(4) テレビ
テレビを見る時間は、「1〜2時間未満」が最も多くなった。
ふだんの日にテレビ(ビデオ、DVDを含む)を見る時間を第5回調査と比較すると2時間以上が減少し、「1〜2時間未満」が40.0%と最も多くなった(図9)。
ふだんの日の「1〜2時間未満」をみると、日曜日にテレビを見る時間の「1〜2時間未満」が44.9%と最も多く、次いで「2〜3時間未満」40.2%となっている。2時間以上テレビを見る割合は約5割となっている。(表6)
また、テレビの見方との関わり方をみると、「番組の内容によって見せないようにしている」については「している」が68.9%、「連続して長時間見せないようにしている」については「している」が72.2%、「見ている番組について子どもと話をする」は「よく話す」が75.6%となっている(表7)。
ふだんの日にテレビを見る時間を「番組の内容によって見せないようにしている−していない」別にみると、「している」場合は「2時間以上」の割合が40.2%と「していない」(49.5%)場合より低くなっている。
また「見ている番組について子どもとよく話す−あまり話さない」別にみると、「よく話す」場合と「あまり話さない」場合のテレビを見る時間は同様の傾向となっている。(図10)
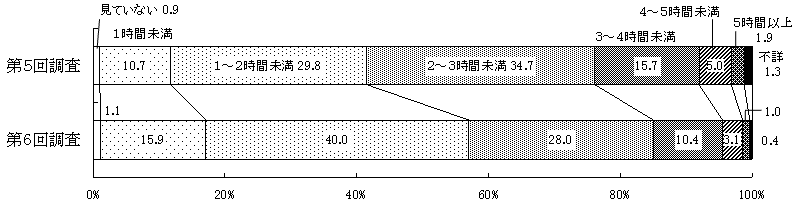
注:1)第5回調査と第6回調査の回答を得た者(総数 37,294)を集計。 |
| (単位:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:1)第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:第6回調査の回答を得た、「ふだんの日」、「日曜日」のいずれか又は両方テレビを見る者(総数 38,309)を集計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
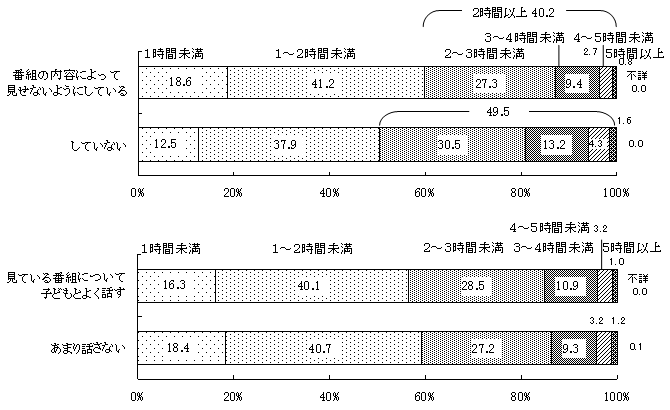
注:1)第6回調査の回答を得た、「ふだんの日」、「日曜日」のいずれか又は両方テレビを見る者(総数 38,309)を集計。 |
(5) コンピュータゲーム
コンピュータゲームをする子は半数以上。
テレビゲームや携帯型ゲームなどの「コンピュータゲームをする」子は50.6%で、第5回調査の「コンピュータゲームをする」子と比較すると、22.7ポイントの増加となっている(図11)。
ふだんの日と日曜日を比較すると、日曜日に「する」子は48.0%とふだんの日より多く、男児の場合は53.3%と半数を超えている。コンピュータゲームをする時間は、ふだんの日、日曜日ともに「1時間未満」が多くなっている。(表8)
また、ふだんの日と日曜日の組合せをみると、「ふだんの日」、「日曜日」ともにする子は37.0%、「日曜日」のみする子は10.8%、「ふだんの日」のみする子は2.0%となっている(表9)。
ふだんの日にテレビを見る時間別にコンピュータゲームをする子の割合をみると、テレビを見る時間が長い子ほど、コンピュータゲームを「する」割合が高くなっている(図12)。
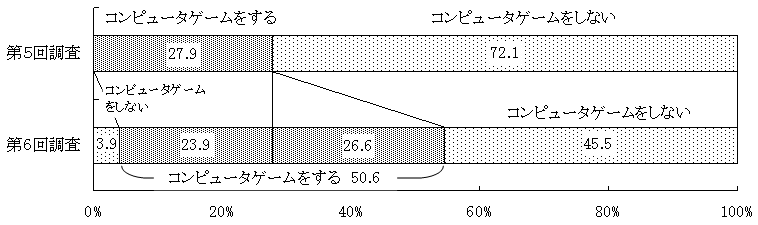
注:1)第5回調査と第6回調査の「コンピュータゲームをする時間」の回答を得た者(総数 36,844)を集計。 |
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:第6回調査の回答を得た者(総数 38,535(男児 20,013、女児 18,522))を集計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
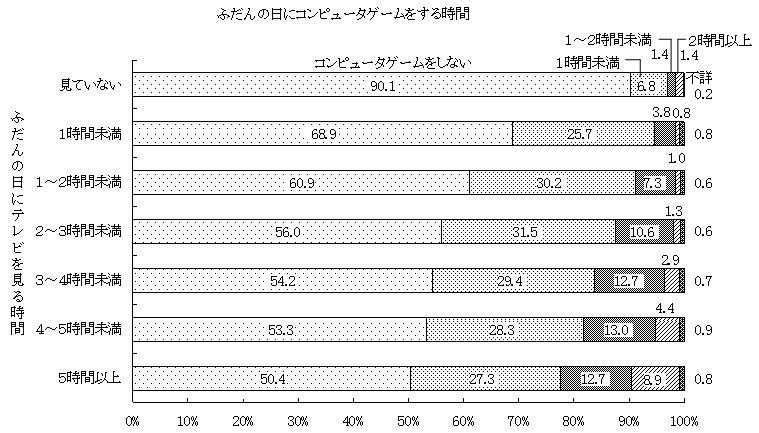
注:1)第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。
|
(6) 子どもの接し方
約7割の子が「自分の気持ちを言葉で伝える」などを「よくする」。
子どもが父母との接し方で「よくする」割合が高い接し方をみると、「自分の気持ちを言葉で伝える」(71.2%)、「一緒に遊びたがる」(69.9%)、「「なぜ」、「どうして」と疑問に思うことを質問する」(69.7%)、「親の体に触れたがる」(69.3%)、「その日の出来事などを親に話しをする」(67.3%)と約7割となっている。
一方、「抱っこやおんぶをせがむ」は37.8%、「友だちやきょうだいが持っている物をねだる」は31.0%となっている。(表10)
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。 |
(7) 子どもの行動
子どもの行動で「できる」と回答のあった割合は女児の方が高い。
子どもの行動で「できる」と回答のあった割合は、「集団で行動すること」が92.2%、「ひとつのことに集中すること」が85.8%、「落ち着いて話しを聞くこと」が80.9%となっている。
性別にみると、男児より女児の方が割合が高くなっている。(図13)
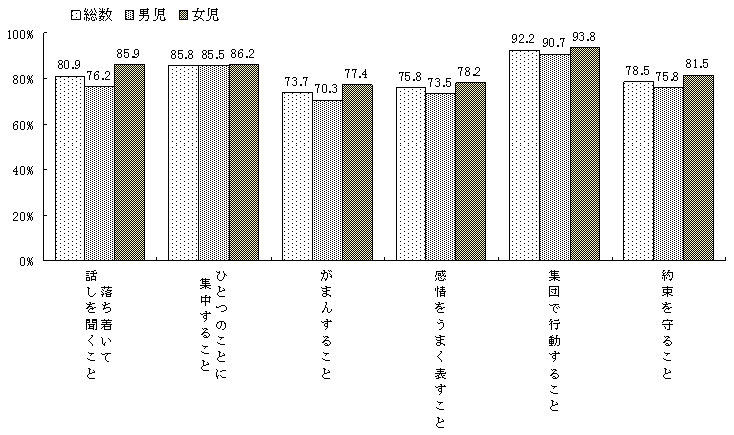
注:第6回調査の回答を得た者(総数 38,535(男児 20,013、女児 18,522))を集計。 |
(8) 手伝い
「食卓に食器を並べる、片づける」が最も多い。
手伝いの状況(複数回答)をみると、「食卓に食器を並べる、片づける」が74.1%と最も多くなっている。
性別にみると、男児は「食卓に食器を並べる、片づける」(69.2%)、「買い物の荷物を持つ」(47.1%)、「掃除」(35.7%)の割合が多く、女児は「食卓に食器を並べる、片づける」(79.4%)、「洗たく物をたたむ」(55.6%)、「買い物の荷物を持つ」(47.5%)の割合が多い。
また、弟妹がいる場合では「弟や妹の面倒をみる」が83.4%となっている。(図14)
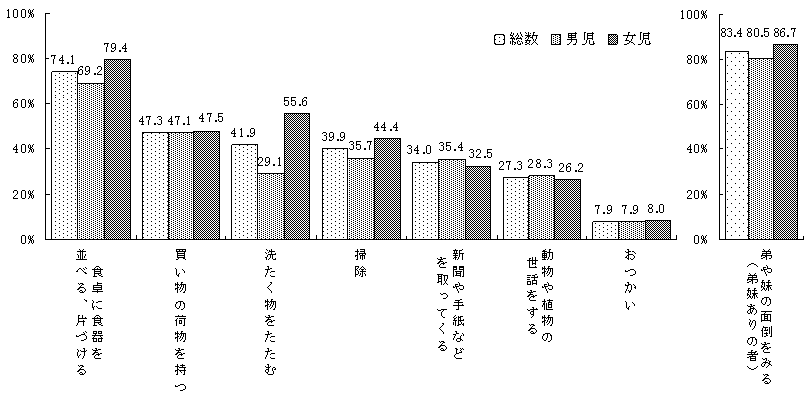
注:第6回調査で回答を得た者(総数 38,535(男児 20,013、女児 18,522))を集計。ただし、「弟や妹の面倒をみる」の数値は、 |
(9) 病気やけが
この1年間に「う歯〔むし歯〕」で病院や診療所にかかった子は36.2%
この1年間に病院や診療所にかかった主な病気やけが(複数回答)は「かぜ、咽頭炎、扁桃(腺)炎、気管支炎、肺炎」が79.2%と最も多く、次いで、「う歯〔むし歯〕」が36.2%、「胃腸炎など消化器系の病気、下痢、腹痛、便秘などの症状」が21.9%となっている。
第2回調査からの推移をみると、第2回調査以降「かぜ、咽頭炎、扁桃(腺)炎、気管支炎、肺炎」が約8割と最も多くなっている。
また、「う歯〔むし歯〕」は第3回調査の6.9%から、第6回調査の36.2%に大幅に上昇している。(図15)
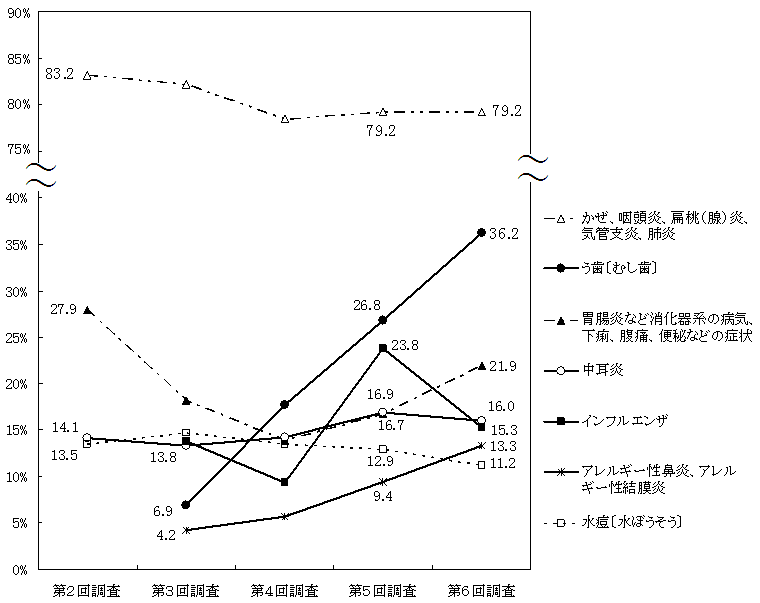
注:1)第2回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,783)を集計。 |