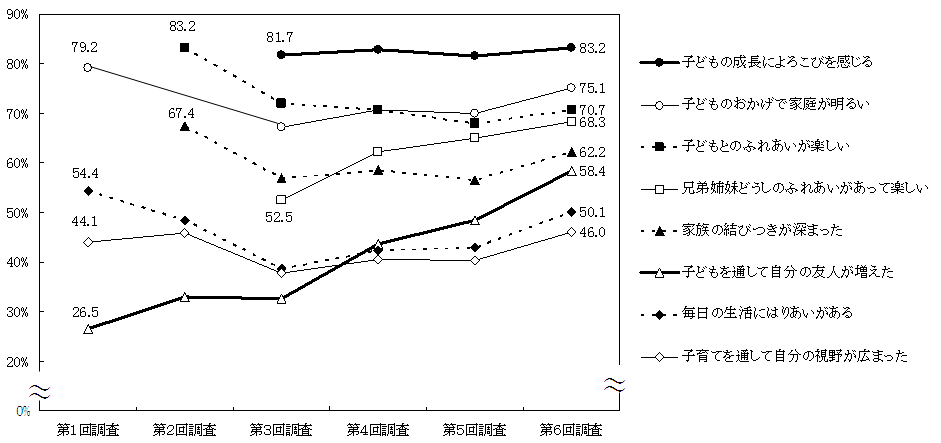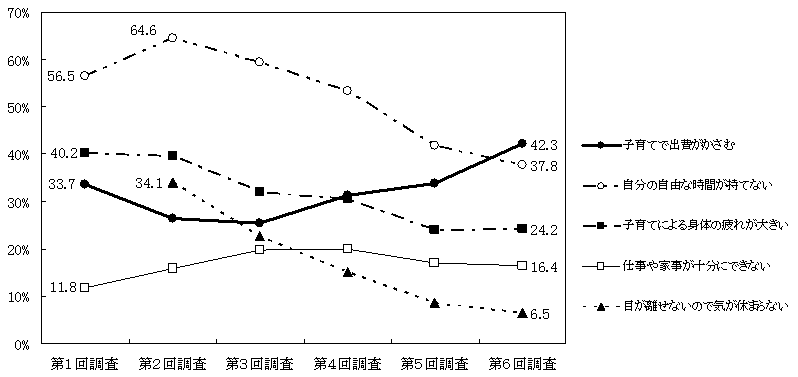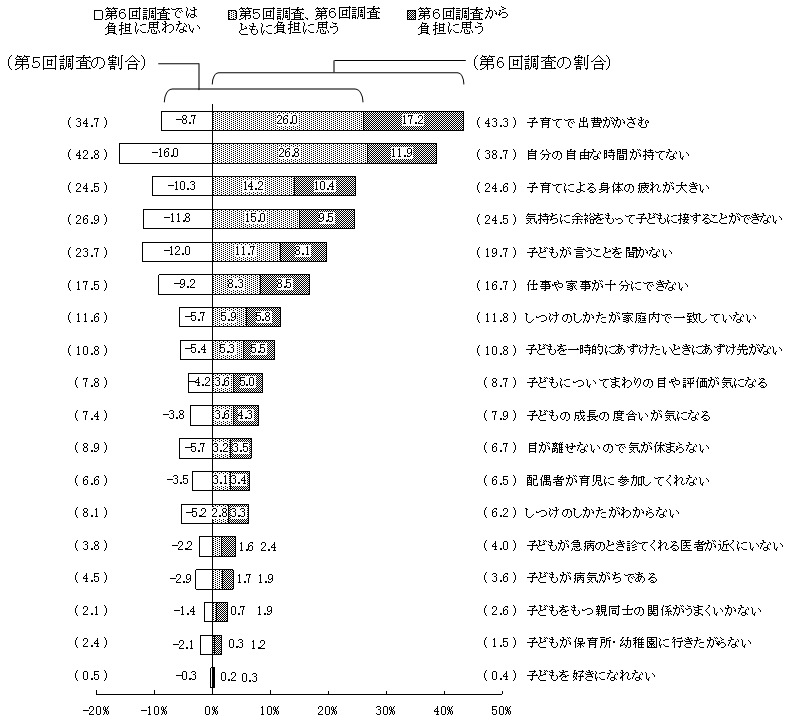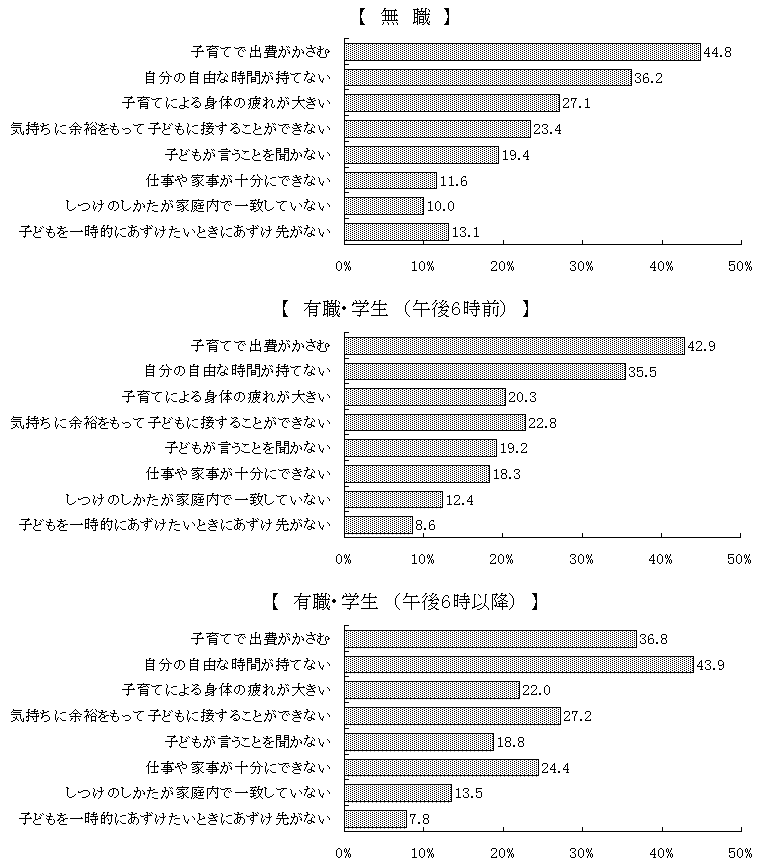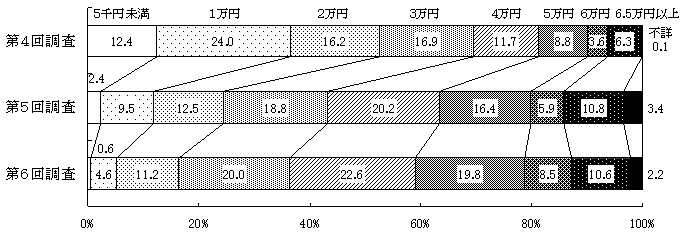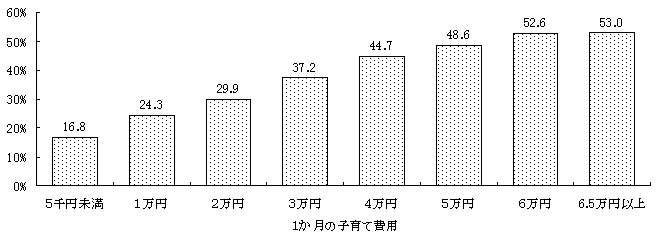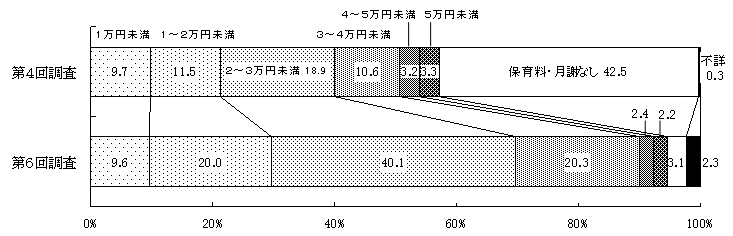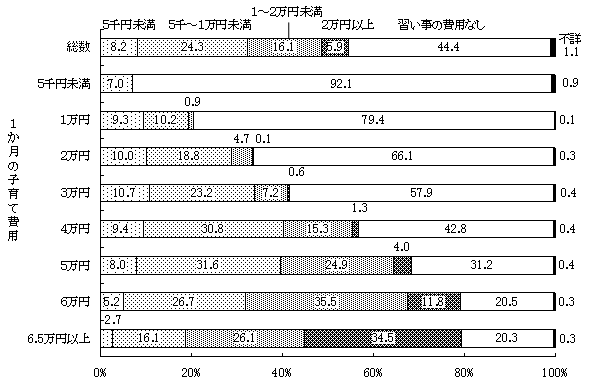3 子育ての意識
(1) 父母の子どもとの接し方
父は子どもと一緒に「トランプやおもちゃなどで遊ぶ」「体を動かす遊びをする」を「よくしている」割合が高い。
父母の子どもとの接し方で「よくしている」割合をみると、母は「子どもと一緒に食事をする」が89.0%と最も多く、次いで、「積極的に子どもに話しかける」が73.3%となっている。父は「積極的に子どもに話しかける」が51.0%と最も多く、次いで、「膝に乗せるなどスキンシップをはかる」が45.7%となっている。
父母を比較すると、「子どもと一緒にトランプやおもちゃなどで遊ぶ」、「子どもと一緒に体を動かす遊びをする」は、父が「よくしている」割合が高く、これ以外はすべて母が「よくしている」割合が高くなっている。
また、「膝に乗せるなどスキンシップをはかる」を「よくしている」割合を弟妹の有無別にみると、父は「弟妹あり」45.9%、「弟妹なし」45.5%とほぼ同じとなっているが、母は「弟妹あり」48.5%、「弟妹なし」69.9%と、「弟妹なし」の方が21.4ポイント高くなっている。(表11)
表11 父母の子どもとの接し方
(単位:%)
| |
総数 |
よくしている |
できるだけ
するように
している |
していない |
(再掲)よくしている |
| 弟妹あり |
弟妹なし |
母
の
子
ど
も
と
の
接
し
方 |
子どもと一緒にトランプやおもちゃなどで遊ぶ |
100.0 |
14.7 |
66.2 |
17.4 |
13.2 |
15.8 |
| 子どもと一緒に体を動かす遊びをする |
100.0 |
12.5 |
62.5 |
23.4 |
12.9 |
12.2 |
| 子どもと一緒にお風呂に入る |
100.0 |
71.8 |
18.3 |
8.6 |
75.4 |
69.2 |
| 本や絵本の読み聞かせをする |
100.0 |
34.3 |
51.5 |
12.8 |
37.0 |
32.3 |
| 積極的に子どもに話しかける |
100.0 |
73.3 |
24.0 |
1.2 |
72.1 |
74.2 |
| 子どもと一緒に食事をする |
100.0 |
89.0 |
9.2 |
0.5 |
89.6 |
88.7 |
| 膝に乗せるなどスキンシップをはかる |
100.0 |
60.9 |
33.8 |
3.9 |
48.5 |
69.9 |
| 子どもをほめる |
100.0 |
54.2 |
43.7 |
0.8 |
50.6 |
56.7 |
父
の
子
ど
も
と
の
接
し
方 |
子どもと一緒にトランプやおもちゃなどで遊ぶ |
100.0 |
18.1 |
55.0 |
24.8 |
18.1 |
18.2 |
| 子どもと一緒に体を動かす遊びをする |
100.0 |
28.1 |
52.9 |
17.1 |
30.1 |
26.5 |
| 子どもと一緒にお風呂に入る |
100.0 |
35.5 |
48.7 |
13.9 |
38.0 |
33.7 |
| 本や絵本の読み聞かせをする |
100.0 |
8.2 |
36.5 |
53.3 |
9.5 |
7.1 |
| 積極的に子どもに話しかける |
100.0 |
51.0 |
40.6 |
6.5 |
51.5 |
50.7 |
| 子どもと一緒に食事をする |
100.0 |
37.0 |
52.3 |
8.9 |
36.2 |
37.6 |
| 膝に乗せるなどスキンシップをはかる |
100.0 |
45.7 |
42.7 |
9.7 |
45.9 |
45.5 |
| 子どもをほめる |
100.0 |
42.2 |
49.4 |
6.5 |
42.5 |
42.0 |
注:1)第6回調査時に、「母の子どもとの接し方」については母と同居している者(母総数 38,201)、「父の子どもとの接し方」
については父と同居している者(父総数 36,040)を集計。
2)総数には子どもとの接し方「不詳」を含む。
3)「弟妹あり」、「弟妹なし」の総数に対する割合は以下のとおりである。
母と同居している場合 「弟妹あり」42.0%、「弟妹なし」57.5%
父と同居している場合 「弟妹あり」43.3%、「弟妹なし」56.2%
|
食事時に特に気をつけていること(複数回答)をみると、「遊びながら食べない」が76.4%と最も多く、次いで、「あいさつをする(「いただきます」「ごちそうさま」)」が72.5%となっている。一方、「テレビをつけない」は29.2%と最も少ない。
また、性別及びきょうだい構成別にみると、いずれも「遊びながら食べない」が最も多く、次いで「あいさつをする」が多くなっており、総数と同様の傾向となっている。(表12)
表12 性・きょうだい構成別にみた食事時に特に気をつけていること(複数回答)
(単位:%)
| |
総数 |
食事時に特に気をつけていること(複数回答) |
あいさつをす
る(「いただき
ます」「ごちそ
うさま」) |
食べている
ときの姿勢 |
お茶碗やは
しの持ち方 |
食べ物を粗
末にしない |
遊びながら
食べない |
残さず食べ
る |
食事中に席
を立たない |
テレビをつ
けない |
| 総数 |
( 100.0 ) |
100.0 |
72.5 |
65.0 |
50.0 |
64.8 |
76.4 |
54.8 |
58.1 |
29.2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 男児 |
( 51.9 ) |
100.0 |
72.2 |
65.0 |
49.5 |
65.1 |
77.1 |
55.9 |
59.1 |
29.6 |
| 女児 |
( 48.1 ) |
100.0 |
72.9 |
65.0 |
50.5 |
64.5 |
75.7 |
53.6 |
56.9 |
28.7 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ひとり |
( 16.3 ) |
100.0 |
75.0 |
62.2 |
48.5 |
61.0 |
75.3 |
46.2 |
54.3 |
23.9 |
| 弟妹のみ |
( 32.2 ) |
100.0 |
74.3 |
64.7 |
46.9 |
67.9 |
78.8 |
57.3 |
60.8 |
33.6 |
| 兄姉のみ |
( 41.3 ) |
100.0 |
70.2 |
65.5 |
52.3 |
63.1 |
74.9 |
54.3 |
56.7 |
26.8 |
| 兄弟姉妹あり |
( 9.7 ) |
100.0 |
73.0 |
68.9 |
53.1 |
68.6 |
76.8 |
63.0 |
60.8 |
33.4 |
|
注:1)第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。
2)総数にはきょうだい構成の「不詳」を含む。
|
|
子どもを育てていてよかったと思うこと(複数回答)を第5回調査と比較すると、いずれの割合も高くなっている。「子どもの成長によろこびを感じる」は83.2%と第3回調査から引き続き最も高くなっている。
第1回調査からの変化をみると、「子どもを通して自分の友人が増えた」は、第1回調査の26.5%から、第6回調査の58.4%に大幅に上昇している。(図16)
図16 子どもを育てていてよかったと思うこと(複数回答)の変化
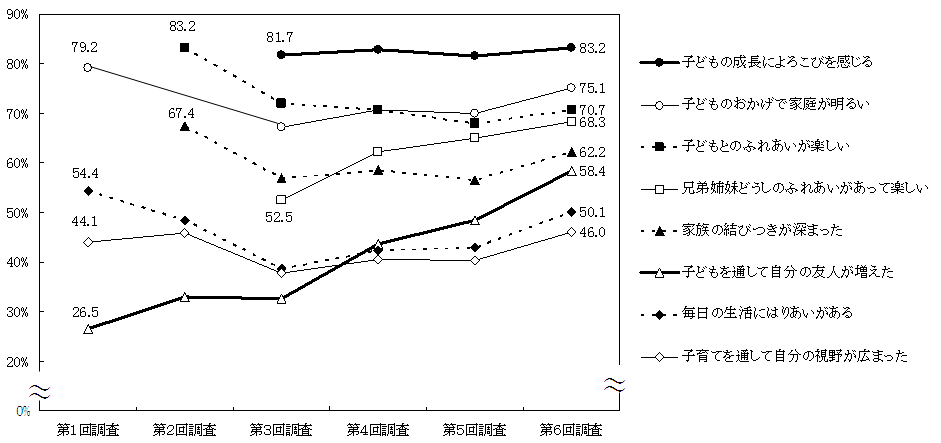
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,783)を集計。
2)「子どもの成長によろこびを感じる」、「兄弟姉妹どうしのふれあいがあって楽しい」は、第1回調査、第2回調査では調査していない。
3)「子どものおかげで家庭が明るい」は、第1回調査は「家庭が明るくなった」であり、第2回調査は調査していない。
4)「子どもとのふれあいが楽しい」、「家庭の結びつきが深まった」は、第1回調査では調査していない。
5)「毎日の生活にはりあいがある」は、第1回調査は「生活にはりあいができた」、第2回調査は「毎日の生活にはりあいができた」である。
|
子どもを育てていて負担に思うことや悩み(複数回答)の変化をみると、「子育てで出費がかさむ」(42.3%)は大幅に増加して第1回調査以降初めて最も多くなり、次いで「自分の自由な時間が持てない」が37.8%となっている(図17、表13)。
図17 主な子どもを育てていて負担に思うことや悩み(複数回答)の変化
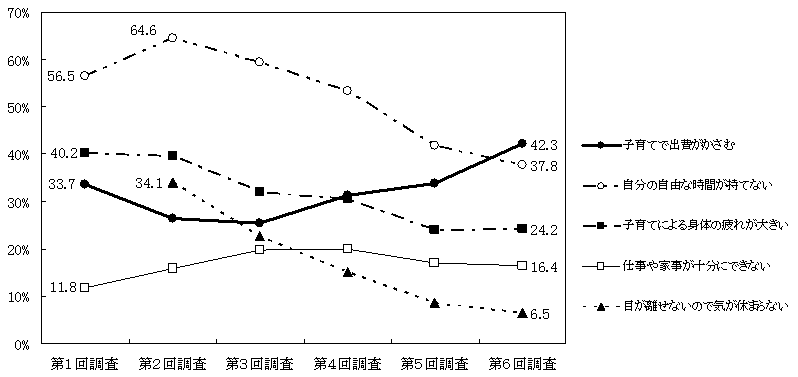
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,783)を集計。
2)「仕事や家事が十分にできない」は、第1回調査、第2回調査では「仕事が十分にできない」である。
3)「目が離せないので気が休まらない」は、第1回調査では調査していない。
|
表13 子どもを育てていて負担に思うことや悩み(複数回答)の変化
(単位:%)
| |
第1回調査 |
第2回調査 |
第3回調査 |
第4回調査 |
第5回調査 |
第6回調査 |
| 総数 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 子育てで出費がかさむ |
33.7 |
26.4 |
25.4 |
31.2 |
33.8 |
42.3 |
| 自分の自由な時間が持てない |
56.5 |
64.6 |
59.4 |
53.4 |
41.8 |
37.8 |
| 子育てによる身体の疲れが大きい |
40.2 |
39.7 |
32.1 |
30.5 |
24.0 |
24.2 |
| 気持ちに余裕をもって子どもに接することができない |
・ |
・ |
・ |
23.0 |
26.2 |
23.9 |
| 子どもが言うことを聞かない |
・ |
・ |
21.9 |
27.5 |
23.0 |
19.3 |
| 仕事や家事が十分にできない |
11.8 |
15.8 |
19.8 |
19.9 |
17.0 |
16.4 |
| しつけのしかたが家庭内で一致していない |
・ |
・ |
9.2 |
11.7 |
11.2 |
11.5 |
| 子どもを一時的にあずけたいときにあずけ先がない |
・ |
・ |
12.0 |
11.1 |
10.5 |
10.6 |
| 子どもについてまわりの目や評価が気になる |
・ |
・ |
5.0 |
8.2 |
7.6 |
8.5 |
| 子どもの成長の度合いが気になる |
・ |
・ |
7.0 |
7.5 |
7.2 |
7.8 |
| 目が離せないので気が休まらない |
・ |
34.1 |
22.7 |
15.1 |
8.7 |
6.5 |
| 配偶者が育児に参加してくれない |
・ |
・ |
6.0 |
6.7 |
6.4 |
6.4 |
| しつけのしかたがわからない |
・ |
・ |
8.6 |
7.3 |
7.8 |
6.0 |
| 子どもが急病のとき診てくれる医者が近くにいない |
・ |
・ |
3.4 |
3.4 |
3.7 |
3.9 |
| 子どもが病気がちである |
3.3 |
6.3 |
4.0 |
3.8 |
4.4 |
3.5 |
| 子どもをもつ親同士の関係がうまくいかない |
・ |
・ |
1.2 |
1.6 |
2.1 |
2.6 |
| 子どもが保育所・幼稚園に行きたがらない |
・ |
・ |
・ |
2.5 |
2.4 |
1.5 |
| 子どもを好きになれない |
・ |
・ |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
| その他 |
6.0 |
3.9 |
3.0 |
3.4 |
3.4 |
3.5 |
| 負担に思うことや悩みは特にない |
19.7 |
12.2 |
13.0 |
12.1 |
15.5 |
15.6 |
| 不詳 |
0.5 |
2.1 |
0.7 |
0.9 |
2.1 |
1.8 |
|
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,783)を集計。
2)「仕事や家事が十分にできない」は、第1回調査、第2回調査では「仕事が十分にできない」である。
|
|
「子育てで出費がかさむ」を第5回調査からの変化でみると、「第6回調査から負担に思う」が17.2%となり、「第6回調査では負担に思わない」が8.7%となっている。
一方、第5回調査まで最も多かった「自分の自由な時間が持てない」は、「第6回調査では負担に思わない」が16.0%となり、「第6回調査から負担に思う」は11.9%となっている。
子どもが成長するにつれて、負担に思うことを思わなくなったり、悩みの種類が変化している。(図18)
図18 子どもを育てていて負担に思うことや悩み(複数回答)の第5回調査からの変化
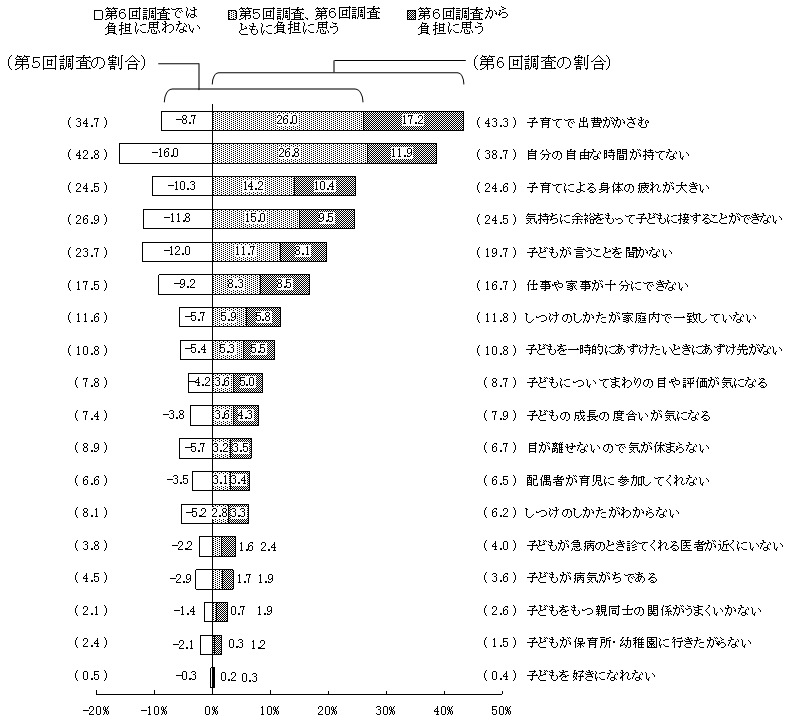
注:1)第5回調査と第6回調査の「子どもを育てていて負担に思うことや悩み」の回答を得た者(総数 35,886)を集計。
2)「第6回調査では負担に思わない」は、第5回調査で負担に思うと回答した者のうち、第6回調査では負担に思うと回答していない者である。
「第5回調査、第6回調査ともに負担に思う」は、第5回調査で負担に思うと回答した者のうち、第6回調査でも負担に思うと回答した者である。
「第6回調査から負担に思う」は、第5回調査では負担に思うと回答していない者のうち、第6回調査では負担に思うと回答した者である。
|
母の就業の有無・帰宅時間別に主な子どもを育てていて負担に思うことや悩みをみると、母が「無職」では、「子育てで出費がかさむ」が44.8%と最も多く、次いで「自分の自由な時間が持てない」(36.2%)、「子育てによる身体の疲れが大きい」(27.1%)となっている。
有職・学生の帰宅時間が「午後6時前」では、「子育てで出費がかさむ」が42.9%と最も多く、次いで「自分の自由な時間が持てない」(35.5%)、「気持ちに余裕をもって子どもに接することができない」(22.8%)となっている。
また、帰宅時間が「午後6時以降」については、「自分の自由な時間が持てない」が43.9%と最も多く、「子育てで出費がかさむ」(36.8%)に続き、「気持ちに余裕をもって子どもに接することができない」(27.2%)が多くなっており、母の就業の有無や帰宅時間により、負担に思うことや悩みに差がでている。(図19)
図19 母の就業の有無・帰宅時間別にみた主な子どもを育てていて
負担に思うことや悩み(複数回答)
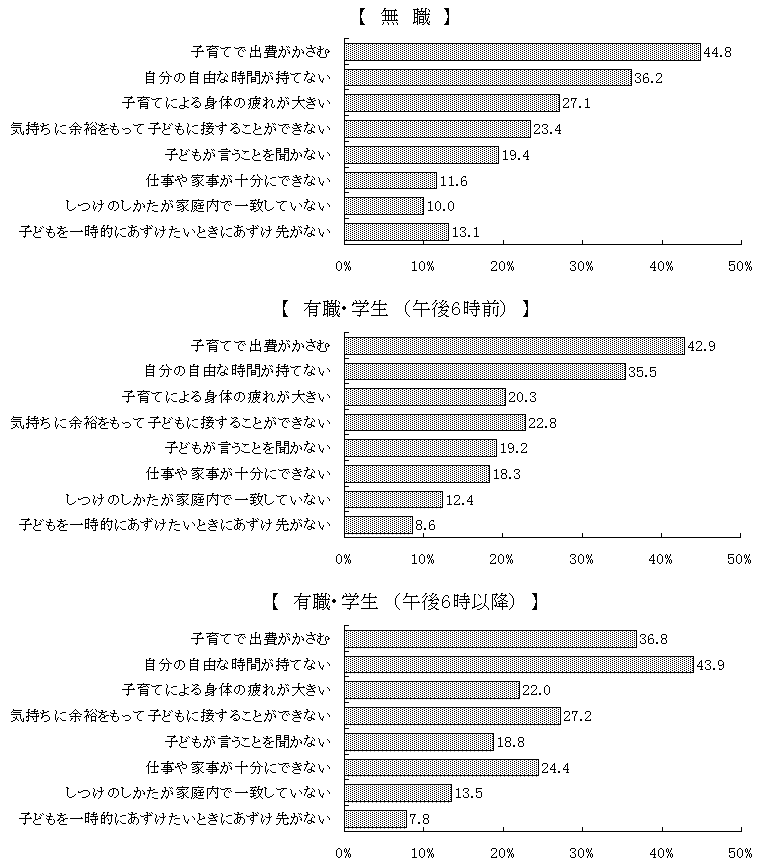
注:1)母と同居している、第6回調査の回答を得た者(総数 38,201)を集計。
2)「無職」には「学生」を含まない。
3)母の帰宅時間の区分及び総数に対する割合、母と同居している場合の回答者の総数に対する割合は以下のとおりである。
| 母の帰宅時間 |
「無職」46.7%
「有職・学生(午後6時前)」(午前6時〜午後6時前) 28.1%
「有職・学生(午後6時以降)」(午後6時〜午前6時前) 19.7% |
| 回答者 |
「母のみ」92.6%、「父のみ」5.7%、「父母のみ」、1.0%
「その他の組み合わせ」0.3%、「不詳」0.4% |
|
1か月の子育て費用をみると、「4万円」が22.6%、「3万円」が20.0%、「5万円」が19.8%となっている。
第4回調査からの変化をみると、「2万円」以下の割合が減少して、「3万円」以上の割合が増加している。(図20)
また、第6回調査の1か月の子育て費用別に子どもを育てていて負担に思うことや悩みで「子育てで出費がかさむ」と回答のあった者の割合をみると、「6万円」(52.6%)、「6.5万円以上」(53.0%)と、金額が高くなるほど割合が高くなっている(図21)。
保育所や幼稚園などの1か月の保育料・月謝をみると、「2〜3万円未満」が40.1%と最も多く、第4回調査と比較すると、約4割であった「保育料・月謝なし」が第6回調査では3.1%に減少した(図22)。
1か月の習い事の費用をみると「5千〜1万円未満」が24.3%と最も多く、「1〜2万円未満」が16.1%となっている。これを1か月の子育て費用の金額別にみると、子育て費用が高くなるほど習い事の費用が高くなる傾向がある。(図23)
図20 1か月の子育て費用の変化
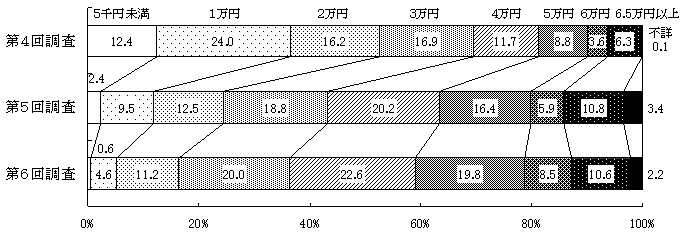
注:1)第4回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 36,691)を集計。
2)1か月間の子育て費用は、万円単位に四捨五入した金額を調査しており、区分は以下のとおりである。
| 「5千円未満」 |
5,000円未満 |
「4万円」 |
35,000〜44,999円 |
| 「1万円」 |
5,000〜14,999円 |
「5万円」 |
45,000〜54,999円 |
| 「2万円」 |
15,000〜24,999円 |
「6万円」 |
55,000〜64,999円 |
| 「3万円」 |
25,000〜34,999円 |
「6.5万円以上」 |
65,000円以上 |
|
図21 1か月の子育て費用別にみた子どもを育てていて負担に思うことや悩みの
「子育てで出費がかさむ」に回答ありの割合
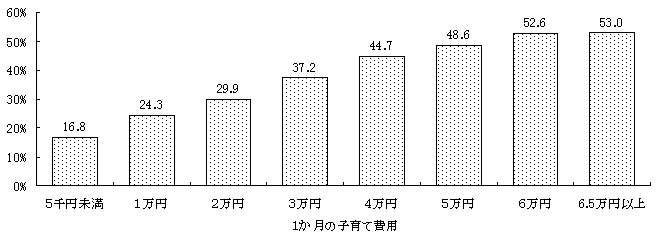
注:1)第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。
2)1か月間の子育て費用は、万円単位に四捨五入した金額を調整しており、区分及び総数に対する割合は以下
のとおりである。
| 「5千円未満」 |
( 5,000円未満) |
0.6% |
「4万円」 |
(35,000〜44,999円) |
22.5% |
| 「1万円」 |
( 5,000〜14,999円) |
4.7% |
「5万円」 |
(45,000〜54,999円) |
19.7% |
| 「2万円」 |
(15,000〜24,999円) |
11.3% |
「6万円」 |
(55,000〜64,999円) |
8.5% |
| 「3万円」 |
(25,000〜34,999円) |
20.0% |
「6.5万円以上」 |
(65,000円以上) |
10.5% |
|
図22 保育所や幼稚園などの1か月の保育料・月謝
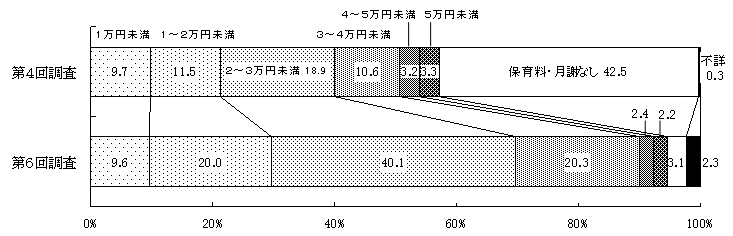
注:1)第4回調査と第6回調査の回答を得た者(総数 37,932)を集計。
2)第5回調査は保育所や幼稚園などの1か月の保育料・月謝は調査していない。
|
図23 1か月の習い事の費用
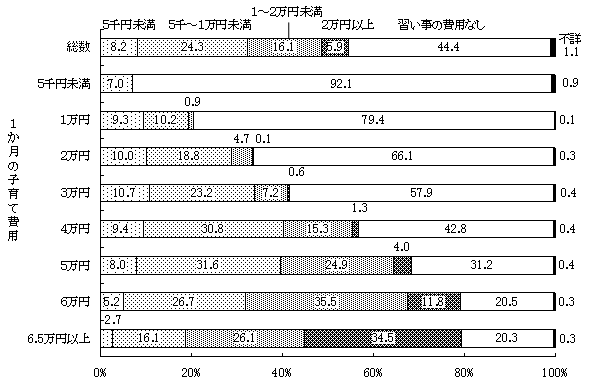
注:1)第6回調査の回答を得た者(総数 38,535)を集計。
2)総数には1か月の子育て費用「不詳」を含む。
3)1か月間の子育て費用は、万円単位に四捨五入した金額を調査しており、区分及び
総数に対する割合は以下のとおりである。
| 「5千円未満」 |
( 5,000円未満) |
0.6% |
| 「1万円」 |
( 5,000〜14,999円) |
4.7% |
| 「2万円」 |
(15,000〜24,999円) |
11.3% |
| 「3万円」 |
(25,000〜34,999円) |
20.0% |
| 「4万円」 |
(35,000〜44,999円) |
22.5% |
| 「5万円」 |
(45,000〜54,999円) |
19.7% |
| 「6万円」 |
(55,000〜64,999円) |
8.5% |
| 「6.5万円以上」 |
(65,000円以上) |
10.5% |
|