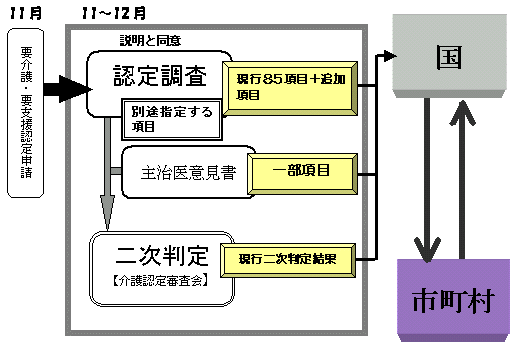
1 経緯
| 平成12年8月 | 要介護認定調査検討会設置 |
| 平成13年2〜3月 | 高齢者介護実態調査(施設調査)実施 |
| 平成13年6月 | 高齢者介護実態調査(在宅調査)実施 |
| 平成13年11〜12月(予定) | 調査実施 |
2 方法
1)対象者
2)対象市町村
3)調査時期
4)調査内容
(2)主治医意見書
要介護認定等申請内容と同じ
(3)介護認定審査会
介護認定審査会における二次判定と同じ
6)報告方法
3 スケジュール
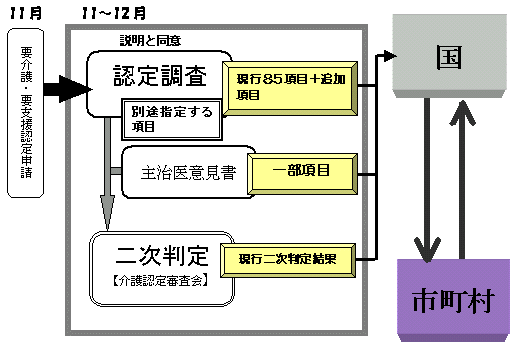
4 その他
標記については、昨年8月に「要介護認定二次判定変更事例集」を示したところであるが、その後の更新認定の増加等の状況を踏まえ、今般、全国の有識者の御協力をいただき、再度標記事例集を作成することとした。
現行の要介護認定又は要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)では、心身の状態に関する調査項目や主治医意見書の記載内容から、介護の手間を定量的に評価した上で審査判定を行うこととしているが、心身の状態の一次判定に係る膨大な組み合わせの中から、要介護認定等推計時間を統計的に推計するという制約上、事例によっては一次判定が必ずしも実際の介護の手間と一致しない場合もある。
このため二次判定においては、要介護認定等基準時間と実際の介護の手間が一致しない事例について、適正な要介護認定等を行う必要がある。ただしこの場合においても、介護認定審査会では、状態像の例の活用などにより、一次判定並びに特記事項及び主治医意見書の記載内容から、どの程度の要介護度等に相当する状態にあるかについて、客観的に審査判定を行なわなければならない。
しかしながら、実際の介護認定審査会では、審査判定が困難な事例の要介護認定等を行わなければならないこともある。このため、本事例集では、23例の事例毎に介護認定審査会において要介護度を変更するに至るまでの検討の過程を含めてその要点をまとめ、整理を行うとともに、総論的に留意点を示した。
本事例集は、10月中に全市町村に配布する予定であるが、次ページ以降に、これら事例の中からの1例及び留意点を掲げることとする。
なお、前回の事例集と同様、本事例集は新たな状態像の例を提供するものや掲載事例の結果を形式的に当てはめることを求めるものではなく、介護認定審査会における検討や、審査会委員の研修等に際し、活用いただくために作成したものである。
各介護認定審査会においては、これまでに多くの事例を経験したことと思うが、今一度、本事例集を基に、要介護認定等の考え方や介護認定審査会の運営について御確認いただき、一層の要介護認定等の適正化・円滑化を図っていただきたい。
要介護認定等の実施に当たっては、既に「要介護認定等の実施について」(平成11年7月26日厚生省老人保健福祉局長通知 老発499号)等でお示ししているところであるが、改めて留意事項を以下の通りまとめた。
今後、介護認定審査会における審査判定のみならず、要介護認定等に携わる総ての者が、これらの点について留意し、より充実した要介護認定等に関する業務を推進していただきたい。
1 基本調査について
○ 特に、心身の状態の変動が大きい事例については、家族等の介護者への聞き取り等を行い、総合的に勘案した上で、判断されたい。
○ このため、調査の内容の確認が出来るよう、家族等に対して、日頃の介護の状況を記録することが望ましいことの伝達に努められたい。
○ また、痴呆性高齢者については、痴呆症状にとらわれるあまり、随伴する身体の状況等に関して、いわゆる「チェック漏れ」がないように、注意を払う必要がある。
○ さらに、委託調査については、以下の事項に留意されたい。
2 特記事項について
○ ただし、各項目に関する頻度等について具体的な記載が必要となる場合の他、自己の判断に十分自信がもてないときや、能力を勘案したとき等には、簡潔かつ明確に記述されたい。
3 一次判定の確定について
4 二次判定について
○ ただし、
○ よって、チェック項目数の多寡や、要介護認定等基準時間以外の数値を用いて一次判定の変更を行うことはできないが、個々の認定審査会委員が自ら審査事例を検討する際に、考え方を整理する上で個別の資料を用いることを妨げるものではない。
○ また、要介護認定は、介護の必要度を判断するものであり、医療的な重症度や障害の程度と必ずしも一致するわけではないことに十分に留意されたい。
5 介護認定審査会が付する意見について
○ 有効期間の延長・短縮については、申請者の状態が安定して継続すると判断できる場合には、有効期間の是非について検討されたい。なお、その後に何らかの事由により状態が変化しても、要介護状態区分の変更・取消により対応できる。
○ また、サービス種類の指定を行う場合は、指定されたサービス以外のサービスは利用できないことから、対象者の状況を具体的に検討の上、種類を指定する必要があるが、要介護状態の軽減又は悪化を防止するため、特に療養上必要がある場合は、複数のサービスの組み合わせが可能であることも踏まえての検討が求められる。
6 状態像の例について
○ 状態像の例との比較検討の際には、単に中間評価項目毎の得点やそれらを表示したレーダーチャートの形状のみではなく、特記事項や主治医意見書などにより総合的に判断するものであることに留意されたい。
(平成13年6月調査実施)
| 市町村数 | 3,247 |
○介護認定審査会に関すること
| 総数 | 1,152 | |
| 単独設置 | 681 | |
| 共同設置 | 471 | |
| 構成市町村数 | 2,545 | |
| 委託実施市町村数 | 21 | |
(2)介護認定審査会委員長の資格(平成13年5月1日現在)
| 人数 | 構成割合 | ||
| A | 医師 | 1,073 | 93.1% |
| B | 歯科医師 | 6 | 0.5% |
| C | 薬剤師 | 1 | 0.1% |
| D | 保健婦(士) | 2 | 0.2% |
| E | 助産婦 | 0 | 0.0% |
| F | 看護婦(士) | 2 | 0.2% |
| G | 准看護婦(士) | 0 | 0.0% |
| H | 理学療法士 | 3 | 0.3% |
| I | 作業療法士 | 0 | 0.0% |
| J | 社会福祉士 | 7 | 0.6% |
| K | 介護福祉士 | 0 | 0.0% |
| L | 視能訓練士 | 0 | 0.0% |
| M | 義肢装具士 | 0 | 0.0% |
| N | 歯科衛生士 | 0 | 0.0% |
| O | 言語聴覚士 | 0 | 0.0% |
| P | あん摩マッサージ指圧師 | 0 | 0.0% |
| Q | はり師 | 0 | 0.0% |
| R | きゅう師 | 0 | 0.0% |
| S | 柔道整復師 | 0 | 0.0% |
| T | 栄養士(管理栄養士を含む) | 0 | 0.0% |
| U | 精神保健福祉士 | 0 | 0.0% |
| V | その他 | 58 | 5.0% |
| 総計 | 1,152 | 100.0% | |
| (3)介護認定審査会委員数(平成13年5月1日現在) | 48,242人 |
|
6人 |
| (4)合議体数(平成13年5月1日現在) | 8,093 |
|
7 |
| (5)平成13年4月の合議体開催総回数 | 13,686回 |
|
1.7回 |
| (6)平成13年4月の合議体での審査総件数 | 407,800件 |
|
50.4件 |
|
29.8件 |
| 人数 | 構成割合 | ||
| A | 医師 | 18,864 | 39.0% |
| B | 歯科医師 | 5,188 | 10.7% |
| C | 薬剤師 | 3,020 | 6.2% |
| D | 保健婦(士) | 2,797 | 5.8% |
| E | 助産婦 | 50 | 0.1% |
| F | 看護婦(士) | 4,850 | 10.0% |
| G | 准看護婦(士) | 192 | 0.4% |
| H | 理学療法士 | 1,696 | 3.5% |
| I | 作業療法士 | 828 | 1.7% |
| J | 社会福祉士 | 1,954 | 4.0% |
| K | 介護福祉士 | 2,743 | 5.7% |
| L | 視能訓練士 | 1 | 0.0% |
| M | 義肢装具士 | 1 | 0.0% |
| N | 歯科衛生士 | 35 | 0.1% |
| O | 言語聴覚士 | 16 | 0.0% |
| P | あん摩マッサージ指圧師 | 18 | 0.0% |
| Q | はり師 | 22 | 0.0% |
| R | きゅう師 | 6 | 0.0% |
| S | 柔道整復師 | 111 | 0.2% |
| T | 栄養士(管理栄養士を含む) | 76 | 0.2% |
| U | 精神保健福祉士 | 129 | 0.3% |
| V | その他 | 5,776 | 11.9% |
| 総計 | 48,373 | 100.0% | |
○認定調査に関すること(平成13年4月)
| 総調査件数 | 418,802 | ||
| 委託事業者数 | 29,996 | ||
| 同件数 | 252,887 | ||
| うち 施設入所者調査件数 | 86,012 | ||
| 委託により調査を行う施設数 | 16,984 | ||
| 同件数 | 52,246 | ||
○申請者に対する調査内容等の開示に関すること
| 市町村数 | 構成割合 | ||
| 請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示 | 75 | 2.3% | |
| 請求があれば提供・開示(申請書不要) | 1,146 | 35.3% | |
| 請求があれば提供・開示(申請書必要) | 1,860 | 57.3% | |
| 非提供・非開示 | 159 | 4.9% | |
| 未実施 | 2 | 0.1% | |
| その他 | 5 | 0.2% | |
| 合計 | 3,247 | 100.0% | |
| ※その他: | 調査項目:請求があれば提供・開示(申請書必要)、特記事項:非提供・非開示 1 調査項目:請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示、特記事項:請求があれば提供・開示(申請書必要) 4 |
(2)一次判定結果
| 市町村数 | 構成割合 | |
| 請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示 | 61 | 1.9% |
| 請求があれば提供・開示(申請書不要) | 1,203 | 37.0% |
| 請求があれば提供・開示(申請書必要) | 1,582 | 48.7% |
| 非提供・非開示 | 398 | 12.3% |
| 未実施 | 3 | 0.1% |
| 合計 | 3,247 | 100.0% |
(3)二次判定変更理由
| 市町村数 | 構成割合 | |
| 請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示 | 76 | 2.3% |
| 請求があれば提供・開示(申請書不要) | 1,179 | 36.3% |
| 請求があれば提供・開示(申請書必要) | 1,452 | 44.7% |
| 非提供・非開示 | 537 | 16.5% |
| 未実施 | 3 | 0.1% |
| 合計 | 3,247 | 100.0% |
(4)主治医意見書
提供の前提として記載医師の提供同意について
| 市町村数 | 構成割合 | ||
| 提供・開示 | |||
| 同意が必要 | 2,754 | 84.8% | |
| 同意は不要 | 261 | 8.0% | |
| 非提供・非開示 | 230 | 7.1% | |
| 未実施 | 2 | 0.1% | |
| 合計 | 3,247 | 100.0% | |
| 市町村数 | 構成割合 | |
| 請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示 | 70 | 2.2% |
| 請求があれば提供・開示(申請書不要) | 1,045 | 32.2% |
| 請求があれば提供・開示(申請書必要) | 1,900 | 58.5% |
| 非提供・非開示 | 230 | 7.1% |
| 未実施 | 2 | 0.1% |
| 合計 | 3,247 | 100.0% |
○主治医意見書記載医師に対する情報提供に関すること
| 市町村数 | 構成割合 | ||
| いずれかの項目を提供・開示 | |||
| 同意が必要 | 2,898 | 89.3% | |
| 同意は不要 | 244 | 7.5% | |
| 全項目非提供・非開示 | 103 | 3.2% | |
| 全項目未実施 | 2 | 0.1% | |
| 合計 | 3,247 | 100.0% | |
(1)認定調査票(特記事項含)
| 市町村数 | 構成割合 | |
| 請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示 | 304 | 9.4% |
| 請求があれば提供・開示(申請書不要) | 1,152 | 35.5% |
| 請求があれば提供・開示(申請書必要) | 1,165 | 35.9% |
| 非提供・非開示 | 623 | 19.2% |
| 未実施 | 3 | 0.1% |
| 合計 | 3,247 | 100.0% |
(2)一次判定結果
| 市町村数 | 構成割合 | |
| 請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示 | 298 | 9.2% |
| 請求があれば提供・開示(申請書不要) | 1,158 | 35.7% |
| 請求があれば提供・開示(申請書必要) | 1,007 | 31.0% |
| 非提供・非開示 | 781 | 24.1% |
| 未実施 | 3 | 0.1% |
| 合計 | 3,247 | 100.0% |
(3)二次判定変更理由
| 市町村数 | 構成割合 | |
| 請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示 | 299 | 9.2% |
| 請求があれば提供・開示(申請書不要) | 1,142 | 35.2% |
| 請求があれば提供・開示(申請書必要) | 943 | 29.0% |
| 非提供・非開示 | 859 | 26.5% |
| 未実施 | 4 | 0.1% |
| 合計 | 3,247 | 100.0% |
(4)認定結果
| 市町村数 | 構成割合 | |
| 請求の有無にかかわらず基本的に提示・開示 | 420 | 12.9% |
| 請求があれば提供・開示(申請書不要) | 1,752 | 54.0% |
| 請求があれば提供・開示(申請書必要) | 953 | 29.4% |
| 非提供・非開示 | 120 | 3.7% |
| 未実施 | 2 | 0.1% |
| 合計 | 3,247 | 100.0% |