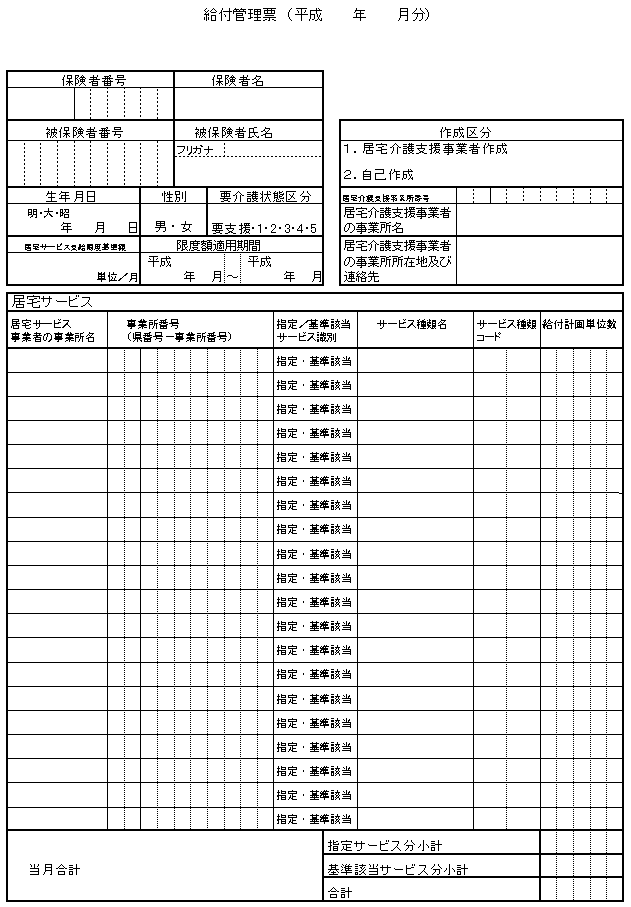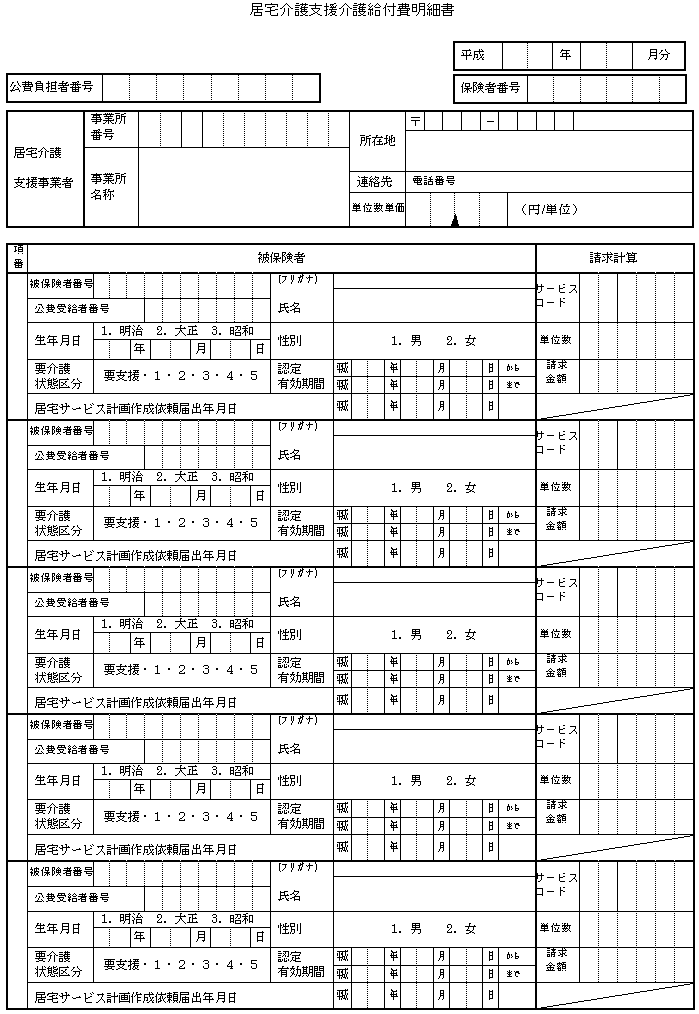
介護給付費請求書等の様式については、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)において規定されているところであるが、その記載要領等について、別紙のとおり定め、平成14年1月1日から適用することとしたので、御了知のうえ、その取扱いに遺憾のないよう関係者等に対し周知徹底を図られたい。
1 介護給付費請求書に関する事項(様式第一)
(1)サービス提供年月
請求対象となるサービスを提供した年月を和暦で、「年」「月」それぞれ右詰で記載すること。
(2)請求先
保険者名、公費負担者名等を記載すること。ただし、記載を省略して差し支えないこと。
(3)請求日
審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。
(4)請求事業所
(2)名称
指定等を受けた際に届け出た事業所名を記載すること。
(3)所在地
指定等を受けた際に届け出た事業所の所在地とその郵便番号を記載すること。
(4)連絡先
審査支払機関、保険者からの問い合わせ用の連絡先電話番号を記載すること。
(5)保険請求(サービス費用に係る部分)
保険請求の介護給付費明細書(生活保護の単独請求の場合を除く。)について居宅サービス・施設サービス及び居宅介護支援の二つの区分ごとに、以下に示す項目の集計を行って記載すること。合計欄には二つの区分の合計を記載すること。
(2)単位数・点数
保険給付対象の単位数及び点数の合計を記載すること。
(3)費用合計
介護給付費明細書の保険請求対象単位数(点数)に単位数(点数)あたり単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)の合計を記載すること(金額は保険請求額、公費請求額及び利用者負担の合計額)。
(4)保険請求額
介護給付費明細書の保険請求額の合計額を記載すること。
(5)公費請求額
介護給付費明細書の公費請求額の合計額を記載すること。
(6)利用者負担
介護給付費明細書の利用者負担額と公費分本人負担額を合計した額を記載すること。
(6)保険請求(食事提供費用に係る部分)
保険請求の介護給付費明細書(生活保護の単独請求の場合を除く。)について以下に示す項目の集計を行って記載すること。合計欄に同じ内容を記載すること。
(2)延べ日数
介護給付費明細書の食事提供延べ日数の合計を記載すること。
(3)金額
介護給付費明細書の食事提供費用を合計した額を記載すること(金額は標準負担額、公費請求額及び保険請求額の合計額)。
(4)標準負担額
介護給付費明細書の標準負担額(月額)を合計した額を記載すること。
(5)公費請求額
介護給付費明細書の食事提供費請求額の公費請求分を合計した額を記載すること。
(6)保険請求額
介護給付費明細書の食事提供費請求額の保険請求分を合計した額を記載すること。
(7)公費請求(サービス費用に係る部分)
保険請求の介護給付費明細書のうち、公費の請求に関わるものについて公費の法別に、以下に示す項目の集計を行って記載すること(生活保護の単独請求の場合は、居宅サービス・施設サービス及び居宅介護支援の二つの区分ごとに集計を行って記載すること。)。合計欄のうち斜線のない欄には全ての公費請求の介護給付費明細書に関する集計を記載すること。
(2)単位数・点数
介護給付費明細書の単位数及び点数(公費対象以外を含む。)の合計を記載すること。
(3)費用合計
介護給付費明細書の保険請求対象単位数(点数)に単位数(点数)あたり単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)の合計を記載すること。
特定診療費や特定治療については、単位数(点数)あたり10円を乗じた額の合計額を記載すること。
(4)公費請求額
介護給付費明細書の当該公費請求額の合計額を記載すること。
(8)公費請求(食事提供費用に係る部分)
保険請求の介護給付費明細書のうち、食事提供費用について公費の請求があるものについて公費の法別に、以下に示す項目の集計を行って記載すること。斜線のない合計欄には全ての公費請求の介護給付費明細書に関する集計を記載すること。
(2)延べ日数
介護給付費明細書の食事提供延べ日数の合計を記載すること。
(3)金額
介護給付費明細書の食事提供費用の合計欄を合計した額を記載すること(金額は標準負担額、公費請求額及び保険請求額の合計額)。
(4)標準負担額
介護給付費明細書の標準負担額(月額)を合計した額を記載すること。
(5)公費請求額
介護給付費明細書の食事提供費請求額の公費請求分を合計した額を記載すること。
(6)保険請求額
介護給付費明細書の食事提供費請求額の保険請求分を合計した額を記載すること。
2 介護給付費明細書記載に関する事項(様式第二から様式第十まで)
(1)共通事項
イ 1枚の介護給付費明細書の明細記入欄に請求明細が記入しきれない場合は、何枚中の何枚目であるかを所定の欄に記載し、複数の介護給付費明細書に分けて明細の記入を行うこと。この際、2枚目以降については、被保険者番号を除く被保険者欄、事業所番号を除く請求事業者欄の記載を省略して差し支えないこと。
また、請求額集計欄は1枚目にのみ記載するものとすること。
ウ 1人の被保険者について同一月分の、同一様式の介護給付費明細書を2件にわけ
て作成することはできないこと(イの場合及び公費併用請求で介護給付費明細書
が2枚以上にわたる場合を除く。)。
(2)サービス種類と介護給付費明細書様式の対応関係
| 区分 | サービス種類 | 明細書様式 | |
| 居宅サービス介護給付費 | 訪問通所区分 | 訪問介護 | 様式第二 |
| 訪問入浴介護 | |||
| 訪問看護 | |||
| 訪問リハビリテーション | |||
| 通所介護 | |||
| 通所リハビリテーション | |||
| 福祉用具貸与 | |||
| 短期入所区分 | 短期入所生活介護 | 様式第三 | |
| 介護老人保健施設における短期入所療養介護 | 様式第四 | ||
| 病院・診療所における短期入所療養介護 | 様式第五 | ||
| 上記区分以外 | 居宅療養管理指導 | 様式第二 | |
| 痴呆対応型共同生活介護 特定施設入所者生活介護 |
様式第六 | ||
| 居宅介護支援介護給付費 | 居宅介護支援 | 様式第七 | |
| 施設サービス等介護給付費 | 介護老人福祉施設 | 様式第八 | |
| 介護老人保健施設 | 様式第九 | ||
| 介護療養型医療施設 | 様式第十 | ||
(3)介護給付費明細書様式ごとの要記載内容
| 様式 | サービス提供年月 | 公費負担者・受給者番号 | 保険者番号 | 被保険者欄 | 請求事業者 | 居宅サービス計画 | 開始日・中止日等 | 短期入所実日数 | 入退所日等 | 給付費明細欄 | 緊急時施設療養費 | 特定診療費 | 請求額集計欄(限度額管理欄を含む) | 請求額集計欄 | 食事費用欄 |
| 様式第二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 様式第三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 様式第四 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 様式第五 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 様式第六 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 様式第七 | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 | *2 | |||||||||
| 様式第八 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 様式第九 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 様式第十 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)生活保護受給者に係る介護給付費明細書
生活保護法(昭和25年法律第144号)の指定を受けた介護機関が、介護保険の被保険者でない生活保護受給者の介護扶助に係る介護サービスを提供した場合、その費用に関する請求は介護給付費明細書によって行うこと。この場合、受給者は被保険者証を保有していないため、福祉事務所の発行する生活保護法介護券の記載事項をもとに介護給付費明細書の記載を行うこと。なお、記載要領については、被保険者でない生活保護受給者に関する場合についても同様とし、「被保険者」と記載している場合は、被保険者でない介護扶助の対象者も含むものとすること。
(2)項目別の記載要領
(2)公費負担者番号・公費受給者番号
イ 公費受給者番号
公費単独請求、公費と公費又は公費と保険の併用請求の場合に、公費受給者番号を記載すること。
(3)保険者番号
被保険者証若しくは資格者証又は生活保護受給者で介護保険の被保険者でない場合は福祉事務所から発行される生活保護法介護券(以下「被保険者証等」という。)の保険者番号欄に記載された保険者番号を記載すること。
(4)被保険者欄
様式第七においては1枚に複数の被保険者欄が存在するが、記載方法は他の様式の場合と同様であること。
イ 公費受給者番号(様式第七の場合のみ記載)
生活保護受給者で、介護保険の被保険者でない場合については、福祉事務所から発行される生活保護法介護券に記載された公費受給者番号を記載すること。
ウ 氏名
被保険者証等に記載された氏名及びふりがなを記載すること。
エ 生年月日
被保険者証等に記載された生年月日を記載すること。
元号欄は該当する元号の番号を○で囲むこと。
オ 性別
該当する性別の番号を○で囲むこと。
カ 要介護状態区分
請求対象となる期間における被保険者の要介護状態区分を被保険者証等をもとに記載すること。月の途中で要介護状態区分の変更認定等があって、要介護状態区分が変わった場合は、月の末日における要介護状態区分を記載すること。この場合において、当該要介護状態区分と、当該月の支給限度基準額設定のもととなった要介護状態区分は一致しない場合があることに留意すること。
介護老人福祉施設の請求の場合(様式第八)において、旧措置者入所者で要介護状態区分が非該当又は要支援の場合は「要支援等」を○で囲むこと。
キ 旧措置入所者特例(様式第八の場合のみ記載)
旧措置入所者の報酬区分の適用有無を確認し、該当する番号を○で囲むこと。
ク 認定有効期間
サービス提供月の末日において被保険者が受けている要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の有効期間を記載すること。
ケ 居宅サービス計画作成依頼届出年月日(様式第七の場合のみ記載)
被保険者証に記載された居宅介護支援事業者に係る居宅サービス計画作成依頼届出年月日を記載すること。ただし、被保険者でない生活保護受給者の場合は記載は不要であること。
(5)請求事業者(様式第七においては居宅介護支援事業者)
事前印刷又はゴム印等による記載であっても差し支えないこと。
イ 事業所名称
指定等を受けた際に届け出た事業所名を記載すること。
同一事業所番号で複数のサービス種類を提供しており、それぞれの名称が異なることで事業所名を特定できない場合は、指定申請等を行った際の「申請(開設)者」欄に記載した名称を記載すること。
ウ 所在地
指定等を受けた際に届け出た事業所の所在地とその郵便番号を記載すること。
エ 連絡先
審査支払機関、保険者からの問い合わせ用連絡先電話番号を記載すること。
オ 単位数単価(様式第七の場合のみ記載)
事業所所在地における単位数あたりの単価を小数点以下2位まで記載すること。
(6)居宅サービス計画(様式第二から様式第五までについて記載)
区分支給限度管理の対象のサービスの請求を行う場合に記載すること(居宅療養管理指導費のみの請求の場合は記載しないこと)。
イ 事業所番号
居宅介護支援事業者作成の場合に、サービス提供票に記載されている居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者の事業所番号を記載すること。
ウ 事業所名称
居宅介護支援事業者作成の場合に、サービス提供票に記載されている居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者の名称を記載すること。居宅介護支援事業者作成の場合は被保険者が市町村に届け出て、被保険者証の「居宅介護支援事業者及び事業所の名称」欄に記載された事業所(被保険者でない生活保護受給者の場合は、生活保護法介護券の「指定居宅介護支援事業者名」欄に記載された事業所)であることが必要であること。
(7)開始日・中止日等(様式第二について記載)
イ 中止年月日
月の途中にサービスの提供を中止した場合に、最後にサービスを提供した日付を記載すること。翌月以降サービスを継続している場合は記載しないこと。
ウ 中止理由
月の途中にサービスの提供を中止した場合の理由について、該当する番号を○で囲むこと。
(8)入退所日(様式第三、第四及び第五について記載)
イ 退所年月日
当該月における最初の退所した日付を記載すること。ただし、月末日において入所継続中の場合は記載しないこと。(連続入所が30日を超える場合は、30日目を退所日とみなして記載すること。)
(9)短期入所実日数等(様式第三、第四及び第五について記載)
イ サービス提供日
実際に事業者が短期入所介護サービスを提供した日の日付を○で囲むこと。
(10)入退所日等(様式第六、第八、第九及び第十について記載)
イ 退所(院)年月日
月の途中に退所(院)した場合に、退所(院)した日付を記載すること。(介護保険適用病床から医療保険適用病床に転床した場合は、当該転床した日付を記載すること。)
退所(院)日の翌月に退所(院)前後訪問指導加算を算定する場合は、退所(院)年月日を記載すること。
ウ 入所(院)実日数
被保険者等が実際に入所していた日数を記載すること。日数には入所日及び退所日を含むものとし、外泊日数は含めないこと。
エ 外泊日数
入所(院)期間中に、被保険者等が外泊した場合、外泊を開始した日及び施設に戻った日を含まない日数(例えば2泊3日の場合は1日)を記載すること。
オ 主傷病(様式第九及び第十について記載)
看護、医学的管理を要する主原因となる傷病名を記載すること。
カ 退所(院)後の状況
月の途中に退所(院)した場合に、退所後の状況として該当する番号を○で囲むこと。
(11)給付費明細欄(様式第七においては請求計算の欄に記載)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法をとっても差し支えないこと。
イ サービスコード
請求対象サービスに対応するサービスコード(6桁)を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する1回又は1日あたりの介護給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。)にしたがって算出した単位数を記載すること。
福祉用具貸与の場合は記載を省略すること。
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「−」の記載をすること。
(記載例:療養型施設医師配置減算「−12」)
エ 回数日数(様式第二においては「回数」の欄、様式第七については記載不要)
サービスの提供回数(期間ごとに給付費を算定するサービスについては算定回数)又は提供日数を記載すること。
福祉用具貸与の場合は、月の一部の期間が生活保護適用であった場合については、福祉用具貸与を現に行った日数を記載し、その他の場合は記載を省略すること。
オ サービス単位数(様式第七については記載不要)
「ウ 単位数」に「エ 回数日数」を乗じて算出した単位数を記載すること。
福祉用具貸与については、費用の額(消費税を含む。)を事業所の所在地域の単位数あたり単価で除した結果(小数点以下四捨五入)を記載すること。
カ 公費分回数等(様式第二においては「公費分回数」の欄、様式第七については記載不要)
「エ 回数日数」のうち、公費負担の対象となる回数又は日数を記載すること(月の途中で公費受給資格に変更があった場合は、対象となった期間に対応する回数または日数を記載すること)。
福祉用具貸与の場合は、月の一部の期間が生活保護適用期間であった場合については、福祉用具貸与を現に行った期間中の生活保護対象期間の日数を記載すること。
キ 公費対象単位数(様式第七については記載不要)
「ウ 単位数」に「カ 公費分回数等」を乗じて算出した単位数を記載すること。
福祉用具貸与の場合は、月を通じて生活保護適用期間である場合は「オ サービス単位数」をそのまま転記し、月の一部の期間が生活保護適用期間であった場合については、「オ サービス単位数」を「エ 回数日数」で除した結果に「カ 公費分回数等」を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記載すること。
ク 摘要(様式第七については記載不要)
サービス内容に応じて(別表1)にしたがって所定の内容を記載すること。
ケ 請求金額(様式第七の場合のみ)
「ウ 単位数」に単位数単価を乗じて得た結果(小数点以下切り捨て)を記載すること。
(12)緊急時施設療養費(様式第四及び第九)
イ 緊急時治療開始年月日
緊急時傷病名ごとの治療を開始した日付を「ア 緊急時傷病名」に対応させて記載すること。
傷病名が3つを超える場合は、欄内に番号を補記して記載すること。
ウ 緊急時治療管理(再掲)
緊急時治療管理の合計単位数と1日あたりの所定の単位数、緊急時治療管理を行った日数をそれぞれ記載すること。
(合計単位数=1日あたり単位数×緊急時治療管理日数)
エ 特定治療の内訳
リハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療の区分ごとに点数の合計を記載すること。
オ 特定治療の合計
特定治療の点数の合計を記載すること。
カ 摘要
特定治療の内容について、処置名等、回数、点数及び使用した薬剤名等の内訳をリハビリテーションから放射線治療の項目との対応が明らかになるように記載すること。
キ 往診日数
入所者のために病院又は診療所から往診を求めた日数を記載すること。
ク 医療機関名
往診を行った医療機関名を記載すること。
ケ 通院日数
入所者を病院又は診療所に通院させた日数を記載すること。
コ 医療機関名
通院した医療機関名を記載すること。
(13)特定診療費(様式第五及び第十)
イ 特定診療費の明細の記載方法
| 保険分 | 公費分 | |
| 特定治療費の内訳 | 指導管理等、単純エックス線、リハビリテーション、精神科専門療法の分類ごとに集計して、単位数の合計を記載すること。 | 左記の特定診療費のうち公費対象分単位数を記載すること。 |
| 合計 | 特定診療費の単位数合計を記載すること。 | 左記の特定診療費合計のうち公費対象分単位数を記載すること。 |
ウ 摘要
特定診療費の算定内容について、下記のとおりに記載すること。この場合の識別番号とは、エの表によること。
(なお、「<備考欄>」について、現時点で記載を必要とする項目はない。)
| 識別番号 名称 単位数×回数(日数) <備考(必要な場合)> / |
記載例: は1文字分以上のスペースを表す。
「@02 特定施設管理 250×30 /
@03 特定施設管理個室加算 300×30 / 」
上記のように、特定診療費の項目ごとに改行して記載することが望ましい。また、算定内容が記載仕切れない場合は、別紙を添付する方法でも可とすること。伝送・磁気で請求する場合は、左詰で、記載項目の間には、1文字以上の空白を入れること。また、1つの算定項目の記載の最後には「/」で区切りをつけること。
エ 特定診療費の分類
| 区分 | 特定診療費の内容(摘要欄での記載名称) | 識別番号 | |
| 1 | 指導管理等 | 感染対策指導管理 | @01 |
| 特定施設管理 | @02 | ||
| 特定施設管理個室加算 | @03 | ||
| 特定施設管理2人部屋加算 | @04 | ||
| 初期入院診療管理 | @05 | ||
| 重症皮膚潰瘍管理指導 | @06 | ||
| 重症皮膚潰瘍管理指導(月途中) | @07 | ||
| 介護栄養食事指導 | @08 | ||
| 薬剤管理指導 | @09 | ||
| 特別薬剤管理指導加算 | @10 | ||
| 医学情報提供(I) | @11 | ||
| 医学情報提供(II) | @12 | ||
| 2 | 単純エックス線 | 単純エックス線撮影・診断 | @13 |
| 3 | リハビリテーション | 理学療法(I)入院6月以内 | @14 |
| 理学療法(I)入院6月超 | @15 | ||
| 理学療法(II)入院6月以内 | @16 | ||
| 理学療法(II)入院6月超 | @17 | ||
| 理学療法(III) | @18 | ||
| 理学療法(IV) | @19 | ||
| 理学療法リハビリ計画加算(1) | @20 | ||
| 理学療法リハビリ計画加算(2) | @21 | ||
| 理学療法日常動作訓練指導加算 | @22 | ||
| 作業療法(I)入院6月以内 | @23 | ||
| 作業療法(I)入院6月超 | @24 | ||
| 作業療法(II)入院6月以内 | @25 | ||
| 作業療法(II)入院6月超 | @26 | ||
| 作業療法リハビリ計画加算(1) | @27 | ||
| 作業療法リハビリ計画加算(2) | @28 | ||
| 作業療法日常動作訓練指導加算 | @29 | ||
| 言語療法 | @30 | ||
| 摂食機能療法 | @31 | ||
| 4 | 精神科専門療法 | 精神科作業療法 | @32 |
| 痴呆性老人入院精神療法 | @33 | ||
(14)請求額集計欄(様式第二における給付率の記載方法)
イ 公費
公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。当該率等については(別表2)を参照すること。
低所得者対策等(いわゆる特別対策)における訪問介護については、公費負担医療に準じた取扱いを行うため、公費の給付率を7(%)ではなく、保険給付率を加えた率として記載すること。
(15)請求額集計欄(様式第二におけるサービス種類別の集計)
以下の「ア サービス種類コード」から「シ 公費分本人負担」までについては、給付費明細欄の内容からサービス種類が同じサービスの情報を抽出し、集計を行って記載すること。
イ サービス種類の名称
当該対象サービス種類の名称(訪問介護、訪問入浴介護等)を記載すること。
ウ サービス実日数
当該対象サービス種類のサービスを行った実日数(当該事業所から訪問または通所サービスのいずれかを行った日数の合計)を記載すること。
エ 計画単位数
居宅介護支援事業者または被保険者が作成したサービス提供票の別表に記載された、当該月中に当該事業所から提供する当該サービス種類における区分支給限度基準内単位数を記載すること。ただし、居宅療養管理指導の場合には記載不要であること。
オ 限度額管理対象単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象部分(特別地域加算及びターミナルケア加算を除く。)のサービス単位数を合計して記載すること。
カ 限度額管理対象外単位数
当該サービス種類のうち、限度額管理対象外(特別地域加算及びターミナルケア加算)のサービス単位数を合計して記載すること。
キ 給付単位数
「エ 計画単位数」と「オ 限度額管理対象単位数」のいずれか低い方の単位数に「カ 限度額管理対象外単位数」を加えた単位数を記載すること。
ク 公費分単位数
当該サービス種類の公費対象単位数の合計と「キ 給付単位数」のいずれか低い方の単位数を記載すること。
ケ 単位数単価
事業所所在地における当該サービス種類の単位数あたり単価を記載すること。
コ 保険請求額
「キ 給付単位数」に「ケ 単位数単価」を乗じた結果(小数点以下切り捨て)に、保険の給付率を乗じた結果の金額(小数点以下切り捨て)を記載すること。
サ 利用者負担額
「キ 給付単位数」に「ケ 単位数単価」を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、「コ 保険請求額」、「シ 公費請求額」及び「ス 公費分本人負担」を差し引いた残りの額を記載すること(サービスの提供の都度利用者負担を徴収している場合等においては、端数処理により徴収した利用者負担の合計とは一致しない場合がありうること。)。
シ 公費請求額
「ク 公費分単位数」に「ケ 単位数単価」を乗じた結果(小数点以下切り捨て)に、更に公費給付率から保険の給付の率を差し引いた率を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、「ス 公費分本人負担」を差し引いた残りの額を記載すること。
公費の給付率が100/100で、保険給付対象単位数と公費対象単位数が等しく、利用者負担額(公費の本人負担額を除く。)が発生しない場合は、「キ 給付単位数」に「ケ 単位数単価」を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、「コ 保険請求額」と「ス 公費分本人負担」を差し引いた残りの額を記載すること。
ス 公費分本人負担
公費負担医療、または生活保護受給者で本人負担額がある場合に、その額を記載すること。
セ 合計
保険請求額から公費分本人負担についてそれぞれの行の合計金額を合計欄に記載すること。
(16)請求額集計欄(様式第三、第四及び第五の(18)、(19)以外の部分)
様式第三から第五までの特定診療費、緊急時施設療養費以外の請求額集計欄は以下の方法により記載すること。
| 項目 | 保険分 | 公費分 |
| (1)計画単位数 | 居宅介護支援事業者または被保険者が作成したサービス提供票の別表に記載された、当該月中に当該事業所から提供する当該サービス種類における区分支給限度基準内単位数を記載すること。 | |
| (2)限度額管理対象単位数 | 給付費明細欄のサービス単位数のうち、支給限度額管理対象部分(緊急時治療管理を除く。)のサービス単位数を合計して記載すること。 | |
| (3)限度額管理対象外単位数 | 給付費明細欄のサービス単位数のうち、支給限度額管理対象外(緊急時治療管理)のサービス単位数を合計して記載すること。 | |
| (4)給付単位数 | (1)計画単位数と(2)限度額管理対象単位数のいずれか低いほうの単位数に(3)限度額管理対象外単位数を加えた単位数を記載すること。 | 当該サービス種類の公費対象単位数の合計と(4)給付単位数(保険分)のいずれか低い方の単位数を記載すること。 |
| (5)単位数単価 | 事業所所在地における当該サービス種類の単位数あたり単価を記載すること。 | |
| (6)給付率 | 介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を百分率で記載すること。 | 公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。 |
| (7)請求額 | (4)給付単位数(保険分)に(5)単位数単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)に(6)給付率(保険分)を乗じた結果の金額(小数点以下切り捨て)を記載すること。 | (4)給付単位数(公費分)に(5)単位数単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)に、更に(6)給付率(公費分)から(6)給付率(保険分)を差し引いた率を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、(8)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 公費の給付率が100/100で、保険分と公費分の(4)給付単位数が等しい時は、(4)給付単位数に(5)単位数単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、(7)請求額(保険分)と(8)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 |
| (8)利用者負担額 | (4)給付単位数(保険分)に(5)単位数単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、(7)請求額(保険分、公費分)と(8)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 | 公費負担医療、または介護扶助で本人負担額がある場合に、その額を記載すること。 |
(17)請求額集計欄(様式第六、様式第八、第九及び第十の(18)、(19)以外の部分)
様式第六及び様式第八から第十までの特定診療費、緊急時施設療養費以外の請求額集計欄は以下の方法により記載すること。
| 項目 | 保険分 | 公費分 |
| (1)単位数合計 | 給付費明細欄のサービス単位数の合計を記載すること。 | 給付費明細欄の公費対象サービス単位数の合計を記載すること。 |
| (2)単位数単価 | 事業所所在地における当該サービス種類の単位数あたり単価を記載すること。 | |
| (3)給付率 | 介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を百分率で記載すること。 | 公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。 |
| (4)請求額 | (1)単位数合計(保険分)に(2)単位数単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)に(3)給付率(保険分)を乗じた結果の金額(小数点以下切り捨て)を記載すること。 | (1)単位数合計(公費分)に(2)単位数単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)に、更に(3)給付率(公費分)から(3)給付率(保険分)を差し引いた率を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 公費の給付率が100/100で、保険分と公費分の(1)単位数合計が等しい時は、(1)単位数合計に(2)単位数単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、(4)請求額(保険分)と(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 |
| (5)利用者負担額 | (1)単位数合計(保険分)に(2)単位数単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、(4)請求額(保険分、公費分)と(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 | 公費負担医療、または介護扶助で本人負担額がある場合に、その額を記載すること。 |
(18)請求額集計欄(緊急時施設療養費)
様式第四及び様式第九の請求集計欄における緊急時施設療養費部分は以下の方法により記載すること。「項目」における( )内は様式第四における項目名。
| 項目 | 保険分特定治療 | 公費分特定治療 |
| (1)点数合計 ((4)給付点数) |
緊急時施設療養費における特定治療の保険分点数合計(緊急時治療管理の単位数は除く。)を記載すること。 | 緊急時施設療養費における特定治療のうち公費分点数を記載すること(緊急時施設療養途中で公費適用の異動がない限り保険分と同じ。)。 |
| (2)点数単価 ((5)点数単価) |
10円/点固定 | 10円/点固定 |
| (3)給付率 ((6)給付率) |
介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を百分率で記載すること。 | 公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。 |
| (4)請求額 ((7)請求額) |
(1)点数合計(保険分)に(2)点数単価を乗じた結果に(3)給付率(保険分)を乗じた結果の金額(小数点以下切り捨て)を記載すること。 | (1)点数合計(公費分)に(2)点数単価を乗じた結果に、更に(3)給付率(公費分)から(3)給付率(保険分)を差し引いた率を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 公費の給付率が100/100で、保険分と公費分の(1)点数合計が等しい時は、(1)点数合計に(2)点数単価を乗じた結果から、(4)請求額(保険分)と(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 |
| (5)利用者負担額 ((8)利用者負担額) |
(1)点数合計(保険分)に(2)点数単価を乗じた結果から、(4)請求額(保険分、公費分)と(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 | 公費負担医療、又は介護扶助で本人負担額がある場合に、その額を記載すること。 |
(19)請求額集計欄(特定診療費)
様式第五及び様式第十の請求額集計欄における特定診療費部分は以下の方法により記載すること。「項目」における( )内は様式第五における項目名。
| 項目 | 保険分特定診療費 | 公費分特定診療費 |
| (1)単位数合計 ((4)給付単位数) |
特定診療費の保険分単位数の合計を記載すること。 | 特定診療費の公費分単位数の合計を記載すること。 |
| (2)単位数単価 ((5)単位数単価) |
10円/単位固定 | 10円/単位固定 |
| (3)給付率 ((6)給付率) |
介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を百分率で記載すること。 | 公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。 |
| (4)請求額 ((7)請求額) |
(1)単位数合計(保険分)に(2)単位数単価を乗じた結果に(3)給付率(保険分)を乗じた結果の金額(小数点以下切り捨て)を記載すること。 | (1)単位数合計(公費分)に(2)単位数単価を乗じた結果に、更に(3)給付率(公費分)から(3)給付率(保険分)を差し引いた率を乗じた結果(小数点以下切り捨て)から、(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 公費の給付率が100/100で、保険分と公費分の(1)単位数合計が等しい時は、(1)単位数合計に(2)単位数単価を乗じた結果から、(4)請求額(保険分)と(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 |
| (5)利用者負担額 ((8)利用者負担額) |
(1)単位数合計(保険分)に(2)単位数単価を乗じた結果から、(4)請求額(保険分、公費分)と(5)利用者負担額(公費分)を差し引いた残りの額を記載すること。 | 公費負担医療、または介護扶助で本人負担額がある場合に、その額を記載すること。 |
(20)食事費用欄(様式第八,第九及び第十)
| 記載内容 | 備考 | |
| (1)基本日数 | 基本食のみの提供日数を記載すること。 | |
| (2)特別食日数 | 特別食の提供日数を記載すること。 | |
| (3)基本単価 | 基本食の提供費用の日額を記載すること。 | |
| (4)特別食単価 | 特別食の提供費用の日額を記載すること。 | (基本食事サービス費+特別食加算) |
| (5)基本金額 | 基本食の提供日数に単価を乗じた額を記載すること。 | (1)×(3) |
| (6)特別食金額 | 特別食の提供日数に単価を乗じた額を記載すること。 | (2)×(4) |
| (7)延べ日数 | 食事を提供した日数を記載すること。 | (1)+(2) |
| (8)公費分日数 | 食事を提供した日のうち、公費適用対象の日数を記載すること。 | |
| (9)合計 | 基本食金額と特別食金額の合計額を記載すること。 | (5)+(6) |
| (10)標準負担月額 | 当月中の公費適用期間分を除く標準負担額の合計額を記載すること。 | 月の途中で標準負担額(日額)に変更がない場合は、標準負担額に公費分日数を除く食事提供日数を乗じた額となること。 |
| (11)食事提供費請求額 | 食事費用の合計金額から標準負担月額と公費請求分を差し引いた金額を記載すること。 | |
| (12)公費請求分 | 公費適用期間分の標準負担額を記載すること。 | |
| (13)標準負担額 | 食事の標準負担額(日額)を記載すること。 | 月を通じて標準負担額に変更がない場合はその額を、月の途中で変更があった場合は減免等を受ける前の標準負担額を記載すること。 |
3 給付管理票に関する事項(様式第十一)
(1)留意事項
(2) 事業所ごと及びサービス種類ごとの居宅サービス計画に位置付けられた介護サービスの給付額を月末時点の「サービス利用票(控)」から作成すること。
(2) 保険者番号
サービス利用票(控)の保険者番号欄に記載された保険者番号を記載すること。
(3) 被保険者番号
サービス利用票(控)の被険者番号欄に記載された被保険者番号を記載すること。
(4) 被保険者氏名
サービス利用票(控)に記載された氏名及びふりがなを記載すること。
(5) 生年月日
サービス利用票(控)に記載された生年月日を記載すること。
元号は該当する元号を○で囲むこと。
(6) 性別
該当する性別を○で囲むこと。
(7) 要介護状態区分
サービス利用票(控)に記載された要介護状態区分を記載すること。要介護状態区分については、月途中で変更があった場合には、いずれか重い方の要介護状態区分を記載すること。
(8) 作成区分
該当する作成者の番号を○で囲むこと。
(9) 居宅介護支援事業所番号
居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所の指定事業所番号または基準該当登録番号を記載すること。ただし、市町村が給付管理票を作成する場合は記載不要であること。(以下、(10)(11)についても同様)
(10) 居宅介護支援事業所名
指定等を受けた際に届け出た事業所名を記載すること。
(11) 居宅介護支援事業者の事業所所在地及び連絡先
指定等を受けた際に届け出た事業所の所在地と審査支払機関、保険者からの問い合わせ用連絡先電話番号を記載すること。
(12) 居宅サービス支給限度基準額
サービス利用票(控)に記載された居宅サービス支給限度基準額を記載すること。
(13) 限度額適用期間
サービス利用票(控)に記載された限度額適用期間を記載すること。
(14) 居宅サービス事業者の事業所名
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載された居宅サービス事業者の事業所名を記載すること。
(15) 事業所番号
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載された居宅サービス事業者の事業所番号を記載すること。
(16) 指定/基準該当サービス識別
指定または基準該当の区分を○で囲むこと。
(17) サービス種類名
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載されたサービス種類の名称(訪問介護、訪問入浴介護等)を記載すること。
(18) サービス種類コード
当該サービス種類のコード(サービスコードの上2桁)を記載すること。
(19) 給付計画単位数
サービス利用票別表(控)のサービス種類ごとの集計行の区分支給限度基準内単位数に記載された額(単位数)を記載すること。
4 公費の介護給付費明細書に関する事項
(1)公費の請求が必要な場合における請求明細記載方法の概要
| 区分 | 適用条件 | 請求明細記載方法の概要 |
| 保険と生活保護の併用 | 被保険者が生活保護受給者の場合 | 1枚の介護給付費明細書で保険請求と併せて生活保護の請求額を公費請求額欄で計算 |
| 生活保護の単独請求 | 被保険者でない生活保護受給者の介護扶助の現物給付に関する請求を行う場合 | 1枚の介護給付費明細書で生活保護の請求額を公費請求額欄で計算 |
| 保険と公費負担医療、生活保護の併用 | 生活保護受給者である被保険者が保険優先公費負担医療の受給者であり、介護保険の給付対象サービスが当該公費負担医療の対象となる場合 | 1枚目の介護給付費明細書で保険請求と併せて公費負担医療の請求額計算を行い、2枚目の介護給付費明細書で生活保護の請求額を計算 |
| 保険と公費負担医療の併用 | 被保険者が保険優先公費負担医療の受給者であり、介護保険の給付対象サービスが当該公費負担医療の対象となる場合 | 1枚の介護給付費明細書で保険請求と併せて公費負担医療の請求額を公費請求額欄で計算 |
| 生活保護と公費負担医療の併用 | 被保険者でない生活保護受給者の介護扶助の現物給付に関する請求を行う場合で、生活保護受給者が保険優先公費負担医療の受給者であり、介護保険の給付対象サービスが当該公費負担医療の対象となる場合 | 1枚目の介護給付費明細書で公費負担医療の請求額計算を行い、2枚目の介護給付費明細書で生活保護の請求額を計算 |
(2) 2種類以上の公費負担医療の適用がある場合は適用の優先順(別表2を参照)に1枚目の介護給付費明細書から順次公費負担医療の請求計算を行うこと。さらに、生活保護の適用(様式第二で医療系サービスと福祉系サービスをあわせて請求する場合など)があれば、最後の介護給付費明細書で生活保護の請求額を計算すること。この場合、介護給付費明細書は3枚以上になる場合があること。
なお、ここでいう公費負担医療には、特別対策(低所得者利用者負担対策)としての「施行時のホームヘルプサービス利用者に対する経過措置」及び「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置」も含むものとすること。
(2)各様式と公費併用請求の関係
各様式ごとの公費請求の組み合わせは下表のようになること。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (生保:生活保護 公費:公費負担医療) |
(別表1)
| サービス種類 | サービス内容 (算定項目) |
摘要記載事項 | 備考 |
| 訪問介護 | 身体介護中心の4時間以上の場合 | 計画上の所要時間を分単位で記載すること。 例 260分 単位を省略することも可。 例 260 |
4時間以上については、1回あたりの点数の根拠を所要時間にて示すこと。 |
| 身体介護及び家事援助が同程度の4時間以上の場合 | 同上 | 同上 | |
| 家事援助中心の4時間以上の場合 | 同上 | 同上 | |
| 訪問看護 | ターミナルケア加算を算定する場合 | 対象者が死亡した日を記載すること。 例 6日 単位を省略することも可。 例 6 |
|
| サテライト事業所からのサービス提供(訪問介護・訪問看護・通所介護) | 「サテライト」の略称として英字2文字を記載すること。 例 ST |
他の摘要記載事項と重複する場合は「/」で区切ること。 例 ST/260 |
|
| 居宅療養管理指導 | 医師及び歯科医師が行う場合 | 居宅訪問日数を記載すること。 例 6日 単位を省略することも可。 例 6 |
居宅を訪問して、居宅サービス計画策定等に必要な情報提供又は居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行うことが算定の要件。 (1月に1回限り) |
| 薬剤師が行う場合 | 居宅訪問日を記載すること。 例 6日,20日 単位を省略することも可。 例 6,20 |
居宅を訪問して薬学的な管理指導を行うことが算定の要件。 (1月に2回限り) |
|
| 管理栄養士が行う場合 |
同上 |
居宅を訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うことが算定要件。 (1月に2回限り) |
|
| 歯科衛生士等が行う場合 | 同上 | 居宅を訪問して療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実技指導を行うことが算定要件。 (1月に4回限り) |
|
| 福祉用具貸与 | 福祉用具貸与 | 別記を参照 | |
| 特別地域加算を算定する場合 | 特別地域加算を算定する場合福祉用具貸与を開始した日付を記載すること。 例 6日 単位を省略することも可。 例 6 |
||
| 介護福祉施設サービス | 退所前後訪問相談援助加算 | 家庭等への訪問日を記載すること。 例 20日 単位を省略することも可。 例 20 |
退所後生活する家庭あるいは他の社会福祉施設等を訪問し、必要な相談援助を行うことが算定の要件。 (入所中1回又は2回、退所後1回限り) |
| 介護保健施設サービス | 退所前後訪問指導加算 | 家庭等への訪問日を記載すること。 例 20日 単位を省略することも可。 例 20 |
退所後生活する家庭を訪問し、療養上の指導を行うことが算定の要件。 (入所中1回又は2回、退所後1回限り) |
| 老人訪問看護指示加算 | 訪問看護指示書の交付日を記載すること。 例 20日 単位を省略することも可。 例 20 |
指定訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付することが算定要件。 (退所する者1人につき1回限り) |
|
| 介護療養施設サービス | 退院前後訪問指導加算 | 家庭等への訪問日を記載すること。 例 20日 単位を省略することも可。 例 20 |
退院後生活する家庭を訪問し、療養上の指導を行うことが算定の要件。 (入院中1回又は2回、退院後1回限り) |
| 老人訪問看護指示加算 | 訪問看護指示書の交付日を記載すること。 例 20日 単位を省略することも可。 例 20 |
指定訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付することが算定要件。 (退院する者1人につき1回限り) |
|
(別表2)
| 項番 | 制度 | 給付対象 | 法別 番号 |
資格証明等 | 公費の 給付率 |
負担割合 | 介護保険と関連する 給付対象 |
| 1 | 結核予防法(昭和26年法律第96号)「一般患者に対する医療」 | 結核に関する治療・検査等省令で定めるもの | 10 | 患者票 | 95 | 介護保険を優先し95%までを公費で負担する | 医療機関の短期入所療養介護、及び介護療養施設サービス(食費を除く) |
| 2 | 結核予防法「従業禁止、命令入所者の医療」 | 従業禁止、命令入所者に対する医療 | 11 | 患者票 | 100 | 介護保険を優先 利用者本人負担額がある |
従業禁止者の訪問看護、居宅療養管理指導 |
| 3 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)「通院医療」 | 通院による精神障害の医療 | 21 | 患者票 | 95 | 介護保険を優先し95%までを公費で負担する | 訪問看護 |
| 4 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)「更生医療」 | 身体障害者に対する更生医療(リハビリテーション) | 15 | 更生医療券 | 100 | 介護保険優先 利用者本人負担額がある |
訪問看護、訪問リハビリテーション、医療機関の通所リハビリテーション、及び介護療養施設サービス |
| 5 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)「一般疾病医療費の給付」 | 健康保険と同様(医療全般) | 19 | 被爆者手帳 | 100 | 介護保険優先、残りを全額公費 | 介護老人保健施設サービス含め医療系サービスの全て |
| 6 | 特定疾患治療研究事業について(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知) 「治療研究に係る医療の給付」 |
特定の疾患のみ | 51 | 受給者証 | 100 | 介護保険優先 利用者本人負担額がある |
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、及び介護療養施設サービス |
| 7 | 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について(平成元年7月24日健医発第896号厚生省保健医療局長通知)「治療研究に係る医療の給付」 | 同上 | 51 | 受給者証 | 100 | 同上 | 同上 |
| 8 | 特別対策 (低所得者対策等) |
低所得者の利用者負担の経過措置 | 56 | 受給者証 | 97 | 介護保険を優先し残りの7%を公費で負担する | 訪問介護 |
| 障害者施策利用者への支援措置 | 57 | ||||||
| 9 | 生活保護法の 「介護扶助」 |
介護保険の給付対象サービス | 12 | 介護券 | 100 | 介護保険優先 利用者本人負担額がある |
介護保険の給付対象と同様 |
(別記)
介護給付費明細書へ記載するコードについては、テクノエイド協会が付しているTAISコード又はJANコードを有している商品についてはいずれかのコードを記載することとすること。
また、両方のコードを有している商品については、どちらのコードを記載しても差し支えないこと。
1 (財)テクノエイド協会が構築している福祉用具情報システムに登録をしている商品について
(1)既にテクノエイド協会で付している番号の内、企業コード(5桁)及び商品コード(6桁)を左詰で記載すること。その際に企業コードと商品コードの間は「−」でつなぐこととすること。
(2)2以上コードを有している商品については、どの種別で保険請求しているかという観点からコードを記載すること。
2 JANコードを取得している商品については、JANコードを左詰で記載
3 いずれのコードも有していない商品については、次のとおりローマ字で記載
(1)メーカー名と商品名を英字(ヘボン式で大文字)で記載し、その間は「−」でつなぐこととすること。
なお、最初の10桁はメーカー名、残りの9桁については商品名とすること。
(2)メーカー名の記載については、株式会社等の各企業で共通するような名称を除き、次頁に定める変換方法により英字(ヘボン式で大文字)で記載
| (例) | アメリカベッドメディカルサービス株式会社 | → | AMERIKABET |
| 株式会社松本製作所 | → | MATSUMOTOS |
(3) 商品名の記載については、型番を有している商品については型番を記載し、型番がない商品については、商品名を別紙に定める変換方法により英字(ヘボン式で大文字)で記載(ヘボン式については次表を参照のこと。)
| (例) | 自走式車いす | AA−12 | → AA−12 |
| アルミ製標準車 | → ARUMISEIH |
(参考) JANコードとは、「国コード」、「商品メーカーコード」、「商品アイテムコード」、「チェックデジット」からなる商品識別コードであること。このコードは、店舗等で商品に印刷されているバーコードの一つであること。
(別紙2)
| あ行 | あ い う え お A I U E O |
や行 | や い ゆ え よ YA I YU E YO |
| か行 | か き く け こ KA KI KU KE KO |
ら行 | ら り る れ ろ RA RI RU RE RO |
| きゃ きゅ きょ KYA KYU KYO |
りゃ りゅ りょ RYA RYU RYO |
||
| さ行 | さ し す せ そ SA SHI SU SE SO |
わ行 | わ ゐ う ゑ を WA I U E O |
| しゃ しゅ しょ SHA SHU SHO |
ん | ん N(M) |
|
| た行 | た ち つ て と TA CHI TSU TE TO |
が行 | が ぎ ぐ げ ご GA GI GU GE GO |
| ちゃ ちゅ ちょ CHA CHU CHO |
ぎゃ ぎゅ ぎょ GYA GYU GYO |
||
| な行 | な に ぬ ね の NA NI NU NE NO |
ざ行 | ざ じ ず ぜ ぞ ZA JI ZU ZE ZO |
| にゃ にゅ にょ NYA NYU NYO |
じゃ じゅ じょ JA JU JO |
||
| は行 | は ひ ふ へ ほ HA HI FU HE HO |
だ行 | だ ぢ づ で ど DA JI ZU DE DO |
| ひゃ ひゅ ひょ HYA HYU HYO |
ば行 | ば び ぶ べ ぼ BA BI BU BE BO |
|
| ま行 | ま み む め も MA MI MU ME MO |
びゃ びゅ びょ BYA BYU BYO |
|
| みゃ みゅ みょ MYA MYU MYO |
ぱ行 | ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ PA PI PU PE PO |
|
| ぴゃ ぴゅ ぴょ PYA PYU PYO |
| 1 | 撥音 ヘボン式ではB、M、Pの前にNの代わりにMをおく。 NAMBA難波(なんば) HOMMA本間(ほんま) SAMPEI三瓶(さんぺい) |
| 2 | 促音 子音を重ねて示す。 HATTORI服部(はっとり) KIKKAWA吉川(きっかわ) ただし、チ(CHI)、チャ(CHA)、チュ(CHU)、チョ(CHO)音に限り、その前にTを加える。 HOTCHI発地(ほっち) HATCHO(はっちょう) |
(PDF:14KB)
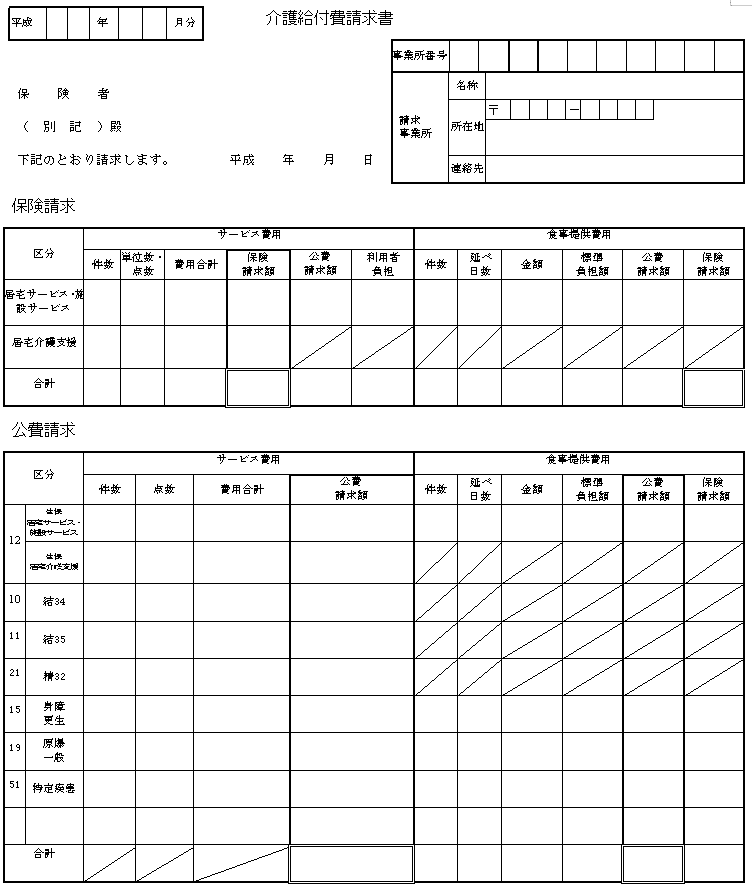
(PDF:33KB)
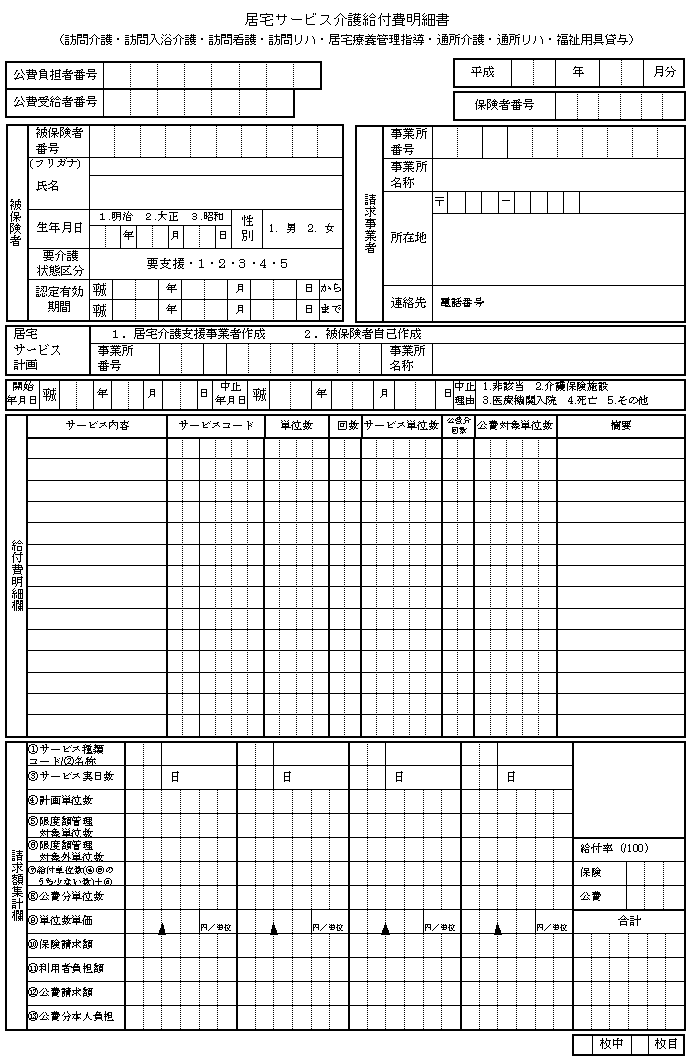
(PDF:25KB)
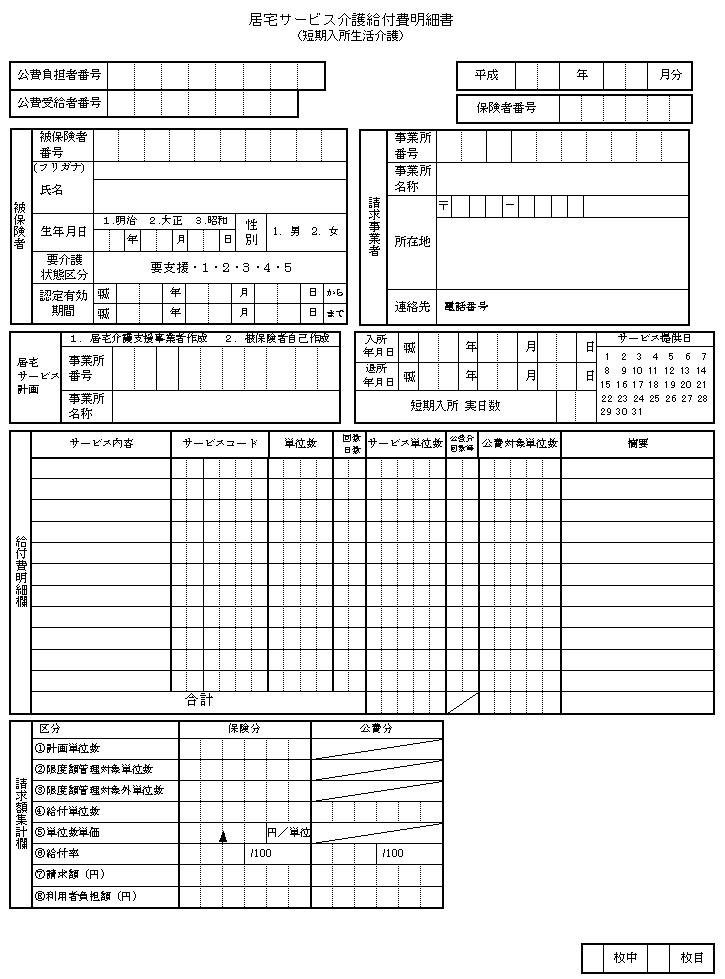
(PDF:28KB)
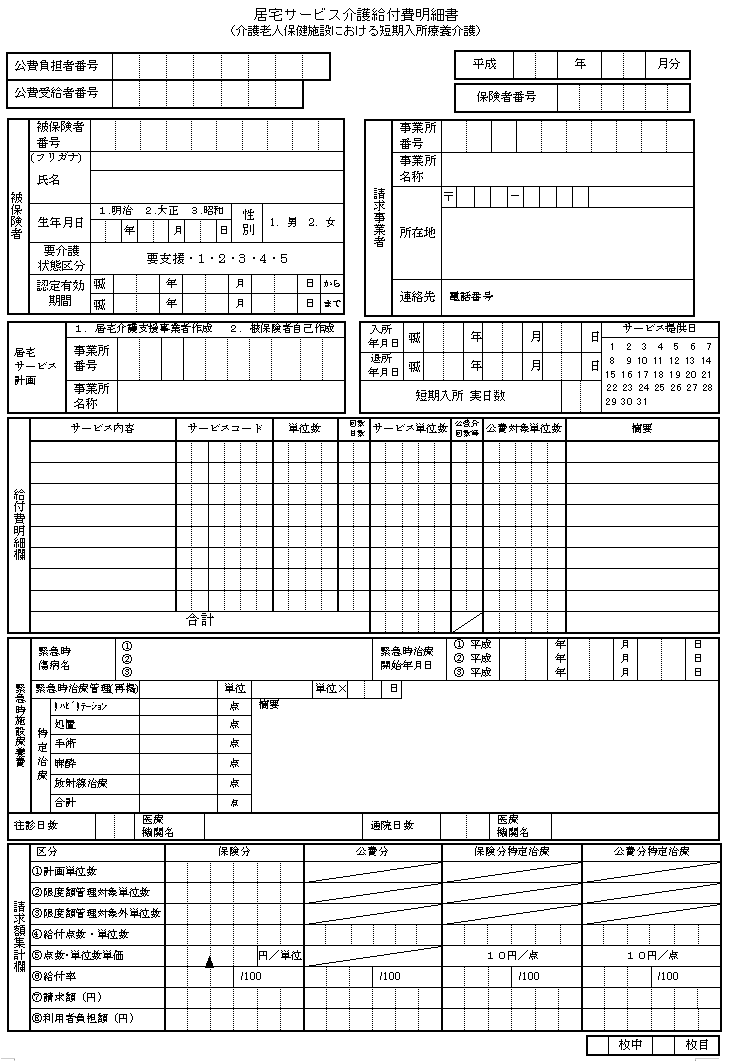
(PDF:27KB)
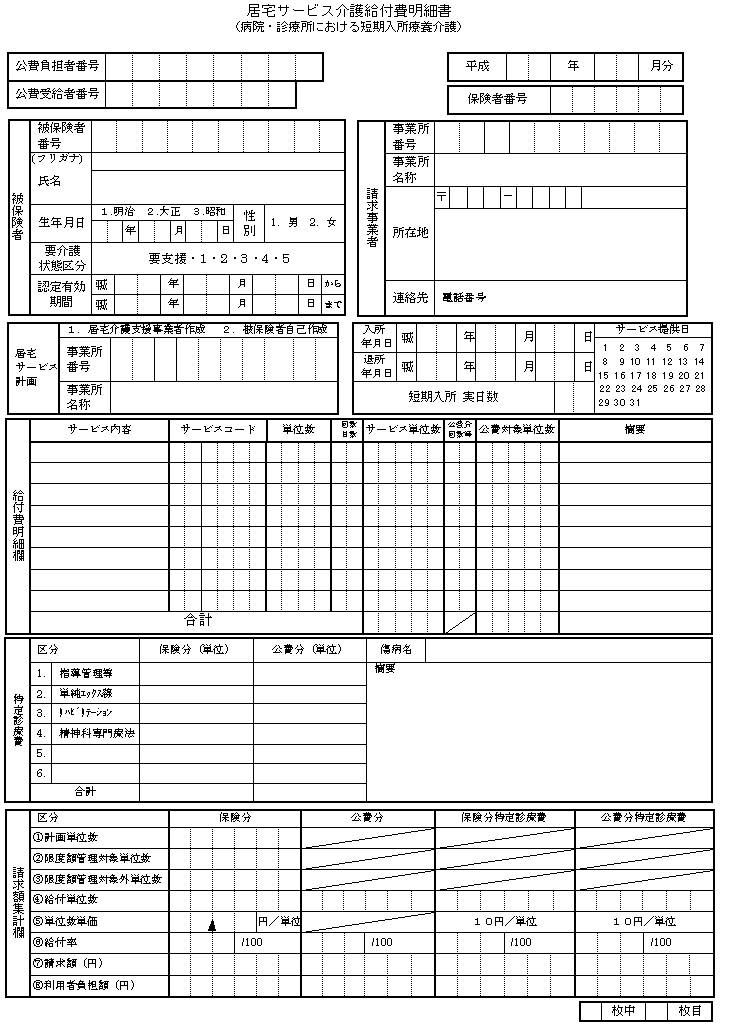
(PDF:24KB)
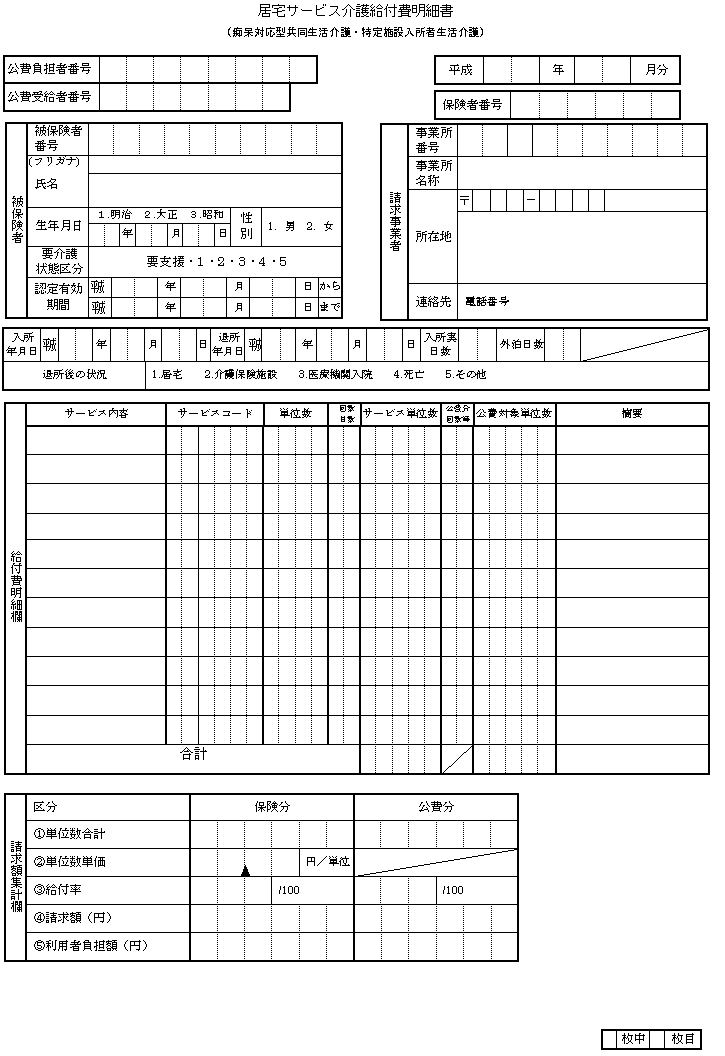
(PDF:33KB)
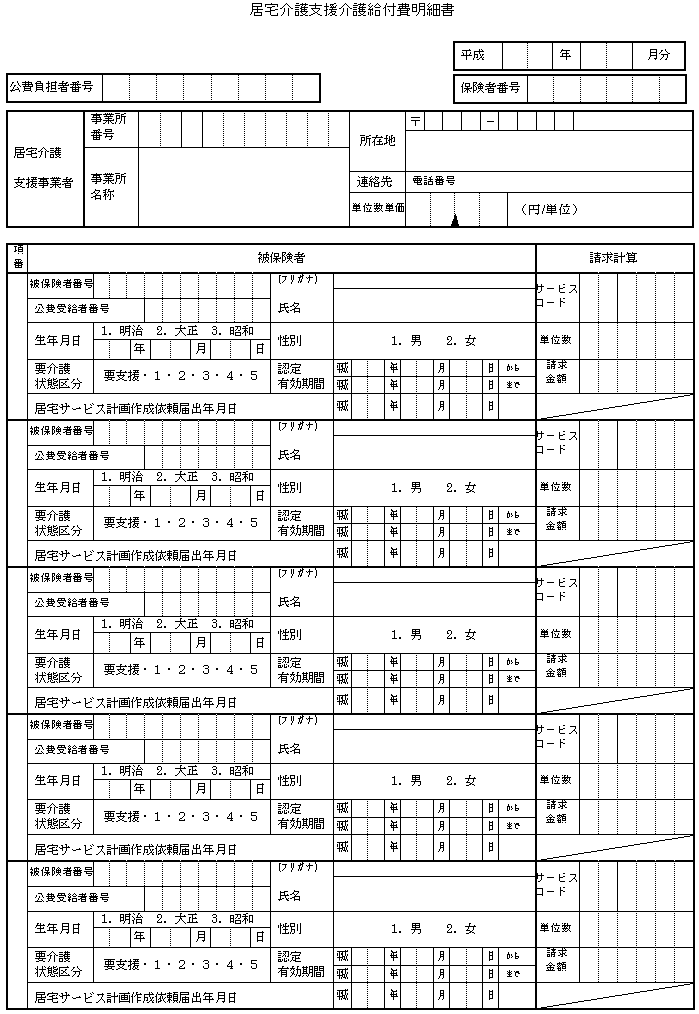
(PDF:19KB)
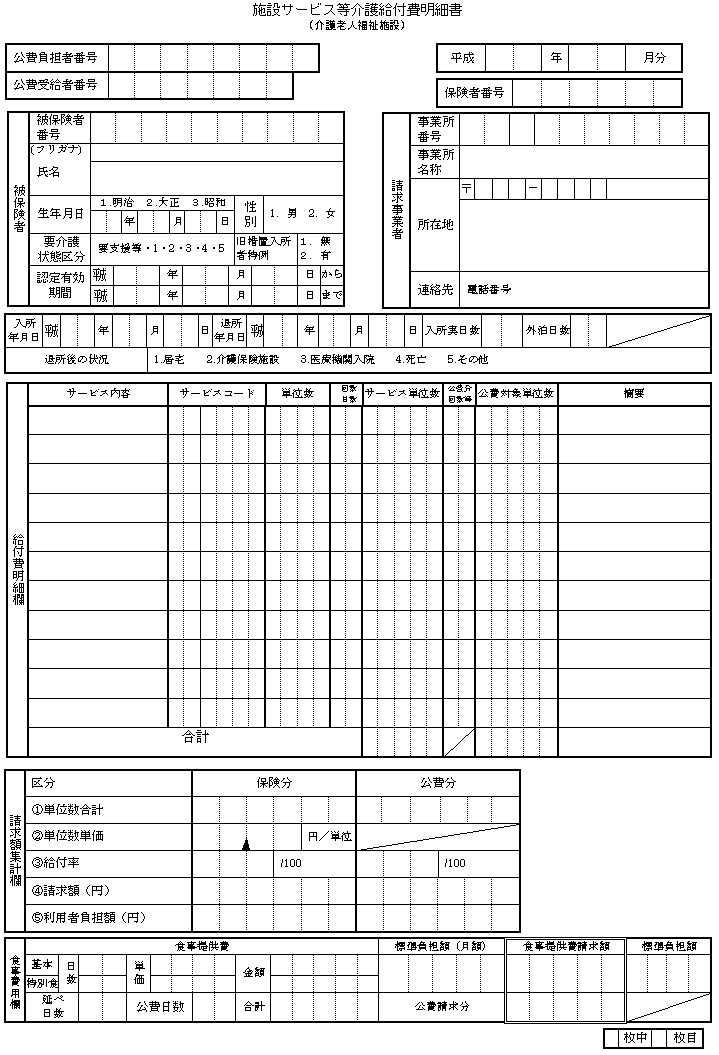
(PDF:20KB)
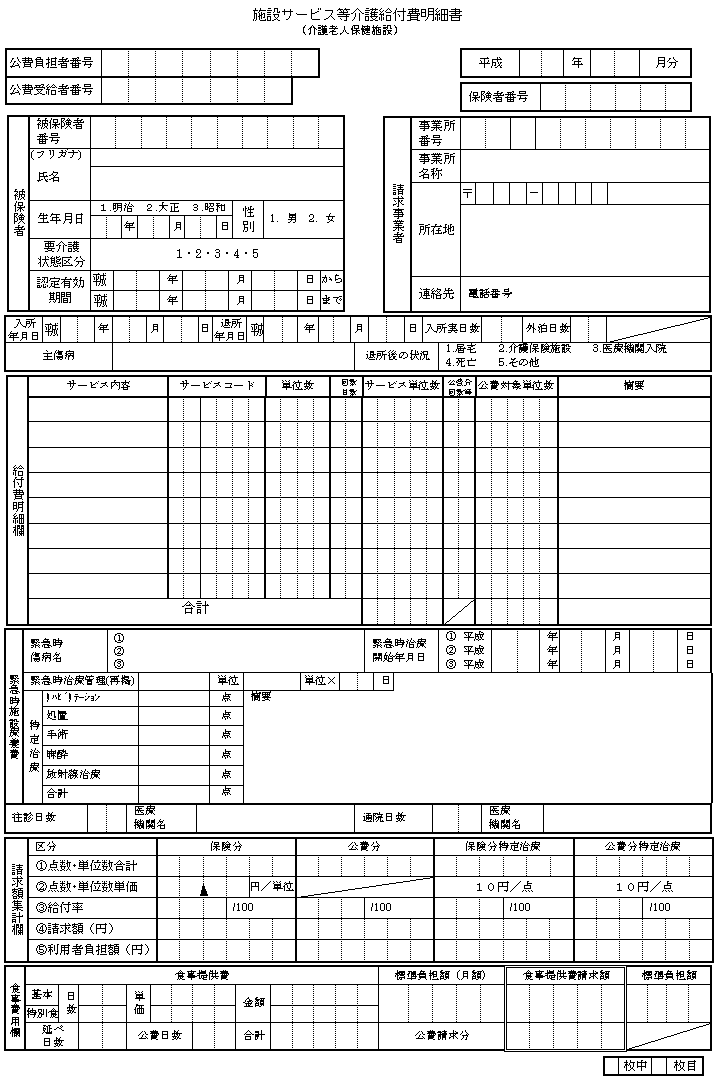
(PDF:21KB)
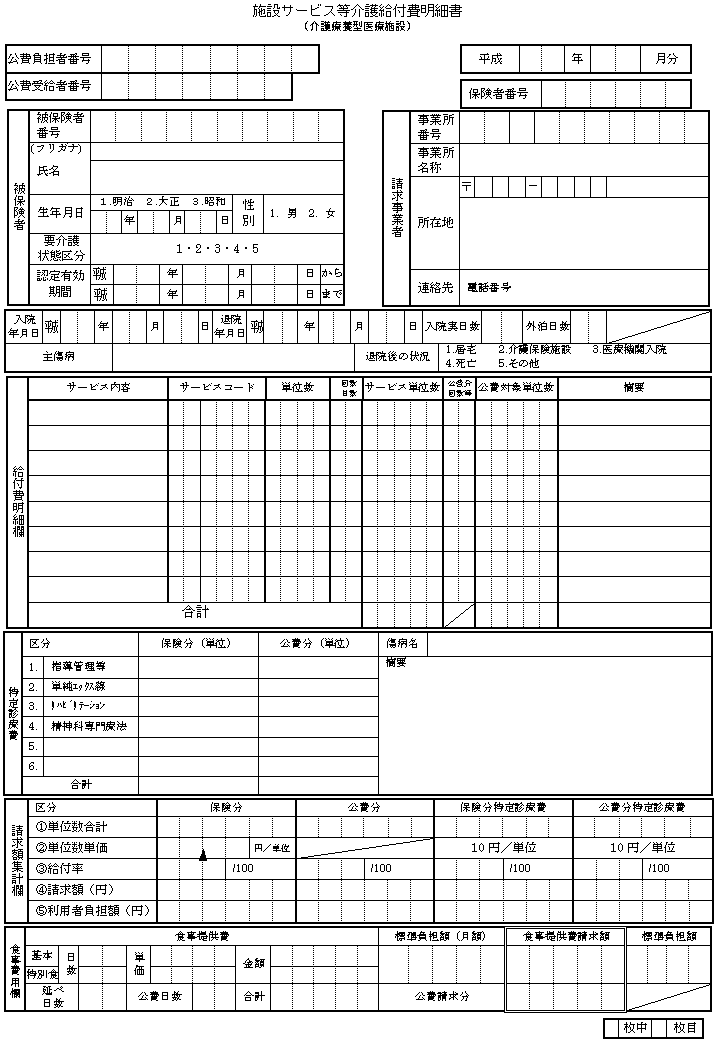
(PDF:6KB)