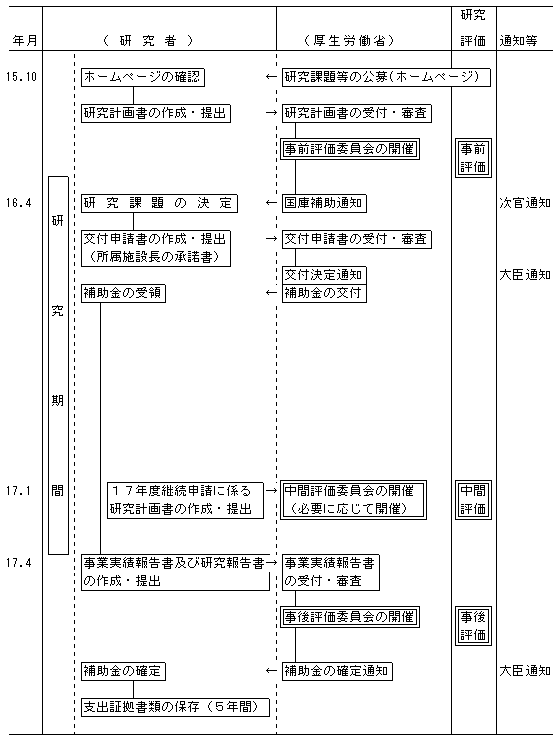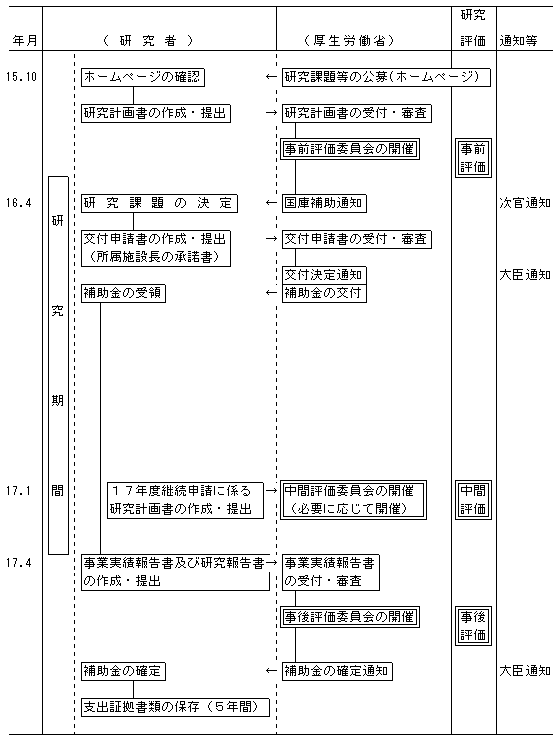| |
| (1) |
健康づくりに関する研究分野
健康増進法を基盤とする国民の健康の増進、生活習慣病に着目した疾病予防の推進のため、栄養学的研究、肥満等の一次予防に関する研究、地方健康増進計画支援に関する研究、喫煙に関する調査研究、健康づくり関連施設等に関する研究を進め、科学的根拠の蓄積を図る。
| (ア) |
健康づくりのための個々人の身体状況に応じた適切な食事摂取に関する栄養学的研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、食事摂取、咀嚼、消化・吸収、代謝、身体活動等との関連に関する研究であり、食事摂取基準及び個々人に応じた適切な栄養管理に資する具体的な手法(アセスメント等)の開発を含めた総合的な栄養学的研究(動物実験を含まない研究)を優先する。
研究費の規模:1課題当たり30,000千円〜50,000千円程度(1年当たり)
研究期間:3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
| (イ) |
健康づくり及び肥満・糖尿病等の一次予防のための身体活動に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、ヘルスプロモーションの一環として身体活動の評価指標及び介入手法の開発、環境整備の効果測定等に関する総合的な研究(疾患を有する者を対象とした臨床的な研究ではなく、健康づくり及び一次予防を主眼とした研究)を優先する。
研究費の規模:1課題当たり10,000千円〜20,000千円程度(1年当たり)
研究期間:3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、地方健康増進計画を目標値だけでなく、計画策定や実行状況について定量的評価を含む具体的かつ実用的な支援手法の開発に関する研究のうち、国の支援及び推進方策の提言を含む研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり10,000千円〜15,000千円程度(1年当たり)
研究期間:3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、未成年者の喫煙状況を全国規模で疫学的手法を用いて把握すると共に、未成年者の喫煙に関連する環境要因や行動要因に基づく、未成年者に有効な喫煙対策の手法の開発に関する研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり10,000千円〜15,000千円程度(1年当たり)
研究期間:3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
| (オ) |
農村地域における身体活動・食生活等の生活習慣環境要因の影響に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、身体活動、栄養摂取、家族形態、ヘルスプロモーションへの取組状況等の生活習慣に関する要素を農村地域間及び農村地域都市地域間で比較を行い年齢、業態別での農村地域における特徴を分析し、今後の農村地域における生活習慣病対策の資とする研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり5,000千円〜10,000千円程度(1年当たり)
研究期間:2年
新規採択予定課題数:2〜3課題程度
|
|
| (2) |
地域保健サービスに関する研究分野
激変する社会状況に対応した地域保健サービスに関する事業を実施するために必要な、地理及び社会状況を加味した地域分析に関する研究、人的ネットワーク分析による新たな普及啓発に関する研究及び地方衛生研究所における基盤的な役割に関する研究等の地域保健サービス実施にあたっての基礎を確立する。
| (ア) |
地理及び社会状況を加味した地域分析方法の開発に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、保健医療福祉情報に加えて地理情報及び社会文化情報に関する情報を収集し、各情報間における関係を含めた分析を行い、その結果に基づきG-XML等を用いたGISシステムと統合された地域分析を支援する情報処理分析システムの開発に関する研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり30,000千円程度(1年当たり)
研究期間:3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
| (イ) |
地域における新たな普及啓発方法の開発に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、国民が形成する種々の人的ネットワークの構成、特性、情報伝達等の実態調査分析及び個々の地域保健対策に応じた人的ネットワークの効率的活用に関する研究のうち、情報科学及び情報工学による研究分析を含むものを優先する。
研究費の規模:1課題当たり30,000千円程度(1年当たり)
研究期間:3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
| (ウ) |
地方衛生研究所における公衆衛生に係る基盤的な役割検討について |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、地方衛生研究所における人員体制、機器設備、対応能力、保健所・国立研究機関との連携体制等の実態把握及び諸外国における地方衛生研究所機能をもつ機関との比較を行い、今後必要となる地方衛生研究所の機能、設備、人員等の体制に関する研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり20,000千円程度(1年当たり)
研究期間:3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、地域における保健所機能、保健指導、地域保健活動、地域保健従事者の資質の向上等に関る研究であること。
研究費の規模:1課題当たり5,000千円〜10,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:1〜2課題程度 |
|
| (3) |
地域における健康危機管理に関する研究分野
健康危機発生時における迅速な初動体制の確保と効率的な対応を確立するために、健康危機発生時における通信連絡体制に関する研究及び健康危機管理担当者の資質の向上を効率的に行うための育成カリキュラムの開発を行い健康危機発生時の迅速かつ適切な対応の基礎の確立を行う。
| (ア) |
地域における健康危機発生時等の通信連絡に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、地域における健康危機対策においての情報通信連絡(携帯型通信端末を含む。)に関する体制、機器、施設等に関する実態把握及び、地域における健康危機管理情報通信連絡に必要な体制、機能、機器等のガイドライン等の作成に関する研究のうち、必要機器機材等の開発を含む研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり40,000千円程度(1年当たり)
研究期間:3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、保健所長及び保健所職員等の健康危機感対策に関する職員の資質の向上のための研修大系及び具体的研修カリキュラムに関する研究であり、諸外国における健康危機研修に関する調査分析を含む研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり10,000千円〜15,000千円程度(1年当たり)
研究期間:2年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
|
| (4) |
生活環境に関する研究分野
室内空気汚染による健康被害、循環式浴槽の浴用水の浄化殺菌方法、生活衛生関係営業の評価手法、その他生活衛生に関する研究を行い、生活衛生の向上及び増進を図る。
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、WHO空気質ガイドラインを踏まえた諸外国における室内空気質規制に関する研究、特定建築物における屋内化学物質汚染実態に関する研究、室内空気汚染による健康被害を主訴とする患者の受療行動等に関する研究、屋内化学物質低減対策が経済社会に及ぼす影響(費用効果分析、費用便益分析等を含む)に関する研究等、室内空気汚染等による健康被害に関し、現状調査分析を中心とした研究であり、その成果が今後の行政施策の推進に資する研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり10,000千円〜15,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:1〜3課題程度 |
| (イ) |
循環式浴槽における浴用水の浄化・殺菌方法の最適化に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、循環式浴槽設備における循環浴槽水の浄化・殺菌方法について、現行用いられている簡易な砂ろ過とその直前に行う塩素消毒による浄化・殺菌方法が十分検証され、かつ、レジオネラ属菌等の汚染指標を用いた他の物理ろ過や生物ろ過等の新た方法の開発を含んだ、循環浴槽水の浄化・殺菌方法の最適化に資する研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり10,000千円〜20,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
| (ウ) |
生活衛生関係営業の衛生水準向上のための経営評価手法等に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法第164号)」の趣旨を踏まえ、かつ生活衛生関係営業の経営手法の実態を踏まえた研究であり、研究成果が都道府県生活衛生指導センターにおける経営指導事業の導入、及び国民生活金融公庫等金融機関における生活衛生関係営業に対する融資審査手法の改善に資する研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり5,000千円〜10,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1年
新規採択予定課題数:1課題程度 |
| (エ) |
その他生活環境における衛生的環境の確保に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、建築物衛生、生活衛生関係営業等に関する研究であり、生活衛生の向上及び増進に資する研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり10,000千円〜15,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:1〜3課題程度 |
|
| (5) |
健全な水循環の形成に関する研究分野
水利用のシステムを水循環系の中で再構築し水利用の合理化を進め、河川、下水道及び環境への負荷を軽減することで健全な水循環を形成するため、家屋スケール及び地域スケールの水利用システムにおける水の有効利用に関する研究を行うとともに、未利用エネルギーの活用や環境管理手法の体系化等、各システムの性格に応じた環境負荷低減に関する研究を行う。また、併せて、水利用のシステムの起点として不可欠である水道水源を保全するため、政策手法や水源水質の監視に関する研究を行う。
なお、本研究事業(健全な水循環の形成に関する研究分野)は、平成14年度から開始された事業であり、総合科学技術会議分野別推進戦略(環境分野)の重点課題のうち自然共生型流域圏・都市再生技術研究のフォローアップ体制のもと関連プロジェクトとの連携を適切に図っていくこととしている。
| (ア) |
最新の科学的知見に基づく水質基準の見直し等に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、厚生科学審議会答申「水道水質基準の見直し等について」(平成15年4月)において今後の課題とされた調査研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり10,000千円〜100,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:1〜3課題程度 |
| (イ) |
地域性を考慮した水道の適正技術に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、水道関連調査研究検討会の「水道分野の調査研究の方向性について中間とりまとめ」(平成15年8月)https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/kentoukai/index.html「小規模水道や末端施設等の施設・設備の整備・管理に関する研究」、「水道に関連する国際的な課題に関する研究」及び「浄水処理技術に関する研究」を踏まえた研究を優先する。
研究費の規模:1課題当たり1,000千円〜10,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:1〜2課題程度 |
| (ウ) |
水道水源の保全のための政策手法等に関する研究 |
<新規課題採択方針>
| |
水道水源を保全するための効果的な政策手法等、健全な水循環の形成及び安全な水道水の安定供給に資する研究を積極的に評価。(昨年度採択指針より)
研究費の規模:1課題当たり1,000千円〜5,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:1〜2課題程度 |
<新規課題採択方針>
| |
課題採択にあたっては、「水道ビジョン」の具現化に当たり参考となる課題を優先する。
研究費の規模:1課題当たり1,000千円〜2,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:1〜2課題程度 |
|
|