| ┌ | | | | | | └ |
<化審法の審査対象外となるもの>
|
┐ | | | | | | ┘ |
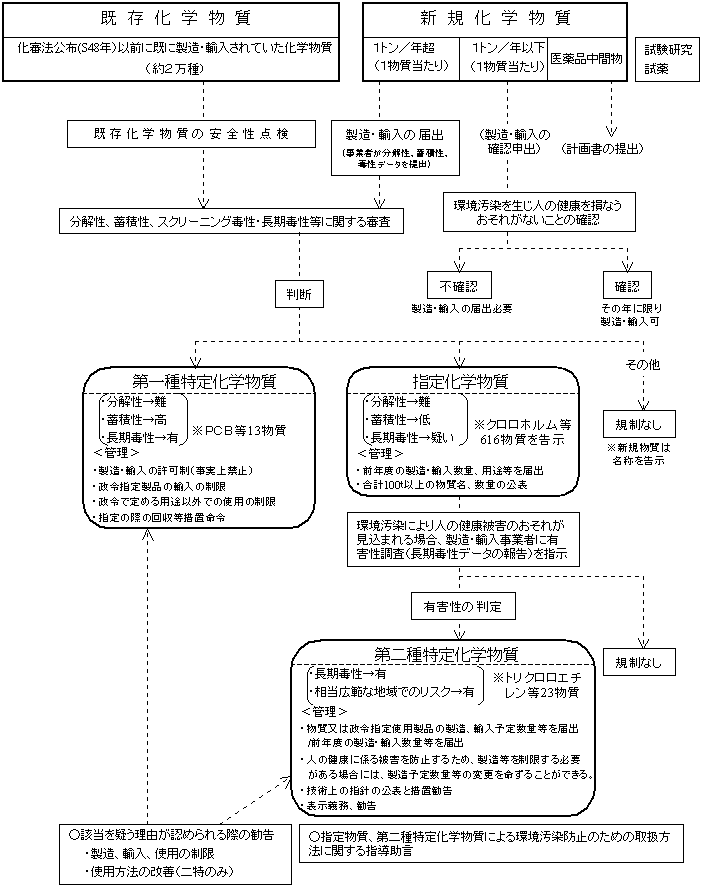
4−1.現行の事前審査・規制制度の概要
(1) 化学物質審査規制法に基づく審査・規制のスキーム
|
|||
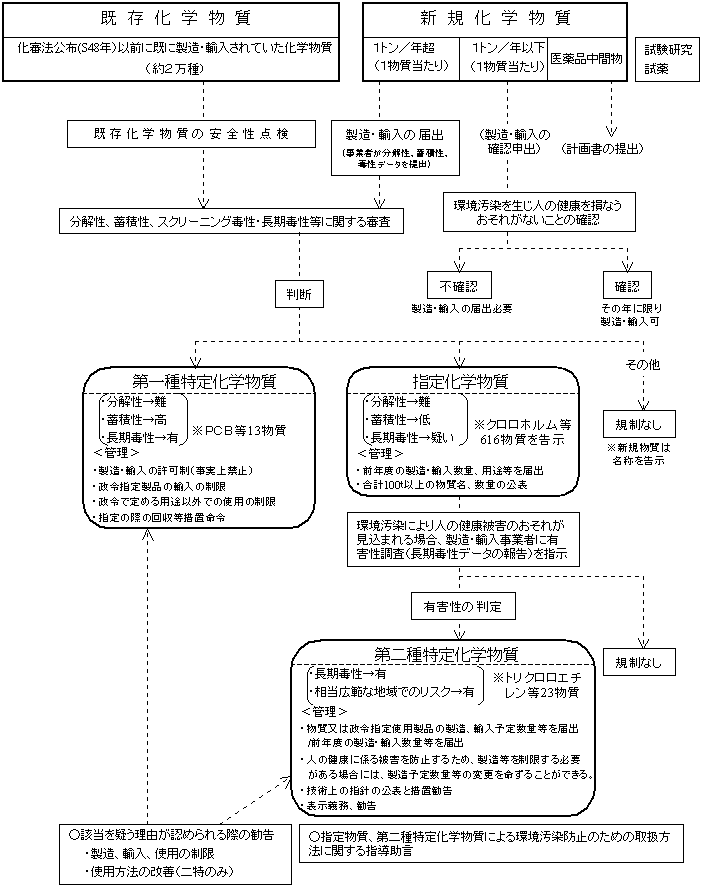 |
(2) 化学物質審査規制法の概要について
| 1.経緯 |
| (1) | 化学物質審査規制法は、難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、昭和48年(1973年)に制定された法律。新規の化学物質の事前審査制度を設けるとともに、PCBと同様、難分解であり高蓄積性を有し、かつ、長期毒性を有する化学物質を特定化学物質(現在の第一種特定化学物質)に指定し、製造、輸入について許可制をとるとともに使用に係る規制を行うこととされた。 |
|
| (2) | その後、難分解性及び長期毒性を有するにもかかわらず蓄積性を有さない物質についても、環境中での残留の状況によっては規制の必要性が生じたことから、昭和61年(1986年)に化審法が改正され、指定化学物質及び第二種特定化学物質の制度が導入された。 |
| 2.概要 |
|
(1) 新規化学物質の審査 これまで我が国で製造、輸入が行われたことのない新規化学物質については、製造又は輸入に際し、事業者からの届出に基づき事前にその化学物質が次の性状を有するかどうかを審査し判定を行っている。
なお、薬事法の許可に係る医薬品の中間物として製造又は輸入する場合並びに、製造量及び輸入量が全国で年間1トン以下の化学物質(少量新規化学物質)であって、事業者からの申出に基づいて確認を行い、既知見等から判断して環境汚染を生じ人の健康を損なうおそれがない場合には、上記の届出を要しないこととしている。 (2) 規制 化学物質の性状に応じて、それぞれ以下の措置を講じることとされている。
(3) その他の措置
|
(3) 化学物質審査規制法における審査項目に係る試験法について
| 分解度試験(微生物等による化学物質の分解度試験) |
化学物質が環境中に放出されたとき自然的作用(主に微生物の作用)により変化を受けるかどうか調べるための試験。
被験物質溶液に活性汚泥を接種して原則28日間培養し、酸素消費量の変化を経時的に測定する等により分解性を評価する。易分解性の判断基準はOECDテストガイドラインの酸素消費量に基づく分解度で60%以上を目安としている。
| 濃縮度試験(魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験) |
魚介類への化学物質の濃縮性の程度を調べるための試験。
ヒメダカ、コイ等を用いて、魚に著しい生理的障害を与えない濃度で、28日間又は定常状態に達するまで(最長60日間)試験を実施。設定した水中濃度と測定した被験物質の魚体中濃度から、魚介類への濃縮倍率を算出する。高濃縮性の判断基準としては第一種特定化学物質であるPCB等の濃縮倍率やPOPs条約等を踏まえ、濃縮倍率5000倍を一つの目安としている。
| スクリーニング毒性試験 |
化学物質審査規制法では長期毒性予測のためのスクリーニング毒性試験として、「ほ乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験」、「細菌を用いる復帰突然変異試験」、「ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験」を選択している。
| (1)ほ乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験 | 化学物質による生体の機能、形態の変化を調べるための試験。ラットの雄及び雌を使用し28日間連続して経口投与を行い、死亡率、出現する変化、最大無作用量、可逆性(2週間の回復期間における毒性影響の変化の様相、遅発性影響の発現)の程度等を評価する。 | |
| (2)変異原性試験 | 化学物質の発がん性等を予測するための試験。 | |
| 細菌を用いる復帰突然変異試験(エームス試験) | ネズミチフス菌及び大腸菌を使用し、復帰突然変異コロニー数の計測により突然変異誘発性を評価する。 | |
| ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験 | チャイニーズハムスター線維芽細胞株等を使用し、染色体異常を持つ細胞の出現率等により染色体異常誘発性を評価する。 | |
| 長期毒性の判定の際の評価項目 |
化学物質が継続的に摂取される場合に人間の健康をそこなうおそれがあるものであるかどうか(長期毒性の有無)についての判定は、以下の試験を実施し、その試験成績に基づいて行うものとされている。
| 慢性毒性試験 | 動物に被験物質を長期間(12ヶ月以上)連続投与したときに現れる生体の機能及び形態等の変化を観察することにより、被験物質の慢性毒性を明らかにするための試験。 |
| 生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験 | 動物の雄及び雌に被験物質を多世代にわたり投与し、被験物質の生殖能及び後世代の発生に及ぼす影響を明らかにするための試験。 |
| 催奇形性試験 | 胎仔の器官形成期に妊娠動物に被験物質を投与し、被験物質の胎仔の発生に及ぼす影響、特に催奇形性を明らかにするための試験。 |
| 変異原性試験 (げっ歯類を用いる小核試験) |
比較的簡便な短期間の試験により、被験物質の発がん性等を予測するための試験。必要に応じ、スクリーニング毒性試験の二試験にげっ歯類を用いる小核試験を追加する。 |
| がん原性試験 | 動物に被験物質をほぼ一生涯にわたる期間連続投与し、被験物質のがん原性の有無を明らかにするための試験。 |
| 生体内運命に関する試験 | 動物に被験物質を投与し、吸収、分布、蓄積、代謝、排泄等を調べることにより、被験物質の生体内における動態を把握するための試験。 |
| 薬理学的試験 | 被験物質の薬理学的特性を明らかにするための試験。 |
| 高分子フロースキーム |
高分子化合物については、化学物質審査規制法における分解度試験や濃縮度試験等の適用が馴染まないこと、欧米においても一般の化学物質とは異なる措置が講じられること等を踏まえ、数平均分子量1000以上で分子量分布を有し、溶解度、融点等が明瞭でない等の特色を有することが確認される場合には、以下の安全性の評価方法が用いられている。
|
(1)安定性試験(生分解性、物理化学的安定性、酸・アルカリ溶解性) 自然環境中での安定性を調べるため、光、熱、水及びpHの変化によって測定方法に起因する誤差範囲以上の重量変化がないことの確認を行う(変化がある場合には、赤外吸収スペクトルにより構造変化がないことを確認。)。 (2)溶解度試験 生体内への取り込みの可能性を評価するため、水、親脂溶性溶媒(生体内脂質類似)及び汎用性溶媒(自然環境中で曝露可能性のあるもの)に対して測定方法に起因する誤差範囲以上の重量変化がなく不溶であること、特定構造(架橋構造、結晶性等)の有無、酸・アルカリに不溶であることについて確認を行う(溶解性がある場合には、分子量1000未満の成分含有が1%以下で高蓄積性を示唆する知見がないことの確認。)。 |
なお、重金属を含まない、化学構造と長期毒性との関連性に関する知見等から判断して、長期毒性を有すると示唆されないことの確認も行われる。
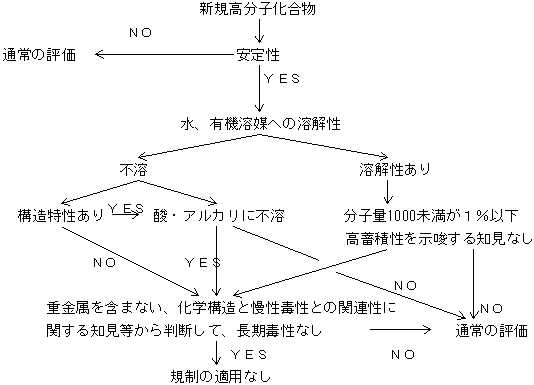
(4) 第一種、第二種特定化学物質の指定状況
○第一種特定化学物質
| 物質名 (政令指定日) |
用途 | 製造時期 (国内) |
指定までの経緯 |
| ポリ塩化ビフェニル (昭49. 6. 7) |
絶縁油 潤滑油 感圧複写紙 塗料 等 |
昭和29年頃〜47年 |
|
| ポリ塩化ナフタレン(PCN) ヘキサクロロベンゼン(HCB) (昭54. 8.14) |
潤滑油 木材用防腐剤 木材用防虫剤 塗料 等 |
PCN 昭和15年 〜50年 HCB 昭和27年 〜47年 |
|
| アルドリン ディルドリン エンドリン DDT (昭56.10. 2) |
木材用防腐剤 木材用防虫剤 塗料 等 |
〜昭和55年 |
|
| クロルデン類 (昭61. 9.17) |
白アリ防除剤 木材用防腐剤 木材用防虫剤 塗料 等 |
昭和30年代〜61年 |
|
| ビス(トリブチルスズ)=オキシド (平元.12.27) |
防腐剤 かび防止剤 塗料 漁網防汚剤 等 |
昭和40年代後半 〜63年 |
|
| N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N'-キシリル-パラ-フェニレンジアミン、又はN,N'-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン (平12.12.27) |
ゴム老化防止剤 | 〜平成5年 |
|
| TTBP (平12.12.27) |
酸化防止剤 (潤滑油、燃料油用) |
輸入のみ |
|
| トキサフェン マイレックス (平14. 9. 4) |
(トキサフェン) 殺虫剤 (マイレックス) 木材用防虫剤 難燃剤 |
製造、輸入 実績なし |
|
○第二種特定化学物質
| 物質名 (政令指定日) |
用途 | 製造時期 (国内) |
指定までの経緯 |
| トリクロロエチレン (平成元. 3. 29) |
洗浄剤 金属加工油 接着剤 塗料 等 |
〜現在 |
|
| テトラクロロエチレン (平成元. 3. 29) |
洗浄剤 加硫剤 接着剤 塗料 繊維仕上剤 等 |
〜現在 |
|
| 四塩化炭素 (平成元. 3. 29) |
洗浄剤 塗料 接着剤 等 |
〜現在 |
|
| TPT化合物 7物質 (平成元. 12. 27) |
防汚塗料(船底、漁網用) 農薬 等 |
〜平成8年 |
|
| TBT化合物 13物質 (平成2. 9.12) |
防汚塗料(船底、漁網用) 防腐剤 かび防止剤 等 |
〜平成10年 |
|
(5) 欧米における化学物質の事前審査制度について
| 1.米国有害物質規制法(TSCA)における事前審査制度について |
|
1) 事前審査の対象とする化学物質の範囲
2)新規化学物質の審査(有害性項目)
3) 主な規制措置 TSCAにおいては、新規化学物質の申請者と評価の各段階で同意を取りながら進めていくという審査体系となっており、上記(1)、(2)のような懸念のある化学物質に対する規制は、個別の申請毎にきめ細かい措置を講じられる体系となっている。 |
| 2.EUにおける事前審査制度について |
|
1) 事前審査の対象とする化学物質の範囲 「危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関する指令(67/548/EEC)」においては、医薬品や農薬等、最終使用者向けを意図した調剤で届出・認可手続きが存在し要件が同指令と同等であるものは指令の適用除外とされている。 (1)完全届出
(2)少量届出
(3)届出不要
2) 新規化学物質の事前審査(有害性項目) EU指令に基づき定められた各国制度において、1)で示した数量に応じて届け出られる物質の固有の性質を記述する技術的文書(上市量に応じた内容)に基づき有害性の評価が行われる。さらに、一定程度以上の有害性が認められる場合には、人の健康及び環境への影響に関するリスク評価が行われる。必要な場合は追加情報、追加試験を要求できることとなっている。 3) 主な規制措置 届出物質に対しては、試験結果による有害性情報及び分類基準に基づき、必要に応じ危険有害性の分類及び表示(リスク警告)が行われる。また、リスク評価の結果を踏まえ、必要に応じて個別の化学物質毎にリスク削減のための措置が求められることとなる。 |