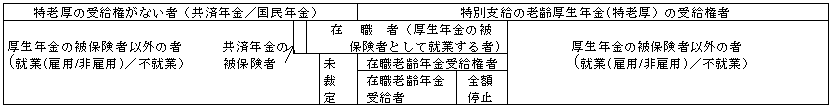
| II 60歳前半層における在職者(厚生年金被保険者として就労している者)の状況等 |
|
(図5) |
(1) 平成12年における「特老厚」の受給権者(受給する資格を有する者)は、386万人(60歳前半層の高齢者の2人に1人(50.3%)。
(2) 「特老厚」の受給権者に占める在職者は、89万人。
(3) 特老厚受給権者に占める在職者の割合(すなわち、「厚生年金の受給資格を有する60歳前半層の高齢者」のうち「厚生年金の被保険者として就労している者」の割合)は、4人に1人(23.1%)。
(4) これは、60歳前半層の高齢者(この中には、厚生年金被保険者となったことのない者や自営業者も多く含まれる)に占める「被用者年金の被保険者数」の割合(20.7%)とほぼ同じである。
(用語の補足説明)
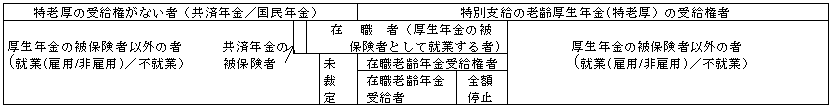
(図5)
60歳台前半層の者にかかる被保険者数等の状況(平成12年度)
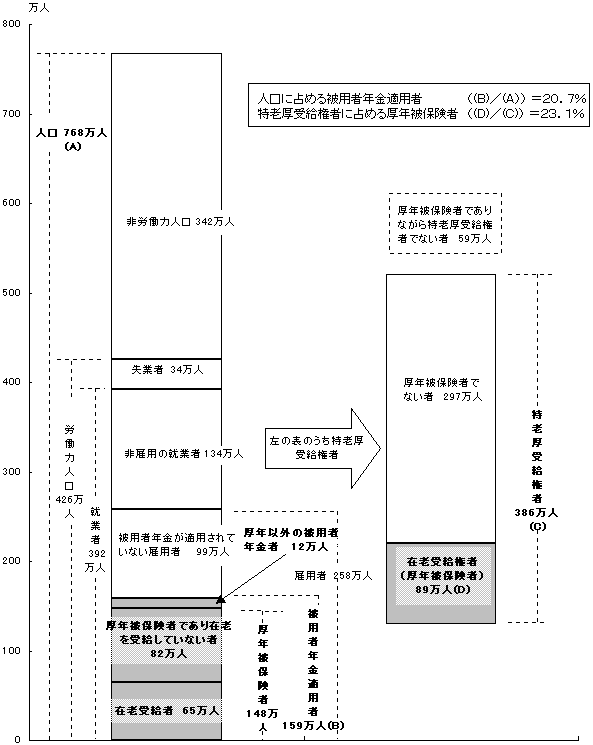 |
| 出典:「労働力調査」(総務省統計局)、「事業年報(H12)」(社会保険庁)、「特老厚受給権者」は社会保険庁調べ |
| (注) | 1. | 端数の調整等により数値が合計値と合致しない場合がある。 |
| 2. | 「厚年被保険者でありながら、特老厚の受給権者でない者」※が59万人いることに留意。仮に、59万人全てが「特老厚の受給資格を有しながら年金の請求をしていない者」とした場合、特老厚受給権者と前述の未請求者に占める厚年被保険者の割合は33.2%となる。 | |
| 3. | 「在老受給者」には、坑内員・船員の特例により、60歳より前で年金を受給している者を含む。 |
※例:「特老厚の受給資格を有しながら年金に請求をしていない者」、「公務員OBで60歳以降初めて厚年被保険者となった者」等
|
(図6、図7) |
(1) 本来の年金月額(注1)の分布をみた場合、一般の受給権者である「特老厚の受給権者」、厚生年金の被保険者として就業している「在職老齢年金受給権者」ともに、約8割が月20万円未満となっている。(図6)
(2) ただし、在職老齢年金受給権者においては本来の年金額が相当低い者(5万円未満の者)の割合が低い(従前の職業履歴(注2)が60歳以降に厚年被保険者として働く割合の低さとして反映されている可能性が考えられる)。(図6)
(注1) 在職老齢年金制度による調整が行われる前の年金の額(すなわち、就労しなければ得られるであろう満額の年金額)。
(注2) 例えば、(1) 比較的若い時期に雇用労働者から自営業に転じたり、(2)結婚までの一時期のみ雇用労働者として就労し、その後は無業やパートタイム労働者に転じたような場合、年金額は低いものとなる。
(3) 「特老厚受給権者に占める在職者の割合」を本来の年金月額別をみた場合、年金額が多いほど在職者割合も緩やかに高まる傾向。ただし、女性にあっては、年金額が相当低い場合(5万円未満)、当該割合は大きく低下。(図7)
(4) 年金額がかなり低い場合には「特老厚受給権者に占める在職者の割合」も低い傾向が見受けられ、特に女性において顕著である((1)と同様の可能性が考えられる)。(図7)
(用語の補足説明)
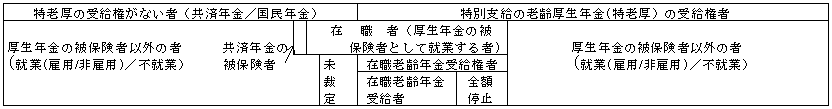
(図6)
特老厚・在老受給権者の分布(本来年金額別)
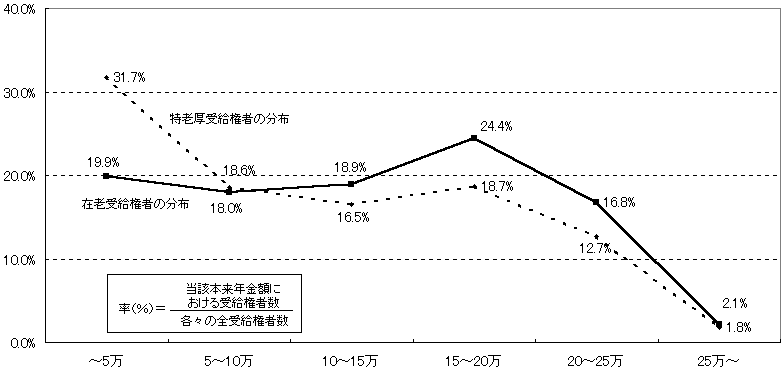 |
社会保険庁調べ(平成12年度) |
(図7)
特老厚受給権者に占める在職者の割合(平成12年度)
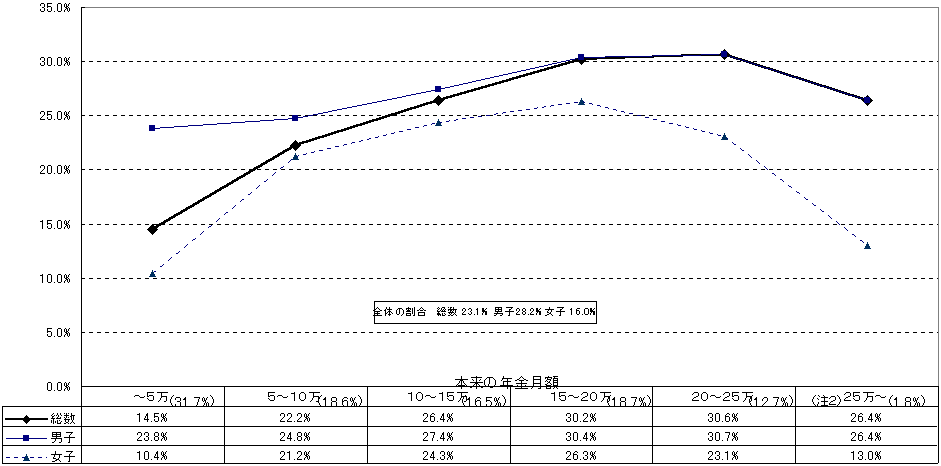 |
| 社会保険庁調べ(平成12年度) |
(注1)「本来年金月額」欄の括弧内のパーセンテージは、特老厚受給権者総数に占める当該階級における受給権者の割合である。
(注2)「25万~」については、サンプル数が少ないことに留意。
|
(図8、図9、図10) |
(1) 在職老齢年金受給権者全体について、本来の年金額と賃金毎の分布状況をみた場合、おおむね年金額20万円未満、賃金(標準報酬)24万円未満の範囲で就業する者の構成割合が高い。(図8)
(2) 在職老齢年金を受給している者(=「特老厚」を受給する権利を有する者のうち厚生年金被保険者として就業している者)について、各「本来の年金額」階層毎に「標準報酬」の分布状況をみた場合、(図9)
(1) 本来年金額が低い者ほど、低い賃金(標準報酬)での就労が多い傾向。
(2) 在職老齢年金受給権者の賃金(標準報酬)についてみた場合、最も多いのは標準報酬15.0万円~19.0万円(21.3%)、次いで20.0~ 24.0万円(18.9%)、10.4~14.2万円(15.4%)、50.0万円~(12.0%)である。
(3) 各年金額階層を比較した場合、次のような特徴がうかがわれる。
(ⅰ) 各本来年金額階層を通じ、最低賃金レベルの低い標準報酬で働く者の割合は、ほぼ一定である。
(ⅱ) 年金額の高い一部の層を除き、各年金額階層を通じ低賃金の者が比較的多い。
(ⅲ) 「本来年金額」が高い層(上位2割)では、標準報酬分布が山形ないし台形の分布を描くことなくなだらかである。
また、全体の2割を占める年金額20万円以上の層では、高額の標準報酬を得ている者の割合が顕著に高まる。
(注2) これについては、
(1) 賃金が、在職老齢年金制度によって年金が全額カットされる水準よりも高い場合は、賃金の増加がそのまま手取りに反映されること、
(2) 稼得能力が高い者ほど、在職老齢年金制度を意識し、年金を多く受給するために賃金抑制することによるデメリットも高まること、に留意する必要があるのではないか。
(3) 標準報酬月額分布をみた場合、厚生年金被保険者(全年齢層)とは異なり、月額20万円前後のほかに月額15万円付近にも分布のピークがある(在老受給権者については、賃金水準の二極分化傾向がうかがわれる)。(図10)
(図8)
在老受給権者(本来年金額・標準報酬月額別)分布
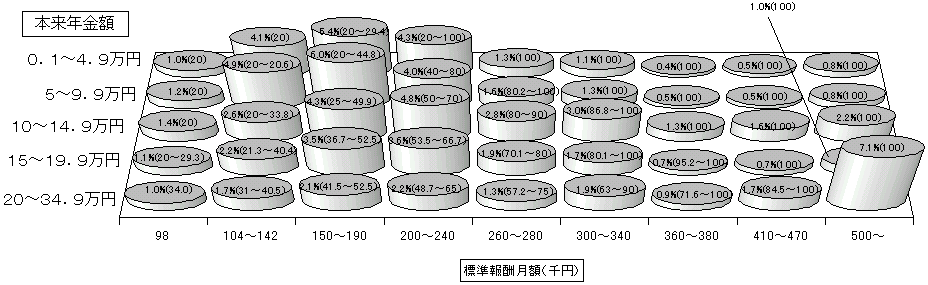 |
| 社会保険庁調べ(平成12年度) |
(注)グラフの各円柱上の率は、全在老受給権者に占める、当該「標準報酬月額」、「本来年金額」の在老受給権者の割合を示し、括弧内の数値は在老調整による年金額の支給停止率を示したものである。
(図9)
在職老齢年金受給権者の分布(標報、本来年金額別)
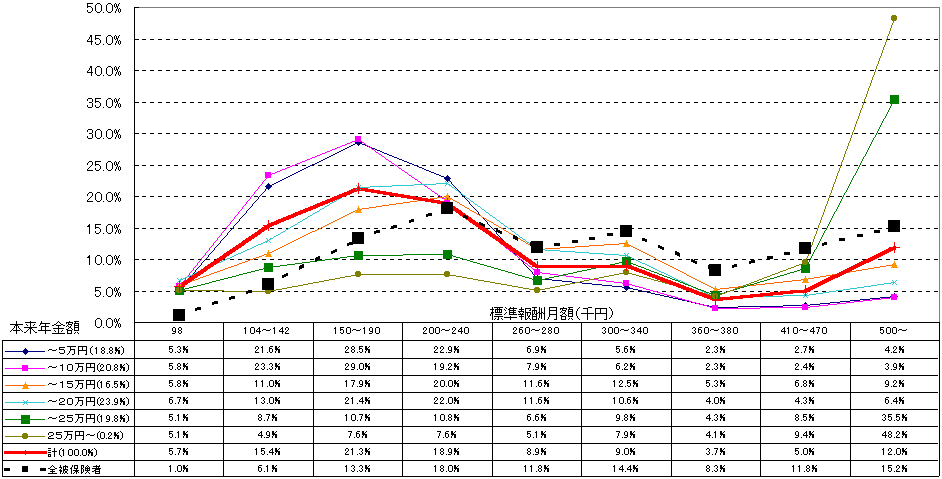 |
| 出典:全厚年被保険者の分布は、「平成12年度事業年報(社会保険庁)」それ以外のデータは社会保険庁調べ(平成12年度) |
(注)「本来年金額」欄内の括弧内の割合は、当該階級における受給権者の分布割合である。
(図10)
厚生年金被保険者(全年齢)、在老受給権者の分布(標準報酬月額別)
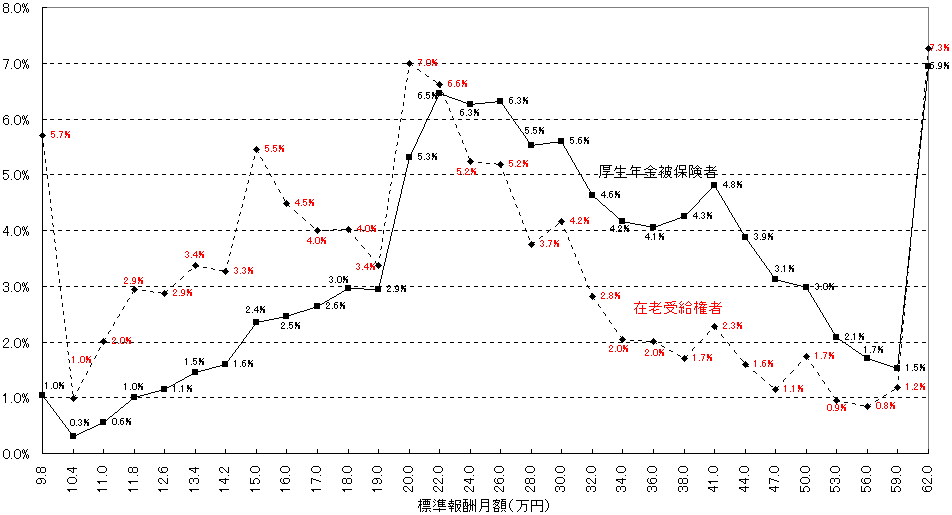 |
| 出典:「平成12年事業年報」(社会保険庁) |
|
|
|
(図11) |
年金が全額停止になっている「特老厚の受給権者」(すなわち、「特別支給の老齢厚生年金」の受給権を放棄して、厚生年金の被保険者として就労している者)の状況。
(1) 受給権者全体に占める全額支給停止者の割合は、24.7%(すなわち、在職者のうち、年金を実際に受給している者としていない者の比率は、3:1)。
(2) 本来の年金額階層別に全額停止者の分布をみれば、
(ⅰ) 年金額が低い場合には、全額停止となる者の割合は低い傾向。
(ⅱ) 年金額が「20万円未満」までの層においては、全額停止者の割合は最大で2割程度。
(ⅲ) 年金額が20万円程度以上(上位2割)の階層においては、全額支給停止者の割合が急激に高まる。
(用語の補足説明)
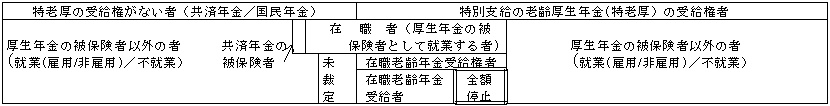
(図11)
年金が全額支給停止になっている在職老齢年金受給権者の割合(平成12年度)
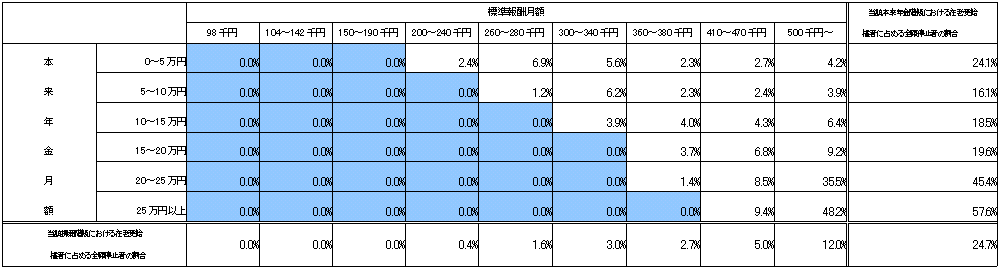 |
| 全額停止者数は、「社会保険庁調べ」の数値を基に推計したもの。 |
(注)上記の割合は、各本来年金月額階級毎の在老受給権者数を100%とした場合の割合である。
|
(図12、図13) |
(1) 「平成12年 高年齢者就業実態調査」によれば、高齢者を雇用する事業所の半数弱(45.6%)において、在職老齢年金受給権者に対し、賃金・労働時間に関し「何らかの措置を講じている」。(図12)
このことが、人的資源の有効活用の阻害要因となっている可能性があり得る。
(2) 具体的には、調整ルール上の屈折点等に着目した調整や、年金と賃金を合わせた手取額を一定以上にするための調整が行われている。(図12)
(ⅰ) 合算額22万円ライン(→カット額最小限)
(ⅱ) 標準報酬37万円ライン(→賃金増加分全額カットの回避)
(ⅲ) 手取額を一定額以上にする
(ⅳ) その他
(2) 企業規模別にみれば、規模が大きいほど「何らかの措置を講じている」事業所の割合が高くなる傾向。
(3) 高齢者雇用の取組別に「何らかの措置を講じている」企業の割合をみれば、「勤務延長又は再雇用制度がある」事業所では53.9%で、全体(45.6%)と比べ2割近く高い。(図13)
(今後、60歳前半層の再雇用・雇用延長がさらに進展するにつれて、調整行動をとる事業所は拡大する可能性があるのではないか。)
(図12)
企業規模別の在職老齢年金受給権者に係る賃金・労働時間に関する措置(平成12年)
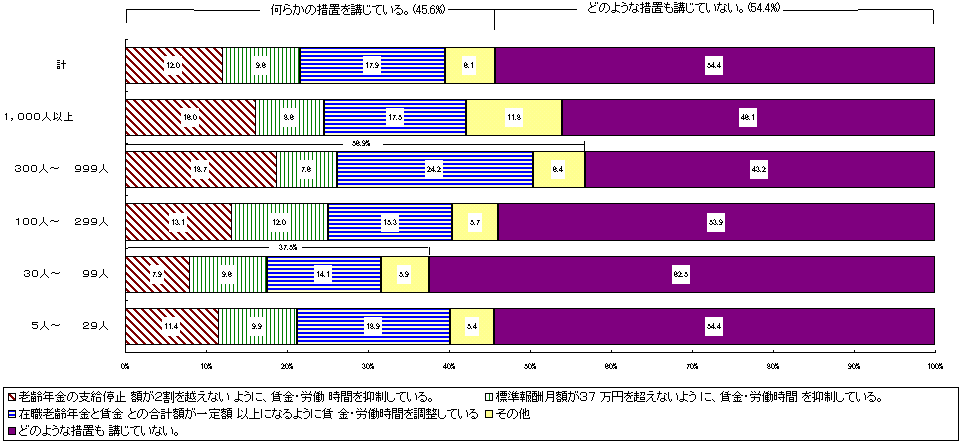 |
| 出典:「平成12年高年齢者就業実態調査」(厚生労働省大臣官房) |
(注) 選択肢中、
(1)「老齢年金の支給停止額が2割を越えないように賃金・労働時間を抑制している」場合は、年金額の2割カットのみで、賃金の増加2に対し年金1が減額される調整は行われないこととなり、
(2) 「標準報酬月額を37万円を超えないように賃金・労働時間を抑制している」場合には、賃金額が37万円を超す場合の賃金増加分に対する調整が行われないこととなる。
(図13)
定年制等が有る事業所の在職老齢年金受給権者に係る賃金・労働時間に関する措置(平成12年)
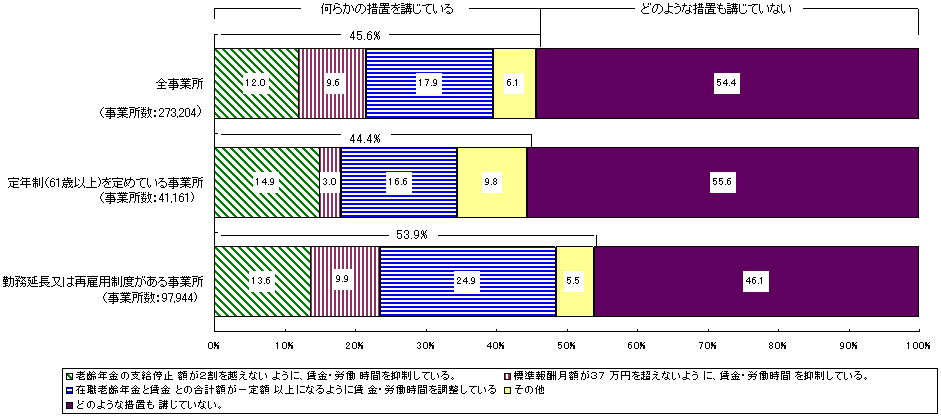 |
| 出典:「平成12年高年齢者者就業実態調査」(厚生労働省大臣官房) |