
介護医療院とは?
このページでは、介護医療院の創設経緯、他施設との違い、類型について説明しています
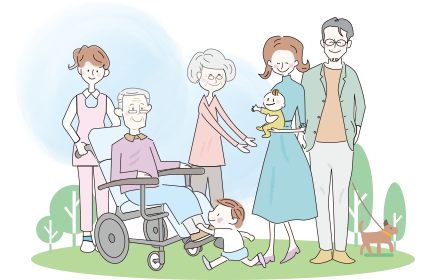
- TOP
- 介護医療院とは
創設経緯
2025年に向け、慢性期の医療ニーズに対応する今後の医療・介護サービス提供体制について、療養病床の在り方をはじめ、具体的な改革の選択肢の整理等を行うために「療養病床・慢性期医療の在り方等に関する検討会」において対応方針の検討を進めて参りました。
この検討を進めるに当たり、これまでの介護を必要とする介護保険施設入所者にも、医療の必要性の高低にかかわらず、病態によっては容体が急変するリスクを抱える方もあり、そうしたニーズに完全に対応可能な介護保険サービスが存在せず、そうした高齢者の増加が想定されているため新たな選択肢を検討する必要があるのではないかという問題意識がありました。こうした方のニーズを満たす新たな選択肢を検討するに当たっては、療養病床等の利用者像の整理と、それに即した機能の明確化が必要であり、具体的には、
- 経管栄養や喀痰吸引等の日常生活上に必要な医療処置や充実した看取りを実施する体制
- 利用者の生活様式に配慮し、長期療養生活をおくるのにふさわしい、プライバシーの尊重、家族や地域住民との交流が可能となる環境が整えられた施設
が必要と結論づけられました。
この後、「療養病床・慢性期医療の在り方等に関する検討会」での議論を経て、「社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会」で新たな施設類型についての制度的枠組みについて整理されました。具体的には、新たな施設類型は、利用者の状態や地域の実情等に応じた柔軟な対応を可能とする観点から
- 介護療養病床相当以上
- 介護老人保健施設相当以上
の大きく2つの類型を設けることが必要であるとされました。
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)」が2017年6月2日に公布され、介護保険法(平成9年法律第123号)が改正されたことに伴い、新たな介護保険施設として、「介護医療院」が創設されました。
役割・理念
当面の間、介護医療院は、療養病床等からの移行が見込まれますが、単なる療養病床等からの移行先ではなく、「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」として創設されました。介護医療院においては、「利用者の尊厳の保持」と「自立支援」を理念に掲げ、「地域に貢献し地域に開かれた交流施設」としての役割を担うことが期待されます。
具体的には、医療提供施設の側面も持ちながら生活施設としての役割を果たすために、ハード面として、パーティションなどの視線を遮るものの設置のみならず、ソフト面にも配慮したプライバシーの尊重などが求められています。
一方で利用者を支える観点から医療提供施設としては、要介護高齢者の長期療養・生活施設として、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)の2つのサービスを提供することができ、利用者の「看取り・ターミナル」を支えることも重要な役割のひとつと想定されています。
また介護医療院は、介護老人保健施設や特別養護老人ホームと同様に地域交流を基本方針として位置づけています。このため、介護医療院に参入しようとする事業者には地域の中でどういう役割を果たし、地域といかに交流をしていくのか等について、地域の住民に対し懇切丁寧に説明を行うことが求められます。閉鎖的な存在となることなく、地域交流やボランティアの受け入れなどに積極的に取り組むことで、介護医療院が地域に開かれた施設となると期待されます。
今後、急速に増えていくと予測される医療ニーズのある要介護高齢者の生活を医療と介護で支える施設として、介護医療院を運営する事業者・自治体に理念と役割を十分に理解していただき、地域の中で成熟し、さらなる努力を続けサービスの質の向上につながっていくことを祈ります。
他の介護施設との違い
介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。
要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
介護老人保健施設は、要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰・在宅支援を目指す施設です。
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、要介護高齢者のための生活施設です。
入居する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とする施設です。
施設基準・類型
施設基準について
介護医療院の施設基準については、医療を内包した施設系サービスの観点から、
- 面積基準は老人保健施設相当以上(8.0m² 以上)
-
プライバシーに配慮した環境整備
(多床室の場合でも家具やパーティション等による間仕切りの設置)
これらなどが求められ、
介護医療院は、生活施設としての機能を併せ持っていることが特徴です。
介護医療院は、原則として以下に掲げる施設基準をみたしている必要があります。
| 施設(第5条第1項) | 施設の基準(第5条第2項) |
|---|---|
| 療養室 |
|
| 診察室 |
|
| 処置室 |
|
| 機能訓練室 | 内法による測定で40m2 以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。 ただし、併設型小規模介護医療院にあっては、機能訓練を行うために十分な広さを有し、 必要な器械及び器具を備えること。 |
| 談話室 | 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 |
| 食堂 | 内法による測定で、入所者1人当たり1m2 以上の面積を有すること。 |
| 浴室 |
|
| レクリエーション・ルーム | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。 |
| 洗面所 | 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 |
| 便所 | 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 |
詳細はハンドブックのP.13をご覧ください。
施設類型について
介護医療院は、施設の人員基準から、
- Ⅰ型介護医療院:介護療養病床相当(主な利用者像は介護療養病床療養機能強化型AB相当)
- Ⅱ型介護医療院:老人保健施設相当以上(主な利用者像はⅠ型より比較的容体が安定した者)
の2つの類型を設けています。
介護医療院の開設許可は1つの介護医療院を単位として行われますが、介護医療院サービスを行う部分として認められる単位は原則60 床以下の「療養棟」単位です。1つの介護医療院でⅠ型・Ⅱ型を組み合わせることで、柔軟な人員配置やサービス提供を担保しています。
以下では基準省令や解釈通知に記載された、人員に関する基本的な基準についてご説明します。
| 人員配置 (指定基準) |
介護医療院 | 医療機関併設型介護医療院 | 併設型小規模介護医療院 (Ⅰ型・Ⅱ型) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ⅰ型) | (Ⅱ型) | (Ⅰ型) | (Ⅱ型) | ||
| 医師 | 48対1(施設で3以上) | 100対1(施設で1以上) | 48対1 | 100対1 | 併設される医療機関の医師により、当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは置かないことができる |
| リハビリ専門職 | 適当数 | 適当数 | 併設される医療機関の職員(病院の場合にあっては医師又はリハビリ専門職。診療所の場合にあっては医師)により、当該施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは置かないことができる | ||
| 薬剤師 | 150対1 | 300対1 | 150対1 | 300対1 | 併設される医療機関の職員(病院の場合にあっては、医師又は薬剤師。診療所の場合にあっては医師)により、当該施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは置かないことができる |
| 看護職員 | 6対1 | 6対1 | 6対1 | ||
| 介護職員 | 5対1 | 6対1 | 5対1 | 6対1 | 6対1 |
| 栄養士又は 管理栄養士 |
定員100以上で1人 | 定員100以上で1人 | 併設医療機関に配置されている栄養士又は管理栄養士により、介護医療院に栄養士を置かないことができる | ||
| 介護支援専門員 | 100対1(施設で1以上) | 100対1(施設で1以上) | 適当数 | ||
| 診療放射線技師 | 適当数 | 併設施設との職員の兼務を行うこと等により、適正なサービスを確保できる場合にあっては、配置しない場合があっても差し支えない | 併設施設との職員の兼務を行うこと等により、適正なサービスを確保できる場合にあっては、配置しない場合があっても差し支えない | ||
| 調理員、 事務員等 |
適当数 | 併設施設との職員の兼務や業務委託を行うこと等により、適正なサービスを確保できる場合にあっては、配置しない場合があっても差し支えない | 併設施設との職員の兼務や業務委託を行うこと等により、適正なサービスを確保できる場合にあっては、配置しない場合があっても差し支えない | ||
※介護療養型医療施設は令和6年3月31日で廃止になりました。
