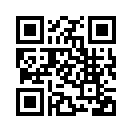ホーム > 報道・広報 > 広報・出版 > 広報誌「厚生労働」 > ニッポンの仕事再発見:機械込造型工 永瀬 勇さん
広報誌「厚生労働」
ニッポンの仕事、再発見!
機械込造型工
金属を鋳物に鋳造する仕事をてがける。加熱して溶かした金属を砂型に流し込み、冷えて固まった後、型から取り出して金属製品を製造する。現在は、工業用鋳物の製造が主流となっている。
スマホなど先進的工業製品の製造を陰で支える伝統的な鋳物の技
永瀬 勇
ながせ・いさむ
1947年、埼玉県生まれ。芝浦工業大学電子工学科卒業後、株式会社永瀬留十郎工場に入社。現在、技術顧問として後進の指導に注力している。特級鋳造技能士、金属溶解技能士1級(鋳鉄)など多くの資格を取得。2008年、川口産業技術・技能者大賞、09年、滝沢賞(日本鋳造協会)、14年、技能功労知事賞を受賞。16年、「現代の名工」に選定される。(株式会社永瀬留十郎工場 住所:埼玉県川口市金山町15-9)
溶かした金属を砂型に流し込んで製造するのが鋳物です。かつては鍋や釜などの日用品が主流でしたが、時代の変化にともない、現在は工業製品が中心となるなど、鋳物は新たな進化を遂げています。約300年前から鋳物業に携わってきた家業を引き継ぐ永瀬勇さんに、鋳物の現在とその技術の継承についてお聞きしました。
代々鋳物に携わって300年 時代のニーズに応えて進化を図る
今年創業146年を迎える鋳物工場を、埼玉県川口市で代々営んできた永瀬家。その4世代目に当たるのが永瀬勇さんです。川口市は古くから鋳物業が盛んなところで、創業者が4代続いた鋳物屋から独立したために、その歴史は約300年にもわたります。
「鋳物業は粘土が適度に混じっている砂が必要だったので川のそばで発展してきました。川口では鋳物を製造するのに適切な砂が手に入ったのです」
機械込造型工は、金属を鋳物に鋳造することが仕事です。鋳物は、溶かした金属を砂でつくった型に流し込んでつくります。砂型を使うのは、溶かした金属の高温に耐える素材がほかにないからだそうです。
「鉄でつくった型に鉄を流し込んだら型は溶けてしまい、くっついてしまいます。一方、砂型は高純度のものだと融点は1,600度にも達します。鉄は1,400度。200度も高いから耐えられるんですよ」
鋳物というと鉄瓶や鍋や釜などの日用品を思い浮かべますが、日常生活のなかで目にする機会はほとんどなくなりました。現在も日用品を製造している業者はいますが、工業製品の製造が中心になっています。
「鋳物には重い、さびる、割れるという欠点があるため、日用品はアルミやステンレスにとって代わられました。でも、栓抜きやマンホールの蓋、レールのポイント切り替えや踏切の遮断機の装置は鋳物です。注目されづらいところではありますが、生活に役立っているんですよ。しかも、実は鋳物技術はどんどん進化しているんです。スマートフォンや液晶テレビも、鋳物技術があればこそ高性能の製品が製造できていることを知らない人が多いのではないでしょうか」
伝統的な鋳物と先進的な工業製品。そのギャップに驚かされますが、進化しているのは、鋳物の優れた特性が評価されているからだといいます。時代の要請に応えて、永瀬さんの工場の現在のメイン製品は、半導体のICを製造する露光装置と液晶の露光装置です。
「液晶パネルを製造している機械は鋳物でできています。半導体はミクロンの世界ですから、精密さを実現するためには、製造時に振動が起きてはいけません。鉄板は叩くといつまでも振動が続きますが、鋳物の場合は振動がすぐに収まるという利点があります」
工業製品が主流になっている鋳物業ですが、川口市は伝統的な美術工芸鋳物の技術の伝承にも取り組んでいます。約50年前に川口鋳金工芸研究会が発足し、永瀬さんは会長を兼務。美術工芸鋳物を制作している人が少ない現状のなかで、同会では教室を開いて制作指導をし、作品展も催しています。
特級鋳造技能士として後進の育成に力を注ぐ
永瀬さんが、今後取り組みたいと考えているのは、昔の鋳物業者が行ってきた手作業で鋳造する技術の継承です。
「今はコンピュータで製造できるかどうかを確認してから取りかかりますが、昔は、自分の技術と経験だけで製造していました。今のほうが相当ラクなのに、現代の技術をもってしても、昔の人が手作業でつくっていた鋳物の再現ができないんですよ。図面は残っているので形はわかる。でも、鋳造の方法が継承されていないので、どうやってつくるのかがわからない。昔の人の努力と発想力はすごかったんです」
技術の継承も、後進の育成の一環です。永瀬さんは川口市で3人しかいない特級鋳造技能士で、14年間にわたり技能検定受験に向けた講師としても活動しています。
「鋳物業の二大作業は溶解と型込めですから、冶金(金属に関する技術と理論を含む幅広い学問技術領域)についての知識が必要とされます。昔と違って高精度の製品を求められることから、冶金について十分にわかっていないと、お客さまの要望に応えられませんし、壁にぶつかったとき乗り越えられません」
進化を遂げた現代の鋳物業は、機械を使うことが多く、機械を扱うための知識など学ぶことが幅広くあるといいます。永瀬さんは、昨年、金属溶解技能士1級(鋳鉄)の資格も取得。経験におごることなくスキルアップに貪欲に取り組んでいます。