| 資料2 |
報告書
平成17年5月
労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会
| はじめに | |||||||||||||||
| 第1 | 国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価について
|
||||||||||||||
| 第2 | リスク評価の結果に基づき講ずべき措置について
|
||||||||||||||
| 第3 | ばく露関係情報の届出について
|
||||||||||||||
| 参考資料 | |||||||||||||||
| 労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会開催要綱 | |||||||||||||||
| 労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会 参集者名簿 | |||||||||||||||
平成16年5月に報告された「職場における労働者の健康確保のための化学物質管理のあり方検討会報告書」(以下「あり方検討会報告書」という。)においては、以下の趣旨が述べられている。
我が国の産業界では、5万種類を超える化学物質が使用されているが、これらの物質の中には労働者に健康障害を生ずるおそれのあるものも多く存在している。
また、近年、国際的には「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」(以下「GHS」という。)の推進、EUにおいては化学物質に対する厳しい規制の検討がなされているほか、我が国でもダイオキシン、石綿、シックハウス症候群等の化学物質による健康問題が社会的に大きな関心を集めるようになっている。
このような人への健康障害を生ずるおそれのある化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物(以下「化学物質等」という。)のうち法令で規制されていないもの(以下「未規制化学物質」という。)をすべて法令で規制することは現実的ではないことから、未規制化学物質の管理は事業者自ら、当該物質の有害性等と労働者の当該物質へのばく露レベルに応じて生ずる健康障害の可能性及び程度について評価(以下「リスク評価」という。)を行い、必要な措置を講ずる自律的な管理が基本である。
しかしながら、現に発生している化学物質による職業性疾病のうち、未規制化学物質によるものが半数程度を占めていること、中小企業等では自律的な化学物質管理が十分でないこと等を考慮すると、国自らも、必要に応じてリスク評価を行い、健康障害発生のリスクが特に高い作業等については、製造等の禁止、特別規則による規制を行うなどの国によるリスク管理が必要であり、また、国によるリスク評価を可能とするためには、事業場における労働者の作業内容、作業従事労働者数、密閉系で使用する等の作業環境等のばく露関係情報を収集するとともに、提供する仕組みが必要であるとしている。
また、化学物質へのばく露後長期間を経過して発症する場合があること等を考慮すると、職業性疾病が発生していない段階においても、化学物質に対する予防的取り組みを踏まえた管理が必要であるとしている。
これらの提言を踏まえ本検討会においては、化学物質のリスク評価の考え方やその方法、リスク評価後の国が講ずべき措置、ばく露関係情報の収集等に関することについて検討を重ね、このたびその結果をとりまとめた。
| 第1 | 国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価について |
| 1 | リスク評価の概要 |
| (1) | リスク評価の方法の概要 リスク評価においては、化学物質等の有害性の種類及び程度の特定、ばく露レベルに応じて生ずるおそれのある健康障害の可能性及びその程度(以下「量―反応関係」という。)、労働者の当該物質へのばく露レベルについて把握(以下「ばく露評価」という。)することにより、スクリーニング的なリスクの判定を行う。その結果、リスクが高いと判定された場合には、データ等について詳細に検証し、再度リスクの判定を行う(別紙「リスク評価の進め方」参照)。
|
||||||||||
| (2) | 考慮すべき事項 リスク評価の実施に当たっては、次の事項について考慮する必要がある。
|
| 2 | 有害性の種類及び程度の特定 主要文献等を利用することにより、調査対象化学物質等の有害性について把握する。有害性はGHSのクラス分けに従い、急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷性・刺激性、呼吸器感作性・皮膚感作性、発がん性、生殖毒性及び臓器毒性・全身毒性とする。 主要文献等から、日本産業衛生学会の提案している許容濃度(以下「許容濃度」という。)、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)で定める時間加重平均濃度(以下「TLV―TWA」という。)、無毒性量(NOAEL)、最小毒性量(LOAEL)、無影響量(NOEL)、最小影響量(LOEL)、有害性に係るGHSの区分等の量―反応関係に係る有害性データに関する情報を把握する。 |
| 3 | 量―反応関係の把握 |
| (1) | 臓器毒性・全身毒性又は生殖毒性 物質が臓器毒性・全身毒性又は生殖毒性を有することを把握し、ばく露限界等について調査を行う。
|
||||||||
| (2) | 急性毒性 急性毒性については、動物実験等のデータから得られた急性毒性に係るGHSの区分、LD50又はLC50の値、蒸気圧等のばく露に関係する物理化学的性状について把握する。 |
||||||||
| (3) | 皮膚腐食性・刺激性又は眼に対する重篤な損傷性・刺激性 物質が当該性質を有することを把握する。 皮膚に対する不可逆的な損傷、若しくは可逆的な刺激性又は眼に対する重篤な損傷、若しくは刺激性を生じさせる有害性に係るGHSの区分について調査する。 |
||||||||
| (4) | 呼吸器感作性又は皮膚感作性 化学物質等を吸入の後で気道過敏症を誘発する性質、又は当該物質との皮膚接触の後でアレルギー反応を誘発する性質について把握する。 |
||||||||
| (5) | 発がん性 発がん性を有することを把握し、閾値がないと考えられている場合にはがんの過剰発生率を、閾値がないと考えられている場合以外の場合には、無毒性量等を把握する。 |
||||||||
| (6) | データの検討 量−反応関係等から得られる有害性データについて、動物実験から得られたデータと人から得られたものがある場合には、原則として人のデータを優先的に用いる。 また、実験に基づくデータを使用する場合には、これらのデータが適切な手法を用いて得られたものであること等データの信頼性について十分調査する。 |
| 4 | ばく露評価 |
| (1) | ばく露評価の手順 ばく露評価に用いるばく露レベルは、当該作業環境の空気中の濃度の測定又は個人ばく露濃度の測定から次の手順で把握する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 調査対象物質及び取扱い作業等の優先順位付けのための分類
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 作業環境の測定の対象とする作業の把握
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | ばく露レベルの把握
|
| 5 | リスクの判定等 |
| (1) | 判定の概要 リスクの判定は、発がん性以外の場合には、原則として、作業に従事する労働者の化学物質等へのばく露レベルと、許容濃度、無毒性量 (NOAEL) 等を定量的に比較することにより行い、許容濃度、無毒性量 (NOAEL)等の値を文献等から把握できない場合には、評価対象としての優先順位を繰り下げる。発がん性の場合は、閾値がないと考えられている場合と閾値がないと考えられている場合以外とに分けて判定する。 スクリーニング的なリスク評価において、リスクが高いと判定された場合には、有害性データ、作業環境の空気中の濃度の測定結果等のデータの検証、又は追加を行い学識経験者の意見を聴き詳細な検討を行う。 さらに、詳細な検討においてリスクが高いと判断される場合には、ばく露を防止するための所要の措置を講ずる。 |
||||||||||||||||||||
| (2) | 判定の手順 リスクの判定に際しては、許容濃度、人に対する無毒性量(NOAEL)等を優先的に用いるが、当該値が存在しない場合には、動物実験等から得られた値を外挿して用いる。 無毒性量等を得ることができないクラスの有害性の場合には、量―反応関係、有害性等、ばく露労働者の数等を考慮することにより総合的にリスクの判定を行う。
|
||||||||||||||||||||
| (3) | 判定基準 リスクは次の基準に従い判定し、必要な場合には詳細な検討の対象とする。
|
||||||||||||||||||||
| (4) | 詳細な検討の手順 詳細な検討は次の手順によって行う。
|
別紙
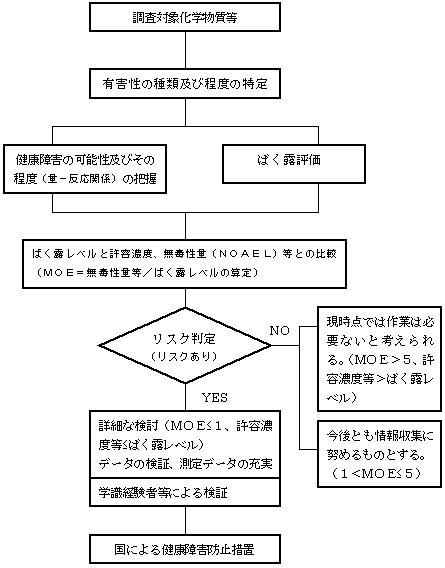
リスク評価の進め方(発がん性の場合)
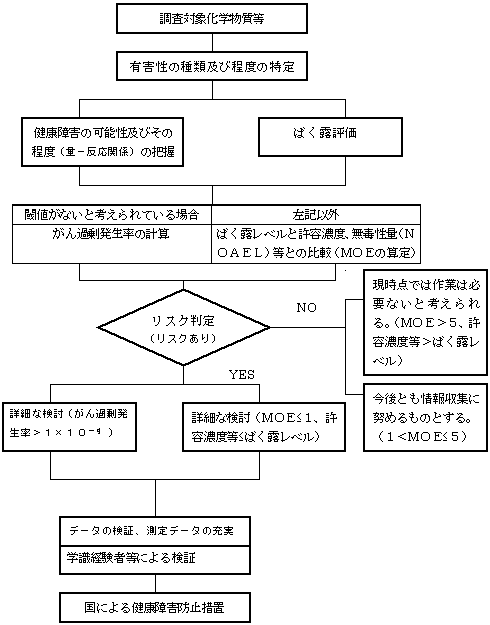
| 第2 | リスク評価の結果に基づき講ずべき措置について |
| 1 | 趣旨 あり方検討会報告書において、国自らも、必要に応じてリスク評価を行い、健康障害発生のリスクが特に高い作業等については、製造等の禁止、特別規則による規制を行うなどの国によるリスク管理が必要であるとの提言を踏まえ、リスク評価の実施により、リスクがあると判定された作業等について、国による健康障害防止措置について検討した。 |
| 2 | 国による化学物質等に係る労働者の健康障害の防止等に係る規制 労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)やその関係法令、通達において、化学物質等による労働者の健康障害の防止対策が講じられているが、その概要は次のとおりである。 |
| (1) | 製造等の禁止 安衛法第55条では、「黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物」として10の物について製造等を禁止している。 |
| (2) | 製造の許可 安衛法第56条では、「ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物」として7物質について製造に当たり許可を要する物質としている。 |
| (3) | 特別規則等による規制 安衛法第22条第1項第1号では、事業者は、「原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害」を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされている。原材料、ガス、蒸気、粉じんに係る健康障害防止の具体的な措置については、特別規則として有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則(以下「特化則」という。)等において定められている。 また、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第3編「衛生基準」においては、有害な作業環境、廃棄物の焼却施設に係る作業、保護具等その他について規制している。 |
| (4) | 表示等 安衛法第57条では、「ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物」として、92物質について、譲渡等に際して名称、人体に及ぼす作用等の容器等への表示が義務付けられている。 |
| (5) | 文書の交付等 安衛法第57条の2では、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物として638物質について、譲渡等に際して化学物質等安全データシート(以下「MSDS」という。)の交付が義務付けられている。 |
| (6) | 化学物質の有害性の調査 安衛法第57条の3では、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、有害性の調査結果を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされている。 |
| (7) | 事業者の行うべき調査等 安衛法第58条では、化学物質等を事業場で新たに使用する場合、事業者はあらかじめその有害性等を調査して、その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。 |
| (8) | 指針の公表 安衛法第28条第3項第2号では、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある物を製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表することとされている。これに基づき、これまで四塩化炭素等12物質について指針が公表されている。 また、強度の変異原性が認められた化学物質の取扱いにおける労働者へのばく露を低減するため、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」が行政指導通達として出されている。 |
| (9) | 皮膚又は眼障害に係る規制 GHSにおいて、有害性のクラス分けとして、皮膚腐食性・刺激性又は眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性の分類がなされているが、これらの健康障害防止については、特化則及び安衛則において保護具に係る規制がなされている。 平成15年8月11日付け「化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について」(以下「眼・皮膚通達」という。)においては、特化則第44条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等及び安衛則第594条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与える物質、安衛則第593条に規定する有害物で保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならない物質を示している。 |
| 3 | リスク評価結果に基づく措置に係る考え方 |
| (1) | 基本的考え方 化学物質管理の基本は、事業者が自ら当該化学物質の取扱い等に係る健康障害のリスクを評価し、その結果に基づきばく露防止対策を講ずることであり、また、安衛法第58条においても事業者は労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものについては、あらかじめ、これらの物の有害性等を調査し、その結果に基づき必要な措置を講ずることとされている。 このように、リスク評価によりリスクがあると判定された場合には、事業者は自らMSDS等の情報に基づき、自主的に必要な健康障害防止対策を講ずる必要がある。また、国は必要に応じ、MSDSを交付すべき対象物質を追加することが求められている。 さらに、あり方検討会報告書でも指摘されているように、有害性の程度の高い物質を労働者が取り扱う作業等のリスクが特に高い場合には、その程度に応じて規制を行うなどの国によるリスク管理を実施する必要がある。 一方、リスク管理としての措置を検討するに際しては、リスク評価は得られた範囲の限られた情報に基づくもの等であることから、リスクの判定には不確実性が含まれることを踏まえて評価していることを考慮する必要がある。 |
||||||||||||||
| (2) | 考慮すべき事項 上記基本的考え方を踏まえると、リスクがあると判断された化学物質等を取り扱う作業等については、次の事項を考慮し、行政的措置を講ずることが求められる。
|
| 4 | 発がん性のリスク低減のための措置 |
| (1) | 閾値がないと考えられている場合 閾値がないと考えられている場合には、がんの過剰発生率によりリスクの判断を行うこととされているが、一般的には当該値を算定できる物質は限定されている場合が多いことから、リスクの判定ができない場合も考慮する必要がある。 このような場合においても、がんの重篤性を考慮すると、労働者の発がん性物質へのばく露を可能な限り少なくすることにより、健康障害の発生を防止することが 求められることから、次の行政的措置を講ずべきである。
|
||||||
| (2) | 上記(1)以外 上記(1)以外の場合には、ばく露レベルを閾値以下に抑制するよう管理することにより、健康障害の発生を防止することが可能であると考えられるが、がんの重篤性を勘案して(1)と同様な措置を講ずべきである。 なお、上記(1)及び(2)のように人に対して発がん性があると判断された物質等を禁止、許可、管理(特別規則による規制)の3段階に分類して法規制することは、昭和52年に批准されたILO職業がん条約の考え方による規制とも一致する。 |
||||||
| (3) | 人に対する発がん性が知られている物質等に係る留意事項 人に対する発がん性が知られている物質、又は人に対しておそらく発がん性がある物質については、国が行うリスク評価の結果、「現時点では作業は必要ないと考えられる」又は「今後とも情報収集に努めるものとする」とされた場合であっても、発がん性の重篤性に鑑み3の(2)のイ及びウの事項を考慮し、必要に応じて適切な措置を講ずべきである。 |
| 5 | 発がん性以外のリスク低減のための措置 リスクがあると判断された臓器毒性・全身毒性又は生殖毒性の有害性クラスについては3の(2)を考慮して、次の措置を講ずることが妥当である。 |
| (1) | ばく露量が多く、重度の健康障害を生ずる物、または重度の健康障害を生ずるおそれのある物については、禁止、製造許可又は特別規則による規制の対象とすべきである。 |
| (2) | ばく露量が多く、健康障害を生ずるおそれのある物については、特別規則による規制、安衛則第3編の衛生基準の適用又は行政指導により対応すべきである。 |
| 6 | 短い期間のばく露によりリスクが発生する有害性のあるもの等 有害性の区分のなかには、短い期間のばく露によりリスクが発生する有害性のあるもの又は無毒性量等とばく露レベルとの比であるMOEの概念によるリスク評価になじまないものもあることから、これらのクラスの有害性については、次の措置を講ずることが妥当である。 |
| (1) | 急性毒性 急性毒性のGHSの区分に応じて有害性の程度が記載されてくることから、講ずべき措置を検討するに当たっては、急性毒性のGHSにおける該当区分、発じん性、揮発性等の物理化学的性状、ばく露状況を勘案し、特別規則による規制、安衛則第3編衛生基準の適用又は行政指導により対応すべきであること。 |
| (2) | 皮膚腐食性・刺激性、眼に対する損傷性・眼刺激性又は感作性 当該クラスの有害性に係る措置については、眼・皮膚通達に該当するものである場合には、発じん性、揮発性等の物理化学的性状、ばく露状況を勘案し、同通達に基づく措置又は行政指導により対応すべきである。 |
| (3) | 変異原性について 変異原性が強いと判断された物質については、変異原性の評価、国内における当該物質の製造量、使用量、用途等を勘案し、行政指導の対象とすべきである。 |
| 7 | 現時点では作業は必要ないと考えられる等の場合 国が行うリスク評価において、「現時点では作業は必要ないと考えられる」又は「今後とも情報収集に努めるものとする」と判断された場合でも、リスク評価の対象となった作業等では有害物の取扱い作業等が行われていること、また、リスク評価は得られた範囲の限られた情報に基づくもの等であることから、不確実性が含まれることを踏まえると、事業者は健康障害を防止するためにMSDS等に基づき自主的に化学物質管理を行うことが求められる。 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3 | ばく露関係情報の届出について |
| 1 | 趣旨 あり方検討会報告書においては、国によるリスク評価を可能とするためには、事業場におけるばく露関係情報の把握が必要とされ、このためには、事業場における労働者の作業内容、作業従事労働者数、密閉系で使用する等の作業環境等のばく露関係情報を収集、提供する仕組みが必要であるとしている。 また、平成16年12月27日、労働政策審議会から厚生労働大臣に対して「今後の労働安全衛生対策について」建議が行われた。このなかで、「国はリスク評価のための情報収集を目的に、事業場における労働者の作業内容、従事労働者数、密閉系での使用等のばく露関係情報を収集する仕組みを整えること。」とされている。 このため、ばく露関係情報の届出の義務を課する際の事業者の要件、届け出るべき項目等について検討した。 |
| 2 | ばく露関係情報の把握の目的及びその現状と課題 |
| (1) | 目的 ばく露関係情報を収集する主要な目的は、事業場から提出された作業内容、作業環境の状況等のばく露関係情報から判断して、労働者の化学物質へのばく露の程度やその広がりを推定し、健康障害の発生のおそれのある作業等を事前に把握し、必要に応じて関係事業場の指導、支援等を行うこと、次に、これらの作業等のうち有害性やばく露レベルが高く健康障害のおそれがあると想定されるものについて、ばく露関係情報を分析のうえ、ばく露評価による定量的なリスクの判定を行い、必要な場合には国として健康障害防止措置を講ずることである。 |
| (2) | 現状及び課題 事業場で製造し、又は使用されている未規制化学物質に係るばく露関係情報については、法令に特段の規定がないことから、調査等を行わない限りこれを把握することは困難である。 一方、アンケート調査、ヒアリング等により対象事業場を把握し、ばく露関係情報を得る方法のうち、アンケート調査等は対象事業場が把握できる場合に実施が可能であり、未規制物質の使用状況が未知の場合は調査そのものの実施が困難である。 また、仮に対象事業場を把握できたとしても、協力の得られる事業場のみの回答となるおそれがあり、健康障害のおそれのある作業等の状況を十分に把握することができなくなる。 一方、国によるリスク評価では統計的な代表性を担保するために無作為に抽出されたデータに基づいて実施することが重要であるが、これらの無作為性を損なわないためには、測定データを任意に抽出することができる仕組みを整える必要がある。 |
| 3 | 届出の対象物質等 |
| (1) | 届出の対象物質 安衛法第57条の2の通知対象物は、労働者に健康障害を生ずるおそれのあるものとして譲渡等に際して有害性等の情報の提供が義務付けられている物質であること、事業者はMSDSにより有害性や取扱い物質の成分を知ることができ、従って、届出の対象物質に該当するか否かを判断することができること等を勘案すると、通知対象物を届出の対象とする必要がある。ただし、特化則等の特別規則において規制している一定の物質を除く。 |
| (2) | 混合物の取扱い 譲渡等を行う物質が、通知対象物を重量の1%を超えて含む場合には、MSDS交付の対象となる。一方、GHSでは、発がん性物質等以外のものについては1%以上含有するもの、区分1の発がん性物質等については0.1%以上含有するものを対象としている。したがって、届出を義務付ける対象物質についても、MSDSの交付の基準がGHSに沿って改正された場合には、同様な含有率の物を対象とすることが適当である。 |
| 4 | 事業者等の要件 |
| (1) | 事業者 届出の対象となる物質を取り扱うすべての事業者に対して、届出の義務を課すことが望ましいが、国が行うリスク評価は、ばく露レベルが高くリスクが高いと想定される作業等を対象としている。このため、届出の義務を課す事業者としては、ばく露レベルが高いと想定される作業等で、届出対象物質を一定量以上取り扱っている者に限定することは合理的と考えられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 事業場 安衛法では、事業場における安全衛生管理は、事業場単位で実施することとされ、また、同法に基づく各種の報告は原則として事業場単位となっていることから、事業者は、ばく露関係情報の届出を事業場別に行うことが合理的である。
|
| 5 | 届出項目及びその必要性 届出を行う項目は、事業場の名称、所在地等の基本的な情報の他、ばく露レベルを把握するために次の項目が必要である。 |
| (1) | 取り扱う化学物質等の名称 取り扱う化学物質等の名称は、報告の対象物質名及び当該対象物を重量の1%を超えて含有する製剤その他の物の名称とする。 |
| (2) | 用途 ばく露の状況を推定するための情報として、原材料として使用されるのか、溶剤として使用されるのか等の基本的な情報として使用目的を知る必要がある。 |
| (3) | 化学物質の性状 取り扱う物質が、揮発性や発じん性が高い場合には、作業場の空気中の濃度が高くなる可能性が高いことから、どのような性状で取り扱われているか、ばく露評価を実施する際の情報として必要なものである。 |
| (4) | 取扱量及び対象労働者 取扱量が多い開放系等の作業においては、一般的に空気中の濃度も高く、したがってばく露レベルが高くなることが予想されることから取扱量は必要な情報である。 また、ばく露労働者の範囲を把握することにより、その広がりを把握することが可能となる。なお、取扱量については、製造者にあっては製造量を、使用者にあっては消費量等とすることが適切である。一定の要件のもとでは消費量は、購入量で代替することは可能である。 届出の対象となる労働者は、対象物質の取扱い作業から発散する有害物にばく露すると考えられる範囲内の場所において行われる作業に従事している労働者及び当該場所に近接している場所においてばく露を受けるおそれのある労働者とすることが適当と考えられる。 |
| (5) | 換気設備等の設置状況等 労働者のばく露の程度は、密閉系又は開放系のいずれの工程で化学物質が取り扱われている作業に従事しているかに大きく影響される。また、開放系の工程等で取り扱われている場合には、使用している換気設備の設置状況がばく露レベルに影響するので必要な情報である。 |
| (6) | 対象作業 届出の対象となる作業は、ばく露を受けるおそれのある作業とする。したがって、密閉系の工程における作業等のばく露をうけるおそれのない作業は除かれる。 |
| (7) | 取扱い時の温度等 高温の物質を取り扱っている場合には、ばく露の可能性が高くなることから、物質の取扱い時の温度を知る必要がある。 |
| (8) | 作業時間 有害物にばく露すると考えられる範囲内の場所等において作業等に従事している時間が、ばく露を受ける時間と想定されることから、作業時間はばく露時間を知るために必要な情報である。 |
| (9) | その他 提出事項の記載の方法等については、事業者に対する負担と当該義務を課すことによる効果に留意する必要がある。このため、届出様式については作業を類型化、分類し、これを選択できるような方式等について配慮するものとする。 |
| 6 | 届出の仕組みについて 届出の仕組みの例として、別紙の方法を示す。 |
別紙
| 1 | 届出の対象物質 |
| (1) | 届出の対象となる物質は、労働安全衛生法第57条の2第1項において、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物として、政令で定めている物(通知対象物)のうち、厚生労働大臣が指定するもの。ただし、特化則等の特別規則において規制している一定の物を除く。 |
| (2) | 通知対象物又は通知対象物を重量の1%を超えて含有するもの。 |
| 2 | 届出対象物質名の公表 |
| (1) | 届出対象物質名の公表 国は、届出の対象となる化学物質の名称及び時期を定期的に公表することとする。 |
| (2) | 届出の期間等 届出の対象となる物質名が公表された後、一定期間内に所定の様式に必要事項を記載し、所轄労働基準監督署に届け出るものとする。ただし、同一物質に関して定期的に届け出る必要はない。 |
| 3 | 対象事業者の範囲 |
| (1) | 事業者 | 届出対象物質にばく露するおそれのある作業を行っている事業者 第一種衛生管理者を選任すべき業種等一定の業種が主要な対象 |
| (2) | 規模 | すべての規模の事業場 |
| (3) | 範囲 | 届出の対象となる化学物質を、前年度の1年間に0.5トン以上製造又は消費等した事業場 |
| 4 | 届出項目 |
| (1) | 事業場の名称等 事業場の名称、事業の種類、所在地、労働者数 |
||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ばく露関係情報
|
| 5 | ばく露関係情報の取扱い |
| (1) | 国によるリスク評価、ばく露評価での活用、またリスク評価後、リスクありと判定された場合の講ずべき措置の検討資料として活用 |
| (2) | 必要に応じて、指導、支援、関連情報の提供 |
| 6 | 事業場における届出の手順例 対象となる化学物質を製造し、又は使用している事業場が、取扱量を把握するためには、次の方法が考えられる。 |
| (1) | 化学物質を含有している製剤等について台帳等から確認する。 |
| (2) | MSDSを用いて届出の対象となる化学物質が含まれていること及びその含有率が1%を超えていることを確認する。 |
| (3) | 前年度の1年間の化学物質の取扱量を、台帳等から把握する。 |
| (4) | 取扱量とMSDSから、前年度の調査対象化学物質の合計量が0.5トン以上の場合には、所定の様式により国に届け出る。 |
| 国 |
|
届出の対象となる事業場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公表 |
|
製造又は使用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
届出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||