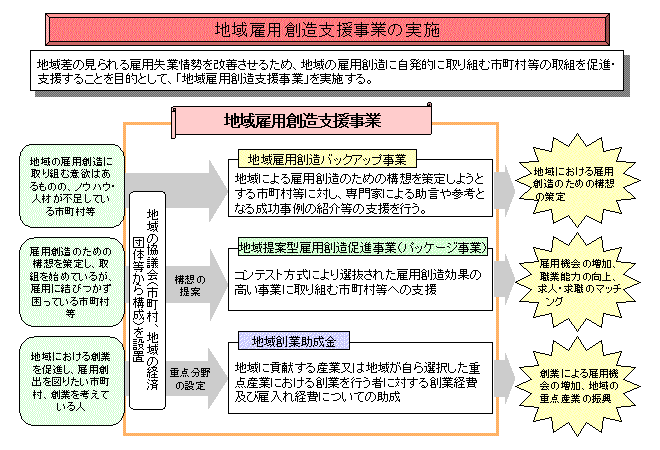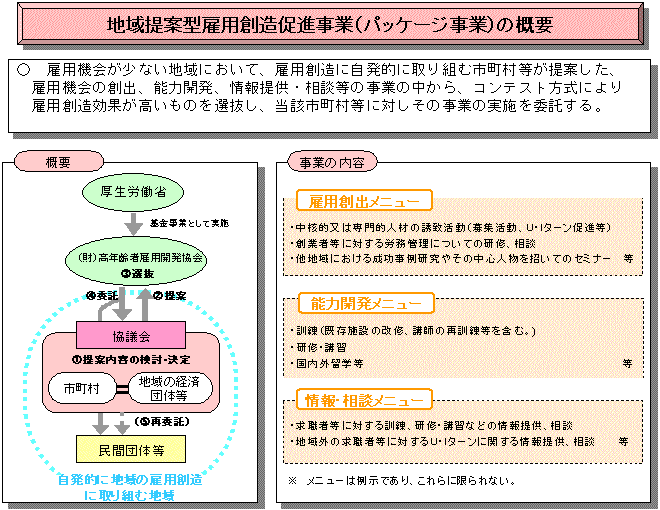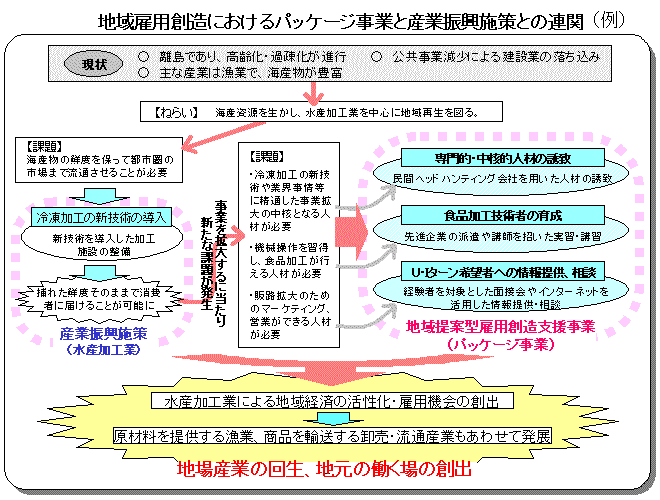地域提案型雇用創造促進事業について(平成18年度)
平成18年1月
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| I 事業の概要 |
1 趣旨
|
雇用失業情勢は全国的には改善しているものの、地域差がみられます。 地域を取り巻く環境等は様々であり、地域の雇用創造をより効果的に行うためには、国が一律に対策を講じるのではなく、できるだけ現場に近い意欲のある地域による自主性・創意工夫ある取組を支援することが必要です。 一方、政府においては、地域の自発的な地域経済の活性化や雇用機会の創出の取組を国が支援する「地域再生」の取組を開始したところであり、雇用対策についても、地域の自発的な取組を競争的・選択的に支援することが重要です。 このため、雇用機会が少ない地域において、雇用創造に自発的に取り組む市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域の経済団体等から構成される協議会が提案した雇用対策の事業の中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高いものを選抜し、当該協議会等に対しその事業の実施を委託する地域提案型雇用創造促進事業(以下「パッケージ事業」といいます。)を創設しました。 なお、本事業については、財団法人高年齢者雇用開発協会(以下「協会」といいます。)が実施している「緊急雇用創出特別基金事業」のうち「地域雇用受皿事業」の一事業として実施しています。 |
2 事業の対象地域
| (1 | ) 基本的考え方 以下のいずれをも満たす地域を対象地域とします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2 | ) 具体的な判断基準 (1)[1]について 以下のいずれかを満たす地域
(1)[2]について 事業実施までに、対象地域の市町村(複数の場合はそのすべて)により、パッケージ事業を活用することを盛り込んだ地域再生計画を策定し、内閣総理大臣の認定を受けてください。なお、都道府県が策定者に含まれていても差し支えありませんが、対象地域内のすべての市町村が策定主体となることが必要です。 また、事業の実施を希望する場合には、地域再生計画の認定申請に先んじてパッケージ事業の事業構想を提案(※)することになります。地域再生計画の認定を受けることを前提として、パッケージ事業への応募をしてください。 さらに、パッケージ事業の事業構想の審査は、地域再生計画の認定申請に先行することとなりますが、パッケージ事業の採択の内定を受けた後であっても、地域再生計画の認定が受けられなかった場合には、事業を委託することはできません。
|
3 事業の提案・実施主体
| (1 | ) 基本的考え方 パッケージ事業については、より現場に近い立場で地域経済の活性化と地域雇用の創造に責任をもって取り組む行政主体である市町村と地域の経済・雇用を担う立場の地域の経済界とが一致協力して地域の雇用創造に取り組むことが効果的であり、国の委託事業として相応しいとの考え方の下、市町村、経済団体等により構成される協議会が事業の提案や実施を行うこととしています。 |
||||||||||||
| (2 | ) 協議会の要件 事業の提案主体は、以下の[1]〜[3]のいずれも満たす協議会とします。なお、協議会は、法人格を要さず、いわゆる権利能力なき社団で差し支えありません。
|
||||||||||||
| (3 | ) 事業構想の提案 事業構想の提案は協議会が行うこととします。提案の時点において協議会が正式に設置されていない場合には、設立準備会議から提出することで差し支えありませんが、この場合でも、地域再生計画認定申請時までには協議会を設立することが必要です。 なお、1つの市町村が提案できるパッケージ事業の構想は、各年度につき1つのみとします。(構成市町村が異なる協議会に参加する場合も同様です。) なお、事業構想は、事業の実施を希望する期間(最大3年度間)全体にわたるものを提案することとします。 |
||||||||||||
| (4 | ) 事業の実施主体 事業の委託先は原則として協議会とします。なお、協議会から民間団体等への再委託は可能です。 また、特に必要と認められる場合には、協議会等があらかじめ事業構想において指定した民間団体等に対して直接委託することも可能とします。 いずれの場合であっても、委託先である民間団体等は、当該委託に係る事業と同じ分野の事業の実施について過去に実績があり、かつ、事業実施体制が整備されていることが不可欠です。また、事業実施全体に係る管理・責任主体は、あくまでも協議会であり適切な民間団体等へ委託することはもとより、協会から直接委託を受けた民間団体等を含め事業の実施状況の把握を行い、より効果的な事業となるよう取り組むとともに事業評価や会計処理等についても協議会が責任をもって行うこととします。 |
4 事業内容
| (1 | ) 基本的な考え方 パッケージ事業は、対象地域内の市町村や経済団体等の創意工夫により、地域の特性・資源を顕在化させ、これらを有効に活用した地域経済の活性化や雇用機会の創出に資する地域再生の具体的な取組と一体となって実施することにより、それらの取組による雇用創造効果をさらに高めることが見込まれる雇用面での対策、具体的には雇用機会の創出、求職者等の能力開発及び求職者への情報提供、相談等といった取組を支援するものです。 従って、協議会等においては、地域再生の取組の推進に伴う雇用創造に関する課題を適切に把握し、それを解決するために真に必要であり、かつ、効果の高いものを事業内容とすることが重要です。 なお、こうした観点から、すでに実施している市町村等の事業の単純な財源の振り替えたにすぎないような事業は、本事業の対象とはなりません。また、同様に、求職活動援助事業など、既に対象地域で実施中の国の委託事業等と重複する内容のものも本事業の対象とはなりません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2 | ) 事業内容例 具体的には、以下のメニュー例のような雇用対策事業を行うことができます。 なお、これらはあくまでも例示であり、これらの他にも地域の創意工夫を活かした事業であり、上記(1)の考え方に合致するものであれば実施が可能です。(具体的にどこまでの範囲の事業が可能かについては、都道府県労働局に個別に御照会ください。) (メニューの例)
|
5 市町村や経済団体等が実施する地域や産業の開発・振興の取組
パッケージ事業の実施に係る区域において、協議会の構成員である市町村、経済団体等が、パッケージ事業と一体的に地域経済の活性化や雇用機会の創出のための具体的な取組を行うことが必要です(ただし、これらの取組はパッケージ事業の対象にはなりません。)。また併せて、それら地域経済の活性化や雇用機会の創出のための具体的な取組と一体的にパッケージ事業に係る事業を行うことにより、地域における雇用創造がさらに 促進されることが必要です。当該取組の例としては、以下のようなものが考えられます。 なお、平成18年度において新たに実施する取組である必要はなく、従来から実施している取組で差し支えありません。
|
6 事業規模等
| (1 | ) 事業実施期間及び事業規模 パッケージ事業の委託に係る事業の実施期間は、1地域当たり最大3年度間とし、事業実施に係る経費は、1年度につき2億円、最大3年度間で6億円を上限とします。 ただし、事業の実施に当たっては、各年度ごとに中間評価を行い、事業終了時に当初の目標を達成する可能性が極めて低い場合には、翌年度以降の事業の委託を取り消すこととします。 また、事業内容が異なるとしても、1つの市町村が実施できるパッケージ事業は1年度に1事業に限られ(3(3)参照)、かつ、通算で3年度間を上限とします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2 | ) 委託費で措置する経費 委託費で措置する経費は、主に以下のものを想定していますが、疑問がある場合には、都道府県労働局に個別に御照会ください。 講師等については、謝金による対応を原則とし、必要と認められる場合に限り、常勤として人件費を措置します。また、パソコン・OA機器等の機器が必要な場合については、原則としてリースによる利用とすることとします。(経費積算の詳細については、18〜19ページを参照ください。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3 | ) 委託費で措置しない経費
パッケージ事業は、地域の取組に伴って生じる人材面での課題を解決するため、地域における人材育成・人材確保に係る事業を支援することを目的としています。 したがって、以下のような経費については、委託費 による措置の対象となりません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4 | ) 事業推進員の配置
パッケージ事業の企画及び実施並びに関係行政機関及び関係団体等との連絡調整に当たる者として、事業の一環として、協議会の事務局に事業推進員を配置することができます。事業推進員は、協議会が事業を企画・実施するにあたり必要な知識、経験等を有すると認められる者であることが必要です。事業推進員の職務としては、以下のものが挙げられます。
|
7 事業の仕組み
Iの3の(2)の協議会等から、事業構想を募集し、有識者等からなる第三者委員会(以下、「選抜・評価委員会」といいます。)による審査により高い雇用創出効果が見込まれ、パッケージ事業の委託対象として適切と認められる事業構想を選抜し、当該事業構想を提案した協議会等に事業を委託します。 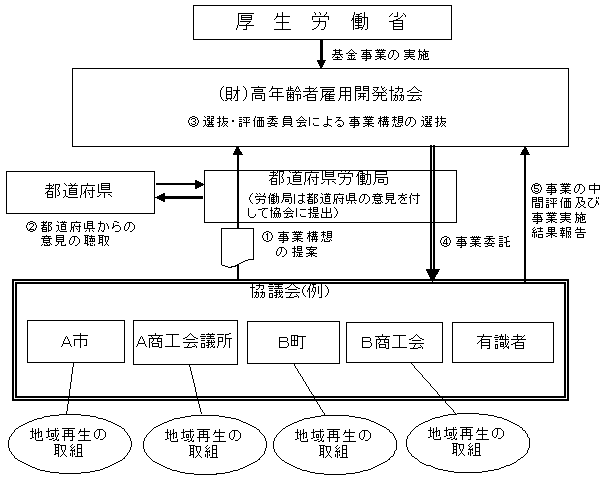 |
| II 応募方法 |
1 応募者
応募(事業構想の提案)は、パッケージ事業を受託しようとする協議会又はその設立準備会議が行ってください。 |
2 必要書類
|
事業構想の提案は、以下の書類の提出により行ってください。 提出書類の様式は、A4版の用紙に片面印刷としてください。複数ページから成る書類については、左上1カ所をステープルでとめた上で、全書類をダブルクリップでとめ、正1部、副3部の計4部を協会会長あて提出してください。
|
3 事業構想提案書の作成方法
| (1 | ) 事業構想は、事業の実施を希望する期間(最大3年度間)全体にわたるものを作成してください。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2 | ) 事業構想提案書の1ページ目及び2ページ目は、20ページ〜21ページの様式により、事業のタイトル、事業の実施に係る地域、ヒアリングの希望の有無、協議会の構成等について記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||
| (3 | ) 事業構想提案書の3ページ目以降に、22ページ〜25ページの様式を参考に、以下の事項を盛り込んで、事業構想の内容を記述してください。
|
||||||||||||||||||||||||
| (5 | ) 事業構想提案書のすべてのページの下中央にページ番号を振ってください。 | ||||||||||||||||||||||||
| (6 | ) 事業構想提案書の総ページ数は、概ね20ページ以内としてください。 |
4 提出先
|
パッケージ事業の実施に係る地域を管轄する都道府県労働局へ提出してください。 |
5 問い合わせ及び相談
|
パッケージ事業に係る問い合わせは、都道府県労働局へお願いします。 また、都道府県労働局より、必要に応じて、事業構想の立案等に係る助言を行いますので、御相談ください。 |
| III 事業構想の選抜 |
1 選抜への流れ
|
事業構想の提出を受けた都道府県労働局は、当該事業構想について都道府県の意見を聴取します。都道府県は、その事業構想が地域の実情に応じた適切なものか、都道府県の行う産業施策等との整合性があるか等についての意見を都道府県労働局に提出します。都道府県労働局は、都道府県から聴取した意見を付して、提出された応募書類を協会に送付します。各都道府県労働局から送付された事業構想の選抜については、公平・客観性の担保の観点から、選抜・評価委員会において提案内容を比較・検討のうえ、後述2の基準に照らして選抜します。 |
2 選抜の基準
|
事業構想については、以下の基準で選抜されることになります。
|
3 選抜結果の通知
|
事業構想の選抜結果の通知は、都道府県労働局を通じて行います。 その際、選抜された事業構想について、必要に応じ、事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件を付すことがあります。 |
| IV 契約 |
1 委託契約の締結
|
選抜された事業構想については、地域再生計画認定後速やかに協議会と協会会長が委託契約を締結することになります。なお、契約は事業構想に示された期間(最大3年度間)にわたるものとなります。委託契約に係る協議その他の各種の連絡等は、都道府県労働局を通じて行います。委託契約に係る詳細については、別途お知らせします。 設立準備会議が事業構想の提案を行った場合には、当該構想に係る地域再生計画の認定申請までに協議会を設置する必要があります。 なお、実際の契約の際の契約金額は、必ずしも提案された事業構想の所要経費概算とは一致するものではありません。 |
2 委託費の支払い
所定の手続を踏まえた得た上で、四半期ごとに委託費を支払うこととしています。 |
| V 事業の評価 |
1 事業の中間評価
事業の委託を受けた協議会は、各年度ごと、別途通知する期限までに、事業の実施状況、雇用創造効果に係る目標の達成状況等事業の実績及びそれに対する評価を盛り込んだ事業中間評価報告書を協会会長に提出していただくことになります。 |
2 次年度以降の事業の実施
上記Iの6の(1)のとおり、事業の実施期間は最大3年度間ですが、各年度ごとに上記1の中間評価報告書の内容を踏まえ、事業終了時に当初の目標を達成する可能性が極めて低い場合は、事業の委託を取り消すことになります。 なお、引き続き事業を実施する場合であっても、効率的・効果的な事業実施の観点から、必要に応じて、当初の事業構想にある事業内容の一部変更や実施に係る条件を付す等の措置を講ずることとなります。 |
3 事業の実施結果の報告
事業の委託を受けた協議会は、事業終了時(事業が終了した翌年度の4月10日まで)に事業実績報告書を提出していただくことになります。また、事業の実施状況、雇用創造効果に係る目標の達成状況、それに対する評価を盛り込んだ事業実施評価報告書を別途通知する期限までに協会会長に提出していただくことになります。 |
(パッケージ事業の経費積算に係る留意事項について)
1 経費の根拠| ・ | 基本的に10万円を超える高額な経費については、全てその根拠を示してください。なお、根拠としては、以下のようなものが想定されます。 業者による見積もり 業者等の料金表(カタログ、運賃等) 同様の事業を行った際の実績(過去の同様のセミナー講師の謝金等) 自治体又は経済団体による経費にかかる規程 |
2 管理費
| (1 | ) 事業推進員
|
||||||||||
| (2 | ) 自動車のリース
|
||||||||||
| (3 | ) パソコン・OA機器
|
3 事業費
| (1 | ) 再委託における一般管理費等
|
||||
| (2 | ) 講師謝金の単価
|
||||
| (3 | ) 地域外への研修
|
||||
| (4 | ) 研修受講者への日当
|
||||
| (5 | ) 施設改修
|
4 消費税
|
消費税の計上は、個々の経費について課税か、非課税を判断して計上するのではなく、以下により一括して計上してください。 消費税=(管理費のうち人件費及び旅費を除いたもの+事業費の計)×0.05 |
(事業構想提案書 様式)
財団法人高年齢者雇用開発協会
| 会長 殿 |
地域提案型雇用創造促進事業(パッケージ事業)について、以下のとおり提案します。
<事業タイトル>
事業の趣旨・目的を端的に表現したタイトルをつけてください。(例:「○○産業の振興を通じた雇用機会の増大」) |
<事業の実施に係る地域>
パッケージ事業の実施に係る区域の市町村名を記入してください。 |
<ヒアリング希望の有無>
希望する ・ 希望しない
協議会名 代表者 役職・氏名 印 住所 〒 連絡担当者 所属・役職・氏名 TEL: FAX: |
| 構成員 | 住所 | 担当者氏名・連絡先 |
| (市町村、経済団体その他の団体については団体名及び代表者氏名、有識者等の個人については氏名及び肩書きを記入してください。)
|
〒 | (団体については担当者の氏名・役職・TEL・FAX・E-mailを、個人についてはTEL・FAX・E-mailを記入してください。) |
タイトル |
1 趣旨・目的
(地域の経済・産業動向を踏まえ、パッケージ事業の趣旨・目的を記述してください。)
|
2 市町村又は経済団体等が実施する地域再生の取組
| (1 | )・・・・・・
|
||||||
| (2 | )・・・・・・
|
各取組項目ごとに、具体的内容(対象地域を含む)、実施主体、事業規模等を記述してください。なお、「地域創業助成金の活用」を予定している地域については、それを取組の1つとしてあげ、「イ 内容」の部分に重点分野として申請する予定の産業分野を記述してください。 |
3 課題
|
4 パッケージ事業として実施しようとする事業の内容
| (1 | )・・・・・・
|
||||||||||||
| (2 | )・・・・・・
|
パッケージ事業の実施を希望する期間中に実施する事業全てを記述して下さい。また、各事業項目(例えば、「中核的人材の招聘のための説明会の開催」、「地域外の先進的な企業等への労働者等の派遣による研修の実施」等)ごとに、事業の具体的内容、実施期間及びその2の取組のいずれか又は全部との連携方法(3の課題をどのように解決するのかを含む)を記述してください。 |
5 雇用創出についての目標
| (1 | ) アウトプット指標
|
||||||
| (2 | ) アウトカム指標(累積)
|
それぞれ、可能な限り具体的な指標、データ把握方法を明らかにしつつ、定量的に記述してください。なお、(1)、(2)ともに、事業の実施を希望する期間が1年度限りの場合は[2]及び[3]、2年度限りの場合は[3]は不要です。 |
6 所要経費の概算(予定額)
|
| 委託事業対象経費 | 委託費の額 | 備考 | ||||||||||||||||
1 管理費
2 事業費
3 消費税 |
千円 | |||||||||||||||||
(事業構想要約版 様式)
| 1 協議会構成員 | |
| 2 パッケージ事業の実施に係る地域 | |
| 3 パッケージ事業の趣旨・目的 | |
| 4 市町村又は経済団体等が実施する地域再生の取組 | |
| 取組の概要 | 実施主体 |
| 5 4の取組の課題 | |
| 6 パッケージ事業の内容及び4の取組との連携方法 | |
| 内容 | 連携方法 |
| 7 雇用創造効果の見込み | |
○○○名(平成18年度○○○名、19年度○○○名、20年度○○○名) |
|
第1章 総則
| ( | 名称) |
| 第 | 1条 本協議会は、○○○○協議会と称する。 |
| ( | 事務所) |
| 第 | 2条 本協議会は、主たる事務所を○○県○○市○○町○丁目○番地に置く。 |
| 2 | 本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
| ( | 目的) |
| 第 | 3条 本協議会は、会員である市町村の区域において、市町村や経済団体等の創意工夫により実施する地域経済の活性化や雇用機会の創出のための地域再生の具体的取組と相まって、その取組の雇用機会増大効果を高める事業を実施し、当該地域の雇用構造の改善を図ることを目的とする。 |
| ( | 事業) |
| 第 | 4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、地域提案型雇用創造促進事業その他本協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
第2章 会員
| ( | 会員) | ||||||||||||||
| 第 | 5条 本協議会の会員は、次の通りとする。
|
第3章 役員
| ( | 代表) |
| 第 | 6条 本協議会に、1名の代表を置く。 |
| 2 | 代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。 |
| ( | 監事) |
| 第 | 7条 本協議会に、○名の監事を置く。 |
| 2 | 監事は、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。 |
| ( | 選任等) |
| 第 | 8条 代表及び監事は総会において選出する。 |
| 2 | 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 3 | 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 4 | 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第4章 総会
| ( | 構成) | ||||||||||
| 第 | 9条 総会は、会員をもって構成する。 | ||||||||||
| 2 | 総会の議長は、代表が務める。 |
||||||||||
| ( | 権能) | ||||||||||
| 第 | 10条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。 | ||||||||||
| ( | 開催) | ||||||||||
| 第 | 11条 総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の請求があったとき、開催する。 | ||||||||||
| ( | 定数及び議決) | ||||||||||
| 第 | 12条 総会は、全会員の出席がなければ開催することができない。 | ||||||||||
| 2 | 総会の議事は、全会員の賛成をもって決する。 |
||||||||||
| ( | 議事録) | ||||||||||
| 第 | 13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
|
||||||||||
| 2 | 議事録には、議長が、署名、押印をしなければならない。 |
第5章 運営委員会
| ( | 構成) |
| 第 | 14条 運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。 |
| ( | 機能) |
| 第 | 15条 運営委員会は、次の事項を行う。 (1) 事業計画案の策定 (2) 事業の具体的な企画・運営に係る事項 (3) その他事業実施に必要な事項 |
| ( | 開催) |
| 第 | 16条 運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。 |
第6章 財産及び会計等
| ( | 財産) |
| 第 | 17条 本協議会の財産は、寄付金品、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。 |
| 2 | 本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。 |
| ( | 事業構想、事業実施計画及び予算) |
| 第 | 18条 本協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表が作成し、総会において、全会員の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
| ( | 事業報告及び決算) |
| 第 | 19条 本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、全会員の議決を得なければならない。 |
第7章 規約の変更及び解散
| ( | 規約の変更) |
| 第 | 20条 この規約は、総会において、全会員の議決を得なければ変更することができない。 |
| ( | 解散) |
| 第 | 21条 本協議会は、総会において、全会員の議決を得て解散することができる。 |
| ( | 残余財産の処分) |
| 第 | 22条 本協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において、全会員の議決を得て、本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 |
第8章 事務局
| ( | 設置等) |
| 第 | 23条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
| 2 | 事務局には、事業推進員及び会計事務責任者を置く。 |
| 3 | 事業推進員及び会計事務責任者は、代表が任命する。 |
| ( | 備え付け書類) |
| 第 | 24条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。 (1) 本規約 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 (3) 代表、監事及び職員の名簿 (4) 規約に定める機関の議事に関する書類 (5) その他必要な書類 |
第9章 補足
| ( | 委任) |
| 第 | 25条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。 |
付則
1 この規約は、本協議会が設立された日から施行する。
| ( | 目的) |
| 第 | 1条 この規程は、○○○○協議会(以下「協議会」という。)が、地域提案型雇用創造促進事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費として交付を受けた委託費(以下「委託費」という。)に係る会計事務に関し必要な事項を定め、適正な事務処理を図ることとを目的とする。 |
| ( | 予算) |
| 第 | 2条 事業に係る予算は、委託費をもってあてることとする。 |
| 2 | 事業に係る予算に委託費以外のものがある場合には、委託費と区分して経理しなければならない。 |
| ( | 会計事務責任者) |
| 第 | 3条 会計事務責任者は、協議会規約に基づき任命された者とする。 |
| 2 | 会計事務責任者は、必要があると認めるときは、出納者及び補助者を任命して、会計事務の一部を行わせることができる。 |
| ( | 委託費の受入口座) |
| 第 | 4条 会計事務責任者は、○○銀行○○支店に代表名義の口座を開設し、その口座に委託費を受け入れるものとする。 |
| 2 | 受入口座の名義は、必ず協議会の名称及び前項の職名を含むものとする。 |
| ( | 支出事務) |
| 第 | 5条 会計事務責任者は、予算の範囲内において、支出決議書により支出決議を行うも のとする。 |
| 2 | 支出決議された債務は、速やかに支払うものとし、支払方法は銀行振込とする。ただし、必要と認められる事情がある場合は現金払とする。 |
| ( | 帳簿) |
| 第 | 6条 会計事務責任者は、現金出納簿、科目整理簿及び物品管理簿を備え付け、会計事務の執行状況及び物品の在庫状況を記録、計算、整理し、実績を明らかにしておくもの とする。 |
| ( | その他) |
| 第 | 7条 この規程で定めるもののほか、会計事務処理上必要な事項については、協議会の総会の議決を経て、協議会の代表が別に定めるものとする。 |
付則 この規約は、平成18年 月 日から施行する。