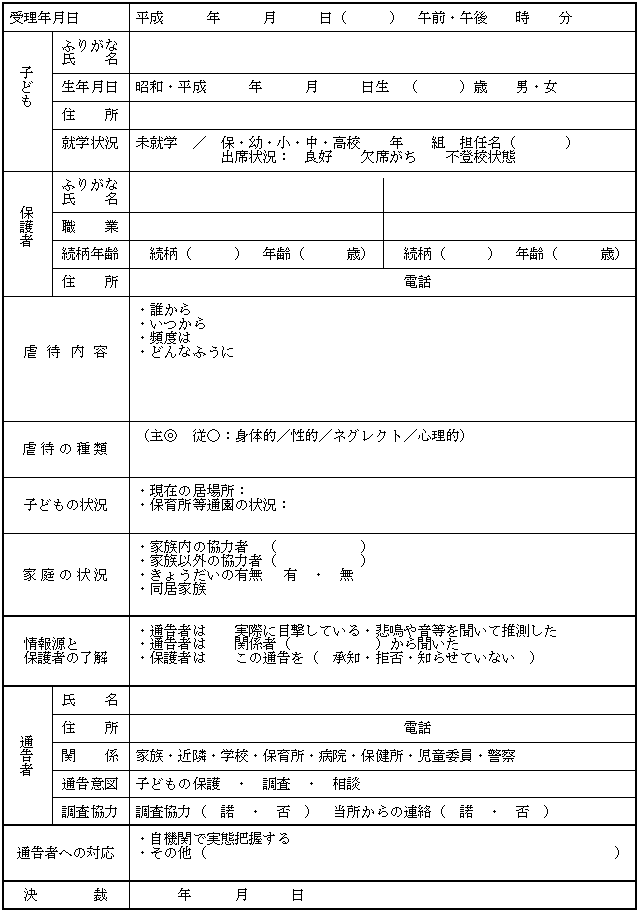ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 子ども虐待対応の手引きの改正について(平成19年1月23日雇児発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知) > 子ども虐待対応の手引き > 第3章 通告・相談への対応
第3章 通告・相談への対応
| 1. |
通告・相談時に何を確認すべきか
虐待については、子ども本人や虐待を行っている保護者からの相談と近隣等個人や関係機関等からの文書または口頭による通告のほか、匿名の通告もある。
通告者が個人の場合には、「虐待でなかったらどうしよう」と通告することを躊躇する気持ちや、「恨まれたり、責任を問われるのではないか」と通告後の事態への危惧感から不安な心理状態で通告してくることが多い。一方で、児童相談所や市町村が、すぐに虐待をやめさせて問題を解決してくれると期待して、通告してくる場合もある。
いずれの場合であっても、不安や不信感を相手に与えない対応によって、通告・相談の内容を聴取し、確認しなければならない。 |
| (1) |
通告の対象となる子ども
子ども虐待の早期発見を図るためには、広く通告が行われることが望ましい。しかし、従来の児童虐待防止法では、通告の対象は「児童虐待を受けた児童」とされており、基本的には、子どもが虐待を受けているところを通告者が目の前で見た、あるいは子どもの体に虐待によるあざや傷があるのを見たといった児童虐待が行われていることが明白な場合が想定されていた。
このため平成16年児童虐待防止法改正法により、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大された。これにより虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、子どもの福祉に関わる専門家の知見によって児童虐待が疑われる場合はもちろんのこと、一般の人の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば、通告義務が生じることとなり、児童虐待の防止に資することが期待される。
なお、こうした通告については、児童虐待防止法の趣旨に基づくものであれば、それが結果として誤りであったとしても、そのことによって刑事上、民事上の責任を問われることは基本的には想定されないものと考えられる。 |
| (2) |
通告・相談時に確認すべき事項(虐待相談・通告受付票の記入)
あらかじめ必要事項を記載した虐待相談・通告受付票を作成しておき、これに基づいて聴取する。(表3−1参照)
虐待の第一報を受けたら、まず通告者からできる限りの情報提供をしてもらい、その情報を虐待相談・通告受付票(表3−1)に記入する。多少あいまいな情報や不明な項目があっても、記入可能な事柄を記入しておくことが重要である。
後日法的対応をとる際の家庭裁判所への提出書類の一つとなる可能性もあるので、鉛筆ではなく、ボールペンなどによって記入する。
記入後は、所長などの責任者の決裁を受ける。
決裁後は、虐待通告受付台帳に編綴するとともに、児童記録にも添付する。
なお、虐待の「通告」という形を取らない一般的「相談」などの中やその子ども以外のきょうだいへの虐待が潜んでいる場合があるので、注意を払う必要がある。
たとえば、「たびたび嘘をつく」「おもらしをする」「夜遅くまで帰らない」「親の言うことを聞かない」など、子どもの行動や性格、育児などの相談、非行の通告などの場合でも、虐待の潜在に留意しなければならない。 |
| (3) |
通告・相談のパターン
最近は子ども虐待についての世間の認識が広がり、児童相談所や福祉事務所等に「虐待かもしれない」との通告や相談が数多く寄せられるようになった。通告や相談のパターンは大きく分けて次の三つになる。
| [1] |
学校、保育所、病院等、子どもが通ってくる、または現実にいる機関からの通告や相談で、家庭内の状況はある程度分かるし、通告や相談内容も具体的なものが多い。 |
| [2] |
同居の家族や親族など、子どもの虐待を直接見ているが、独力では解決が困難で通告や相談をしてくるもの。多くは自分が通告・相談したことを秘密にしてほしいとの気持ちが強く、直接の援助や介入の糸口を期待しにくい。また、主観的・感情的な表現が多く、緊急な対応を求められることも多い。 |
| [3] |
近隣住民等からの通告・相談で、子どもや家族の様子は断片的にしか分からないが、貴重な情報になる。しかし住所や氏名、家族構成など基本的なことから調査が必要になる。 |
|
| (4) |
通告・相談者別の対応
| [1] |
子ども本人からの相談
| ア. |
児童相談所や市町村が必ず安全や秘密を守ることを伝えた上で、子どもの状況を把握する。
| (ア) |
協力してもらえる人はいるか。 |
| (イ) |
虐待の内容と程度。 |
| (ウ) |
子どもが一人で行動できる力の程度や範囲。 |
| (エ) |
連絡方法の確認や会って話を聴く約束をする等、子どもとの継続的な関わりが持てるようはたらきかける。 |
|
| イ. |
児童相談所や市町村の援助の内容、方法を具体的に説明する。 |
| ウ. |
子どもと関わりのある学校等の関係機関と協力して解決していくことを説明して子どもの了解を得る。 |
|
| [2] |
虐待を行っている保護者からの相談
| ア. |
非難や批判をせず、訴えを傾聴する。共に問題を考える姿勢を示し、必要な場合には解決への方法や見通しについて、具体的な助言や指示をする。 |
| イ. |
虐待の内容と程度。 |
| ウ. |
虐待を受けている子どもに対する気持ち。 |
| エ. |
家族関係や生活の状況。 |
| オ. |
援助者(親族・関係機関)の有無。 |
| カ. |
どんな援助を求めているか。 |
| キ. |
児童相談所や市町村の援助の内容、方法を具体的に説明し、来所できなければ訪問することを伝える。 |
|
| [3] |
家族、親族からの相談・通告
| ア. |
家族、親族としての立場や心配を受け止めながら話を傾聴し、虐待を行っている保護者や虐待を受けている子どもとの関係等についての情報を聴取する。 |
| イ. |
家族については、虐待状況の中に置かれている当事者として受け止め、共に家族の問題を考える姿勢で向かい合う。解決への方法や見通しについて具体的助言や指示が必要な場合もある。 |
| ウ. |
親族の通告には、虐待を行っている保護者への恐れからの躊躇や、家族間の軋轢による中傷等が含まれることもあるので、通告の真意を十分理解して状況を把握する必要がある。具体的な助言や指示等は慎重に行わなければならない。 |
|
| [4] |
地域、近隣住民からの相談・通告
| ア. |
匿名通告の場合は、通告者のプライバシーの保護をていねいに説明して、氏名、住所、連絡先等を教えてもらう努力をする。また、以後の情報を受ける窓口として、担当者名を伝える。 |
| イ. |
児童相談所や市町村が責任を持って対応することを伝え、継続的な情報提供等の協力を依頼する。 |
| ウ. |
通告者の考え方や態度から、直接的行動が危惧されるような場合は、注意を喚起する必要がある。 |
|
| [5] |
警察からの通告
| ア. |
虐待を通告の理由としたものの他、家出、徘徊、迷子、万引き等の背景に虐待がある場合も多いので留意が必要である。 |
| イ. |
通告がされた場合
| (ア) |
虐待内容と受傷の程度等の情報を聴取し、一時保護所で保護が可能かどうか、入院の要否や医師の待機の必要性を確認する。 |
| (イ) |
通告がされたことについて保護者に連絡したか、していれば保護者の反応はどうだったかを確認する。 |
| (ウ) |
保護者からの物理的な抵抗を受けるおそれがあり、児童相談所だけでは一時保護の実施や子どもの安全の確保等が困難な場合には、警察への援助の依頼を検討する。 |
| (エ) |
関係機関(学校、保育所、保健所、福祉事務所等)から情報を収集する。 |
| (オ) |
状況により、警察にパトロール等を依頼する。なお、身柄の引き渡しがない場合であっても、児童相談所又は市町村として受け付け、状況の聴取、関係者への調査、子どもの安全の確認等適切に対処する。 |
|
| ウ. |
警察が一時保護を要すると思料する要保護児童を発見し、児童相談所に通告した場合、児童相談所においては、夜間、休日等であっても原則として速やかに警察に赴いてその子どもの身柄の引継ぎを行うことが必要である。
ただし、児童相談所が遠隔地にある場合などやむを得ない事情により、児童相談所が直ちに引き取ることができないときには、警察に対して一時保護委託を行うことも考えられる。
また、特に夜間において、児童相談所の職員だけでは対応が著しく困難な場合には、警察職員に一時保護所までの同行を依頼するといった対応が必要となることも考えられる。
児童相談所においては、こうした点も踏まえ、警察との日常的な協力関係を築くよう努めること。 |
| エ. |
児童福祉法及び児童虐待防止法は、一時保護の要否に応じて通告先を異ならせておらず、また警察に一時保護の要否を判断する権限はないことから、警察は、一時保護の要否その他の事情にかかわらず、市町村、福祉事務所及び児童相談所のいずれの機関に対しても通告を行うことができる。
ただし、深刻な虐待が疑われる場合など緊急性、専門性が高いと警察が判断した場合には、一般的には、市町村や福祉事務所ではなく、児童相談所に直接通告することとなる。
なお、市町村、福祉事務所及び児童相談所は、警察からの要保護児童の通告について、身柄付であるか否かを問わず、その受理を拒否することはできない。このため、市町村又は福祉事務所は、警察からの通告を受けた場合において、その子どもについて一時保護が必要であると判断するときは、通告を受理した上で児童相談所に送致することとなる。また、児童相談所が市町村等が対応することが適当と判断する場合は、通告を受理した上で、市町村等と連携を図りつつ対応することとする。 |
|
| [6] |
保育所、幼稚園・小学校・中学校等の学校等からの相談・通告
| ア. |
身体的虐待やネグレクト、性的虐待がみられたり疑われる場合には、訪問調査により実態を把握する。
| (ア) |
虐待を受けた子どもの在籍状況(入所年月日、入所理由、出欠状況等)。
なお、きょうだいが在籍していればその状況も聴取する。 |
| (イ) |
虐待を受けた子どもの状況(身辺の様子、行動、食欲等)。 |
| (ウ) |
虐待を行っている保護者の状況(虐待の認否、負傷についての受診の有無、送迎等の状況、家族関係、性格、経済状況等)。 |
|
| イ. |
子どもが帰宅を拒否したり、けがが重い場合には、一時保護を検討する。 |
| ウ. |
受傷の程度によっては、医療機関へ受診させ、写真を撮影する。 |
| エ. |
身柄の緊急保護を要請された場合には、身柄付通告に準じて対応する。 |
| オ. |
福祉事務所、教育委員会等関係機関から情報を収集する。 |
|
| [7] |
福祉事務所からの相談・通告
| ア. |
調査に際しての立会いや同行訪問の協力を依頼する。 |
| イ. |
ケースカンファレンス等により、緊密な情報交換を行い、経済的援助や入院指導などによる家族環境の改善等についての協力体制をつくる。 |
|
| [8] |
保健所・市町村保健センターからの相談・通告
| ア. |
家族状況、きょうだい関係や健康診断歴等の情報を確認する。 |
| イ. |
虐待を行っている保護者に精神疾患が疑われるある場合は、精神保健福祉相談員または保健師と連携し、必要な場合は主治医、警察等への協力を要請する。 |
| ウ. |
緊急性を見極めながら、緊密な情報交換や同行訪問などの連携体制をつくる。 |
|
| [9] |
医療機関からの相談・通告
ほとんどは入院中のケースであるが、外来受診時に虐待を危惧して通告される場合もある。通告を受けたら、医療機関に出向いて主治医や関係職員から状況を聴取し、子どもが入院中の場合はその状態を直接確認する。
| ア. |
受診経過(いつ、どこから、誰が付き添って来たか)。 |
| イ. |
子どもの状態と見通し(外来であれば継続あるいは再受診の可能性の確認)。 |
| ウ. |
虐待と判断もしくは疑った根拠(診断書発行の依頼)。 |
| エ. |
警察への通報の確認(場合によっては通報を要請)。 |
| オ. |
保護者に対して、主治医から受傷等についての所見をどのように説明したり、伝えているか。(保護者が若年の場合には、祖父母が同席での説明が望ましい)。 |
| カ. |
保護者の病院に対する反応はどうか。 |
| キ. |
保護者について病院が知り得ている情報と意見。 |
| ク. |
児童相談所や市町村が関わることについての事前設定と紹介の方法および今後の連携の窓口担当者を確認。 |
|
| [10] |
民生・児童委員(主任児童委員)からの相談・通告
| ア. |
通告の内容を聴取し、地域での家族の生活状況や、家庭への援助者の有無等について、当該家族の人権を配慮した調査協力を要請する。 |
| イ. |
継続的な観察情報の提供と協力について依頼する。 |
|
| [11] |
配偶者暴力相談支援センターからの相談・通告
| ア. |
配偶者からの暴力がある家庭においては、子どもの面前で配偶者に対する暴力が行われる等の心理的虐待だけでなく、子どもが身体的虐待、性的虐待又はネグレクトを受けている場合も多いことに留意する。 |
| イ. |
子ども又は子どもの保護者に対応する場合、その対応によって配偶者からの暴力の被害者が、配偶者からの更なる暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるなど、配偶者からの暴力の被害者及びその子どもの安全が損なわれることのないよう、ケースカンファレンス等により、事前に必ず配偶者暴力相談支援センターと十分な協議を行う。 |
|
|
| 2. |
通告・相談があった場合にまず何をやるべきか
通告・相談を受理した児童相談所や市町村は、虐待を受けた子どもの生命を守り、安全を確保することを最優先して対応することが必要である。
虐待が疑われる事例や、将来虐待にいたる可能性の高い事例等も、児童相談所や市町村が相談や情報提供等を受けたことをもって通告として受理する。
通告・相談を受けた者は、単独で判断せずに速やかに責任者に報告し、緊急受理会議を開催して、初期対応を検討する。 |
| (1) |
緊急受理会議の開催
| [1] |
虐待相談・通告受付票(表3−1)に記入した後、速やかに緊急受理会議を開催する。 |
| [2] |
緊急受理会議の準備の一環として、通告を受けた事例について、過去の通告や援助などを通して児童相談所や市町村に情報が蓄積されているかどうかを確認しておく。 |
| [3] |
所内の管理職、通告受理者を中心に対応可能な職員が参加する。必要に応じて、一時保護所職員の参加を求める。 |
| [4] |
協議決定事項は、受理会議録として決裁を受け保存する。 |
|
| (2) |
緊急受理会議の検討事項
虐待相談・通告受付票(表3−1)に基づいて検討する。
| [1] |
虐待の確認と判断
通告内容から虐待が明確に判断できない場合でも、子どもの安全を確認するための調査を行う。 |
| [2] |
緊急性の判断
子どもの被虐待状況(症状・程度)はどうか。生命の危険はないか等緊急保護の必要性について、関係機関との連携も考慮しながら判断する。 |
| [3] |
担当者の決定
原則として複数体制とし、身体的虐待が疑われる場合には、医療職(医師・看護師・保健師・助産師)を加える。 |
| [4] |
初期調査の内容
| ア. |
虐待通告の正確な内容把握と事実の確認(虐待相談・通告受付票情報の補完)。 |
| イ. |
危機状況の評価と緊急保護の判断(第4章1参照)。 |
| ウ. |
関係する機関の確認と調査依頼および役割分担。 |
|
|
| (3) |
緊急受理会議後の対応
| [1] |
緊急を要すると判断される事例では、その場にいる職員で分担して対応を開始する。一時保護が必要と判断された場合には、現場に向かう役割・一時保護の段取りをする役割・調査をする役割・警察等他機関との調整をする役割などを分担して、即刻対応を開始する。この場合、所長等の管理職の1人は児童相談所に待機し、職員からの連絡を待つとともに、必要な指示を与える。
子どもの身柄の保護を優先し、保護した後早急に保護者等から事情を聴取し、一時保護あるいは入院についての相談、説得を行う。
なお、市町村においては、至急、児童相談所に送致することとする。 |
| [2] |
通告の段階で得られた情報では緊急性がないと判断できる場合や、情報が不足する場合は、その後の調査方針と調査担当者を決定する。調査しなければならない項目を列挙し、誰がどこの機関に何を聞くかを明確にして分担する。 |
| (3) |
緊急受理会議で決定した内容は、受理会議録に記入し、速やかに所長などの責任者の決裁を受ける。 |
| (4) |
受理会議録は2部作成し、一部は受理会議簿に、一部は児童記録票に編綴する。 |
|
| (4) |
時間外の対応
休日、夜間についても適切な対応ができる体制(時間外窓口、職員連絡網、夜間対応のマニュアルなど)の整備が必要である。
市町村においては、例えば、当直体制の整備など、自らが通告を受けて適切な対応が取れるような体制の確保に努めるほか、夜間、休日等の執務時間外における電話等による通告の受理について、
| [1] |
複数の市町村、都道府県の設置する福祉事務所が広域で連携し、輪番制等により担当する。 |
| [2] |
児童家庭支援センターなどの民間の相談機関に対応を委託する。 |
| [3] |
児童相談所の担当区域内の市町村、都道府県の設置する福祉事務所への通告については、児童相談所に自動転送し、児童相談所において対応する。 |
といった手法により対応することとし、通告受理後の対応は事例の緊急度等に応じて行うといった体制を整備することが考えられる。
また、児童相談所においては、当直体制の整備など自らが通告を受けて適切な対応が取れるような体制の確保に努めるほか、児童相談所が市町村や福祉事務所とは異なり、立入調査や一時保護等の権限の行使を認められた児童福祉の専門機関であることも踏まえ、夜間、休日等の執務時間外の市町村等からの送致や相談に適切に対応することが必要である。
緊急対応を要する場合には、当面の対応方針と担当職員(チーム体制)を決定して初期対応を行う。
翌日等に緊急受理会議を開き、時間外対応の状況報告と評価を行い、今後の方針を決定する。 |
| (5) |
通告者への報告
虐待の通告をした人は、多くの場合、児童相談所や市町村の対応に期待と関心を寄せている。守秘義務の許す範囲で、対応方針について報告することが望ましい。
また、通告者が子どもや家族に引き続き関わる可能性がある場合は、どのような関わり方をすることが望ましいのか、児童相談所又は市町村としての要望やアドバイスを伝える。 |
| 3. |
子どもが自ら保護を求めてきた場合、どう対応すべきか
子どもが自ら保護を求める状況とは、激しい身体的虐待を継続的に受けていたり、性的虐待を受けているなど、子どもがせっぱつまった状態で、救助を求めている危機状況にあると受け止め、事実の確認を早急に行って対応する必要がある。
ほとんどの子どもは、自分が保護を求めることにより、保護者の虐待の事実が顕在化することや保護者に対する恐怖心等から、心理的に動揺している状態にある。
児童相談所や市町村が必ず守ってあげることを伝えた上で、子どもの訴えをまず聴くことに徹し、その話を支持して安心感を与え、緊張状態を緩和することが大切である。子どもの年齢に合わせた対応の仕方と表情や態度の観察を通して、緊急保護対応の判断のための情報収集を行わなければならない。
一方で関係機関からの情報収集と対応についての意見を聴取し、緊急受理会議によって方針を決定する。 |
| (1) |
子どもが電話や手紙等で保護を求めてきた場合
| [1] |
本章1(4)[1]による対応をする。 |
| [2] |
原則として来所を促し、信頼のおける人に同行してもらうように助言する。 |
| [3] |
来所できない場合には出向くことを伝え、本人の意思を尊重して対応する。 |
| [4] |
緊急の場合には110番通報や警察に助けを求めるように助言する。 |
|
| (2) |
子どもが来所して保護を求めた場合
| [1] |
子どもとの面接により、下記の事項を把握する。
| ア. |
虐待の内容と程度(事実の確認、証拠資料が得られるか)。 |
| イ. |
子どもの状態(外傷の有無・程度、衣服の様子等)。 |
| ウ. |
自分の身を守り、危機を回避できる能力がどの程度あるか。 |
| エ. |
保護者へはどんな気持ちを持っているのか。 |
| オ. |
親族のなかに援助を期待できる人はいるのか。 |
| カ. |
保護者の状況。
| (ア) |
保護者は、保護を求めたことを知っているのか。 |
| (イ) |
保護者は、児童相談所や市町村から連絡するとどんな反応や行動をとるか。 |
|
|
| [2] |
児童相談所や市町村の援助について説明する。 |
| [3] |
学校、警察や福祉事務所等の関係機関へ連絡協議することの了解を得る。 |
| [4] |
関係機関から情報収集を行う。情報収集については、第4章1を参照。 |
|
| (3) |
緊急受理会議
本章2(2)と同様に対応方針を決定する。
| [1] |
緊急保護する。
身柄を一時保護する。
本章2(2)および(4)により初期対応を行う。 |
| [2] |
緊急保護はしない。
虐待の程度が比較的軽く、子どもが危険から逃れる能力があり、子ども自身も保護について決心がつかない場合、必要な調査や情報収集を行った後に対応方針を決定する。
子どもに対しては、今後、いつ、どんな時でも必要があれば保護することができると伝え、連絡方法や警察などの連絡窓口等についての情報を具体的に教える。
関係機関に連絡し、今後の情報交換、連携について協力を依頼する。 |
|
| 表3−1 虐待相談・通告受付票 |
聴取者( ) |
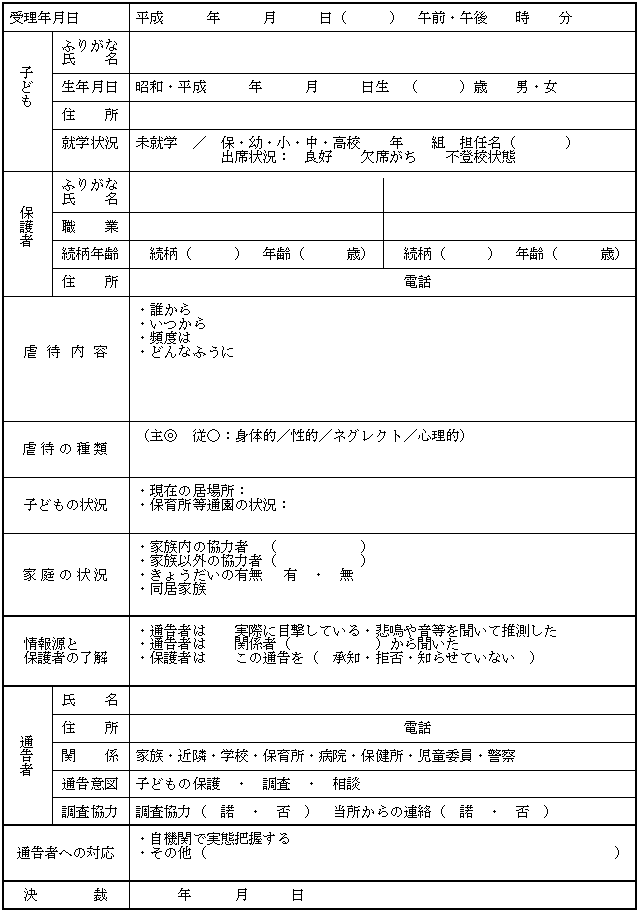 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 子ども虐待対応の手引きの改正について(平成19年1月23日雇児発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知) > 子ども虐待対応の手引き > 第3章 通告・相談への対応