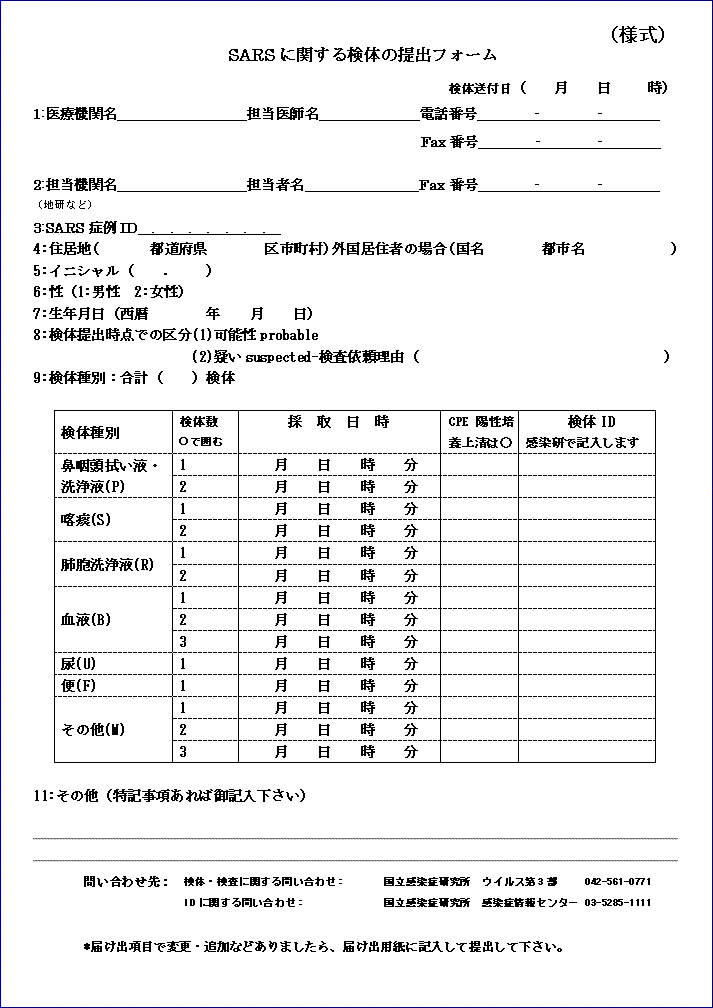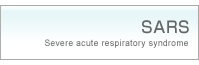
重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報
| 別紙 |
I 「疑い例(Suspected case)」の外来での管理
| 1. | SARS(渡航歴、発熱、呼吸器症状)を心配されている患者には、すみやかに受け付けなどに申し出てもらう(患者への注意書き等で掲示しておくことが望ましい)。マスク(外科用)を着用してもらい、出来るだけ他の患者と接触しないような隔離室・個室等の場所に誘導する。 | ||||||||||
| 2. | 診療に当たる医療従事者は接触感染及び空気感染に対する予防策をとり、N95マスク(なければ外科用マスク)を着用する。 | ||||||||||
| 3. | (1)発熱、(2)咳又は呼吸困難感、(3)伝播確認地域への発症前10日以内の旅行歴又は居住歴があるか確認する。 | ||||||||||
| 4. | 上記3点をみたす「疑い例(Suspected case)」であると考えられた場合にはすみやかに胸部レントゲン撮影、血球検査(CBC)、生化学検査、インフルエンザ等の可能な迅速診断法を行う。この際、病原体検査用の検体採取等を行う。 | ||||||||||
| 5. | 胸部レントゲン写真に異常所見が無い場合は、
| ||||||||||
| 6. | 胸部レントゲン写真で、片側、または両側性の肺浸潤影を認めた場合は、「可能性例」として対応する。 |
II 「可能性例(Probable case)」の管理
| 1. | 可能性例は入院を原則とする。 | ||||||||
| 2. | 病室は個室を原則とする。病室は陰圧、独立した空調設備である方がより望ましい。個室が不足している場合は、SARSの可能性例と診断された複数の患者を同室に入室させ入院とする。 | ||||||||
| 3. | 以下の臨床検体を採取し、既知の異型肺炎の病原体感染を除外する。
| ||||||||
| 4. | 通常の肺炎(異型肺炎を含む)に対する治療および臨床症状に応じた治療を開始する。(飛沫を生じる可能性のある治療あるいは処置には特別の注意を払い、これらが必要な場合には、適切な感染予防措置を講ずること) | ||||||||
| 5. | SARSにおいては多数の抗菌薬が試用されてきたが、明らかな効果のあるものはなかった。海外では、ステロイド併用あるいは併用なしで静注用リバビリン(国内未承認薬)使用の報告があるが、その明確な効果は証明されていない。 | ||||||||
| 6. | 臨床状態の改善をみた場合、個々の症例により退院時期を決定する。 |
| (注) | 臨床経過、検査その他によりSARS以外の疾患であることが説明できる場合、標準の抗生剤治療で改善する等、病状の改善を医師が認めるものについては、SARSの可能性は低い。 |
III 「疑い例」、「可能性例」との接触者の管理
接触者とは、SARSの「疑い例」あるいは「可能性例」の患者が症状を呈している間に、濃厚な接触をもった者とする。濃厚な接触とは、「疑い例」あるいは「可能性例」のSARS患者の介護、同居、又は体液や気道分泌物に直接触れた場合を言う。
| 1. | SARSに関する情報を提供する。 |
| 2. | 症状がない場合は、日常の行動を続けてよい。 |
| 3. | 発熱や呼吸器症状が出た場合は、すみやかに医療機関に連絡し、受診すること。 |
| 4. | その際は、「疑い例」、「可能性例」に準じた取り扱いをすること。 |
IV SARSの可能性例に対する院内感染対策
SARS症例に対しては、空気、飛沫、接触感染への予防措置を全て含めた、バリアナーシング手技(注:病原体封じ込め看護)が推奨されている。
| 1. | 医療機関にインフルエンザ様の症状を呈する患者が受診した場合、待合室で他の患者への伝播を最小限に止めるため、担当看護師は速やかにその患者を、出来るだけ他の患者と接触しないような隔離室・個室等の場所に誘導する。SARSが否定されるまで、患者には外科用マスクを着用させる。 | ||||||
| 2. | SARS可能性例は次の優先順位に従って病室に入院させる。
可能であれば、SARSの疑いで検査を受けている患者と、診断が確定した患者は同室にしない。 | ||||||
| 3. | 可能な限りSARSの患者には使い捨て医療器具を用いる。再使用する時は、製造業者の仕様書に沿って消毒する。器具の表面は細菌、真菌、ウイルスに有効な広域の消毒剤で消毒する。 | ||||||
| 4. | 患者の移動は可能な限り避ける。移動させる必要が生じた場合、飛沫の拡散を避けるため、外科用マスクを着用させる。SARS可能性例または疑い例患者の病室に入る全ての面会者、スタッフにN95マスクを着用させる。 | ||||||
| 5. | 手洗いが感染予防のためには重要であり、手袋を使えば手洗いは不要と考えてはならない。どのような患者であっても接触した後、病原体に暴露される可能性のある医療行為を行った後、および手袋をはずした後も手洗いする。手洗いできない場合には、アルコールを含む手指消毒剤を用いる。看護師は全ての患者の看護を行う際には手袋を着用する事が推奨される。手袋は、患者毎に、または患者の気道分泌物に汚染される可能性がある酸素マスク、酸素チューブ、経鼻酸素チューブ、ティッシュペーパーなどの物品に触れた後は必ず交換する。 | ||||||
| 6. | 患者の気道分泌物、血液、その他の体液の飛沫や飛散が発生する可能性のある処置や看護の際には、N95マスク、耐水性ガウン、頭部カバー、ゴーグル、顔面カバー等を使用する。SARSの患者に付き添う場合にあっても同様とする。 | ||||||
| 7. | いかなる医療廃棄物の取り扱いにおいても、標準予防策を適応する。全ての医療廃棄物の取り扱いの際には、紛れ込んだ注射針などによる外傷に注意する。医療廃棄物の入ったゴミ袋、ゴミ箱を取り扱う場合も、手袋と防護服を着用し、素手では取り扱わない。なお医療廃棄物はバイオハザードが印された漏出しない強靱な袋、ゴミ箱に入れ、安全に廃棄する。 |
V 検体の取り扱い
| 1. | 「疑い例」及び「可能性例」の検査は、原則的に、病院検査部もしくは地方衛生研究所において、通常の病原体取り扱いに準じてバイオセーフティレベル(BSL)2で、既知の肺炎を起こす(異型肺炎含む)病原体について一次スクリーニングを行う。 これには、一般細菌培養、迅速診断法(連鎖球菌など一般細菌、レジオネラ、クラミジア、マイコプラズマ、アデノウイルス、インフルエンザウイルス、RSウイルス、その他状況に応じて行う)、血清学的方法(マイコプラズマ、クラミジア)を含む。 |
| 2. | ウイルス分離が可能な検査室ではウイルス分離を行う。ウイルス分離を行う場合には、SARS病原体の危険度レベルが未確定であるので、BSL3施設内においてレベル3に準じて対応する。 |
| 3. | 国立感染症研究所ウイルス第三部第1室では、上記1、2以外のSARSに関する特異的検査を行う。 |
VI 検査材料の輸送
| 1. | 輸送等に当たっての留意点
| ||||||||||||||||||
| 2. | 感染性材料の持参輸送に用いる容器 基本型三重包装容器を用いる。容器は次の三層からなるものを用いる。
検体データ様式、書面、その他検体を識別又は説明するための情報、及び送り主と受取人を特定する情報を二次容器の外側に貼りつけるものとする。
| ||||||||||||||||||
| 3. | 感染性材料の持参輸送に用いる容器の表示(ラベル)
|
図1 感染性材料の輸送法(持参の場合)
感染性材料は三層に包装する。
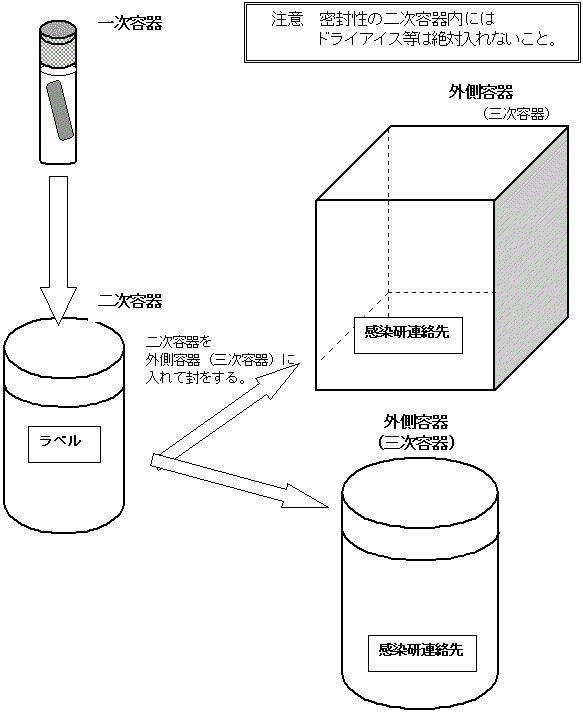
図2 (参考)WHO,Laboratory Biosafety Manual 2nd editionに示されている、郵送のための包装法
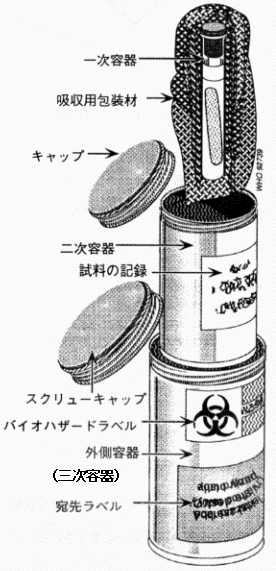
図3 二次容器の例
二次容器には次の表示を行う。
(1) 受取人の名称、住所、電話番号、Fax番号
(2)送り主の名称、住所、電話番号、Fax番号
(3)包装物の数、内容品の詳細、重量等
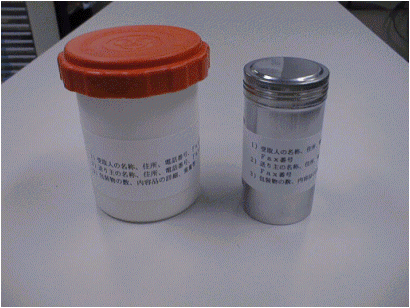
図4 外側容器(三次容器)の例
外側容器(三次容器)には次の表示を行う。
(1)国際感染性物質ラベル(バイオハザードマーク)
(2)国立感染症研究所連絡先