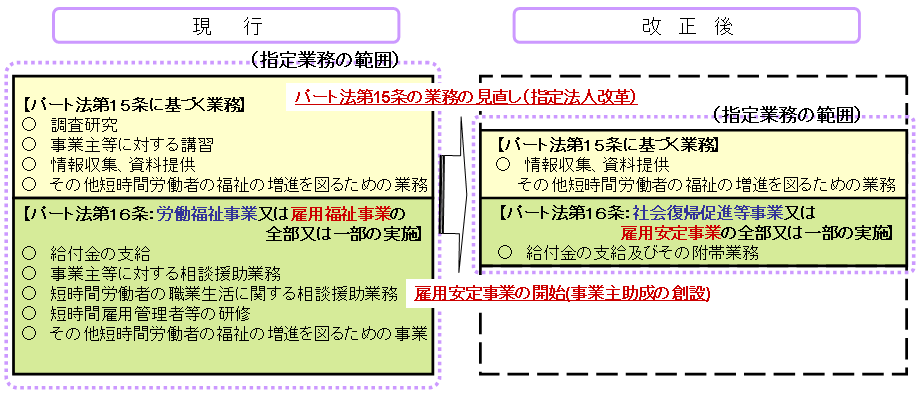パートタイム労働法*の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要
(*「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)
少子高齢化、労働力人口減少社会において、短時間労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転換の推進を図る等のための所要の改正を行う。
就業形態の多様化の進展に対応した共通の職場ルールの確立 |
1 労働条件の文書交付・説明義務
労働条件を明示した文書の交付等の義務化(過料あり)等
2 均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
(1)すべての短時間労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等
(2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取扱いの禁止
3 通常の労働者への転換の推進通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化 |
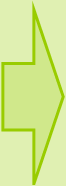 |
|
||
4 苦情処理・紛争解決援助(1)苦情を自主的に解決するよう努力義務化 (2)行政型ADR(調停等)の整備 |
5 事業主等支援の整備
短時間労働援助センターの事業の見直し(事業主等に対する助成金支給業務に集中)
施行期日 平成20年4月1日施行(ただし、5に関しては平成19年7月1日施行)
労働条件の文書交付・説明義務 |
現状・課題 |
○ 多様な働き方であるゆえに個々の労働者の労働条件が不明確となり、相談事例が多いほか、待遇の決定理由が不明であるために、その待遇について不満を持つ者が多い。
○ 労働条件の明示、待遇の説明をすることにより、納得性を向上させることが必要。
|
|
||||||
|
|
均衡のとれた待遇の確保の促進 |
現状・課題 |
○ 短時間労働者の基幹化を背景として、通常の労働者と同じ仕事を行っているにもかかわらず、その働きに見合った待遇がなされない等の不満が高まっている。
○ 働きに見合った公正な待遇の決定ルールを作り、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を図ることが必要。
| 【短時間労働者の態様】 通常の労働者と比較して、 |
賃 金 | 教育訓練 | 福利厚生 | |||||
| 職務関連賃金 ・基本給 ・賞与 ・役付手当等 |
左以外の賃金 ・退職金 ・家族手当 ・通勤手当等 |
職務遂行に必要な能力を付与するもの | 左以外のもの(ステップアップを目的とするもの) | 健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用 | 左以外のもの(慶弔見舞金の支給、社宅の貸与等) | |||
| 職務(仕事の内容及び責任) | 人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲) | 契約期間 | ||||||
| [1] 同視すべき者 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 同じ | 全雇用期間を通じて同じ | 無期or反復更新により無期と同じ | ||||||
| [2] 職務と人材活用の仕組みが同じ者 | □ | − | ○ | △ | ○ | − | ||
| 同じ | 一定期間は同じ | − | ||||||
| [3] 職務が同じ者 | △ | − | ○ | △ | ○ | − | ||
| 同じ | 異なる | − | ||||||
| [4] 職務も異なる者 | △ | − | △ | △ | ○ | − | ||
| 異なる | 異なる | − | ||||||
□・・・同一の方法で決定する努力義務 △・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
通常の労働者への転換の推進 |
現状・課題 |
○ 短時間労働者の一部は、非自発的に短時間労働者となっている者であるにもかかわらず、一度短時間労働者として就職すると、希望にかかわらずその働き方が固定化してしまう。
○ 意欲のある者は、通常の労働者へ転換できるような機会をつくることが必要。
改正内容 |
○ 事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならないこととする
(例)
- 当該事業所の外から通常の労働者を募集する場合には、
その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う - 社内公募として、短時間労働者に対して、通常の労働者のポストに応募する機会を与える
- 一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設ける等、転換制度を導入する等
通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる
苦情処理・紛争解決援助 |
現状・課題 |
○ 「公正な待遇の決定ルール」の担保として、
- 事業所内で苦情を自主的に解決するよう努めることとするほか、
- 均衡待遇等に関する紛争の解決手段として、行政型ADR※(調停等)を整備することが必要。
改正内容 |
|
○ 事業主は、苦情の自主的な解決を図るよう努めることとする ○ 紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停の対象とする ○対象となる苦情・紛争: |
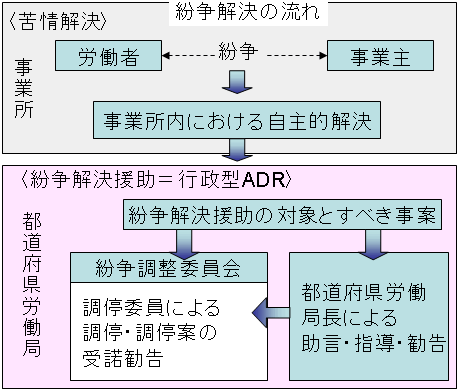 |
※ADR・・・Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争処理手続の略
短時間労働援助センターの業務の見直しについて |
現状・課題 |
○ 均衡のとれた待遇の確保措置等に対する事業主の取組みをより円滑に進めるため、国としてその支援が必要。
○ 同時に、指定法人の業務については、行政改革の観点から大幅に縮小してそのスリム化を図ることとする。