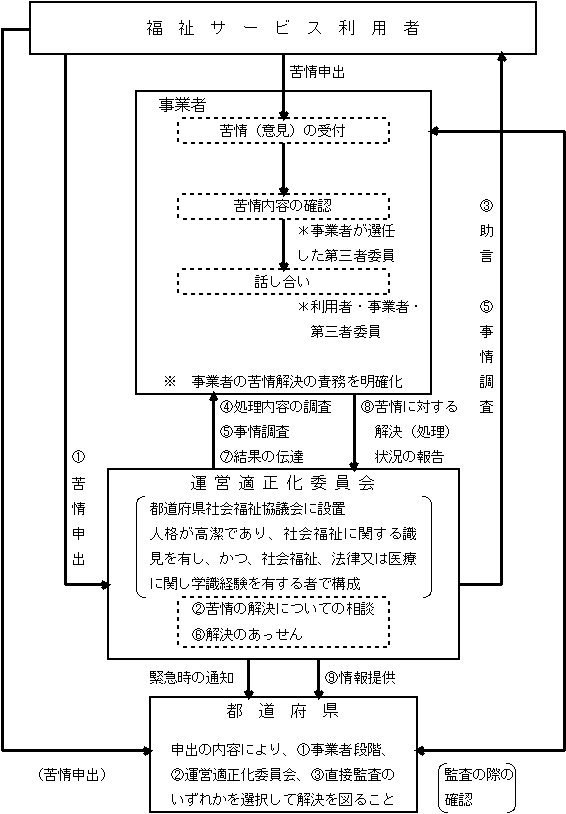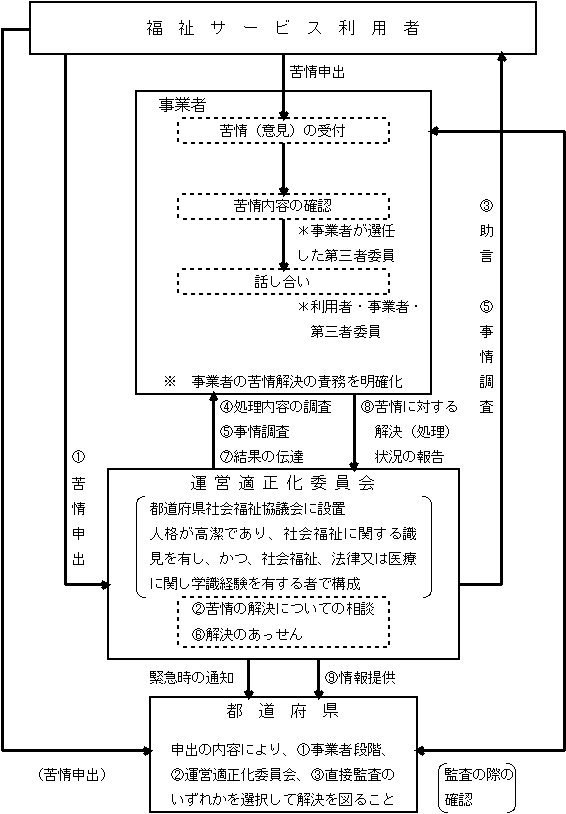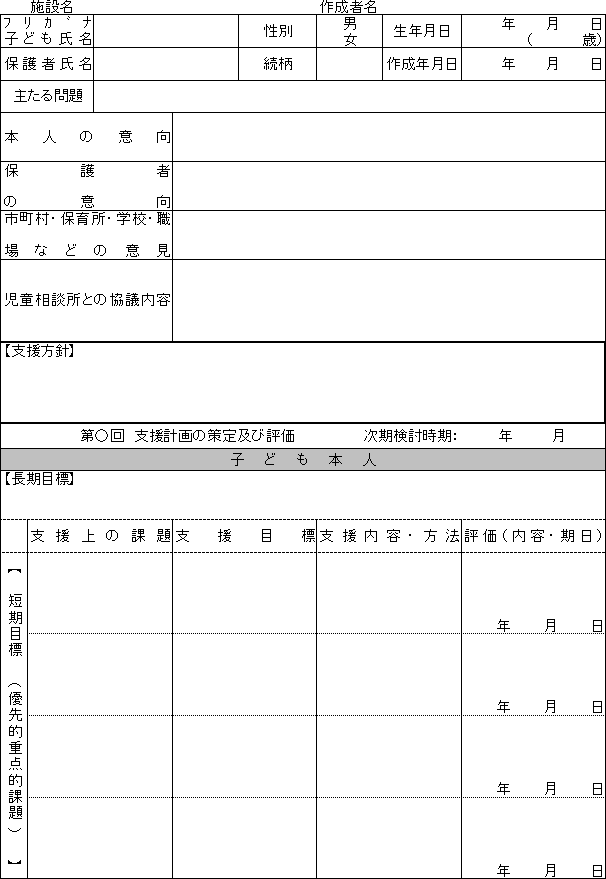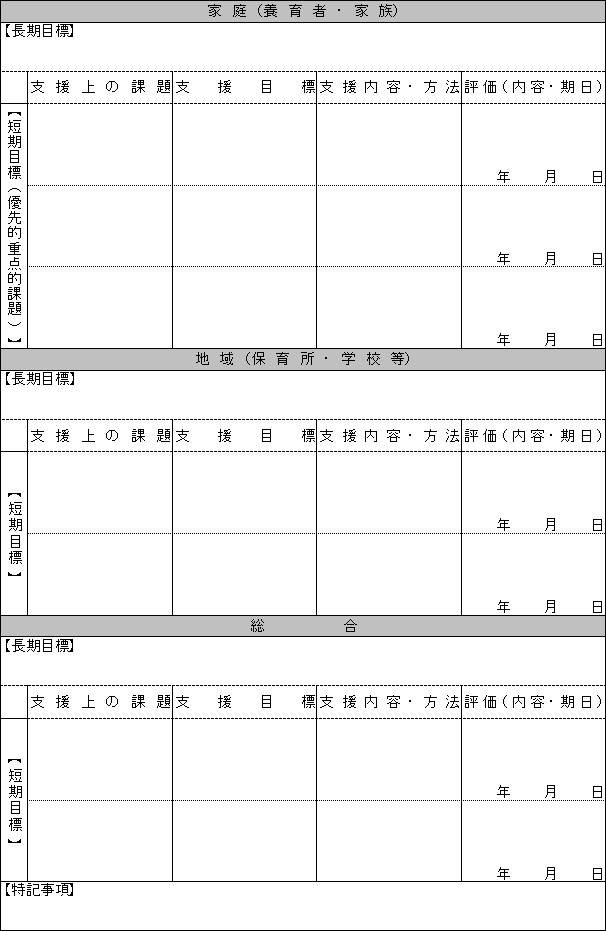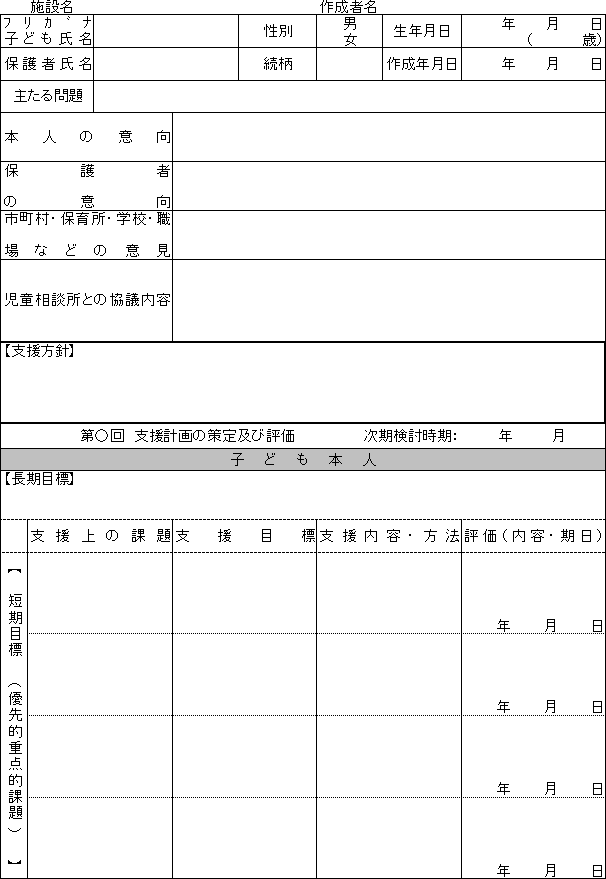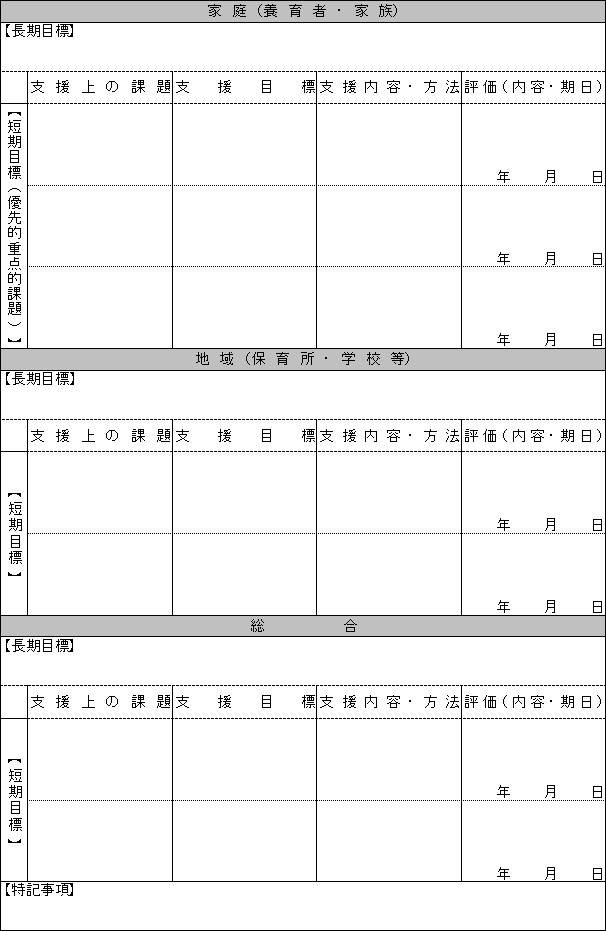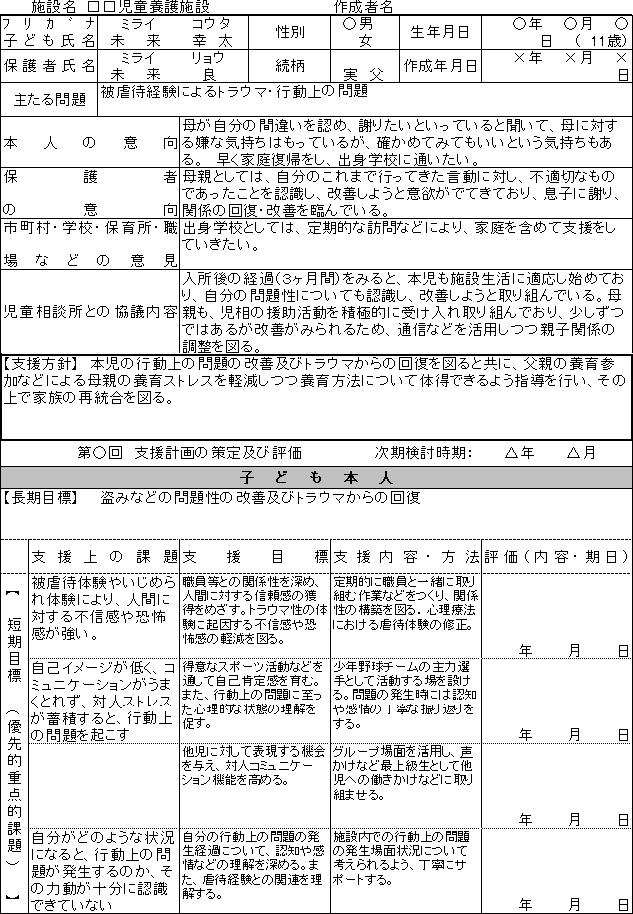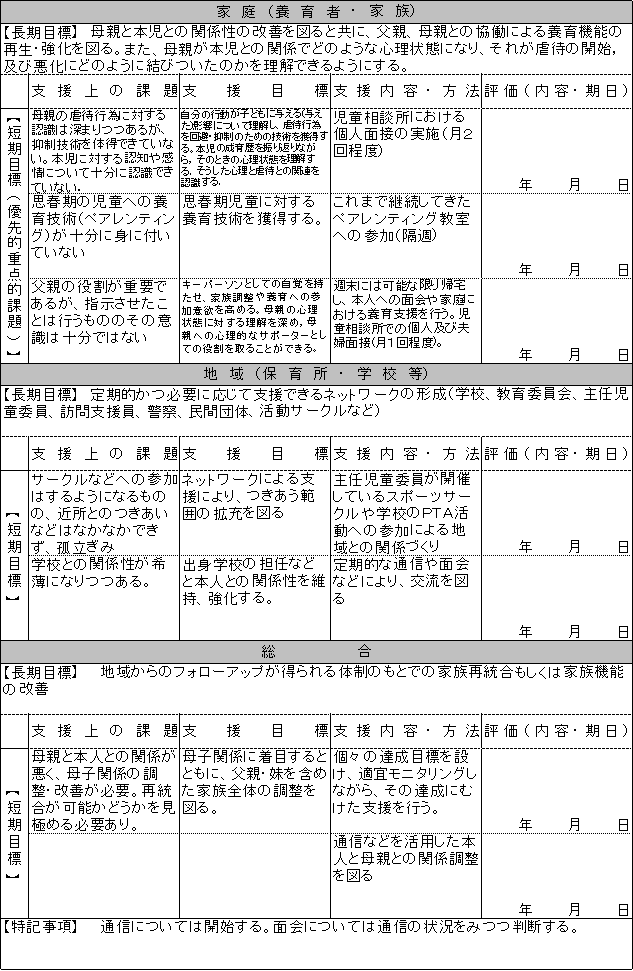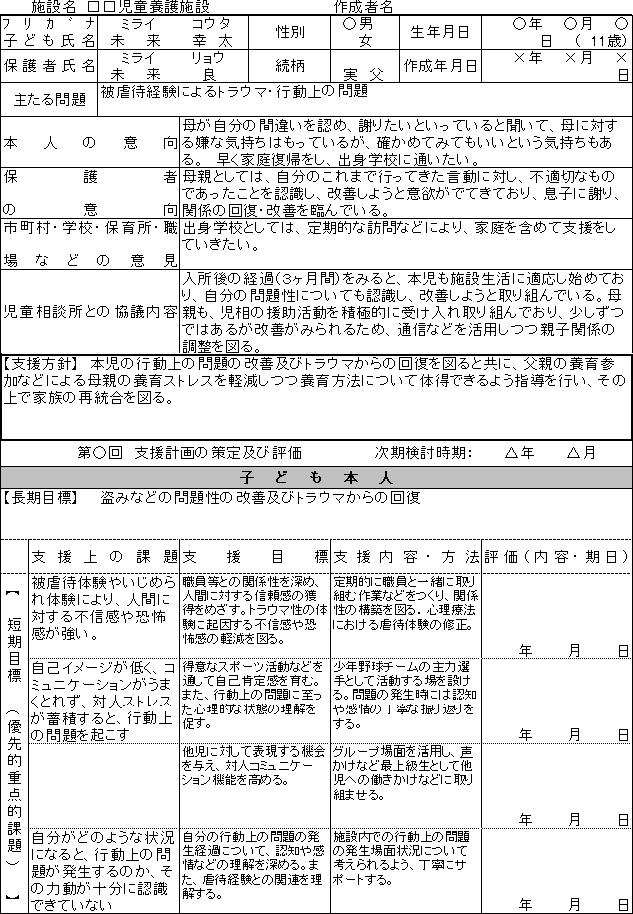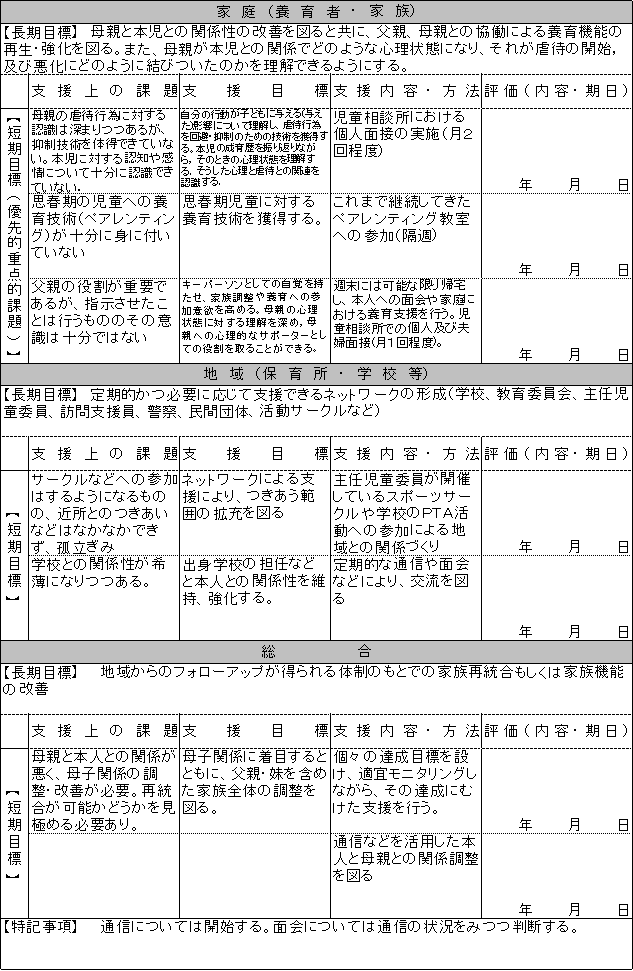ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 子ども虐待対応の手引きの改正について(平成19年1月23日雇児発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知) > 子ども虐待対応の手引き > 第9章 援助(親子分離)
第9章 援助(親子分離)
| (1) |
親子分離(施設・里親)について子ども、保護者にどう説明するか
虐待を受け危機的状況にある子どもとその家族に対し、家族関係の修復に向けた援助を試みた結果、どうしても在宅での援助が困難であると判断した場合には施設入所の措置(里親委託を含む)を採ることが必要になる。その場合速やかに保護者と子どもを説得することになるが、さまざまな困難が予想される。
| [1] |
保護者への説明
初めは保護者の気持ちの流れに逆らわない対処を心がける。「親子でうまくやってほしいと思いましたが、お互いに少し距離をとったほうがよさそうですね」「しばらくこちらで本人と話を続けてみて、親御さんの気持ちをよく伝えたいと思います」「子どもさんの育てにくさが集団生活の中で少し変わるかも知れませんね」など保護者の気持ちを酌んだ言葉かけをする。
保護者が虐待の事実を認め、子どもとの関係改善を望んでいる場合は同意を得やすいが、全く虐待の事実を認めなかったり、子どもの問題行動が原因で自分は少し厳しくしただけだと正当化したり、世間体を気にして施設入所に同意しない保護者も多い。
そういう保護者は次のような言い方で抵抗する。
| ・ |
親が一番子どものことをわかっている。その親が育ててこれないのに、他人が育ててよくなるはずがない。 |
| ・ |
施設は親のない子の行くところ。親がいるのだから行く必要がない。 |
| ・ |
しつけをゆるくしたらもっと悪くなる。そうなったらどうしてくれる。 |
| ・ |
職員が一生子どもの面倒をみてくれるのか。 |
| ・ |
施設に入れるのなら親子の縁を切る。職員の子どもにすればいい。 |
| ・ |
家族は一人でも欠けたら家族ではない。子どもがいないと働く気にならない。金が入ってこなかったらどう責任とってくれるのか。 |
| ・ |
親戚が反対したら説明できない。親が責められる。 |
| ・ |
近所で「子どもはどうしたのか」と聞かれたら困る。 |
| ・ |
他のきょうだいが学校で事情をきかれたら、返事に困る。 |
このような言い方に対しては、「親御さんは一番子どもさんのことを知っておられます。ただ、子どもさんの方はもっと自分の気持ちを分かってほしいようですよ」「そうです。家族は揃って生活するものですね。早くそうなってほしいと子どもさんも望んでいます。そのために何を努力したらいいのかを考えませんか」といったように、まず保護者の言い分を肯定して、それ以上突っ込みようがない形にする対処が有効と思われる。
上記のようなやりとりをしながら同意を取り付けていくが、留意しなければならないことは、保護者が虐待を認めてはいても、「自分が虐待するのは子どもの問題行動が原因である」と自分の行動を正当化しているような場合である。この場合、保護者の主張にそって、表面的に現れている子どもの問題行動を治療するために施設入所が必要であると説明すると同意を得やすい。しかし、この方法では保護者の子どもに対する不適切な養育は不問に付され、保護者は自らの虐待行為を振り返ることもないため、行動が改善される見通しは乏しい。また、子どもも「自分が悪い子だから施設に入れられる」という思いになり、虐待で受けた心身の傷の上に更に傷を負うことになる。これは施設入所後の子どもの情緒や行動にも大きく影響する。そのため、入所はできたものの保護者への治療的関わりができず、問題が持ち越されたままになってしまうこともある。
虐待事例については保護者の不適切な養育が問題なのであり、子どもの問題行動の多くはその結果として現れたものである。したがって、施設入所についての説明をする場合は、保護者が子どもに行ってきた虐待の事実をあいまいにせず、保護者自身の問題として認識させることが必要である。
その上で、
| ・ |
今は子どもが保護者と一緒にいることを苦痛に感じており、安心できる生活を保障することが必要なこと |
| ・ |
安全で伸びやかに生きることは子どもにとっては権利であること |
| ・ |
今のままであれば健全な成長が望めず、もっと性格的な歪みが大きくなること |
| ・ |
ずっと家に帰れないわけではなく、家庭で親子がうまく生活していくためには家族がどのような努力をすればよいのか考え、家庭復帰に向けた具体的な計画を一緒に立てることが必要なこと |
を説明し、同意を得るべく努力する。
施設入所の同意が得られたら書面で確認し、施設での生活と援助(治療)の目的・方針、入所の期間(治療の見通し)、援助方法(親子関係の持ち方、面会、外泊等)、苦情解決の仕組みの概要を説明する。これについては、虐待を行っている保護者のみならず配偶者や同居の親族等の承認を得ることも重要である。
保護者にどのような説明をしても、何を言っても引き下がらず同意をしない場合は、「保護者とわれわれは意見が異なり、折合いがつかないため家庭裁判所の判断を仰ぐことにしたい」と提示するのがよい。保護者はどこかで自分のやったことのまずさを感じているため、裁判所までは行きたくないと思い、消極的ではあるが「施設入所に反対はしない」という態度に軟化することが多い。
それでも引き下がらず、「裁判所に出てもかまわない」という態度であれば、児童相談所としては迷うことなく児童福祉法第28条の申立てをする。
なお、施設入所については保護者の反対を押し切っての措置はできないという意味であり、積極的な同意を条件とはしていない。
|
| [2] |
子どもへの説明
虐待を受けた子どもは、人間に対する不信感を抱いており、なかなか本当のことを言おうとしない。そして次のような特性を持っていることが多い。
| ・ |
虐待の事実を家族内のこととして秘密を守ろうとする |
| ・ |
親はよい存在であってほしいという思いから、親をかばおうとする |
| ・ |
親は悪くない、悪いのは自分だから暴力を振るわれるのだという理解をして、虐待されることを納得しようとする |
| ・ |
こんな悪い子どもは親から見捨てられるのではないか、という不安を持っているためにより親にしがみつく |
したがって虐待が子どもにとって耐えがたい状況になって、明らかに親子を分離し施設に入所させなければならない場合でも、保護者の前では萎縮し、保護者の意向にそった返事しかできないこともある。施設入所についての子どもの意向は、安心した状況のなかで子どもの本心を酌み取るための配慮をした上で確認したい。
一時保護所などで子どもが保護者と分離できている場合、「家には帰りたくない」とはっきり表明することがある。このような場合、子どもは施設入所に納得していると判断できるが、「どういう気持ちで施設にいくの?」と質問すると、「僕が悪いことをするから、イライラしたお父さんが酒を飲んで家の中がもめる。僕がいないほうが家が平和だから施設に行く」と答えた事例もある。これは明らかに「虐待されるのは自分が悪いから」という低い自己評価に陥っており、このような思い込みは修正する必要がある。
| ・ |
保護者がイライラするのは子どもの性格や行動だけが原因ではない。保護者もまた助けを必要としている人である |
| ・ |
すべての子どもは「安全に」「自信をもって」「自由に生きる」権利を持っており、大人はそれを認めなければならない |
| ・ |
今の家族の中では子どもの体や心が傷つき、安心して暮らすことができない |
ことを説明した上で、心身の安全と健やかな成長のために、家族から離れて施設で生活する必要があることを伝える。
また、親が「行け」というなら施設に入所するが、自分から親を切るようなことはしたくないと施設入所に躊躇する子どもに対しては、「児童相談所が様々な状況から判断して施設入所が適当と決定した」と言い渡してやることが、子どもの精神的負担を軽減する。
子どもが施設入所に同意したら、パンフレットやアルバム等で施設の生活について説明するとともに、その目的や入所期間の見通し、施設における苦情解決の仕組みや社会福祉協議会に設置される運営適正化委員会への苦情の申し出の方法、入所中の親子関係の持ち方(治療方法、面会、外泊等)などを分かりやすく説明し、子どもの不安をできるだけ除去しておく。また、「子どもの権利ノ−ト」のようなものに基づいて、施設の中で保障される子どもの権利について、年齢に応じた説明をするのもよい方法である。 |
|
| (2) |
家庭環境調整、保護者への援助はどのように行うか
子どもの状態、保護者の状況をよく観察、把握し、長期的に見て、親子関係の改善ができるように援助するという姿勢で臨む。
また、児童福祉法第28条の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から2年を超えてはならないこととされている。深刻な虐待事例の中には、子どもが再び保護者と生活をともにすることが、子どもの福祉にとって必ずしも望ましいとは考えられない事例もある。このような場合まで親子の再統合を促進するものではないことはいうまでもないが、児童相談所においては、この2年間に親子の再統合その他の子どもが良好な家庭的環境で生活することができるようにすることに向けて、保護者に対する援助や施設や里親に措置(委託)された子どもの訪問面接等に努めるとともに、親子の再統合が可能であるかを検討するものとする。
| [1] |
分離直後の保護者への援助
同意による施設入所であっても、入所直後の保護者の喪失感は大きいことを理解する必要がある。これは、虐待している、いないにかかわらず、どちらの保護者にも起こりうることである。
保護者の思いとしては、次のようなことがよく言われる。
| ・ |
今頃、子どもは何をしているだろうか |
| ・ |
何か欲しがっているもの(足りないもの)はないか |
| ・ |
やはり、預けたのは間違っていたかもしれない |
これらの思いに対処する方法としては、分離の前から「離れた後には、誰にでもこんな気持ちが出てくるもの。その時は、また、話してみてほしい」と説明しておくことも考えられる。保護者が、経験を話しながら、気持ちを整理できるようにするのである。保護者の気持ちの揺れを収めるためにも、入所後は、一定期間子どもとの交流を控えてもらう。子どもにとっても、施設になじむ期間がある程度必要なことも説明する。
一般的には2〜3週間、手紙、電話、面会を控え、この間に積極的に保護者と関わりを持ち、気持ちを受容する。保護者が入所に同意したことは、親子関係をこれまでと違う形で作りなおすために必要だったことを再度説明し、その決断を評価することが必要である。保護者自身が、自らの決断を受け入れ、今後の目標を持てるように動機づけする。
|
| [2] |
保護者と親族等との調整
保護者と親族との葛藤状況が長く続いている場合が多い。親族から、子どもの施設入所に反対されることもある。このようなストレスを、保護者から率直に話せるような相談関係を持ち、共に対応について考えるようにする。
必要であれば、親族と会って、施設利用についての正確な情報を伝え、その目的のために理解と協力を求める。また、子どもの目前で親族間の葛藤をあらわにすると、子どもの気持ちに負担をかけるので、このようなことがないよう配慮を依頼する。
|
| [3] |
転校について
きょうだいの内の一人の子どもだけ分離するような場合で、学校等に所属していれば、転校理由についての配慮が必要である。分離する子どものプライバシーを十分守れるよう、保護者・学校ともよく協議しておく。
|
| [4] |
援助者の体制
援助者自身も、入所当初は保護者の気持ちの揺れがあることを充分理解した上で、急な連絡にも対応できるよう気持ちと体制を整える。
保護者が大変不安定で、不眠・食欲不振等があれば、医療につなげることを検討する。経済的問題が大きければ、生活保護の相談も必要である。いずれの場合も、それぞれの機関の状況を事前によく把握し、初回は保護者に付き添うなどして、できるだけ不安を軽減するように努める。
|
| [5] |
面会・帰省について
面会は、子どもと保護者の安定性を見計らい、それぞれの意向を十分聞いた上で実施する。どちらかがその気持ちになれない時は、児童福祉司が間に入り、双方に理解できる形で説明し、期間をおくようにする。
保護者には「関係の修復には時間を要する。焦らず、じっくり取り組もう」と説明する。子どもの中には、電話や面会は難しくとも「手紙を出す」という気になることもある。施設職員にも、タイミングをみて手紙の内容を一緒に考えてもらう等、援助をしてもらう。児童福祉司が手紙を受け取り、保護者に手渡して気持ちを聞き、返事をもらえるよう働きかけるといったことも想定される。
入所後の初めての面会には慎重な配慮が必要である。特に、保護者が不用意に引取りを口にしそうな場合には注意がいる。子ども・保護者・施設の三者を全体として見極め、今後の方針を確認するため、児童福祉司も同席する。
面会の具体的な進行としては、次のような流れが考えられる。
| ・ |
施設職員と児童福祉司が保護者に会い、入所後の子どもの様子を報告する |
| ・ |
子どものよい面を最初に伝える。「自分の気持ちが少しずつ出せるようになっている」というように、評価できる形で話す |
| ・ |
子どもの今後の課題を話す |
| ・ |
保護者の感想や意見を聞く |
| ・ |
施設職員、児童福祉司が同席し、保護者と子どもに面会してもらう |
入所後の子どもは、それまでの抑圧していた気持ちを、色々な形で表現するものであり、それはごく自然な形であると、保護者に説明しておくことが大切である。
保護者の中には、「施設で子どもが前より悪くなった」と受け取ることもあるが、事前に情報を提供し、これをなるべく防ぐようにする。そのためには、子どもの行動を、評価して報告することが必要である。保護者自身の努力を評価したり、体調を気遣ったりすることも同様に大切である。
面会は、最初からあまり頻繁に設定するのではなく、状況を見て、頻度を決めていく。子どもと保護者が、共に安心感を持って面会できるよう心がけ、面会の様子が落ち着くまで、職員が同席したり様子を見たりして気を配る。
面会後、子どもと保護者双方に感想を尋ね、今後の課題について検討する。例えば、保護者が子どもに「もっとがんばれ、まだよくなっていない」というようなストレスをかける場合は、まず、現在の家庭の家族関係について考えるよう働きかけることも想定できる。子どもと保護者相互のイメージアップにつながるような援助の姿勢を持つことが必要である。
面会状況が安定し、親子関係の改善が見られるようになってくれば、施設からの外出・休日の家庭への帰省も段階を踏んで検討する。特に、子どもが保護者の意向を先に読み取って、それを自分の気持ちより優先してしまわないように気を付ける。
学年終了時期等、節目には、保護者が引取りを希望してくることが予測されるので、十分施設と情報交換し、対応に備えておく。
|
| [6] |
保護者のカウンセリング等について
子どもの施設入所後に、保護者自身がカウンセリングを希望してくることは、まだ事例として少ないが、基本的には大変重要なことである。
施設入所の大きな目標は、子どもの安全を確保し、家族の病理的現象としての虐待を治療し、保護者が虐待の事実と真摯に向き合い、再び子どもとともに生活できるようになる、すなわち親子の再統合をできる限り図ることにある。そのために一定期間親子が離れて生活し、家庭環境や親子関係を適切な状況に変化させる必要がある。
しかしながら、深刻な虐待事例の中には、子どもが再び保護者と生活をともにすることが、子どもの福祉にとって必ずしも望ましいとは考えられない事例もある。このような場合まで親子の再統合を促進するものではないことは、第1章1(2)で述べたとおりである。
カウンセリング等については、施設職員による働きかけとともに、児童相談所としても、保護者の意思を確かめながら、児童相談所の医師や心理職員等と相談し対応する必要がある。場合によっては、地域の資源(保護者への治療を行っている医療機関、保健所やアルコール関係のグループ等)につなぐことも考えられるが、拒否や中断に対しては、虐待を行った保護者には児童相談所の指導を受ける義務のあること、保護者が指導を受けないときには知事は指導を受けるよう勧告を行うことが出来ること、さらには、入所措置等の解除に当たっては、児童福祉法第27条第1項第2号の指導を行った児童福祉司等の意見が聴取されることについても説明しなければならない。
なお、保護者指導や家族再統合に関するプログラムについては、虐待に至る背景は複雑であることから、汎用性の高いプログラムの開発には更なる取組が必要であるが、現時点において行われている様々な取組は、『子ども・家族への支援・治療をするために』(児童虐待防止対策支援・治療研究会編)にまとめているので、参考とされたい。
また、保護者がカウンセリングの必要性を認識していないために、保護者自身何のために援助を受けているか分からず、援助が中断する場合も少なくない。このような場合は、ペアレント・トレーニングをカウンセリングに先行させることも効果的であろう。ペアレント・トレーニングは、保護者として子どもにどう接するかを具体的に教育するものであり、保護者の理解を得やすいからである。ペアレント・トレーニングの実践例については、『子ども・家族への支援・治療をするために』でも紹介されているので、参考とされたい。 |
|
| (3) |
施設入所中の子どもへの心理的援助はどのように行うか
虐待のために家族から分離されて施設に入所することは、子どもにとって非常に重大な体験である。こうした体験は、子どもに「二重のトラウマ(心的外傷)」を生じさせる可能性がある(西澤哲「虐待を受けた子どもへの初期対応」1995)。一つは、保護者からの虐待によるトラウマであり、もう一つは保護者を失ったことによるトラウマである。何らかの手当を施されない限り、こうしたトラウマが自然に癒えていくことはまずないと言っていいだろう。したがって、子どもの施設入所後にも、彼らがこれらのトラウマから回復できるよう、児童相談所はできうるかぎりの援助を行わなければならない。
本項では、施設に入所している子どもに対して児童相談所が行いうる援助を、施設職員へのコンサルテーションと子どもに対する直接的な心理療法の二つに分けて述べる。
| [1] |
施設職員へのコンサルテーション
虐待や家族からの分離によるトラウマは、子どものさまざまな「問題行動」として現れる傾向がある。施設の職員は日常的にこれらの行動に振り回されてしまう傾向があり、そうした事態で子どもが「問題児」のレッテルを貼られてしまうことも珍しくない。
子どものトラウマ性の反応としてまず考えられるのは、PTSD(Posttraumatic Stress-Disorder:心的外傷後ストレス障害)である。Benedek(1985)は、DSM−IIIのPTSDの症状は基本的に成人を対象とはしているものの、子どもにも適用可能であるとしている。しかし、虐待という刺激の反復的、慢性的な特質を考えた場合、子どもが示すトラウマ反応をPTSDにのみ限って考えるのは適切ではないといえる。Terr(1991)が指摘するように、単回性のトラウマ刺激に対するものと、反復継続的なトラウマ刺激に対する子どもの反応には、かなりの違いが見られるようである。またBriere(1992)も、虐待を受けた子どものトラウマ反応は、認知、情緒、感情、行動、対人関係などさまざまな領域において観察されるとしている。
こうした従来の諸研究と、児童養護施設における西澤らの観察(「養護施設における子どもの入所以前の経験と施設での生活状況に関する調査」1996)に基づいて、虐待というトラウマによって生じうると考えられる特徴を列記すると以下のようになる。
| ○ |
入眠困難などの睡眠障害(PTSDの過覚醒症状) |
| ○ |
注意集中困難、多動性(PTSDの過覚醒症状) |
| ○ |
悪夢、夜驚(PTSDの侵入性症状) |
| ○ |
無感情、無感覚(PTSDの回避・麻痺症状) |
| ○ |
無気力、抑うつ(慢性化した回避・麻痺症状) |
| ○ |
年少の子どもや小動物に対する過度の攻撃行動(行動上の再現性) |
| ○ |
かんしゃく・パニックや、それにともなう破壊的行動(感情調整障害) |
| ○ |
年長者や力の強いものに対する従順さ(力に支配された対人関係) |
| ○ |
年少時に見られる無差別的愛着傾向(愛着形成の障害) |
| ○ |
思春期以降に見られる対人関係の希薄さ(愛着形成の障害) |
| ○ |
他者、特に自分にとって重要な意味のある年長者に対する挑発的行動と、それにともなう虐待的な対人関係(トラウマとなった対人関係の反復的再現) |
| ○ |
万引き、暴力的行為、喫煙などの反社会的行為(トラウマ性の情緒の行動化) |
| ○ |
セルフカットなどの自傷行為(感情調整障害、あるいは乖離症状への対処行為) |
| ○ |
拒食や過食などの摂食障害、食べ物への固執(口唇期性障害) |
| ○ |
アルコールや薬物への依存(PTSDの回避・麻痺症状) |
児童相談所としては、以上のような症状もしくは行動を、保護者からの虐待や家族の喪失のトラウマに起因するものであると施設の職員が理解できるようなコンサルテーションを提供することが必要となる。なお、子どもの問題行動への対応については、第9章2(3)で述べる。
|
| [2] |
子どもの心理療法
| ア. |
虐待によるトラウマへの接近
保護者からの虐待という体験は、そのままにしておけば子どもの性格や人格の発達に非常に深刻な影響を与えうるトラウマを生じる可能性がある。こうしたトラウマの多くは、子どもを例えば児童養護施設などの虐待的ではない環境に移しただけで癒えることはない。子どもには、虐待体験を直接扱っていくことでトラウマを軽減するための援助が必要となる。こうした心理療法的な援助のシステムが十分確立されているとは言えない現状において、児童相談所は、施設入所後もできる限り子どもに対する個別的な心理療法や集団療法などの援助を行っていく必要がある。
施設入所後の子どもへの心理的な援助には、児童相談所への子どもの通所と児童相談所職員の施設への訪問という二つの形が考えられる。子どもが思春期年齢に達しており成人型のカウンセリングが可能である場合には、セラピストが定期的に施設に行って個人的なカウンセリングを行うことも可能である。しかし、子どもが低年齢の場合には、プレイセラピーを実施する必要が生じるため、児童相談所への通所が望ましい。ただし、こうした子どもが一人で児童相談所にやってくることは不可能、あるいは望ましくないことが多く、その際には施設職員の付添いが必要となる。施設の職員が子どもの通所に付き添うことには、子どもとの個人的な特別の時間を持つことができるという利点や、来所の機会を利用して施設職員にコンサルテーションを提供できるといった利点があるが、一方で、その時間帯の施設での職員数が1名減になるといったマイナス面もある。どのような形で子どもの心理療法を実施するかは、こうした点も考慮に入れて決定しなければならない。なお、虐待体験によるトラウマを扱っていくための心理療法については、第9章2(4)で述べる。 |
| イ. |
家族の喪失への接近
虐待を受けた子どもへの心理的な援助で、今一つ重要なテーマとなりうるのは、家族との関係である。虐待を受けた子どもは、自己中心的な認知傾向(self-centeredness)と保護者からのメッセージとが相まって、「自分が悪い子どもだから虐待されたんだ」という罪悪感や「それほど悪い子どもだから施設に入れられたんだ」といった見捨てられ感を持っていることが多い。したがって、子どもの心理療法において、こうした罪悪感や見捨てられ感を解決する必要がある。
罪悪感を修正するためには、第9章2(4)で述べるようなトラウマへの接近を通して保護者による虐待行為などを吟味していくことで、最終的には「保護者が間違ったことをしたんだ」という認知を持てるようになることが重要である。その際に、保護者の「意図」と「行為」を分けて、行為を問題にすることが大切であり、決して保護者を「悪者」にしないよう留意しなければならない。
こうした罪悪感への接近に関連して、見捨てられ感を扱っていくことも重要である。その際、援助者は「保護者はあなたを見捨てたりはしないよ」「また家族のところに帰れるよ」などといった、場合によっては非現実的なものとなりうる保証を与えないよう注意する必要がある。むしろ、「見捨てられたんだ」という子どもの思いや、家族を失うことへの喪失感にしっかり寄り添うことが援助者には求められる。また、保護者がどのように変われば家族の元に戻れるかといったテーマを大切に扱うことも重要である。そのためには、家族のソーシャルワークや心理療法の担当者と緊密に連携することが大切である。 |
|
|
| (4) |
施設への技術的支援、家庭環境調整に向けた連携をどう図るか
| [1] |
施設職員への支援
施設入所してきた子どもにとって、最も必要とされる「安心感」を提供してもらえるよう、また、保護者にも受容的かつ的確に対応してもらえるよう、施設職員を支援していくのが児童相談所の役割である。子どもと保護者のこれからの行動をある程度予測して、参考になりそうな文献を紹介し、対応を考えるといった、共に学び対処する姿勢で行う。
|
| [2] |
子どもとの関わり
子どもに関わる職員には、子どもの生育歴をできる限り詳しく知ってもらう。虐待状況に適応するために子どもがどう生き延びてきたのか、施設入所後にその後遺症がどのように出ると予測されるかを併せて説明する。
担当職員に対しては、子どもは攻撃、挑発、過度の要求をぶつけることが多くなる。子どもの行動が激しいほど、職員間に緊張状態が生じ、相互に批判的になりやすいことを当初からよく説明し、対処の方法を共に考えておく必要がある。担当職員が一人で子どもを抱え込まぬよう、また、「担当が子どもを甘やかしすぎるからああなる」と周囲が批判して追い詰めることのないよう、周囲が担当職員を援助できるように働きかける。子どもの日常の様子をそれぞれの職員がよく観察し、情報交換を密にして、行動の流れやパターンを把握したり、何気なく話していることの意味を酌み取ったりしながら、職員全員がよりよく子どもを理解できるような雰囲気を作ってもらう。
予測し得ないことがいろいろ起こることになるので、いつでも、施設から児童福祉司に率直に相談できるような関係を築いておくことが基本である。児童福祉司にとっても施設からの情報は大変貴重なものであり、多くの示唆が得られる機会ととらえて、経験を蓄積するようにしておく。また、心理療法やカウンセリングなどの心理治療が必要な子どもに対して、心理職員は、施設と連携を図り、施設への訪問指導や子どもの通所指導などを検討し、積極的に心理治療を行うことが求められている。
|
| [3] |
保護者への関わり
保護者に一環した対応をするため、基本的には保護者担当の職員を特定してもらう。しかし、保護者によっては、担当が不在でも早急に対応を求めてきたりするので、臨機応変な対応体制を整えておくことが必要である。
施設職員と保護者の関係がうまくつけられるよう、特に入所当初は配慮が必要となる。「保護者自身も困難な生い立ちを抱えている等から、周囲の人に対しては、不信感や攻撃性をあらわにしがちである」というような説明を十分にしておき、保護者の言動に振り回されたり、職員との間に葛藤を引き起こしたりすることを防いでおく。基本的には、保護者の気持ちを受容的に聴いたり、体調を気遣ったり、努力を評価したりして、子どもよりもむしろ保護者自身のことを話題にし、気にかけていくと、より話がしやすくなることも心得てもらう。
子どもの状態については、保護者に不安を与えないよう配慮して報告してもらう。不安な気持ちから、「前よりも施設で子どもが悪くなった」と批判的になることはよく見られる。「子どもなりに気持ちが出せるようになっている」というような評価を基本にしながら報告し、保護者の反応も見ていく。子どもと職員の関係について保護者に、「子どもは何でも話してくれる」などと言ってしまうと、保護者は子どもとの距離を感じたり、施設職員に競争心を持ったりしがちなので注意を要する。
子どもが、恐怖心から保護者との面会や帰省を拒否している場合は、子どもの意向をそのまま保護者に伝えるかどうかは慎重に考慮しなければならない。施設職員、児童福祉司が相談した上で「子どもがまだ十分に気持ちを出せていない。不安定な状態が続いている」と状況説明し、時期が適切でないことを理解してもらう方法も考えられる。
初めての面会、外出、帰省は、大切な節目であり、保護者対応について十分協議できるようにしておく。
いずれにせよ、保護者との関係づけは決して容易ではないことを、全ての職員に理解してもらい、施設、児童相談所の両者で、焦らず、たゆまず取り組めるように働きかけていく。 |
|
| (5) |
措置解除の適否判断と解除時の子ども、保護者等への援助はどうあるべきか
援助指針や自立支援計画に沿って、親子関係の修復・改善がなされ、他に養育上の問題がなければ、子どもを家庭に復帰させることになる。
単に保護者と子の両者が家庭復帰を希望しているからとの理由だけで引き取らせると、虐待行為が再発したり、新たな問題を引き起こすことにもなるので、施設と児童相談所が保護者に対する指導措置の効果、子どもの心身の状況や心情等を十分把握した上で決定することが重要である。
| [1] |
措置解除の条件
措置解除を行うにはおおむね以下のような条件を満たしていなければならない。
| ア. |
家族システムが施設入所措置前(虐待が行われていたころ)から変化し、虐待が再発する可能性が少ないと判断されること。 |
| イ. |
保護者が自分の行為を反省し、「もうしない」と断言しており、これに合理的根拠があると判断されること。 |
| ウ. |
援助機関と保護者の間に信頼関係が樹立されており、今後も継続的な援助が可能と判断されること。 |
| エ. |
援助や再発の早期発見のためのネットワーク(セーフティーネットワーク)が地域に存在すること。 |
|
| [2] |
措置解除に当たっての確認事項
[1]の条件を満たしているか判断するため、施設と児童相談所が次のような点を十分確認することが重要である。
| ア. |
子どもについて確認すべき事項
| ・ |
家庭復帰することを望んでいるか(子どもは家庭復帰を望んでいる一方で、復帰に対する不安を抱いている場合が多い。したがって確認する際には、そのような子どもの心理状態に対して配慮しつつ行うことが重要である。) |
| ・ |
家庭復帰するについて、子どもの意向や条件提示はどのようなものか |
| ・ |
虐待を行った保護者に対する思いはどのようなものか |
| ・ |
一時帰宅(週末帰宅、短期帰省等)等によって、虐待を行っている保護者に対する態度や気持ちがどのように変化したか |
| ・ |
親子関係改善のための援助や心理治療によって、子ども自身の生活態度や性格行動および保護者に対する態度や気持ちが、どのように変化したか |
| ・ |
虐待問題が再発したり、他の問題が発生した時の相談場所や相談者、避難場所の確認をしているか。 |
| ・ |
虐待問題が再発したり、他の問題が発生した時の保護者への対処法が分かっているか。 |
| ・ |
虐待問題が再発したり、他の問題が発生した場合、再入所の可能性もあることを分かっているか。 |
| ・ |
家庭復帰後の親子関係改善や子どもの性格行動問題改善を目的とした治療、あるいは経過観察のための通所や家庭訪問が、どの機関の誰がどのようにするのかを理解しているか。 |
|
| イ. |
虐待を行っていた保護者について確認すべき事項
| ・ |
子どもを家庭に引き取りたいと思っているか |
| ・ |
虐待行為が子どもに与えた心的外傷が理解できているか。また、子どもに対する気持ちはどのようなものか |
| ・ |
虐待の原因について理解できているか |
| ・ |
虐待の原因を解消するように改善努力がなされてきたか。また、解消されているのかどうか |
| ・ |
子どもの心理状態、性格行動や精神的・身体的発達状況が理解できているか。また、家庭復帰するについて、子どもの意向や条件提示をどのように理解しているか |
| ・ |
保護者としての自覚や育児技術の習熟度はどのようなものか |
| ・ |
家族関係、きょうだい関係の状況はどのようなものか |
| ・ |
地域社会、近隣との関係はどのようなものか |
| ・ |
保育所、幼稚園・小学校・中学校等の学校との関係はどのようなものか |
| ・ |
虐待の再発防止のための援助機関(児童相談所、福祉事務所(家庭児童相談室)、市町村保健センタ−、保健所、民間虐待防止団体等)との関係はどのようなものか |
| ・ |
一時帰宅(週末帰宅、短期帰省等)等によって、子どもに対する態度や気持ちがどのように変化したか |
| ・ |
親子関係改善のための援助や心理療法によって、保護者自身の生活態度や性格および子どもに対する態度や気持ちがどのように変化したか |
| ・ |
虐待問題が再発したり、他の問題が発生した時の相談場所や相談者が分かっているか。 |
| ・ |
虐待問題が再発したり、他の問題が発生した場合、再入所の可能性もあることを分かっているか。また、了解できるかどうか。 |
| ・ |
家庭復帰後の親子関係改善や子どもの性格行動問題改善を目的とした治療、あるいは経過観察のための通所や家庭訪問が、どの機関の誰がどのようにするのかを理解しているか。 |
以上のような事項について綿密に協議、評価した結果、親子関係の改善が確認でき、家庭復帰を進める方向に結論が出た場合、次に地域で当該家族を援助する関係機関との調整に入る。 |
| ウ. |
地域関係機関等との調整
| (ア) |
社会資源を利用することは、保護者の精神的・物理的な負担の軽減につながることから、社会資源の有無を確認する。例えば、家庭の養育機能の補完として保育所や放課後児童健全育成事業(学童保育)等を利用することは在宅生活を維持する上で重要であり、同時に虐待の再発を早期発見することにもつながる。 |
| (イ) |
在宅生活を維持する上で、親戚、近隣知人等の家族周辺の援助は重要な意味を有することから、こうした援助の可能性を確認する。 |
| (ウ) |
虐待再発防止のため、福祉事務所(家庭児童相談室)、市町村保健センタ−、保健所、病院、保育所、幼稚園・小学校・中学校等の学校、警察、民生・児童委員(主任児童委員)等、当該家族が生活している地域の関係機関、関係者との相互理解・協力によって虐待を受けた子どもとその家族を援助していくことが非常に重要である。
当該家族のプライバシ−を侵害しないように配慮しながら、関係機関および関係者に対し家庭復帰について説明し、受入れの準備を整えてもらう。
もし、家庭復帰について関係機関から問題点の指摘があった場合は、十分時間をかけて検討・協議し、結論を導き出すようにしなければならない。
また、援助を行うにあたって、関係機関の果たすべき役割や児童相談所の役割について、また、援助内容の適否を点検するため事例検討会を定期的に開催することなどについて確認をしておく。 |
| (エ) |
家族の状況観察と家族援助を実施する場合、緊急時に即応できる相談援助体制(ネットワーク)を整備する必要性がある。例えば、子どもの欠席が続く場合、保育所、学校等に家庭訪問を依頼して家族の状況観察を実施する。そのようなことを想定して家庭引取り前に関係機関との事例検討会等を開催して役割分担を決定しておく。 |
| (オ) |
児童相談所の立地的・物理的限界を考慮し、交通手段等の事情により定期的な家庭訪問等が困難な場合、福祉事務所の社会福祉主事、児童委員、児童家庭支援センター等に指導依頼する。その際、保護者に社会福祉主事、児童委員等が関わることを説明して同意を得るとともに、保護者と子どもに紹介する。
この場合、これらの指導と併用して児童福祉司指導とするなど、児童相談所としては、指導を他機関に依頼した後も引続き進捗状況を把握するとともに必要な指導を行う。 |
| (カ) |
施設を退所した子どもに対し、相談や定期的な訪問等を行い子どもを見守るとともに、家族等に対しても精神的な支援等を行うためには、要保護児童対策地域協議会を活用することも有効と考えられる。このため、協議会との連携を確保しつつ、施設を退所した子どもが新しい生活環境の下で安定した生活を継続できるように必要な調整を行う。 |
|
|
| [3] |
措置解除に当たっての留意事項
| ア. |
措置停止を経てから、措置解除を行うこと
児童相談所との十分な連携のもとに、措置停止の期間をとったのち、措置解除を行うことが必要である。一般的には、家庭復帰直後の数カ月は特に子ども虐待が再発するハイリスクの期間とされており、保護者の強い希望で家庭に返した数週間後に、子どもが保護者の暴行によって死亡するという事例も報告されている。したがって、退所直後は児童相談所と綿密な連携をとりながら、頻繁に家庭訪問等で観察を続けるべきである。 |
| イ. |
子どもにも非常時には緊急通報で連絡をとらせるよう話をすること
学童の場合には、施設へ電話連絡がとれる能力をもっている。退所に際して子どもに万一の場合には、SOSの電話通報を施設にしてくるように話をしておくとよい。こうした方策で実際に、子どもを救出した例が次の事例である。
[事例]
| |
家庭復帰して4カ月経過したある夜、父親が酒を飲んで暴れており、頭を殴られ怖くて家を飛び出した。母親は仕事からまだ戻ってきていないという訴えの電話をA男(小5)から、施設に通報してくる。A男の家は、自動車で施設から20分程度のところにある。家の近くの公衆電話から電話をしたということで、そこで待合せをすることにした。直ちに出向きA男に会い事情を聞く。こうした状況は今回で2回目だという。家に出向くと、父親は酔いも覚めていたようで、バツのわるい顔しておとなしく頭を下げて恐縮した態度をとる。父親に注意をしているところに母親が戻ってくる。母親からも父親の状況を聞き、こうした状況が続くようならば再措置になる旨を伝え、A男が今日のところは家でがんばるということで帰ることにする。もし同じようなことがあったらまた連絡してくるようにA男に伝えておく。その後、半月足らずで同じことが発生し、A男から連絡があり、「家にいたくない」と言ってくる。行ってみると、頬に青あざをつくったA男が泣きながら事情を説明した。そのままA男を施設で保護し、両親にその旨、通告する。 |
|
こうした救出例もあることから、子どもにも退所前によく話をすることが必要である。 |
|
| [4] |
措置解除の適否判断に際しての留意事項
| ア. |
保護者の発言の真相を調査確認する
保護者によっては、子どもを早く引き取りたいために、「仕事を見つけました」「病院に受診しました」等虚偽の発言をする場合がある。ところが、家庭周辺の調査をすると事実と反する場合もあるので、必ず事実確認の調査を実施する。 |
| イ. |
保護者の子どもに対する責任ある行動は引き取る際の重要な判断材料となる
子どもに「面会に来るよ」「外泊の迎えに来るわね」等と約束しながら、実際には来所しない保護者もいる。このような場合、子どもは保護者に対して絶望感と裏切られ感を持ち、心の傷を深める危険性がある。保護者の責任ある態度と子どもの保護者に対する感情等を十分見極める。 |
| ウ. |
面会を通じて親子関係の変化を確認する
通所、家庭訪問等により保護者に一定の改善が見られた場合は、親子関係再構築の作業として面会を実施することとなるが、面会前、面会中、面会後の保護者と子どもの言動等を行動観察して、子どもの心身の安全が確保されると判断できれば、外泊を実施する。 |
| エ. |
外泊時の状況は家庭引取りの最終的な判断材料となる
保護者は「子どもも変わりました」、子どもは「お父さん、お母さん、優しくなった」等と、双方とも面会の一瞬を捉えて問題解決されたと錯覚することが多い。外泊は入所措置後の親子の変化を相互に体験する機会となる。親子関係修復のため、面会、外泊等の回数および期間を変える等、個別の事例に応じて課題内容を検討して実施する。 |
|
| [5] |
子どもに対する留意事項
| ア. |
子どもの意見を聴き、無理のない家庭引取りを考える
子どもは「お父さん、変わるなんて嘘だ」「お母さん、優し過ぎて変な感じ」等と家庭復帰を拒む場合もある。家庭支援専門相談員や児童指導員等がチームを組んで、子どもの意見を聴き、不安を取り除く。また、子どもに無理のない緩やかな家庭引取りプログラムを検討する。 |
| イ. |
子どもにも考えさせる
保護者の不適切な関わりの結果、子どもも自分本位な態度をとったり、ささいな刺激に感情的に反応しやすくなっており、子どもの保護者に対する感情等に配慮しながら自分のことを自分で考える体験を積ませる必要性がある。 |
| ウ. |
子どもは、家庭引取りと同時に児童相談所や施設との関わりがなくなるのではないかと不安を募らせるから、家庭引取り後も、通所、家庭訪問等により保護者や子どもの相談にのっていく旨伝え、安心感を持たせる。 |
| エ. |
子どもに身近な相談相手と緊急避難先を知らせる
家庭引取りは虐待の再発の危険性が解消されたとの判断から実施するが、家庭引取り後、新たな要因により再発する可能性もある。子どもには虐待が再発した場合、親戚、近隣知人あるいは学校、福祉事務所、民生・児童委員(主任児童委員)等の緊急避難先を知らせる。幼児、小学校低学年の子どもの場合、自ら連絡したり、緊急避難することは難しく、緊急避難対策を事前に関係者間で検討しておく。 |
|
| [6] |
保護者に対する留意事項
| ア. |
保護者の家庭引取りの判断材料は問題意識と問題解決能力の有無である
保護者自らが虐待に至る要因に対して問題解決する意識を持っていると、第三者の援助を受け入れる可能性は高くなり、問題解決に向けて進展する。問題意識を持たせるため、保護者との関わりでは虐待に至るストレスの受容と、精神的・物理的な負担を軽減させることに力点を置く。 |
| イ. |
虐待は世代間連鎖の問題がある
保護者自身の被虐待歴を確認する。被虐待歴のある場合、保護者の辛さ、苦しさを共感する。また、保護者との面接中、子どもにとって肯定的な関わりと否定的な関わりを判別して、保護者の自己評価を高めるとともに否定的な関わりを排除するため、肯定的な関わりは賛成、同調して安定した親子関係を強化する。 |
| ウ. |
家族援助の際の留意事項
保護者と児童福祉司等の間で信頼関係を結べるようになると、具体的な虐待要因の問題解決を図る段階へ移行する。例えば、経済困窮、保育所利用等の場合は福祉事務所を保護者に紹介するが、保護者と他機関との信頼関係が樹立されていない場合が多い。このため、児童福祉司が保護者に付き添い、他機関を紹介する等の配慮を要する。 |
| エ. |
家庭訪問して施設入所措置前後の家庭環境の変化を調査する
子どもの施設入所により家庭内の関係に変化が生じる。家庭訪問して夫婦関係および家族関係、親戚関係、保護者の内面的な変化等を把握するとともに、必要に応じ親戚および近隣知人、学校、民生・児童委員(主任児童委員)等から事実関係を確認する。それらの状況の変化を考慮しながら面会、外泊等の具体的な家庭引取りのプログラムを作成する。 |
|
| [7] |
措置解除の手続き
措置の解除に当たっては、上記のほか、児童虐待防止法第13条に基づく保護者の指導を行っていた児童福祉司等からの意見の聴取、児童福祉法施行令第28条に基づく施設長等の意見の聴取を経て、虐待の再発など養育上の問題がないと判断されれば、子どもの家庭復帰は可能となる。
子どもが通学する予定の学校や地域の事例検討会等を児童相談所が中心となって開催・検討したのち、まず措置停止を行い、当該家族の経過観察を行った上で、最終的な解除の判断をする。また、必要に応じ、児童福祉審議会の意見を聴取する。詳細は、第7章を参照のこと。 |
|
| (6) |
保護者の強引な引き取り要求にどう対応するか
保護者が子どもを強引に引き取って家庭に連れ戻した後、子どもの生命を奪ってしまった事件も起きており、また、そこまでいたらなくても、虐待の再発という苦い経験は多くの児童相談所や施設でしている。
子どもの引取りについては、本章1(5)で述べたように、子どもや保護者について必要な事項を確認し、地域関係機関等との調整も行った上で決定されるものである。そうした手続きを無視した強引な引取要求に対しては、以下に述べる[1]ソーシャルワーク的対応、[2]法的対応により拒むことが必要である。
また、保護者への面会要求等に適切に対応する観点からも、虐待を受けた子どもを施設に入所させる場合には、児童相談所がこれまでその子どもの保護者にどのように関わってきたのか、その保護者に対応する際に留意すべき事項はなにかといった事項についても、施設にきちんと伝えておく必要がある。
| [1] |
ソーシャルワーク的対応
| ア. |
同意による入所の場合
件数的には保護者の同意を得て施設入所した虐待を受けた子どものケースは、児童福祉法第28条による施設入所の虐待を受けた子どもをはるかに上回っている。そして、保護者の同意を得て施設入所させたにもかかわらず保護者が、「いかに子どもを早く引き取るか」を考え、一方的に引取要求をする場合もある。保護者の同意を得たとしても、児童相談所の説得によってやっと入所にこぎつけた事例も多く、やむを得ないことであろう。
| (ア) |
入所直後の場合
自ら同意して施設入所させた場合でも、保護者にとって入所直後は子どもがいなくなった喪失感が非常に大きい。「今ごろ子どもは何をしているだろう」「職員はきちんとみてくれているだろうか」「同じ部屋の子どもにいじめられていないだろうか」等、次々と様々な思いが巡り、「淋しくて耐えられない」気持ちになってしまうこともある。
それが「すぐにでも引き取りたい」という短絡的な行動を引き起こしてしまう。このような保護者に対してはじっくり話を聞き、動揺している気持ちを吐露させ、どの保護者も子どもを預けた直後は同じような気持ち、淋しさを経験するものだと説明する。
また、入所については保護者自身が迷った末に、新たな親子関係を築くために決心した経過を再度評価し、今無理に子どもを連れて帰れば、入所前の状態が繰り返されるだけであることを伝える。子どもは新しい環境に慣れようとがんばっており、保護者もがんばることで子どもを支えてほしいと励まし、動揺した気持ちを収めるような面談を行う。
もし、保護者が直接施設に行ってしまった場合は、「引取りについての相談窓口は児童相談所である」と施設から保護者に説明してもらい、児童相談所に来所するよう伝えてもらう。それを納得しない場合は、施設職員に上記と同様の対応をしてもらうが、保護者は「子どもに面会だけでもさせてほしい」と引き下がらない可能性もある。その場合は、引取りの話は絶対出さないことを約束させた上で、職員が同席し、子どもと保護者の話を整理するなどの措置をとる。
いずれにしても、根気強く入所の意味付けを再確認し、その後も積極的に保護者と面接や電話で関わりを持ち、保護者の気持ちを受け止めるよう努力する。 |
| (イ) |
入所後一定期間を経ている場合
施設では虐待を受けて入所してきた子どもに対し、まず大人との信頼関係を取り結べるように受容的な関わりから始める。子どもは、これまでの保護者の対応とは異なる対応を経験するために戸惑うこともあるが、しばらくしてこの場合は安全だとわかると、いままで抑えてきた感情をストレートに表すようになる。どこまで自分を許してくれるかを試すように、攻撃、挑発、過度の要求をぶつけたり、とめどなくわがままや甘えを出してくることもある。こういった様子を保護者が面会時に見たり、外泊時に子どものやりにくさを感じたりすると、「施設に入って前よりも悪くなった。施設の職員が甘やかすからこうなる。やっぱり子どもは親が厳しくしつけるべきだ」と施設を批判し、引取を要求してくる場合がある。
このような主張に対しては、「子どもなりに自分の気持ちを出せるようになってきている」という評価をすることを基本にし、「もう少し上手に表現できるような関わりを持ちたいと思う」とこれからの課題を分かりやすく説明することも必要である。また保護者は「子どもが自分よりも施設の職員になついてしまうのではないか」という不安や焦りの気持ちから引取りを主張していることも考えられるので、子どもが親を肯定的に表現している具体例をあげながら、親は何にも替えがたい存在なのだということを伝える。 |
| (ウ) |
同意によらない入所の場合
児童福祉法第28条や同法第33条の6等家庭裁判所の決定等による入所の場合、保護者は裁判所の決定に従わざるを得ないと半ば納得し、以降児童相談所の指導に応じる場合と、逆に自分の考えや意向が全く無視されたと児童相談所に対し、家庭裁判所に申立てをしたことおよび子どもを施設入所させたことに激しい怒りをぶつけ、衝動の抑制のないまま「子どもを返せ」と怒鳴り、暴力に訴える場合もある。
後者の場合、あくまでも毅然とした態度を失ってはならず、児童相談所としては家庭裁判所の決定に基づいて入所させていること、施設入所は子どもを取り上げたわけではなく、時間をかけて親子関係を修復するためのものと考えていること、そのために保護者の協力が必要なことを説明し、それでも協力が得られない場合は子どもの福祉を守るため居所を教えられないこともあると伝える。 |
|
|
| [2] |
法的対応
| ア. |
同意を得ないで施設入所した場合の引取要求への対応
児童福祉法第28条による家庭裁判所の承認があった以上、児童福祉施設の長に与えられた監護権が保護者等の監護権に優先することになることから、こうした場合に親権者が子どもの引取りを要求してきても拒むことができる。(「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」平成9年6月20日児発第434号厚生省児童家庭局長通知) |
| イ. |
同意を得て施設入所した場合の引取要求への対応
児童福祉法第27条の措置等を採る場合で、子ども又はその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しないとき等については、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととなっている。
具体的な例としては、保護者の同意を得て施設入所措置を採った事例で、その後保護者等の意向が変化し、引き取りを強く要求している場合があり、審議会の意見として保護者による引取りが不可となれば、保護者にその旨伝えて説明することができる。
また、平成16年児童虐待防止法改正法により、虐待を受けた子どもが親権者の同意を得て施設入所している場合に、保護者が子どもの引渡しを求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待が行われること等が認められるときは、児童相談所長は、その子どもを一時保護できることとされた。また、この措置を採った場合は、児童相談所長は、速やかに、児童福祉法第28条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならないとされた。保護者に対し説得を重ねたり毅然とした対応をとってもなお子どもの保護に支障をきたすと認められる場合には、この手続きを採って児童福祉法第28条に基づく措置の承認に関する審判を家庭裁判所に申し立て、措置を承認する審判がされた後に、再度入所の措置をとる。(なお児童福祉法第27条の措置決定は不適法となったので解除する必要があるが、一時保護に際しては当該措置を停止するものとし、解除自体は、児童福祉法第28条の承認審判の申立てまでに行えば差し支えない。)
また、一時保護をしている子どもについて、家庭裁判所に対し児童福祉法第28条第1項の規定に基づく承認に関する審判を申し立てた場合は、家庭裁判所は、申立てにより、審判前の保全処分として、承認に関する審判が効力を生ずるまでの間、保護者について子どもとの面会又は通信を制限することができる。このため、保護者に対し説得を重ねたり毅然とした対応をとってもなお子どもの保護に支障をきたすと認められる場合などには、本保全処分の申立てを検討するのが適当である。
以上は保護者が親権者又は未成年後見人である場合を前提としたが、それ以外の保護者については、当初から反対していても児童福祉法第27条第1項が可能であるし、引取りを求めても無視できる。 |
|
| [3] |
対応における留意点
対応については、複数の職員で臨むことを原則とする。
また、中には、衝動的に暴力を振るう保護者等がいることも予測していなければならない。とくに暴力的な、攻撃的な行為をとりやすい保護者等については、一人で面接することを避け、複数の男性で関わることが必要である。
夜間等の職員の数の少ない場合にも適切に対応することができるよう、あらかじめそうした場合の対処方針、対処方法を決めておくことが重要である。
また、児童相談所と施設は事前に十分、対応について協議しておく必要がある。特に施設に配置される家庭支援専門相談員(ファミリー・ソーシャル・ワーカー)は、入所前から退所、更に退所後のアフターケアに至る総合的な家族調整を担っているので、家庭支援専門相談員とも十分に連携を図ることが重要である。そして前もって施設と児童相談所および最寄りの警察署の三者による協議を設定するなど、事前に警察の協力が得られるよう十分な配慮をすることも求められる。そして、必要に応じて警察に協力依頼し、職員の身の安全を図るとともに、第4章8(2)に述べた法的対応についても検討する必要がある。 |
|
| (7) |
措置解除後の援助をどう行うか
| [1] |
措置解除直後の留意点
子どもが家庭復帰した直後の数カ月は、子ども虐待が再発するハイリスクな時期とされており、保護者の強い希望で家庭に帰った数週間後に、子どもが保護者の暴行によって死亡するという事例も報告されている。家庭に復帰した直後は、児童相談所、学校など地域関係機関との連携を十分行いながら、頻繁な観察・接触を行う必要がある。
|
| [2] |
措置解除後の援助体制
措置解除後の援助に当っては、虐待行為の再発の可能性を十分考慮した取り組みが必要である。
そのため、措置解除と同時に児童福祉司指導に切り替え、継続的な援助を行う。
同時に、家族や子どもに日常的に接触し、様々な援助を行いながら、緊急の場合は児童相談所や福祉事務所に速やかに通告する役割(モニター)を持った人や機関によるネットワークを整備する。
例えば、子どもが通う幼稚園・小学校・中学校等の学校や保育所にはこの役割を依頼しやすいし、地域では民生・児童委員(主任児童委員)に依頼することもできる。また、近くに住む親族や自治会役員などもあり得る。ただ、虐待という事実や家族関係等、かなりプライバシーに関わることであり、人選には慎重さが必要である。
|
| [3] |
子どもの通所
家からの距離にもよるが、小学校4年生程度になると子どもは一人で児童相談所や以前入所していた施設に通うことが出来る。来所した子どもから家庭の状況を聞き、危険度を判断することも大切だが、それ以上に子どもが楽しく遊べることが大切である。
なぜなら、虐待をする保護者は、子どもを自分の支配下に置き、自分と異なる感情や価値観を持つことを許さず、ロボットのようにコントロールしようとする。子どもの通所は、「家族の価値観」というマインドコントロールから子どもを解放し、世の中の常識的な価値観や自分自身の感覚を確認する大切な作業である。
その結果子どもは、保護者の虐待行為を客観的に見つめ直したり、家族のシステムを意識化することで、自らの生き方を主体的に模索することが可能となってくる。何より精神的なバランスの回復を図り、自信をよみがえらせる。
|
| [4] |
家族の援助
子ども虐待は家族システムの問題であるため、家族全体を視野においた援助が常に必要である。
子どもが施設から家庭に復帰する場合、子どもは施設内で様々な経験をしたり、年齢的にも成長しているが、家族は以前のシステムのまま変わっていないこともある。そのため、帰ってきた家に子どもの居場所がなかったり、数日で以前と同じ親子関係の葛藤が再現する場合もある。
家庭復帰に先立って面会や試験外泊を繰り返すなど慎重な対応を行うことは言うまでもないが、家庭引取り後も家族全員に定期的に児童相談所に来てもらい、引取り後の様子や対立点を家族療法的に調整していくことが大切である。
|
| [5] |
要保護対策地域協議会の活用
施設を退所した子どもやその家族に対し、[2]から[4]のような対応を採るためには、要保護児童対策地域協議会を活用することも有効と考えられる。このため、協議会との連携を確保しつつ、施設を退所した子どもが新しい生活環境の下で安定した生活を継続できるように必要な支援を行うことが適当である。 |
|
| (1) |
自立支援計画はどのように作成するか
| [1] |
虐待を受けた子どもにとって……自立支援計画とは
平成9年に児童福祉法等の大幅な改正が行われ、要保護児童、すなわち「保護者のない児童、又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童」(児童福祉法第25条)への施策について、保護から自立支援への基本理念の転換があった。
保護者から虐待を受けた子どもが死亡するという事件が時々発生しており、虐待を行っている保護者から子どもを緊急に分離し、児童養護施設等へ入所させる事例が増加している。これらの介入は、必要な場合、子どもの福祉、子どもの権利を守る意味で速やかに行わなければならない。
虐待を受けた子どもは身体的な目に見える外傷、火傷、熱傷、骨折だけでなく、乳幼児の頃からの保護者の不適切な関わりの中で発達遅滞、情緒・行動障害も併せ持ち、目に見えない心的外傷による後遺症が深刻で複雑・多様な心理的課題を抱えている場合が多い。子どもが受けた身体や心の傷を癒し、まわりの大人や保護者に対する信頼を回復させるとともに、独立した人格と主体性を尊重し、さまざまな要因により停滞していた育ちを保障していくのが自立支援の目的である。
虐待を受けた子どもの年齢と成熟度に応じて子どもの意向を尊重しながら、保護者と共に協働して子どもの自立を支援していくことが児童自立支援施策ではあるが、保護者の求めがなかったり、同意が得られなかったり、また保護者の意に反する場合でも、必要な場合は子どもにとって「最善の利益」を追求しながら、子どもの権利擁護の立場で事にあたることが肝要である。そのためには、関係機関との連携は不可欠で、特に児童相談所とは密接に連携を取りながら、施設での生活と援助の目的、方針、入所期間、援助方法(親子関係の持ち方、面会、帰宅)などを含む児童相談所の「援助指針指針」に対応して児童自立支援計画を策定することが義務づけられている。(「児童養護施設等における入所者の自立支援計画について」平成10年3月5日付児家第9号)
保護者から虐待を受けたり遺棄された子どもは、発達期に十分な心身の回復のための援助を受けないまま成人すると、薬物やアルコールへの嗜癖行動や精神疾患を発症したり、我が子をまた虐待してしまう「虐待の世代間連鎖」が指摘されている。この虐待のチェーンを断ち切り、子どもを健全に育成出来るように児童自立支援計画にのっとり援助し、実効を上げていくことが今、児童福祉施設に求められている。
|
| [2] |
自立支援への取り組みについての考え方
自立支援とは、子どもが社会人として自立して生活していくための総合的な生活力を育てることであり、基本的生活習慣の習得や、職業訓練だけを意味するものではないことは言うまでもない。自立とは孤立ではなく、他者や社会とのよい関係のなかで、社会的資源を活用して生活していく能力を備えることである。しかし、保護者から虐待(不適切な扱い)を受けて入所する子どもは、まわりの大人や保護者に対する不信感(基本的信頼感の欠如)や自己概念の歪み(自信のなさ、劣等感、自己に対するマイナスイメージ)などにより、この社会自立に不可欠な人間関係につまづいている。すなわち低い自己評価や自尊心の欠如から対人関係がうまくとれず、過度の愛着傾向を表したり、攻撃や虐待関係の反復傾向などの「ためし行動」で施設内の生活にも馴染めず孤立してトラブルが頻発する事例も少なくない。しかし、児童福祉施設が虐待を受けた子どもの入所の受け皿として、また「最後の砦」としての役割を担っている以上、この現実から後もどりすることは出来ない。すべての子どもにとって安心して生活出来る環境を保障しながら、心のケアを含めた援助を行っていく具体的な自立支援の取り組みが急がれる。
各施設においては、永年にわたり、地域や施設の特徴を活かして独自に施設としての専門性を高め、地域からも評価を得て事業を展開し、次に述べる課題もすでに研究、実施されていることであろうが、自立支援の考え方に立ってさらに具体的に検討、実施する時が来ている。
| ア. |
「施設内の援助について、地域の人々や、職員間で理解できるものになっているか」(援助の社会化・客観化) |
| イ. |
「子どもの意見表明や最善の利益が尊重されているか」(子どもの権利擁護) |
| ウ. |
「自己実現や存在感の確立が体験できるプログラムが用意されているか」(ウェルビーイング) |
| エ. |
「児童相談所や地域関係機関などと意思伝達、関係がうまくとれているか」(機関との連携) |
| オ. |
「いじめや体罰等の施設内虐待がないか」(暴力の否定、懲戒に係る権限の濫用の禁止、施設内虐待の防止) |
| カ. |
「調理員や事務員などを含む施設職員全員が虐待を受けた子ども一人ひとりに対する共通理解を持っているか」(全職員参加) |
特に施設の全職員が参加して施設内研修やケースカンファレンスを実施するのは困難さを伴うが、虐待を受けた子どもへの援助の専門職集団となるためには不可欠である。すなわち、虐待を受けた子どもおよびその保護者への対応は、担当保育士や児童指導員が一人で関わることは不可能である。虐待関係の再現傾向を示したり職員を挑発するなど、子どものいわゆる「試しの行動」に対して、体罰などの施設内虐待に至らないようにするためにもチームで関わることが大切なのである。生活の場面で発せられる子どものサインや保護者の意向をどのように読み取り、分析、対応していくかが、施設の機能の根幹をなすところである。施設長、保育士、児童指導員、心理療法担当職員、栄養士、事務員、調理員などすべての職員が同じ目的で協働して、連携を図りながら相互理解を深めそれぞれ異なった立場・方法で役割分担していくことで、より高い効果が生まれる。自立支援計画に基づいて子どもの自立支援を図ろうとするならば、どのような計画が適切であるかという職員間の不断の議論が必要となり、その過程を通じて職員の相互理解と連携が図られていくことになる。また、効果を上げるためには児童相談所や関係機関との連携が不可欠であり、日頃より信頼関係を深めるとともに、専門性を向上させ目前の課題に全員で全力で取り組むことが大切である。
特に施設入所初日やはじめに援助に関わった職員の言葉や態度は重要である。「受入れ準備は万全であるか」「歓迎の意の伝達はどのようになされたか」(不安からの解放)、「個別援助プログラムや個別に関わる人がいるか」(自由な自己表現の受容と安心感)、「適切な対人関係の習得プログラムがあるか」(人間関係と歪んだ自己概念の修正)「施設や学校、地域での友だちづくりやグループダイナミクスの活用、集団による育ち合う関係をどうしていくか」など具体的な検討が求められる。
スポーツやレクリエーション、野外活動、キャンプなどは参加すれば本来楽しい行事であるが、「参加できにくい子どもに自主的に判断して参加していく力を養うにはどうすればよいのか」(自我の強化や欲求不満耐性の確立)ということも重要な課題となる。
さらに、「親子関係の改善はいつから、どのように進めていくのか」(親子関係の再構築)ということも重要な検討対象となる。保護者イメージの修正と親子関係の再構築は正比例している。子どもとよく関係の取れている職員が児童相談所と連絡を密にする中で、電話、面会、帰宅等の機会をとらえ、あせらず慎重に進めることが肝要である。
また、「子どもの社会性を養うプログラムはどのようなものを実施しているか」についても留意する。施設を退所して、立派に社会人となって自立している卒園生との交流会や、職場見学、現場実習、ボランティア活動など、生活経験の幅を広げる中で、社会的適応力、達成感が習得されていく。保護者から心と身体に深い傷を受けて、自己評価(Self Esteem)が低く、無力感(Learned Helplessness)を持つ子どもであるが、ただ人から与えられるだけの受動的な立場から、ボランティア活動などのような人の役に立ち、人に喜ばれ、感謝されるという体験を通して得られた実感により、自己評価を高め、自信を身につけ、やらされてやるのではなく、主体的に取り組みながら能動的な立場に立って生活していけるよう援助することが自立支援の最終段階となってくる。
なお、P.T.S.D など心的外傷による後遺症がより重篤な場合は、情緒障害児短期治療施設への入所が適切ではあるが、地域の事情により児童養護施設への入所があった場合は、綿密に児童相談所と対応について協議し、児童相談所や適切な医療機関への通所などによる「心のケア」を行うことも自立支援計画の中に取り入れなければならない。
|
| [3] |
自立支援計画作成のポイント
児童福祉施設最低基準及び「児童養護施設等における入所者の自立支援計画について」(平成10年3月5日付児家第9号厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知)により、子どもが入所している施設は、児童相談所の「援助指針」を受けて子どもおよび保護者の意向と関係機関の意見を踏まえながら、支援計画を作成し、子どもおよびその家庭への援助に当たることになる。
従来、児童福祉施設では、自立支援計画を策定し、援助に当たってきてはいるが、今回改めて、すべての施設に自立支援計画の策定が義務づけられ、子どもの入所時あるいは数ヶ月間援助指針に基づいて支援した後に、ケース検討会議などによる協議に基づき自立支援計画を策定することになった。また、施設入所後も常に子どもの意向を尊重し、これを自立支援計画の中に盛り込み自立支援に当たることとされた。
自立支援計画は、子どもの自立を支援していくための計画であり、実効性を上げるためには、全職員が、入所から退所まで一人ひとりの課題を認識し、自立支援計画を踏まえながら継続して援助にあたる必要がある。また、自立支援計画は、子どもの将来の自立や家庭復帰を見通した長期の目標設定と共に、定期的にその内容を検討し、計画の見直しを図らなければならない。
支援計画策定に当たりまず第一に大切なことは、子どもを理解する力を養うことである。子どもの抱えている問題の本質を見きわめ、現状を客観的に分析することにより達成課題を明確化し、着実に効果的援助が実行できることが求められる。そのためには、高度の専門性をもつ職員集団の育成が急務である。幅広い施設内研修の充実を図るとともに、施設外の研修会への積極的な参加などを通じて広く研鑽をつみ、バランスのとれた熱意のある職員集団を育成する必要があり、そのために施設長の果たす役割は大きい。
子どもの抱えている問題をどうみるか。児童相談所からの援助指針における短期的、長期的課題に基づき、児童相談所と協議の上、緊密に連携を図りながら援助を進めていくことが肝要である。そのためにはまず、子どもの持つ「人間としての力をどうみるか」が重要なポイントになってくる。施設のもつ力量が問われるのである。その子どもの特長を活かしエンパワメントできるように支援することが重要である。また、子どもが抱えている個別の問題や課題は、子ども自身の要因、家庭(保護者・家族)の要因、地域社会の要因が複雑に影響し合っている。そのため、これらの要因について十分な情報を基にして、個々の子どものニーズにあった処方箋とならなくてはいけない。
生活の中の具体的目標を児童指導員・保育士・家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)などが中心となり、可能な限りすべての職員が参加し、組織的な協議の上、自立支援計画の中に盛り込む。
言うまでもないことだが、例え同じように見える子どもでも一人ひとり異なる。したがって、以前支援した子どもと同じような状況にある子どもに対しても、オーダーメイドの計画の策定が必要である。まるで判で押したような計画の策定、あるいは他の子どもの計画を流用するといった計画の策定は避けなければならない。
また、子どもの状況に速やかに対応し、援助に活かしていくために、具体的に支援目標をたて、3カ月程度をめどに評価点検するのもよいであろう。
自立支援計画の策定については、児童自立支援計画研究会「子ども自立支援計画ガイドライン」を参照されたい、なお、ここでは、自立支援計画票について同ガイドラインで提示されているものを掲載するので参考にされたい。(別添9−1参照) |
|
| (2) |
入所時における子ども、保護者への対応はどうあるべきか
| [1] |
施設入所の考え方
−自立支援に向けた援助−
虐待を受けた子どもの施設入所は緊急避難的な意味では、やむを得ないことであるが、心と身体に傷を負って入所した子どもにとって、施設での生活は治療面でも十分とは言えない。しかし、児童養護施設には長い歴史のもと、永年にわたり培ってきた子育てに関する豊富な知識と技術があり、身体的、精神的に虐待を受けた子どもなどを数多く受け入れ、効果を上げつつある。
虐待を受けた子どもも一定期間の施設生活の後退所し、大多数は社会的、経済的に自立して家庭を築き、子どもや伴侶と共に施設に里帰りしたり、あれだけ憎しみ合っていた母など虐待を行っていた保護者との和解を知らせてくれるなど明るいニュースも数多くある。専門的に援助技術等を学習した職員が24時間体制で子どもと生活する中で、その都度発せられるサインを読み取り、どのように対応していくかを相談、連携しながら行っていく子育て技術には、高度な専門性があると言えよう。入所中は、生活環境の保障に加え自立に向けて子どもが受けた身体や心の傷を癒し、大人や保護者に対する信頼を回復していけるよう、直接援助に当たる職員のみならず、施設長をはじめ全職員が専門性の向上に努めることが大切である。
施設入所といえどもすべてが施設だけで完結するのではなく、保護者との適切な対応が求められる。その他学校など地域関係機関との連携、とりわけ児童相談所との密接な連携、協力が不可欠である。保護者と子どもへの適切な援助を積み重ねる中で、傷が癒され成長し、親子関係の再構築が図られる。施設入所の究極の目標は家庭復帰にある。しかし、家庭復帰が出来ず施設から社会へ自立させなければならない事例も数多くある。長期にわたっての入所が続くなかで、大人をイライラさせたり、怒らせたりする「試し行動」や荒っぽい攻撃的な行動などが思春期の問題と重複する時など、施設での援助に困難を感じることがある。虐待を受けた子どもにとって、施設とは何なのだろうか。それは始まりであり、終わりでなければならず、これより先がない、すなわち子どもの権利擁護の「最後の砦」としての役割を担っているという自負心と責任感が求められる。施設や里親を転々と移される「ドリフト」は問題を大きく先送りするだけでなく、ますます心の傷を深めることになるため、厳に心しなければならないことであろう。
|
| [2] |
入所直前の対応とは
−子どもにとってその時点で施設入所が最善という共通認識を持つべきである−
虐待を受けた子どもは基本的な信頼感の欠如からも、きわめて対人関係の取り方が不得手で、一部の例外を除いては極度に緊張したり、不安感をもって入所してくる。保護者についても同様で、なれない公的機関との入所事務手続などのやりとりで疲れ、心痛めて付き添ってくるわけであり、入所前の関わり(admission care)では不安感をどのように取り除くかが重要である。
このためには必要に応じて事前に児童相談所と相談、調整の上、施設職員が一時保護所を訪問して、子どもの権利を説明したり、施設のパンフレットやカラーアルバムで諸行事を見せる、さらには事前に施設を見学させるなどして不安感を軽減したり除去することも必要である。
入所に至る理由や経過については事前に把握し、虐待の事実に関して、保護者、子どもとのやりとりの中で施設職員がどのように触れていけばよいかを児童相談所と調整する。子どもによっては身体的外傷が顕著であったり、表情や態度が固く他の子どもに奇異に映る場合があり、孤立してしまうこともあるので、施設および学校で自然に受け入れられるよう配慮していくことが必要である。
|
| [3] |
入所日には
−子どもの不安を取り除き、物心両面で安心して生活出来る場所だと実感させる−
長年入所している子どもとの会話で「入所当日の昼食のメニューは大好きなハンバーグだった」とか、初めての担当保育士が「添い寝してくれた」など、当日の記憶の確かさには驚かされる。入所日は子どもにとって大きく環境が変わる重要な日であり、不安も大きいことから、緊急の入所であってもネーム入りのスリッパを揃えたり、生活に必要な物をあらかじめ準備しておくといった配慮が大切である。また、勤務を工夫するなどして担当保育士、児童指導員、施設長などが揃って入所時の面接に立ち合いたいものである。
入所当初の関わり(beginning care)は歓迎の意をどのように伝えるかが目標であるから、緊張がほぐれ、ほっと出来るように温かく受け入れる配慮、および一人の人間として尊敬の念を持って受容的な態度で接することが肝要で、事務的な取扱いや保護者に対して高圧的な態度は禁物である。また、入所後も、施設と保護者が補い合いながら協働して子育てに当たっていくことを確認することも重要である。
入所時の面接において、施設の生活について分かりやすく説明する。子どもは虐待により心身に深い傷を受け、大人に対する不信感からどう救いを求めていのかわからないなど施設生活への不安感を抱いており、「苦情解決のしくみ」(図9−1)、保護者と子どもの関係の持ち方(面会、帰宅)、保護者と施設との協働の子育てなどについて説明し、子どもと保護者に安心感を抱いてもらえるよう配慮することが必要である。また、児童福祉法第47条や児童虐待防止法第12条に基づき、子どもの健全育成の観点から子どもと保護者との通信や面会を制限する場合もある。この場合は、児童相談所と連携し、子どもと保護者との関係が断絶してしまわないように十分、配慮、調整する必要がある。
また、入所中に児童相談所等への通所指導等が併用される場合においても、その目的や方法についても説明しておく必要がある。
子どもの不安を軽減し、1日でも早く施設生活になじめるようホーム歓迎パーティー、レクリエーションの実施、担当保育士との一対一の食事やショッピング、入浴、添い寝などきめ細かな個別プログラムを検討するとともに、学校へ事前に見学に行くなど、地域、学校による受入れ調整を行う。
児童相談所からの援助指針を受けて「この施設では何を学ぶのか」といった生活目標を子どもと話し合う中で具体的に設定し、児童自立支援計画の中に盛り込む。それを踏まえて「正しい理解と適切な対応」を施設の全職員が習得、理解するためにケースカンファレンスには全員の参加を求めるべきである。
|
| [4] |
入所初期には
−受容体験の積み重ねと集団の中でのステイタスの確立−
虐待を受けた子どもの多くは対人関係の取り方が不得手であったり、性格行動面に問題を抱えていることがあるので、入所初期には自立支援計画に沿って計画的な援助に当たらなければならない。子どもを暖かく受け入れ、あらゆる場面で支持し、共感してくれる職員との出会いの場が重要である。このような受容体験が積み重なるにつれ、不安が取り除かれ「私は守られている……」と安心して生活できる場所になり、ステイタスの確立(居場所)が実感できていくのである。
保護者との基本的な信頼関係につまづいている子どもは、少し注意されただけでもふてくされたり、閉じこもったり、ささいなことでけんかをしたり、相手を怒らせたり、他罰的、攻撃的な態度をとったりする。甘えや暴言など「試し行動」をも暖かく受け止め、理解し、頭ごなしに叱りつけるようなことは慎むべきである。従来から施設が備えている幅広い年令層の安定した職員集団がそれぞれ異なった価値観を持ちながらも、自立支援計画に基づいて協力し、虐待を受けた子どもの抱える問題ならびに保護者への対応について共通認識を持ち、ていねいな対応がなされなければならない。また、援助に当たり、難しいケースを持つ担当職員に適切な助言、指導を行えるスーパーバイザーなど、経験豊かな専門性に富んだ職員の養成も重要である。子どもが虐待に起因する心的後遺症を有している場合は、児童相談所へ通所して心理療法を受けたり、児童相談所の心理療法担当職員が施設を訪問して治療を行う等の方法を児童相談所と連絡調整しながら検討することが必要である。
|
| [5] |
施設における援助は人として「生きる力」の学習
−自分を肯定的に見ることができるために−
21世紀の我が国を担うかけがえのない存在である子どもを、心身ともに健やかに育成し、社会人として自立して生活していくための総合的な生活力を育てるのが児童福祉施設の役割であり、その基礎となるのは「生きる力」の学習である。本来大切にされ愛されたいと願い慕っていた親からさえも、「保険金が欲しいから生んでやっただけだ!」とか「おまえの顔を見ているとうっとおしいだけ、むこうへ行け!」など人間の尊厳を傷つけられたり、物心がつかない乳幼児期から心身の成長および発達を支え育むための適切な関わりがなされなかった状況や不適切な関わりの結果、「どうせオレはバカだ!」と自己に対するマイナスイメージ、すなわち自己評価(SelfEsteem)が低く、「誰も信じない」「大人はみんな嘘つきだ!」と人に対する不信感(基本的信頼感の欠如)や、自信が無く、劣等感など自己概念に歪みが見られ、ときには「学習された無力感・絶望感」(Learned Helplessness)さえ認められたりする。
施設が従来から備えている24時間生活を共にし、職員と子どもとの適切な関わりにより、心身の成長および発達の回復が図られる。自分の誕生を否定し、自分自身をも信じられなかった子どもが、自分が大事な存在だと自覚したり、大事なものとして自分の持物を大切にできるようになっていく。様々な行事などの実体験を通して、「やったらできたじゃないか」と自信を取り戻してゆき、表情が豊かとなり、「今生きててよかった」と自分が今生きていること、すなわち自分の人生を肯定的にとらえ、生きていく意味や「希望」、「生きる力」を学習していくのである。
「児童の権利に関する条約」の批准・発効などを背景に、子どもの権利が尊重され、いじめや体罰などを許さず、平和と正義に満ちた施設環境を整備することが求められている。
一人ひとりのつぶやきや意見に耳を傾けることの出来る職員や、落ち着いて目標に向かって励んでいる安定した年長児から多くのことを学習し、集団の遊びやスポーツ活動、各種の行事等により、自分自身を見つめることのできた子どもは、今まで学び得なかった「自我の強化」を学習するよいきっかけをつかみ、正しいルールに裏打ちされた評価や承認による達成感を得て「欲求不満耐性の確立」や「社会的適応力」等を獲得していくことができるのである。
しかし、虐待を受けた子どもに係る施設での援助においては、子どもが虐待関係の再現傾向を示すことに注意しなければならない。子どもは「自分が悪いから罰として虐待を受ける」と思っていて、罰を受けないと不安定になり挑発してくる。いわゆる虐待されたことによる「試し行動」である。そのため、虐待を受けた子どもの中には、職員の指導に対し過度に反抗的、挑発的であったり、暴力で問題を解決しようとする傾向を示す子どももみられる。職員が虐待関係の再現に巻き込まれてしまい、子どもに対して虐待的感情を持ってしまうこと(逆転移現象)になってはならないし、体罰等の施設内虐待をしてはならない。心の傷が深い子どもほど、何度も何度もこのような行為を繰り返すことによって職員の人間性を確かめようとすることが多いのである。その職員は本当に自分のことを受容し自立させてくれる人なのか、その真意や力量などを見定めようとするものであれば、その子どもがその職員を見切らない限り、信頼を寄せるようになるまで続くのである。だからこそ、職員はこのような「試しの行動」や「問題行動」などへ適切に対応することが大切なのである。虐待を受けた子どもの心理、行動特性について十分な理解に基づいて援助に当たる必要がある。児童相談所等の専門職員を交えた研修や事例研究会を実施して、施設の全職員が虐待についての正しい認識と適切な対応を習得し、一貫したしつけと愛情に満ちた援助がなされなければならない。また、職員相互の協力、連携プレーが大切で、担当職員といえども個人プレーは慎まねばならない。一人だけで関わってしまうと、精神的な負担が大きく、援助の効果が上がらないどころか抱えこんでしまって大きな問題に発展する場合がある。連携していくためには、生活の場面で発せられる様々な子どものサインをどう読み取り、分析、対応するのかが問われる。また、子どもの行動を観察する際も、ややもすると否定的言動、問題行動に視点が偏りがちであるが、常に子どもの長所や可能性に目を向ける必要があり、これらを適切に助言し援助するスーパーバイザーやサポートスタッフを各施設で工夫しなければならない。 |
|
| (3) |
虐待を受けた子どもへの心理的援助の基本的枠組
| [1] |
保護者等から虐待を受けて施設に入所してきた子どもは、直接的な身体の外傷が治癒した後も、心理的虐待や虐待的な生育環境、分離体験等から生じる様々な課題を抱えていることが多い。その場合には職員や他の子どもとの間で安定した関係を取り結ぶことが難しく、自立した社会人として成長していくための障害となること等が指摘されている。 |
| [2] |
虐待を受けた子どもの援助に当たっては、施設が従来から持ってきた受容と支持の機能が基盤となる。職員と子どもが起居を共にする中で、施設が子どもを暖かく受け入れている場所であることを伝え、職員が子どもの感情を否定的な感情も含めて支持し共感的に理解するなかで、子どもが物心両面で安心して生活できる場、守られているという実感をもてる場を提供していくことが援助の基本である。日常生活の場面場面での職員と子どもとの感情の交流を通して密接な信頼関係を築き、それを維持していくことによって、子どもが心の傷を癒し、自立した社会人として成長していくための基盤ができるのである。
このことを可能とするためには、児童福祉司、心理職員、精神科医等の児童相談所の専門職が共同の事例検討や助言・指導を通じて施設を技術的に支援していくことが不可欠であるとともに、施設職員が虐待を受けた子どもの心理・行動特性を理解し、社会福祉援助技術と臨床心理学等の基礎的知識・技術を身につけるための研修の機会を体系的に充実していく必要がある。 |
| [3] |
虐待を受けた子どものうち、虐待に起因する心的後遺症(単なる心の傷ではなく日常生活に支障があって治療を要するもの。)を有していて、心理療法や精神科医の治療・助言等が必要と考えられる子どもに対しては、児童相談所への通所や児童相談所職員の施設訪問等により、心理療法等必要な治療を受けさせるとともに、生活上の援助に当たる職員への専門家の助言を得ることが必要である。
これら心理療法を必要とする子どもが一定数以上入所している場合には、通所や施設訪問が困難となる場合があるため、平成11年度から、こうした児童養護施設等が非常勤の心理療法を担当する職員を雇い上げるための経費が計上されている。また、平成16年度からは、子どもが虐待を理由に児童養護施設等に入所した場合には、心理療法担当職員の雇上費や子どもの生活諸費等に充てるための経費を加算して支弁することとなった。心理療法担当職員が行う心理療法等の子どもへの援助および施設職員への助言等は、児童相談所と密接に連携しつつ、その指導・助言の下に行われるものである。
また、独りで心理的治療に取り組むことの危険性が指摘されているように、虐待を受けた子どもへの心理的援助を行う上で大切なのが、チームによる援助体制の確立である。心理的援助をスムーズに展開していくための前提条件となるのが、援助者をサポートできる良好なチームを維持することであり、専門家としての姿勢と資質を兼ね備え、職員間のチームワークを良好に維持していくことによって、はじめて心的外傷を受けた子どもの心理的援助が促進されるのである。 |
| [4] |
ただし、虐待を受けた子どもの心的後遺症が重篤な場合には情緒障害に該当し、情緒障害児短期治療施設の対象となるから、情緒障害児短期治療施設に入所して精神科医と心理療法を担当する職員による治療とそれら専門家の助言をもとに行われる生活指導を受けることが適切である。情緒障害児短期治療施設は昭和36年に創設された児童福祉施設であるが、十分な整備が進んでいない。未設置の都道府県では児童相談所の通所部門や医療機関等を活用して必要な子どもへの援助に当たっているとしているが、虐待を受けた子どもの急増から心理・精神医学的治療の必要な子どもも増加しており、整備の促進が望まれている。 |
| [5] |
虐待を受けた子どもへの心理的援助は、環境療法的接近と心理療法的接近とに大別される。環境療法的接近については、本章2(4)において、心理療法的接近については、本章2(5)において説明する。 |
|
| (4) |
環境療法的接近による心理的援助
虐待を受けた子どもは、そのトラウマゆえに対人関係や感情体験に様々な問題を抱える傾向がある。こうした子どもの問題、たとえば自分にとって養育的、保護的立場にある大人に挑発的に関わって虐待的な人間関係を繰り返す、あるいは、かんしゃくを起こしてパニックに陥り、暴力的、破壊的な行動にでるなどといったことは、カウンセリングルームでよりも、施設での日常生活場面において生じやすい。そのため、施設環境が環境療法(milieutherapy: Trieschman etal., 1969)的な要素を備えることによって、子どもの問題行動への修正的接近が可能になると考えられる。
虐待を受けた子どもに対して、施設が備えていなければならない環境療法的特徴の中で特に重要なものを以下に列記する。
| [1] |
安全感・安心感の再形成
虐待を経験した子どもは、いつ身体的暴力を受けるか分からないといった危険に満ちた環境で成長してきたわけで、そのために自分を取り囲む環境が危険なものだという学習をしてきている。環境や他者が危険なものだという認知は、当然、子どもと他者の関係に大きく影響する。そのため、子どもは環境や他者が安全なものであり、自分は安心できる環境にいるのだということを再学習しなければならない。他者が自分にとって危険な存在ではないという再学習を可能にするためには、子どもを取り巻く環境を「非虐待的」なものにすることが重要となる。
|
| [2] |
保護されているという感覚(保護膜)の再形成
子どもが心理的に健康な発達をとげていくためには、「自分は保護されている」「自分は守られている」という感覚を持てることが非常に重要である。「自分は守られている」という感覚は、子どもの心を様々なストレスから守ってくれる保護膜とでもいえるような機能をはたすのである。しかし、虐待環境で育った場合、子どもの心は保護膜を持つことができなくなる。自分を最も愛してくれて、守ってくれるはずの存在である保護者から暴力を受けるということが、子どもの心から保護膜を奪ってしまうのである。
したがって、虐待環境で育ち、保護膜を持たない子どもに対して、施設環境は保護膜の再形成を目指した関わりを行う必要がある。子どもが、「自分は守られている」という感覚を回復できるためには、まず「自分のことが分かってもらえている」という感じが持てることである。現在の自分を取り巻く施設環境内に存在する大人が、自分の苦しい体験、現在抱えている様々な問題や不安、そして自分の考えや気持ちを理解してくれていると感じられることが、保護膜の再形成に向けた第一歩となるのである。虐待を受けた子どもたちは、その体験に関連したトラウマ性の感情や思考、認知を日常生活において持ちやすい。また、虐待のために家族から分離されて養育される子どもは、自分が保護者から見捨てられたという考えを持ちやすく、それが日常において様々な悲しみや怒りを生じることが多い。子どもの養育に関わる大人が子どものこうした状態を理解し、「おうちであったことを思い出して怖くなったみたいだね」「もしかしてお母さんから見捨てられたような気持ちになって悲しくなったのかなあ」といったような言葉を子どもに向けることによって、子どもは「この人は自分のことを分かってくれているのかもしれない」という考えを持つようになる。自分が理解されているという体験を積み上げた子どもは、次第に、その大人に対して心の中にある様々な思考や感情を伝えていくようになる。こうした関係の中で、子どもは「この人は自分を守ってくれているんだ」という思いを持つことができるようになるのである。
|
| [3] |
人間関係の修正
虐待環境で成長することによって、子どもの対人関係のパターンは様々な歪みを抱えてしまう。その最たるものが虐待的人間関係の再現傾向である。その他にも、無差別的愛着傾向を中心とする親密な人間関係の歪み、強いものへの従順さと弱いものへの抑圧・攻撃性を特徴とした「力に支配された対人関係」、人間関係を苦痛なもの、不快なものとして避ける対人関係の回避傾向などが見られることもある。
こうした対人関係のパターンを身に付けてしまった子どもに対して、施設環境はそのパターンを修正する機会を提供しなければならない。たとえば虐待的な対人関係を再現する傾向のある子どもが挑発的な言葉や行動で関わってきたとき、そうした再現傾向に捕まることなく、子どもがどのような心理状態にあるのかを理解しようとする態度を大人が示すことによって、子どもの対人関係パターンの修正への道が開かれることになる。「今、あなたは僕を怒らせようとしているみたいなんだけど、どんな気持ちでそうするのかなあ」といった言葉が大人から返ってきたとき、自分の言葉に対する大人からの虐待的な反応に慣れている子どもは虚を突かれて驚くことになる。もちろん、これがすぐに子どもの人間関係の修正につながるわけではないことは言うまでもないが、こうした体験の積み重ねが、子どもをして自分の行動傾向に目を向けさせることになるのである。そして、子どもと大人の間で、対人関係パターンの裏に潜む子どもの不安や恐れなどの感情が次第に理解されていくことになる。こうした理解を通して、次第に子どもはそのパターンを変えていくのである。
|
| [4] |
感情コントロールの形成
虐待などによるトラウマを抱えた子どもはトラウマ性の感情反応を生じやすく、また、保護者の不適切な関わりのために感情調整能力が形成されていない場合が多い。虐待環境で育った子どもは、それが怒りや不安などの否定的なものであれ、あるいは喜びや興奮などの肯定的なものであれ、ある程度の強度を持った感情を抱えておくことができなくなり、それを爆発的な行動として表現したり、パニックを起こしてしまうことが多い。こういった傾向を示す子どもに対して、施設環境は感情コントロールの形成に向けた関わりを行わねばならない。
感情コントロールの形成のためにまず必要となるのが、環境による「抱きかかえ」(holding)である。子どもは自分の中に起こった感情を抱きかかえておくことができないため、爆発的に表現したり行動化することでそれを自分の外に放り出す。それを環境が抱きかかえて吸収するわけである。そして、次に必要となるのが、環境から子どもへのフィードバックである。子どもの感情表現を受け止めて抱きかかえた環境が、今度は受け止めたものを子どもが理解し受け入れることのできる言葉に直して再び子どもに戻す、つまりフィードバックしてあげるのである。たとえば「あなたが〜したかったのに、私が忙しくてあなたの相手をできなかったから、あなたは私に無視されたような気持ちになって、すごく悲しくなって、それからとっても腹が立ったのね」といった具合にである。
自分の気持ちを抱えることができない子どもにとって、環境がそれを抱きかかえてくれて、さらに言葉で自分の心の状態についてのフィードバックを受けるという体験は、抱えられたことによる安心感と、そして、フィードバックによる自己の感情の理解へとつながっていく。こうした体験を積み重ねることにより、子どもは次第に自分の感情を理解し始める。こういった感情の理解は、子ども自身が次第に自分の感情を抱きかかえておくことができるといった状態へとつながる。
感情コントロールの形成に向けた関わりとして、もう一つ必要とされるのが、言語化の促進である。これまで述べてきたプロセスによって、自分の感情についての子どもの理解はある程度進んできたと考えられるが、今度は、その自己理解の言語的表現を促進するわけである。こうした言語化の促進によって、感情をコントロールする力が次第に獲得されていく。「あなたが〜したから、僕はとっても腹が立った」と言える子どもは、その怒りを爆発させたり、あるいは行動で表さなくてもいいようになるのである。 |
|
| (5) |
子どもへの心理的援助をどのように行うか
本項では、虐待を受けた子どもの心理療法の中でもっとも多く行われるプレイセラピー(遊びを通じて行う心理療法)のあり方について述べる。虐待を受けて施設に入所している子どもの多くが、児童相談所の心理職員、施設に勤務している非常勤セラピスト、病院や相談所など子どもが援助を受けている相談・医療機関のセラピストなどから、この種の援助を必要としているのである。
| [1] |
プレイセラピーの目標
虐待を受けた子どもに対するプレイセラピーの目標は、虐待やネグレクトによって生じたトラウマティックなストレスを子どもが乗り越えられるように子どもを援助することである。そうすることによって、子どもの心理社会的発達の歪みを修正、もしくは予防することが可能となる。
|
| [2] |
プレイセラピーにおいて扱われなければならないテーマ
虐待を受けた子どもの心理的な問題として、比較的共通に見られるテーマを以下に示す。プレイセラピーにおいては、これらのテーマが評価され、取り扱われなければならない。
| ア. |
身体的暴力の恐怖、および見捨てられの恐怖:こうした恐怖が、抑うつ感や強い不安につながることがある。また、こうした恐怖がきっかけとなって、攻撃性、人間に対する不信感、衝動コントロールの欠如が生じることが多い。 |
| イ. |
保護者の歪んだ期待に応えられなかったこと:こうした「失敗体験」が、対象関係の歪み、依存−自立葛藤、極端に自己評価の低い「悪い子ども」という自己イメージの形成につながることが多い。また、抑うつ状態を悪化させることも多い。 |
| ウ. |
分離や自立性の獲得の困難性:予測のできない恣意的な報酬と拒否の交代にさらされ続けたことによって、子どもは自己と対象をいわゆる“all good”と“all bad ”に乖離させるという原始的な状態にとどまってしまうことが多い。 |
| エ. |
複数にわたる拒否体験と家庭外への措置による問題:虐待を受けた子どもは、病院への入院や里親委託、児童養護施設への入所など、保護者からの分離を体験することが多い。こうした体験は、分離不安を強めるとともに、他者への愛着形成の障害を生じることが多い。 |
|
| [3] |
子どもの適用年齢
プレイセラピーという媒体の性格から、その適用には年齢的な限界がある。年齢の下限は約3歳であろう。Gil(1991)は、知的な発達の高い子どもの場合には2歳6カ月でも適用が可能な例があるとしている。年齢の上限は、小学校の高学年、10歳から12歳あたりであると考えられる。ただし、子どもの状況次第で、もう少し上の年齢でも適用が可能な場合がある。
|
| [4] |
方法
過去には、子どもの抱えるあらゆる問題の心理療法の方法として、プレイセラピーが用いられてきた。しかし、プレイセラピーに対するこうした期待は非現実的と云わざるを得ない。現在では、虐待などを体験した子どもの心理療法の道具として、プレイセラピーが再評価されてきている(Man & McDermott, 1983)。その際に、従来のプレイセラピーのあり方とは違い、以下のような点に注意が向けられなければならない。
| ア. |
プレイセラピーに用いられるおもちゃなどの道具が、子どもが体験した特定の出来事をプレイで扱う上で適したものであるという基準で選択されていること。 |
| イ. |
子どもが自分のトラウマティックな体験を扱うための方向付けがセラピーにおいてなされること。 |
| ウ. |
プレイセラピーが、子どもの虐待などの体験の再現を中心に展開し、その再現を通して、より適応的なレベルの回復を目指したものであること。 |
|
| [5] |
プレイルームのセッティング
虐待を受けた子どもは、一般的にいって注意の集中が困難で易刺激的であり(注意欠陥多動性障害の診断を受けていることも珍しくない)、衝動コントロール障害のために爆発的な暴力的行動化を示すことが多い。したがって、こうした子どものプレイセラピーを行う空間としては、適度の広さを持った刺激の少ない質素な部屋であることが望まれる。プレイルームには、本棚などの固定式の家具はおかないようにする。机やいすも、容易に移動可能なシンプルなものであることが望ましい。また、部屋の装飾はできるだけ少なくし、特に、子どもが興奮したり攻撃的になったときに「武器」になるようなものは置かないようにする。
また、一般のプレイルームに多く見られるような、部屋の棚に遊具を並べておくといった形態は避けるべきである。こうしたおもちゃの配置は、子どもにとって過剰な刺激となってしまう。子どもは目に飛び込んでくるおもちゃという刺激に翻弄され、次から次へと新しいおもちゃを手にとるといった行為に終始し、その結果、「まとまりのないプレイ」に終わってしまうことが多い。したがって、虐待を受けた子どもへのプレイセラピーを行う場合、部屋にはおもちゃを置いておかず、別の部屋におもちゃをストックしておき、プレイの始まりの時点で子どもがおもちゃの部屋に行って自分が遊びたいおもちゃを選ぶといった方式にするとよい。また、こうした方式をとるようにすれば、適切なタイミングで、子どもが自分の受けた虐待を再現するのに適したおもちゃをセラピストが選んであらかじめプレイルームに置いておくといった方法で、子どもの再現性を刺激することも可能である。
|
| [6] |
プレイセラピーに使用するおもちゃ
おもちゃの選択は、子どもの年齢、セラピーの進展、子どもの体験の種類によって異なるが、原則的には高価でなく、壊れにくく、子どもがそれを「武器」として使っても安全なものであることが望まれる。以下に、虐待を受けた子どものプレイセラピーに必要なおもちゃを列記する。
| ・ |
ドールハウスおよび家族人形 |
| ・ |
様々なままごとの道具 |
| ・ |
赤ちゃん人形とほ乳瓶 |
| ・ |
医療セットや救急車のミニカー |
| ・ |
各種のパペット(様々な動物や、魔女や妖精などの手人形) |
| ・ |
象徴的な意味を持つ人形 |
| ・ |
電話、サングラスなど |
| ・ |
描画の道具や粘土など |
| ・ |
その他、子どもの体験に応じた特定のおもちゃ |
|
| [7] |
虐待を受けた子どものプレイセラピーの展開
以下に、虐待を受けた子どものプレイセラピーの展開を4段階に分けて述べる。
【第I段階:関係の形成】子どもはセラピストとの関係において、虐待的人間関係の再現やリミット・テスティングを示し、次第に退行を示すようになる。こうした退行によって、子どもはセラピストからエネルギーを得るのである。
【第II段階:虐待の再現的表現】セラピストとの関係でエネルギーを得た子どもは、次第に自分の受けた虐待行為などの体験をプレイの中で再現するようになる。こうした体験の再現を中心としたプレイを、ポストトラウマティック・プレイと言う(Gil, 1991)。
【第III段階:人間関係への適応の試み、衝動コントロールの形成、自己評価の修正】前段階で自分の体験を再現し、その体験にともなう恐怖、不安、怒りなどを解放した子どもは、次第に現実的なテーマをセラピーに持ち込むようになる。そこで取り扱われるべきテーマは、現実の人間関係への適応、衝動コントロールの形成、自己評価の修正などである。
【第IV段階:終結】虐待を受けて施設に入所している子どもは、分離・喪失をめぐる葛藤を抱えている。そして、心理療法の終結は、子どもにとってもう一つの分離喪失体験となり得る。それだけに、この終結の段階では終結に対する子どもの反応をていねいに扱っていく必要がある。
|
| [8] |
心理治療事例紹介
[事例I]児童養護施設における心理治療、ケースワーク援助
| 1. |
事例の概要
Aは実母からの身体的・心理的虐待のために1歳時に乳児院に入所し、その後、2歳時に児童養護施設に措置変更となり、9歳時に実父・継母のもとに退所した。
実母は精神的に不安定で、情緒的に混乱しやすく、非常に暴力的になりやすいといったことが原因でAの父親と離婚し、乳児であったAを連れて母子での生活を始めた。その直後からAに対する様々な虐待行為が顕著となり、近隣から児童相談所への通告がなされ、Aは1歳時に一時保護の後、乳児院への入所となった。
一時保護および乳児院への入所に際して、実母は特に抵抗を示さなかった。また、乳児院への入所後に、親権は父親に移されたが、この時点で父親はAの養育に当たることが困難であったため、施設養育の継続を希望し、2歳時に乳児院から児童養護施設への措置変更が行われた。
|
| 2. |
援助の経過
数年後、実母は再婚し、再婚相手との間に男児を出産したが、その頃からAを引き取りたいと考えるようになった。母親は周囲の反対を押し切って児童養護施設に連絡を取り、施設で心理職員とのカウンセリングが開始された(当面Aに会うことはできないことを了解してもらった)。カウンセリングでは、「虐待行為については何も覚えていない」としながらも、「自分は夫との離婚などでとてもつらい思いをしているのにAはニコニコして寄ってきて憎らしかった」「叩いても叩いても寄ってくるのはなぜなのかわからなかった」など、虐待を生じていた頃の心理的な状況に関する話や、思春期の頃の精神的な混乱、自分の母親との関係などが中心になり、このようなカウンセリングが約一年続いた。その後、実母側からの連絡が突然途絶え、施設から実母に連絡を取ると、現在の育児が大変なためなかなか施設に行くことができない、この状況では引き取りについても考え直したいとのことであった。
Aが小学校3年の頃、児童福祉司が父親に働きかけを開始し、それに応じて父親はAと再会した。父親は引き取る意向を示し、週末を利用しての一時帰宅など、父親との関係形成のためのプログラムが実施された。しかし、一方で、この時期、Aは施設での生活で、万引きの増加や暴力的な行動化の激化など、様々な不適応を示すようになった。
こうした状況の変化に対応するため、Aに対して定期的なプレイセラピーが開始された。プレイセラピーにおいて、Aは自分を捨てていった実母に対する攻撃性と思慕の入り交じった感情を表現したり、あるいは2人の大人が子どもを競って奪い合おうとしており、子どもがその2人の間に挟まれて非常に苦しい想いをしているなどといったテーマを持つ物語を展開するなど、現在の自分をめぐる混乱状況を表現した。こうしたプレイセラピーの内容から、母親への断ちきれない想いや自分を「捨てた」実母への怒り、あるいは自分の意向とは無関係に進められた父親との関係形成といった方向性に対する納得のいかなさがAの問題行動の増悪と関連しているのだろうと判断された。
こうしたプレイセラピーでのA自身の心理面への理解に基づき、施設側は父親にAの気持ちを伝えるなど、積極的な働きかけを継続した。既に再婚していた父親は、Aを引き取りたいとの意思は非常に強固なものとなっており、実母に対するAの気持ちについては「それはわがままなことで、直ぐにでも引き取る」との主張をしたが、施設側のねばり強い働きかけが功を奏し、「Aの実母に対する想いが断ち切れないうちに引き取ることは、大人の都合で子どもを振り回すことになってしまう」との施設側の考えを、徐々にではあるものの理解するようになった。その結果、父親の承諾のもと、Aと実母の面会が可能となり、実母との面会の場で、実母の口から直接「引き取れない」という意思を伝えてもらい、さらに父親が「自分が引き取りたい」ということを伝えるという方針で面会が実施された。
その後、Aはプレイセラピーにおいて実母との別れや父親との和解をテーマとしたプレイを展開し自分の気持ちに何とか区切りをつけた後、父親の元に引き取られていった。
引き取り後も、Aが施設に遊びに来たいとのことで、何度も気軽に訪れている。その後も父親宅でうまく適応できていると思われる。
|
| 3. |
考察
日常生活における暴力的な行動化が激しく、周りの子ども達への影響力も強かったため、施設側としては積極的に関わらざるを得ないケースだった。日常的なケアにおいては包み込むようなケアを心がけた。また、プレイセラピーの場面では「大人が子どもを奪い合う」「母親が抱えていた赤ちゃんを悪者がさらっていく」といったテーマを中心として展開が見られた。セラピストは、これらは子どもの実母への想いが表現されており、こうした混乱した情緒状態がさまざまな行動化の根底にあるものと解釈し、その解釈を日常生活を担当するケアワーカーに伝えた。ケアワーカーはこうした理解に基づいたケアワークに心がけ、Aの行動化は次第に影を潜めるようになった。施設における心理療法と日常レベルでのケアワークとがうまく連動した事例といえよう。心理職員とケアワーカーとの連携についてもうまくいったといえる。また、こうした連携は、心理療法とソーシャルワークの領域でも見られた。Aの家庭引き取りを目指して開始された父親への働きかけは、Aに対して様々な心理的影響を生ずることになったが、そうした心理的反応をプレイセラピーによってうまく扱っていくことが可能となった。また、Aの心理的状況を父親に説明することで、ねばり強いソーシャルワークの展開が行われ、最終的な引取りへと結びついたと言える。さまざまな局面で引き取りに向けて丁寧に関わり、それが功を奏したと思われるケースである。 |
|
[事例II]情緒障害児短期治療施設における心理治療
| 1. |
主訴:小学校4年生男児A 家の金の持ち出し、盗み食い、衝動的な暴力
|
| 2. |
生育歴:Aは出生すぐから母親に受け入れられず、実母から厳しい体罰と家庭のことに無関心な父親のもとで育つ。夜尿しないようにとペニスを紐で縛られたこともある。夫婦関係は悪く、家の中は冷たい雰囲気であった。小1の時、実母が自宅で急死し、Aが発見する。学校では明るくひょうきん者で振る舞う一方、友達はなく、家の軒下に木などで作った武器を大量に隠し、裏山に行っては小動物に危害を加えていた。スパナを隠し持ち、女児にケガを負わせたり、年下の子を階段から突き落としてケガを負わせた。家庭では、盗み食い、ウンチを隠す、家の金の持ち出しなどが始まるが、注意しても耳に入らない。継母がAの有様を心配し、困り果て、小4になって児童相談所に相談する。
|
| 3. |
診断:行為障害
|
| 4. |
施設での受け入れ:Aの問題に対して心理治療的なケアが十分に行われることが必要であり、情緒障害児短期治療施設であるX学園が紹介される。しかしAの衝動的な暴力や隠蔽行動などに現れている問題の深さに、学園が十分対応できるかどうかが懸念され、見学や面接などを繰り返し、治療の動機をAと家族に慎重に確かめた上で入園となった。
|
| 5. |
治療経過
第1期:入園後しばらくは、一見陽気に振る舞っているが、落ち着きがなく、何かしていないと気がすまないようであった。食事はむさぼるように大量に食べた。あれをやらせろこれをやらせろと要求が多く、生活の枠になかなか収まらない。妬みや恨みを抱きやすく、他児とのトラブルが増え、険しい表情で「殺したい。凶器で殴って殺す。」などの言葉を平気で口にする。入園後1ヶ月したところでプレイセラピーを開始する。箱庭を創り、内面にある深く恐ろしい世界を表現する。その後のプレイは人形を使った戦いが執拗に繰り返されるが、心底にある闇の世界と必死に戦っているようであった。生活場面でも「いざというときに使うんだ。」と木製の刀を作り持ち歩くようになり、やがて「お母さんが幽霊になって出てくる。怖い。」と訴え、脅えて眠れない日が続く。小5になったある日のプレイセラピーで、玩具の鉄砲を手に取ったとたんに表情が青ざめ倒れてしまう。病院に運ばれ、不整脈と分かる。Aは「プレイは続けたいけれど、もうあの部屋は嫌だ。」と訴え、その後のプレイは場所を変え、ブロック遊びやラジコンバギーといったAの内面にあまり触れずにすむ活動に移行し、穏やかな場面に変わる。不整脈はその後日常生活場面でも頻発するようになり、安静時に職員が寄り添い、脈を計るなど、不整脈のケアに重点を置いた関わりが中心となる。その後腹痛や頭痛などの身体症状も増え始め、それらのケアを通して大人との信頼関係が芽生えてきた。よく眠れるようになり、疲労感を訴えることが減る。食事も適量をゆっくりと食べるようになった。
第2期:小6になると、「自分のことを考えると惨めな気持ちになる。」「将来はどうせだめ。」など自分を卑下し将来を悲観する言動が目立つようになってくる。中1になると、そうした苦しみから逃れたい気持ちから、「退園したい。」と強く訴えるようになる。まずはしばらく帰省して、退園については改めて検討することにした。ところが帰省中に不整脈が生じ「学園に戻りたい」とSOSの電話が学園に入る。「家に帰ってもイライラする。しばらく帰省せずに自分のことを考えたい。」と語る。中1の終わり頃、学校の授業でマラソン大会の練習が始まる。不整脈のあるAの参加をどうするかで学校職員と話し合い、ゆっくり自分のペースを守ることを目標に、学園職員が授業に参加してAと併走し、脈を取りながら練習することになる。これを契機に職員との関係がより確かなものとなり、Aは自信をつけていく。
第3期:中3になってからはさまざまな活動に積極的に挑戦し、学力や体力が著しく向上する。不整脈などの身体症状が嘘のように減ってくる。個人心理治療場面は自分のことや家族のことを言葉にして語ることが増え、将来に対しても「やりたいことが一杯ある。昔はなかったんだよ。」と希望を抱くようになる。一方で父親に対して否定的な言動が増え、父親の面会さえ拒絶するようになる。卒業を機に退園後は家に帰らず、児童養護施設から高校に通うことを自ら決めた。高校卒業後父親に対する感情にも折り合いをつけ、同居が可能となった。
|
| 6. |
まとめ
乳幼児期から虐待環境におかれた子どもは、Aのように根深い不信感、恐怖感、攻撃的衝動の処理のできなさ、過剰な欲求とそれが通らないときの恨みなどの問題を呈しやすい。こうした初期の心理的な発達に障害を受けた子どもの治療に当たる場合、大きく分けると次の3つの段階が重要であろう。
第1段階:安心感と安全感を抱き、大人との信頼関係を構築する段階。生活の中で安心感や安全感を抱けるよう環境を工夫する必要がある。同時に子どもがそうした治療環境を受け入れるには相当の時間がかかることを熟知しておくことが大切であろう。無理やり施設のプログラムに乗せようとしても被害感を強める結果に陥りやすい。
第2段階:自分自身の有り様や自分の過去、家族を振り返り収める段階。この段階は思春期に、より顕著に生じやすい。短期間の外傷を振り返るのとは違って、長期にわたって劣悪な環境におかれていた子どもは、自分の生い立ちの喪失感を伴うため、自己を卑下し、将来に対して絶望感さえ抱いてしまいやすい。治療者はそっとかたわらに寄り添い続けながら、新たな希望を抱けるように支えることが必要である。
第3段階:地域社会への復帰の準備をする段階。培われてきた力を基盤に様々な物事に挑戦し自身を深めるときである。
第1段階から第3段階まで行きつ戻りつしながら進むのが普通であり、治療には常に困難を伴う。単独で治療を行うことは不可能であり、チームを組むことが不可欠となる。チーム治療は治療者の抱え込みを防ぎ、皆で見ているという感覚は治療者を安心させる。さらに様々な視点があることで子どもへの理解を深めることを可能にする。また、個人心理治療などの特別な治療プログラムは日常生活という現実場面から遊離することなく常に有機的関連性を意識しながら進めることが重要であろう。 |
|
|
|
| (6) |
親子関係の調整をどのように行うか
| [1] |
保護者への援助に当たっての姿勢
保護者への援助に当たっては、懲罰的な意識を持ってはならない。受容と保護者の置かれた状況への共感的理解を基本に、虐待する保護者から子どもを取り上げたのではなく、親子関係が改善されるよう援助するのが児童福祉施設の立場で、究極の目的は家庭復帰である。
虐待をする保護者には、依存性が強い者や地域社会で孤立し、対人関係を円滑に持つことができない者、神経症に苦しんでいる者もおり、また保護者自身が幼児期に保護者からの虐待を受けた者も多く、児童相談所を中心に保健所、精神保健福祉センターや医療機関、児童家庭支援センターや福祉事務所、母子自立支援員、民生・児童委員(主任児童委員)等と連携を密にする中で、施設としても専門的な対応を図っていく必要がある。
このような保護者の多くは、子どもを施設に入所させたことにより「親失格」という烙印を押されたと恥じているから、「子育てが大変だったね!よくここまで頑張ってこられたね!」と理解の態度や支持的関わりに努め、いつでもどのようなことでも保護者とともに考える姿勢であること、協働して子育てしていくことを根気強く言葉や態度で表わしていくことが重要である。
保護者と施設の関係がよくなると子どもも安定していき、成長と発達の回復にも効果が現われてくるので、施設が保護者にとっても「ここへくるとほっとする」所として、心のよりどころとなるよう接することが親子関係の修復にも役立つのである。
|
| [2] |
カウンセリング
児童相談所と協議の上で、保護者へのカウンセリングを施設内で実施する場合においては、児童相談所の保護者を指導してきた担当職員と緊密な連携を図り、チームによって実施することが重要である。(第8章3を参照)
児童相談所で立てた保護者に対する指導計画に基づき実施することになるが、目標は、明確かつ具体的で、しかも実用的であることが望ましい。取り組むべき課題についてどのような行動をとれるようになったら課題達成なのか、具体的で実用的な目標行動について保護者と担当職員とで一致しておくことや、保護者が目標を確認でき、その有効性について納得できることが大切である。「子どもに対して適切な対応をとれるようになること」という抽象的な目標ではなく「体罰を用いないで子どものしつけを行うこと」といった具体的な目標を立てることが望ましい。
こうした明確かつ具体的な目標の設定により、保護者自身も課題への取り組みに対する自己評価ができ、課題をクリアーしたときの達成感や満足感を自己認識に基づき味わうことによって肯定的な自己イメージや自主性等の強化を図れるからである。
また、児童虐待防止法第12条に基づき子どもの健全育成の観点から子どもと保護者との通信や面会を制限している場合、児童相談所による指導に対する保護者の態度や施設での子どもの状況等が、通信や面会をさせるか否かの判断をする上でのポイントになることはいうまでもない。このため、施設職員は、親子関係の調整について的確に判断するためにも、児童相談所での保護者へのカウンセリングについて、児童相談所の担当職員と共通認識を持ちながら、前もって保護者に対する理解を深めていくことが大切である。
|
| [3] |
面会
| ア. |
面接についての基本的な姿勢
面会は家族との関係の維持または親子の再統合を図る上で、重要な役割を持つ。入所している子どもに面会にくる保護者は、何らかの形で子どもとの関係がうまくいかないことで傷ついており、勇気を出して出かけてきている。受容的関わりと共感的支持に努め、保護者と施設が補い合いながら協働して子育てに当たっていることを常に念頭において保護者を迎えることが大切である。
面会から面会の間の親子の空白を埋めるため、子どもの生活について話したり、絵画・工作などの子どもの作品を見せたり、身長・体重の増加を知らせたり、行事の写真を見せて説明し、持ち帰ってもらうなどのことを通して、共に育てているという実感を持てるようやわらかな接触態度が肝要である。
「今回の面会が、職員の対応いかんによって最後になるかもしれない。子どもと保護者との絆を危ういものにしてしまうかもしれない」という緊張感や危機感を職員が持ち、次の面会をイメージして保護者が来所しやすいような雰囲気が感じられるような対応が望まれる。
施設が、子どものみならず保護者を歓迎していることが感じられるように、また、いつでもどんなことでも子どもに対する問題は、ともに考え答えを出していく重要なパートナーであると保護者が感じられるよう配慮することが肝要である。加えて、保護者参加のレクリエーションへの呼びかけや施設の行事などを通し、面会そのものを関係改善の機会としてとらえたい。面会や外出等については児童相談所と施設が協議しながら、具体的対応策を決めていくことが必要である。
常に児童相談所の「援助指針」や施設の「自立支援計画」にそって、施設と児童相談所が緊密な連絡を取り合い、状況の変化に的確に対応しながら援助すべきである。状況は刻々と変化しており、それぞれの機関の役割と守備範囲に応じて連絡をとり、援助を推し進めていくこととなる。
また、面会時には、親子関係のあり方や子育て等についての助言なども押付けにならないように配慮しながら、会話の中に盛り込んでいくこともよい。
保護者と子どもの関係の変化を児童相談所、施設がともに正確に把握するとともに、柔軟に対応し、時には勇気ある英断も必要となる場合もでてくる。
何より子どもに必要なサービスを提供し、子どもの権利保障をしなければならないという基本理念にもとづき援助を行うことが大切である。
保護者が暴力をふるうなどの加害行為に及ぶことが予想される場合には、児童相談所が中心となって、児童相談所・施設・警察の三者が協議し、協力が得られる体制を事前に確保しておく必要がある。 |
| イ. |
面会、通信の制限
入所中の子どもに対する面会、通信の制限について、児童虐待防止法第12条において児童福祉法第28条の規定により家庭裁判所の承認の審判に基づき入所した子どもに対する保護者からの面会、通信については、虐待の防止及び虐待を受けた子どもの保護の観点から、児童相談所長又は施設長はこれを制限することができることとされている。
また、児童福祉法第28条によらない場合の入所についても、子どもが面会や通信を拒否したり、精神的に動揺したりあるいは保護者が子どもを威圧、脅迫したりする恐れがある場合には、施設長は、児童福祉法第47条第2項において、監護に関して入所している子どもの福祉のために必要な措置をとることができることとされている趣旨にもかんがみ、子どもの最善の利益を図る観点から、面会、通信を制限することについて、保護者の理解を得るよう努める、時には毅然とした態度で対応することが求められている。
また、平成16年児童虐待防止法改正法により、保護者が子どもの引渡しを求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待が行われること等が認められるときは、児童相談所長は、その子どもを一時保護できることとされた。また、この措置を採った場合は、児童相談所長は、速やかに、児童福祉法第28条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならないとされた。このため、保護者に対し説得を重ねたり毅然とした対応をとってもなお子どもの保護に支障をきたすと認められる場合などには、この手続きを採り、児童福祉法第28条に基づく措置の承認に関する審判を家庭裁判所に申し立て、措置を承認する審判がされた後に、再度入所の措置をとることとする。
なお、一時保護をしている子どもについて、家庭裁判所に対し児童福祉法第28条第1項の規定に基づく承認に関する審判を申し立てた場合は、家庭裁判所は、申立てにより、審判前の保全処分として、承認に関する審判が効力が生ずるまでの間、保護者について子どもとの面会又は通信を制限することができる。このため、保護者に対し説得を重ねたり毅然とした対応をとってもなお子どもの保護に支障をきたすと認められる場合などには、本保全処分の申立てを検討するのが適当である。
保護者が暴力を振るうなどの加害行為に及ぶことが予想される場合には、警察に対して、児童虐待防止法第10条に準じた対応を依頼するのが適当である。 |
|
| [4] |
一時帰宅
施設退所にいたるまでの間に子どもの面会、外泊体験を重ねたり、また親子関係の修復等のための合宿体験を行ったりという工夫をしているところもある。しかし、短期間でも親子分離していた子どもを家庭復帰させれば、家庭内は少なからず変化することは当たり前である。それが比較的長期間であれば、保護者や家族にとっても思いもかけない変化となって現れることがある。こうした大きな変化にとまどい、保護者も子どももストレスが高まって行動に現れ、それが虐待の再発につながることもある。
例えば、治っていた子どもの夜尿やおもらしが再発してしまい、保護者の叱責から虐待につながった例や、また家庭に戻ってみたら家族以外の見知らぬ男性や女性が一緒に生活していたことから、その者との人間関係から問題が発生してくる例もある。さらには、一時帰宅中の子どもが保護者からの虐待により死亡するという事件も発生しているのである。
このように、一時帰宅は、事例によって大変危険を伴うものとなってしまうこともあり、その時期の見極めは慎重に行う必要がある。
虐待を行っている保護者は多くの問題を抱えている上、子どもによっては虐待等に起因する発育、発達障害を残している場合もある。どちらにもそれぞれに応じた暖かな配慮が必要であり、一時帰宅を一つの試行として引き続き援助していくことが求められる。
帰宅時期の決定に際しては、保護者や子どもの具体的な会話や面会時の様子などを児童相談所に連絡し、懸念される事柄を率直に伝える必要がある。帰宅中でも行事等の連絡をするなど子どもと接触を持ったり、帰園当日の入浴時などにゆったりとした時間の経過の中で、家庭での出来事や身体観察などを行うのも一考である。一時帰宅時の様子をどう理解し、事を進めていくかは、職員の専門性と取り組みに対する姿勢が問われるのである。
虐待を受けた子どもの一時帰宅等への対応については、以上に加え、「被虐待児童の一時帰宅等へ適切な対応について」(平成13年12月12日雇児総発第58号・雇児福発第72号)を参照のこと。
|
| [5] |
施設行事等
施設行事への参加は、保護者と子どもの関係改善や関係を促進していくための重要な役割を果してくれるものである。
施設と保護者が協働して子育てをしているのだということを実感できる機会として行事参加をとらえるべきである。お祝い会や親子遠足、クリスマス会、卒業送別会など、各施設独自のプログラムを作成し、当日は、保護者にも役割を担ってもらうなど、施設業務に貢献してもらうことにより、その後好展開が図られることも多い。
親子の関係を改善するためには、一緒にいて楽しいことがあったとか、互いにいて助かったといった体験のつみ重ねが重要である。行事を通じ、親としての役割を果たす中で親としての喜びが実感出来るよう工夫することが大切である。学校との事前調整の上、授業参観や懇談会、運動会などへも保護者の参加を求め、子どもへの理解を深めてもらうことも必要となろう。 |
|
| (7) |
保護者の強引な引取要求への対応をどうするか
本章1(6)「保護者の強引な引き取り要求にどう対応するか」を参照されたい。 |
| (8) |
退所する子どもとその保護者への援助はどうあるべきか。
本章1(5)「措置解除の適否判断と解除時の子ども、保護者等への援助はどうあるべきか」を参照されたい。 |
| (9) |
退所後のアフターケアをどう行うか
施設入所している子どもに対する支援は、児童自立支援計画に基づき、入所から退所後までを見通して継続的・総合的に行われる必要がある。とりわけ虐待を受けた子どもの退所後の援助は児童相談所との密接な連携のもとに継続的に行われなければならない。
退所にいたるまでの期間、虐待を行っていた保護者に対して、家庭環境の調整、とりわけ親子関係の調整に援助してきた結果、保護者も心理的に安定して、虐待の再発の危険がないと診断されれば家庭復帰が可能になる。もちろん子どもも保護者に対して、依存できる信頼関係が回復していることが前提であることは言うまでもない。事例によっては、親子分離によって時間の経過を得たことや、空間的な距離ができたことによって、保護者、子どもそれぞれが自己を振り返るよい機会になり、関係が修復されることがある。もちろん自立支援計画に基づいて、虐待を行っていた保護者、虐待を受けた子どもの両者への根気強い援助の成果によるものである。
また、平成16年児童福祉法改正法により、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設について、施設の業務として、退所した者について相談その他の援助を行うこと(アフターケア)が明確化された。
従来から、施設においては、退所した子どもが社会の中で様々な問題にぶつかり相談等に訪れたときには助言等を行ってきており、今般の改正により明確化されたアフターケアの内容も、このような援助が想定されている。
さらに、平成16年度からは、家庭支援専門相談員を全児童福祉施設に配置しており、施設においては、このような職員も活用しながら、入所している子どもに対するケアに支障が生じない範囲でできる限り、退所した子どもに対するアフターケアを行うことが必要である。
| [1] |
地域の関係機関との連携を十分に図ること
児童相談所との連携は当然であるが、それだけでは必ずしも十分ではない。子どもが通所、通学する保育所や幼稚園・小学校・中学校等の学校をはじめ地域の民生・児童委員(主任児童委員)、保健所、福祉事務所(家庭児童相談室)等との連携を十分に図ることが大切である。そのためには児童相談所を介して連携方策を見いだすことが必要である。
虐待の再発を防ぐために、早期発見、早期対応が最も重要である。ただし、密室化している家庭は早期発見が困難な場合が多く、しかも様々な問題を多く抱える虐待問題の対応には、各関係機関の緊密な連携が不可欠である。関係機関が一同に会し、情報交換を行うとともに共通の認識に立って、それぞれの役割分担を協議する等、各関係機関が連携しながら早期発見並びに効果的対応を図ることが極めて重要である。
施設を退所した子どもに対し、相談や定期的な訪問等を行い子どもを見守るとともに、家族等に対しても精神的な支援等を行う。虐待が再発した場合の早期発見、早期対応を実現するためには、要保護児童対策地域協議会を活用することも有効と考えられるので、協議会との連携を確保しつつ、施設を退所した子どもが新しい生活環境の下で安定した生活を継続できるように必要な調整を行う。
|
| [2] |
家庭復帰後、転居した際の移管についての対応
家庭復帰後、時には転居する場合が起きてくることがある。それには意図的に転居する場合と就労の事情によって転居する場合とがある。そうした時は、例えば、事例を所管していた児童相談所や市町村、要保護児童対策地域協議会の要保護児童対策調整機関に連絡をとり、連携を図りつつ対応してきた関係機関等に連絡してもらうとともに、児童福祉法第25条等に基づき、転出先の自治体を管轄する児童相談所や市町村に通告してもらい、ケースを移管することが必要である。その際には、これまでの対応状況など必要な情報を提供することが必要である。
しかし、とくに公的関与を好まない保護者が意図的に転居するとなると、消息不明になる危険性は大きい。保護者のプライバシーの問題はあるにしても、子どもの生命・安全が優先されることから、情報収集の方策を工夫していかなければならない。
平成11年中に保護者の他県への失踪により、転居先での対応が手遅れになった例があったことから全国の児童相談所間で児童虐待に関する情報交換を行い、円滑な初期対応が図れるように児童相談所CA(Child Abuseの頭文字)情報連絡表に基づく情報連絡システムが実施された。
情報を得た転居先の児童相談所(ケース移管を受ける児童相談所)は、元の児童相談所に情報の確認をするとともに地域の中で関係機関とネットワークを組むなど迅速な対応を図らなければならない。
また、要保護児童対策地域協議会を活用し、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしまった子どもや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見し、必要な支援を行うことも有効と考えられる。 |
|
| (10) |
施設内虐待の対応はどうあるべきか。
児童福祉施設の長は、監護・教育・懲戒に関し子どもの福祉のため必要な措置を採ることができるが、懲戒に関する権限については、あくまでも子どもの健全な育成のために認められているものであり、決して濫用されるようなことがあってはならない。
もとより、児童福祉施設の職員は、入所している子どもに対して、児童虐待防止法に規定する児童虐待その他子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないものであり、体罰や言葉による暴力も正当化されるものではない。特に、体罰や言葉による暴力は、大人に対する不信感を受け付け、子どもの生涯に残る心の傷になりかねないものであるだけでなく、子ども自身による暴力を正当化・肯定することにもつながるものである。
また、児童福祉施設の職員から虐待を受けた子どもは、児童福祉法第25条の通告の対象となるものである。
入所している子どもやその保護者から、懲戒に係る権限の濫用や虐待等の訴え等があったときや児童福祉法に基づく通告を受けたときには、あくまで客観的事実の把握に努め、事実に基づく対応をしなければならない。
その際、その子どもの最善の利益に配慮して適切なケアを行うこととし、必要に応じてその子どもの一時保護、措置変更を行うとともに、援助上の問題について施設に対し技術的助言、指導を行う。また、再発防止の観点から、必要に応じて児童福祉施設に対する指導権限を有する本庁と連携を図りつつ対応することが必要である。
施設内虐待においては、虐待者を特定しにくい場合もある。例えばある子どもに不審なアザがあった場合、次のような推測が成り立つからである。
| ア |
事故によるもの |
| イ |
他児によるいじめや暴行によるもの |
| ウ |
他児との喧嘩によるもの |
| エ |
本児自身による自傷行為 |
| オ |
職員による身体的虐待 |
それぞれの可能性の高さはその子どもの特徴、置かれた立場、環境などによって異なってくる。その子どもの行動特性から、いくつものことを同時に推測させるような子どももいる。したがって安易な憶測や判断は慎むべきであり、虐待の再発防止に向けた取り組みを強化するなど、何よりも子どもの立場に立った子どもの権利擁護を最優先すべきである。
仮に不審なアザなどを発見した場合、数人の職員で確認の上、発見した日時、傷の状態、箇所などの記録を残し、可能な場合には、写真に撮っておくことも必要である。また、できる限り速やかに施設長をはじめ他の職員に報告することや、会議等で問題提起をすることが大切であり、重大な問題として表面化させることが虐待の防止に結びつくからである。
もし虐待が疑われるような不適切な場面を発見した場合には、子どもの安全を確保するために制止するとともに施設長に報告することが必要である。
虐待であった場合、報告を受けた施設長は、虐待を受けた子どもに対する心理的なケアをはじめ、そのような事態が二度と起こらないよう速やかに対策を講じなければならない。
また、子どもや保護者及び関係機関に謝罪や報告をすることは言うまでもないが、虐待の内容や程度によっては、子どもの意向等を尊重しつつ、緊急一時保護を行うなど安心できる生活の場を確保するといった児童相談所等の関係機関との連携による対応が必要である。
虐待は身体的虐待に限られたことではない。職員が気づかない内に言葉の暴力による心理的虐待を行っている場合もあり、施設内虐待については十分な注意と配慮が必要である。
施設内虐待は起こってはならないことであるが、起こりうることを十分認識すべきである。虐待を防止するためにも、施設における施設内虐待防止の姿勢を明確に打ち出すとともに、施設全体における虐待防止の雰囲気づくり、研修などによる職員の資質の向上、職員間での相互チェック、ケース・カンファレンス、スーパービジョン、援助に対する自己評価システム、苦情解決システムなどにより、施設内虐待の未然防止に努めることが何よりも重要である。 |
| (1) |
里親委託時における子ども、保護者への対応はどうあるべきか
里親は、虐待を受けた子どもの援助において重要な社会資源である。個別的で、親密な人間関係を保障する里親養育は、虐待を受けた子どもの援助において大きな可能性を有している。このため、平成14年度から、虐待を受けるなどして専門的なケアが必要な子どもを対象とする「専門里親」や、3親等内の親族を里親とする「親族里親」を創設するなど、制度の充実を図っており、里親養育のより一層の活用が期待されている。
一方で、里親養育には、その特徴ゆえの困難さもある。個別的であるがゆえに施設のように各種専門職員の連携、援助が期待しにくい。また、親密な人間関係ゆえに里親と子どもの関係がうまくいかなかった場合、委託された子ども、里親ともに傷が深いものとなる。
このため、里親委託に当たっては、下記の点に留意する必要がある。
| [1] |
子どもや保護者等の意向、意見を十分尊重するとともに、これまで育んできた人間関係や地域環境への配慮などケアの連続性の確保に配慮しつつその子どもに最も適合する里親の選定に努める。 |
| [2] |
子どもを紹介するに当たって、子どもの状況(性格や行動、発達状態等)を具体的に説明するほか、子どもの養育に参考となるよう必要な範囲で、子どもの生育歴、里親委託に至る経緯、家族の人間関係、児童相談所の援助方針等を具体的に説明する。 |
| [3] |
委託前における里親と子どもの面会を十分に行うなど、両者の関係づくりに十分配意する。 |
| [4] |
里親委託を決定する際は子どもの意向を確認するとともに、里親宅での生活や実親との面会等について懇切に説明し、不安の軽減を図る。
また、子どもが有する権利や子どもが守らなければならない約束などについてわかりやすく説明する。そのためには、大阪府が作成した「子どもの権利ノート」のようなものを作成して活用するのも一つの方法であろう。 |
| [5] |
虐待を受けた多くの子どもが、はじめは不安や緊張で「いい子」であるが、慣れてくるにしたがって注意獲得行動や過度の依存、退行現象、攻撃的行動等を現しやすい。
また、虐待を受けた子どもは、大人との関わりの中で、いらだちを引き出しやすいなどの傾向が認められる。
このような虐待を受けた子どもに現れやすい行動特徴等について里親に十分説明し、理解を得ておくとともに、もしそのような行動が現れた場合には早めに児童相談所に相談するよう周知を図ることが肝要である。 |
| [6] |
保護者との面会のあり方や引取り希望への対応等について綿密に打合せを行う。特に、約束外の面会希望や引取り希望については里親だけで対応したり判断したりすることは絶対に避け、児童相談所の指示を仰ぐよう周知を図る。 |
|
| (2) |
里親への支援、連携をどう図るべきか
里親は子どもにとって重要な社会資源であり、相互の密接な連携を図ることは言うまでもないが、他方里親はクライエントとしての側面も有する。特に、虐待を受けた子どもの場合、1で述べた問題行動等が出やすいので、児童相談所や市町村、施設による里親援助、児童相談所等と里親との緊密な連携がとりわけ重要となる。
以下、里親委託後の里親への援助、里親との連携上の留意点について述べる。
| [1] |
里親に対し、自立支援計画に加え、委託の理由や経緯、子どもや保護者の態様や必要とする援助の内容等、里親がその子どもの養育を適切に行うために必要な資料を送付する。 |
| [2] |
保護者の動向や子どもの状況等について情報交換を密にし、共通認識を図るとともに、役割分担を行うなど、一体的な援助活動を心がける。 |
| [3] |
児童相談所の担当者や市町村の保健師等が定期的に訪問したり、乳幼児健康診査の場を活用して、里親の相談に応じるとともに、子どもの問題行動等の早期発見、早期対応に努める。特に、子どもに問題行動等が出現した時や里親の不安等が強いと思われる時には訪問頻度を増やす等、柔軟な対応を図る。 |
| [4] |
子どもに問題行動等が出現した場合、里親は「自己の至らなさからそうなった」と自罰的心情を抱いたり自信喪失に陥ったりする場合がある。このような時には、受容的、共感的態度に心がけ、必要な援助を行う。また、必要に応じて子どもに対する心理検査や医師の診察、訪問や通所による心理的ケア等について検討する。 |
| [5] |
子どもの問題行動等への対応について児童相談所が支援を行っても改善されず、子どもの問題行動がエスカレートしたり、里親が子どもに対して拒否的感情を募らせている場合は、一時保護等による冷却期間を設けたり、どうしても事態の改善が期待できないと判断される場合は委託解除を検討するなど、柔軟な対応を行う。なお、委託後、何らかの事情で他の里親へ委託するなど、措置の内容を変更する場合には、子どもにとって精神的負担が大きく、心的外傷体験になる危険性があることから、子どもへの影響に十分配慮しつつ行うことが必要である。 |
|
| (3) |
里親を支援するための主な取り組み
里親の専門性の確保や精神的負担の軽減などを図るために次のような支援を行うことが必要である。
| [1] |
里親に対し基礎研修を実施し、里親制度や子どもの養育に関する基礎的な知識・技術の修得を図る。
また、専門里親になることを希望する者に対しては、より専門的な研修を実施し、子どもの養育に関する知識・技術の向上を図る。(里親研修事業) |
| [2] |
児童相談所等に里親対応の職員を配置し、里親から寄せられる子どもの養育や里親自身についての相談に応じる。(里親養育相談事業) |
| [3] |
里親が児童相談所等に集い、児童福祉司のOB等の援助のもとに子どもの養育について話し合う場を設け、里親相互の交流を通じて、里親の養育技術の向上、精神的負担の軽減等を図る。(里親養育相談援助事業) |
| [4] |
里親の養育負担を軽減するため、児童相談所において研修の上登録された者を、里親からの援助の求めに応じて里親家庭に派遣し、生活支援(家事や養育の補助等)や相談支援(軽度な養育相談等)を行う。(里親養育援助事業) |
| [5] |
里親家庭が一時的な休息のための援助(レスパイト・ケア)を必要とする場合には、乳児院、児童養護施設等又は他の里親を活用して、当該里親家庭に委託されている子どもの養育を行う。(里親の一時的な休息のための援助) |
|
| (4) |
虐待を受けた子どもを受託している里親への支援をどう行うか
| [1] |
児童相談所と里親との信頼関係
委託された子どもが様々な「問題行動」を起こしたりすることがある。それに対して里親が混乱したり不適切な対応をしている場合、児童相談所は速やかに関わらなくてはならない。
問題の解決に向けて重要なポイントは、里親が「問題行動」をどのように理解し、どの程度受容できるかである。里親が「問題行動」を理解し受容するためには、里親自身が変わらなくてはならない場合もあり、多大な負担をかけることにもなる。
まず、家庭内(家族関係;里父母との関係、他の子どもとの関係など)の変化を求めているサインではないかという判断がある場合は、夫婦面接や家族面接が家族変化のための有効な手段となる。
また、必要な場合は、地域の資源を積極的に活用する。身近な相談相手としては市町村児童福祉担当者、福祉事務所(家庭児童相談室)、民生・児童委員(主任児童委員)、保健所や市町村保健センターの保健師等がある。この場合、児童相談所が中心となって連絡を密にし、虐待を受けた子どもを受託している里親家庭についての共通認識を関係者に十分持ってもらうことが前提である。
また、先輩里親(虐待を受けた子どもの養育経験者)との交流が、里親にとっての大きな支えになるので、里親同士が互いに触れあえる機会を児童相談所が積極的に保障していくことも必要である。
さらに里親制度の認知にも努めることが重要である。里親制度については、残念ながら広く一般に認知されるまで普及されていないのが現状である。このため、近隣に対して子どもの人権に配慮しつつ説明することがよいであろう。
児童相談所は、里親に同行して、里親制度や委託した子どもの状況などを学校に説明するとともに、実名にするのか通名にするのかなど、子どもがスムーズに学校に適応できるよう配慮ある対応を依頼することが必要である。
子どもが引き起こす行動上の問題などに対しても、その原因などについて学校側に理解してもらい、里親に過度な負担がかからないよう関係諸機関が連携して対応できるような体制を整えておくことが重要である。
いずれにしても、これらのことは児童相談所と里親との間に十分な信頼関係がなければ成り立たないことを銘記すべきである。
|
| [2] |
養育上の視点
| ア. |
初期
一般に委託当初は、親子関係も浅く、なじみのない環境の中で、子どもは想像以上に緊張し、いわゆる「良い子」になりがちである。それまでの生活の中で体験してきたしつけや規則を守ろうという形で現われることが多い。この時期には里親家庭内の大人が徹底して子どもを受け容れることが重要である。
特に虐待を受けた子どもの場合、その表現が固すぎたり、過剰だったりする。無理に悪いところを矯正するような対応をすると緊張が長期化し、親子関係を築く妨げになる。
また、この時の子どもの姿を本来の姿だと思うのは危険であるので児童相談所としては特に委託直後は頻繁に往き来しなくてはならない。この「良い子」の状態が長く続く場合は、子どもが里親家庭で緊張し続けていると考えられるので注意を要する。
この時期に児童相談所が状況把握するポイントとして
| ・ |
食事、入浴、睡眠等基本的な生活を誰とどのように送っているか |
| ・ |
排泄や着脱衣はどうしているか |
| ・ |
問題があった場合、それを誰が受け止め、誰がどう対応しているか |
| ・ |
夫婦、家族の協力の状況について |
| ・ |
家族の中で、子どもが大切にされている雰囲気やエピソ−ドはどんなものか |
| ・ |
家族のコミュニケ−ションのあり方に、年齢や委託日数を考慮して、自然な感じがあるか |
| ・ |
子どもの発達に応じた部屋の雰囲気があるか |
| ・ |
ペットがいる場合、子どもとペットとの関係はどうか |
| ・ |
里親が子どものことを語る時、可愛いいという感じが伝わってくるか |
| ・ |
地域や学校に子どもをどのように紹介しているか |
| ・ |
子どもが安心していられる決まった居場所があるか |
等々が挙げられる。 |
| イ. |
中期(混乱期)
子どもが里親家庭に慣れるに従い、個人差があるものの、手のかからない「良い子」から手をかけさせる「悪い子」や「赤ちゃん」に変わっていく。ある年齢まで退行していく現象は「赤ちゃん返り」と言われ、新しい親、特に里母との関係を確認するために、本来の養育経験をやり直しているものと考えられている。そして、子どもなりに満たされると自然に年齢相応のところに戻ってくるものである。
これはあるがままの自分をどこまで受け入れてくれるのか無意識のうちに試しているということである。そこで子どもは親の愛情を確認するために、親の一番嫌がることをしがちであり、特に虐待を受けた子どもには行動の逸脱や激しさが目立つ。
これらの特徴について列挙すると
| ・ |
里母から片時も離れず、里父になつかない |
| ・ |
反抗的な態度をとり続ける(自己中心的で叱っても効果がない状態) |
| ・ |
自分を表現しない(何を考えているかわからない) |
| ・ |
嘘をつく |
| ・ |
里親以外の大人に甘えたり、他の家に行き食事等を欲しがる |
| ・ |
過食が続く |
| ・ |
排泄、着脱衣、あいさつ等できていたことができなくなる |
| ・ |
夜泣きや夜尿が続く |
| ・ |
教室や友人の家から物を持って来たり、里親宅からお金を持ち出す |
| ・ |
同年齢の子どもに乱暴する、噛みつく |
等々が挙げられるが、これらの行動は環境の大きな変化による心因的なものが大半である。しかし、一部には器質的な原因を内在している場合もあるので、児童相談所は十分な観察をしなければならない。
この時期に里親が子どもの状態をどのように受け止め、どのように対応するかによって、状況が変わる。里親が振り回されて混乱したり、しつけを急いだりするとさらに「悪い子」になるという悪循環に陥ることとなる。
児童相談所はこの時期に頻繁に訪問して(内容によっては心理職員が関わっての通所も考えられる)問題を共有の上、一緒に問題を乗り切る姿勢をとらなくてはならない。
ここで里親が陥りやすい状態として
| ・ |
子どもに振り回され、心身ともに疲れ果てる |
| ・ |
受託前に抱いていた子どものイメ−ジと、現実との違いに失望する |
| ・ |
「良い子にしなければ」としつけが厳しくなる |
| ・ |
溺愛したり、拒否的になったりと、片寄った養育姿勢をとる |
| ・ |
「子どもが急に変化するのではないか」と過度の期待感を持つ |
| ・ |
養育方針の違いで里親夫婦の葛藤が新たに起きる |
| ・ |
祖父母と同居している場合、関わり方について互いに批判的になる等、世代間の葛藤が表面化する |
| ・ |
実子がいる場合、実子との違いに戸惑い、愛情が公平に持てないと悩む(二人目以降の里親委託でも同様である) |
等々がある。
この時期を乗り越えるために児童相談所はいろいろな形態で援助を行うが、その場合の留意点は以下のとおりである。
| ・ |
里親はかくあるべきという先入観を持ったり、実子でもこの程度のことはある(問題を大げさにとらえているのではないか、問題にする里親こそ問題)という視点で臨むことは避ける |
| ・ |
里親も子どもも変化するものであるという視点で、焦らず、問題を一緒に解決していこうという姿勢を持ち続ける |
| ・ |
育てていく中での心配や不安の訴えが「里親失格」や(余程のことがない限り)子どもを引き離すことにつながるのではないかという不安を里親が感じないよう配慮する |
| ・ |
児童相談所が行うグル−プ指導や里親会の活動に積極的に誘い、里親同士のつながりが持てるように配慮する |
このように里親と児童相談所が協調しても「問題行動」が軽減しなかったり、逆にエスカレ−トし続けるようであれば、里親家庭への不適応行動と考えて、援助の再検討をする必要がある。 |
| ウ. |
後期(安定期)
安定したかどうかは、「問題行動」が落ち着くということ以外に、次の点を目安にする。
| ・ |
子どもが安心してくつろいでいる |
| ・ |
子どもが自由にふるまえる |
| ・ |
子どもが家族全員に親愛感を持つ |
| ・ |
子どもを含め、家族全員の表情がよい |
| ・ |
里親の言動に自信(安定感)が感じられる |
| ・ |
混乱期の大変さを理解して、里親なりにその意味をつかんでいる |
| ・ |
理屈抜きに子どもを可愛いと感じている雰囲気がある |
|
|
|
| (5) |
里親による懲戒権濫用の禁止等
平成16年児童福祉法改正法により、里親についても、児童福祉施設の長と同様に、監護・教育・懲戒に関し子どもの福祉のため必要な措置を採れることが明確化されたが、懲戒に関する権限については、あくまでも子どもの健全な育成のために認められているものであり、決して濫用されるようなことがあってはならない。
もとより、里親は、委託されている子どもに対して、児童虐待防止法に規定する児童虐待その他子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないものであり、また、里親から虐待を受けた子どもは、児童虐待防止法第6条の通告の対象となるものである。
委託されている子どもやその保護者から、懲戒に関する権限の濫用や虐待等の訴え等があったときや児童虐待防止法に基づく通告を受けたときには、客観的事実の把握に努め、事実に基づく対応をしなければならない。
その際、その子どもの最善の利益に配慮して適切なケアを行うこととし、必要に応じてその子どもの一時保護、措置変更を行うとともに、養育上の問題について里親に対し技術的助言、指導を行う。また、再発防止の観点から、必要に応じて里親に対する指導権限を有する本庁と連携を図りつつ対応することが必要である。
なお、都道府県等が行った指導又は助言について、「里親が行う養育に関する最低基準」第13条第2項により、里親は必要な改善を行わなければならないことが明示されている。 |
図9−1
福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの概要図
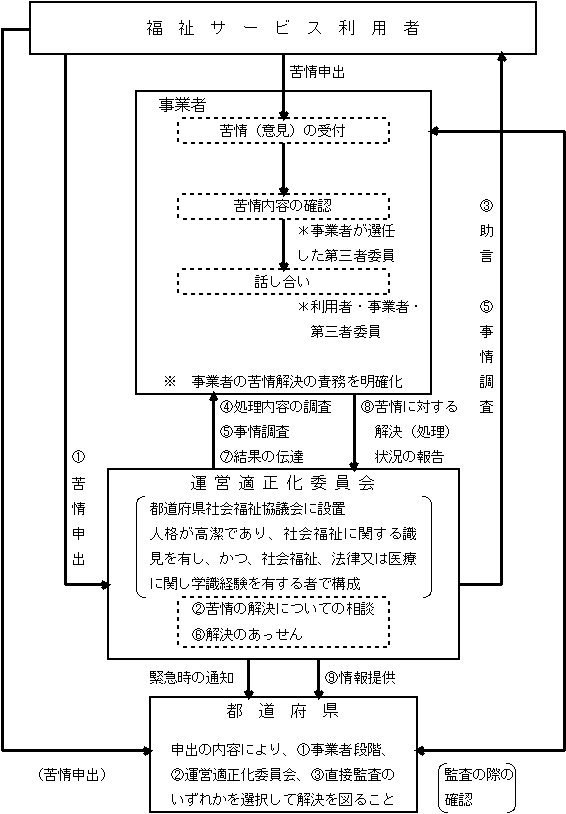
(別添9−1)
自立支援計画票
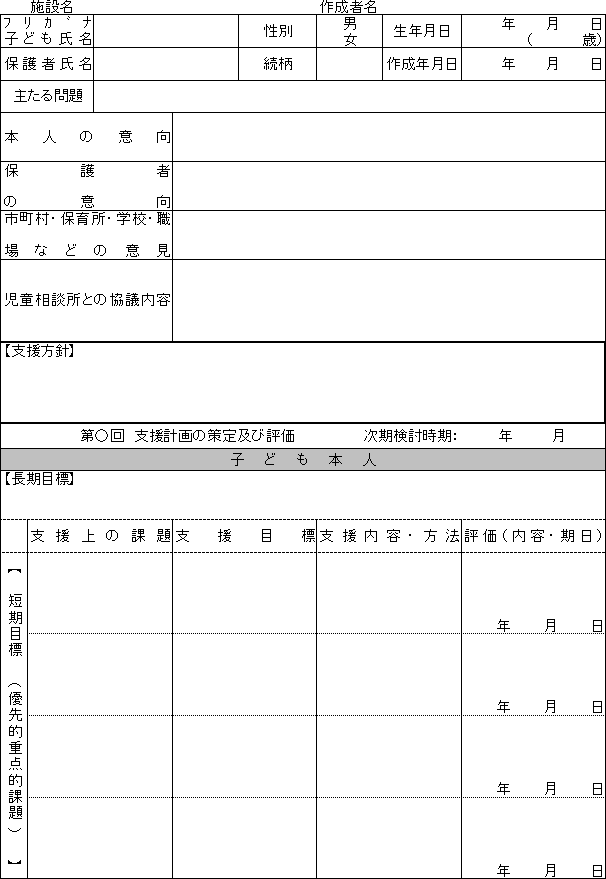
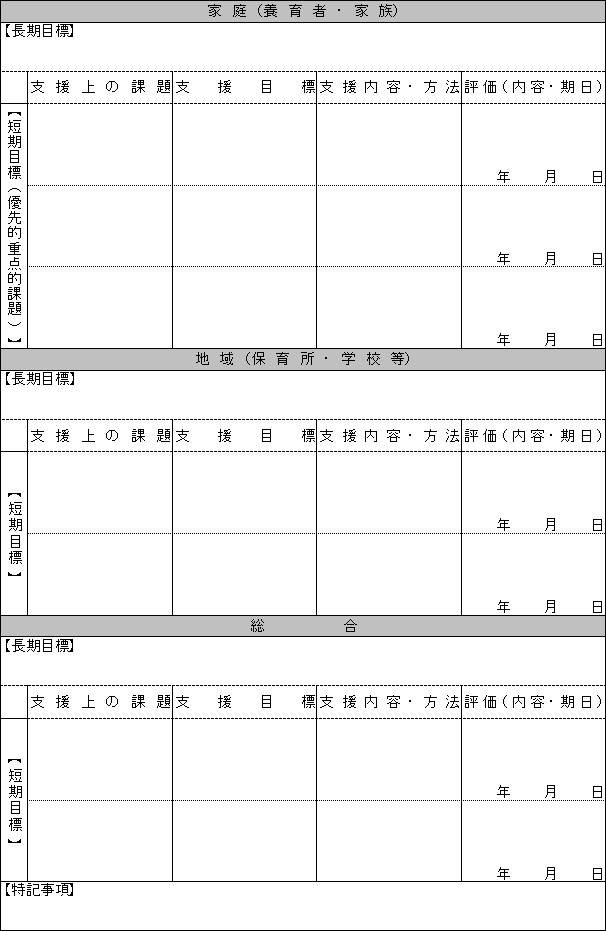
自立支援計画票(記入例)
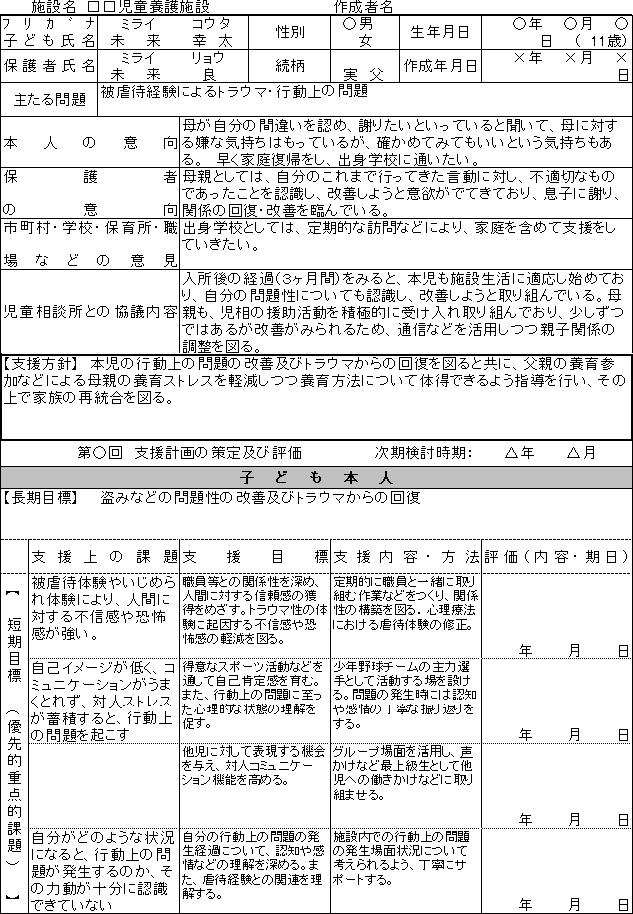
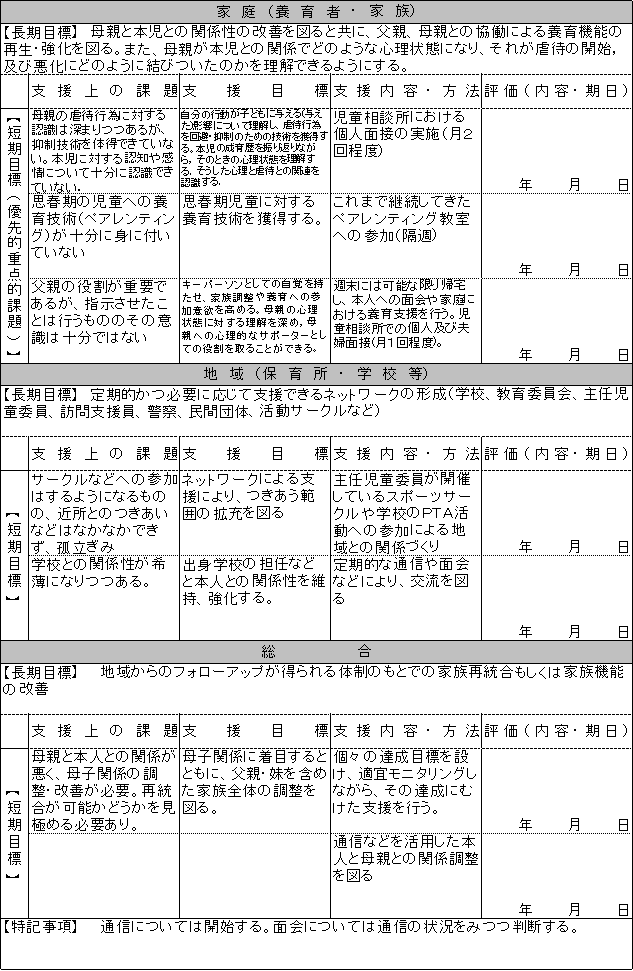
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 子ども虐待対応の手引きの改正について(平成19年1月23日雇児発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知) > 子ども虐待対応の手引き > 第9章 援助(親子分離)