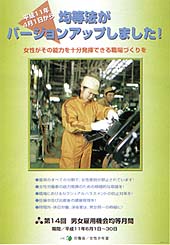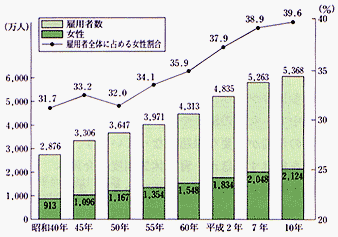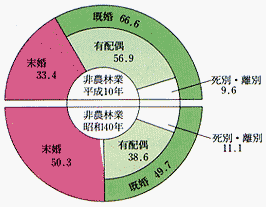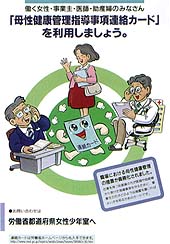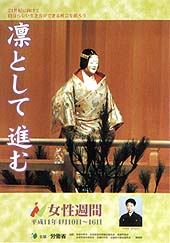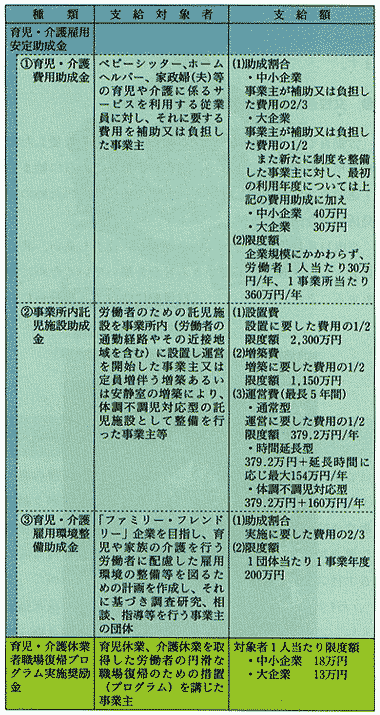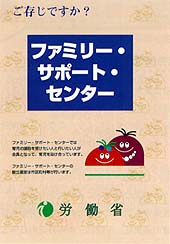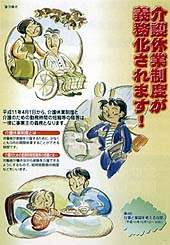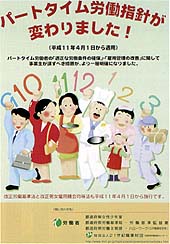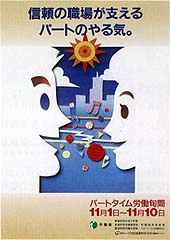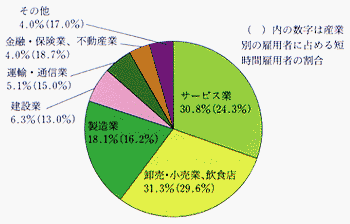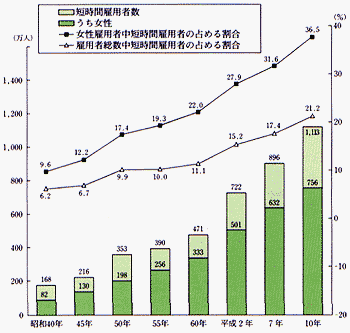働く女性が性により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するとともに、働きながら安心して子供を産むことができる環境をつくることは、働く女性のためだけでなく、少子・高齢化の一層の進展の中で、今後引き続き我が国経済の活力を維持していくためにも、大変重要な課題です。
このような課題に適切に対処し、雇用の分野における男女の均等な取扱いの一層の確保を図るため、改正男女雇用機会均等法が、平成11年4月1日から全面施行されています。
(イ)個別紛争の解決援助及び適切な行政指導の実施
| |
労働省では、労使をはじめ社会一般に対して、改正法の周知徹底を図るとともに、事業主や女性労働者からの相談を受け付け、女性労働者と事業主の間の個別紛争について解決の援助が求められた場合には、女性少年室長の助言、指導、勧告及び機会均等調停委員会の調停による紛争の迅速かつ円滑な解決を図っています。また、企業において均等法に沿った雇用管理が確実に実現されるよう、法に基づく指導を積極的に展開しています。
女子学生の就職問題に対しては、女子学生が男子学生に比べ均等法上問題となるような不利な取扱いを受けることなく就職活動が進められるよう、女性少年室において年間を通し、相談に応じるとともに、問題のある企業に対しては指導を行っています。
改正均等法をはじめ男女雇用機会均等への理解を深めるための機会として、特に、6月の「男女雇用機会均等月間」において効果的な広報啓発活動を実施しています。 |
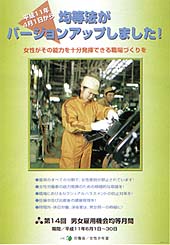 |
| 第14回「男女雇用機会均等月間」ポスター |
| |
| 雇用者数の推移(全産業) |
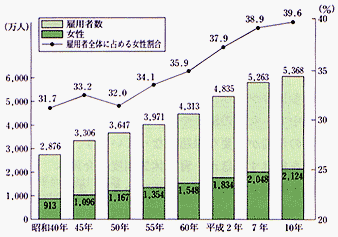 |
| 資料出所:総務庁統計局「労働力調査」 |
| |
| 女性雇用者の既婚率(単位%) |
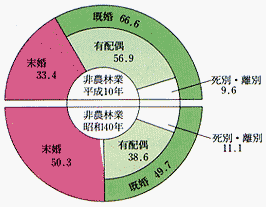 |
| 資料出所:総務庁統計局「労働力調査」 |
(ロ)職場におけるセクシュアルハラスメント防止のための取組
| |
職場におけるセクシュアルハラスメントに関する女性労働者からの相談にていねいに対応するとともに、均等法に照らし問題がある場合には、企業に対し適切な指導を行っています。また、相談者が精神的ダメージを受けているような場合については、室に設置されるセクシュアルハラスメントカウンセラーを活用し、必要な助言、指導を行っています。
さらに、企業がセクシュアルハラスメント防止対策を効果的に実施することができるよう、具体的取組のノウハウを提供する講習会の実施等の事業を行っています。 |
| |
(ハ)母性健康管理対策の推進
| |
女性労働者が妊娠中及び出産後も安心して健康に働くことができるよう、平成10年4月から事業主の義務とされた母性健康管理の措置について、事業主、女性労働者、医師等に対し、周知徹底を図っています。特に、事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるようにするため、医師の指導事項を事業主に明確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進しています。 |
| |
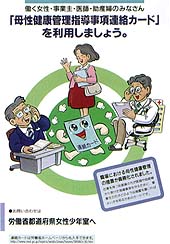 |
| 「母性健康管理指導事項連絡カード」ポスター |
(ニ)女性労働者が能力を発揮しやすい環境整備の促進
| |
男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目指し、女性労働者の能力発揮を促進する企業の積極的取組(ポジティブ・アクション)を促すため、各事業所において選任されている機会均等推進責任者の活用を図るとともに、企業の具体的取組を援助しています。 |
| |
(ホ)女性の地位向上のための施策の推進
| |
真の男女平等を推進していくためには、意識面で今なお根強く残っている男女の能力や役割に対する固定的な考え方を改めていくとともに、女性が男性に比べて不利な立場におかれているという状況を改善していくことが重要です。このため、平成11年度においては、働く女性に対する支援事業を総合的に展開するとともに、啓発活動を行い、あらゆる分野への女性の参画の促進に努めます。 |
| |
| 1) | 「女性の歴史と未来館(仮称)」を通じた働く女性の能力発揮支援事業の展開 |
| |
| 「女性の歴史と未来館(仮称)」において、女性の能力発揮のためのセミナーや相談、女性起業家支援、女子生徒の適切な職業選択のための情報その他働く女性に関する情報の提供等を行い、働く上で男性に比べて困難な状況に直面することが少なくない女性の能力発揮を支援します。 |
| |
| 2) | 女性起業家の支援施策の推進 |
| |
| 近年、就労機会が多様化する中で、自ら事業を起こすことを希望する女性が増加しつつあります。しかし、女性は、起業、事業運営に役立つ職業経験が少ないなど、困難に直面するケースが少なくありません。特に、育児等により職業生活を中断したことによるブランクが、起業、事業経営に当たっての困難をもたらす場合があります。
このような状況を踏まえ、女性起業マニュアルの作成等起業を希望する女性等を対象に起業家支援セミナー、コンサルティング及び起業家交流会等の支援施策を展開しています。 |
| |
| 3) | 女性週間(4月10日〜16日)の実施 |
| |
| 労働省では、我が国の女性が初めて参政権を行使した昭和21年4月10日を記念して、昭和24年以来この日に始まる1週間を「女性週間」と定め、女性の地位向上のための啓発活動を全国的に展開しています。
平成11年は男女双方が互いを理解し、協力しあい、共に自分らしい生き方を実現できる社会を築いていくために努力することを目標として、「21世紀に向けて 自分らしい生き方ができる社会を創ろう」をテーマとして実施しました。また、静岡県と共催で、全国会議を開催しました。 |
|
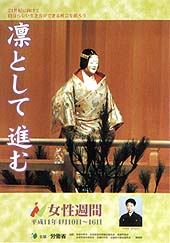 |
 |
平成11年「女性週間」
ポスター |
平成11年「女性週間」
全国会議 |
|