官民連携した雇用情報システム(仮称)の政策効果について
| 1 | システム構築の基本的考え方 | |
| 官民連携した雇用情報システム(仮称。以下「システム」という。)は、公正かつ効率的な労働市場の形成に寄与するものである。すなわち、求職者から信頼できる参加機関の保有する情報へのアクセス機会の増大をもたらすことにより、参加機関の利用促進を図るとともに、仕事を探す労働者(求職者)の失業(求職)期間の短縮と労働者を採用する企業の円滑な人材確保を可能とするものである。
|
||
| 2 | 求職者の効率的な求人探索の可能性 | |
| システムが構築される場合、利用者(求職者)はシステムを活用して、信頼できる参加機関が保有する求人情報を共通情報として、自らが求める求人を検索することが可能となり、当該求人を保有する参加機関へのアクセスが容易となる。これにより、利用者の求人情報への接触の機会が増大し、早期の就職が可能となる。 これに対し、システムがない場合、求職者は、自らが求める求人がどこにあるのかわからないまま、自分の力で民間機関のホームページアドレスを探し出し、各機関のホームページにアクセスして検索を行ったり、各機関に直接訪問したり、電話による問い合わせを行ったりする等により求人情報を探すこととなる。このため、システムが構築される場合に比し、求人情報を探すのに相当な手間がかかり、場合によっては情報が発見できないこともある。 さらに、システムにおいて求職者情報が提供できるようになれば、一層利便性が高まる。 (参考) |
||
[システム構築後]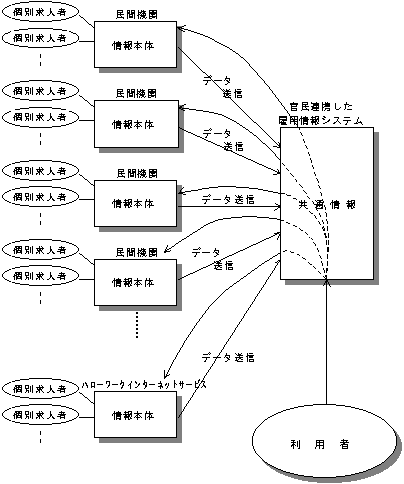 |
[システムがない場合]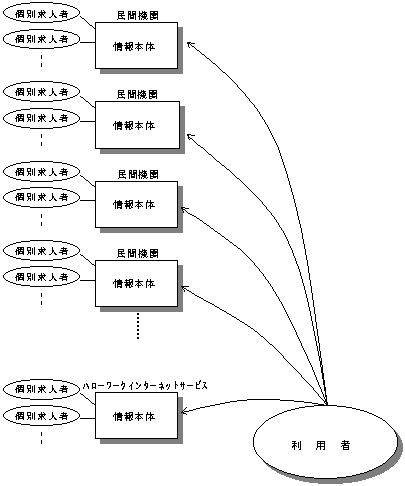 |
| 3 | 企業の人材確保の円滑化 | |
| 個別の求人企業が利用する労働力需給調整機関がシステムに参加した場合、より多くの求職者が効率的に当該求人企業の求人情報にアクセスできるようになる結果として、これまで接触がなかった層も含めて選考対象とした上で、かつ、早期に、選考、採用を行うことが可能となる。 さらに、システムにおいて求職者情報が提供できるようになれば、一層利便性が高まる。 | ||
| 4 | 国民生活・経済上の効果 | |
| システムの構築による労働力需給のマッチング機能の強化は、勤労権や職業選択の自由を保障する憲法の規定(第22条、第27条)を具体化するものと位置づけることができるが、さらに、国民生活、国民経済の観点からみた場合、次のような意義があると考えられる。 | ||
 | 個々の労働者(求職者)の早期再就職による生活の安定により、労働者やその世帯のモラールの向上をもたらし、国民生活全体の安定に寄与する。 | |
 | 職務に適う人材の確保が円滑に進められるようになることにより、企業活動が活性化し、ひいては国民経済の安定に寄与する。 | |
 | 失業期間中に要する社会保障経費(失業給付費)の削減を可能とするのみならず、社会保険料さらには税金を納付する労働者層の増大に寄与し、社会保障制度全体の適切、健全な運営に資する。 | |