| 3階級の場合 | 5階級の場合 | ||
|---|---|---|---|
|
|
年齢調整死亡率が47都道府県平均から統計的 にみて低いと判断される県 (47都道府県平均から標準偏差以上低い県) 年齢調整死亡率が47都道府県平均から統計的 にみて同程度と判断される県 (47都道府県平均から標準偏差以内の県) 年齢調整死亡率が47都道府県平均から統計的 にみて高いと判断される県 (47都道府県平均から標準偏差以上高い県) |
|
同 左 ┐ │ │ │ │ 1/3に分けている │ │ │ ┘ 同 左 |
| HOME | 目次へ戻る | 次ページ |
まえがき
1.年齢調整死亡率について
都道府県別に死亡数を人口で除した通常の死亡率(以下「粗死亡率」という。)を比較すると、各都道府県の年齢構成に差があるため、高齢者の多い都道府県では高くなり、若年者の多い都道府県では低くなる傾向がある。このような年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡率が年齢調整死亡率である。この死亡率を用いることによって、年齢構成の異なる集団について、年齢構成の相違を気にすることなく、より正確に地域比較や年次比較をすることができる。
平成7年都道府県別年齢調整死亡率は、平成7年人口動態統計死亡数を平成7年国勢調査人口で除した粗死亡率及び「昭和60年モデル人口」(昭和60年の国勢調査人口を基に補正した基準人口;2ページ参照)を用いて、次式で求められる。
平成7年都道府 県別(死因別) = 年齢調整死亡率 |
┌ │平成7年都道府県別 │年齢5歳階級別(死 │因別)粗死亡率 └ |
× | ┐ 「昭和60年モデル│ 人口」のその年齢階│ 級の人口 │ ┘ |
の各年齢階級 の総和 |
| ―――――――――――――――――――――――――――――― | ||||
| 「昭和60年モデル人口」の総数 | ||||
死因別、都道府県別の年齢調整死亡率は、「昭和60年モデル人口」を基準人口として昭和35年から5年ごとに算出しており、単位はすべて人口10万対で表章している。
なお、年齢調整死亡率の基準人口については、昭和60年までは全国の年次比較には昭和10年人口、都道府県の比較には昭和35年人口を使用してきたが、いずれも高齢者の占める割合が極めて低く、最近の人口構成とは乖離していたため、平成2年に「昭和60年モデル人口」を採用した。頻繁に基準人口の変更を行うことは混乱を招くことから、平成7年についても同じ基準人口を用いている。
2.平成7年の結果の注意点について
| 1) |
平成7年1月から世界保健機関(WHO)の「第10回修正国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD−10)」を我が国の死因統計に適用したこと及び死亡診断書の改正を行ったことによる影響があること。 |
| (心疾患死亡数の減少、脳血管疾患死亡数の増加、悪性新生物死亡数の増加等) | |
| 2) | 平成7年1月の阪神・淡路大震災の影響があること。 |
| (兵庫県の死亡数(不慮の事故)の増加等) | |
| 3) | 日本地図の階級分けについて |
| 日本地図については、次のように3階級及び5階級に分けている。 |
| 3階級の場合 | 5階級の場合 | ||
|---|---|---|---|
|
|
年齢調整死亡率が47都道府県平均から統計的 にみて低いと判断される県 (47都道府県平均から標準偏差以上低い県) 年齢調整死亡率が47都道府県平均から統計的 にみて同程度と判断される県 (47都道府県平均から標準偏差以内の県) 年齢調整死亡率が47都道府県平均から統計的 にみて高いと判断される県 (47都道府県平均から標準偏差以上高い県) |
|
同 左 ┐ │ │ │ │ 1/3に分けている │ │ │ ┘ 同 左 |
基準人口 −昭和60年モデル人口−
| 年齢 | 基準人口 |
|
0〜4歳 5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85歳以上 |
8,180,000 8,338,000 8,497,000 8,655,000 8,814,000 8,972,000 9,130,000 9,289,000 9,400,000 8,651,000 7,616,000 6,581,000 5,546,000 4,511,000 3,476,000 2,441,000 1,406,000 784,000 |
| 総 数 | 120,287,000 |
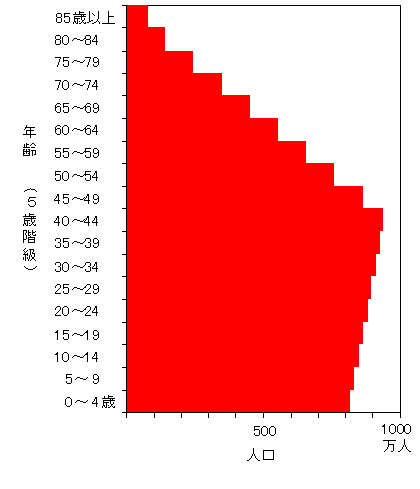
注: |
昭和60年モデル人口は、昭和60年国勢調査を基礎に、ベビーブームなどの極端な増減を補正し、四捨五入によって1000人単位としたものである。 |
| HOME | 目次へ戻る | 次ページ |