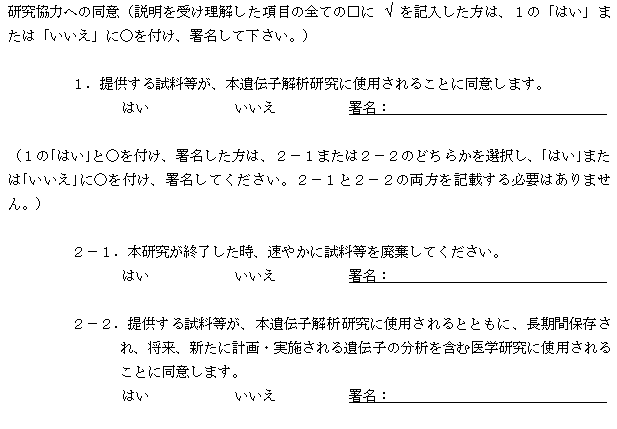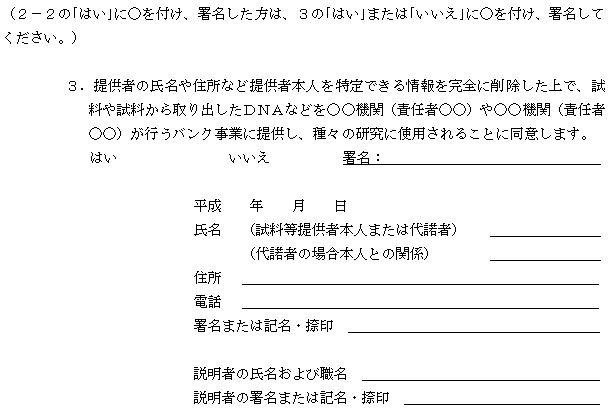1.個人情報の保護
(1)研究機関の長
平成12年4月28日
厚生科学審議会
先端医療技術評価部会
指 針 目 次
前 文
遺伝子の解明とヒトゲノムの全塩基配列の解読が進む中で、一人ひとりの遺伝情報の違いと疾病との関連を研究し、それを疾病の予防、早期発見、早期治療に結びつけ、さらには薬剤の開発にも役立たせる努力が開始されている。このような研究の成果は、患者一人ひとりの体質や薬剤の副作用の強さの違いなどをより科学的に明らかにし、その違いに応じた医療の提供(オーダー・メイド医療)、医薬品の適正使用などを通じて人々の福祉に大きく貢献することが期待されている。
このため、政府においても、新しい千年紀のプロジェクト(ミレニアム・プロジェクト)の一つとして、痴呆、がん、糖尿病等の高齢者の主要な疾患や薬剤の反応性に関連する遺伝子の解明とそれに基づくオーダー・メイド医療などの実現を目標とするプロジェクトを平成12年度から5か年計画で実施することとしている。
一方、遺伝子解析研究には、従来の医学研究が経験していない面がある。すなわち、ある種の病気では、試料等提供者が将来罹患するであろう疾病を予測できると同時に、遺伝子の一部を共有するその血縁者についても、疾病の罹患を予測できるという点である。この事実は、遺伝子解析研究の結果が様々な倫理的・法的・社会的問題を招く可能性を示している。このため研究に当たっては、試料等提供者、その家族や血縁者さらには同じような病気にかかっている他の患者の尊厳を尊重し、人権を守り、利益を保護することが重要である。しかしながら、我が国においては、遺伝子解析研究において倫理面を重視した統一的な指針がなく、研究機関および研究者が、独自の対応をとることを余儀なくされている。
このような状況を踏まえ、厚生省において、平成12年度から開始される「遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究」の実施に当たって、研究機関や研究者が遵守するべき統一的な指針の策定に着手することとされ、厚生科学特別研究事業として「遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究における生命倫理問題に関する調査研究」が実施された。この生命倫理に関する調査研究を行うに当たっては、国立高度専門医療センターや国立試験研究機関等の長、生命倫理に関する有識者からなる検討委員会が設けられ、具体的な指針起草の作業は検討委員会に設置された作業委員会で行われた。
上記のとおり、生命倫理に関する調査研究では、当初、ミレニアム・プロジェクトの一つである厚生省の「遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究」を念頭において指針の検討作業が進められた。しかしながら、検討委員会の報告においても、また、それについて募集された意見においても、この指針の基本理念と内容はミレニアム・プロジェクトとして行われるすべての遺伝子解析研究においても遵守されるべきであり、さらに、一般的な遺伝子解析研究に適用される指針の必要性が指摘されている。
当厚生科学審議会先端医療技術評価部会においても、生命倫理に関する調査研究の報告やその報告に寄せられた多数の意見も参考として審議を行った結果、ミレニアム・プロジェクトとして行われる遺伝子解析研究の共通の指針としてこの「遺伝子解析研究に付随する倫理問題に対応するための指針」を取りまとめたので報告する。
さらに、この指針の実際の適用状況を把握しつつ、国立、公立または私立を問わずすべての研究機関および研究者が一般に行っている遺伝子解析研究の指針についても、引き続き厚生科学審議会先端医療技術評価部会で審議することが適当との結論に至ったので、あわせて報告する。
この指針を契機として、生命倫理問題への理解が進み、人権を守り、生命の尊厳を守るための意識の高まりを期待したい。また、今後、医療および健康の保持・増進を責務とする厚生省が、関係省庁との緊密な連携の下に、遺伝子解析研究の適正な推進について積極的な取り組みを進めるべきこと、医療の場において行われる予防、診断または治療において行われる遺伝子診断の在り方やその結果の取扱い方針などについては別途の検討が必要であることを、指摘しておきたい。
遺伝子解析研究は、研究への協力を要望された人、その家族や血縁者、さらには同じような病気にかかっている他の患者の視点に立って進められるべきである。
この指針は、この考え方に基づき、試料等を提供する人の人権を守ることと適切な研究の実施を両立させるため、以下の6点を基本方針としている。
この指針は、この基本方針が研究現場で理解され、遵守されるよう、具体的な表現を用いて作成されている。
(1-1)試料等提供者の意思の尊重
研究への協力を要望された人は、研究を行う者から十分な情報の提供を受けるべきである。
その上で、研究への協力を要望された人は、その自由意思に基づいて協力または非協力を決めるべきである。
(1-2)倫理審査委員会の審査および外部の者の調査
研究責任者は、責任体制および実施体制を明確にした研究計画を策定し、事前に倫理審査委員会の審査を受けるべきである。試料等提供者またはその家族等の人権が守られるように、研究の実施状況は、外部の有識者によって実地に調査され、研究実施機関の長に報告されるべきである。
(1-3)試料等提供者の人権
研究を行う者は、法令、この指針および研究計画を遵守し、研究の遂行に当たっては、適切なインフォームド・コンセント、身体的安全性およびプライバシー保護など、試料等提供者またはその家族等の尊厳および人権を尊重すべきである。
そのために、研究実施機関は、試料等提供者の個人識別情報保護のために、個人識別情報を厳重に管理する手続きおよび設備などの体制を整えるべきである。
(1-4)既提供試料
既に収集されている試料等の研究利用の可否は、試料等が集められた時の同意の有無または内容を踏まえ、倫理審査委員会の審査に基づいて研究実施機関の長が決定するべきである。
(1-5)遺伝カウンセリング
試料等の提供が行われる機関は、試料等提供者またはその家族等を対象とした遺伝カウンセリングを必要に応じて行えるよう、その体制を整備するべきである。
(1-6)研究の透明性
研究を行う者は、遺伝子解析研究の実施状況について、試料等提供者またはその家族等に対し様々な機会をとらえて説明すべきである。研究に責任を持つ者は、試料等提供者またはその家族等の人権侵害が生じない範囲で、研究の状況を広く社会に公開するべきである。
この指針のため、次のように用語を定義する。
(2-1)試料等
研究に用いる血液、組織、細胞、体液および排泄物やこれらから抽出したDNAなど人の体の一部をいう。死者から提供された試料を含む。臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づいて脳死と判定された人からの試料等の提供は想定していない。試料等には、提供者の診療情報が含まれる。ただし、研究とその評価により学術的な価値が定まり、研究実績として十分に認められ、研究用に広く一般に利用され、さらに一般に入手可能な組織、細胞、体液および排泄物並びにこれらから抽出したDNAなどは含まれない。
(2-2)診療情報
診断および治療を通じて得られた疾病名、投薬名、検査結果等の情報をいう。
(2-3)遺伝情報
試料等を用いて行われる遺伝子の解析を通じて得られた情報をいう。
(2-4)遺伝子解析研究
疾病の予防、診断および治療法の向上や新薬の開発を目的として行われる遺伝子の機能および構造を明らかにする研究をいう。この指針では、遺伝子発現解析研究、体細胞遺伝子解析研究および生殖細胞系列遺伝子解析研究が念頭におかれている。この指針でいう「遺伝子解析研究」には、試料等の提供も含まれる。
医療の場において診療のみを目的として行われる遺伝子解析は、この指針でいう「遺伝子解析研究」には含まれない。
(2-4-1)遺伝子発現解析研究 ある特定の遺伝子の機能を調べるため、mRNA量を調べる研究をいう。
(2-4-2)体細胞遺伝子解析研究 体細胞のDNAに起きた病的な変化を調べるため、DNAまたはmRNAから作られた相補DNAの塩基配列等の構造を解析する研究をいう。
(2-4-3)生殖細胞系列遺伝子解析研究 生殖細胞系列におけるDNAの変化または個体差を調べるため、DNAまたはmRNAから作られた相補DNAの塩基配列等の構造を解析する研究をいう。遺伝子多型を調べる研究もこれに含める。
(2-5)個人識別情報
個人の氏名、身元など、その人を特定する情報をいう。代表的な個人識別情報には、人の氏名、生年月日、住所、電話番号の他、患者一人ひとりに付された診療録番号等の符号などがある。試料等に関する情報のうち、それだけでは人を特定できない情報であっても、各種の名簿など他で入手できる情報と組み合わせることによりその人を特定できる場合には、その組合せに用いることができる情報は個人識別情報に含まれる。
ある人の個人識別情報を含む情報が法令、この指針または研究計画に反して外部に漏洩しないように、その人に関する情報から個人識別情報の全部または一部を取り除き、代わりにその人と関わりのない符号または番号を付すことをいう。試料等に付随する情報のうち、ある情報だけでは特定の人を識別できない情報であっても、各種の名簿など他で入手できる情報と組み合わせることによりその人を識別できる場合には、組合せに必要な情報の全部または一部を取り除いて、その人が識別できないようにすることをいう。
匿名化には、次の種類がある。
試料等の提供が行われる機関において、所属する機関の長の指示を受け、試料等提供者の個人識別情報を含む情報がその機関の外部に漏洩しないように個人識別情報を含む情報を管理し、匿名化を行う職員をいう。
(2-8)インフォームド・コンセント
試料等の提供を求められた人が、倫理審査委員会により認められた説明者から遺伝子解析研究に関する十分な説明を受け、その研究の目的、方法、予測される成果や不利益等を理解し、自由意思に基づいてする試料等提供の同意をいう。
(2-9)代諾者
試料等の提供を求められた本人が、インフォームド・コンセントを与えるかどうかを決めることができない場合に、その人の代わりに決める人をいう。試料等提供者本人が死者の場合には遺族をいう。
なお、代諾者は、あくまでも試料等提供者の人権を守る観点から、その人の代わりに同意するかどうかを決める人であり、代諾者自身の遺伝的問題については、別途の対応の考慮が必要である。
の中から選ばれるのが一般的と考えられる。しかし、代諾者の選定は、その試料等提供者が置かれている状況によって個別に判断されるべきであり、この指針で一義的に定義しない。
遺伝子解析研究を実施する機関をいう。試料等の提供が行われる機関も含まれる。
(2-11)試料等の提供が行われる機関
研究実施機関のうち、人々から試料等の提供が行われる機関をいう。通常は、医療機関または保健所が想定される。
(2-12)共同研究機関
倫理審査委員会により認められた遺伝子解析研究を共同して行う国公立または民間の研究実施機関(大学を含む。)をいう。ある研究実施機関が、遺伝子解析の対象となる試料等をその機関以外の試料等の提供が行われる機関から提供してもらう場合には、その試料等の提供が行われる機関も含まれる。
(2-13)倫理審査委員会
研究実施機関の長の求めに応じ、遺伝子解析研究の実施の適否その他の事項について、試料等提供者またはその家族等の人権尊重等の倫理的観点を中心に、科学的観点を含めて調査審議するため、研究実施機関に置かれた合議機関をいう。
(2-14)研究遂行者
研究責任者および研究実施担当者をいう。
(2-15)研究責任者
個々の研究実施機関において、遺伝子解析研究を遂行するとともに、その研究に係る業務を統括する者であって、遺伝子解析研究の有用性と限界および生命倫理について十分な知識を有する研究者をいう。
(2-16)研究実施担当者
研究責任者の指示や委託に従って遺伝子解析研究を実施する者であって、業務の内容に応じて必要な知識と技能を持つ研究者、医師、薬剤師、看護婦(士)、臨床検査技師等をいう。
(2-17)試料等提供者
遺伝子解析研究のために試料等を提供した人をいう。第一群試料等提供者から第四群試料等提供者に分かれる。
(2-17-1)第一群試料等提供者 単一遺伝子疾患(一つの遺伝子の変化による遺伝素因の明らかな疾患)の患者など。すなわち、研究開始の時点において、遺伝素因の関与が明らかな、遺伝性疾患や重篤な薬剤反応性異常を有する人およびその可能性のある人をいう。ただし、試料等提供の依頼をできるのは、その病名などの告知を受けている人に限られる。遺伝子解析研究を通じた原因遺伝子の特定など新たな知見が、その人の健康状態の評価および疾病の予防、診断および治療方針に影響すると考えられる。
(2-17-2)第二群試料等提供者 第一群試料等提供者以外の疾患の患者など。すなわち、研究開始の時点においては、遺伝素因の関与の程度が明らかでない疾病や、薬剤反応性異常等を有する人、およびそれらの可能性のある人をいう。ただし、試料等提供の依頼をできるのは、その病名などの告知を受けている人に限られる。遺伝子解析研究の結果は、その人の健康状態の評価や疾病予防、診断または治療方針に直ちには影響しないと考えられる。
(2-17-3)第三群試料等提供者 ふつうの健康状態の人。すなわち、集団検診等の健康診断受診者およびこの研究に自発的に協力する人であって、研究の対象となる病気にかかっているかどうか明らかでない人をいう。遺伝子解析研究の結果は、ほとんどの場合、その人の健康状態の評価や疾病の予防、診断または治療方針に影響しないと考えられる。
(2-17-4)第四群試料等提供者 コホート研究への参加者など。すなわち、健康の維持や疾病にかかることについて、環境要因と遺伝素因との相互作用等の解明を目的としたコホート研究などに自発的に協力する人をいう。コホート研究などに参加後ある病気にかかった人は、集団の構成員の一人として引き続きコホート研究などに参加する場合には、第四群試料等提供者である。遺伝子解析研究の結果は、ほとんどの場合、その人の健康状態の評価や疾病の予防、診断または治療方針に影響しないと考えられる。
研究実施機関において、この指針の作成前に集められ、保存されている試料等をいう。集められた時における同意の状況に応じてA群試料等からC群試料等に分かれる。
(2-18-1)A群試料等 試料等の提供時に、遺伝子解析研究での利用が明示された同意が得られた人から提供を受けた試料等をいう。
(2-18-2)B群試料等 試料等の提供時に、「医学的研究に用いることに同意する」などのように遺伝子解析研究での利用が明示されない同意のみを得られた人から提供された試料等をいう。
(2-18-3)C群試料等 試料等が集められた時に、研究に用いることの同意が得られていない人から収集された試料等をいう。
(2-19)遺伝カウンセリング
遺伝医学に関する知識および遺伝カウンセリングの技能を用いて、患者やその家族等からの求めに応じ、対話と情報提供を繰り返しながら、遺伝性疾患をめぐり生じ得る倫理的、法的、社会的または精神心理的諸問題の解消または緩和を目指し、援助や支援をすることをいう。
(2-20)細胞・遺伝子・組織バンク
匿名化された細胞・遺伝子・組織を一般的に研究用資源として分譲するために保存し、分譲する事業をいう。
(3-1)研究実施機関の長の責務
(3-1-1)研究実施機関の長は、その機関の研究遂行者および個人識別情報管理者に対し、遺伝子解析研究が、倫理的、法的または社会的問題を引き起こす可能性があること、それゆえに、試料等提供者の人権を最大限尊重しなければならないことを周知徹底しなければならない。
(3-1-2)研究実施機関の長は、その機関の研究遂行者が、法令、この指針または研究計画に反して遺伝子解析研究を実施した場合には、その研究者に対して次に掲げるような不利益処分や措置がとられる可能性があることを周知徹底しなければならない。
(3-1-2-1)その研究に対する公的な研究費の返還。
(3-1-2-2)職務上の処分。
(3-1-2-3)試料等提供者に身体的、精神的または財産的損害を与えた場合には、民事上の損害賠償もしくは刑事上の処罰または両者。
(3-1-3)研究実施機関の長は、その機関における遺伝子解析研究の実施の適否その他の事項に関する調査審議を行わせるため、倫理審査委員会を設置しなければならない。ただし、次に掲げる場合には、研究実施機関の長は、それぞれの規定に定める措置をとることができる。
(3-1-3-1)この指針の規定に従って審査を行う場合に、研究機関に既に設置されている類似の委員会の委員構成を特別に再編成することにより、この指針に適合する倫理審査委員会とすること。
(3-1-3-2)試料等の提供が行われる機関が小規模であることにより倫理審査委員会を設置できない場合に、共同研究機関に設置された倫理審査委員会を活用すること。ただし、その倫理審査委員会の構成および運営は、この指針の規定に適合してなければならない。
(3-1-4)研究実施機関の長は、その研究機関において遺伝子解析研究を行うときは、研究を始める前に研究責任者に研究計画を提出させ、研究の可否を審査し、許可するかどうかを決定しなければならない。
(3-1-5)研究実施機関の長は、研究計画を許可するかどうかを審査し、決定する前に、倫理審査委員会の意見を求め、その意見を尊重しなければならない。研究実施機関の長は、倫理審査委員会の意見に反し、試料等提供者またはその家族等の不利益になるような決定をしてはならない。
(3-1-6)研究実施機関の長は、試料等またはそれから得られた遺伝情報を国内外の営利を目的としている団体の研究実施機関が行う遺伝子解析研究のために提供する場合には、提供元において行われる匿名化の方法、提供先における利用目的、責任体制等について、書面で契約を結ばなければならない。
(3-1-7)研究実施機関の長は、試料等またはそれから得られた遺伝情報を国内外の営利を目的としている団体、事業者等に提供して遺伝子解析研究の業務の一部を委託する場合には、委託する業務の内容、提供元において行われる匿名化の方法、提供先における責任体制等について、書面で契約を結ばなければならない。
(3-1-8)研究実施機関の長は、契約に基づき試料等を提供し、または遺伝子解析業務の一部を委託した国内外の営利を目的としている団体、事業者等が契約に反する行為を遵守していないことを把握したときには、その団体、事業者等に対してとった措置および再発防止のための新たにとる措置を倫理審査委員会に報告し、意見を求めなければならない。
(3-1-9)研究実施機関の長は、試料等提供者またはその家族等の人権を守るため、遺伝子解析研究の実施状況について、次のような措置をとらなければならない。
(3-1-9-1)研究責任者に対し、定期的に、必要があると判断した場合にはその都度、遺伝子解析研究の実施状況を報告させること。
(3-1-9-2)研究実施機関の長が指名する外部の有識者に、1年に1回以上、インフォームド・コンセントのための手続きの実施状況および個人識別情報の保護の状況について、遺伝子解析研究が研究計画書に沿って行われているかどうかを実地調査させること。調査を担当するその外部の有識者は、指名前の5年の間にその機関に所属していなかった人でなければならない。
(3-1-9-3)研究実施機関の長は、報告または調査の結果、試料等提供者またはその家族等の人権を守るため必要と認められる場合には、許可した遺伝子解析研究の実施方法の改善、中止または研究計画の変更を命じなければならない。
(3-1-9-4)研究実施機関の長は、中止を命じた遺伝子解析研究の再開または変更を命じた研究計画を許可する場合には、あらかじめ倫理審査委員会の意見を聴かなければならない。
(3-1-10)研究実施機関の長は、試料等提供者またはその家族等から、提供した試料等の取扱い、個人識別情報を含む情報の取扱い、研究遂行者または遺伝カウンセリング部門の対応等についての苦情の適切な処理に努めなければならない。
(3-1-11)試料等の提供が行われる機関の長は、遺伝子解析研究に係る個人識別情報を含む情報の保護を図るため、個人識別情報管理者を置かなければならない。
(3-1-12)試料等の提供が行われる機関の長は、試料等提供者またはその家族等に対して、必要に応じ遺伝カウンセリングを行える体制を整備しなければならない。
(3-2)研究責任者の責務
(3-2-1)研究責任者は、法令、この指針および研究計画に従って研究が進められるように、所属する機関において、研究実施担当者を指導し、遺伝子解析研究に係る業務を統括しなければならない。
(3-2-2)研究責任者が、法令、この指針または研究計画に反して遺伝子解析研究を実施した場合には、次のような不利益処分または措置がとられる可能性がある。
(3-2-2-1)その研究に対する公的な研究費の返還。
(3-2-2-2)職務上の処分。
(3-2-2-3)試料等提供者に身体的、精神的または財産的損害を与えた場合には、民事上の損害賠償もしくは刑事上の処罰または両者。
(3-2-3)研究責任者は、遺伝子解析研究の実施に当たって、あらかじめ、次の事項を記載した研究計画書を作成し、所属する機関の長に許可を求めなければならない。
研究計画を変更する場合にも同様に許可を求めなければならない。
(3-2-3-1)試料等提供者を選ぶ方針、考え方または基準。
(3-2-3-2)研究の目的、方法、期間、予測される成果、予測される試料等提供者に対する危険や不利益および個人識別情報を含む情報の保護の方法。
(3-2-3-4)提供を受けようとする試料等の種類とそれぞれの量。
(3-2-3-5)インフォームド・コンセントのための説明者の氏名およびその説明者に対する説明項目、その他の研究遂行者および遺伝カウンセリング部門の担当者の氏名および役割。試料等の提供依頼を他の研究機関と共同で行う場合には、関係する研究機関の中で中心となる研究機関の研究責任者が作成した説明項目を含む。
(3-2-3-8)既提供試料等を研究に用いる場合には、その試料等の提供を受けるときの同意の有無、同意を得ている場合にはその内容、同意がないか若しくは不十分な場合には研究対象として用いる必要性。
(3-2-3-9)試料等またはそれから得られた遺伝情報を国内外の公的研究機関、営利を目的としていない団体の研究機関または大学に対して提供する場合には、次の事項。
(3-2-3-9-1)提供の必要性。
(3-2-3-9-2)提供先の機関名。
(3-2-3-9-3)提供元において行われる匿名化の方法。
(3-2-3-9-4)匿名化しない場合はその理由および個人識別情報を含む情報の保護の方法。
(3-2-3-9-5)試料等を提供した機関において、提供した試料等の遺伝子解析研究を行う場合には、その旨。
(3-2-3-9-6)反復、継続して提供する場合には、その旨。
(3-2-3-10)試料等またはそれから得られた遺伝情報を、国内外の営利を目的としている団体の研究実施機関に提供する場合または国内外の民間の機関に遺伝子解析研究の一部の作業や研究用資材の作成を委託する場合には、次の事項。
(3-2-3-10-1)提供の必要性。
(3-2-3-10-2)提供先の機関名。
(3-2-3-10-3)提供元において行われる匿名化の方法。
(3-2-3-10-4)提供先における責任者の氏名、責任体制および予定する契約の内容。
(3-2-3-11)研究期間の間または研究期間の終了後のそれぞれにおいて、研究遂行者が試料等を研究実施機関内で保存する場合には、保存の方法および保存の必要性。
(3-2-3-12)試料等を細胞・遺伝子・組織バンクに寄託することを予定している場合には、そのバンクが運営されている機関の名称、試料等の匿名化の方法および責任者の氏名。
(3-2-3-13)試料等を廃棄する場合には、廃棄の方法および匿名化の方法。
(3-2-3-14)第一群試料等提供者から試料等の提供を受ける場合には、遺伝カウンセリングの体制。第二群から第四群試料等提供者から試料等の提供を受ける場合には、遺伝カウンセリング体制の必要性の有無、必要性がある場合にはその体制。
(3-2-4)研究責任者は、定期的に、次に掲げる事項を所属する機関の長に報告しなければならない。
(3-2-4-1)提供された試料等の数。
(3-2-4-2)所属外の機関への試料等の提供数。
(3-2-4-3)遺伝子解析が行われた試料の数。
(3-2-4-4)遺伝子解析研究の実施に伴う問題の発生の有無。
(3-2-5)試料等の提供が行われる機関においては、研究責任者は、上記の事項に加えて、匿名化を行った試料の数も所属する機関の長に報告しなければならない。
(3-2-6)研究責任者は、インフォームド・コンセントのための説明者に対し、説明に当たり理解しておくべき説明項目を作成の上、周知しなければならない。
(3-2-7)複数の研究機関が共同して遺伝子解析研究を行う場合には、その共同研究の中心となる研究実施機関の研究責任者は、他の共同研究機関の研究責任者が作成する説明項目、説明文書および同意文書の整合性を図らなければならない。
(3-2-8)研究責任者は、試料等提供者およびその家族等の人権の尊重や、特許権などの知的財産権の保護に配慮しながら、試料等提供者、その代諾者および社会に対し、遺伝子解析研究の進み具合およびその成果を、定期的におよび求めに応じて説明し、または公表しなければならない。説明または公表のための資料は、一般の人に分かりやすいものでなければならない。
(3-3)研究遂行者等の責務
(3-3-1)研究遂行者は、試料等提供者およびその家族等の人権を守る観点から重大な懸念が発生した場合等には、速やかに所属する機関の長および研究責任者に報告し、その対処方法について判断を仰がなければならない。
(3-3-2)試料等の提供が行われる機関の研究遂行者は、所属外の研究機関に試料等を提供する場合には、所属する機関の個人識別情報管理者により匿名化された試料等を提供しなければならない。
試料等の提供が行われる機関の研究遂行者は、在職中またはその職を退いた後といえども、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。
試料等の提供が行われる機関が試料等の提供を受けると同時にその機関において遺伝子解析研究も行う場合には、その試料等を用いて遺伝子解析研究を行う部門は、所属外の研究機関とみなされる。
所属外の研究機関等への試料等の提供は、反復継続して提供するかどうかを問わない。
(3-3-3)試料等の提供が行われる機関の研究遂行者は、倫理審査委員会が認めた研究計画書において匿名化をしないことが認められており、かつ、試料等提供者またはその代諾者が匿名化しない試料等の提供に同意している場合には、その研究計画書およびインフォームド・コンセントに従って、匿名化されていない試料等を提供することができる。匿名化されていない試料等を提供された他の研究遂行者も同様とする。
(3-3-4)研究遂行者は、所属する機関の長が指名した外部の調査担当者が行う実地調査に協力しなければならない。
(3-3-5)研究実施担当者は、法令、この指針、研究計画および研究責任者の指示や委託に従って遺伝子解析研究を行わなければならない。法令、この指針または研究計画に反して遺伝子解析研究を実施した場合には、次のような不利益処分または措置がとられる可能性がある。
(3-3-5-1)その研究に対する公的な研究費の返還。
(3-3-5-2)職務上の処分を受ける可能性。
(3-3-5-3)試料等提供者に身体的、精神的または財産的損害を与えた場合には、民事上の損害賠償もしくは刑事上の処罰または両者。
(3-3-6)研究実施機関の長が指名した外部の調査担当者は、実地調査を行う上で知り得た個人に関する情報を、法令または裁判所の命令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。調査担当者を退いた後といえども同様とする。
(3-4)個人識別情報管理者の責務
(3-4-1)個人識別情報管理者は、試料等の提供が行われる機関に置かれ、刑法(明治40年法律第45号)により業務上知り得た秘密の漏示を禁じられている医師、薬剤師等であって、研究遂行者以外の者でなければならない。
(3-4-2)個人識別情報管理者は、所属外の研究機関に試料等が提供される場合には、その試料等の匿名化を行わなければならない。
試料等の提供が行われる機関が試料等の提供を受けると同時にその機関において遺伝子解析研究も行う場合には、その試料等を用いて遺伝子解析研究を行う部門は、所属外の研究機関とみなされる。
所属外の研究機関等への試料等の提供は、反復継続して提供するかどうかを問わない。
(3-4-3)個人識別情報管理者は、倫理審査委員会が認めた研究計画書において匿名化をしないことが認められており、かつ、試料等提供者またはその代諾者が匿名化しない試料等の提供に同意している場合には、その試料等の匿名化を行わないことができる。
(3-4-4)個人識別情報管理者は、その所属する機関の長が倫理審査委員会に諮った上で許可しなければ、匿名化により取り除かれた個人識別情報を所属する機関の外部に提供してはならない。
個人識別情報管理者は、所属する機関の長に提供の許可を受けようとするときは、提供先の機関名、提供の目的および必要性を説明しなければならない。
(3-4-5)個人識別情報管理者は、所属する機関の長が指名した外部の調査担当者が行う実地調査に協力する場合には、その者に個人識別情報を含む情報を開示できる。
(3-4-6)個人識別情報管理者は、所属する機関の長の指示を受け、試料等提供者の個人識別情報が含まれている情報を厳重に管理しなければならない。個人識別情報管理者を退いた後といえども同様とする。個人識別情報管理者が、法令、この指針または研究計画に反して個人識別情報を含む情報を漏洩した場合には、次のような不利益処分または措置がとられる可能性がある。
(3-4-6-1)その研究に対する公的な研究費の返還。
(3-4-6-2)職務上の処分。
(3-4-6-3)試料等提供者に身体的、精神的または財産的損害を与えた場合には、民事上の損害賠償もしくは刑事上の処罰または両者。
(3-5)倫理審査委員会の責務および構成
(3-5-1)倫理審査委員会の責務
(3-5-1-1)倫理審査委員会は、研究実施機関の長から研究計画の実施の適否その他の事項について意見を求められた場合には、試料等提供者またはその家族等の尊厳、人権等の倫理的観点を中心に、科学的観点を含めて、厳格に調査審査し、文書により意見を述べなければならない。
(3-5-1-2)倫理審査委員会は、運営方法等に関する規則を定め、それを公開しなければならない。規則では、次に掲げる事項が定められるべきである。
(3-5-1-2-1)委員長の選任方法。
(3-5-1-2-2)会議の成立要件。
(3-5-1-2-3)議決方法。
(3-5-1-2-4)審査に係る記録の保存期間。
(3-5-1-3)倫理審査委員会は、研究実施機関の長から、遺伝子解析研究を遂行する上で生じた倫理上の疑問等につき意見を求められた場合には、意見を述べなければならない。
(3-5-1-4)倫理審査委員会の議事要旨は、公開されなければならない。
ただし、公開することによって、試料等提供者またはその家族等の人権、研究に係る独創性または特許権などの知的財産権の保護に支障が生じるおそれがある部分は非公開とすることができる。
(3-5-1-5)倫理審査委員会の委員は、審査を行う上で知り得た人に関する情報を法令または裁判所の命令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。委員を退いた後といえども同様とする。
(3-5-2)倫理審査委員会の構成等
(3-5-2-1)倫理審査委員会は、遺伝子解析研究に関する事項を総合的に審査するために必要な次のような人により構成されなければならない。
(3-5-2-1-1)倫理・法律面の有識者。すなわち、遺伝子解析研究に関する倫理的事項を総合的に審査するに必要な優れた識見を有する人文科学、社会科学等の専門家。
(3-5-2-1-2)科学面の有識者。すなわち、遺伝子解析研究に関する科学的事項を総合的に審査するに必要な優れた識見を有する専門家や試料等提供者などの診療に従事する専門家。
(3-5-2-1-3)市民の立場の人。すなわち、試料等提供者の人権について広く一般の人々の意見を反映できると考えられる人。
(3-5-2-2)委員のうち、半数以上は外部の人でなければならない。
外部の人には、委員就任の前5年の間において、その機関に所属していた者や倫理審査委員会が設置される研究実施機関と利害関係を有していた者は、含まれない。
さらに、その外部の人のうち半数以上(全体の4分の1以上)は、倫理・法律面の有識者または市民の立場の人でなければならない。
(3-5-2-4)倫理審査委員会は、倫理・法律面の有識者または市民の立場の人が1名以上出席しなければ、審議または採決のための会議を開くことができない。
(3-5-3)迅速審査手続き
(3-5-3-1)倫理審査委員会は、研究計画の軽微な一部変更であって、次に掲げるような試料等提供者の人権に重大な支障を来さないと考えられる事項を審査するために、その決定により、迅速審査手続きを設けることができる。
(3-5-3-1-1)研究実施担当者が異動した場合。
(3-5-3-1-2)当初の研究計画で共同研究機関の類型を記載した遺伝子解析研究において、具体的な共同研究機関が定まった場合。
(3-5-3-1-3)当初の研究計画で連結可能匿名化を行って用いることとしていた試料等を連結不可能匿名化する場合。
(3-5-3-2)迅速審査手続きは、倫理審査委員会の委員の中から委員長があらかじめ指名した委員により行われる。
(3-5-3-3)迅速審査手続きにより審査された案件は、その手続きが終了したときは、その手続きに参加していない倫理審査委員会の委員に通知されなければならない。
(4-1)インフォームド・コンセントの一般的な原則
(4-1-1)試料等提供の依頼を受ける人
研究責任者は、試料等提供の依頼を受ける人を、その人が置かれている立場を不当に利用するなど、不合理または不公平な方法で選んではならない。
(4-1-2)説明の原則
(4-1-2-1)倫理審査委員会により認められた説明者は、試料等の提供を求める場合には、説明文書を用いて分かりやすく、かつ、十分に説明しなければならない。
(4-1-2-2)説明者は、試料等の提供を求められた人が、その自由意思に基づいて提供に同意し、または提供を拒否することができるように説明しなければならない。
(4-1-2-3)身体障害等により説明文書を読むことができない人のインフォームド・コンセントに係る一連の手続きは、研究遂行者でない者を立ち会わせた上で行われなければならない。
(4-1-2-4)試料等提供の同意を受けることができる場合には、その同意は文書によらなければならない。
(4-1-2-5)第一群試料等提供者または第二群試料等提供者となることを念頭において行われるインフォームド・コンセントのための説明およびそれに用いる説明文書と同意文書は、診療のためのものと区別されなければならない。
(4-1-3)遺伝情報の開示に関する原則
(4-1-3-1)研究遂行者は、遺伝情報の開示を希望し、または非開示を希望する試料等提供者の意思を尊重しなければならない。
(4-1-3-1-1)個々の試料等提供者の遺伝情報が明らかとなる遺伝子解析研究に試料等を提供した人がその人自身の遺伝情報の開示を希望している場合には、開示の前に、その情報が有する医学的な意義など関係する情報を十分説明し、その意思を十分に確認しなければならない。
(4-1-3-1-2)個々の試料等提供者の遺伝情報が明らかとなる遺伝子解析研究に試料等を提供した人がその人自身の遺伝情報の開示を希望している場合であっても、次のような研究のときには、個々の試料等提供者の遺伝情報の開示に代えて、個々の試料等提供者の遺伝情報を開示しない理由を分かりやすく説明するとともに、将来学術的な意義が明らかになった時点においてその意義を広く社会に分かりやすく公表することができる。
(4-1-3-1-2-1)多数の人または遺伝子の遺伝情報を相互に比較することにより、ある疾患とある遺伝子の関連やある遺伝子の機能を明らかにしようとする遺伝子解析研究。
(4-1-3-1-2-2)多数の人の遺伝情報から特定の人の結果を取り出す作業過程に比べて、その情報がその人の健康状態などを評価するための情報としての精度や確実性に欠けており、提供者個人またはその代諾者に知らせるには十分な意義がないような大規模研究。
(4-1-3-1-3)個々の試料等提供者の遺伝情報が明らかとなる遺伝子解析研究に試料等を提供した人がその人自身の遺伝情報の開示を希望していない場合には、その人に開示してはならない。
(4-1-3-1-4)個々の試料等提供者の遺伝情報が明らかとなる遺伝子解析研究に試料等を提供した本人がその人自身の遺伝情報の開示を希望していない場合であっても、その遺伝情報が試料等提供者の生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な治療方法があるときは、研究実施機関の長は、開示についての倫理審査委員会の意見に基づき、研究責任者、試料等提供者の診療を担当する医師およびその医師が所属する医療機関の長等と対応を協議しなければならない。
試料等提供者の血縁者に対する開示についても、試料等を提供した本人に対する開示と同様に対応されなければならない。
(4-1-3-2)試料等提供者の遺伝情報は、原則として、試料等提供者の意思に反して、それ以外の人に開示されてはならない。
(4-1-3-3)試料等提供者の代諾者に対する開示に関する原則
(4-1-3-3-1)試料等提供者の遺伝情報は、原則として、代諾者(親権者として代諾した人を除く。)に対しても開示されてはならない。
(4-1-3-3-2)代諾者(親権者として代諾した人を除く。)が試料等提供者本人の遺伝情報の開示を希望する場合には、その代諾者が開示を求める理由または必要性を倫理審査委員会に諮った上で、委員会の意見に基づき研究実施機関の長が対応を決定しなければならない。
(4-1-3-4)試料等提供者が未成年者である場合の開示に関する原則
(4-1-3-4-1)未成年者の遺伝情報は、その未成年者の代わりに試料等提供の同意をした親権者が開示を希望している場合には、その親権者に開示することができる。ただし、未成年者の意向を確認し、それを尊重しなければならない。差別、養育拒否、治療への悪影響が心配される場合には、必要に応じ、開示の前に、開示についての倫理審査委員会の意見や未成年者と親権者の話し合いを求めるべきである。
(4-1-3-4-2)未成年者の遺伝情報は、その未成年者が開示を明確に希望している場合には、その未成年者に開示することができる。ただし、親権者の意向を確認し、それを尊重しなければならない。差別、養育拒否、治療への悪影響が心配される場合には、必要に応じ、開示の前に、開示についての倫理審査委員会の意見や未成年者と親権者の話し合いを求めるべきである。
(4-1-3-4-3)未成年者の遺伝情報が開示される場合には、その遺伝情報の科学的意義、必要に応じて治療方法や専門の医療機関など診療に関する情報が提供されなければならない。
(4-1-3-5)第一群試料等提供者に対して遺伝情報を開示する場合には、特に遺伝カウンセリングの担当者との連携を緊密に保たなければならない。
(4-1-4)説明事項
説明文書には、次の事項を記載しなければならない。ただし、遺伝子解析研究の目的、対象とする人または解析方法の違いに応じ、一部を省略することができる。
(4-1-4-1)試料等の提供は任意であること。
(4-1-4-2)試料等の提供の依頼を受けた人は、提供に同意しないことにより不利益な対応を受けないこと。
(4-1-4-3)試料等提供者またはその代諾者は、同意はいつでも撤回でき、同意の撤回により不利益な対応を受けないこと。
(4-1-4-4)次の場合を除き、試料等提供者またはその代諾者により同意が撤回された場合には、その撤回に係る試料等およびその研究結果は廃棄されること。
(4-1-4-4-1)提供された試料等が連結不可能匿名化されてしまっている場合の試料等または研究結果。
(4-1-4-4-2)既に研究結果が公表されている場合、廃棄しないことにより個人識別情報を含む情報が明らかになるおそれが小さく、かつ、廃棄作業が極めて過大である場合等やむを得ない場合の試料等または研究結果。
(4-1-4-5)試料等提供者として選ばれた理由。
(4-1-4-6)研究の目的および方法。
(4-1-4-6-1)研究の目的および方法には、遺伝子解析の対象となる遺伝子、その遺伝子の機能および構造、遺伝子と特定の疾病(がん、痴呆、高血圧、糖尿病、ぜんそく等)の関連性、遺伝子と薬剤の効果または副作用との関連性等を調べることなどが含まれる。
(4-1-4-6-2)将来、解析対象となる疾病に関連する遺伝子または薬剤反応に関連する遺伝子が追加される可能性がある場合、または研究の目的や方法の変更が予想される場合には、その旨。
(4-1-4-7)研究責任者の氏名および職名。
(4-1-4-8)予測される研究結果および試料等提供者に対して予測される危険や不利益。
その危険や不利益には、心身に対する悪影響とともに、社会的な差別など社会生活上の不利益も含まれていなければならない。
(4-1-4-9)試料等提供者の希望により、他の試料等提供者の個人情報の保護や研究の独創性の確保に支障が生じない範囲で、その試料等を用いた遺伝子解析研究の研究計画および研究の方法についての資料を入手または閲覧できること。
(4-1-4-10)提供を受けた試料等についての連結可能匿名化または連結不可能匿名化の別およびその匿名化の具体的方法。匿名化できない場合にあっては、その旨および理由。
(4-1-4-11)試料等またはそれから得られた遺伝情報を他の機関へ提供する場合は、倫理審査委員会により、個人識別情報を含む情報の取扱い、提供先の機関名、提供先における利用目的が妥当であることについて、審査されていること。
(4-1-4-12)遺伝情報の開示に関する事項。
(4-1-4-12-1)個々の試料等提供者の遺伝情報が開示できる研究の場合には、その旨、および開示はその試料等提供者本人にのみ、その求めに応じてなされること。
(4-1-4-12-2)試料等提供者の家族等または代諾者から試料等提供者の遺伝情報を開示する求めがあっても開示しないこと。ただし、試料等提供者が家族等に開示してもよいことを表明する場合には、それを尊重すること。
(4-1-4-12-3)個々の試料等提供者の遺伝情報が開示できる研究の場合であって、試料等提供者に代わって代諾者(親権者として代諾した人を除く。)が同意したときには、提供者本人の遺伝情報は、この指針の「試料等提供者の代諾者に対する開示に関する原則」に従ってその代諾者に対して開示され、または開示されないこと。
(4-1-4-12-4)個々の試料等提供者の遺伝情報が開示できる研究の場合であって、試料等提供者が未成年者であるときは、未成年者の遺伝情報は、この指針の「試料等提供者が未成年者である場合の開示に関する原則」に従ってその未成年者または親権者に開示され、または開示されないこと。
(4-1-4-12-5)個々の試料等提供者の遺伝情報が開示できない研究の場合には、その旨、およびその理由。
(4-1-4-13)将来、研究の成果が特許権など知的財産権を生み出す可能性があること。特許権などの知的財産権を生み出した場合は、その権利は試料等提供者には帰属しないこと、およびその権利の帰属先。
(4-1-4-14)試料等から得られた遺伝情報は、匿名化された上、学会等に公表され得ること。また、データベース化された上で、連結不可能匿名化された遺伝情報として他の研究機関等に公表され得ること。
(4-1-4-15)研究終了後の試料等の保存または廃棄の方針。保存する場合にあっては、その必要性、方法、場所および匿名化の方法。廃棄する場合にあっては、廃棄の方法および匿名化の方法。
(4-1-4-16)試料等を細胞・遺伝子・組織バンクへ寄託し、一般的に研究用資源として分譲することがあり得る場合には、バンクの学術的意義、そのバンクが運営されている機関の名称、寄託される試料等の匿名化の方法およびバンクの責任者の氏名。
(4-1-4-17)遺伝カウンセリングの利用についての情報を提供すること。
(4-1-4-17-1)第一群試料等提供者を対象とする遺伝子解析研究の場合には、本人およびその家族等に対して遺伝カウンセリングが行われること。
(4-1-4-17-2)第二群から第四群の試料等提供者を対象とする遺伝子解析研究の場合であって、倫理審査委員会において遺伝カウンセリングの提供の必要性があるとされたときは、利用可能な遺伝カウンセリングについての情報。
(4-1-4-18)試料等の提供の対価はないこと。また、研究の結果に応じて治療が必要になる場合等における試料等提供者の費用負担に関する事項。
(4-1-5)遺伝カウンセリングとの関係
(4-1-5-1)試料等の提供についてのインフォームド・コンセントのための手続きにおいては、倫理審査委員会の承認を得た説明者は、遺伝カウンセリングの担当者等と連携を保たなければならない。
(4-1-5-2)倫理審査委員会の承認を得た説明者は、遺伝カウンセリングを利用できることを理由に安易な説明をしてはならない
(4-1-5-3)倫理審査委員会の承認を得た説明者は、インフォームド・コンセントのための説明と遺伝カウンセリングとは、別個独立のものであることを理解していなければならない。
(4-1-6)代諾について
(4-1-6-1)試料等提供者本人が痴呆等により有効なインフォームド・コンセントを与えることができないと客観的に判断され、かつその遺伝子解析研究が、その本人からの試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合には代諾者から、試料等提供のインフォームド・コンセントを受けなければならない。この場合において、代諾者は、その推測される本人の意思に配慮しなければならない。
遺伝子解析研究が、死者からの試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合には遺族から、それぞれ試料等提供のインフォームド・コンセントを受けなければならない。
ただし、死者からの試料等の提供を受ける場合には、遺伝子解析研究への試料等の提供を生前にその死者が明確に拒否していない場合に限る。
(4-1-6-2)遺伝子解析研究が未成年者からの試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合には、その未成年者の親権者からインフォームド・コンセントを受けなければならない。さらに、未成年者の年齢に応じて、次のような対応がとられなければならない。
(4-1-6-2-1)未成年者が16歳以上である場合には、親権者とともに、その未成年者本人からもインフォームド・コンセントを受けなければならない。
(4-1-6-2-2)未成年者が16歳未満の場合であっても、その未成年者本人が理解できる言葉で十分な説明を行い、できる限りその未成年者も試料等の提供に同意するように努めなければならない。
(4-1-6-3)代諾者は、試料等提供者の利益を最もよく代弁できると考えられる人でなければならない。
(4-1-6-3-1)代諾者は、次の人の中から選定する。
(4-2)インフォームド・コンセントに係る一連の具体的手続き等
(4-2-1)第一群試料等提供者の場合
説明項目(別添資料(第一群に対する説明者用説明資料例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)の内容を理解した説明者が、試料等提供者または代諾者に対し、説明文書(別添資料(第一群用説明文書例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)を用いて説明しなければならない。
試料等提供者または代諾者が、同意文書(別添資料(第一群用同意文書例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)により同意することを表明することにより、その試料等は遺伝子解析研究に利用できる。
(4-2-1-1)第一群試料等提供者に対するインフォームド・コンセントのための説明においては、遺伝カウンセリングを考慮した説明がなされなければならない。ただし、インフォームド・コンセントのための説明をもって、遺伝カウンセリングを行ったこととしてはならない。このため、研究遂行者は、遺伝カウンセリング等の担当者と特に緊密に連携を保たなければならない。
(4-2-1-2)第一群試料等提供者およびその家族等に対しては、必要に応じて、遺伝カウンセリングが行われなければならない。
(4-2-1-3)試料等提供者の遺伝情報は、この指針の「遺伝情報の開示に関する原則」に従って、診療を担当する医師が試料等提供者(この指針の「遺伝情報の開示に関する原則」が認めている場合には、代諾者または親権者)に対してのみ開示することができる。
(4-2-1-4)診療を担当する医師は、試料等提供者が遺伝情報の開示を希望しない場合には、その人に開示してはならない。
(4-2-1-5)試料等提供者から開示の求めはないが、研究責任者が試料等提供者やその血縁者に対する結果の開示が必要と認めるときは、研究実施機関の長は、開示についての倫理審査委員会の意見に基づき、研究責任者、試料等提供者の診療を担当する医師およびその医師が所属する医療機関の長等と対応を協議しなければならない。
(4-2-1-6)試料等提供者の診療を担当する医師が遺伝情報を開示しようとするときは、その結果が試料等提供者やその血縁者へ与える影響、治療法の有無等を考慮して十分な情報を提供するとともに、必要に応じ、遺伝カウンセリングを行わなければならない。
(4-2-1-7)試料等提供者の診療を担当する医師以外の者は、試料等提供者またはその血縁者に遺伝情報を開示してはならない。
(4-2-2)第二群試料等提供者の場合
説明項目(別添資料(第二群に対する説明者用説明資料例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)の内容を理解した説明者が、試料等提供者または代諾者に対し、説明文書(別添資料(第二群用説明文書例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)を用いて説明しなければならない。
試料等提供者または代諾者が、同意文書(別添資料(第二群用同意文書例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)により同意することを表明することにより、その試料等は遺伝子解析研究に利用できる。この場合、倫理審査委員会が必要と判断したときなど必要に応じ、試料等提供者またはその家族や血縁者に対して遺伝カウンセリングが行われなければならない。
遺伝情報の開示が可能な遺伝子解析研究の場合に、その結果を開示しようとする場合には、第一群試料等提供者に対する遺伝情報の開示と同様とする。
(4-2-3)第三群試料等提供者の場合
説明項目(別添資料(第三群に対する説明者用説明資料例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)の内容を理解した説明者が、試料等提供者または代諾者に対し、説明文書(別添資料(第三群用説明文書例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)を用いて説明しなければならない。
試料等提供者または代諾者が、同意文書(別添資料(第三群用同意文書例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)により同意することを表明することにより、その試料等は遺伝子解析研究に利用できる。
(4-2-4)第四群試料等提供者の場合
説明項目(別添資料(第四群に対する説明者用説明資料例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)の内容を理解した説明者が、試料等提供者または代諾者に対し、説明文書(別添資料(第四群用説明文書例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)を用いて説明しなければならない。
試料等提供者または代諾者が、同意文書(別添資料(第四群用同意文書例)を参考に、研究の対象や方法を考慮して研究責任者が個別に作成)により同意することを表明することにより、その試料等は遺伝子解析研究に利用できる。
(5-1)A群試料等の場合
既に提供されている試料等の提供者または代諾者が既に与えた同意の範囲内で、試料等を遺伝子解析研究に利用できる。
(5-2)B群試料等の場合
原則として、既に提供されている試料等の提供者または代諾者が遺伝子解析研究に用いることの同意を与えなければ、遺伝子解析研究に利用してはならない。
遺伝子解析研究のうち、遺伝子発現解析研究と体細胞遺伝子解析研究のみを行う研究である場合には、既に与えられた同意の範囲内で研究に利用することができる。
また、次のいずれかの要件が満たされる場合には、生殖細胞系列遺伝子解析研究にも利用できる。
原則として、既に集められている試料等の本人または代諾者が遺伝子解析研究に用いることの同意を与えなければ、遺伝子解析研究に利用してはならない。
ただし、次の要件のいずれかが満たされる場合には、生殖細胞系列遺伝子解析研究を含む遺伝子解析研究に利用できる。
(6-1)保存の一般原則
研究遂行者は、研究実施機関内で試料等を保存する場合には、試料等提供者の同意事項を遵守し、研究計画書に定められた方法に従わなければならない。
(6-2)バンクへの寄託
研究遂行者は、試料等を細胞・遺伝子・組織バンクに寄託する場合には、試料等提供者の同意事項を遵守しなければならない。
(6-3)バンクからの分譲
細胞・遺伝子・組織バンクの責任者は、試料等提供者の同意事項を遵守し、保存した試料等を一般的な研究用資源として用いる場合には、連結不可能匿名化して分譲しなければならない。
(6-4)試料等の廃棄
研究遂行者は、研究計画書に従い自ら保存する場合および細胞・遺伝子・組織バンクに寄託する場合を除き、試料等の保存期間が研究計画書に定めた期間を過ぎた場合には、試料等提供者の同意事項を遵守し、匿名化して廃棄しなければならない。
(7-1)業務
遺伝子解析研究における遺伝カウンセリングは、試料等提供者またはその家族等の求めに応じて行われなければならない。
遺伝子解析研究における遺伝カウンセリングにおいては、試料提供者および家族に正確な情報を提供し、対話を通じて、その人たちが遺伝子解析研究や遺伝性疾患に関する理解を深め、その人自身の不安や悩みを解消し、生活設計上の選択を自らの意思で決定し、行動できるように支援、援助が行われなければならない。
(7-2)実施方法
遺伝カウンセリングは、遺伝医学に関する十分な知識を有し、遺伝カウンセリングに習熟した医師、医療従事者等が協力して行われなければならない。
第一群試料等提供者から試料等の提供を受けようとするときは、インフォームド・コンセントのための説明の時点から、遺伝カウンセリングに配慮した説明がなされなければならない。
(7-3)情報提供
遺伝カウンセリング体制が整備されていない試料等の提供が行われる機関は、試料等提供者またはその家族等から遺伝カウンセリングの求めがあった場合には、適切な施設を紹介しなければならない。
この指針は、遺伝子解析の技術、遺伝子解析に対する社会情勢の変化などを勘案して、必要に応じて見直されなければならない。
厚生科学審議会先端医療技術評価部会名簿
| 雨 宮 浩 | 国立小児病院小児医療研究センター長 | |
| 入 村 達 郎 | 東京大学大学院薬学系研究科教授 | |
| 小 澤 えい二郎 | 国立精神・神経センター神経研究所名誉所長 | |
| 加 藤 尚 武 | 京都大学文学部教授 | |
| ○ | 軽 部 征 夫 | 東京大学国際・産学共同研究センター所長 |
| ○ | 木 村 利 人 | 早稲田大学人間科学部教授 |
| 金 城 清 子 | 津田塾大学学芸学部教授 | |
| ○ | 柴 田 鐵 治 | 株式会社朝日カルチャーセンター社長 |
| ○ | 曽 野 綾 子 | 作家 |
| ◎ | 高 久 史 麿 | 自治医科大学学長 |
| ○ | 竹 田 美 文 | 国立感染症研究所長 |
| ○ | 寺 田 雅 昭 | 国立がんセンター総長 |
| 廣 井 正 彦 | 山形県立保健医療大学副学長 | |
| 松 田 一 郎 | 熊本大学名誉教授 |
(五十音順。◎は部会長、○は審議会委員。)
「遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究における
生命倫理問題に関する調査研究」検討委員会名簿
| 雨 宮 浩 | 国立小児病院小児医療研究センター長 | |
| 位 田 隆 一 | 京都大学大学院法学研究科教授 | |
| 宇都木 伸 | 東海大学法学部法律学科教授 | |
| ◎ | 垣 添 忠 生 | 国立がんセンター中央病院長 |
| 金 澤 一 郎 | 東京大学大学院医学系研究科教授(神経内科学) | |
| 木 谷 健 一 | 国立療養所中部病院長寿医療研究センター長 | |
| 島 崎 修 次 | 杏林大学医学部教授(救急医学) | |
| 竹 田 美 文 | 国立感染症研究所長 | |
| 寺 尾 允 男 | 国立医薬品食品衛生研究所長 | |
| 埜 中 征 哉 | 国立精神・神経センター武蔵病院長 | |
| 福 嶋 義 光 | 信州大学医学部教授(衛生学) | |
| 眞 崎 知 生 | 国立循環器病センター研究所長 | |
| 矢 崎 義 雄 | 国立国際医療センター病院長 | |
| 山 口 建 | 国立がんセンター研究所副所長 |
(平成12年3月末現在。五十音順。◎は委員長。)
作業委員会名簿
| 味 木 和喜子 | 大阪府立成人病センター調査部調査課集検整合係長 | |
| 池 田 恭 治 | 国立療養所中部病院長寿医療研究センター老年病研究部長 | |
| 稲 田 俊 也 | 国立精神・神経センター精神保健研究所老人精神保健部老化研究室長 | |
| 上 田 実 | 名古屋大学医学部口腔外科教授 | |
| 岡 慎 一 | 国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター臨床研究開発部長 | |
| 岡 本 高 宏 | 東京女子医科大学内分泌外科講師 | |
| 掛 江 直 子 | 早稲田大学人間総合研究センター助手 | |
| 菅 野 康 吉 | 栃木県立がんセンター遺伝子検査・DNA解析室医長 | |
| 駒 村 和 雄 | 国立循環器病センター研究所循環動態機能部心臓動態研究室長 | |
| 斎 藤 博 久 | 国立小児病院小児医療研究センター免疫アレルギー研究部長 | |
| 斎 藤 有紀子 | 明治大学法学部兼任講師 | |
| 佐 藤 恵 子 | 国立がんセンター臨床試験管理室臨床試験コーディネーター | |
| 鈴 木 盛 一 | 国立小児病院小児医療研究センター実験外科・生体工学研究部長 | |
| 祖父江 友 孝 | 国立がんセンター研究所がん情報研究部がん発生情報研究室長 | |
| 田 中 秀 治 | 杏林大学医学部救急医学講師 | |
| 田 村 友 秀 | 国立がんセンター中央病院特殊病棟部11A病棟医長 | |
| 塚 田 俊 彦 | 国立がんセンター研究所細胞増殖因子研究部受容体研究室長 | |
| 津 金 昌一郎 | 国立がんセンター研究所支所臨床疫学研究部長 | |
| 外 口 崇 | 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構研究振興部長 | |
| 中 川 徹 | 日立製作所日立健康管理センター主任医長 | |
| ぬで 島 次 郎 | 三菱化学生命科学研究所社会生命科学研究室主任研究員 | |
| 橋 本 雄 之 | 国立感染症研究所遺伝子資源室長 | |
| 長谷川 知 子 | 静岡県立こども病院遺伝染色体科医長 | |
| 福 田 治 彦 | 国立がんセンター研究所がん情報研究部がん臨床情報研究室長 | |
| 二 見 仁 康 | 国立がんセンター研究所細胞増殖因子研究部増殖因子研究室長 | |
| 前 川 真 人 | 国立がんセンター中央病院臨床検査部生化学検査室医長 | |
| 松 野 吉 宏 | 国立がんセンター中央病院臨床検査部細胞検査室医長 | |
| 真 弓 忠 範 | 大阪大学副学長・薬学部教授 | |
| 丸 山 英 二 | 神戸大学法学部教授 | |
| 水 沢 博 | 国立医薬品食品衛生研究所変異遺伝部第3室(細胞バンク)室長 | |
| 森 崎 隆 幸 | 国立循環器病センター研究所バイオサイエンス部長 | |
| 山 縣 然太朗 | 山梨医科大学医学科保健学II講座教授 | |
| ◎ | 山 口 建 | 国立がんセンター研究所副所長 |
| 山 口 直 人 | 国立がんセンター研究所がん情報研究部長 | |
| 山 本 順 司 | 国立がんセンター中央病院第一領域外来部通院治療センター医長 | |
| 吉 田 輝 彦 | 国立がんセンター研究所分子腫瘍学部長 |
(平成12年3月末現在。五十音順。◎は座長。)
| インフォームド・コンセントに係る一連の手続きにおいて説明を担当する者に対する説明用資料、試料等の提供を依頼する患者などに説明するための説明用文書、同意文書のイメージ
(注) 以下のイメージは、連結可能匿名化等一定の条件を仮定して作成してあります。この資料は、あくまでもイメージであって、具体的な研究計画の策定に当たっては、その目的、対象疾患、対象者等を考慮して、それぞれの研究責任者が別途策定しなければなりません。 |
第一群試料等提供者用
《説明者用説明資料:第一群用例文》(イメージ)
厚生省におけるミレニアム・プロジェクトの一環として実施される「遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究」においては、個体の持つ遺伝的な多様性と様々な疾病との関連を研究し、それを疾病の予防、早期発見、早期治療さらには薬剤の開発に応用し、人々の福祉に大きく貢献することが期待されている。一方、遺伝子解析により、被験者、その家族・血縁者さらには関連する疾病の罹患者が、様々な倫理的・法的・社会的問題に直面する可能性がある。この問題に対処するため、被験者およびその関係者の尊厳、人権および利益を保護することを目的とし、厚生科学審議会において、「遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するための指針」が作成された。
本文書は、この指針の「第一群試料等提供者」を対象としている。第一群試料等提供者とは、遺伝病の患者など、すなわち、遺伝素因の関与が明らかな、遺伝性疾患や重篤な薬剤反応性異常等を有する者およびその可能性のある被験者である。ただし、被験者はその病名などの告知を受けている人に限られる。本文書は、これらの被験者を対象に、研究協力へのインフォームド・コンセントに係る説明にあたる者が、指針の「5.試料等提供者のインフォームド・コンセント」の記載を十分に理解することを目的として作成されたものである。
「第一群試料等提供者」においては、遺伝子解析研究を通じて得られた原因遺伝子の変化に関する情報が、疾患等の予防・診断・治療の方針に大きく影響する可能性が高く、説明に当たっては、被験者がその特殊性を十分に理解した上で、研究協力の同意を与えることができるよう配慮する必要がある。また、患者や家族のプライバシーを最大限に保護し、被験者からの質問に対しては、必要に応じて診療を担当する医師や遺伝カウンセリング担当者等の協力を得て対応せねばならない。
なお、以下の文章においては、具体的なインフォームド・コンセントの手続きの進め方に応じて説明者のなすべきことを説明し、指針で説明されている部分の項目番号を(
)にて示した。
《説明に当たる者の資格》
インフォームド・コンセントの手続きにおける説明は、研究遂行者の一員であり、倫理審査委員会で承認された研究計画書のなかで「インフォームド・コンセントに係る一連の手続きにおける説明者」として認められた人が行わなければならない(4-1-2-1)。
《代諾について》
被験者が、痴呆等の疾患のため、有効なインフォームド・コンセントを与えることができないと客観的に判断され、かつその研究がそれらの人から試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合、その人に代わってインフォームド・コンセントを与える者として、代諾者に対し説明を行い、同意を得る必要がある(4-1-6-1)。
一方、被験者が未成年者であって、かつその研究が未成年者から試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合、試料等の提供に当たっては、親権者等の代諾者がインフォームド・コンセントを与える必要がある。ただし、未成年者が16歳以上である場合には、親権者等の代諾者とともに、その未成年者本人の同意も必要である。また、未成年者が16歳未満の場合には、代諾者の同意によって試料を提供していただくことが可能であるが、この場合においても、その未成年者本人に十分な説明を行い、できる限りその未成年者からも試料提供の同意が与えられるように努めなければならない(4-1-6-2)。
代諾者は、
《具体的な手順》
インフォームド・コンセントの手続きにおける説明に当たっては、説明者は倫理審査委員会で認められた説明文書を用い、以下に述べる項目について適切かつ十分な説明を行い、説明を受ける者が自由意思に基づいて、試料等の提供への同意を表明できるようにしなければならない。
なお、身体障害などにより説明文書を読むことができない被験者に対しては、研究遂行者でない者を立ち会わせた上で、説明を行わねばならない。
その上で、説明者は署名した同意書の写しを被験者または代諾者に渡し、同意書を所定の場所に保管する。
《説明事項》
(1)研究協力の任意性と撤回の自由
被験者に対し、試料等の提供は任意であっていつでも同意は撤回できることを伝える。さらに、被験者が試料提供に同意しない場合、あるいは同意を撤回した場合においても、疾病等の診療において不利益な扱いを受けないことを説明する(4-1-4-1、2および3)。同意を撤回した場合、その撤回に係わる試料および研究結果は廃棄されるが、既に研究結果が公表されている場合、あるいは廃棄しないことにより被験者の個人識別情報を含む情報が明らかになるおそれが小さく、かつ廃棄作業が極めて過大である場合等やむを得ない場合には、試料や研究結果の廃棄はできないことがあることを説明する(4-1-4-4-2)。
(2)研究協力を要請する理由
被験者がいかなる理由で、遺伝素因の関与が明らかな、遺伝性疾患や重篤な薬剤反応性異常等を有する、あるいはその可能性があると判断されたかを述べ、当該疾患発症者で診断が確定している者、当該疾患の疑いがあるが診断が確定していない者、当該疾患患者の家族などに分け、被験者の試料や診療情報をどのような研究に用いるかを説明する(4-1-4-5)。
その上で、被験者の遺伝素因に関連すると推測される遺伝子について調べることを方法も含め説明する(4-1-4-6-1)。さらに、将来、解析対象となる疾病や薬剤反応に関連する遺伝子を探索するために試料が保存、利用される可能性がある場合または研究の目的や方法の変更が予想される場合にはその旨を説明する(4-1-4-6-2)。
(3)研究責任者の氏名および職名
研究責任者の氏名および職名を告げる(4-1-4-7)。
(4)予測される研究結果と被験者の危険・不利益
遺伝子解析研究の成果が、被験者の診断の確定や適切な治療法の選択などに役立つ可能性がある場合には、それを伝える。また、被験者に直接利益を与えないが、将来、解析対象となる疾病や重篤な薬剤反応性異常の克服に寄与する可能性についてもそれを伝える。
一方、遺伝子解析を実施しても診断が確定できない可能性がある場合や、仮に遺伝子解析により診断が確定しても、予防法や治療法がないなど、今後の診療方針に大きな変更をもたらさない場合等は、大きな利益が得られないことを説明する。また、研究によって、被験者が遺伝的素因を有することが確定された場合などには、後に遺伝カウンセリングに関する部分で述べられているような不利益を被る可能性があることも告げる。逆に、保因者診断等で、遺伝的素因を有しないことが確定した場合においても、被験者あるいは家族の間で心理的な問題が起こりうることを説明する。さらに、試料採取において、身体的な危険が予想される場合には、それについても説明する(4-1-4-8)。
(5)研究計画、方法の開示
希望により、他の試料等提供者の個人情報保護や遺伝子解析研究の独創性の確保に支障が生じない範囲で、その試料等を用いた遺伝子解析研究の研究計画、遺伝子解析の方法等の資料を入手または閲覧することができることを告げる(4-1-4-9)。
(6)試料および診療情報の匿名化
匿名化(氏名、生年月日、住所などの個人を特定できる情報を取り除き、代わりに新たな符号をつけることなどによって、試料や情報の由来する個人を特定できなくすること)を行うこと、提供者と新たにつける符号との対応表は厳重に管理され、解析を行う研究者は誰のものかわからない状態で研究を行うことなどを説明する(4-1-4-10)。
(7)試料、診療情報、遺伝情報の他の研究機関への提供
試料、診療情報、またはそれから得られた遺伝情報を他の機関へ提供する場合は倫理審査委員会により、個人識別情報を含む情報の取扱い、提供先の機関名、提供先における利用目的が妥当であることについて、審査されていることを説明する(4-1-4-11)。
(8)研究結果の開示
被験者本人の求めに応じて遺伝情報を開示できることを説明する。この場合、遺伝情報は診療を担当する医師からそれぞれ被験者のみに開示され、それ以外の者にはたとえ家族であっても、被験者の承諾がない限り開示しないこと、さらに、結果の開示を望む場合は、遺伝子解析前後の予め定めた一定期間内に結果の開示を求めるべきこと、およびこの期間が過ぎた場合は結果の開示が不可能になる場合があることをも告げる。また、一旦結果の開示を望んだ場合でも、実際に開示を受ける前であれば、いつでもこの要求を撤回できることを告げる(4-1-4-12-1および2)。
被験者が未成年者である場合には、基本的に提供に同意した親権者の求めに応じて、遺伝情報が開示できること、この場合にあっては、当該未成年者の意向を確認し、それを尊重することもあわせて説明する(4-1-3-4-1)。
未成年者の遺伝情報は、その未成年者が開示を明確に希望している場合には、基本的に開示できること、この場合にあっては、親権者の意向を確認し、それを尊重することもあわせて説明する(4-1-3-4-2)。
なお、被験者が未成年者であって、遺伝子解析結果が本人に説明されなかった場合で、成人後に被験者が説明を受けることを希望したときは、予め定めた一定期間内であれば本人に説明することを告げる。
代諾者(親権者として代諾した人を除く。)が提供者の遺伝情報の開示を望む場合には、その理由や必要性について倫理審査委員会で審議された上、対応が決定されることを説明する(4-1-4-12-3)。
なお、被験者が開示を求めていない場合であっても、その遺伝情報が被験者の生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な治療方法があるときは、倫理審査委員会の意見を聞いた上で、被験者に対し、その情報の開示につき照会がなされることもあることを説明する。また、このようなときには、被験者の血縁者にも同様の措置がとられることもあることを説明する(4-1-3-1-4)。
(9)知的財産権、研究成果の公表
将来、遺伝子解析研究の成果が知的財産権を生み出す可能性があり、その場合、当該知的財産権は国や研究者などに属し、被験者には帰属しないことを説明する(4-1-4-13)。また、試料から得られた遺伝情報などの研究成果は、匿名化により試料等提供者を特定できなくした上で、学会発表やデータベースとして公表される場合があることを告げる(4-1-4-14)。
(10)試料、診療情報の保管と廃棄
被験者の生体試料や診療情報は、研究計画書に明記され、倫理審査委員会の承認を得たうえで、インフォームド・コンセントの範囲内で、将来の研究のための資源として保管されることがあること、この場合、被験者に対し、その必要性、保管の方法、期間、場所、および匿名化の方法を告げる。廃棄に当たっては、その方法と匿名化の方法を説明する(4-1-4-15)。
(11)細胞・遺伝子・組織バンクへの寄託
試料を細胞・遺伝子・組織バンクへ寄託し、一般的に研究用資源として分譲することがあり得る場合には、バンクの学術的意義、当該バンクが設置されている機関の名称、寄託される試料等の匿名化の方法およびバンクの責任者の氏名を説明する(4-1-4-16)。
(12)試料提供の対価
試料提供に当たっての対価はないこと、また、研究結果によって、診療が必要になった場合、被験者の医療費負担が生じうることを告げる(4-1-4-18)。
(13)遺伝カウンセリングの実施
遺伝性疾患などの患者やその家族の求めに応じ、遺伝性疾患や遺伝子解析についての疑問や不安を解消できるよう援助・支援するための遺伝カウンセリングの体制について説明する。遺伝カウンセリングの体制が整備されていない研究機関においては、遺伝カウンセリングの体制が整備された適切な施設を紹介する等の対応をする(3-2-3-14および4-1-4-17-1)。
なお、遺伝カウンセリングは以下のような倫理規範に基づいて行われるものである。
《遺伝子とは》
「遺伝」という言葉は、「親の体質が子に伝わること」を言います。ここでいう「体質」の中には、顔かたち、体つきのほか、性格や病気に罹りやすいことなども含まれます。ある人の体の状態は、遺伝とともに、生まれ育った環境によって決まってしまいますが、遺伝は基本的な部分で人の体や性格の形成に重要な役割を果たしています。「遺伝」という言葉に「子」という字が付き「遺伝子」となりますと,「遺伝を決定する小単位」という科学的な言葉になります。人間の場合、10万個以上の遺伝子が働いていますが、その本体は「DNA」という物質です。「DNA」は,A,T,G,Cという四つの印(塩基)の連続した鎖です。印は、一つの細胞の中で約30億個あり、その印がいくつかつながって遺伝子を司っています。このつながりが遺伝子です。
一つの細胞の中には10万個以上の遺伝子が散らばって存在しています。この遺伝情報を総称して「ゲノム」という言葉で表現することもあります。人間の体は、60兆個の細胞から成り立っていますが、細胞の一つ一つにすべての遺伝子が含まれています。
遺伝子には二つの重要な働きがあります。一つは,遺伝子が精密な「人体の設計図」であるという点です。受精した一つの細胞は,分裂を繰り返してふえ、一個一個の細胞が、「これは目の細胞」、「これは腸の細胞」と決まりながら、最終的には60兆個まで増えて人体を形作りますが、その設計図はすべて遺伝子に含まれています。第2の重要な役割は「種の保存」です。両親から子供が生まれるのもやはり遺伝子の働きです。人類の先祖ができてから現在まで「人間」という種が保存されてきたのは、遺伝子の働きによっています。
《遺伝子と病気》
こうした非常に大事な役割を持つ遺伝子の違いはさまざまな病気の原因になります。完成された人体を形作る細胞で遺伝子の違いが起きると、違いのある細胞を中心にその人限りの病気が発生することがあります。これを体細胞変異といい、がんがその代表的な病気です。一方、ある遺伝子に生まれつき違いがある場合には,その違いが子,孫へと伝わってしまいます。この場合,遺伝する病気が出てくる可能性が生じます。
このように説明すると、遺伝子の変化が必ず病気を引き起こすと思われるかもしれません。事実は遺伝子の変化が病気を引き起こすことはむしろきわめてまれなことと考えられています。たとえば、一人一人の顔や指紋が違っているのと同じように人によって生まれつき遺伝子に違いが見られ、その大部分は病気との直接の関わりがないことがわかってきました。また、人体を形作る60兆個の細胞では頻繁に遺伝子の変化が起きていますが、そのほとんどは病気との関わりがありません。遺伝子の変化のうちごく一部の変化のみが病気を引き起こし、遺伝する病気として気が付かれるのだと思われます。
《遺伝病における原因遺伝子解析研究の特徴》
遺伝子には、「人体の設計図」、「種の保存」という二つの重要な役割があることをすでに述べました。ある病気の原因となる遺伝子に生まれつきの違いが生じている場合には、この二つの役割に応じた遺伝子解析研究の有用性が考えられます。まず、原因となる遺伝子の生まれつきの違いを持つ人では、将来かかる病気を予測することが可能となり、その情報をもとに、病気を予防したり、早期発見をすることができます。また、患者さんの血縁者の中から患者さんを見つけだし、予防につとめ、また早期発見、早期治療により病気を治すことが可能となります。
しかし、今は健康な人に対し,将来病気になることを告げること、あるいは一人の患者さんの診療によって,その家族の遺伝病を予測してしまうということは従来の医療には見られなかったことです。この結果、新たな倫理的、法的、社会的問題が生じてきますが、これには、将来の発病に対する不安、就職・結婚・生命保険加入などへの影響、家族の中での不安など、様々な問題が考えられます。
あなた(注)が強い遺伝的素因を有している、あるいはその可能性があると判断しており、本遺伝子解析研究にご協力いただきたいと考えております。研究への協力の可否を決めるに当たっては、遺伝子解析研究の持つ利点と不利な点に配慮していただかねばなりません。
なお、ご心配の方には、研究施設に整備され、あるいは研究施設から紹介される遺伝カウンセリングの部門での相談も可能ですので利用してください。
(注)あなたが提供者の代わりに説明を受けている場合には、その提供者のことです。
《遺伝子解析研究への協力について》
この研究は、遺伝子の作りや働き具合を調べ、あなたが今かかっている病気や将来かかるかも知れない病気との関係を調べます。最近、○○○という遺伝子に変化があると、○○○症候群という病気にかかりやすいことがわかってきました。そこで、あなたの○○○遺伝子を調べ、病気を引き起こす違いが見つかれば、診療に生かすことができます。しかし、診断方法は確実なものではなく、○○○遺伝子が原因となる遺伝子ではないことも考えられるので、この研究により違いが見つからない場合には、遺伝する病気にかかっているかもしれないし、そうではないかもしれないと言うどっちつかずの状況になる可能性もあります。ただ、この研究では、より診断技術を向上させ、新しく原因となる遺伝子を探し出すなどの努力を続けていきます。
あなたは、この病気にかかっている・将来かかる可能性が強いので、血液や手術によって取り出された体の一部を診療記録とともにこの研究に利用させていただきたいのです。血液の採取は大きな危険を伴いません。また、手術は病気を治すために行うものですが、取り出した病気によって異常を生じた体の一部、あるいは手術のために一緒に取り出さざるを得ない正常な体の一部で、診療のための分析には不要な部分を研究に利用します。
具体的には、まず、あなたにこの研究への協力をお願いするため、研究の内容を含め、あなたが同意するための手続きについて説明を行います。あなたがこの説明をよく理解でき、あなたが研究に協力して血液や体の一部を提供することに同意しても良いと考える場合には、「遺伝子解析研究への協力の同意書」に署名することにより同意の表明をお願いいたします。
《同意の表明の前提》
(1)研究協力の任意性と撤回の自由
この研究への協力の同意はあなたの自由意志で決めてください。強制いたしません。また、同意しなくても、あなたの不利益になるようなことはありません。
一旦同意した場合でも、あなたが不利益を受けることなく、いつでも同意を取り消すことができ、その場合は採取した血液や遺伝子を調べた結果などは廃棄され、診療記録などもそれ以降は研究目的に用いられることはありません。ただし、同意を取り消した時すでに研究結果が論文などで公表されていた場合などのように、血液や遺伝子を調べた結果などを廃棄することができない場合があります。
(2)研究計画
研究題目:○○○症候群における○○○遺伝子の突然変異の解析
研究機関名および研究責任者氏名:
この研究が行われる研究機関と責任者は下に示すとおりです。
| 研究機関名 | 研究責任者名 | 職名 |
| ○○○センター | ○○ ○○ | ○○○○ |
| ○○○病院 | ○○ ○○ | ○○○○ |
ただし、この他に共同研究を行う研究機関や研究責任者が追加される可能性があります。
研究目的:
この研究は○○○症候群を発病するという生まれながらの体質があるかどうかを、血液などから取り出した遺伝子(○○○)を調べることよって、より正確に診断できるようにしようとするものです。ただし、この研究のために使われるあなたの病気や体の様子、生活の様子についての情報や血液などは、医学の発展にともなって将来計画される別の研究にとっても貴重なものになる可能性があるので、今回の試料提供について、あなたの同意がいただけるならば、将来、同じ病気や別の病気に関連する遺伝子や薬剤の反応に関連する遺伝子の研究のためにもできましたら使わせていただけるようお願いいたします。
研究方法:
血液を通常の方法で約○○ml採血します。採血にともなう身体の危険性はほとんどありません。また、この病気の治療のための手術を受ける場合には、手術によって取り出された体の一部を使用します。この場合は、手術によって取り出されたあとの組織を用いますから、研究にともなう身体の危険性は全くありません。これらの組織に含まれるDNAという物質を取り出し、これを調べることにより、○○○症候群の原因となる遺伝子と考えられている○○○遺伝子の作りがわかります。
この遺伝子のかたちが他の人とどのように違うかを調べ、さらにあなたの症状との関係を調べます。
研究計画等の開示:
希望があれば、この研究の計画の内容を見ることができます。また、遺伝子を調べる方法等に関する資料が必要な場合も用意します。
(3)試料提供者にもたらされる利益および不利益
あなたが既に○○○症候群と確実に診断されている場合は、この遺伝子を調べる方法を用いても、あなた自身の診療方針が大きく変わることはありません。ただ、あなたの遺伝子に原因となる変異が見つかった場合は、血縁者が同じ遺伝体質をもっているかどうかを同様の検査によって確かめやすくなります。
あなたが○○○症候群の疑いがあるけれども、まだ確実に診断されていない場合は、この遺伝子を調べる方法によって、診断が確実になる場合があり、その場合はあなたの血縁者の遺伝体質を調べることも容易になります。また、診断が確実になった場合は、○○○という予防的な治療法を選ぶことができます。ただし、遺伝子を調べてもあなたがこの病気ではないということを確実には言えない場合もあります。
あなたが○○○症候群の原因となる遺伝子の違いがつきとめられている人の血縁者であり、あなたがまだ病気にかかっていない場合、この病気にかかる体質であるかどうかを発病する前に診断することができます。だたし、その体質があると診断された場合、就職・結婚・保険への加入などに関して現時点では予測できないような不利益をこうむる可能性があります。また、たとえその体質ではないと診断された場合でも、家族が不安を感じたり、悩むことがあるかもしれません。そこで、本研究においては、研究施設の責任で、遺伝カウンセリングの部門を整備し、あるいは紹介する体制を整えています。
(4)個人情報の保護
遺伝子の研究結果は、様々な問題を引き起こす可能性があるため、他の人に漏れないように、取扱いを慎重に行う必要があります。あなたの血液などの試料や診療情報は、分析する前に診療録や試料の整理簿から、住所、氏名、生年月日などを削り、代わりに新しく符号をつけます。あなたとこの符号を結びつける対応表は、○○○○(試料等の提供が行われる機関名または部署)において厳重に保管します。このようにすることによって、あなたの遺伝子の分析結果は、分析を行う研究者にも、あなたのものであると分からなくなります。ただし、遺伝子解析の結果についてあなたに説明する場合など、必要な場合には、○○○○(試料等の提供が行われる機関名または部署)においてこの符号を元の氏名などに戻す操作を行い、結果をあなたにお知らせすることが可能になります。
(5)遺伝子解析結果の開示
あなたの遺伝子を調べた結果についての説明は、あなたが説明を望む場合に、あなたに対してのみ行い、たとえあなたの家族に対しても、あなたの承諾または依頼なしに結果を告げることはいたしません。
また、あなたの遺伝子解析の結果、重大な病気との関係が見つかり、あなたやあなたの血縁者がその結果を知ることが有益であると判断される場合には、診療を担当する医師からあなたやあなたの血縁者に、その結果の説明を受けるか否か問い合わせることがあります。
あなたの遺伝子解析の結果について説明を希望される場合は、血液採取後○年以内に申し出て下さい。それ以後はその結果を保管できない場合があります。
あなたの協力によって得られた研究の成果は、提供者本人やその家族の氏名などが明らかにならないようにした上で、学会発表や学術雑誌およびデータベース上等で公に発表されることがあります。
(7)研究から生じる知的財産権の帰属
遺伝子解析研究の結果として特許権などが生じる可能性がありますが、その権利は国、研究機関、民間企業を含む共同研究機関および研究遂行者などに属し、あなたには属しません。また、その特許権などをもととして経済的利益が生じる可能性がありますが、あなたはこれについても権利があるとは言えません。
(8)遺伝子解析研究終了後の試料等の取扱の方針
あなたの血液などの試料は、原則として本研究のために用いさせていただきます。しかし、もし、あなたが同意してくだされば、将来の研究のための貴重な資源として、研究終了後も保管させていただきたいと思います。この場合も、(4)で説明した方法により、分析を行う研究者にはどこの誰の試料かが分からないようにした上で、試料が使い切られるまで保管します。
なお、将来、試料を研究に用いる場合は、改めてその研究計画書を倫理審査委員会において承認を受けた上で利用します。
また、提供された試料やそこから取り出したDNAなどを、どこの誰の物であるかを誰も分からないようにした上で保存し、広く研究用に提供する事業(バンク事業)を○○機関(責任者○○)や○○機関(責任者○○)が行っています。あなたからいただいた試料やそれから取り出したDNAなどもこのバンク事業に提供し、国民の共有財産として様々な研究に利用させていただくことも併せてお願いします。
(9)費用負担に関する事項
ここで行われる遺伝子解析研究に必要な費用は、厚生省の研究に対する助成金から出され、あなたが負担することはありません。また、交通費などの支給は行いません。しかし、この研究によって病気のかかりやすさが明らかとなり、その診断あるいは治療が必要となることがあります。この一般診療に要する費用のうち自己負担分については、あなたが負担せねばなりません。
(10)遺伝カウンセリングの体制
あなたが、病気のことや遺伝子解析研究に関して、不安に思うことがあったり、相談したいことがある場合に備えて、遺伝カウンセリング部門を設置しています。ここでは、遺伝カウンセリング担当者があなたの相談を受けることが可能です。診療を担当する医師、インフォームド・コンセント担当者、あるいは医事課職員にその旨申し出てください。
| 平成 年 月 日(印刷)
研究実施機関名および責任者(印刷) お問い合わせ先(印刷) |
遺伝子解析研究への協力の同意文書
研究責任者あるいは機関の長(試料等の提供が行われる機関における研究責任者名) 殿
私は遺伝子解析研究(研究題目)について、(説明をした者の氏名)より説明文書を用いて説明を受け、その方法、危険性、分析結果のお知らせの方法等について十分理解しました。ついては、次の条件で研究協力に同意致します。
説明を受け理解した項目(□の中にご自分でレを付けて下さい。)
| □ | 遺伝子の分析を行うこと。 |
| □ | 研究協力の任意性と撤回の自由 |
| □ | 研究目的 |
| □ | 研究方法 |
| □ | 研究計画書等の開示 |
| □ | 試料提供者にもたらされる利益および不利益 |
| □ | 個人情報の保護 |
| □ | 遺伝子解析結果の開示 |
| □ | 研究成果の公表 |
| □ | 研究から生じる知的財産権の帰属 |
| □ | 遺伝子解析研究終了後の試料等の取扱の方針 |
| □ | 費用負担に関する事項 |
| □ | 遺伝カウンセリングの体制 |
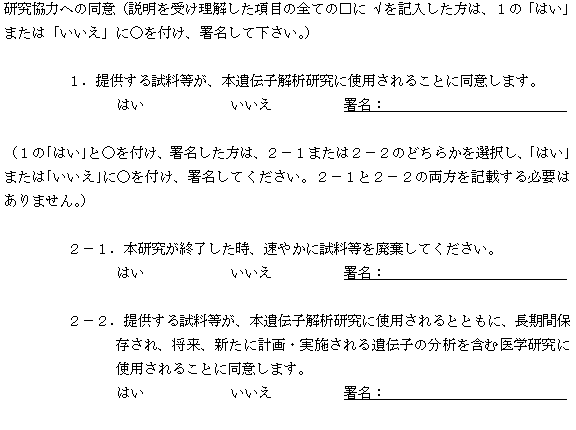
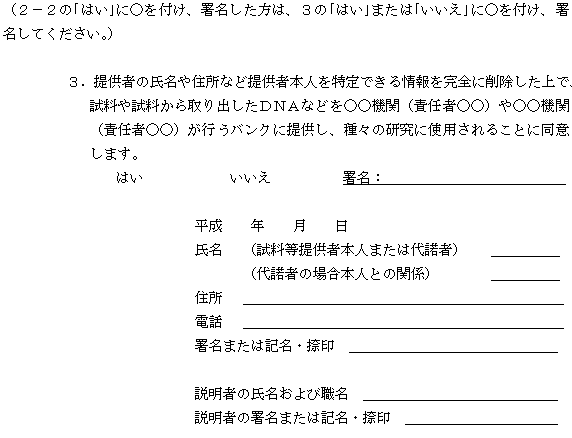
| インフォームド・コンセントに係る一連の手続きにおいて説明を担当する者に対する説明用資料、試料等の提供を依頼する患者などに説明するための説明用文書、同意文書のイメージ
(注) 以下のイメージは、連結可能匿名化等一定の条件を仮定して作成してあります。この資料は、あくまでもイメージであって、具体的な研究計画の策定に当たっては、その目的、対象疾患、対象者等を考慮して、それぞれの研究責任者が別途策定しなければなりません。 |
第二群試料等提供者用
《説明者用説明資料:第二群用例文》(イメージ)
厚生省におけるミレニアム・プロジェクトの一環として実施される「遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究」においては、個体の持つ遺伝的な多様性と様々な疾病との関連を研究し、それを疾病の予防、早期発見、早期治療さらには薬剤の開発に応用し、人々の福祉に大きく貢献することが期待されている。一方、遺伝子解析により、被験者、その家族・血縁者さらには関連する疾病の罹患者が、様々な倫理的・法的・社会的問題に直面する可能性がある。この問題に対処するため、被験者およびその関係者の尊厳、人権および利益を保護することを目的とし、厚生科学審議会において、「遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するための指針」が作成された。
本文書は、この指針の「第二群試料等提供者」を対象としている。第二群試料等提供者とは、遺伝病と判断されない疾患にかかっている人、すなわち、一般の痴呆、がん、高血圧、糖尿病、ぜんそく、薬剤反応性異常など遺伝素因の関与の程度が明らかでない病態を有する者およびその可能性のある者である。ただし、試料等提供の依頼はその病名などの告知を受けている人に限られる。本文書は、これらの被験者を対象に、研究協力へのインフォームド・コンセントに係る説明にあたる者が、指針の「4.試料等提供者のインフォームド・コンセント」の記載を十分に理解することを目的として作成されたものである。
「第二群試料等提供者」においては、遺伝子解析研究を通じて得られた情報が、疾患等の予防・診断・治療の方針に影響を与える可能性は低いと考えられるが、説明に当たっては、被験者が遺伝子解析研究の持つ特殊性を十分に理解した上で、研究協力への同意を与えることができるよう配慮する必要がある。また、患者や家族のプライバシーを最大限に保護し、被験者からの質問に対しては、必要に応じて主治医や遺伝カウンセリング担当者等の協力を得て対応せねばならない。
なお、以下の文章においては、具体的なインフォームド・コンセントの手続きの進め方に応じて担当者の成すべきことを説明し、指針で説明されている部分の項目番号を(
)にて示した。
《説明に当たる者の資格》
インフォームド・コンセントの手続きにおける説明は、研究遂行者の一員であり、倫理審査委員会で承認された研究計画書のなかで「インフォームド・コンセントに係る一連の手続きにおける説明者」として認められた人が行わなければならない(4-1-2-1)。
《代諾について》
被験者が、痴呆等の疾患のため、有効なインフォームド・コンセントを与えることができないと客観的に判断され、かつその研究がそれらの人から試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合、その人に代わってインフォームド・コンセントを与える者として、代諾者に対し説明を行い、同意を得る必要がある(4-1-6-1)。
一方、被験者が未成年者であって、かつその研究が未成年者から試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合、試料等の提供に当たっては、親権者等の代諾者がインフォームド・コンセントを与える必要がある。ただし、未成年者が16歳以上である場合には、親権者等の代諾者とともに、その未成年者本人の同意も必要である。また、未成年者が16歳未満の場合には、代諾者の同意によって試料を提供していただくことが可能であるが、この場合においても、その未成年者本人に十分な説明を行い、できる限りその未成年者からも試料提供の同意が与えられるように努めなければならない(4-1-6-2)。
代諾者は、
《具体的な手順》
インフォームド・コンセントの手続きにおける説明に当たっては、説明者は倫理審査委員会で認められた説明文書を用い、以下に述べる項目について適切かつ十分な説明を行い、説明を受ける者が自由意思に基づいて、試料等の提供への同意を表明できるようにしなければならない。
なお、身体障害などにより説明文書を読むことができない被験者に対しては、研究遂行者でない者を立ち会わせた上で、説明を行わねばならない。
その上で、説明者は署名した同意書の写しを被験者または代諾者に渡し、同意書を所定の場所に保管する。
《説明事項》
(1)研究協力の任意性と撤回の自由
被験者に対し、試料等の提供は任意であっていつでも同意は撤回できることを伝える。
さらに、被験者が試料提供に同意しない場合、あるいは同意を撤回した場合においても、疾病等の診療において不利益な扱いを受けないことを説明する(4-1-4-1、2および3)。同意を撤回した場合、その撤回に係わる試料および研究結果は廃棄されるが、既に研究結果が公表されている場合、あるいは廃棄しないことにより被験者の個人識別情報を含む情報が明らかになるおそれが小さく、かつ廃棄作業が極めて過大である場合等やむを得ない場合には、試料や研究結果の廃棄はできないことがあることを説明する(4-1-4-4-2)。
(2)研究協力を要請する理由
被験者がいかなる理由で、遺伝素因の関与の程度が明らかでない疾患や薬剤反応性異常等を有する、あるいはその可能性があると判断されたかを述べ、当該疾患発症者で診断が確定している者とそうでない者などに分け、被験者の試料や診療情報をどのような研究に用いるかを説明する(4-1-4-5)。
その上で、被験者の遺伝素因に関連すると推測される遺伝子、あるいは具体的な遺伝子が特定できない場合には様々な遺伝子について調べることを方法も含め説明する(4-1-4-6-1)。さらに、将来、解析対象となる疾病や薬剤反応性に関連する遺伝子を探索するために試料が保存、利用される可能性がある場合または研究の目的や方法の変更が予想される場合にはその旨説明する(4-1-4-6-2)。
(3)研究責任者の氏名および職名
研究責任者の氏名および職名を告げる(4-1-4-7)。
(4)予測される研究結果と被験者の危険・不利益
遺伝子解析研究の成果が、被験者に直接利益を与えないが、将来、解析対象となる疾病や薬剤反応性異常の克服に寄与する可能性について伝える。
また、研究によって、被験者が遺伝的素因を有することが確定されることがまれには存在すること、その場合、倫理的・法的・社会的問題が生じうることも告げる。さらに、試料採取において、身体的な危険が予想される場合には、それについても説明する(4-1-4-8)。
(5)研究計画、方法の開示
希望により、他の試料等提供者の個人情報保護や遺伝子解析研究の独創性の確保に支障が生じない範囲で、その試料等を用いた遺伝子解析研究の研究計画、遺伝子解析の詳しい方法等の資料を入手または閲覧することができることを告げる(4-1-4-9)。
(6)試料および診療情報の匿名化
匿名化(氏名、生年月日、住所などの個人を特定できる情報を取り除き、代わりに新たな符号をつけることなどによって、試料や情報の由来する個人を特定できなくすること)を行うこと、提供者と新たにつける符号との対応表は厳重に管理され、解析を行う研究者は誰のものかわからない状態で研究を行うことなどを説明する(4-1-4-10)。
(7)試料、診療情報、遺伝情報の他の研究機関への提供
試料、診療情報、またはそれから得られた遺伝情報を他の機関へ提供する場合は倫理審査委員会により、個人識別情報を含む情報の取扱い、提供先の機関名、提供先における利用目的が妥当であることについて、審査されていることを説明する(4-1-4-11)。
(8)研究結果の開示
この遺伝子解析研究は、多くの被験者の協力を得て、疾患にかかっている集団とそうでない集団、その治療に用いる薬剤の副作用がでる集団とそうでない集団など、それぞれの集団の間に遺伝子の違いがあるかどうかを比べるものであること、その結果、なんらかの違いが見いだされたとしても、その違いと病気との関係などを明らかにするには、まだまだ多くの研究が必要であることなどから、倫理審査委員会の審議の結果、認められた場合には、誰にも研究結果は開示しないことについて説明する(4-1-3-1-2)。ただし、被験者の遺伝子解析の結果が被験者等の生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な治療方法があるときは、倫理審査委員会の意見を聞いた上で、被験者やその血縁者に対し、その情報の開示につき照会がなされることもあることを説明する(4-1-3-1-4)。
研究の進み具合やその成果、学術的な意義は定期的に分かりやすい形で広く公表されること、また、提供者の求めがあればそれに応じて説明することを告げる(3-2-8)。
(9)知的財産権、研究成果の公表
将来、遺伝子解析研究の成果が知的財産権を生み出す可能性があり、その場合、当該知的財産権は国や研究者などに属し、被験者には帰属しないことを説明する(4-1-4-13)。また、試料から得られた遺伝情報などの研究成果は、匿名化により試料等提供者を特定できなくした上で、学会発表やデータベースとして公表される場合があることを告げる(4-1-4-14)。
(10)試料、診療情報の保管と廃棄
被験者の生体試料や診療情報は、研究計画書に明記され、倫理審査委員会の承認を得たうえで、インフォームド・コンセントの範囲内で、将来の研究のための資源として保管されることがあること、この場合、被験者に対し、その必要性、保管の方法、期間、場所、および匿名化の方法を告げる。廃棄に当たっては、その方法と匿名化の方法を説明する(4-1-4-15)。
(11)細胞・遺伝子・組織バンクへの寄託
試料を細胞・遺伝子・組織バンクへ寄託し、一般的に研究用資源として分譲することがあり得る場合には、バンクの学術的意義、当該バンクが設置されている機関の名称、寄託される試料等の匿名化の方法およびバンクの責任者の氏名を説明する(4-1-4-16)。
(12)試料提供の対価
試料提供に当たっての対価はないこと、また、研究結果によって、診療が必要になった場合、被験者の医療費負担が生じうることを告げる(4-1-4-18)。
(13)遺伝カウンセリングの実施
第二群生体試料等提供者について遺伝カウンセリングが必要となる状況は多くはないが、倫理審査委員会がその必要性を指摘した場合、あるいは被験者の希望がある場合には、それを援助・支援するための遺伝カウンセリングの体制が整備され、あるいは紹介できることを説明する(3-2-3-14および4-1-4-17-2)。
《遺伝子とは》
「遺伝」という言葉は、「親の体質が子に伝わること」を言います。ここでいう「体質」の中には、顔かたち、体つきのほか、性格や病気にかかりやすいことなども含まれます。ある人の体の状態は、遺伝とともに、生まれ育った環境によって決まってしまいますが、遺伝は基本的な部分で人の体や性格の形成に重要な役割を果たしています。「遺伝」という言葉に「子」という字が付き「遺伝子」となりますと,「遺伝を決定する小単位」という科学的な言葉になります。人間の場合、10万個以上の遺伝子が働いていますが、その本体は「DNA」という物質です。「DNA」は,A,T,G,Cという四つの印(塩基)の連続した鎖です。印は、一つの細胞の中で約30億個あり、その印がいくつかつながって遺伝子を司っています。このつながりが遺伝子です。
一つの細胞の中には10万個以上の遺伝子が散らばって存在しています。この遺伝情報を総称して「ゲノム」という言葉で表現することもあります。人間の体は、60兆個の細胞から成り立っていますが、細胞の一つ一つにすべての遺伝子が含まれています。
遺伝子には二つの重要な働きがあります。一つは,遺伝子が精密な「人体の設計図」であるという点です。受精した一つの細胞は,分裂を繰り返してふえ、一個一個の細胞が、「これは目の細胞」、「これは腸の細胞」と決まりながら、最終的には60兆個まで増えて人体を形作りますが、その設計図はすべて遺伝子に含まれています。第2の重要な役割は「種の保存」です。両親から子供が生まれるのもやはり遺伝子の働きです。人類の先祖ができてから現在まで「人間」という種が保存されてきたのは、遺伝子の働きによっています。
《遺伝子と病気》
ほとんどすべての病気は、その人の生まれながらの体質(遺伝素因)と病原体、生活習慣などの影響(環境因子)の両者が組合わさって起こります。遺伝素因と環境因子のいずれか一方が病気の発症に強く影響しているものもあれば、がんや動脈硬化などのように両者が複雑に絡み合って生じるものもあります。遺伝素因は遺伝子の違いに基づくものですが、遺伝子の違いがあればいつも病気になるわけではなく、環境因子との組合せが重要であるのは先に述べたとおりです。
《遺伝子解析研究への協力について》
この研究は、○○○症候群という病気や薬の効き目の違いに関係があると考えられる遺伝子、などについて、その作りや働きを調べ、○○○症候群という病気や薬の効き目に遺伝子が関係しているかどうかを調べることを目的としています。
あなた(注)は、この病気にかかっていますが、血液や手術によって取り出された体の一部を診療記録とともに、この研究に利用させていただきたいのです。血液の採取は大きな危険を伴いません。また、手術は病気を治すために行うものですが、取り出した病気によって異常を生じた体の一部、あるいは手術操作のために一緒に取り出さざるを得ない正常な体の一部で、診療のための分析には不要な部分を研究に利用します。
具体的には、まず、あなたにこの研究への協力をお願いするため、研究の内容を含め、あなたが同意するための手続きについて説明を行います。あなたがこの説明をよく理解でき、あなたが研究に協力して血液や体の一部を提供することに同意しても良いと考える場合には、「遺伝子解析研究への協力の同意書」に署名することにより同意の表明をお願いいたします。
(注)あなたが提供者の代わりに説明を受けている場合には、その提供者のことです。
《同意の表明の前提》
(1)研究協力の任意性と撤回の自由
この研究への協力の同意はあなたの自由意志で決めてください。強制いたしません。
また、同意しなくても、あなたの不利益になるようなことはありません。
一旦同意した場合でも、あなたが不利益を受けることなく、いつでも同意を取り消すことができ、その場合は採取した血液や遺伝子を調べた結果などは廃棄され、診療記録などもそれ以降は研究目的に用いられることはありません。ただし、同意を取り消した時すでに研究結果が論文などで公表されていた場合などのように、血液や遺伝子を調べた結果などを廃棄することができない場合があります。
(2)研究計画
研究題目:
○○○症候群に関連する遺伝子の探索に関する研究
(○○○症候群の発病に関係している遺伝子を見つけだすための研究です。)
研究機関名および研究責任者氏名:
この研究が行われる研究機関と責任者は下に示すとおりです。
| 研究機関名 | 研究責任者名 | 職名 |
| ○○○センター | ○○ ○○ | ○○○○ |
| ○○○病院 | ○○ ○○ | ○○○○ |
ただし、この他に共同研究を行う研究機関や研究責任者が追加される可能性があります。
研究目的:
この研究は○○○症候群という病気の発病やその治療に用いる○○ブロッカーという薬の効き目の違いが、生まれながらの体質と関係するかどうかを、血液などから取り出した遺伝子を調べることによって、より正確な診断やより有効な治療ができるようにしようとするものです。ただし、この研究のために使われるあなたの病気や体の様子、生活の様子についての情報や血液などは、医学の発展にともなって将来計画される別の研究にとっても貴重なものになる可能性があるので、今回の試料提供について、あなたの同意がいただけるならば、将来、別の病気や薬剤の反応性に関係する遺伝子の研究のためにもできましたら使わせていただけるようお願いいたします。
研究方法:
血液を通常の方法で約○○ml採血します。採血にともなう身体の危険性はほとんどありません。また、この病気の治療のための手術を受ける場合には、手術によって取り出された体の一部を使用します。この場合は、手術によって取り出されたあとの組織を用いますから、研究にともなう身体の危険性は全くありません。調べる対象となる遺伝子は、現在明らかではありません。そこで、関係する可能性のある遺伝子など数多くの遺伝子を調べることになります。場合によっては、御家族が今までにかかった病気について詳しい説明をお願いすることもあります。
研究計画等の開示:
希望があれば、この研究の研究計画の内容を見ることができます。また、遺伝子を調べる方法等に関する資料が必要な場合も用意します。
(3)試料提供者にもたらされる利益および不利益
本遺伝子解析研究の結果があなたに有益な情報をもたらす可能性は非常に低いと考えられます。まれに、遺伝子の分析研究の結果、偶然に重大な病気との関係が見つかることがあります。この時は、あなたあるいはあなたの家族や血縁者がその結果を知ることが有益であると判断される場合に限り、診療を担当する医師からあなたあるいはあなたの家族や血縁者に、その結果の説明につき照会されることがあります。研究の成果は今後の医学の発展に寄与します。その結果、将来、あなたと同じような病気に苦しむ方々の診断や予防、治療などがより効果的に行われるようになるかもしれません。
本研究では、遺伝子の研究結果があなたに提供していただいた試料によるものであることが特定されないように種々の歯止めを設けていますが、あなたの遺伝子の研究を行うことは、就職・結婚・保健への加入などに関して、現時点では予測できないように不利益をこうむる可能性があります。
(4)個人情報の保護
遺伝子の研究結果は、様々な問題を引き起こす可能性があるため、他の人に漏れないように、取扱いを慎重に行う必要があります。あなたの血液などの試料や診療情報は、分析する前に診療録や試料の整理簿から、住所、氏名、生年月日などを削り、代わりに新しく符号をつけます。あなたとこの符号を結びつける対応表は、○○○○(試料等の提供が行われる機関名または部署)において厳重に保管します。このようにすることによって、あなたの遺伝子の分析結果は、分析を行う研究者にも、あなたのものであると分からなくなります。ただし、遺伝子解析の結果についてあなたに説明する場合など、必要な場合には、○○○○(試料等の提供が行われる機関名または部署)においてこの符号を元の氏名などに戻す操作を行い、結果をあなたにお知らせすることが可能になります。
(5)遺伝子解析結果の開示
本研究は、多くの方々の協力を得て、○○○症候群にかかっている集団とそうでない集団、その治療に用いる○○ブロッカーという薬の副作用がでる集団とそうでない集団など、それぞれの集団の間に遺伝子の違いがあるかどうかを比べるものです。この結果、なんらかの違い見いだされたとしても、その違いと病気との関係などを明らかにするには、まだまだ多くの研究が必要となります。したがって、あなた個人の病気の治療などに有益な結果が出る可能性は極めて低く、あなたを含め、だれにも解析結果を開示することはありません。
ただし、偶然に重大な病気との関係が見つかり、あなたやあなたの血縁者がその結果を知ることが有益であると判断される場合に限って、診療を担当する医師からあなたやあなたの血縁者に、その結果の説明を受けるか否か問い合わせることがあります。
研究の進み具合やその成果、学術的な意義については、定期的に、また、あなたの求めに応じ、分かりやすい形で、公表あるいは説明がされます。
(6)研究成果の公表
あなたの協力によって得られた研究の成果は、提供者本人やその家族の氏名などが明らかにならないようにした上で、学会発表や学術雑誌およびデータベース上等で公に発表されることがあります。
(7)研究から生じる知的財産権の帰属
遺伝子解析研究の結果として特許権などが生じる可能性がありますが、その権利は国、研究機関、民間企業を含む共同研究機関および研究遂行者などに属し、あなたには属しません。また、その特許権などをもととして経済的利益が生じる可能性がありますが、あなたはこれについても権利があるとは言えません。
(8)遺伝子解析研究終了後の試料等の取扱の方針
あなたの血液などの試料は、原則として本研究のために用いさせていただきます。しかし、もし、あなたが同意してくだされば、将来の研究のための貴重な資源として、研究終了後も保管させていただきたいと思います。この場合も、(4)で説明した方法により、分析を行う研究者にはどこの誰の試料かが分からないようにした上で、試料が使い切られるまで保管します。
なお、将来、試料を研究に用いる場合は、改めてその研究計画書を倫理審査委員会において承認を受けた上で利用します。
また、提供された細胞や血液などの体の一部やそこから取り出したDNAなどを、どこの誰の物であるかを誰も分からないようにした上で保存し、広く研究用に提供する事業(バンク事業)を○○機関(責任者○○)や○○機関(責任者○○)が行っています。あなたからいただいた試料やそれから取り出したDNAなどもこのバンク事業に提供し、国民の共有財産として様々な研究に利用させていただくことも併せてお願いします。
(9)費用負担に関する事項
ここで行われる遺伝子解析研究に必要な費用は、厚生省の研究に対する助成金から出され、あなたが負担することはありません。また、交通費などの支給は行いません。しかし、この研究によって病気のかかりやすさが明らかとなり、その診断あるいは治療が必要となることがあります。この一般診療に要する費用のうち自己負担分については、あなたが負担せねばなりません。
(10)遺伝カウンセリングの体制
あなたが、病気のことや遺伝子解析研究に関して、不安に思うことがあったり、相談したいことがある場合に備えて、遺伝カウンセリングを行っています。ここでは、遺伝カウンセリング担当者があなたの相談を受けることが可能です。主治医、インフォームド・コンセント担当者、あるいは医事課職員にその旨申し出てください。
| 平成 年 月 日(印刷)
研究実施機関名および責任者(印刷) お問い合わせ先(印刷) |
遺伝子解析研究への協力の同意文書
研究責任者あるいは機関の長(試料等の提供が行われる機関における研究責任者名) 殿
私は遺伝子解析研究(研究題目)について、(説明をした者の氏名)より説明文書を用いて説明を受け、その方法、危険性、分析結果のお知らせの方法等について十分理解しました。ついては、次の条件で研究協力に同意致します。
説明を受け理解した項目(□の中にご自分でレを付けて下さい。)
| □ | 遺伝子の分析を行うこと。 |
| □ | 研究協力の任意性と撤回の自由 |
| □ | 研究目的 |
| □ | 研究方法 |
| □ | 研究計画書等の開示 |
| □ | 試料提供者にもたらされる利益および不利益 |
| □ | 個人情報の保護 |
| □ | 遺伝子解析結果の開示 |
| □ | 研究成果の公表 |
| □ | 研究から生じる知的財産権の帰属 |
| □ | 遺伝子解析研究終了後の試料等の取扱の方針 |
| □ | 費用負担に関する事項 |
| □ | 遺伝カウンセリングの体制 |
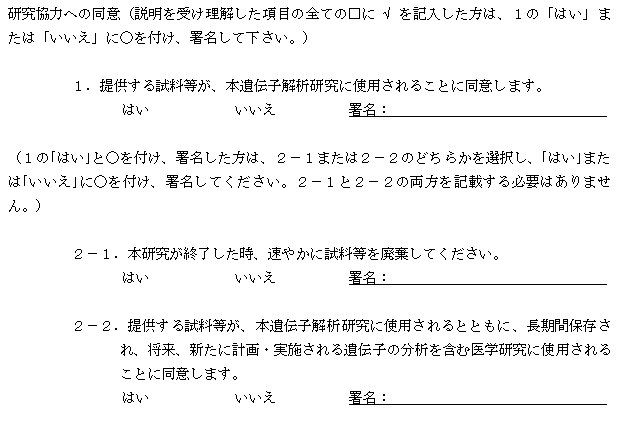
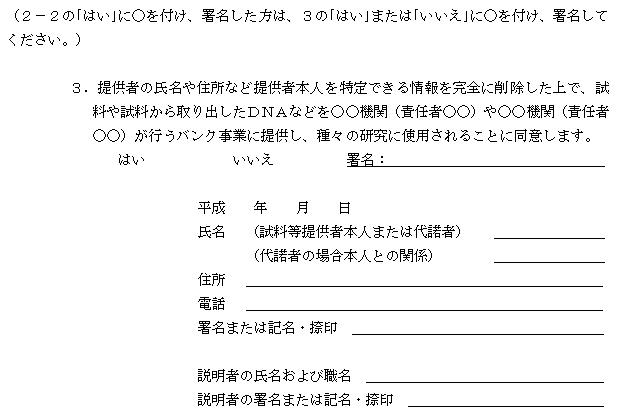
| インフォームド・コンセントに係る一連の手続きにおいて説明を担当する者に対する説明用資料、試料等の提供を依頼する患者などに説明するための説明用文書、同意文書のイメージ
(注) 以下のイメージは、連結可能匿名化等一定の条件を仮定して作成してあります。この資料は、あくまでもイメージであって、具体的な研究計画の策定に当たっては、その目的、対象疾患、対象者等を考慮して、それぞれの研究責任者が別途策定しなければなりません。 |
第三群試料等提供者用
《説明者用説明資料:第三群用例文》(イメージ)
厚生省におけるミレニアム・プロジェクトの一環として実施される「遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究」においては、個体の持つ遺伝的な多様性と様々な疾病との関連を研究し、それを疾病の予防、早期発見、早期治療さらには薬剤の開発に応用し、人々の福祉に大きく貢献することが期待されている。一方、遺伝子解析により、被験者、その家族・血縁者さらには関連する疾病の罹患者が、様々な倫理的・法的・社会的問題に直面する可能性がある。この問題に対処するため、被験者およびその関係者の尊厳、人権および利益を保護することを目的とし、厚生科学審議会において、「遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するための指針」が作成された。
本文書は、この指針の「第三群試料等提供者」を対象としている。第三群試料等提供者とは、ふつうの健康状態の人、すなわち、ある疾病の健康対照群として、あるいは健康診断受診者として研究に自主的に協力する人である。ミレニアム・プロジェクトにおいては健康な集団を代表し、あるいは遺伝子解析を疾病の検診に役立たせるための技術開発など、重要な役割を担うことが想定される。本文書は、「第三群試料等提供者」を対象にインフォームド・コンセントに係る説明を行う者が、指針の「5.試料等提供者のインフォームド・コンセント」の記載を十分に理解することを目的として作成されたものである。
「第三群試料等提供者」に係る研究の結果は、研究段階のものが多くその解釈が確定しておらず、また集団として解析されるため、個々の被験者の健康状態の評価や疾病の予防・診断・治療に影響する可能性は極めて低いものと予測される。しかし、このようにして得られた遺伝情報が、被験者やその家族等に対し様々な不利益を被らせる可能性を否定することはできない。そこで、研究協力に関するインフォームド・コンセントのための説明に当たっては、被験者が遺伝子解析研究の持つ特殊性を十分に理解した上で、研究への協力または非協力を自発的に決定できるよう配慮する必要がある。また、被験者や家族のプライバシーを最大限に保護し、被験者からの質問に対しては、必要に応じて医師や遺伝カウンセリング担当者等の協力を得て、対応することが望まれる。
以下に、インフォームド・コンセントを得るための具体的な手続きを記載するが、理解をより深めるために、指針で説明されている部分の項目番号を( )にて示した。
《説明に当たる者の資格》
インフォームド・コンセントの手続きにおける説明は、研究遂行者の一員であり、倫理審査委員会で承認された研究計画書のなかで「インフォームド・コンセントに係る一連の手続きにおける説明者」として認められた人が行わなければならない(4-1-2-1)。
《代諾について》
被験者が、痴呆等の疾患のため、有効なインフォームド・コンセントを与えることができないと客観的に判断され、かつその研究がそれらの人から試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合、その人に代わってインフォームド・コンセントを与える者として、代諾者に対し説明を行い、同意を得る必要がある(4-1-6-1)。
一方、被験者が未成年者であって、かつその研究が未成年者から試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合、試料等の提供に当たっては、親権者等の代諾者がインフォームド・コンセントを与える必要がある。ただし、未成年者が16歳以上である場合には、親権者等の代諾者とともに、その未成年者本人の同意も必要である。また、未成年者が16歳未満の場合には、代諾者の同意によって試料を提供していただくことが可能であるが、この場合においても、その未成年者本人に十分な説明を行い、できる限りその未成年者からも試料提供の同意が与えられるように努めなければならない(4-1-6-2)。
代諾者は、
《具体的な手順》
インフォームド・コンセントの手続きにおける説明に当たっては、説明者は倫理審査委員会で認められた説明文書を用い、以下に述べる項目について適切かつ十分な説明を行い、説明を受ける者が自由意思に基づいて、試料等の提供への同意を表明できるようにしなければならない。
なお、身体障害などにより説明文書を読むことができない被験者に対しては、研究遂行者でない者を立ち会わせた上で、説明を行わねばならない。
その上で、説明者は署名した同意書の写しを被験者または代諾者に渡し、同意書を所定の場所に保管する。
《説明事項》
(1)研究協力の任意性と撤回の自由
被験者に対し、試料等の提供は任意であっていつでも同意は撤回できることを伝える。
さらに、被験者が試料提供に同意しない場合、あるいは同意を撤回した場合においても、疾病等の診療において不利益な扱いを受けないことを説明する(4-1-4-1、2および3)。同意を撤回した場合、その撤回に係わる試料および研究結果は廃棄されるが、既に研究結果が公表されている場合、あるいは廃棄しないことにより被験者の個人識別情報を含む情報が明らかになるおそれが小さく、かつ廃棄作業が極めて過大である場合等やむを得ない場合には、試料や研究結果の廃棄はできないことがあることを説明する(4-1-4-4-2)。
(2)研究協力を要請する理由
第三群試料等提供者は、遺伝子解析研究に自発的に協力する意思を持ち、年齢、性、検診結果など一定の条件を満たす者、あるいはランダムに選ばれた者であることを説明する(4-1-4-5)。その上で、この研究の目的が、第三群試料等提供者を健康対照群として遺伝子解析を行い、ある病気の患者における分析結果などを解釈するために重要な役割を果たすこと、さらに、遺伝子解析による疾病検診技術の開発などを目指すものであることを説明する。このため、いろいろな病気や薬剤反応について遺伝子を調べること、現段階で特定の遺伝子の名前を示すことはできないことを説明する(4-1-4-6-1)。また、将来、他の病気の原因遺伝子探索における対照群あるいは検診のための技術開発のため、試料が保存、利用される可能性がある場合、あるいは研究の目的や方法の変更が予想される場合にはその旨説明する(4-1-4-6-2)。
(3)研究責任者の氏名および職名
研究責任者の氏名および職名を告げる(4-1-4-7)。
(4)予測される研究結果と被験者の危険・不利益
第三群試料等提供者は、遺伝子解析を用いた疾病検診技術の開発に協力し、さらに、第一群および第二群の生体試料等提供者を対象とした研究において患者の対照群として重要な役割を果たす。
また、本研究においては、遺伝子解析研究の成果が集団で解析されるため、被験者にとっての直接的な利益は期待できないこと、また、被験者にとって不利益な事象としては、検査時の注射針を刺す痛みがあるが、これは一般の検査採血時の痛みと同じであること、さらに、遺伝子検査の結果が外部に漏れた場合、生命保険加入の際の障害になるなどの不利益を被る可能性が考えられることなどを告げる(4-1-4-8)。
なお、研究成果を公表する際には、個人が特定される形では公表しないことなども説明する。
(5)研究計画、方法の開示
希望により、他の試料等提供者の個人情報保護や遺伝子解析研究の独創性の確保に支障が生じない範囲で、その試料等を用いた遺伝子解析研究の研究計画、遺伝子解析の方法等の資料を入手または閲覧することができることを告げる(4-1-4-9)。
(6)試料および診療情報の匿名化
匿名化(氏名、生年月日、住所などの個人を特定できる情報を取り除き、代わりに新たな符号をつけることなどによって、試料や情報の由来する個人を特定できなくすること)を行うこと、提供者と新たにつける符号との対応表は厳重に管理され、解析を行う研究者は誰のものかわからない状態で研究を行うことなどを説明する(4-1-4-10)。
(7)試料、診療情報、遺伝情報の他の研究機関への提供
試料、診療情報、またはそれから得られた遺伝情報を他の機関へ提供する場合は倫理審査委員会により、個人識別情報を含む情報の取扱い、提供先の機関名、提供先における利用目的が妥当であることについて、審査されていることを説明する(4-1-4-11)。
(8)研究結果の開示
第三群試料等提供者を対象として得られた遺伝子解析結果は、疾病検診技術の開発あるいは疾病群などに対する対照群として、多くの人の解析結果をまとめて集団として解析されるために、個々の試料等提供者についての遺伝情報は、試料等提供者又は代諾者を含め誰にも開示できないことを説明する(4-1-3-1-2)。ただし、被験者の遺伝子解析の結果、被験者等の生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な治療方法があるときは、倫理審査委員会の意見を聞いた上で、被験者やその血縁者に対し、その情報の開示につき照会がなされることもあることも説明する(4-1-3-1-4)。
研究の進み具合やその成果、学術的な意義は定期的に分かりやすい形で広く公表されること、また、提供者の求めがあればそれに応じて説明することを告げる(4-2-8)。
(9)知的財産権、研究成果の公表
将来、遺伝子解析研究の成果が知的財産権を生み出す可能性があり、その場合、当該知的財産権は国や研究者などに属し、被験者には帰属しないことを説明する(4-1-4-13)。また、試料から得られた遺伝情報などの研究成果は、匿名化により試料等提供者を特定できなくした上で、学会発表やデータベースとして公表される場合があることを告げる(4-1-4-14)。
(10)試料、診療情報の保管と廃棄
被験者の生体試料や診療情報は、研究計画書に明記され、倫理審査委員会の承認を得たうえで、インフォームド・コンセントの範囲内で、将来の研究のための資源として保管されることがあること、この場合、被験者に対し、その必要性、保管の方法、期間、場所、および匿名化の方法を告げる。廃棄に当たっては、その方法と匿名化の方法を説明する(4-1-4-15)。
(11)細胞・遺伝子・組織バンクへの寄託
試料を細胞・遺伝子・組織バンクへ寄託し、一般的に研究用資源として分譲することがあり得る場合には、バンクの学術的意義、当該バンクが設置されている機関の名称、寄託される試料等の匿名化の方法およびバンクの責任者の氏名を説明する(4-1-4-16)。
(12)試料提供の対価
試料提供に当たっての対価はないこと、また、研究結果によって、診療が必要になった場合、被験者の医療費負担が生じうることを告げる(4-1-4-18)。
(13)遺伝カウンセリングの実施
第三群生体試料等提供者について遺伝カウンセリングが必要となる状況はまれなことと考えられるが、倫理審査委員会がその必要性を指摘した場合、あるいは被験者の希望がある場合には、それを援助・支援するための遺伝カウンセリングの体制が整備され、あるいは紹介できることを説明する(3-2-3-14および4-1-4-17-2)。
○○○センターでは、○○○○(共同研究機関)と共同で、病気に関係する遺伝子や薬の効き目に関係する遺伝子を見つけ出したり、遺伝子解析技術を取り入れた病気の検診のための技術開発を行っています。本文書は、あなた(注)に、この研究への協力をお願いしたく、病気と遺伝子との関係、研究内容などについて説明したものです。この文書をよく理解した上で、あなたが研究協力に同意していただける場合には、「遺伝子解析研究への同意文書」に署名することにより同意の表明をお願いいたします。もちろん、同意いただけないからといって、それを理由にあなたが不利益を被ることはありません。
以下に、遺伝子解析に関する説明と研究協力への同意に関わるいくつかの重要な点を説明します。
(注)あなたが提供者の代わりに説明を受けている場合には、その提供者のことです。
《遺伝子とは》
遺伝子とは人間の身体をつくる設計図に相当するものです。ヒトには10万個以上の遺伝子があると考えられています。人間の身体は、約60兆個の細胞と呼ばれる基本単位からなっていますが、この細胞の核と呼ばれる部分に遺伝子の実体となる物質であるDNAが存在しています。
人間の身体は、この遺伝子の指令に基づいて維持されています。
《病気と遺伝子》
ほとんどすべての病気は、その人の生まれながらの体質(遺伝素因)と病原体、生活習慣などの影響(環境因子)の両者が組合わさって起こります。遺伝素因と環境因子のいずれか一方が病気の発症に強く影響しているものもあれば、がんや動脈硬化などのように両者が複雑に絡み合って生じるものもあります。遺伝素因は遺伝子の違いに基づくものですが、遺伝子の違いがあればいつも病気になるわけではなく、環境因子との組合せが重要であるのは先に述べたとおりです。
《遺伝性の病気》
遺伝性疾患とは、遺伝子の違いによる病気をいいます。これには、親が遺伝子の違いを持っていて、その違いが子に伝わる(いわゆる遺伝する)場合と、親の遺伝子にはまったく違いがないにも関わらず、精子や卵子の遺伝子に突然変異が生じて病気になる場合とがあります。これに対して、身体を構成する細胞に遺伝子の違いが生じて、がんやその他の病気になることがありますが、この場合には病気が子孫に伝わることはなく、遺伝性疾患という言葉は使いません。遺伝子に違いがあっても必ずしも病気になるわけではありません。人間には染色体が2本(1対)ずつあり、1本の染色体の遺伝子に違いが起きても違いが起きていないもう一方の遺伝子が機能を補って病気になるのを防いでいます。また、遺伝子の違いが身体機能の異常につながらないこともあります。一方、病気を引き起こす環境因子への反応の違いが遺伝子の性質によって決まることも多いので、一見遺伝しないように見える多くの病気が遺伝子の違いに起因することも分かってきました。
《遺伝子の解析とは》
この研究はいろいろな病気に関係する生まれつきの体質(遺伝素因)の有無や薬の効き目の違いを、血液などから取り出した遺伝子のかたちを調べることにより明らかにし、病気の予防や早期治療に結びつけようとするものです。あなたの血液をこれまでの病気や生活の状況などの記録とともに、この研究に利用させていただきたいのです。血液の採取は大きな危険を伴いません。
具体的には、まず、あなたにこの研究への協力をお願いするため、研究の内容を含め、あなたが同意するための手続きについて説明を行います。あなたがこの説明をよく理解でき、あなたが研究に協力して血液を提供することに同意しても良いと考える場合には、「遺伝子解析研究への協力の同意書」に署名することにより同意の表明をお願いいたします。
《本研究に関する説明》
(1)研究テーマ
○○病における遺伝子解析研究(○○病における遺伝子解析を利用した検診法に関する研究など)
(2)研究機関名および研究責任者氏名
この研究が行われる研究機関と責任者は下表に示すとおりです。
| 研究機関名 | 研究責任者名 | 職名 |
| ○○○センター | ○○ ○○ | ○○○○ |
| ○○○病院 | ○○ ○○ | ○○○○ |
ただし、この他に共同研究を行う研究機関や研究責任者が追加される可能性があります。
(3)研究目的
この研究は○○という疾患の発病に関わる生まれつきの体質(遺伝素因)の有無や薬の効き目の違いを、血液などから取り出した遺伝子のかたちを調べることにより明らかにし、病気の予防や早期治療に結びつけようとするものです。あなたから提供される試料はこのような研究を進めるに当たって、病気の人の遺伝子と比べるために、健康な人の遺伝子の形を調べる目的で使用されます。また、遺伝子の分析を病気の検診に用いる方法を開発するため、試料の分析をさせていただきます。このため、いろいろな病気や薬の反応に関係する遺伝子を調べたいと考えており、今は特定の遺伝子の名前をお示しすることはできません。
(4) 遺伝子解析に必要なもの
遺伝子解析に必要なものは、(血液 約○○ml)です。これらの試料からDNAなどをとりだして、病気に関係した遺伝子や薬の効き目に影響する遺伝子の違いの有無を調べます。
(5)遺伝子解析の費用
この遺伝子解析にかかる費用は厚生省の研究に対する助成金により支払われますので、あなたの負担はありません。
(6)研究計画等の開示
希望があれば、この研究の研究計画の内容を見ることができます。また、遺伝子を調べる方法等に関する資料が必要な場合は用意します。
(7)個人情報の保護について
遺伝子の研究結果は、様々な問題を引き起こす可能性があるため、他の人に漏れないように、取扱いを慎重に行う必要があります。あなたの血液などの試料や診療情報は、分析する前に診療録や試料の整理簿から、住所、氏名、生年月日などを削り、代わりに新しく符号をつけます。あなたとこの符号を結びつける対応表は、○○○○(試料等の提供が行われる機関名または部署)において厳重に保管します。このようにすることによって、あなたの遺伝子の分析結果は、分析を行う研究者にも、あなたのものであると分からなくなります。ただし、遺伝子解析の結果についてあなたに説明する場合など、必要な場合には、○○○○(試料等の提供が行われる機関名または部署)においてこの符号を元の氏名などに戻す操作を行い、結果をあなたにお知らせすることが可能になります。
(8)試料の他の研究への利用について
この研究のために提供していただくあなたの試料や診療情報は、将来計画される別の研究にとっても貴重なものになるので、今回の試料提供にあなたの同意がいただけるならば、将来の別の遺伝子解析研究のためにもできましたら使わせていただけるようお願いします。
また、提供された試料やそこから取り出したDNAなどをどこの誰の物であるかを誰も分からないようにした上で保存し、広く研究用に提供する事業(バンク事業)を○○機関(責任者○○)や○○機関(責任者○○)が行っています。あなたからいただいた試料やそれから取り出したDNAなどもバンク事業に提供し、国民の共有財産として様々な研究に利用させていただくことも併せてお願いします。
(9)遺伝子解析を受ける人の権利
この研究に協力するかどうかは、あなたの自由意思で決定して下さい。強制はいたしません。また、同意しなくても、あなたの不利益になるようなことはありません。
一旦同意した場合でも、あなたが不利益を被ることはなく、いつでも同意を取り消すことができます。その場合は採取した血液や遺伝子を調べた結果などは廃棄され、それ以降は研究目的に用いられることはありません。ただし、同意を取り消した時にすでに研究結果が論文などで公表されていた場合は、血液や遺伝子を調べた結果などを廃棄することができない場合もあります。
(10)解析結果の報告
本研究で得られる遺伝子解析結果は、さらに詳しい研究が必要なものが多く、結果をどのように理解すべきかがはっきりとは分かっていません。また、ご協力いただいた多くの方々を集団として、例えばある病気にかかっている方々の遺伝子と比べる研究を行います。したがって、個々の方について解析結果はお知らせできません。
ただし、偶然に重大な病気との関係が見つかり、あなたやあなたの血縁者がその結果を知ることが有益であると判断される場合に限って、医師からあなたやあなたの血縁者に、その結果の説明を受けるか否かについて問い合わせることがあります。
研究の進み具合やその成果、学術的な意義については、定期的に、また、あなたの求めに応じ、分かりやすい形で、公表あるいは説明がされます。
(11)研究に協力することによる利益と不利益
本研究に参加することにより、あなたが個人的に受ける利益はありません。しかし、本研究によって解明された成果を社会へ還元することにより、その一員として、新しい知見にもとづく病気の予防や治療を受けることができます。
遺伝子を分析する研究の結果として特許権など、ひいてはそれに基づく経済的利益が生じる可能性がありますが、あなたはこの特許権などが自分のものであると言えません。
一方、あなたが受ける不利益としては、あなた自身の遺伝子解析結果が外部に漏れた場合、生命保険加入の際の障害、社会における不当な差別などにつながる可能性が考えられます。しかし、前でも述べたとおり、この研究では多くの方々を対象として、集団として分析を行うのでその恐れはまずないと考えられます。それでも、万が一の漏洩による不利益を防ぐため、遺伝子を調べたあなたや御家族の機密保持については、機密保持のための責任者を置くなどの配慮をしています。
なお、研究成果を公表する際には、個人が特定される形では公表しませんので、それにより不利益を受けることはありません。
| 平成 年 月 日(印刷)
研究実施機関名および責任者(印刷) お問い合わせ先(印刷) |
遺伝子解析研究への協力の同意文書
研究責任者あるいは機関の長(試料等の提供が行われる機関における研究責任者名) 殿
私は遺伝子解析研究(研究題目)について、(説明をした者の氏名)より説明文書を用いて説明を受け、その方法、危険性、分析結果のお知らせの方法等について十分理解しました。ついては、次の条件で研究協力に同意致します。
説明を受け理解した項目(□の中にご自分でレを付けて下さい。)
| □ | 遺伝子の分析を行うこと。 |
| □ | 研究目的 |
| □ | 遺伝子解析に必要なもの |
| □ | 遺伝子解析の費用 |
| □ | 研究計画書等の開示 |
| □ | 個人情報の保護 |
| □ | 試料の他の研究への利用 |
| □ | 遺伝子解析を受ける人の権利 |
| □ | 解析結果の報告 |
| □ | 研究に協力することによる利益と不利益 |
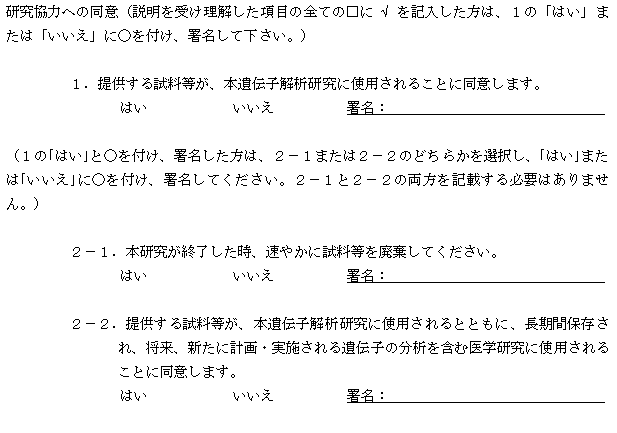
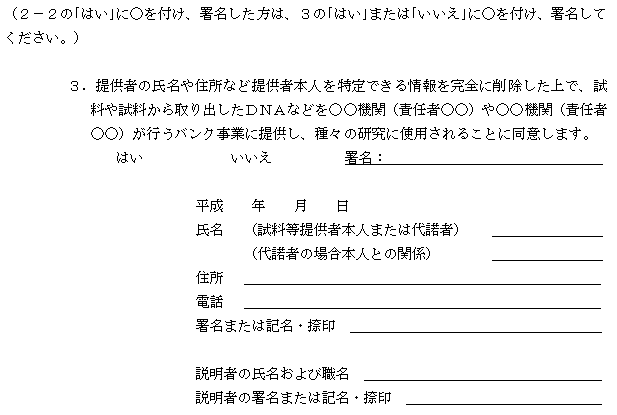
| インフォームド・コンセントに係る一連の手続きにおいて説明を担当する者に対する説明用資料、試料等の提供を依頼する患者などに説明するための説明用文書、同意文書のイメージ
(注) 以下のイメージは、連結可能匿名化等一定の条件を仮定して作成してあります。この資料は、あくまでもイメージであって、具体的な研究計画の策定に当たっては、その目的、対象疾患、対象者等を考慮して、それぞれの研究責任者が別途策定しなければなりません。 |
第四群試料等提供者用
《説明者用説明資料:第四群用例文》(イメージ)
厚生省におけるミレニアム・プロジェクトの一環として実施される「遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究」においては、個体の持つ遺伝的な多様性と様々な疾病との関連を研究し、それを疾病の予防、早期発見、早期治療さらには薬剤の開発に応用し、人々の福祉に大きく貢献することが期待されている。一方、遺伝子解析により、被験者、その家族・血縁者さらには関連する疾病の罹患者が、様々な倫理的・法的・社会的問題に直面する可能性がある。この問題に対処するため、被験者およびその関係者の尊厳、人権および利益を保護することを目的とし、厚生科学審議会において、「遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するための指針」が作成された。
本文書は、「第四群試料等提供者」を対象としている。「第四群試料等提供者」とは、コホート研究への参加者など、すなわち、健康の維持や疾病にかかることについて、環境要因と遺伝素因との相互作用等の解明を目的としたコホート研究などに、自発的に協力する人を対象としている。これらの方々は健康の維持や疾病の罹患における環境因子と遺伝素因との相互作用等の解明に重要な役割を担うことが想定される。本文書は、「第四群試料等提供者」を対象にインフォームド・コンセントに係る説明を行う者が、指針の「4.試料等提供者のインフォームド・コンセント」の記載を十分に理解することを目的として作成されたものである。
「第四群試料等提供者」に係る研究の結果は、研究段階のものが多く、その解釈が確定しておらず、また集団として解析されるため、個々の被験者の健康状態の評価や疾病の予防・診断・治療に影響する可能性は極めて低いものと予測される。しかし、このようにして得られた遺伝情報が、被験者やその家族等に対し様々な不利益を被らせる可能性を否定することはできない。そこで、研究協力に関するインフォームド・コンセントのための説明に当たっては、被験者が遺伝子解析研究の持つ特殊性を十分に理解した上で、研究への協力または非協力を自発的に決定できるよう配慮する必要がある。また、患者や家族のプライバシーを最大限に保護し、被験者からの質問に対しては、必要に応じて医師や遺伝カウンセリング担当者等の協力を得て、対応することが望まれる。
以下に、インフォームド・コンセントを得るための具体的な手続きを記載するが、理解をより深めるために、指針で説明されている部分の項目番号を(
)にて示した。
《説明に当たる者の資格》
インフォームド・コンセントの手続きにおける説明は、研究遂行者の一員であり、倫理審査委員会で承認された研究計画書のなかで「インフォームド・コンセントに係る一連の手続きにおける説明者」として認められた人が行わなければならない(4-1-2-1)。
《代諾について》
被験者が、痴呆等の疾患のため、有効なインフォームド・コンセントを与えることができないと客観的に判断され、かつその研究がそれらの人から試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合、その人に代わってインフォームド・コンセントを与える者として、代諾者に対し説明を行い、同意を得る必要がある(4-1-6-1)。
一方、被験者が未成年者であって、かつその研究が未成年者から試料等の提供を受けないと成り立たないと倫理審査委員会が認めた場合、試料等の提供に当たっては、親権者等の代諾者がインフォームド・コンセントを与える必要がある。ただし、未成年者が16歳以上である場合には、親権者等の代諾者とともに、その未成年者本人の同意も必要である。また、未成年者が16歳未満の場合には、代諾者の同意によって試料を提供していただくことが可能であるが、この場合においても、その未成年者本人に十分な説明を行い、できる限りその未成年者からも試料提供の同意が与えられるように努めなければならない(4-1-6-2)。
代諾者は、
《具体的な手順》
インフォームド・コンセントの手続きにおける説明に当たっては、説明者は倫理審査委員会で認められた説明文書を用い、以下に述べる項目について適切かつ十分な説明を行い、説明を受ける者が自由意思に基づいて、試料等の提供への同意を表明できるようにしなければならない。
なお、身体障害などにより説明文書を読むことができない被験者に対しては、研究遂行者でない者を立ち会わせた上で、説明を行わねばならない。
その上で、説明者は署名した同意書の写しを被験者または代諾者に渡し、同意書を所定の場所に保管する。
《説明事項》
(1)研究協力の任意性と撤回の自由
被験者に対し、試料等の提供は任意であっていつでも同意は撤回できることを伝える。
さらに、被験者が試料提供に同意しない場合、あるいは同意を撤回した場合においても、疾病等の診療において不利益な扱いを受けないことを説明する(4-1-4-1、2および3)。同意を撤回した場合、その撤回に係わる試料および研究結果は廃棄されるが、既に研究結果が公表されている場合、あるいは廃棄しないことにより被験者の個人識別情報を含む情報が明らかになるおそれが小さく、かつ廃棄作業が極めて過大である場合等やむを得ない場合には、試料や研究結果の廃棄はできないことがあることを説明する(4-1-4-4-2)。
(2)研究協力を要請する理由
第四群試料等提供者は、遺伝子解析研究に自発的に協力する意思を持ち、居住地域、疾患の有無など一定の条件を満たす者、あるいはランダムに選ばれた者であることを説明する(4-1-4-5)。その上で、この研究の目的が、ある病気の発病過程における遺伝素因と環境要因の関与、さらには、その相互作用を調べ、個人の病気に対する遺伝的感受性(体質)を評価する方法論を開発することにあること、そして、このような情報が、病気の発症につながる喫煙や食生活などの生活習慣を本人の意思で改める際に重要な役割を果たすことを説明する。このため、いろいろな病気や薬剤反応について遺伝子を調べること、現段階で特定の遺伝子の名前を示すことはできないことを説明する(4-1-4-6-1)。さらに、将来、別の病気や薬剤に関する遺伝子を探索するため試料が保存、利用される可能性がある場合、あるいは、研究の目的や方法の変更が予想される場合には、その旨を説明する(4-1-4-6-2)。
(3)研究責任者の氏名および職名
研究責任者の氏名および職名を告げる(4-1-4-7)。
(4)予測される研究結果と被験者の危険・不利益
第四群生体試料等提供者は、健康の維持や疾患の罹患における病原体、生活習慣等の環境因子と遺伝素因との相互作用等の解明に重要な役割を果たす。
また、本研究においては、遺伝子解析研究の成果が集団で解析されるため、被験者にとっての直接的な利益は期待できないこと、また、被験者にとって不利益な事象としては、検査時の注射針を刺す痛みがあるが、これは一般の検査採血時の痛みと同じであること、さらに、遺伝子解析の結果が外部に漏れた場合、生命保険加入の際の障害になるなどの不利益を被る可能性が考えられることなどを告げる(4-1-4-8)。
なお、研究成果を公表する際には、個人が特定される形では公表しないことなども説明する。
(5)研究計画、方法の開示
希望により、他の試料等提供者の個人情報保護や遺伝子解析研究の独創性の確保に支障が生じない範囲で、その試料等を用いた遺伝子解析研究の研究計画、遺伝子解析の方法等の資料を入手または閲覧することができることを告げる(4-1-4-9)。
(6)試料および診療情報の匿名化
匿名化(氏名、生年月日、住所などの個人を特定できる情報を取り除き、代わりに新たな符号をつけることなどによって、試料や情報の由来する個人を特定できなくすること)を行うこと、提供者と新たにつける符号との対応表は厳重に管理され、解析を行う研究者は誰のものかわからない状態で研究を行うことなどを説明する(4-1-4-10)。
(7)試料、診療情報、遺伝情報の他の研究機関への提供
試料、診療情報、またはそれから得られた遺伝情報を他の機関へ提供する場合は倫理審査委員会により、個人識別情報を含む情報の取扱い、提供先の機関名、提供先における利用目的が妥当であることについて、審査されていることを説明する(4-1-4-11)。
(8)研究結果の開示
第四群試料等提供者を対象として得られた遺伝子解析結果は、疫学研究において多くの人の結果をまとめて集団として解析されるために、個々の試料等提供者についての遺伝情報は、試料等提供者又は代諾者を含め誰にも開示できないことを説明する(4-1-3-1-2)。
ただし、被験者の遺伝子解析の結果、被験者等の生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な治療方法があるときは、倫理審査委員会の意見を聞いた上で、被験者やその血縁者に対し、その情報の開示につき照会がなされることもあることも説明する(4-1-3-1-4)。
研究の進み具合やその成果、学術的な意義は定期的に分かりやすい形で広く公表されること、また、提供者の求めがあればそれに応じて説明することを告げる(3-2-8)。
(9)知的財産権、研究成果の公表
将来、遺伝子解析研究の成果が知的財産権を生み出す可能性があり、その場合、当該知的財産権は国や研究者などに属し、被験者には帰属しないことを説明する(4-1-4-13)。また、試料から得られた遺伝情報などの研究成果は、匿名化により試料等提供者を特定できなくした上で、学会発表やデータベースとして公表される場合があることを告げる(4-1-4-14)。
(10)試料、診療情報の保管と廃棄
被験者の生体試料や診療情報は、研究計画書に明記され、倫理審査委員会の承認を得たうえで、インフォームド・コンセントの範囲内で、将来の研究のための資源として保管されることがあること、この場合、被験者に対し、その必要性、保管の方法、期間、場所、および匿名化の方法を告げる。廃棄に当たっては、その方法と匿名化の方法を説明する(4-1-4-15)。
(11)細胞・遺伝子・組織バンクへの寄託
試料を細胞・遺伝子・組織バンクへ寄託し、一般的に研究用資源として分譲することがあり得る場合には、バンクの学術的意義、当該バンクが設置されている機関の名称、寄託される試料等の匿名化の方法およびバンクの責任者の氏名を説明する(4-1-4-16)。
(12)試料提供の対価
試料提供に当たっての対価はないこと、また、研究結果によって、診療が必要になった場合、被験者の医療費負担が生じうることを告げる(4-1-4-18)。
(13)遺伝カウンセリングの実施
第四群生体試料等提供者について遺伝カウンセリングが必要となる状況はまれなことと考えられるが、倫理審査委員会がその必要性を指摘した場合、あるいは被験者の希望がある場合には、それを援助・支援するための遺伝カウンセリングの体制が整備され、あるいは紹介できることを説明する(3-2-3-14および4-1-4-17-2)。
○○○センターでは、○○○○(共同研究機関)と共同で、病気の原因をより正確に明らかにし、効果的な治療法や予防法を調べるため、遺伝子の解析研究を取り入れ、多くの方についてかかったことのある病気、遺伝子の状況、生活の状況との関連などを調べる研究を行っています。
本文書は、あなた(注)に、この研究への協力をお願いしたく、病気と遺伝子との関係、研究内容などについて説明したものです。この文書をよく理解した上で、あなたが研究協力に同意していただける場合には、「遺伝子解析研究への同意文書」に署名することにより同意の表明をお願いいたします。もちろん、同意いただけないからといって、それを理由にあなたが不利益を被ることはありません。
以下に、遺伝子解析に関する説明と研究協力への同意に関わるいくつかの重要な点を説明します。
(注)あなたが提供者の代わりに説明を受けている場合には、その提供者のことです。
《遺伝子とは》
遺伝子とは人間の身体をつくる設計図に相当するものです。ヒトには10万個以上の遺伝子があると考えられています。人間の身体は、約60兆個の細胞と呼ばれる基本単位からなっていますが、この細胞の核と呼ばれる部分に遺伝子の実体となる物質であるDNAが存在しています。
人間の身体は、この遺伝子の指令に基づいて維持されています。
《病気と遺伝子》
ほとんどすべての病気は、その人の生まれながらの体質(遺伝素因)と病原体、生活習慣などの影響(環境因子)の両者が組合わさって起こります。遺伝素因と環境因子のいずれか一方が病気の発症に強く影響しているものもあれば、がんや動脈硬化などのように両者が複雑に絡み合って生じるものもあります。遺伝素因は遺伝子の違いに基づくものですが、遺伝子の違いがあればいつも病気になるわけではなく、環境因子との組合せが重要であるのは先に述べたとおりです。
《遺伝性の病気》
遺伝性疾患とは、遺伝子の違いによる病気をいいます。これには、親が遺伝子の違いを持っていて、その違いが子に伝わる(いわゆる遺伝する)場合と、親の遺伝子にはまったく違いがないにも関わらず、精子や卵子の遺伝子に突然変異が生じて病気になる場合とがあります。これに対して、身体を構成する細胞に遺伝子の違いが生じて、がんやその他の病気になることがありますが、この場合には病気が子孫に伝わることはなく、遺伝性疾患という言葉は使いません。遺伝子に違いがあっても必ずしも病気になるわけではありません。人間には染色体が2本(1対)ずつあり、1本の染色体の遺伝子に違いが起きても違いが起きていないもう一方の遺伝子が機能を補って病気になるのを防いでいます。また、遺伝子の違いが身体機能の異常につながらないこともあります。一方、病気を引き起こす環境因子への反応の違いが遺伝子の性質によって決まることも多いので、一見遺伝しないように見える多くの病気が遺伝子の違いに起因することも分かってきました。
《遺伝子の解析とは》
この研究は、○○地域に住んでおられる方に協力をお願いして、多くの方がかかったことのある病気、遺伝子の状況、生活の状況との関連を調べようとするものです。
あなたの血液をこれまでの病気や生活の状況などの記録とともに、この研究に利用させていただきたいのです。血液の採取は大きな危険を伴いません。
具体的には、まず、あなたにこの研究への協力をお願いするため、研究の内容を含め、あなたが同意するための手続きについて説明を行います。あなたがこの説明をよく理解でき、あなたが研究に協力して血液を提供することに同意しても良いと考える場合には、「遺伝子解析研究への協力の同意書」に署名することにより同意の表明をお願いいたします。
《本研究に関する説明》
(1)研究テーマ
○○地域における遺伝子解析を利用した疫学研究(疫学研究とは、多くの方について、かかった病気、その病気の原因ではないかと考えられることの関係を調べ、病気の原因を明らかにする研究のことです。)
(2)研究機関名および研究責任者氏名
この研究が行われる研究機関と責任者は下表に示すとおりです。
| 研究機関名 | 研究責任者名 | 職名 |
| ○○○センター | ○○ ○○ | ○○○○ |
| ○○○病院 | ○○ ○○ | ○○○○ |
ただし、この他に共同研究を行う研究機関や研究責任者が追加される可能性があります。
(3)研究目的
この研究の目的は、多くの方々がかかる病気について、生まれつきの体質(遺伝素因)と病原体、生活習慣などの影響(環境因子)が、その病気の発生や薬剤の反応にどのように影響しているかどうかを調査し、病気の予防や早期治療に結びつけようとすることです。生まれつきの体質を調べるために、血液などから取り出した遺伝子のかたちを調べることになりますが、いろいろな病気や薬の反応に関係する遺伝子を調べたいと考えており、今は特定の遺伝子の名前をお示しすることはできません。
(4)遺伝子解析に必要なもの
遺伝子解析に必要なものは、(血液 約○○ml)です。これらの試料からDNAなどをとりだして、病気に関係した遺伝子や薬の効き目に影響する遺伝子の違いの有無を調べます。
(5)遺伝子解析の費用
この遺伝子解析にかかる費用は厚生省の研究に対する助成金により支払われますので、あなたの負担はありません。
(6)研究計画等の開示
希望があれば、この研究の研究計画の内容を見ることができます。また、遺伝子を調べる方法等に関する資料が必要な場合は用意します。
(7)個人情報の保護について
遺伝子の研究結果は、様々な問題を引き起こす可能性があるため、他の人に漏れないように、取扱いを慎重に行う必要があります。あなたの血液などの試料や診療情報は、分析する前に診療録や試料の整理簿から、住所、氏名、生年月日などを削り、代わりに新しく符号をつけます。あなたとこの符号を結びつける対応表は、○○○○(試料等の提供が行われる機関名または部署)において厳重に保管します。このようにすることによって、あなたの遺伝子の分析結果は、分析を行う研究者にも、あなたのものであると分からなくなります。ただし、遺伝子解析の結果についてあなたに説明する場合など、必要な場合には、○○○○(試料等の提供が行われる機関名または部署)においてこの符号を元の氏名などに戻す操作を行い、結果をあなたにお知らせすることが可能になります。
(8)試料の他の研究への利用について
この研究のために提供していただくあなたの試料や診療情報は、将来計画される別の研究にとっても貴重なものになるので、今回の試料提供にあなたの同意がいただけるならば、将来の別の遺伝子解析研究のためにもできましたら使わせていただけるようお願いします。
また、提供された試料やそこから取り出したDNAなどをどこの誰の物であるかを誰も分からないようにした上で保存し、広く研究用に提供する事業(バンク事業)を○○機関(責任者○○)や○○機関(責任者○○)が行っています。あなたからいただいた試料やそれから取り出したDNAなどもバンク事業に提供し、国民の共有財産として様々な研究に利用させていただくことも併せてお願いします。
(9)遺伝子解析を受ける人の権利
この研究に協力するかどうかは、あなたの自由意思で決定して下さい。強制はいたしません。また、同意しなくても、あなたの不利益になるようなことはありません。
一旦同意した場合でも、あなたが不利益を被ることはなく、いつでも同意を取り消すことができます。その場合は採取した血液や遺伝子を調べた結果などは廃棄され、それ以降は研究目的に用いられることはありません。ただし、同意を取り消した時にすでに研究結果が論文などで公表されていた場合は、血液や遺伝子を調べた結果などを廃棄することができない場合もあります。
(10)解析結果の報告
本研究で得られる遺伝子解析結果は、さらに詳しい研究が必要なものが多く、結果をどのように理解すべきかがはっきりとは分かっていません。また、ご協力いただいた多くの方々を集団として、例えばある病気にかかっている方とかかっていない方に分けて、研究を行います。したがって、個々の方について解析結果はお知らせできません。
ただし、偶然に重大な病気との関係が見つかり、あなたやあなたの血縁者がその結果を知ることが有益であると判断される場合に限って、医師からあなたやあなたの血縁者に、その結果の説明を受けるか否かについて問い合わせることがあります。
研究の進み具合やその成果、学術的な意義については、定期的に、また、あなたの求めに応じ、分かりやすい形で、公表あるいは説明がされます。
(11)研究に協力することによる利益と不利益
本研究に参加することにより、あなたが個人的に受ける利益はありません。しかし、本研究によって解明された成果を社会へ還元することにより、その一員として、新しい知見にもとづく病気の予防や治療を受けることができます。
遺伝子を分析する研究の結果として特許権など、ひいてはそれに基づく経済的利益が生じる可能性がありますが、あなたはこれらの権利権などがあるとは言えません。
一方、あなたが受ける不利益としては、あなた自身の遺伝子解析結果が外部に漏れた場合、生命保険加入の際の障害、社会における不当な差別などにつながる可能性が考えられます。しかし、前でも述べたとおり、この研究では多くの方々を対象として、集団として分析を行うのでその恐れはまずないと考えられます。それでも、万が一の漏洩による不利益を防ぐため、遺伝子を調べたあなたや御家族の機密保持については、機密保持のための責任者を置くなどの配慮をしています。
なお、研究成果を公表する際には、個人が特定される形では公表しませんので、それにより不利益を受けることはありません。
| 平成 年 月 日(印刷)
研究実施機関名および責任者(印刷) お問い合わせ先(印刷) |
遺伝子解析研究への協力の同意文書
研究責任者あるいは機関の長(試料等の提供が行われる機関における研究責任者名) 殿
私は遺伝子解析研究(研究題目)について、(説明をした者の氏名)より説明文書を用いて説明を受け、その方法、危険性、分析結果のお知らせの方法等について十分理解しました。ついては、次の条件で研究協力に同意致します。
説明を受け理解した項目(□の中にご自分でレを付けて下さい。)
| □ | 遺伝子の分析を行うこと。 |
| □ | 研究目的 |
| □ | 遺伝子解析に必要なもの |
| □ | 遺伝子解析の費用 |
| □ | 研究計画書等の開示 |
| □ | 個人情報の保護 |
| □ | 試料の他の研究への利用 |
| □ | 遺伝子解析を受ける人の権利 |
| □ | 解析結果の報告 |
| □ | 研究に協力することによる利益と不利益 |